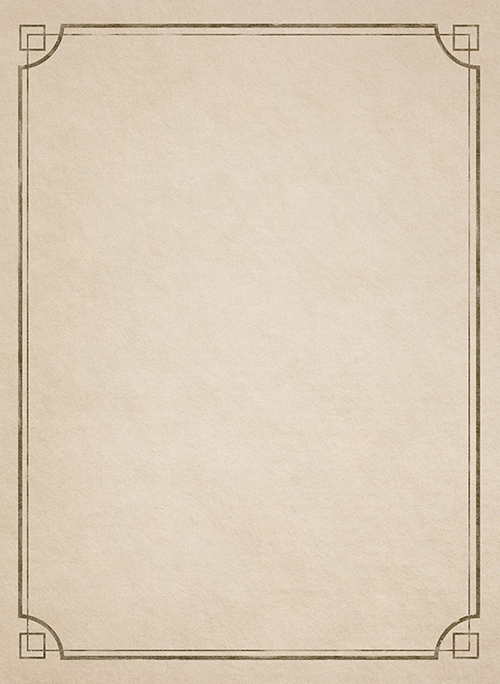四
朝になった。
昨日の葡萄酒がまだ効いているようで、頭が朦朧としている。
雷梧は旅籠の寝床で、昨日のことを一つ一つ思い出した。最後に、胡姫に見つめられたところに至り、思わず布団をかぶる。
あれでは、逃げ出したようなものだ。
だから、今日も行って、彼女たちの踊りを今度は動じずに見ていよう。
精一杯考えて、そんな反省をした。
そのとき、部屋の戸を叩く音がして、王金鹿が呼びに来た。
旅籠の一階が食堂になっており、すでに方翔が朝食をとっている。
雷梧は彼らと食事をしながら、笑顔になる。
「思っていたより、ずっと楽しいところでした。今日は、土産を買いに行こうと思います」
しかし、二人は苦笑いを見せる。
「それが、すぐに戻ることになってしまいまして。これを食べたら、范陽へ出立します」
雷梧は驚いた。四、五日はゆっくりできると思っていたのに。しかし、連れてきてもらった身では嫌だともいえず、結局また六日ほど馬を飛ばし、范陽へと戻って来てしまった。
戻った翌日、時仁夏より一着の鎧が贈られて来た。
青白い鉄の小板を連ねた本体に、白く走る稲妻の模様。胸の左右には楕円の護心鏡、背面は浮き彫りにされた雷公(嘴と翼のある雷神)の姿。
これは自分の名にちなんだ鎧だと分かり、雷梧は心の底から喜んだ。
「こんな良いものを。明日にでも、お礼を述べにいきます」
しかし、届けてくれた兵士は、沈痛な表情だった。
「できたら、今すぐ来ていただけませんか」
それ以上は言わず、外へ促す仕草をする。
嫌な予感がした。
「近くへ」
時仁夏が、雷梧を手招きする。額には脂汗が浮かんでいた。
「辛いのですか。しっかりしてください」
雷梧はすぐに駆けより、その手を握る。ぞっとするほど指が細くなっていた。
「鎧は、気に入ったか」
「ありがとうございます。いえ、それより」
鎧のことなど、いまは頭から離れていた。
もう少し、時間があると思っていたのに。
「お前の副将に就きたいと、宇文平が志願していた。奴なりに気懸かりなのだろう。――雷梧、いろいろ学んで、強い男になれよ」
声は本当に小さく、吐息が音になっているだけだった。それでも時仁夏は休もうとせず、口を動かしている。
「お前に、謝らなければいけない。矢に当たったあの日、俺は、新兵のお前を盾にするつもりで連れていったんだ。敵が多すぎて、怖くてな」
雷梧は、少しだけ驚いた。しかし、憎くなど思わない。
それよりも、早く元気になって、僕を鍛えてください。
そう言いたいのに、どうしても嗚咽になってしまう。
時仁夏の細い手が、雷梧の頭をなでる。
「あの時、お前の決断が皆を救った。だからもし、お前が迷うようなときは、人のためになる方を選べ。それが正しい道だ」
その言葉を最後に、時仁夏は目を閉じ、動かなくなった。
雷梧はなんとか目を覚まさせようと、とりすがって叫んだ。
しかしそれは叶わなかった。
時仁夏の葬儀が終わった翌日あたりから、軍の全体が急に慌ただしくなった。細かく兵の配置が分けられ、武装も揃う。雷梧の率いる兵も、五千に増員された。しかし、何の為かは知らされない。
「雷将軍、契丹(モンゴル系民族)の大軍でも来るんですか? そんな気配もないですが」
演習場の整備のとき、宇文平が不審そうに言った。
副将となった宇文平は、教官だった事は忘れたかのように丁寧だった。雷梧も立場を自覚し、上官らしい口を利くよう努めている。
「分からない。敵の姿は無いから、大規模な演習だと思うんだが」
妙ですね、と宇文平は訝って去る。
やがて伝令が来た。
将軍たちは、会議室へ集れという。
「急がせて済まない。さすがは将軍たちだ、滞り無く進んでいるな」
集まった全将軍を、厳荘が誉めた。千人近くを無理矢理詰め込んだ会議室は狭く、息苦しい。
全員に、唐の東都・洛陽までの地図が配られていた。日取りと道順が示してある。
「諸君をわざわざ屋内に集めたのは、これから話す事を部外に漏らさぬためだ。――ここより先は、殿からお話し頂く」
ぬっと、巨体が入って来た。部屋の圧迫感が増す。単純に空間の問題ではなかった。その目が、抜き身の刀のように光っている。
全体を舐めるように見渡し、安禄山は口を開いた。
「諸君も知っているだろうが、長安にいる宰相・楊国忠は、楊貴妃の一族というだけで、その地位を得た。奴は、政務を取り仕切って皇帝陛下を操り、専横は極まりなくなっている。――唐の天下は、一匹のコソ泥に動かされているのが現状だ」
重々しく、怒りを抑えている口調だった。
「ところが最近、わしは陛下より密書を賜った。『安禄山よ、頼れる者はお前しかいない。急ぎ都へ上り、奸臣楊国忠を討伐せよ』と、悲痛に綴られている」
安禄山は書状をかざし、ため息をつく。
雷梧は、都のそんな事態など、今初めて知った。周りの将軍たちも同じらしく、ざわざわ話し始める。
「事態は急を告げている。わしはすぐにも楊国忠を討って、唐に平和を取り戻すつもりだ」
勢いのある声だった。
将軍たちは、逆に静まり返る。
雷梧は、あの王金鹿と方翔が皇帝への使者だったのだと気付いた。急に帰るはめになったのは、この密書のせいに違いない。
「楊国忠を討つ事は、陛下をお救いする事だ。頂ける恩賞はこれまでと比べ物にならんだろう。諸君は将軍だから、都に邸を構えて、女も囲える。それでもまだまだ余るぞ」
将軍たちから、期待と驚嘆の声が上がる。
雷梧も反射的に、あの舞姫の姉妹を思い出した。
長安を巻き込む戦。それはつまり、あの姉妹にも危険が及ぶという事ではないか。
「地図は行き渡ったな。まずは東都洛陽を目指す。わしと共に行く者は、声をあげろ!」
安禄山は右拳を高々と振り上げる。
数十人が、方々で雄叫びを上げた。それに遅れまいとするように、残りの将軍たちも次々に声を上げる。営舎の壁が、雷鳴に似た咆吼で震えた。
雷梧も、拳を振り上げて叫んでいた。