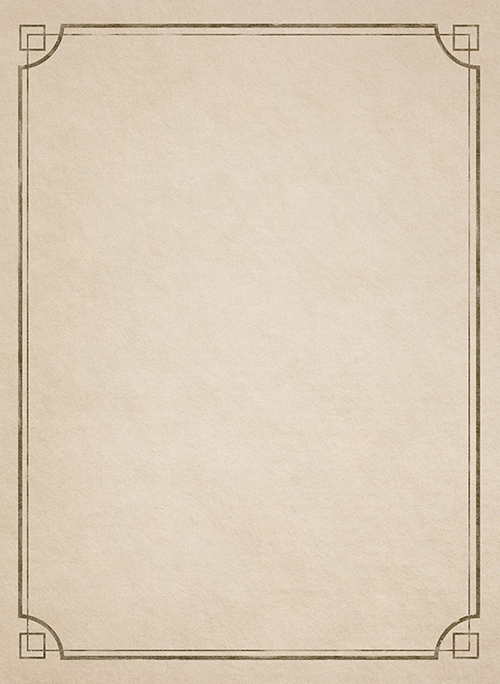三
岩場や、林の中を走らされる。
次に重い砂袋を上げ、最後は剣術。
宇文平に特訓を頼み、もう二ヶ月が過ぎたが、これがひたすらに厳しい。雷梧は、毎日のように嘔吐した。
しかし、もう限界ですと根を上げる直前で、いつも訓練は終わりになる。宇文平がうまく教えるという理由は、そういうことだった。
「立て。敵に背を向けるな、死ぬぞ」
面長な顔の、宇文平が言う。四つん這いで吐いている雷梧には、答える気力もない。
雷梧は将軍になってから、すでに何度か実戦にも出た。いくらか強くなったはずだが、まだ慣れたとはいえない。
「王金鹿と、方翔じゃないか。何の用だ」
宇文平が、誰かに声をかけた。大柄と小柄の男が歩いて来る。昔の部隊仲間らしい。
彼らと話をした宇文平は、頷きながら雷梧に告げた。
「今日は上がれ。安禄山殿が、お前を呼んでいるそうだ」
また何か、話があるのだろうか。
雷梧は、貧血も忘れて起き上がる。宇文平に挨拶をすると、王金鹿らに同行した。
「雷梧、都を見てみたくはないか?」
司令室に入ると、安禄山はいきなり言った。
玄宗皇帝のよき遊び相手でもある安禄山は、たびたび唐の都・長安に赴いている。
彼は、少年将軍として頑張っている雷梧への褒美として、長安を見せてやりたくなったという。
「仮とはいえ、親子の関係だからな。少しは父親らしいこともしてやりたい」
安禄山は優しく笑った。
確かに、雷梧も一度は都に行ってみたいと思っていた。仮父の配慮が、暖かく染みる。
「わしは行けぬが、この王金鹿と方翔を付かせる」
「はい。ありがとうございます」
雷梧は喜んで部屋に帰ると、行李に服を詰め、厩に行った。
黒い馬が、嬉しそうに前脚を上げる。
時仁夏から譲られた、例の黒馬である。闇鵬と名付けていた。
その闇鵬の、額だけにある白い毛を撫でる。
「都に行けるぞ。いろんな物があって、何日いても飽きないんだそうだ。お前にもきれいな鞍を買ってやるからな」
辺境の軍人は、軍営の近くで屯田をしながら生活する。だから雷梧は、田畑と草原しか見たことがなかった。
彼の想像する都は、広野の中に城がひとつあるくらいのものだったが、それでもとにかく嬉しい。
眠る時ふと、時仁夏の顔を思い出した。養子の話の時に見せた、奥歯に物の挟まったような顔。
しかし、安禄山の配慮は、本心からだろう。そう思うと、疑問も消えていった。
三日後、雷梧は長安へ向けて出発した。
のんびりした旅を予想していたのだが、王金鹿たちはなぜか道を急ぎ、昼夜を構わず馬を駆けさせる。雷梧はろくに寝食もとれぬまま、延々と六日間も走り続けた。
しかし、いよいよ長安に入ると、長旅の疲れなど消しとんでしまった。
柱や屋根にまで緻密な彫刻を施した建物。
極彩色の旗指物で人目を引いている商店。
行き交う人々も、活気に溢れて見える。
雷梧は、目に映るものを全て追った。
唐の国は、今が一番ともいわれる太平の世を送っている。しかし彼の住むような辺境地は、国境を守るための戦いは絶えておらず、決して平和とはいえないのである。
(まさに栄華の都だ。僕らの戦いは、これを支えるためにあったんだな)
道行く人の笑顔が、雷梧は自分の働きの結果のように思えてきた。
「雷将軍。私たちはちょっと所用がありますので、ここで失礼します」
大柄な体の王金鹿が、突然言った。
「え、ここで、ですか」
戸惑った雷梧に、小柄の方翔が紙片を渡す。
「旅籠の場所は、この地図に。夜になったら私たちも行きますので」
そう告げると、二人は馬首の向きを変え、街の奥へと消えていってしまった。
一人になった雷梧は、少し心細くなりはしたが、菓子の店や馬具の店などを見ていると、そのうち気楽になってきた。
雷梧は続いて、長安の西の市場へ出かけた。
ここには、西域人とも呼ばれる胡人(ペルシア、トルコ等の民族)が多く、シルクロードを経て来た織物や香料などが売られ、大いに賑わっている。
景教(キリスト教)や拝火教(ゾロアスター教)の寺院もあり、異国の風情が漂っていた。雷梧の部隊にも西域人はいたので、案外に見慣れたものもある。
時刻は夕方に近くなっていた。
腹も減ったので、酒場を探す。
見つけた店に入ると、客は漢胡入り交じりで男ばかり。皆何かを待っているようで、やたら下品な笑い声が響く。
雰囲気に戸惑いながら、雷梧は串刺し焼き肉のケバブ料理を食べた。ついでに葡萄酒も飲んでみる。
「何だ、子供のくせに酒なんか」
突然声をかけられて振り向くと、店主の男がばつの悪そうな顔をして立っていた。
「帰りな。今から舞台なんだ。ガキが見るようなもんじゃない」
確かに、店員が忙しげに店の中を片付け、中央に台のようなものをしつらえている。
雷梧は咄嗟に、こういう場所に慣れているような表情を作った。
「これでも軍人だよ。童顔で悪かったな」
子供に見せられない出し物なら、尚更見てみたい。周りの連中を真似て、荒っぽく酒をあおった。店主は訝しげな顔で離れていく。
舞台は完成し、たくさんの蝋燭を鏡で反射させ、白昼のように照らしている。
店主の声が響いた。
「お待たせしました。当店が誇る胡姫の姉妹、沙維謝と沙維羅でございます。遙か遠い康国(現ウズベキスタンのサマルカンド)よりやって参りました。十六歳と十二歳が織りなす、艶媚な胡旋舞を、どうぞお楽しみください」
西域人の踊りを胡旋舞、その舞姫を胡姫と呼ぶ。雷梧も話には聞いていたが、見るのは初めてだった。
舞台の脇にいる数人の楽団が、絡みつくような気だるい音楽を奏で始めた。それに伴って、金の髪、緑の瞳に白い肌の踊り子が二人、ゆっくりと舞台に上がる。
蛇と葡萄を描いた紫色の衣装は、薄い上に、身体を最小限にしか覆っていない。二人は細身の身体を柔らかくうねらせ、二匹の蛇が絡むように踊り続けた。
店内は喝采と野次が入り交じり、大騒ぎになった。常連らしい客は、踊り子の名を呼びながら拍手を送っている。
雷梧は軍隊生活ばかりで、あまり女というものを見た事がない。年上の兵士たちはしばしば妓館に通っているが、何が楽しいのかよく分からないでいた。
だが、今は違う。
彼女たちのしなやかな身体に、雷梧の目は釘付けになった。酒の力も手伝って、自分の奥で育って来ていた何かが、強烈に叩き起こされてくる。
そんなとき、胡姫の妹が、雷梧の方を見た。
どうして、こんな若い人が。
そんな視線である。
雷梧は緊張して、顔面に汗が噴き出た。
観客もそれに気付き、「小僧、気に入られたみたいだな」と囃す。
雷梧は真っ赤になってうつむき、固まってしまった。しかし周りは、更に囃す。
とうとう雷梧は居たたまれなくなり、適当な額の銀子を置いて、駆け足で店を出てしまった。