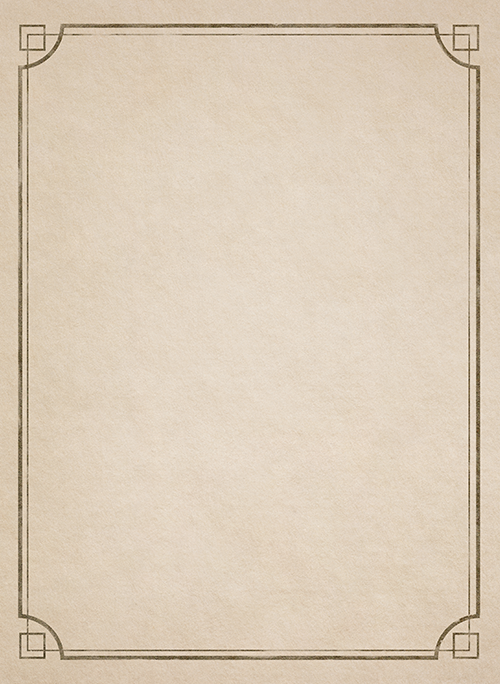二
唐の国、范陽(現在の北京)。
長安の都を遠く南西に見て、国境を守っている要衝の地である。異民族との衝突が多く、戦は度々起こっていた。
雷梧に、恩賞があるという。
急いで司令室に出向き、この范陽を治めている節度使(地方を守る軍政司令官)の前に跪いた。
その名は、安禄山。
戦に強いばかりでなく、唐の皇帝・玄宗と、その寵姫・楊貴妃からも信頼されている人物。
(大きい。噂通りだ)
安禄山は、三五○斤(約二○九キロ)という超肥満体で有名だった。司令室が、やけに狭く感じられる。
「奇襲部隊の主将を討った者か。ずいぶん若いな。名は?」
聞かれて雷梧は一人前ぶりたくなり、いつもより低い声を出した。
「姓は雷、名を梧と申します。幼い頃からこの地の駐屯軍にいます。十三歳になった今年より、正式に入隊致しました」
それを聞いた安禄山が、分厚い瞼をゆるめた。笑っているらしい。
「小さい身体で、見事な働きだ。わしはもう五十三だが、国境を守る任務は、楽ではない。お前のような若者がいるのは嬉しい事だ」
「は、ありがとうございます」
恩賞ではなく、労いだけか。雷梧は残念に思った。
が、安禄山は側近の厳荘と何やら話し、
「わしには将軍を任命できる権限がある。お前も加えておこう。まずは兵三千を率いよ。将軍用の剣も渡しておく」
と告げた。厳荘に促された兵士が、雷梧の目の前に一本の直剣を置く。
雷梧は呆然となって、安禄山を見た。予想外の昇進だ。たった一人斬っただけなのに。
安禄山は、更に言った。
「お前の両親は、戦乱で死んだそうだな。わしには大勢の養子がいるのだが、どうだ、お前もわしの子になる気はないか?」
雷梧は冗談を言われたのかと思い、周囲を見渡す。
厳荘が、微笑みながら言った。
「良かったじゃないか、お受けしなさい」
とりあえず、雷梧は頷いた。
実際は、頭の中が真っ白だった。話が早すぎて、飲み込めない。
下がってよいと言われて、我に返った。
雷梧はしどろもどろに礼を言い、剣を拝領して退室した。
「その歳で将軍か。大出世じゃないか」
かすれた声で、時仁夏は笑った。
射られた上官は、なんとか一命を取り留めていたのだ。しかし、首の包帯からは血が滲んでいる。
「雷梧。お前は見込みがある。学ぶべき事はたくさんあるが、きっと良い武将になれるだろう」
時仁夏が言った。笑っているが、顔色は悪い。三五歳の活発な武人だったのに、今は初老くらいに見える。
「でも、自信がありません。部下になる人は、皆年上ですし」
雷梧が素直に不安を告げると、時仁夏は、当たり前だと手を振った。
「部下の命を預かるんだ、いきなり自信など持てんさ。まあ、用兵の機微については、俺が時間の限り教えてやる」
心強い言葉だったが、時間の限りという言い方は重かった。
雷梧は、話題を変えようと思った。
「それよりも僕は、養子にしてくれた事が嬉しかったです。唐国随一の節度使が、父親になってくれるなんて」
――安禄山は、一人で三鎮(范陽、平廬、河東)の節度使を兼任していた。その兵力は全国の三分の一を占め、唐の軍事を大きく掌握している。
そんな名誉ある人の養子になれて、雷梧は本当に嬉しかった。
しかし、時仁夏は苦く笑っただけで、まあ養子はともかく、と話を打ち切ってしまう。
「そうだ、武芸も磨かねばならんな。お前、宇文平という男を知っているだろう」
「はい。あなたの副将ですね」
宇文平は、鮮卑族(モンゴル系民族)の血を引く、三十代半ばの武将である。元は斥候隊にいた。敏捷で、力も強い。
「あいつに習え。少々荒っぽいが、うまく教える奴だ」
荒っぽいと聞いて、雷梧は背筋が寒くなる。
「がんばれよ。お前の出世は、みんなの励みになる。多少の厳しさは覚悟」
そこまで言って、時仁夏は激しく咳込んだ。傍にいた看護の兵が慌てて彼を支え、背中をさする。
雷梧は、促されて退室した。
痰を詰まらせた咳が、外に出ても聞こえた。