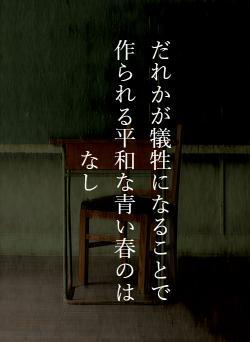六 桔梗の戦い
桔梗は名を呼び続けたが友成は一度も振り返ることはなかった。
「あの男に賭けるかい、お嬢ちゃん」
賭けの胴元が陽気な声をかけてくる。
「賭けようにも元手がないの」
「あんたの姉さんが持ってる檜扇や唐衣を賭けてもかまやしないぜ。あの小僧が勝てば大儲けできるって」
「友成は賭けのために戦ってるんじゃないのよ」
「名誉を賭けて戦うのが男ってもんだ。たとえ死んでもな」
桔梗がにらみつけると、胴元は舌打ちをして背を見せた。
そのあいだにも、友成は入道の懐に入り込み、がっちりと帯を掴んでいた。入道は腰を左右に振るが友成はタコのように離れない。
「ふん、うっとうしい」
入道は友成のうなじを鷲掴んだ。懸命に抗う友成の健闘もむなしく、強引に剥がされる。そのまま宙に吊り上げられた。
「おいおい、あれじゃ死んじまうぞ」
手足をばたばたさせてもがく友成を、入道は玩具のように揺すった。
「人形みたいだなあ」
言いざま、入道は友成の左足に手刀を当てた。
「あ」
鈍い音がした。
「ああ、壊れちまった。腕はどうだろうなあ」
入道は順番に手足の骨を砕いて、なぶり殺しにする気だ。
出居はちらちらと帝の顔をうかがってなかなか判定を出さない。
私は名誉なんていらない。一生友成のそばにいて、友成の笛を聴きたいだけ。
「お姉さま、檜扇を貸して」
桔梗は杏子から檜扇を奪った。
「ちょっとどいて、どいて。どきなさい!」
人混みを掻きわけて、良い位置を見つけた。角力入道の頭の上に太陽が照り輝いている。
桔梗は声の限りに叫んだ。
「角力入道さまあああ。素敵~!こっちを見てえ~!」
「ん?」
振り返った入道に向けて檜扇を広げた。
「うっ……!」
ぎらぎらした檜扇に反射した光が角力入道の目を射る。
驚いて緩めた手から友成が滑り落ちた。
「勝負あった。勝者、角力入道」
すぐさま出居が審判を下す。
地面に仰向けになった友成がはあはあと荒い息をついている。悔し涙だろうか、ごしごしと手で拭っている。
「友成……!」
立ちあがろうとするが左足に力が動かないようだ。
「手当てをしてやれ」
帝の指示により友成は控えの間に連れられていった。
その途中でちらと桔梗を振り返った友成の瞳は空虚だった。
友成の容態が心配だ。なんとかして控えの間に忍び込まねば。
人混みに揉まれてなかなか移動できないでいる桔梗の耳朶に帝の言葉が流れ込んでくる。
「素晴らしい戦いだった。角力入道よ。お主が戦う姿をもっと見たかったのだが、思いの外参加者が少なくて実に残念だった」
「わしもそう思うておりました。都人は意気地がないことですな」
角力入道が出場者を脅して辞退させたことを帝は知りもしない。脅しに屈せず参加した者は称えられるべきだ。桔梗は悔しさに奥歯を噛みしめた。
「そうか、やはり物足りなかったか」
「はい、物足りません。もし望む者がいれば飛び込みで参加してもらいたいくらいですわ、がっはっは」
「そうか、それはいい」
帝は庶民席に視線を移した。
「誰ぞ。勇者はおらぬか」
会場はしんと静まる。
「誰もいないのか。このさい、近衛府の者でも蔵人衆でもよいぞ」
みな一斉に顔をうつむかせる。化け物と好んで戦いたい者などいない。
角力入道は腕を組んで、得意げに鼻の穴を広げた。
「ふうむ」
帝は優雅に扇を揺らしたあと、首を傾げた。
「面白そうなのに誰も手をあげぬか。では、しかたない、わ──」
「はい!」
桔梗はまっすぐに腕を上げた。
会場は一瞬静まったあと、どっと笑声がわく。
「お嬢ちゃん、にらめっこじゃないんだぞ」
「この細っこい体でなにをする気だ」
桔梗の挙手に、角力入道はぽかんと口を開けた。
嘲笑にかまってなぞいられなかった。桔梗は柵から身を乗り出した。
「女が挑戦してはいけないのですか。高札にはそんなことは書いてなかったですよね」
帝がにやりと笑った。
「面白い女子だ。かまわん。中央に出てこい」
おおお、と地鳴りのような音が響き渡った。
「なんという無慈悲な帝だ」
「むごいことじゃ」
「ああいうでしゃばりな女にはいい薬だろう」
桔梗は柵を乗り越えた。
「諸肌脱ぎになるので、代わりにさらし布を巻かせてください」
控えの間に案内された。屏風や几帳で仕切られた中で手渡されたさらしを胸が邪魔にならないようにきつく巻いた。
無闇に肌をさらすのははしたないことだとはわかっている。だが諸肌脱ぎにならなければ、短衣の襟を掴まれやすい。弱点はふさいでおかなければ。
準備をしながら、友成を探した。
奥の几帳の裏に長椅子があった。そこに友成は横たわっていた。青白い顔で目を瞑っている。
「と、友成!?」
「大丈夫だ。気を失っているだけだから」
帝の侍医と名乗る男が友成の足に添え木を指さした。
「三月もすれば歩けるようになる」
「よかった」
「お嬢ちゃん、裏口はあっちだ。そっと出て行くがいい」
侍医は桔梗の小さな体を見やって、ぽそりと囁いた。
「え」
「女子の骨など脆いものだ。筋肉の鎧もないのだろう。粉々になったら骨接ぎもできん」
「ご心配はたいへんありがたく、でも」
祈りの形に合わさっていた荒れた手に目を落とし、ぎゅっとこぶしを握った。
「女でも戦わねばならないときはあるのです」
「愚かな。女が名誉を欲するのか」
名誉を欲する女が愚かかどうかはわからない。だが桔梗が欲するのは名誉ではなかった。
「この戦い、勝てば帝から賞金がいただけます。それがあれば父の命を救える。それに友成をいたぶった角力入道にせめて一矢報いねば、生涯後悔することでしょう」
「いずれ命を粗末にするのは愚かなことにかわらんぞ。一矢報いる方法はきっとほかにもある」
「……粗末にしないよう、気をつけます。友成をよろしくお願いします」
もの言いたげな侍医を断ち切るように桔梗は会場に戻った。
桔梗は名を呼び続けたが友成は一度も振り返ることはなかった。
「あの男に賭けるかい、お嬢ちゃん」
賭けの胴元が陽気な声をかけてくる。
「賭けようにも元手がないの」
「あんたの姉さんが持ってる檜扇や唐衣を賭けてもかまやしないぜ。あの小僧が勝てば大儲けできるって」
「友成は賭けのために戦ってるんじゃないのよ」
「名誉を賭けて戦うのが男ってもんだ。たとえ死んでもな」
桔梗がにらみつけると、胴元は舌打ちをして背を見せた。
そのあいだにも、友成は入道の懐に入り込み、がっちりと帯を掴んでいた。入道は腰を左右に振るが友成はタコのように離れない。
「ふん、うっとうしい」
入道は友成のうなじを鷲掴んだ。懸命に抗う友成の健闘もむなしく、強引に剥がされる。そのまま宙に吊り上げられた。
「おいおい、あれじゃ死んじまうぞ」
手足をばたばたさせてもがく友成を、入道は玩具のように揺すった。
「人形みたいだなあ」
言いざま、入道は友成の左足に手刀を当てた。
「あ」
鈍い音がした。
「ああ、壊れちまった。腕はどうだろうなあ」
入道は順番に手足の骨を砕いて、なぶり殺しにする気だ。
出居はちらちらと帝の顔をうかがってなかなか判定を出さない。
私は名誉なんていらない。一生友成のそばにいて、友成の笛を聴きたいだけ。
「お姉さま、檜扇を貸して」
桔梗は杏子から檜扇を奪った。
「ちょっとどいて、どいて。どきなさい!」
人混みを掻きわけて、良い位置を見つけた。角力入道の頭の上に太陽が照り輝いている。
桔梗は声の限りに叫んだ。
「角力入道さまあああ。素敵~!こっちを見てえ~!」
「ん?」
振り返った入道に向けて檜扇を広げた。
「うっ……!」
ぎらぎらした檜扇に反射した光が角力入道の目を射る。
驚いて緩めた手から友成が滑り落ちた。
「勝負あった。勝者、角力入道」
すぐさま出居が審判を下す。
地面に仰向けになった友成がはあはあと荒い息をついている。悔し涙だろうか、ごしごしと手で拭っている。
「友成……!」
立ちあがろうとするが左足に力が動かないようだ。
「手当てをしてやれ」
帝の指示により友成は控えの間に連れられていった。
その途中でちらと桔梗を振り返った友成の瞳は空虚だった。
友成の容態が心配だ。なんとかして控えの間に忍び込まねば。
人混みに揉まれてなかなか移動できないでいる桔梗の耳朶に帝の言葉が流れ込んでくる。
「素晴らしい戦いだった。角力入道よ。お主が戦う姿をもっと見たかったのだが、思いの外参加者が少なくて実に残念だった」
「わしもそう思うておりました。都人は意気地がないことですな」
角力入道が出場者を脅して辞退させたことを帝は知りもしない。脅しに屈せず参加した者は称えられるべきだ。桔梗は悔しさに奥歯を噛みしめた。
「そうか、やはり物足りなかったか」
「はい、物足りません。もし望む者がいれば飛び込みで参加してもらいたいくらいですわ、がっはっは」
「そうか、それはいい」
帝は庶民席に視線を移した。
「誰ぞ。勇者はおらぬか」
会場はしんと静まる。
「誰もいないのか。このさい、近衛府の者でも蔵人衆でもよいぞ」
みな一斉に顔をうつむかせる。化け物と好んで戦いたい者などいない。
角力入道は腕を組んで、得意げに鼻の穴を広げた。
「ふうむ」
帝は優雅に扇を揺らしたあと、首を傾げた。
「面白そうなのに誰も手をあげぬか。では、しかたない、わ──」
「はい!」
桔梗はまっすぐに腕を上げた。
会場は一瞬静まったあと、どっと笑声がわく。
「お嬢ちゃん、にらめっこじゃないんだぞ」
「この細っこい体でなにをする気だ」
桔梗の挙手に、角力入道はぽかんと口を開けた。
嘲笑にかまってなぞいられなかった。桔梗は柵から身を乗り出した。
「女が挑戦してはいけないのですか。高札にはそんなことは書いてなかったですよね」
帝がにやりと笑った。
「面白い女子だ。かまわん。中央に出てこい」
おおお、と地鳴りのような音が響き渡った。
「なんという無慈悲な帝だ」
「むごいことじゃ」
「ああいうでしゃばりな女にはいい薬だろう」
桔梗は柵を乗り越えた。
「諸肌脱ぎになるので、代わりにさらし布を巻かせてください」
控えの間に案内された。屏風や几帳で仕切られた中で手渡されたさらしを胸が邪魔にならないようにきつく巻いた。
無闇に肌をさらすのははしたないことだとはわかっている。だが諸肌脱ぎにならなければ、短衣の襟を掴まれやすい。弱点はふさいでおかなければ。
準備をしながら、友成を探した。
奥の几帳の裏に長椅子があった。そこに友成は横たわっていた。青白い顔で目を瞑っている。
「と、友成!?」
「大丈夫だ。気を失っているだけだから」
帝の侍医と名乗る男が友成の足に添え木を指さした。
「三月もすれば歩けるようになる」
「よかった」
「お嬢ちゃん、裏口はあっちだ。そっと出て行くがいい」
侍医は桔梗の小さな体を見やって、ぽそりと囁いた。
「え」
「女子の骨など脆いものだ。筋肉の鎧もないのだろう。粉々になったら骨接ぎもできん」
「ご心配はたいへんありがたく、でも」
祈りの形に合わさっていた荒れた手に目を落とし、ぎゅっとこぶしを握った。
「女でも戦わねばならないときはあるのです」
「愚かな。女が名誉を欲するのか」
名誉を欲する女が愚かかどうかはわからない。だが桔梗が欲するのは名誉ではなかった。
「この戦い、勝てば帝から賞金がいただけます。それがあれば父の命を救える。それに友成をいたぶった角力入道にせめて一矢報いねば、生涯後悔することでしょう」
「いずれ命を粗末にするのは愚かなことにかわらんぞ。一矢報いる方法はきっとほかにもある」
「……粗末にしないよう、気をつけます。友成をよろしくお願いします」
もの言いたげな侍医を断ち切るように桔梗は会場に戻った。