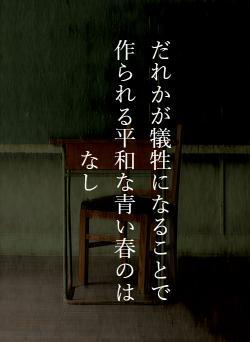四 友成の戦い
「私たちは十条家です。どきなさい。ちょっと桔梗、こんな汚い地べたに座るなんてとんでもないわ。畳か倚子を用意しなさい」
義母の一喝は庶民席に充分な空白を作った。
眺めのいい場所を確保したためか、久しぶりに気分転換ができるからか、義母の機嫌がよくなっている。
「ほら、楼台に向けて、玉をかざしなさい。注目を集めなさい。唐衣をひらひらさせるのです」
姉たちはしかたないといったようすで、キラキラと光る特別仕立ての檜扇を顔の前で閃かせた。
庶民席に十二単の装束があるだけで充分注目を集めているとは思うのだが。
徐々に埋まっていく貴族席を見上げ、始まりが近いことを知る。
「あら、桔梗。どこへ行くの」
「友成を探してきます」
腰をあげたとき、会場がざわざわと波立った。帝の来臨だ。楼台の一番高い位置にしつらえられた倚子に今上帝が腰をおろす。歓声がわいた。扇で顔が見えないが青年のようだった。
太鼓が鳴らされ、試合開始が告げられた。
友成を探している時間はない。せめてひとことでも応援の声をかけてあげたかったのに。桔梗はがっくりと腰を落とした。
「相撲人をここへ」
控えの間に続くと思われる布幕の奥から、武官に引率された参加者が姿を現した。
はやし立てる声が湧き上がった。
「いた、友成だ」
二番目に現れたのが友成だった。友成の顔は緊張で硬直していた。きりりとした眉はりりしく、なにかを狙いすましたような目は力にみなぎっていた。
だが前後の男たちに比べたら、その体躯はまるで子供だった。武官を望む庶民は体を鍛えているのが当然なのだろう。
最後に現れた人物に、観衆はどよめいた。
「なんだ、あれは」
「化け物じゃねえか」
角力入道だ。薄気味悪い笑みを浮かべ、ひとり悠々と肩を揺らしている。
どよめきが去ると、人々は口々に囁きだした。
「おい、これだけか」
「たったの六人かよ」
「しかたないだろう、あの大男を見たら誰でも逃げ出すわ」
桔梗は声の限りで叫んだ。
「友成! いまからでいいから辞退して!」
友成は桔梗の声に気がついたのだろう、ひょいと顔をあげると微笑んだ。
「桔梗、応援しててくれ。かならず勝って賞金を取る。それから……いや、それはまたあとで」
「友成!」
太鼓と鉦が鳴り、会場がしんと静まった。
くじ引きにより相撲人は三人一組に分かれた。まずそのうちの二人が戦い、勝った方が残ったもう一人と戦う。それぞれの組で勝ったもの同士で決勝戦を行うと説明がある。
友成は角力入道とは別の組になった。組分けが二つしかないため便宜上、左組と右組と呼ばれることになった。友成のいるほうは右組、入道がいるほうは左組だ。
もう一度くじを引き、友成は初戦と決まる。
友成の負けを願うのも心苦しい。かといって勝ち進んだら入道と対戦するはめになってしまう。
「出世してほしいし賞金も惜しいけれど、友成の命には代えられないよ」
怪我のひとつもしないうちに、さっくりと負けてほしかった。両手を合わせ、はらはらしながら成りゆきを見守るしかない自分が情けなかった。
参加者はみな諸肌を脱ぎ、腰に細帯をぐるぐると巻いた。
女性たちから「ほう」と溜息が漏れる。鍛え上げられた肉体の持ち主が四人。化け物が一人。
細くしなやかな友成を見つめているのは桔梗しかいなかった。
右組の第一戦、友成と対戦したのは漁師だった。
「友成、がんばって」
そして適当なところで負けて、と心中で叫ぶ。
友成とがっぷり組んだ漁師は背中から肩、腕にかけてこぶのような筋肉が盛り上がっている。
「あの小僧は童相撲と間違えたんじゃないか」
「おい、手加減してやれ」
「見応えのない取組だなあ」
無責任な言葉が飛び交う。
楼台を見上げると、帝は組んだ足の上で肘をつき、頬杖をついた。絵に描いたような退屈の表現だ。
いくら帝とはいえ、眼前で懸命に頑張っている人間にたいして失礼な態度ではないか。
友成が近衛府になったらこの帝の身辺警護の任につくのだ。そう思うと無性に腹立たしくなった。
「ううう」
友成の食いしばった歯のあいだから唸り声が聞こえてくる。
漁師の腕に抱き潰された友成の肩がいまにも音を立てて折れそうだ。
「友成!」
「よし、そのまま倒せ」
「背中に土がつけば負けだ」
帯を掴んで左右に振り切ろうとする漁師。必死に食らいついていく友成。
友成の踏ん張りは素晴らしいが、このままでは楽師として大切な腕を骨折してしまうのではないか。
「友成、足を使って!」
思わず声を出していた。
声が聞こえたのか、友成は片足を漁師の足首に引っかけた。
「おおっ……?!」
次の瞬間、どんと音がし、漁師は仰向けに倒れた。
胸に抱えられる形の友成がひょこりと顔を上げた。
桔梗と視線が合う。
「やった!」
桔梗は両腕をふりあげた。
友成が片腕を高くあげて応える。
会場が歓声に包まれた。
ふと楼台を見上げると、帝は蔵人衆を呼び寄せてなにか告げていた。
「見事であった」
蔵人衆が帝の言葉を伝えた。間接的ではあるが友成を讃えたのだ。
桔梗は広場と客席を分かつ柵をぎゅっと掴んだ。形容しがたい思いが胸中で渦を巻く。
負けてほしかったのに、友成の快勝は嬉しかった。誇らしさで目頭が熱くなる。心配で胸が張り裂けそうなのに目標に向かって一所懸命に手を伸ばしている姿を目の前にして応援したくなったのだった。
「私たちは十条家です。どきなさい。ちょっと桔梗、こんな汚い地べたに座るなんてとんでもないわ。畳か倚子を用意しなさい」
義母の一喝は庶民席に充分な空白を作った。
眺めのいい場所を確保したためか、久しぶりに気分転換ができるからか、義母の機嫌がよくなっている。
「ほら、楼台に向けて、玉をかざしなさい。注目を集めなさい。唐衣をひらひらさせるのです」
姉たちはしかたないといったようすで、キラキラと光る特別仕立ての檜扇を顔の前で閃かせた。
庶民席に十二単の装束があるだけで充分注目を集めているとは思うのだが。
徐々に埋まっていく貴族席を見上げ、始まりが近いことを知る。
「あら、桔梗。どこへ行くの」
「友成を探してきます」
腰をあげたとき、会場がざわざわと波立った。帝の来臨だ。楼台の一番高い位置にしつらえられた倚子に今上帝が腰をおろす。歓声がわいた。扇で顔が見えないが青年のようだった。
太鼓が鳴らされ、試合開始が告げられた。
友成を探している時間はない。せめてひとことでも応援の声をかけてあげたかったのに。桔梗はがっくりと腰を落とした。
「相撲人をここへ」
控えの間に続くと思われる布幕の奥から、武官に引率された参加者が姿を現した。
はやし立てる声が湧き上がった。
「いた、友成だ」
二番目に現れたのが友成だった。友成の顔は緊張で硬直していた。きりりとした眉はりりしく、なにかを狙いすましたような目は力にみなぎっていた。
だが前後の男たちに比べたら、その体躯はまるで子供だった。武官を望む庶民は体を鍛えているのが当然なのだろう。
最後に現れた人物に、観衆はどよめいた。
「なんだ、あれは」
「化け物じゃねえか」
角力入道だ。薄気味悪い笑みを浮かべ、ひとり悠々と肩を揺らしている。
どよめきが去ると、人々は口々に囁きだした。
「おい、これだけか」
「たったの六人かよ」
「しかたないだろう、あの大男を見たら誰でも逃げ出すわ」
桔梗は声の限りで叫んだ。
「友成! いまからでいいから辞退して!」
友成は桔梗の声に気がついたのだろう、ひょいと顔をあげると微笑んだ。
「桔梗、応援しててくれ。かならず勝って賞金を取る。それから……いや、それはまたあとで」
「友成!」
太鼓と鉦が鳴り、会場がしんと静まった。
くじ引きにより相撲人は三人一組に分かれた。まずそのうちの二人が戦い、勝った方が残ったもう一人と戦う。それぞれの組で勝ったもの同士で決勝戦を行うと説明がある。
友成は角力入道とは別の組になった。組分けが二つしかないため便宜上、左組と右組と呼ばれることになった。友成のいるほうは右組、入道がいるほうは左組だ。
もう一度くじを引き、友成は初戦と決まる。
友成の負けを願うのも心苦しい。かといって勝ち進んだら入道と対戦するはめになってしまう。
「出世してほしいし賞金も惜しいけれど、友成の命には代えられないよ」
怪我のひとつもしないうちに、さっくりと負けてほしかった。両手を合わせ、はらはらしながら成りゆきを見守るしかない自分が情けなかった。
参加者はみな諸肌を脱ぎ、腰に細帯をぐるぐると巻いた。
女性たちから「ほう」と溜息が漏れる。鍛え上げられた肉体の持ち主が四人。化け物が一人。
細くしなやかな友成を見つめているのは桔梗しかいなかった。
右組の第一戦、友成と対戦したのは漁師だった。
「友成、がんばって」
そして適当なところで負けて、と心中で叫ぶ。
友成とがっぷり組んだ漁師は背中から肩、腕にかけてこぶのような筋肉が盛り上がっている。
「あの小僧は童相撲と間違えたんじゃないか」
「おい、手加減してやれ」
「見応えのない取組だなあ」
無責任な言葉が飛び交う。
楼台を見上げると、帝は組んだ足の上で肘をつき、頬杖をついた。絵に描いたような退屈の表現だ。
いくら帝とはいえ、眼前で懸命に頑張っている人間にたいして失礼な態度ではないか。
友成が近衛府になったらこの帝の身辺警護の任につくのだ。そう思うと無性に腹立たしくなった。
「ううう」
友成の食いしばった歯のあいだから唸り声が聞こえてくる。
漁師の腕に抱き潰された友成の肩がいまにも音を立てて折れそうだ。
「友成!」
「よし、そのまま倒せ」
「背中に土がつけば負けだ」
帯を掴んで左右に振り切ろうとする漁師。必死に食らいついていく友成。
友成の踏ん張りは素晴らしいが、このままでは楽師として大切な腕を骨折してしまうのではないか。
「友成、足を使って!」
思わず声を出していた。
声が聞こえたのか、友成は片足を漁師の足首に引っかけた。
「おおっ……?!」
次の瞬間、どんと音がし、漁師は仰向けに倒れた。
胸に抱えられる形の友成がひょこりと顔を上げた。
桔梗と視線が合う。
「やった!」
桔梗は両腕をふりあげた。
友成が片腕を高くあげて応える。
会場が歓声に包まれた。
ふと楼台を見上げると、帝は蔵人衆を呼び寄せてなにか告げていた。
「見事であった」
蔵人衆が帝の言葉を伝えた。間接的ではあるが友成を讃えたのだ。
桔梗は広場と客席を分かつ柵をぎゅっと掴んだ。形容しがたい思いが胸中で渦を巻く。
負けてほしかったのに、友成の快勝は嬉しかった。誇らしさで目頭が熱くなる。心配で胸が張り裂けそうなのに目標に向かって一所懸命に手を伸ばしている姿を目の前にして応援したくなったのだった。