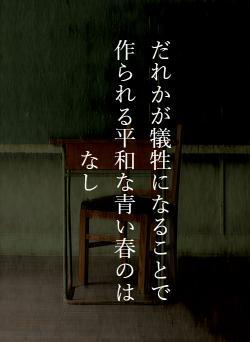三 相撲の宴
いつもどおり忙しい日々を送っているうちに、相撲の宴当日を迎えてしまった。
あれから友成とは会っていない。
桔梗が「参加しないで」と請えば、友成はますます意固地になってしまうだろう。
「桔梗、桔梗」
義母が呼んでいる。
「もっと派手な唐衣はなかったかしらね」
急いで向かうと十二単に裳までつけた盛装でたたずむ姉二人を、義母がさらに飾り立てようとしている。
「七色の糸で刺繍したものがあったでしょう」
「そういえば檜扇もあったわね。蝙蝠では威儀が正せないわ」
「檜扇に磨いた玉を下げましょう。遠くからでも輝くように」
「……いったいどうしたのです。その装いは……?」
義母はまなじりを吊り上げた。
「これから帝ご臨席の相撲の宴があるのですよ」
「はい」
「本来なら貴族席で観覧できる身分ですけど、いまは庶民の席で我慢するしかありませんね」
耳を疑った。屋敷の奥深くで暮らしていた三人が、相撲の宴を観覧に行くというのだ。
「相撲、お好きでいらしたんですね」
「まさか。相撲なんてどうでもいいのよ。で、桔梗、牛車と牛はどこにあるの」
「牛車はありますが……牛はもうとうに」
売り払ってしまっています。牛車も処分する予定でした。などと口にできる雰囲気ではなかった。
だが義母は察したらしく、顔をしかめた。
「まあ、じゃあどうしたらよいというの。そこらの庶民にまじって観ろとでも」
「牛車で庶民席に乗り込むのは無理があります。あの……どうしてそこまでして相撲の宴を観にいかれるのですか」
「わからないの。そんなのきまっているじゃないの」
義母は蝙蝠で口元を隠した。笑っているようだ。
「帝のお目に留まるかもしれないでしょ」
なるほどと納得した。だからやたらギラギラと派手に飾り立てているのだ。
「帝のほかにも貴族の若君が数多臨席するのですよ。泥臭い相撲を観戦して気が高ぶったところで、ふと目をやると華やかな姫が神々しく座している。泥中の蓮のごとし。あの煌びやかな姫はどのようなかたなのかと興味を持たれて、桜子や杏子に文が殺到すること間違いなしっ!」
義母の読みはなるほどと膝を打つものではあった。
だが牛車を用意できないのではせっかくの十二単も披露のしようがない。牛車には御簾を垂らすので、どちらにしても、衣装の一部を牛車の外に垂らして気を惹くのが精一杯なのだが。
続けて義母はとんでもないことを言い出した。
「では桔梗、おまえが牛の代わりに牛車を牽いて行きなさい」
「……」
桔梗は父に朝餉を持っていき、病状が悪化していないことに安堵すると、牛車の用意をした。
三人を載せた牛車は呻くほどに重かったが会場まではたいした距離ではない。なんとかなるだろうと高をくくっていたが、牛車はいっこうに前に進まなかった。
「なにをしているの桔梗」
「すみません、道が混雑していて……」
大路も小路も人がごった返している。相撲は格好の見世物だ。相撲を観に都人が大挙して押し寄せているのだろう。
「こまったわね、これじゃ辿り着けやしない」
いったん屋敷に戻ると義母は眉間に皺を寄せて嘆いた。
「桜子と杏子を目立たせるにはどうしたらいいの」
「ひとつ提案があります」
三人は一斉に興味のまなざしを桔梗に注いだ。
「相撲の合間に歌舞楽を披露するそうです。節会では宮廷楽師と女官が役にあたりますが、今回は庶民の参加を募っています。姉様がた、歌や舞をご披露されてはいかがでしょうか。桜子お姉様は声量がおありですから歌を、杏子お姉様は所作が優美ですから舞を。上手くいけば帝を魅了できるかもしれません」
「庶民の歌舞など、田植え歌のようなもんだろうに。そんな中に混じるなんて恥ずかしいことよ」
義母は気乗りしないようすだったが、桜子と杏子は互いに顔を見合わせた。
「かえって目立つかもしれませんことよ」
「でも、顔容を晒すわけには……」
「薄布を垂らしておけばよいのです」
桔梗の案に姉二人は小さく頷いた。
「おまえたち、本気かえ」
「だってお母様、このまま朽ちるのは悔しいではありませんか」
珍しく桜子が母親に言い返した。杏子も諾と言いそえる。
「私は良いとは思わないが……おまえたちがいいなら……」
義母は不承不承のていで了承した。
だがそれからが大変だった。せっかく盛装したのだ、十二単で参加したいというものだから、姉たちは長袴をたくしあげ十二単の裾を抱えあげて人混みに突入した。
「十条家が通りますよ。ほら、さっさとどきなさい」
先導する母親ともども猛烈な勢いで会場まで進んでいく。
桔梗は姉の衣を担ぐのを手伝いつつ、最後尾についた。
「なんだ、あれは」
「ほほう、十条の姫か」
「ああ、あの零落した……」
好奇の目が姉たちに注ぐ。心ない言葉も降ってくる。
幸い、参加希望はまだ募っていた。担当の官吏は歓迎してくれた。
「十条の姫様がたとは、これはこれは、華があってよい。優勝者を称える宴で披露してもらうのがふさわしい」
「もっとも盛り上がる頃ですわね」
義母はにこやかに笑む。
「実は」ここで係官が顔をくもらせた。「歌舞楽は何回かに分けて披露する予定だったのだ。相撲の参加者は多いだろうと踏んでいたからな。一回戦のあと、決勝戦の前、優勝者を讃える宴……など合間合間に挟む予定だったのだが、最後の一回だけに変更になってしまったのだ」
「あら、最後の一回に参加できるなんて、運がいいこと。でもなぜなんです?」
担当者は頭を掻いた。
「相撲の参加者が次々に辞退しちゃってね。案外早く終わりそうなんだ。宴の時間を延ばしてなんとか体裁を整えないといかん……」
相撲の参加者が次々に辞退した──理由はあきらかだ。
桔梗は胸騒ぎをおさえて確かめた。
「角力入道ですね。あの大男が出場するからでしょう」
「そうだ。あいつを怖れて棄権者が続出している。お嬢さん、よく知ってるな」
「あの、友成は、佐原友成は、棄権したでしょうか」
「ええ、と、佐原友成……?」
担当官はぱらぱらと名簿をめくり、ああ、と声を出した。
「彼は参加しますよ。数少ない貴重な参加者だ。爽やかな若者だが……殺されないといいなあ」
その声音にはすでに諦観が滲んでいた。
この会場のどこかに友成がいる。そう思うといてもたってもいられない気持ちになった。
いつもどおり忙しい日々を送っているうちに、相撲の宴当日を迎えてしまった。
あれから友成とは会っていない。
桔梗が「参加しないで」と請えば、友成はますます意固地になってしまうだろう。
「桔梗、桔梗」
義母が呼んでいる。
「もっと派手な唐衣はなかったかしらね」
急いで向かうと十二単に裳までつけた盛装でたたずむ姉二人を、義母がさらに飾り立てようとしている。
「七色の糸で刺繍したものがあったでしょう」
「そういえば檜扇もあったわね。蝙蝠では威儀が正せないわ」
「檜扇に磨いた玉を下げましょう。遠くからでも輝くように」
「……いったいどうしたのです。その装いは……?」
義母はまなじりを吊り上げた。
「これから帝ご臨席の相撲の宴があるのですよ」
「はい」
「本来なら貴族席で観覧できる身分ですけど、いまは庶民の席で我慢するしかありませんね」
耳を疑った。屋敷の奥深くで暮らしていた三人が、相撲の宴を観覧に行くというのだ。
「相撲、お好きでいらしたんですね」
「まさか。相撲なんてどうでもいいのよ。で、桔梗、牛車と牛はどこにあるの」
「牛車はありますが……牛はもうとうに」
売り払ってしまっています。牛車も処分する予定でした。などと口にできる雰囲気ではなかった。
だが義母は察したらしく、顔をしかめた。
「まあ、じゃあどうしたらよいというの。そこらの庶民にまじって観ろとでも」
「牛車で庶民席に乗り込むのは無理があります。あの……どうしてそこまでして相撲の宴を観にいかれるのですか」
「わからないの。そんなのきまっているじゃないの」
義母は蝙蝠で口元を隠した。笑っているようだ。
「帝のお目に留まるかもしれないでしょ」
なるほどと納得した。だからやたらギラギラと派手に飾り立てているのだ。
「帝のほかにも貴族の若君が数多臨席するのですよ。泥臭い相撲を観戦して気が高ぶったところで、ふと目をやると華やかな姫が神々しく座している。泥中の蓮のごとし。あの煌びやかな姫はどのようなかたなのかと興味を持たれて、桜子や杏子に文が殺到すること間違いなしっ!」
義母の読みはなるほどと膝を打つものではあった。
だが牛車を用意できないのではせっかくの十二単も披露のしようがない。牛車には御簾を垂らすので、どちらにしても、衣装の一部を牛車の外に垂らして気を惹くのが精一杯なのだが。
続けて義母はとんでもないことを言い出した。
「では桔梗、おまえが牛の代わりに牛車を牽いて行きなさい」
「……」
桔梗は父に朝餉を持っていき、病状が悪化していないことに安堵すると、牛車の用意をした。
三人を載せた牛車は呻くほどに重かったが会場まではたいした距離ではない。なんとかなるだろうと高をくくっていたが、牛車はいっこうに前に進まなかった。
「なにをしているの桔梗」
「すみません、道が混雑していて……」
大路も小路も人がごった返している。相撲は格好の見世物だ。相撲を観に都人が大挙して押し寄せているのだろう。
「こまったわね、これじゃ辿り着けやしない」
いったん屋敷に戻ると義母は眉間に皺を寄せて嘆いた。
「桜子と杏子を目立たせるにはどうしたらいいの」
「ひとつ提案があります」
三人は一斉に興味のまなざしを桔梗に注いだ。
「相撲の合間に歌舞楽を披露するそうです。節会では宮廷楽師と女官が役にあたりますが、今回は庶民の参加を募っています。姉様がた、歌や舞をご披露されてはいかがでしょうか。桜子お姉様は声量がおありですから歌を、杏子お姉様は所作が優美ですから舞を。上手くいけば帝を魅了できるかもしれません」
「庶民の歌舞など、田植え歌のようなもんだろうに。そんな中に混じるなんて恥ずかしいことよ」
義母は気乗りしないようすだったが、桜子と杏子は互いに顔を見合わせた。
「かえって目立つかもしれませんことよ」
「でも、顔容を晒すわけには……」
「薄布を垂らしておけばよいのです」
桔梗の案に姉二人は小さく頷いた。
「おまえたち、本気かえ」
「だってお母様、このまま朽ちるのは悔しいではありませんか」
珍しく桜子が母親に言い返した。杏子も諾と言いそえる。
「私は良いとは思わないが……おまえたちがいいなら……」
義母は不承不承のていで了承した。
だがそれからが大変だった。せっかく盛装したのだ、十二単で参加したいというものだから、姉たちは長袴をたくしあげ十二単の裾を抱えあげて人混みに突入した。
「十条家が通りますよ。ほら、さっさとどきなさい」
先導する母親ともども猛烈な勢いで会場まで進んでいく。
桔梗は姉の衣を担ぐのを手伝いつつ、最後尾についた。
「なんだ、あれは」
「ほほう、十条の姫か」
「ああ、あの零落した……」
好奇の目が姉たちに注ぐ。心ない言葉も降ってくる。
幸い、参加希望はまだ募っていた。担当の官吏は歓迎してくれた。
「十条の姫様がたとは、これはこれは、華があってよい。優勝者を称える宴で披露してもらうのがふさわしい」
「もっとも盛り上がる頃ですわね」
義母はにこやかに笑む。
「実は」ここで係官が顔をくもらせた。「歌舞楽は何回かに分けて披露する予定だったのだ。相撲の参加者は多いだろうと踏んでいたからな。一回戦のあと、決勝戦の前、優勝者を讃える宴……など合間合間に挟む予定だったのだが、最後の一回だけに変更になってしまったのだ」
「あら、最後の一回に参加できるなんて、運がいいこと。でもなぜなんです?」
担当者は頭を掻いた。
「相撲の参加者が次々に辞退しちゃってね。案外早く終わりそうなんだ。宴の時間を延ばしてなんとか体裁を整えないといかん……」
相撲の参加者が次々に辞退した──理由はあきらかだ。
桔梗は胸騒ぎをおさえて確かめた。
「角力入道ですね。あの大男が出場するからでしょう」
「そうだ。あいつを怖れて棄権者が続出している。お嬢さん、よく知ってるな」
「あの、友成は、佐原友成は、棄権したでしょうか」
「ええ、と、佐原友成……?」
担当官はぱらぱらと名簿をめくり、ああ、と声を出した。
「彼は参加しますよ。数少ない貴重な参加者だ。爽やかな若者だが……殺されないといいなあ」
その声音にはすでに諦観が滲んでいた。
この会場のどこかに友成がいる。そう思うといてもたってもいられない気持ちになった。