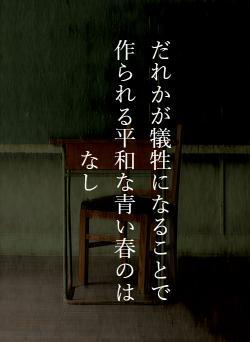二 誓い
夕餉を用意し、洗濯と縫い物を終えたころには灯りが恋しい頃合いなってしまった。築地塀の修繕は後日にしよう。
なんとはなしに庭に出てみた。どこからか笛の音が聞こえてくる。
「あの音色は友成だ」
崩れた築地塀をまたいで外に出る。
音を辿ると友成が楼台に腰掛けて龍笛を吹いていた。龍笛は竹でできた管楽器で、篳篥の旋律を装飾する役割なのだが、桔梗は高く響く龍笛の独奏が好きだった。
「友成!」
楼台は皇族や貴族が高覧する場所なので高く作られている。
「いいのかしら、ここ」
「だれもいない」
木工も衛士もいないのを見計らい、楼台のふちに友成と並んで座った。
雲ひとつない夜空には星が輝いている。
「友成の笛は疲れた体に効くね。凄く元気が出る」
「そうかな。そんなこと言うの、桔梗ぐらいだよ。師匠にはよく音が澄みすぎていると叱られるんだから」
友成は照れたように笑う。
すこんと突き抜けたような友成の笛の音色は龍笛の役目を逸脱していると叱られているのは本当のことらしい。だが桔梗にとってはお世辞でもなんでもなく、友成の笛は真夏の涼風のように心地よかった。体はもちろん心の中の汚泥もすっかり取り除いてくれる。隠れていた元気が湧いてくるのだ。
大きく息を吐き出すとさらに気持ちが楽になる。
義母や姉に過大な期待をしてもしかたない。だれかに期待するひまがあれば自分が動けばいいんだ。
姉たちのように、屋敷の奥深くでひっそりと暮らすのが貴族の令嬢のたしなみである。まずは文のやり取りから始めて几帳や御簾越しに言葉を交わし、意気投合すれば……。
三夜連続で男が通うと婚姻成立。桔梗が知るかぎり、姉たちの元に男が忍んできたことはない。それは自分も同じだが、奴婢扱いの桔梗には結婚は望むべくもないと思っている。期待するだけ傷つく。
「ここで相撲の宴が開かれるのね。七月の相撲節会とはなにが違うのかしら」
相撲節会は左右近衛府から屈強な兵士が選ばれ、帝の御前で行われる。武芸の奨励が目的だが、豊穣を願う神事でもある、重要な宮中行事のひとつだ。
「今上帝は相撲がお好きらしい。だからいつも同じような顔ぶれに飽きてしまったんだろう。本番の節会に向けて新しい相撲人を広く大衆から集めたいのさ」
「相撲の宴、というからには、宴が催されるの」
「列席する貴族の目的はそっちだろうね。合間に歌舞楽もあるそうだから」
「あら、じゃあ、友成は忙しいのね」
「いえ、今回は楽師や舞姫も庶民から募るそうです。だから俺は相撲に集中する。もう参加登録も済ませた。……頑張って優勝します」
友成は桔梗の手をぐいと掴んだ。
「?? 友成?」
「優勝したら近衛府の武官になれる。だから、もし、もし俺が優勝したら……求婚させてほしい」
友成の掌が熱い。かすかに震えている。
桔梗はしばし言葉を失ってしまった。
いま、友成はなんと言った。
「キュウコン?」
頭の中で言葉がバラバラになる。
「俺と結婚してほしいんだ。妻になってくれ。祝言をあげよう! どう、聞こえた?」
「うん、びっくりした」
衝撃に目を瞬かせつつも、桔梗は友成を見つめた。
「武官になれば桔梗の家とも釣り合うだろ。優勝したら武官になれるだけでなく賞金ももらえる。お父さんの病気も治せるし、下働きも雇える。桔梗を楽にさせてあげられると思うんだ」
熟した柿のような顔色で、友成は必死で説得してくる。友成が本気だとわかって、桔梗の胸は急に激しく鳴り始めた。
まさか友成が結婚を望んでいたなんて思ってもみなかった。なにより桔梗の身の上をよく理解したうえで家族のことまで考えてくれていることが嬉しかった。
「まだ返事はしないでくれ。優勝したときにあらためて求婚するから」
「うん、待ってる」
答えはもう決まっている。高鳴る胸を必死で抑えつつ、友成の優勝を星に祈った。
さっきまで結婚を諦めていたのが嘘のようだ。
「もう一度、笛を聴かせて」
「いいよ」
友成が手汗を拭って、いつもより緊張しながら笛を手にしたとき、楼台がぎしと嫌な音を立てた。
「おまえが相撲の宴に出るだと。笑わせやがる」
獣声じみた低い声がして、楼台の床板がギギギと悲鳴を上げた。
目の前に現れたのは雲を突くような大男である。
「やめておけ。ガキは殺したくない」
友成の三倍はあると思われる大きな顔をぬっと近づけてきた。ぎょろっとした丸い目玉は充血し、てかてかした頭には毛が一本もない。
「あんた、誰だ」
友成の声は震えている。これほどの巨体を前にしてに怯まない者はいないだろう。
桔梗にいたっては山で熊に遭遇したときのような心持ちだった。
「わしは角力入道という者だ。優勝するのはわしにきまっとる。無駄死にはするな」
殺すやら無駄死にやらの言葉が桔梗の頭にこだまする。
「相撲って、し、死ぬまで戦うの」
「まさか。素手で組み合って、どちらか、背中に土がついたほうが負けだ」
友成の返答にほっと息をついた桔梗を見て、角力入道はガハハと笑う。
「わしは手加減がわかんねえんだ。軽く叩いたりちょんと蹴ったりするだけで、相手の首の骨が折れたり腰が砕けたりしちまうんだ。だからやめておけ。わしからの親切な忠告だ」
角力入道はみずからの拳を握ってバキバキと骨を鳴らした。
自分の骨が砕かれたような気がして、首がすくむ。
「命が惜しけりゃ賢明になれ」
二人の怯えた姿を見て満足したのか、角力入道はひとつ鼻息を吐くと、品のない笑い声を残して去って行った。
「まるで地獄の鬼のよう。あんな人が参加するなんて。友成、やめておいたほうがいい」
「脅しに負けてたまるか。俺は出場するよ。優勝して、そして……」
「友成」
仰ぎ見た友成の顔はすっかり青白くなっていた。
「もう遅い。帰ろう」
ぎこちない笑顔。どう説得すべきかわからずにもどかしい。
『優勝しなくても、いや、参加しなくても、友成に求婚されたら応じるから。だから参加を取りやめて』
出かかった言葉は喉元にひっかかって音にならない。友成が欲しているのはそんな約束ではないのだ。
せめて角力入道と当たりませんようにと星に願う桔梗だった。
夕餉を用意し、洗濯と縫い物を終えたころには灯りが恋しい頃合いなってしまった。築地塀の修繕は後日にしよう。
なんとはなしに庭に出てみた。どこからか笛の音が聞こえてくる。
「あの音色は友成だ」
崩れた築地塀をまたいで外に出る。
音を辿ると友成が楼台に腰掛けて龍笛を吹いていた。龍笛は竹でできた管楽器で、篳篥の旋律を装飾する役割なのだが、桔梗は高く響く龍笛の独奏が好きだった。
「友成!」
楼台は皇族や貴族が高覧する場所なので高く作られている。
「いいのかしら、ここ」
「だれもいない」
木工も衛士もいないのを見計らい、楼台のふちに友成と並んで座った。
雲ひとつない夜空には星が輝いている。
「友成の笛は疲れた体に効くね。凄く元気が出る」
「そうかな。そんなこと言うの、桔梗ぐらいだよ。師匠にはよく音が澄みすぎていると叱られるんだから」
友成は照れたように笑う。
すこんと突き抜けたような友成の笛の音色は龍笛の役目を逸脱していると叱られているのは本当のことらしい。だが桔梗にとってはお世辞でもなんでもなく、友成の笛は真夏の涼風のように心地よかった。体はもちろん心の中の汚泥もすっかり取り除いてくれる。隠れていた元気が湧いてくるのだ。
大きく息を吐き出すとさらに気持ちが楽になる。
義母や姉に過大な期待をしてもしかたない。だれかに期待するひまがあれば自分が動けばいいんだ。
姉たちのように、屋敷の奥深くでひっそりと暮らすのが貴族の令嬢のたしなみである。まずは文のやり取りから始めて几帳や御簾越しに言葉を交わし、意気投合すれば……。
三夜連続で男が通うと婚姻成立。桔梗が知るかぎり、姉たちの元に男が忍んできたことはない。それは自分も同じだが、奴婢扱いの桔梗には結婚は望むべくもないと思っている。期待するだけ傷つく。
「ここで相撲の宴が開かれるのね。七月の相撲節会とはなにが違うのかしら」
相撲節会は左右近衛府から屈強な兵士が選ばれ、帝の御前で行われる。武芸の奨励が目的だが、豊穣を願う神事でもある、重要な宮中行事のひとつだ。
「今上帝は相撲がお好きらしい。だからいつも同じような顔ぶれに飽きてしまったんだろう。本番の節会に向けて新しい相撲人を広く大衆から集めたいのさ」
「相撲の宴、というからには、宴が催されるの」
「列席する貴族の目的はそっちだろうね。合間に歌舞楽もあるそうだから」
「あら、じゃあ、友成は忙しいのね」
「いえ、今回は楽師や舞姫も庶民から募るそうです。だから俺は相撲に集中する。もう参加登録も済ませた。……頑張って優勝します」
友成は桔梗の手をぐいと掴んだ。
「?? 友成?」
「優勝したら近衛府の武官になれる。だから、もし、もし俺が優勝したら……求婚させてほしい」
友成の掌が熱い。かすかに震えている。
桔梗はしばし言葉を失ってしまった。
いま、友成はなんと言った。
「キュウコン?」
頭の中で言葉がバラバラになる。
「俺と結婚してほしいんだ。妻になってくれ。祝言をあげよう! どう、聞こえた?」
「うん、びっくりした」
衝撃に目を瞬かせつつも、桔梗は友成を見つめた。
「武官になれば桔梗の家とも釣り合うだろ。優勝したら武官になれるだけでなく賞金ももらえる。お父さんの病気も治せるし、下働きも雇える。桔梗を楽にさせてあげられると思うんだ」
熟した柿のような顔色で、友成は必死で説得してくる。友成が本気だとわかって、桔梗の胸は急に激しく鳴り始めた。
まさか友成が結婚を望んでいたなんて思ってもみなかった。なにより桔梗の身の上をよく理解したうえで家族のことまで考えてくれていることが嬉しかった。
「まだ返事はしないでくれ。優勝したときにあらためて求婚するから」
「うん、待ってる」
答えはもう決まっている。高鳴る胸を必死で抑えつつ、友成の優勝を星に祈った。
さっきまで結婚を諦めていたのが嘘のようだ。
「もう一度、笛を聴かせて」
「いいよ」
友成が手汗を拭って、いつもより緊張しながら笛を手にしたとき、楼台がぎしと嫌な音を立てた。
「おまえが相撲の宴に出るだと。笑わせやがる」
獣声じみた低い声がして、楼台の床板がギギギと悲鳴を上げた。
目の前に現れたのは雲を突くような大男である。
「やめておけ。ガキは殺したくない」
友成の三倍はあると思われる大きな顔をぬっと近づけてきた。ぎょろっとした丸い目玉は充血し、てかてかした頭には毛が一本もない。
「あんた、誰だ」
友成の声は震えている。これほどの巨体を前にしてに怯まない者はいないだろう。
桔梗にいたっては山で熊に遭遇したときのような心持ちだった。
「わしは角力入道という者だ。優勝するのはわしにきまっとる。無駄死にはするな」
殺すやら無駄死にやらの言葉が桔梗の頭にこだまする。
「相撲って、し、死ぬまで戦うの」
「まさか。素手で組み合って、どちらか、背中に土がついたほうが負けだ」
友成の返答にほっと息をついた桔梗を見て、角力入道はガハハと笑う。
「わしは手加減がわかんねえんだ。軽く叩いたりちょんと蹴ったりするだけで、相手の首の骨が折れたり腰が砕けたりしちまうんだ。だからやめておけ。わしからの親切な忠告だ」
角力入道はみずからの拳を握ってバキバキと骨を鳴らした。
自分の骨が砕かれたような気がして、首がすくむ。
「命が惜しけりゃ賢明になれ」
二人の怯えた姿を見て満足したのか、角力入道はひとつ鼻息を吐くと、品のない笑い声を残して去って行った。
「まるで地獄の鬼のよう。あんな人が参加するなんて。友成、やめておいたほうがいい」
「脅しに負けてたまるか。俺は出場するよ。優勝して、そして……」
「友成」
仰ぎ見た友成の顔はすっかり青白くなっていた。
「もう遅い。帰ろう」
ぎこちない笑顔。どう説得すべきかわからずにもどかしい。
『優勝しなくても、いや、参加しなくても、友成に求婚されたら応じるから。だから参加を取りやめて』
出かかった言葉は喉元にひっかかって音にならない。友成が欲しているのはそんな約束ではないのだ。
せめて角力入道と当たりませんようにと星に願う桔梗だった。