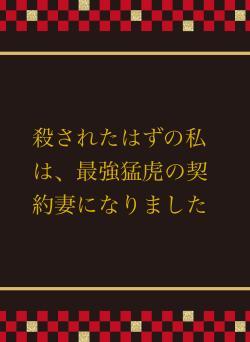ひだまりの美術室。連続的に聞こえてくる、鉛筆の芯が画用紙を擦る音。
それを心地良いと感じたのは、もしかすると生まれて初めてかもしれない。塁はじんわりと胸の奥が温まっていくのを覚えた。
何度も注がれる雪の真剣な視線が、対象物となる塁の横顔を捉える。そしてまた滑るように鉛筆を動かして、デッサンを完成へと導いていく。
夏休みまで、あと一週間という暑い日の出来事だった。
*
「三崎!」
二年生の教室が並ぶ廊下で、担任教師の柴に呼び止められた。帰りのSHRが終わり、いの一番に教室を出た塁が気怠けに振り返る。
「柴ちゃん,なに?」
吊り上がった目尻と威圧的な高身長が、近寄るなオーラを放つ。が、本人にその自覚はない。
センターパートの長い前髪と襟足、イエローブラウンに染めた髪色は校内でももちろん目立っていた。おまけに両耳にはピアスを計四つ光らせる。こんな派手な生徒、この高校には一人もいない。
そんなわけで全校生徒は学年問わず、みんな塁を周知している。さらに陰では“目が合っただけで討ち取られる三崎塁”という異名も囁かれていた。
「なに? じゃないよ。今日は三崎の三者面談日なんだぞ?」
「…………あ」
「帰る気だったな⁉︎」
全校生徒に恐れられている塁にも、柴は分け隔てなく接する。教師であり担任という立場ももちろんだが、そもそも柴は塁のことを手のつけられない問題児とは思っていなかった。どちらかというと、優秀な問題児。
「なるほど、面談だからそんな服着てんだ?」
「先生の服について触れなくていいんだよまったく」
普段はジャージだったりTシャツだったり、動きやすい服装をしている柴。それが今日は、カチッとした白ワイシャツに皺のないチノパンを穿いている。三十八歳、年相応の服装だけど、多分奥さんに選んでもらったんだろうなと塁が勝手に予想する。
高校二年生は年に一度しか行われない三者面談が、本日からはじまった。夏休み前の一週間が全て午前授業なのは、そのためだ。
「十六時に親御さんくるんだから、その時間は校内にいろよ?」
柴に言われた途端、塁は眉根を寄せてそっと視線を逸らす。
塁の唯一の"親御さん"である母が、今日の面談にくる保証がなかった。
ヘアサロンを三店舗経営していて、毎日忙しい日々を送っている。だから三者面談という大事な予定をスケジュールに組み込んだものの、本当にくるかは謎だった。仕事以外のことは、どうでもいいと思っている人だから。
柴の期待を裏切るかもしれない。後ろめたい気持ちを抱きつつ、塁は頭をかきながら返事をした。
「はいはい、学校にいればいいんだろ」
「あと柴ちゃんて呼ぶな。“柴先生”だ」
柴はキメ顔でそう指摘すると、面談準備のために職員室へと向かった。
面倒そうな表情を浮かべる塁は、重いため息をついて校内をぶらぶら歩く。
現在、午後の一時を過ぎた頃。
面談がある生徒は、一時帰宅してもいいし校内で時間を潰していてもいい。そして面談も部活もない生徒は、さっさと校門に向かい下校していく。
塁は三階の廊下の窓から、生徒たちの下校の様子を眺めていた。
(……家に帰るのも面倒だしな)
面談開始の十六時まで、まだまだ時間がある。
どこか静かなところで昼寝でもしようか。塁がそう考えていた時、突然背中に衝撃を受けた。
どかっという鈍い音と共に、塁がゆっくり振り返る。そこには他クラスの男子二人組が、しまったという顔で立っていた。
「ひぃ、三崎くん! すすすみませんでした!」
塁が先輩だったらまだわかる反応だが、同級生だというのにこの怯え様。まだ何も声を発していない塁の鋭い目つきは、怒っていなくても誤解されやすい。
二人組は青ざめたまま、逃げるようにその場を走って逃げていった。
今となってはこんなことで傷つかないし、誤解されることにも慣れている。
生まれ持った目つきは弄らない限り変えられないわけで、今更身長を縮めるなんてことも不可能。
元々無口で群れるのも苦手な塁にとっては、たいした問題ではなかった。
ただ、一つだけ納得していないことがある。
(誰だよ。目が合っただけで討ち取られるなんて変な異名言い出したやつは……)
いつから自分は武将扱いになったのだろうと思いながら、塁は廊下の姿見に映った自分を見る。
顔のパーツに触れるのはもうやめるとして。ワイシャツの首元はボタンを外し、深緑色のネクタイはゆるゆるにただぶら下がっているだけ。
鞄は教科書が入っているのか疑うほどに薄っぺらく、上履きの踵は踏んづけていてもはやスリッパ。
見た目は確かにヤンキー。ただ、これは自分が好んでいるスタイルという理由だけの、偽のヤンキー。
そのせいで他校のヤンキーに絡まれることはあったけれど、敵意がないことを話して持っていた飴を配り、安いカラオケ店を教えたらいつも穏便に済んでいた。
だから人を殴ったことも、ましてや討ち取るなんて行為もしたことがない。
(って説明する機会もないし、めんどいわ)
そう結論に至り、卒業までの残り一年半を変な異名に付き纏われる覚悟を決めていた。
塁が思考を巡らせながら歩いていると、いつの間にか静かな場所まできていた。
三階は二年生の教室があり、他にも部活動の教室も奥にある。塁がたまたま足を止めたのは、同じ階の美術室の前だった。
二年の教室から離れているせいか、帰り支度をする生徒の声も遠くに聞こえる。静かな時間が過ごせそうだと思った塁が、その扉に手をかけた。
特別教室は本来、利用する時以外は施錠が義務。なのにガラッと音を立てて、美術室の扉が簡単に開いてしまった。
(鍵かかってねーのかよ)
施錠忘れか、すでに誰かが中にいるのか。塁はそっと室内を覗いた。
閑散とした広めの教室の隅に、木製のイーゼルがいくつも並べて保管されている。
大きな窓からは夏の午後の太陽光が差し込むが、空調が効いていて暑苦しくはない。
ただ、人の気配はなかった。
ということは前回の利用者の施錠忘れ。そう判断した塁は、ここで昼寝をすることに決めた。
できれば人目につかず、空調が直接当たらない場所。そんな条件で塁が周囲を見渡す。
その時、背後から声をかけられた。
「あれ? 君……」
ドキッとした塁が慌てて振り向く。すると一人の男子生徒が、扉付近に呆然と立ち止まったまま塁を見上げていた。
ストレートマッシュの黒髪から覗く、パッチリとした丸目が塁に突き刺さる。
そこで塁は、名前を呼ばれるより前に振り向いたことを後悔した。
全校生徒に知られている、塁の変な異名。
どうせまた“目が合っただけで討ち取られる”と恐れられ、謝られて逃げられるのがオチだ。
と思っていたら、男子生徒は塁の予想の逆をいく。
「やっぱり! 二年の三崎塁くんだよね?」
呆然としていた顔が、突然パッと笑顔を咲かせて距離を詰めてきた。
不意を突かれて、小さく頷いた塁の方が一歩後ろに下がってしまう。
三年専用の紺色ネクタイをかっちりと首元で締め、色白で細身の平均身長。見た感じは、ザ優等生。
そんな彼が“目が合っただけで討ち取られる”という異名を持つ塁と、視線を合わせたまま話しはじめた。
「僕、三年の丹野雪。美術部の部長だよ」
「……三崎塁」
「知ってる知ってる。もしかして入部希望⁉︎」
「……いや、昼寝場所を探し――」
言いかけて塁は口を噤んだ。
入部希望を期待する雪のキラキラした瞳を見てしまい、本当のことは言わない方が良い気がした。
しかし、聞き逃していなかった雪は眉を下げてしゅんと肩を落とす。
「そっか〜残念」
「……なんか、すんません」
「いいよ。昼寝も大歓迎だからどうぞ」
「は……?」
「僕がいる間だけだけど、その辺の机使ってもいいし」
雪は塁に気軽に話しかけながら、イーゼルとカルトンをセッティングしていく。
何もお咎め無し。それだけでなく塁に怯えることなく、美術室での昼寝も許された。
一つ上の先輩だけれど、ちょっと変わった人。そんな第一印象だった。
「……迷惑だろ、普通」
誰の意見なのかわからないことを、塁が口走る。
ただ、恐れられている自分の存在は、他の生徒にとっては迷惑だと思い込んでいた。
カルトン上に四つ切サイズの画用紙を固定していた雪が、ふと手元の動きを止める。
そして意外そうな顔を塁に向けた。
「それが普通なの? じゃあ僕は普通じゃないのかも」
柔らかく目尻を下げて、塁の後ろめたさを跳ね返すくらい明るい笑い声を漏らした。
校内でこんなふうに普通に会話するのは、担任教師の柴以外で初めて。
雪の反応が新鮮すぎて胸の奥がざわついた塁が、声の出し方を忘れた。
「塁くん?」
「⁉︎」
塁を心配して雪がそっと寄ってくる。いきなり下の名前で呼ばれて、思わず塁の肩が跳ねた。
感動を通り越して、意味不明な怒りのようなものまで込み上げてくる。
絶賛混乱中の塁が雪を直視できず、誤魔化すように顔を背けた。
その横顔を見つめていた雪に、突然落雷を受けたような衝撃が走る。
「あああ三崎塁くん!!!!」
腹から出てきた大きな声と、今度は改まってフルネームで呼ばれた塁がさらに驚く。
そしてガシッと強く腕を掴まれて、雪に顔を覗き込まれた。
その燃えたぎった瞳と塁を掴む力には、「逃がさん」という雪の強い意思が込められているようだった。
「な、なんだよ……」
「正面向かない! 横向いて!」
「????」
ものすごい剣幕で怒られた塁は眉根を寄せる。納得いかない表情を浮かべながら、言われるまま横を向いた。
塁の心情を気にも留めない雪は、その横顔をまじまじと見つめて――。
「良い、良いよ塁くん。君の横顔最高だよ!!」
「……はあ?」
星々を撒き散らすような輝いた瞳で、雪は塁を褒めまくってきた。
言っている意味が理解できず、雪のテンションにもついていけない。
そんな塁の頭の中では、思考停止音が鳴り続けた。