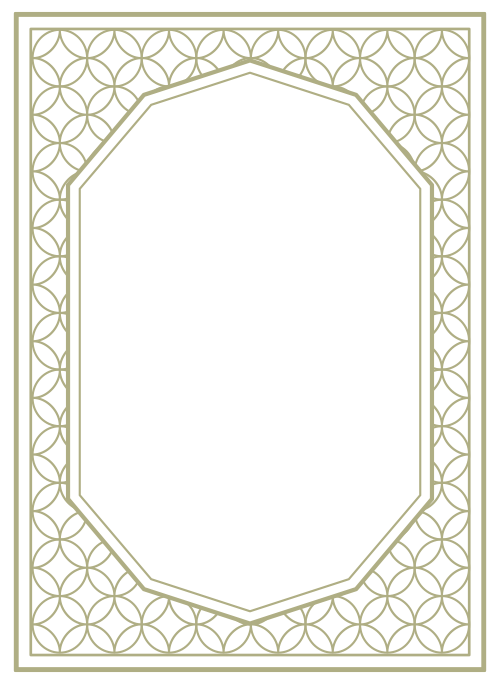「デスゲームってこんな感じなんだろうな」
鬼塚くんの言葉に、その場にいる全員に緊張感が走った。
「どう考えてもそうだろ。一人ずつ秘密が暴かれて、内定から遠ざかってくんだから」
「……次は、どっちなんだろうね」花屋さんが私たちを見る。
すると、麻月さんが慌てたようにジャケットのポケットから何かを取り出した。あれは見たことがある。どこで見たんだっけ。みるみるうちに麻月さんの呼吸が荒くなる。取り出したものを口元に当てたのを見て、ああ、廊下に落ちていたやつだとわかった。
「麻月さん?」
慣れた様子で麻月さんは大きく深呼吸を繰り返そうとしていた。その背中を撫でる。麻月さんの口元にあるのはビニール袋だ。なぜこんなところにあるのだろうと不思議だったが、彼女のものだった。
そういえば、十五分休憩のとき、私の前に会議室を出たのは麻月さんだった。もしかすると、こっそりと香田さんたちの話を聞いていたのかもしれない。
ということは、内定枠が一人だったということを知ることはできた。
今残されているのは、私と麻月さん。この二人が本当に犯人だとしたら、お互いにわかっているはずだ。自分は犯人ではないと。
かさり、音がしていたのは、麻月さんがこうなることを予測してポケットに忍ばせていたのだとわかる。
「これ、よかったら」花屋さんが新品の水を麻月さんに差し出す。「まだ飲んでないから」
少し落ち着きを取り戻した麻月さんは、呼吸を整えながら「ありがとうございます」と受け取った。
「犯人かもしれない奴に、優しくする必要ないんじゃないですか」冷酷なことを言ったのは長谷川くんだ。彼はどこまでも裏切らない。
「本当に苦しんでるやつだっただろ」
鬼塚くんが眉間に皺を寄せたが、
「演技の可能性だったあるじゃないですか」
「これを演技って……お前、頭どうかしてんじゃねえの」
「本当に過呼吸なら、こんなにも臨機応変に自分でなんとかできますかね」
「……過呼吸は、癖になるんだよ」
私も背中を撫でながら、これは演技ではないと思っていた。この経験は、私も何度かある。過呼吸に慣れると、できるだけ対処しようと余裕ができたりする。なるべく大きく息を吸うようにして、それから吐くことを意識的にする。
それでも手が痺れだして、指がどんどんグーの形になっていく。これは意識的にやろうとしても難しいし、そもそもかなりの演技力が問われるはずだ。経験がある私から見ても、やはりこの特徴的な仕草は嘘に見えない。
彼女はビニール袋を持って口に当てるだけでも辛かったはずだ。それでも、私が犯人ではないとしたら、彼女ということになってしまう。
「犯人がどうであれ、目の前で苦しんでいる人を見たら、放っておいていい理由にはならない。それに、麻月さんが犯人だと決まったわけでもないんだから」
確定ではない。それなのに、助けないという選択肢を取っていいわけではない。
「そうでしょうか。やっぱりあとで助けないほうがよかったって思いません?」
「どうして」
「じゃあ仮にですよ。今回のことがきっかけで、人が亡くなったらどうしますか」
「亡くなるって……」
いきなり何を言われているのだろう。私たちが行っているのは、人の命を懸けたものではない。内定を賭けたものだ。そのことを見透かしているのか長谷川くんは「この時間がきっかけで起こりえる最悪のケースです」と続けた。
「しかも麻月さんのせいで人が亡くなるんです。そうなったとして、あとで後悔しても遅いんですよ、助けてしまった過去は変わらないし、犯人を助けたことによって今度、苦しむことがあるかもしれないんですから」
「……そんなこと、起こるはずがない」
「わからないじゃないですか。むしろ、この状況だって最初からわかってました? こんなデスゲームが開始されるような予想、森さんはできていたっていうんですか」
そんなこと、できるはずがなかった。
私はここで内定がもらえるかどうか、それだけを気にしていた。
「これだけかき乱したのが麻月さんだったってあとでわかったら、助けた自分を後悔しませんか。あのとき、背中なんて撫でなければよかった。自分は犯罪者を助けようとしたんだって思いませんか」
「それは」
「なぜ、真っ先にあなただけが麻月さんの背中を撫でたか、要は助けたか、自分でわかってますか」眼鏡の奥にある瞳が、私に訴えかけてくる。「まだあなたが、犠牲者になっていないからです」
私以外が、犯人に苦しめられている。その犯人が、私か森さんかで疑われていて、そのどちらかがいきなり苦しみ出したとしても、助ける必要はないと言いたいのだろう。
「おそらく、これからまた動きはあるでしょう。そして、場合によっては麻月さんの潔白が証明されるかもしれない。それでも、僕はさっき麻月さんを助けようと思わなかったことを後悔することはないですね。こういう状況にいるんですから」
演説が終わったかのように、長谷川くんはすっと喋るのをやめた。鬼塚くんも、花屋さんも、会話に入ってくることはなかった。
私たちは、犯人として疑われている。そのことは紛れもない事実だ。
「……すみません、森さん」か細い声で麻月さんが言った。「私のせいで、こんなことになってしまって」
「いや、麻月さんのじゃないよ」
お互いに犯人じゃない可能性もある。けれど、ほんの少し、彼女に触れていた手にぎこちなさが残る。長谷川くんの言葉に影響を受けている。そんな自分が嫌になる。貫き通すことができない意志の弱さ。
けれど、廊下に落ちていたビニール袋。あれは、彼女が香田さんたちの話を聞いて、内定枠が一人だと知っていたとすれば。そのあとに起こったこのデスゲームは彼女が引き起こしたと考えることもできるだろう。
「そろそろ始めてもらっていいですよ」
挑発するように言った長谷川くんに、まるで応えるようにプリンターが動き出した。
次は私か、彼女か。
「……ああ、そういうパターンもあったか」
確認しに行った長谷川くんは、プリンターを見て呟いた。その手には二枚ある。
【NPO活動では支援活動の一環で収集した個人情報(子どもたちや家族のデータ)を不正に利用していた】
【環境保護団体での活動は全て虚偽であり、捏造されている。】
「二人同時に出てしまえば、どちらが犯人かは曖昧にできますよね」
いざ、自分のものが出てくると、頭を鈍器で殴られたような錯覚に陥る。そうか、本当に出てきたのか。
「じゃあ、一人ずつ弁明タイムといきましょう」ここに来たときと同一人物とは思えないほど、長谷川くんはよく喋る。表情こそ変わらないものの、私たちの、どちかが犯人であると確信を得ているような顔だ。
「……不正に利用していたつもりは、なかったんです」最初に口を開いたのは麻月さんだった。「結果的に、第三者に売却されていたってだけで……」
その言葉を聞いて、一瞬場が凍りついた。全員の視線が一斉に麻月さんに集中する。彼女の言葉がどういう意味を持つのか、誰もが理解しつつも、次に何を言うのか待っていた。沈黙の中で、ついに鬼塚くんが口を開いた。
「麻月さんがやったんじゃないの?」
その問いは、冷たいというよりも直球だった。麻月さんはその言葉に一瞬たじろいだが、すぐに首を振って否定した。
「そんなこと絶対にしません。ただ……」麻月さんの視線が床に落ちる。「ただ、高校のときの先輩から頼まれてしまったんです」
「先輩?」と花屋さんが不思議そうに聞き返す。
麻月さんは苦しそうに口を開く。
「私がNPOに関わっていたとき、その先輩がボランティアで参加していて、何かと手伝ってくれていたんです。最初は普通の依頼だったんですけど、活動を広げるために、支援者を増やしたいって言っていて……信じてしまいました」
「信じて、何をしたの?」と鬼塚くんが険しい顔で問い詰める。
「……先輩が“寄付者に感謝のメッセージを送りたいから、支援してくれている人たちの連絡先を教えてくれ”って言ってきたんです。その頃の私は、特に疑いもなく、それが正しいことだと思ってしまって……」麻月さんは、申し訳なさそうに肩をすくめた。「私が持っていたリストを渡しました。それで、その後……先輩がそのリストをどうしたか、私にはわからなくて。後になって、それが第三者に渡っていたことを知って……」
「リストが売られていたということですね?」長谷川くんが冷静なトーンで確認する。
麻月さんは力なくうなずいた。「はい……でも、私は本当に知らなかったんです。最初は支援者にお礼を言うためのものだって信じてたんです」
「信じたとしても、それは管理者としての責任を果たしていないということですよね?」長谷川くんが冷酷に言う。
「わかってます……」麻月さんは声を絞り出すように言った。「だから、それがわかったとき、どうしていいか。でも、自分がやってしまったことの重さに気づいたときには、もう遅くて」
「でも、結局のところ、第三者に個人情報が売られたってことだよな?」鬼塚くんがさらに突っ込む。「それって、かなりヤバいことだろ」
「本当にごめんなさい……」麻月さんは涙をこらえながら頭を下げた。
花屋さんが、静かに息を吸って口を開いた。
「麻月さん、先輩がどうやってその情報を使ったか調べたの?」麻月さんは首を振った。
「……調べていません。でも、私のせいで支援者の皆さんに迷惑をかけたのは事実で」
「事実がわかってたら、もう少し何かをする必要があったと思う」花屋さんは優しく問いかける。「もし麻月さんが悪意なく先輩に渡してしまったとしても、結果的に被害が出てしまったなら、申し訳ないって思うだけじゃなくて、何かしら動いたほうがよかったはずだし、何もできなかったりしても、自分なりに対応できることがあったんじゃないかな」
沈黙が続いた。麻月さんの肩が震えているのがわかるが、誰も次の言葉を探せずにいた。
過ぎてしまったことを責めてしまうのはどうしようもない。麻月さんも、どうしたらいいかわからずにずっと苦しんでいたのかもしれない。
それでも、結果だけを見たら放置したということになってしまう。たとえ麻月さんが悪くなかったとしても。
「……それでも麻月さんも騙されてたんだよね、ごめんね」
花屋さんは、麻月さんの側に歩み寄り、そっと彼女の肩に手を置いた。その優しい仕草に、麻月さんはほんの少しだけ顔を上げた。
「だって、先輩に頼まれたんでしょ? 先輩がやってることだし、信じてたんだもん。誰だってそんな状況だったら、同じようにしちゃうと思う。私もたぶん……」花屋さんは優しく微笑んで、麻月さんの肩を軽く叩いた。「私も、同じことしちゃってたかも」
その言葉に麻月さんは驚いたような表情を浮かべ、かすかな声で「ありがとう」と言った。
けれど、そのやりとりを見つめていた鬼塚くんは眉をひそめた。
「いやいや、そんな同情で済む話じゃないだろ。個人情報を流してたことには変わりがないわけなんだし。被害が出てるかもしれないんだぞ」
「そうかもしれないけど、責めるだけじゃなくて、どうすればいいかを考えるべきじゃない? 麻月さんが過ちを犯したことはわかったけど、それを責め続けても何も変わらないでしょ? 大事なのは、これからどうするかじゃないの?」
鬼塚くんはその言葉に一瞬言葉を失ったが、やや皮肉っぽく口元を歪めた。
「それは綺麗事だ。世の中はそんなに甘くない。こんなミス一つで信用を失うんだから。特に俺たちみたいに内定がかかった状況では、些細なミスでも致命的なんだから。それに、麻月さんのことをフォローしてるけど、事実は変わらない」
長谷川くんもここで静かに口を開いた。
「そこに関しては僕も同じ意見です。自分だけ悪くないでは済まされないですから」
「……でも、私たちは人を責められるような立場でもないでしょ」
花屋さんのその一言が、鬼塚くんと長谷川くんを黙らせた。それ以上を追求するようなことはなかったが、花屋さんのこの言葉がなければ、麻月さんは一方的に責められ続けていただろう。
麻月さんは「ごめんなさい」と目に涙を浮かべた。責められ、守られ、そしてまた責められ。可哀想だし、同情はしてしまうけど、結果は変わらない。
それに、麻月さんがこのデスゲームの犯人なのかは、結局のところ有耶無耶になってしまっている。どちらが犯人なのか、そこについて話し合わなくてもいいのだろうか。
今は麻月さんの罪にばかり焦点が当たってしまっているけれど、それを言えばほかの三人だって同じだ。自分の罪を棚に上げて、寄ってたかって麻月さんの罪にしがみつこうとしている。
罰せられるようなことを、それぞれがやってきたというのに。そういう過去があるはずなのに。なぜ、ここで罪が麻月さん一人だけに絞られてしまっているのは納得がいかない。
麻月さんは「私が悪いんです」としきりに顔を伏せていた。償いたいです、と言った彼女は、まるで罪悪感から押しつぶされそうな、そんな横顔をしていた。
鬼塚くんの言葉に、その場にいる全員に緊張感が走った。
「どう考えてもそうだろ。一人ずつ秘密が暴かれて、内定から遠ざかってくんだから」
「……次は、どっちなんだろうね」花屋さんが私たちを見る。
すると、麻月さんが慌てたようにジャケットのポケットから何かを取り出した。あれは見たことがある。どこで見たんだっけ。みるみるうちに麻月さんの呼吸が荒くなる。取り出したものを口元に当てたのを見て、ああ、廊下に落ちていたやつだとわかった。
「麻月さん?」
慣れた様子で麻月さんは大きく深呼吸を繰り返そうとしていた。その背中を撫でる。麻月さんの口元にあるのはビニール袋だ。なぜこんなところにあるのだろうと不思議だったが、彼女のものだった。
そういえば、十五分休憩のとき、私の前に会議室を出たのは麻月さんだった。もしかすると、こっそりと香田さんたちの話を聞いていたのかもしれない。
ということは、内定枠が一人だったということを知ることはできた。
今残されているのは、私と麻月さん。この二人が本当に犯人だとしたら、お互いにわかっているはずだ。自分は犯人ではないと。
かさり、音がしていたのは、麻月さんがこうなることを予測してポケットに忍ばせていたのだとわかる。
「これ、よかったら」花屋さんが新品の水を麻月さんに差し出す。「まだ飲んでないから」
少し落ち着きを取り戻した麻月さんは、呼吸を整えながら「ありがとうございます」と受け取った。
「犯人かもしれない奴に、優しくする必要ないんじゃないですか」冷酷なことを言ったのは長谷川くんだ。彼はどこまでも裏切らない。
「本当に苦しんでるやつだっただろ」
鬼塚くんが眉間に皺を寄せたが、
「演技の可能性だったあるじゃないですか」
「これを演技って……お前、頭どうかしてんじゃねえの」
「本当に過呼吸なら、こんなにも臨機応変に自分でなんとかできますかね」
「……過呼吸は、癖になるんだよ」
私も背中を撫でながら、これは演技ではないと思っていた。この経験は、私も何度かある。過呼吸に慣れると、できるだけ対処しようと余裕ができたりする。なるべく大きく息を吸うようにして、それから吐くことを意識的にする。
それでも手が痺れだして、指がどんどんグーの形になっていく。これは意識的にやろうとしても難しいし、そもそもかなりの演技力が問われるはずだ。経験がある私から見ても、やはりこの特徴的な仕草は嘘に見えない。
彼女はビニール袋を持って口に当てるだけでも辛かったはずだ。それでも、私が犯人ではないとしたら、彼女ということになってしまう。
「犯人がどうであれ、目の前で苦しんでいる人を見たら、放っておいていい理由にはならない。それに、麻月さんが犯人だと決まったわけでもないんだから」
確定ではない。それなのに、助けないという選択肢を取っていいわけではない。
「そうでしょうか。やっぱりあとで助けないほうがよかったって思いません?」
「どうして」
「じゃあ仮にですよ。今回のことがきっかけで、人が亡くなったらどうしますか」
「亡くなるって……」
いきなり何を言われているのだろう。私たちが行っているのは、人の命を懸けたものではない。内定を賭けたものだ。そのことを見透かしているのか長谷川くんは「この時間がきっかけで起こりえる最悪のケースです」と続けた。
「しかも麻月さんのせいで人が亡くなるんです。そうなったとして、あとで後悔しても遅いんですよ、助けてしまった過去は変わらないし、犯人を助けたことによって今度、苦しむことがあるかもしれないんですから」
「……そんなこと、起こるはずがない」
「わからないじゃないですか。むしろ、この状況だって最初からわかってました? こんなデスゲームが開始されるような予想、森さんはできていたっていうんですか」
そんなこと、できるはずがなかった。
私はここで内定がもらえるかどうか、それだけを気にしていた。
「これだけかき乱したのが麻月さんだったってあとでわかったら、助けた自分を後悔しませんか。あのとき、背中なんて撫でなければよかった。自分は犯罪者を助けようとしたんだって思いませんか」
「それは」
「なぜ、真っ先にあなただけが麻月さんの背中を撫でたか、要は助けたか、自分でわかってますか」眼鏡の奥にある瞳が、私に訴えかけてくる。「まだあなたが、犠牲者になっていないからです」
私以外が、犯人に苦しめられている。その犯人が、私か森さんかで疑われていて、そのどちらかがいきなり苦しみ出したとしても、助ける必要はないと言いたいのだろう。
「おそらく、これからまた動きはあるでしょう。そして、場合によっては麻月さんの潔白が証明されるかもしれない。それでも、僕はさっき麻月さんを助けようと思わなかったことを後悔することはないですね。こういう状況にいるんですから」
演説が終わったかのように、長谷川くんはすっと喋るのをやめた。鬼塚くんも、花屋さんも、会話に入ってくることはなかった。
私たちは、犯人として疑われている。そのことは紛れもない事実だ。
「……すみません、森さん」か細い声で麻月さんが言った。「私のせいで、こんなことになってしまって」
「いや、麻月さんのじゃないよ」
お互いに犯人じゃない可能性もある。けれど、ほんの少し、彼女に触れていた手にぎこちなさが残る。長谷川くんの言葉に影響を受けている。そんな自分が嫌になる。貫き通すことができない意志の弱さ。
けれど、廊下に落ちていたビニール袋。あれは、彼女が香田さんたちの話を聞いて、内定枠が一人だと知っていたとすれば。そのあとに起こったこのデスゲームは彼女が引き起こしたと考えることもできるだろう。
「そろそろ始めてもらっていいですよ」
挑発するように言った長谷川くんに、まるで応えるようにプリンターが動き出した。
次は私か、彼女か。
「……ああ、そういうパターンもあったか」
確認しに行った長谷川くんは、プリンターを見て呟いた。その手には二枚ある。
【NPO活動では支援活動の一環で収集した個人情報(子どもたちや家族のデータ)を不正に利用していた】
【環境保護団体での活動は全て虚偽であり、捏造されている。】
「二人同時に出てしまえば、どちらが犯人かは曖昧にできますよね」
いざ、自分のものが出てくると、頭を鈍器で殴られたような錯覚に陥る。そうか、本当に出てきたのか。
「じゃあ、一人ずつ弁明タイムといきましょう」ここに来たときと同一人物とは思えないほど、長谷川くんはよく喋る。表情こそ変わらないものの、私たちの、どちかが犯人であると確信を得ているような顔だ。
「……不正に利用していたつもりは、なかったんです」最初に口を開いたのは麻月さんだった。「結果的に、第三者に売却されていたってだけで……」
その言葉を聞いて、一瞬場が凍りついた。全員の視線が一斉に麻月さんに集中する。彼女の言葉がどういう意味を持つのか、誰もが理解しつつも、次に何を言うのか待っていた。沈黙の中で、ついに鬼塚くんが口を開いた。
「麻月さんがやったんじゃないの?」
その問いは、冷たいというよりも直球だった。麻月さんはその言葉に一瞬たじろいだが、すぐに首を振って否定した。
「そんなこと絶対にしません。ただ……」麻月さんの視線が床に落ちる。「ただ、高校のときの先輩から頼まれてしまったんです」
「先輩?」と花屋さんが不思議そうに聞き返す。
麻月さんは苦しそうに口を開く。
「私がNPOに関わっていたとき、その先輩がボランティアで参加していて、何かと手伝ってくれていたんです。最初は普通の依頼だったんですけど、活動を広げるために、支援者を増やしたいって言っていて……信じてしまいました」
「信じて、何をしたの?」と鬼塚くんが険しい顔で問い詰める。
「……先輩が“寄付者に感謝のメッセージを送りたいから、支援してくれている人たちの連絡先を教えてくれ”って言ってきたんです。その頃の私は、特に疑いもなく、それが正しいことだと思ってしまって……」麻月さんは、申し訳なさそうに肩をすくめた。「私が持っていたリストを渡しました。それで、その後……先輩がそのリストをどうしたか、私にはわからなくて。後になって、それが第三者に渡っていたことを知って……」
「リストが売られていたということですね?」長谷川くんが冷静なトーンで確認する。
麻月さんは力なくうなずいた。「はい……でも、私は本当に知らなかったんです。最初は支援者にお礼を言うためのものだって信じてたんです」
「信じたとしても、それは管理者としての責任を果たしていないということですよね?」長谷川くんが冷酷に言う。
「わかってます……」麻月さんは声を絞り出すように言った。「だから、それがわかったとき、どうしていいか。でも、自分がやってしまったことの重さに気づいたときには、もう遅くて」
「でも、結局のところ、第三者に個人情報が売られたってことだよな?」鬼塚くんがさらに突っ込む。「それって、かなりヤバいことだろ」
「本当にごめんなさい……」麻月さんは涙をこらえながら頭を下げた。
花屋さんが、静かに息を吸って口を開いた。
「麻月さん、先輩がどうやってその情報を使ったか調べたの?」麻月さんは首を振った。
「……調べていません。でも、私のせいで支援者の皆さんに迷惑をかけたのは事実で」
「事実がわかってたら、もう少し何かをする必要があったと思う」花屋さんは優しく問いかける。「もし麻月さんが悪意なく先輩に渡してしまったとしても、結果的に被害が出てしまったなら、申し訳ないって思うだけじゃなくて、何かしら動いたほうがよかったはずだし、何もできなかったりしても、自分なりに対応できることがあったんじゃないかな」
沈黙が続いた。麻月さんの肩が震えているのがわかるが、誰も次の言葉を探せずにいた。
過ぎてしまったことを責めてしまうのはどうしようもない。麻月さんも、どうしたらいいかわからずにずっと苦しんでいたのかもしれない。
それでも、結果だけを見たら放置したということになってしまう。たとえ麻月さんが悪くなかったとしても。
「……それでも麻月さんも騙されてたんだよね、ごめんね」
花屋さんは、麻月さんの側に歩み寄り、そっと彼女の肩に手を置いた。その優しい仕草に、麻月さんはほんの少しだけ顔を上げた。
「だって、先輩に頼まれたんでしょ? 先輩がやってることだし、信じてたんだもん。誰だってそんな状況だったら、同じようにしちゃうと思う。私もたぶん……」花屋さんは優しく微笑んで、麻月さんの肩を軽く叩いた。「私も、同じことしちゃってたかも」
その言葉に麻月さんは驚いたような表情を浮かべ、かすかな声で「ありがとう」と言った。
けれど、そのやりとりを見つめていた鬼塚くんは眉をひそめた。
「いやいや、そんな同情で済む話じゃないだろ。個人情報を流してたことには変わりがないわけなんだし。被害が出てるかもしれないんだぞ」
「そうかもしれないけど、責めるだけじゃなくて、どうすればいいかを考えるべきじゃない? 麻月さんが過ちを犯したことはわかったけど、それを責め続けても何も変わらないでしょ? 大事なのは、これからどうするかじゃないの?」
鬼塚くんはその言葉に一瞬言葉を失ったが、やや皮肉っぽく口元を歪めた。
「それは綺麗事だ。世の中はそんなに甘くない。こんなミス一つで信用を失うんだから。特に俺たちみたいに内定がかかった状況では、些細なミスでも致命的なんだから。それに、麻月さんのことをフォローしてるけど、事実は変わらない」
長谷川くんもここで静かに口を開いた。
「そこに関しては僕も同じ意見です。自分だけ悪くないでは済まされないですから」
「……でも、私たちは人を責められるような立場でもないでしょ」
花屋さんのその一言が、鬼塚くんと長谷川くんを黙らせた。それ以上を追求するようなことはなかったが、花屋さんのこの言葉がなければ、麻月さんは一方的に責められ続けていただろう。
麻月さんは「ごめんなさい」と目に涙を浮かべた。責められ、守られ、そしてまた責められ。可哀想だし、同情はしてしまうけど、結果は変わらない。
それに、麻月さんがこのデスゲームの犯人なのかは、結局のところ有耶無耶になってしまっている。どちらが犯人なのか、そこについて話し合わなくてもいいのだろうか。
今は麻月さんの罪にばかり焦点が当たってしまっているけれど、それを言えばほかの三人だって同じだ。自分の罪を棚に上げて、寄ってたかって麻月さんの罪にしがみつこうとしている。
罰せられるようなことを、それぞれがやってきたというのに。そういう過去があるはずなのに。なぜ、ここで罪が麻月さん一人だけに絞られてしまっているのは納得がいかない。
麻月さんは「私が悪いんです」としきりに顔を伏せていた。償いたいです、と言った彼女は、まるで罪悪感から押しつぶされそうな、そんな横顔をしていた。