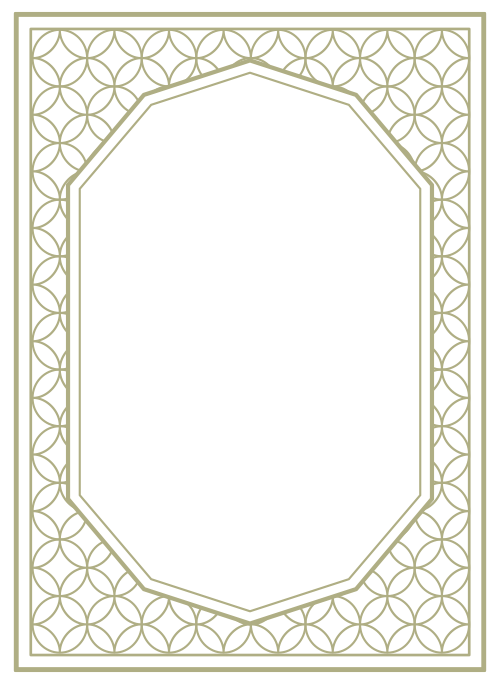「思うんだけど、これって長谷川くんの仕業じゃないの?」
花屋さんは長谷川くんを見ていた。
「何度も言いますが、僕ではありません。スマホは鞄に入っていたんですから」
「そうじゃなくても別の方法で操作できたりするんでしょう?」
「曖昧ですね。もう少し具体的な見解を述べていただけませんか」
誰もが長谷川くんを見ていた。そう、見ている間に、プリンターがまた動きだした。
そのとき、彼はなにかを操作するような手順は何一つ取っていなかった。
つまり、長谷川くんが印刷することはできなかったということが証明されてしまった。
「……次は誰だ」
鬼塚くんに応えるように、長谷川くんが紙を持ち上げた。
「僕のようですね」
【長谷● 聡●。ゼミで行っている経済学の研究において、不正なデータ解析が行われていた】
「……不正」ついこぼした私の声にも、長谷川くんは過剰に反応することはなかった。
むしろ、こうなることを予測していたような余裕さえ伺える。けれどそうかもしれない。彼の場合、最初から予感していた。
この場にいる全員が、内定をもらえるわけではないということを。
「これでも僕が犯人だと疑いますか」
「自作自演ってこともあるだろ」
「なるほど、それはあり得ますね。否定はできません」彼は、少し微笑んだ。
「なんで……笑っていられるの?」花屋さんが気味悪がるように長谷川くんを見ていた。
「笑うというよりも、まあ、事実ですからね。反論はないです。僕のターンはもう終わりでいいですよと犯人に合図したつもりだったんですが」
「……お前、自分が何言ってるのかわかってんのか」
「ええ、僕はリーダーとして複数のプロジェクトをまとめ、僕の結果を支持するような形で操作したことはあります」
「いやいや、何開き直ってんだよ」
「開き直ったつもりはなく、これは事実です」
「事実って……」鬼塚くんが信じられないとでも言いたげだった。
「バレたら、内定はもらえない……かもしれないんですよ?」 麻月さんが問いかけるが、しかし長谷川くんにはあまり響かなかった。
「そうなれば、別のところを受ければいいだけの話です。ずっと思っていたんですが、みなさんは何をそんなに怯えているんですか」
何に怯えているのか。そう問われると、自分の中でくすぶっていたものが、ものすごく小さくて、意味のないようなものに思えた。
だからといって、目の前の問題が消えたわけではない。ここをクリアしなければ、内定をもらうことはできない。
何に怯えているのか──怯えて当然だ。ここに人生がかかっているのだから。
「会社ならいくらでもあります。これだけ力を注いだこの企業だって、入社してから死ぬまで働きたいと思うような場所でした? 僕はここをステップアップのつもりで考えていましたが」
「ステップアップって……そんな簡単に」つい声が漏れてしまう。そんな余裕はなかった。とにかくここで内定が欲しい。それだけだった。
「難しく考えすぎなんですよ。就活って、そんなにしんどい思いをしなければだめなものなんですか。僕にはわかりません」
しんどい思いを、しなければだめなものなのか。
その言葉がやけに頭の奥で響いていた。私はどうして就活をしているのだろう。しなければいけないという流れにのり、当たり前のようにスーツを買った。
これから働こうとしているのに、どうしてこのお金が出ていくのだろうと、会計の時に思わないではなかった。服装は、自分が好んだものを着れば。もしくは、国が支給してくれたら。それが甘えになることはわかっていたから、胸の内に秘めていた。
働くために、出費がどんどん重なっていく。自販機で飲み物を買うことすら躊躇われるようになった。マイボトルは必須で、けれどこのマイボトルを用意するというお金もわざわざ工面しなければならなかった。ちょっとでもいいものを買おうとしたら千円札など平気で何枚も飛んでいく。
昼食をいかに安く済ませられるか、そのことだけを考えて生活することが当たり前にもなっていた。デザートは買わなくなった。いや、買えなくなった。コンビニのスイーツコーナーは、通ったとしても視界に入らないようにした。
それなのに、あの売り場はやけに白いからつい、釘付けになりがちだ。きらきらと輝いた甘いものたち。それを見ると、我慢できなくなって手が伸びそうになる。
我慢だ、就活が終わるまでの間。ぐっと我慢して、総菜コーナーへと向かい、金額重視で選ぶ。食べたいものよりも、たいして興味がないもののほうが安ければ、当然のように後者を選んだ。
お腹に入ればなんでもいい。たまには贅沢をしたくなったし、実家にも帰りたくなった。けれど家賃を全額援助してもらい、食品も送ってもらっている身としては、いそいそと帰れるはずもなかった。
毎日、当たり前のように出てきていた母のごはんが無性に恋しくなった。どうしても我慢できないときは、よく母が作ってくれた砂糖入りの甘い卵焼きを作った。甘いものは疲れた身体によく効いた。昔、好きな人が「こんなのは卵焼きじゃない」と否定したことがあり、そのときはやたらと傷ついたことが何度か思い出す。
今になって思うが、これは自分のためだけに作る大事なおかずでよかった。わざわざ人に振る舞うものではない。宝物は、見せびらかすものではないのだ。
デザートが甘い卵焼きになって、けれど卵も高くて買えないこともあり、また我慢が続け、そうしてまた、出費が増えていく。
バイトを考えないわけでもなかった。むしろ最初はバイトと就活を両立させようと自分なりに努力していたつもりだ。それでも急な説明会や面接が入るとバイトを休むしかなくなり、そうなると迷惑をかけてしまうからと就活に専念するようになった。
それに、私は絶対に内定を取らなければいけないという焦りがあったのも大きかった。せめて一つぐらいは内定を、そう思っていたのに、ここまで一つも箸にも棒にも掛からなかった。就活が続けば続くほど、未来のためにとかかっていくお金が増え続けた。
ここで決めなければいけないと焦る私と、長谷川くんとでは何が違うのだろう。
「……じゃあ、内定がもらえなくてもいいんですか」
「もちろんです。次に進めますし。ただ、ここの企業に費やした時間はできれば返してほしいなと思います。時間は大事ですから」
「時間は大事って……なんか長谷川くんだけ別次元にいるみたいだね」花屋さんが呆れたような笑いを、ふっとこぼした。
「そう思ってもらっても構いません。僕とあなたたちでは住む世界が違いますから」
「住む世界?」
「今、ここで同じ空気を吸っていることが信じられないんですよ。普通に生きていれば、あなたたちのような人と関わるようなことはなかったはずですからね。てっきり僕のような人間を最終に残しているのかと思っていたんですが、そうでもなかったですね。残念です」
「お前、ふざけてんのか」
「でも、これでわかってもらえたんじゃないですか」彼は自分の告発文を手にした。「プリンターの犯人は僕ではないと」
自然と、鬼塚くんと花屋さんの視線が私を見た。そしてその隣にいた麻月さんにも。
「……残るはお二人ですが、少し難しいですね」
長谷川くんは探偵気取りで会議室を歩いた。
「次に出てくるのはどちらか──ですが、出なかったほうが犯人にされますよね。そういうことを犯人は考えていないわけでもないと思うんですよね」
「それは……」
「少し整理しませんか」
「整理?」
「この告発です。鬼塚くんと花屋さんと僕は除外ということでいいですか」
「え……待ってください」麻月さんが声をあげた。
「それじゃあ、私と森さんが犯人だってことになりませんか」
「可能性としてはあるでしょう。犯人は必ずここにいます」
「犯人って……」
「今なら自首したほうが、まだ印象はいいと思いますよ。あとからあぶり出されるよりも、自分から名乗り出たほうがいいと思いませんか。それとも、僕に名指しされたほうがいいですか」
「……お前、犯人わかってるのかよ」
「予想はついていますね」
「誰なんだよ」
「落ち着いてください。犯人にも心の準備ぐらいは必要でしょう」
「心の準備って」
「ああ、そうだ。花屋さんはどちらだと思いますか」
「え、どうして私」
「意見を聞いてみたかったんです。周りをよく見ていたあなたなら僕と答えが一緒なのではと」
「……わからないけど」
「そうですか。僕としては、どちらが犯人だったとしても興味はないんですけど。ただハッキリさせておきたいかなとは思います。さ、次に出てくるのはどちらなんでしょうか」
花屋さんは長谷川くんを見ていた。
「何度も言いますが、僕ではありません。スマホは鞄に入っていたんですから」
「そうじゃなくても別の方法で操作できたりするんでしょう?」
「曖昧ですね。もう少し具体的な見解を述べていただけませんか」
誰もが長谷川くんを見ていた。そう、見ている間に、プリンターがまた動きだした。
そのとき、彼はなにかを操作するような手順は何一つ取っていなかった。
つまり、長谷川くんが印刷することはできなかったということが証明されてしまった。
「……次は誰だ」
鬼塚くんに応えるように、長谷川くんが紙を持ち上げた。
「僕のようですね」
【長谷● 聡●。ゼミで行っている経済学の研究において、不正なデータ解析が行われていた】
「……不正」ついこぼした私の声にも、長谷川くんは過剰に反応することはなかった。
むしろ、こうなることを予測していたような余裕さえ伺える。けれどそうかもしれない。彼の場合、最初から予感していた。
この場にいる全員が、内定をもらえるわけではないということを。
「これでも僕が犯人だと疑いますか」
「自作自演ってこともあるだろ」
「なるほど、それはあり得ますね。否定はできません」彼は、少し微笑んだ。
「なんで……笑っていられるの?」花屋さんが気味悪がるように長谷川くんを見ていた。
「笑うというよりも、まあ、事実ですからね。反論はないです。僕のターンはもう終わりでいいですよと犯人に合図したつもりだったんですが」
「……お前、自分が何言ってるのかわかってんのか」
「ええ、僕はリーダーとして複数のプロジェクトをまとめ、僕の結果を支持するような形で操作したことはあります」
「いやいや、何開き直ってんだよ」
「開き直ったつもりはなく、これは事実です」
「事実って……」鬼塚くんが信じられないとでも言いたげだった。
「バレたら、内定はもらえない……かもしれないんですよ?」 麻月さんが問いかけるが、しかし長谷川くんにはあまり響かなかった。
「そうなれば、別のところを受ければいいだけの話です。ずっと思っていたんですが、みなさんは何をそんなに怯えているんですか」
何に怯えているのか。そう問われると、自分の中でくすぶっていたものが、ものすごく小さくて、意味のないようなものに思えた。
だからといって、目の前の問題が消えたわけではない。ここをクリアしなければ、内定をもらうことはできない。
何に怯えているのか──怯えて当然だ。ここに人生がかかっているのだから。
「会社ならいくらでもあります。これだけ力を注いだこの企業だって、入社してから死ぬまで働きたいと思うような場所でした? 僕はここをステップアップのつもりで考えていましたが」
「ステップアップって……そんな簡単に」つい声が漏れてしまう。そんな余裕はなかった。とにかくここで内定が欲しい。それだけだった。
「難しく考えすぎなんですよ。就活って、そんなにしんどい思いをしなければだめなものなんですか。僕にはわかりません」
しんどい思いを、しなければだめなものなのか。
その言葉がやけに頭の奥で響いていた。私はどうして就活をしているのだろう。しなければいけないという流れにのり、当たり前のようにスーツを買った。
これから働こうとしているのに、どうしてこのお金が出ていくのだろうと、会計の時に思わないではなかった。服装は、自分が好んだものを着れば。もしくは、国が支給してくれたら。それが甘えになることはわかっていたから、胸の内に秘めていた。
働くために、出費がどんどん重なっていく。自販機で飲み物を買うことすら躊躇われるようになった。マイボトルは必須で、けれどこのマイボトルを用意するというお金もわざわざ工面しなければならなかった。ちょっとでもいいものを買おうとしたら千円札など平気で何枚も飛んでいく。
昼食をいかに安く済ませられるか、そのことだけを考えて生活することが当たり前にもなっていた。デザートは買わなくなった。いや、買えなくなった。コンビニのスイーツコーナーは、通ったとしても視界に入らないようにした。
それなのに、あの売り場はやけに白いからつい、釘付けになりがちだ。きらきらと輝いた甘いものたち。それを見ると、我慢できなくなって手が伸びそうになる。
我慢だ、就活が終わるまでの間。ぐっと我慢して、総菜コーナーへと向かい、金額重視で選ぶ。食べたいものよりも、たいして興味がないもののほうが安ければ、当然のように後者を選んだ。
お腹に入ればなんでもいい。たまには贅沢をしたくなったし、実家にも帰りたくなった。けれど家賃を全額援助してもらい、食品も送ってもらっている身としては、いそいそと帰れるはずもなかった。
毎日、当たり前のように出てきていた母のごはんが無性に恋しくなった。どうしても我慢できないときは、よく母が作ってくれた砂糖入りの甘い卵焼きを作った。甘いものは疲れた身体によく効いた。昔、好きな人が「こんなのは卵焼きじゃない」と否定したことがあり、そのときはやたらと傷ついたことが何度か思い出す。
今になって思うが、これは自分のためだけに作る大事なおかずでよかった。わざわざ人に振る舞うものではない。宝物は、見せびらかすものではないのだ。
デザートが甘い卵焼きになって、けれど卵も高くて買えないこともあり、また我慢が続け、そうしてまた、出費が増えていく。
バイトを考えないわけでもなかった。むしろ最初はバイトと就活を両立させようと自分なりに努力していたつもりだ。それでも急な説明会や面接が入るとバイトを休むしかなくなり、そうなると迷惑をかけてしまうからと就活に専念するようになった。
それに、私は絶対に内定を取らなければいけないという焦りがあったのも大きかった。せめて一つぐらいは内定を、そう思っていたのに、ここまで一つも箸にも棒にも掛からなかった。就活が続けば続くほど、未来のためにとかかっていくお金が増え続けた。
ここで決めなければいけないと焦る私と、長谷川くんとでは何が違うのだろう。
「……じゃあ、内定がもらえなくてもいいんですか」
「もちろんです。次に進めますし。ただ、ここの企業に費やした時間はできれば返してほしいなと思います。時間は大事ですから」
「時間は大事って……なんか長谷川くんだけ別次元にいるみたいだね」花屋さんが呆れたような笑いを、ふっとこぼした。
「そう思ってもらっても構いません。僕とあなたたちでは住む世界が違いますから」
「住む世界?」
「今、ここで同じ空気を吸っていることが信じられないんですよ。普通に生きていれば、あなたたちのような人と関わるようなことはなかったはずですからね。てっきり僕のような人間を最終に残しているのかと思っていたんですが、そうでもなかったですね。残念です」
「お前、ふざけてんのか」
「でも、これでわかってもらえたんじゃないですか」彼は自分の告発文を手にした。「プリンターの犯人は僕ではないと」
自然と、鬼塚くんと花屋さんの視線が私を見た。そしてその隣にいた麻月さんにも。
「……残るはお二人ですが、少し難しいですね」
長谷川くんは探偵気取りで会議室を歩いた。
「次に出てくるのはどちらか──ですが、出なかったほうが犯人にされますよね。そういうことを犯人は考えていないわけでもないと思うんですよね」
「それは……」
「少し整理しませんか」
「整理?」
「この告発です。鬼塚くんと花屋さんと僕は除外ということでいいですか」
「え……待ってください」麻月さんが声をあげた。
「それじゃあ、私と森さんが犯人だってことになりませんか」
「可能性としてはあるでしょう。犯人は必ずここにいます」
「犯人って……」
「今なら自首したほうが、まだ印象はいいと思いますよ。あとからあぶり出されるよりも、自分から名乗り出たほうがいいと思いませんか。それとも、僕に名指しされたほうがいいですか」
「……お前、犯人わかってるのかよ」
「予想はついていますね」
「誰なんだよ」
「落ち着いてください。犯人にも心の準備ぐらいは必要でしょう」
「心の準備って」
「ああ、そうだ。花屋さんはどちらだと思いますか」
「え、どうして私」
「意見を聞いてみたかったんです。周りをよく見ていたあなたなら僕と答えが一緒なのではと」
「……わからないけど」
「そうですか。僕としては、どちらが犯人だったとしても興味はないんですけど。ただハッキリさせておきたいかなとは思います。さ、次に出てくるのはどちらなんでしょうか」