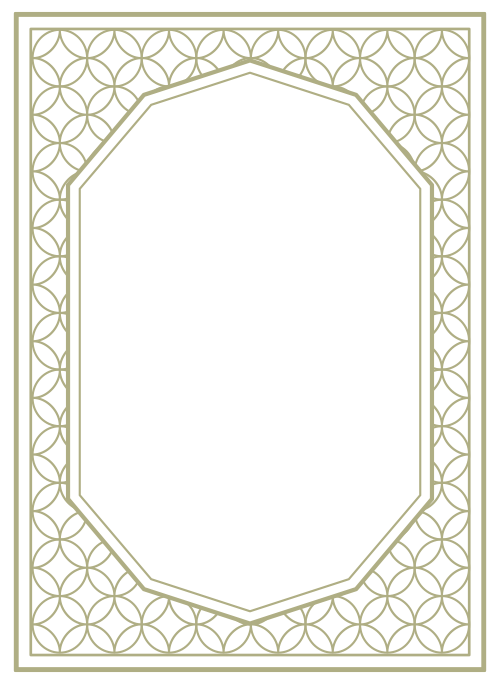「なんでこんなことになったんだよ」
鬼塚くんは落ち込んでいた。それもそうだ。あんな真実かどうかわからないものを、これから香田さんに知られてしまうかもしれない恐怖と戦わなければならない。
「……大丈夫だよ、まだ挽回のチャンスはあるから」花屋さんが鬼塚くんを励まそうとするが、まるで声が聞こえていないかのように反応しない。
さっきまで、散々彼女の会話に合の手を入れていたのに。
「圧倒的な不利にはなるのですから、棄権されるということも選択肢に入れておいたらどうでしょう」
そう言ったのは長谷川くんだった。
「……それ、俺をここから追い出そうとしてるわけ?」
「事実を述べただけで、判断は鬼塚くんに委ねますよ。もちろん、自分が無関係であることを証明する手段があるなら、それも選択肢でしょう。しかし、現状では疑惑が強まっていることも事実ですからね」
鬼塚くんは険しい顔をして、長谷川くんを睨みつけた。
「俺を排除しようとしてんのか。こんな一方的な噂を信じて、棄権なんかしたら、全部認めたことになるだろ」
「感情的にならずに話し合いませんか……?」と、麻月さんが静かに口を挟む。
「私たちが対立しても意味がないです。今は冷静に……あの、情報を集めるべきだと思うんです。本当にこの噂が事実かどうかも、きちんと確かめないと」
「冷静って……こんな状況でどうやって冷静になれっていうんだよ」
鼻で笑うような鬼塚くんに、長谷川くんもなおも冷静に諭した。
「それはあなたの選択次第です。もしこのまま続けたいなら、自分を守るしかない。でも、この状況が不利であることは、他の皆さんも理解しているはずです」
「……俺は何もしていない。絶対にこのまま棄権なんてしない」
「そうだよ、棄権なんてすれば、こんなことをした人の思う壺だよ」
花屋さんは、鬼塚くんだと示唆する内容の紙を手に取った。
「考えたんですが、これってここにいる誰かが印刷したんじゃないでしょうか」
「誰かって……誰ですか?」麻月さんの質問に全員がそれぞれの顔を見た。
「それは私にもわからないですけど……ただ、人事部の人たちが用意したとなると、これは悪質過ぎると思うので」
「タイミングとしては、内定者が一人だって明かされたあとからでしたよね」
私が言うと、麻月さんが「他己紹介が匿名だってこともありました」と付け足した。
「こう言ったら語弊があるかもしれないんですが、ここには他人を陥れてでも内定を勝ち取りたいって人がいるんだと思うんですよ」花屋さんが言うよう、なんとしてでも内定を勝ち取りたい、その一心で真っ先に鬼塚くんがターゲットになった可能性はある。
彼の場合、真正面からやり合うとなると体格に怖気づいてしまうこともありそうだが、匿名であればその壁は比較的乗り越えやすい。
「誰だよ、俺を陥れようとしてる奴」
ガン、と鬼塚くんがテーブルの足を蹴り上げる。隣に座っていた麻月さんが「ひっ」と小さな悲鳴をこぼした。
「鬼塚くん、落ち着いて。陥れようとしてる人はいるかもしれないけど、だからって全員を疑うのはよくないよ」
「何言ってんの?」鬼塚くんが立ち上がり、そして花屋さんを睨む。
「そっちが言ったんだろ。俺を陥れたい人間がいるって。ここに、少なからず一人はいるってわかれば、全員を疑って当然だろ」
「ごめん、それはそうなんだけど……でも、疑いだけだと見えなくなるものもあるし」
「見えてるだろうがよ、ふざけやがって!」
「それでも、私が知ってる鬼塚くんは、冷静でどんなときにもうまく対処してたはずだよ。あのときの飲み会のお金だって、最後は鬼塚くんが解決してくれたでしょ」
花屋さんの言葉に、一瞬鬼塚くんの目が揺れた。
「お金って、何があったんですか?」
訊ねると、花屋さんは一度鬼塚くんを見たあと、困ったように言った。
「私たちが二次の集団面接で一緒だったって話はしましたよね」
二人は面識があった。しかも飲み会にまで参加したような仲だ。
「あのとき、みんな酔っぱらって会計がまとまらなくなっちゃって。ちょっとした金額ってこともあったんだけど、誰かがお金を誤魔化してるみたいな話になったんですよ。俺は出したとか、あいつが出してないとか。それを見てた鬼塚くんがその場で立て替えてくれたことがあったのを思い出して」
その話を聞くと、第一印象だったリーダーシップと一致する。おそらく、そういう問題があったとき、何度か自分が引き受けていたのかもしれない。
「あのとき鬼塚くんがいなかったら、あの場は崩壊してたかも。お金の話になると気まずくなるし、なんとなく誰も仕切れない感じだったから」
花屋さんは、微笑みながら思い出すように語った。
「あのときの呼びかけとか、みんなをまとめる力とか、鬼塚くんならではの吸引力があったんです。そんな鬼塚くんを知ってるからこそ、こういうときは信じたいっていうか」
いい話だ、と思っていたものの「関係ないと思います」と割って入ったのは長谷川くんだった。
「今の花屋さんの話は主観的な部分が見受けられましたから。客観的に見た意見を聞かないと、鬼塚くんを信用できるかという問題の解決にならないかと」
「そもそもさ」鬼塚くんが長谷川くんを見ていた。「あの紙、印刷したのって長谷川なんじゃないの?」
「……はい?」
「得意げに語ってただろ。機械周りが得意だとかなんとか」
「そんな言い方はしていないと思いますが」
「でも、得意だって話だったよな。だとしたら、可能性があるのって長谷川一択だと思うんだけど」
「機械周りが得意というだけで犯人にされるんですか」
「可能性として高いんじゃねえの」
「僕は、鬼塚くんを貶めるようなことはしていません」
「証拠は?」
「なんですか」
「だから証拠だよ、お前が好きな。俺に何度か言ってたよな、証拠出せって。お前も出してみろよ、自分がやってないっていう証拠を」
「……無茶苦茶ですね」
「お前がやってたことだろうが」
舌打ちをした鬼塚くんだったが、けれど正論だった。
やっていないことの証明は難しい。それを信じてもらうとなると、自分一人の力ではどうしようもないことがある。そのことを、鬼塚くんは身をもって証明した。
鬼塚くんは冷静さを取り戻すようにスクリーンを眺めていた。今はもう会社のコマーシャルのような映像は流れていない。
そのとき、静まり返った部屋の中で、突然プリンターが動き始めた。機械音が鳴り響き、全員の視線がそちらに向いていた。誰もが息を飲む。次は誰だ──誰が標的にされるのか。
プリンターから出てきた一枚の紙。それを取り上げたのは、再び長谷川くんだった。
彼は無言で紙を見つめ、軽く眉をひそめた後、ため息をついた。
「次は……花屋さんのようですね」
「え?」花屋さんが驚いた声を上げた。「どうして」
長谷川くんは紙を掲げて、みんなに見えるようにした。そこには、まるで他人事のように冷徹な文章が並んでいた。
【●屋凛。彼女はSNSでの人気を誇り、表向きは明るく親しみやすいアイドル的存在。しかし、その裏では、フォロワーを利用した広告収入を目的に、密かに利益を得ているという疑惑が浮上している】
「……嘘、でしょ?」花屋さんは顔を強張らせた。彼女の笑顔が急速に消え、動揺が露わになった。
「まさか、これもお前なのか」
鬼塚くんは長谷川くんを真っ先に疑った。
「あなたなら一番分かってくれると思いましたけどね。印刷する時間がどこにありましたか」
「わかんねえけど、あんなもん用意しとけば操作するだけだろ。だったら、お前しかありえねえ」
「では仮に僕だとしましょう。操作というのは、スマホなどの端末機器という認識でよろしいですか」
「俺はそうだと思ってたけど」
長谷川くんは自身のバッグからスマホを取り出した。
「残念ながら操作できる環境ではありませんでした。スマホは会議室に入ってきてから一度も取り出していません」それに、と長谷川くんは鬼塚くんに詰め寄った。「スマホ、本当に圏外だったんですか?」
「は?」
「ずっと言ってましたよね? 他人にも確認させて、やたらと自分のスマホは圏外だとかアピールしてましたけど」
「だからなんだよ、嘘だって言いたいのか」
「可能性の話をするなら、の話です。あなたが好きな、ね」
鬼塚くんの言い回しを、挑発するような形で長谷川くんは言った。
「……ねえ、それはいいから」花屋さんの声が震えていた。
「これ、嘘だから。フォロワーが多いのは事実だけど、利益を得ているとかそんなことは」
鬼塚くんが苦笑し、冷たく言い放った。
「俺の次は花屋さんか。こうやって一人ずつ潰していくつもりなんだろうな」
部屋は再び不穏な空気に包まれた。全員が、次は自分かもしれないという恐怖に怯え始めていた。そして、花屋さんが最も信頼されていた人物であることが、この場をさらに混乱に導いていた。
「あの……私、SNSに詳しくなくて」麻月さんが言った。「フォロワーで利益を得るってどういうことなんですか?」
「有名な話だとアフィリエイトですかね」長谷川くんは紙をテーブルに置きながら言った。
「自分の投稿に特定の商品やサービスのリンクを貼り、フォロワーがそのリンクをクリックし購入することで報酬を得る仕組みはあります。あとはスポンサーシップを受けていることも少なくないようですから、花屋さんほどの影響力を考えれば、無視できない告発かと」
「……だから、違うって言ってるでしょ。確かにそういう依頼はあるけど、私はフォロワーさんを大事にしてるから、裏切るみたいな形になるなと思って断ってるし。お金なんてもらってない」
そう思いたかった。協調性のないこの場所で、彼女だけが必死でまとめてくれようとしていた。だからこそ、この内容は信じられないものだった。
「ねえ、誰がやってるの? 鬼塚くん以外だよね?」
「待ってください。花屋さんが鬼塚くんに言ったんですよ」私は必死になって彼女の言葉を思い出す。「全員を疑うのはよくないって」
はっとしたような顔で花屋さんは私を見ていた。自分が言っていたことを忘れていたらしい。
「……そうだった。言ってた……そんなこと」肩を落とした彼女は、反省したように続けた。
「みんなを疑いたいわけじゃない。ただ、こんな風に思ってる人がいるんだって知ると、なんか……まともじゃないられないっていうか。さっきまで鬼塚くんに言ってたことがブーメランで返ってきてて……なんか、最悪だ」
頭を抱えた花屋さんは、しばらく黙っていた。
「これ……他己紹介で言わないでほしい気持ち、すごいよくわかる。私、ここまでくるのに、本当に頑張ったから」
余裕そうに駆け上がってきていた彼女にも苦悩があった。
「……無理だろうなって思ってた。ここに受かるの。それでもなんとかしないといけないって思ったから、人より誇れるものはなんだろうって思ったとき、真っ先にSNSが浮かんだ」
「あれは、誇れるものですよ」
麻月さんは同調にするように言ったが、花屋さんはゆっくりと首を振った。
「正真正銘、私の力かって言われたら、そうじゃない」
「どういうことですか?」つい聞いてしまった。
「……私のフォロワー、変だなって思うでしょ」
花屋さんの言葉に、周囲が一瞬静まり返る。彼女の言いたいことが、少しずつ理解できてきた。
「ただの大学生に過ぎないのに、インフルエンサーと同じくらいのフォロワー数を持ってるって。それってアカウントが、少し前は買えたりしたからなんだよね。かさ増しみたいなことはやってて。今はちょっと厳しくなってできないけど、私のアカウント、もう十年前からあるものだから」
今は、フォロワーの数で仕事が決まったり、単価が変わることがあるという話は聞いたことがあった。そこに花屋さんのような人も入っていたのかと思うと信じられない。
「確かに、フォロワー数は多いけど、実際に私の投稿に反応してくれるのは、ほんの一握りの人たちだけ。あとは、私が自分で作ったアカウントとか、……あとはいろいろな人にお願いして、いいね押してもらったりしてるだけ」
「……それは、いけないことなんですか?」
信じられないこそ、この現実をどうにか受け止めようとして肯定したい自分がいた。花屋さんは、え、と私を見た。
「それって、花屋さんがSNSと真剣に向き合ってる証拠じゃないですか。言ってましたよね、根気と継続を大切にしてるって。私、その言葉がすごく好きだなって思ったんですよ」
「そんなことも」花屋さんは苦笑する。「言ってたかな、私」
鬼塚くんは落ち込んでいた。それもそうだ。あんな真実かどうかわからないものを、これから香田さんに知られてしまうかもしれない恐怖と戦わなければならない。
「……大丈夫だよ、まだ挽回のチャンスはあるから」花屋さんが鬼塚くんを励まそうとするが、まるで声が聞こえていないかのように反応しない。
さっきまで、散々彼女の会話に合の手を入れていたのに。
「圧倒的な不利にはなるのですから、棄権されるということも選択肢に入れておいたらどうでしょう」
そう言ったのは長谷川くんだった。
「……それ、俺をここから追い出そうとしてるわけ?」
「事実を述べただけで、判断は鬼塚くんに委ねますよ。もちろん、自分が無関係であることを証明する手段があるなら、それも選択肢でしょう。しかし、現状では疑惑が強まっていることも事実ですからね」
鬼塚くんは険しい顔をして、長谷川くんを睨みつけた。
「俺を排除しようとしてんのか。こんな一方的な噂を信じて、棄権なんかしたら、全部認めたことになるだろ」
「感情的にならずに話し合いませんか……?」と、麻月さんが静かに口を挟む。
「私たちが対立しても意味がないです。今は冷静に……あの、情報を集めるべきだと思うんです。本当にこの噂が事実かどうかも、きちんと確かめないと」
「冷静って……こんな状況でどうやって冷静になれっていうんだよ」
鼻で笑うような鬼塚くんに、長谷川くんもなおも冷静に諭した。
「それはあなたの選択次第です。もしこのまま続けたいなら、自分を守るしかない。でも、この状況が不利であることは、他の皆さんも理解しているはずです」
「……俺は何もしていない。絶対にこのまま棄権なんてしない」
「そうだよ、棄権なんてすれば、こんなことをした人の思う壺だよ」
花屋さんは、鬼塚くんだと示唆する内容の紙を手に取った。
「考えたんですが、これってここにいる誰かが印刷したんじゃないでしょうか」
「誰かって……誰ですか?」麻月さんの質問に全員がそれぞれの顔を見た。
「それは私にもわからないですけど……ただ、人事部の人たちが用意したとなると、これは悪質過ぎると思うので」
「タイミングとしては、内定者が一人だって明かされたあとからでしたよね」
私が言うと、麻月さんが「他己紹介が匿名だってこともありました」と付け足した。
「こう言ったら語弊があるかもしれないんですが、ここには他人を陥れてでも内定を勝ち取りたいって人がいるんだと思うんですよ」花屋さんが言うよう、なんとしてでも内定を勝ち取りたい、その一心で真っ先に鬼塚くんがターゲットになった可能性はある。
彼の場合、真正面からやり合うとなると体格に怖気づいてしまうこともありそうだが、匿名であればその壁は比較的乗り越えやすい。
「誰だよ、俺を陥れようとしてる奴」
ガン、と鬼塚くんがテーブルの足を蹴り上げる。隣に座っていた麻月さんが「ひっ」と小さな悲鳴をこぼした。
「鬼塚くん、落ち着いて。陥れようとしてる人はいるかもしれないけど、だからって全員を疑うのはよくないよ」
「何言ってんの?」鬼塚くんが立ち上がり、そして花屋さんを睨む。
「そっちが言ったんだろ。俺を陥れたい人間がいるって。ここに、少なからず一人はいるってわかれば、全員を疑って当然だろ」
「ごめん、それはそうなんだけど……でも、疑いだけだと見えなくなるものもあるし」
「見えてるだろうがよ、ふざけやがって!」
「それでも、私が知ってる鬼塚くんは、冷静でどんなときにもうまく対処してたはずだよ。あのときの飲み会のお金だって、最後は鬼塚くんが解決してくれたでしょ」
花屋さんの言葉に、一瞬鬼塚くんの目が揺れた。
「お金って、何があったんですか?」
訊ねると、花屋さんは一度鬼塚くんを見たあと、困ったように言った。
「私たちが二次の集団面接で一緒だったって話はしましたよね」
二人は面識があった。しかも飲み会にまで参加したような仲だ。
「あのとき、みんな酔っぱらって会計がまとまらなくなっちゃって。ちょっとした金額ってこともあったんだけど、誰かがお金を誤魔化してるみたいな話になったんですよ。俺は出したとか、あいつが出してないとか。それを見てた鬼塚くんがその場で立て替えてくれたことがあったのを思い出して」
その話を聞くと、第一印象だったリーダーシップと一致する。おそらく、そういう問題があったとき、何度か自分が引き受けていたのかもしれない。
「あのとき鬼塚くんがいなかったら、あの場は崩壊してたかも。お金の話になると気まずくなるし、なんとなく誰も仕切れない感じだったから」
花屋さんは、微笑みながら思い出すように語った。
「あのときの呼びかけとか、みんなをまとめる力とか、鬼塚くんならではの吸引力があったんです。そんな鬼塚くんを知ってるからこそ、こういうときは信じたいっていうか」
いい話だ、と思っていたものの「関係ないと思います」と割って入ったのは長谷川くんだった。
「今の花屋さんの話は主観的な部分が見受けられましたから。客観的に見た意見を聞かないと、鬼塚くんを信用できるかという問題の解決にならないかと」
「そもそもさ」鬼塚くんが長谷川くんを見ていた。「あの紙、印刷したのって長谷川なんじゃないの?」
「……はい?」
「得意げに語ってただろ。機械周りが得意だとかなんとか」
「そんな言い方はしていないと思いますが」
「でも、得意だって話だったよな。だとしたら、可能性があるのって長谷川一択だと思うんだけど」
「機械周りが得意というだけで犯人にされるんですか」
「可能性として高いんじゃねえの」
「僕は、鬼塚くんを貶めるようなことはしていません」
「証拠は?」
「なんですか」
「だから証拠だよ、お前が好きな。俺に何度か言ってたよな、証拠出せって。お前も出してみろよ、自分がやってないっていう証拠を」
「……無茶苦茶ですね」
「お前がやってたことだろうが」
舌打ちをした鬼塚くんだったが、けれど正論だった。
やっていないことの証明は難しい。それを信じてもらうとなると、自分一人の力ではどうしようもないことがある。そのことを、鬼塚くんは身をもって証明した。
鬼塚くんは冷静さを取り戻すようにスクリーンを眺めていた。今はもう会社のコマーシャルのような映像は流れていない。
そのとき、静まり返った部屋の中で、突然プリンターが動き始めた。機械音が鳴り響き、全員の視線がそちらに向いていた。誰もが息を飲む。次は誰だ──誰が標的にされるのか。
プリンターから出てきた一枚の紙。それを取り上げたのは、再び長谷川くんだった。
彼は無言で紙を見つめ、軽く眉をひそめた後、ため息をついた。
「次は……花屋さんのようですね」
「え?」花屋さんが驚いた声を上げた。「どうして」
長谷川くんは紙を掲げて、みんなに見えるようにした。そこには、まるで他人事のように冷徹な文章が並んでいた。
【●屋凛。彼女はSNSでの人気を誇り、表向きは明るく親しみやすいアイドル的存在。しかし、その裏では、フォロワーを利用した広告収入を目的に、密かに利益を得ているという疑惑が浮上している】
「……嘘、でしょ?」花屋さんは顔を強張らせた。彼女の笑顔が急速に消え、動揺が露わになった。
「まさか、これもお前なのか」
鬼塚くんは長谷川くんを真っ先に疑った。
「あなたなら一番分かってくれると思いましたけどね。印刷する時間がどこにありましたか」
「わかんねえけど、あんなもん用意しとけば操作するだけだろ。だったら、お前しかありえねえ」
「では仮に僕だとしましょう。操作というのは、スマホなどの端末機器という認識でよろしいですか」
「俺はそうだと思ってたけど」
長谷川くんは自身のバッグからスマホを取り出した。
「残念ながら操作できる環境ではありませんでした。スマホは会議室に入ってきてから一度も取り出していません」それに、と長谷川くんは鬼塚くんに詰め寄った。「スマホ、本当に圏外だったんですか?」
「は?」
「ずっと言ってましたよね? 他人にも確認させて、やたらと自分のスマホは圏外だとかアピールしてましたけど」
「だからなんだよ、嘘だって言いたいのか」
「可能性の話をするなら、の話です。あなたが好きな、ね」
鬼塚くんの言い回しを、挑発するような形で長谷川くんは言った。
「……ねえ、それはいいから」花屋さんの声が震えていた。
「これ、嘘だから。フォロワーが多いのは事実だけど、利益を得ているとかそんなことは」
鬼塚くんが苦笑し、冷たく言い放った。
「俺の次は花屋さんか。こうやって一人ずつ潰していくつもりなんだろうな」
部屋は再び不穏な空気に包まれた。全員が、次は自分かもしれないという恐怖に怯え始めていた。そして、花屋さんが最も信頼されていた人物であることが、この場をさらに混乱に導いていた。
「あの……私、SNSに詳しくなくて」麻月さんが言った。「フォロワーで利益を得るってどういうことなんですか?」
「有名な話だとアフィリエイトですかね」長谷川くんは紙をテーブルに置きながら言った。
「自分の投稿に特定の商品やサービスのリンクを貼り、フォロワーがそのリンクをクリックし購入することで報酬を得る仕組みはあります。あとはスポンサーシップを受けていることも少なくないようですから、花屋さんほどの影響力を考えれば、無視できない告発かと」
「……だから、違うって言ってるでしょ。確かにそういう依頼はあるけど、私はフォロワーさんを大事にしてるから、裏切るみたいな形になるなと思って断ってるし。お金なんてもらってない」
そう思いたかった。協調性のないこの場所で、彼女だけが必死でまとめてくれようとしていた。だからこそ、この内容は信じられないものだった。
「ねえ、誰がやってるの? 鬼塚くん以外だよね?」
「待ってください。花屋さんが鬼塚くんに言ったんですよ」私は必死になって彼女の言葉を思い出す。「全員を疑うのはよくないって」
はっとしたような顔で花屋さんは私を見ていた。自分が言っていたことを忘れていたらしい。
「……そうだった。言ってた……そんなこと」肩を落とした彼女は、反省したように続けた。
「みんなを疑いたいわけじゃない。ただ、こんな風に思ってる人がいるんだって知ると、なんか……まともじゃないられないっていうか。さっきまで鬼塚くんに言ってたことがブーメランで返ってきてて……なんか、最悪だ」
頭を抱えた花屋さんは、しばらく黙っていた。
「これ……他己紹介で言わないでほしい気持ち、すごいよくわかる。私、ここまでくるのに、本当に頑張ったから」
余裕そうに駆け上がってきていた彼女にも苦悩があった。
「……無理だろうなって思ってた。ここに受かるの。それでもなんとかしないといけないって思ったから、人より誇れるものはなんだろうって思ったとき、真っ先にSNSが浮かんだ」
「あれは、誇れるものですよ」
麻月さんは同調にするように言ったが、花屋さんはゆっくりと首を振った。
「正真正銘、私の力かって言われたら、そうじゃない」
「どういうことですか?」つい聞いてしまった。
「……私のフォロワー、変だなって思うでしょ」
花屋さんの言葉に、周囲が一瞬静まり返る。彼女の言いたいことが、少しずつ理解できてきた。
「ただの大学生に過ぎないのに、インフルエンサーと同じくらいのフォロワー数を持ってるって。それってアカウントが、少し前は買えたりしたからなんだよね。かさ増しみたいなことはやってて。今はちょっと厳しくなってできないけど、私のアカウント、もう十年前からあるものだから」
今は、フォロワーの数で仕事が決まったり、単価が変わることがあるという話は聞いたことがあった。そこに花屋さんのような人も入っていたのかと思うと信じられない。
「確かに、フォロワー数は多いけど、実際に私の投稿に反応してくれるのは、ほんの一握りの人たちだけ。あとは、私が自分で作ったアカウントとか、……あとはいろいろな人にお願いして、いいね押してもらったりしてるだけ」
「……それは、いけないことなんですか?」
信じられないこそ、この現実をどうにか受け止めようとして肯定したい自分がいた。花屋さんは、え、と私を見た。
「それって、花屋さんがSNSと真剣に向き合ってる証拠じゃないですか。言ってましたよね、根気と継続を大切にしてるって。私、その言葉がすごく好きだなって思ったんですよ」
「そんなことも」花屋さんは苦笑する。「言ってたかな、私」