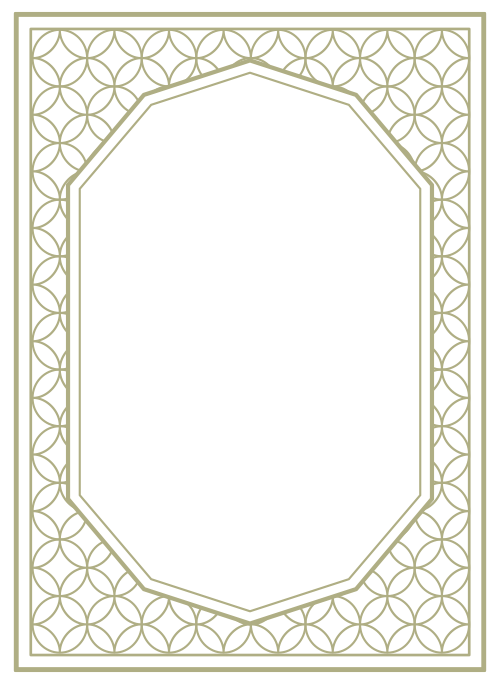靴擦れにリップクリームがいいと知ったのは就活を始めてからのことだった。
駅のホームに座り、かかとより少し上にできた傷に塗り込んでから絆創膏を貼った。これで痛みがなくなるわけではないが、軽減はされる。応急処置程度のものだったが、何度も靴擦れができるためか、これが通常となった。履き慣れなかった新品のパンプスは、すでに細かな傷が入っていた。
電車が来るまでの数分間。ホームに立って並んでいたほうがいいとはわかっていても、今日に至るまでの疲労からか、今座れることを優先してしまう。電車では立つことになるかもしれないのに、その少しあとのことを考えられるほどの余裕がない。
スマホを取り出すと、友人のストーリーに【納得内定もらえた】という投稿があった。
つい数週間前は【ES一枚で私の良さなんてわかるわけねえだろ】と毒づいていたが、どうやらうまくいったらしい。納得、という言葉が引っかかったが、だからなんだという話だ。
内定をもらったという話を聞く度に、焦りや不安がないぜまになったような、どうしようもない感情が湧き上がってくる。
私の場合は周りよりも先に就活を始めたことが原因のひとつだった。自分よりも後から始めた人たちのほうが内定をもらい始めている。その現実から遠ざかるように、何枚もESと略されるエントリーシートを書いては企業に応募を続けた。
けれど、そんな生活も今日で終わるかもしれない。
手の中にあったスマホが僅かに震え出したのは電話を知らせる合図だった。表示されているのは母だ。もしもし、と出れば快活な声が聞こえてくる。
『今日が最終面接だったでしょ。ほら、あそこ、なんて名前だったかな。あれよ、パンみたいな名前のところ』
「ベーグル社。みたいじゃなくて、そのままだよ」
『そうそう、そこ。お母さん、会社の名前とかは知らなかったけど、同じパートさんで知ってる人いたんだわ。なんか、ものすごいところらしいね。娘が最終面接に残ってるって話をしたら果帆のことを褒めてたよ。競争率も高いんだってね。なんかパソコンの人たちを応援するみたいな会社らしいけど』
母は動画配信にはからっきし弱い。
ベーグル社。近年急成長を見せる企業と知られ、革新的なアイデアを持つ企業文化が特徴的だった。福利厚生も充実しており、社員同士の関係が良好であることが多くの就活生を惹きつける要因──とそれは上辺だけの理由だ。
ここにいる全員、破格の初任給に飛びついているとっても過言ではないだろう。しかも年に二回あるボーナスが、入社一年目では考えられないような金額であることも関係している。
若手社員の意欲を引き出すために、企業側がしっかりと評価していることが感じられ、どこよりも気合いを入れて挑んでいた。また、リモートワーク制度を推奨しているあたり、ここ以外にはもう考えられなかった。
事業内容はプラットフォームで成功するためのオンラインコースやワークショップを提供。内容には動画の編集、コンテンツの企画、SEO対策、マーケティング戦略などを含んだりと多岐にわたる。正直、大学時代にかじったことがある経験が功を奏し、結果的に最終までこぎつけることができた。
それらの話を以前、母にしたことはあったが「難しいところだね。やっていけそう?」などと返された。ほとんど理解できなかっただろう。母は高校を卒業してすぐに父と結婚をし、専業主婦を経て今は気ままにパートをしている。
就活などの経験はないためか、私がどれだけ大変だと嘆いても「内定さえもらっちゃえばいいんだから」と片付けてしまう。
その内定を勝ち取ることがどれだけ難しいか、わからない人と会話をするというのは今の私にとって心底嫌悪しかない。
『それでね、果帆のこと話してたら子どものときのことも思い出して。ほら、覚えてる? 小学生のときにお友達と喧嘩になってお母さんと謝りに行ったこと』
「……いつの話をしてるの」
『果帆ってば、意地張って謝れなかったでしょう。明日からこの子、学校に行けるのかなって心配だったけど、ちゃんと自分たちで仲直りしてたもんねえ』
昔の話になると長くなる。平気で一時間を取られてしまうだろう。
『まあ、果帆ならできるから。自分らしくやればいいのよ』
鼻で笑ってしまいそうだった。就活を始めてから自分のことなんてわからなくなり、自己PRや学生時代に力を入れたことなんかを聞かれる度に、自分という人間を作り上げてきた。
長所も短所もわからない。自分の魅力はなんですかと聞かれた面接もあったが、そんなものは教えてほしいぐらいだった。
母との電話は苦痛となり、電車がもうくるからと嘘をついて切った。まだ話したそうにしていた母は、おそらく娘がすごい企業に入れそうだという優越感にもう少し浸っていたかったのかもしれない。正直言って迷惑だった。
目の前でキャリーケースを引いた就活生が横切っていく。同じく黒のスーツを身に纏った女性だ。あの人も今からどこかの面接だろうか。同じような姿をした人を見ると、妙な親近感を覚える。ここまでどれだけの苦労があったか語ってみたい。
ベンチから立ち上がると靴擦れをしたところが痛んだ。その場しのぎを続けたところで根本的な解決にはつながらない。パンプスを買い替えればいいだけの話だけど、余計な出費は出したくない。就活費用の平均金額は約十万円前後とされている。交通費、被服費、宿泊、それに加えて飲食費から就活のための書籍などを揃えていくと、とてもじゃないがパンプス一足を買うことが躊躇われてしまう。
大丈夫、今日で最後になるかもしれない。それなら、このパンプスでもう少し耐えよう。
とある会議室に通されたのは最終選考に残った五人と、企業の経営陣が五人。左から事業部長、執行役員、社長、人事部二人。これまでにもほかの企業で面接を受けたことはあったが、最終面接ともなればこれだけの面接官がいるのかと正直怖気づいてしまいそうだった。それとも、ベーグル社の気合いがこうして現れているのか。どちらにせよ、ここで合否の判断が下されてしまう。
進行役を務めていたのは人事部の一人、香田さんだった。それぞれが名前と志望動機を話し終えると、ありがとうございました、と朗らかに微笑んだ。
「では、あとは事前にお知らせをしていた他己紹介ですね。その前に休憩を挟みましょうか」
十五分でどうでしょう、と香田さんは自身の腕時計を確認した。シンプルながらも洗礼されたデザインで、着こなしていた深いネイビーブルーのスーツにもよく似合っている。
いかにも仕事ができる人のようで、この人と一緒に働けたらどんなにいいだろうかと気分が高揚してしまう。それを隠しながら気を引き締めた。
自然と壁に設置されたスクリーンに視線が流れた。ついさっきまで流れていた映像は、今では会社の広告へと切り替わっている。企業理念は「つながりを創り、成長を支える」。
その言葉が流れてくるのはもう何度目だろうか。
ここに来るまでにも何度か頭に叩き込み、自分の志望動機と絡められるようにしたつもりだが、そこまで響いていなかったように思う。
ただ、そのときの反応だけで結果がわからないところがもどかしい。これまで受けてきた三十社の中では、ぜひ前向きに採用を検討したいと言ってもらったこともあった。
そう言われてしまえば少なからず期待してしまうものだが、大体はお祈りメールが届く。どうせ落とすなら、舞い上がらせないでほしい。就活生を弄んで楽しいのか。苛立ち、そうしてまた新しくエントリーシートを書いては、直近の説明会やインターンのスケジュールを確認する。こんな生活がもう何ヶ月と続いている。
大丈夫、ここまできたんだから。最終選考に残れるなんて初めてだ。ここで結果を残さないと。
最も危惧していたガクチカが終わったことで安心を覚えている一方で、私はまだ運に恵まれているほうなのだと知る機会でもあった。そもそも、ここまで残れたことが奇跡としか言いようがない。
香田さん以外が続々と会議室から出て行く。全員が私たちに「お疲れ様」と声をかけてくれる。なんといい人たちばかりなのだろう。これまで圧迫面接を受けた経験もあるからか、ベーグル社の人の良さというものをつくづく実感する。
「みなさん、あと少しですがリラックスしましょう」
最後に香田さんが出て行くと、どことなく張りつめていた緊張感が僅かにほぐれたように感じた。しばらく静寂が包まれる。十五分となるとお手洗いを済ませておけということだろう。しかし誰も立つことはない。
会議室は広く、正面がガラス張りだった。向かい側の企業が忙しなく働いている。身に纏っている服装が色鮮やかで、就活生の象徴となる黒のスーツを今すぐ脱ぎ捨ててしまいたくなる。
会議室には、ホワイトボード、プロジェクター、観葉植物、プリンター、パソコン、プロジェクター、あとはテーブルや椅子が置かれていた。
いまだに面接の空気が残る会議室で、一番最初に動いたのは扉に近い男性だった。たしか鬼塚と言っていた。体格が良く、学生時代はラグビーかなにかのスポーツをやっていたと話していた。それから今度は綺麗な栗色に染まった髪の女性が出て行き、続くように銀縁のメガネをかけた男性が出て行った。
残ったのは一つ椅子を挟んだ先にいる女性だけ。適度に時間を潰そう。ここでスマホを使うことは避けたほうがいいとは分かっていても、ついSNSをチェックしてしまう。私と同じように今日が最終選考だと呟いていたあの人はどうだったのだろう。今頃は終わっているかもしれない。
就活用のアカウントを作ってからは、あまり呟くことはせず、見る専門となっていた。どうやらまだ面接は続いているようで、私も残りの時間をなんとか耐えようと自分に鼓舞する。そのまま流れるようにメールをチェックする。
時折、急な連絡が入っていることもあれば、お祈りはされたけれど、もしかしたら、みたいな可能性があるのではないかと馬鹿みたいにまだ期待してしまう自分がいる。
内定がもらえれば、この地獄から抜け出せる。そのとき、気になるメールを見つけた。内定の文字が見えたような気がしたそのとき、「あの」と声をかけられた。残り十一分というところだった。
「一次の集団面接で一緒……でしたよね?」
一列に並んだ椅子で、左から二番目に座っていた女性が少し立って私を見ていた。一次と聞いて、そういえばここは一次の時から集団面接だったということを思い出す。
控えめな印象愛らしい笑顔で、黒い髪が肩上で切り揃えられていた。名前はなんだっけ。さっき聞いたはずなのに。顔はなんとなく覚えているぐらいだった。ただ、学生時代のエピソードでカンボジアの子どもたちの話をしていたことだけは覚えている。
そうでしたよね、と話を合わせながら思い出そうとするが、やはりカンボジア以上の情報が思い出せそうにない。とはいえ、今さら「お名前は」と聞くのも失礼だろう。
「あのとき、絆創膏をお借りして、……あ、一枚お返しします」
絆創膏?
言われてみれば、面接の前に絆創膏を自分ではない誰かに渡した記憶がある。律儀に一枚だけ絆創膏を取り出すと、そのまま渡された。
「ありがとうございました。また会えたらお返ししたいと思っていたんです」
「いや、そんな。たかが絆創膏一枚なので」
「本当に助かったんです」
そこまで感謝されるものだったのだろうか。私にとって絆創膏は、靴擦れの痛みを耐える代物でしかない。おそらく彼女にも似たような意味合いで渡したのだろうとは思うけど、ここまでありがたく思ってもらうと、この一枚を受け取るのは気が引ける。
そんな私を察してか「あ、あのお返ししたいだけなので」と念押しをされる。人との貸し借りはきちんと清算しないと気がすまない人なのかもしれない。ここは素直に受け取っておこう。
「ではお言葉に甘えて。ありがとうございます……って、これちょっといいやつじゃないですか」
一枚、百五十円ぐらいするものだ。
私が彼女に渡したのは百円ショップで買ったものの一枚だ。ちなみに六十枚も入っていたから、それに比べると高価なものだ。おそらく今の私なら絶対に手を伸ばすことはないであろう価格帯の一枚だった。
たかが絆創膏を買うことが、今の私にとっては痛手だ。彼女はそうではなかったのだろうか。こういう些細なところで金銭感覚の余裕を感じてしまう。別に何を買おうがその人の自由で、安いだけを重要視したのは私の問題だ。それなのに、この世は不公平だ、なんて思わないわけでもない。
同じ就活生であっても、財布やキーケースなどの小物がブランドものだったりすると、この人とは仲良くなれそうにないなと思ってしまう。私が、というよりも、私のような人間がこういう人たちと関わることは避けたいだろうなと思うからだ。
小物に気を遣う人は、やはり他人の小物も見ている。自分が気にしているところは、いくら「関係ない」と割り切っていたとしても目につくだろう。そうして、無意識な判断が瞬時に繰り広げられる。この人とは仲良くなれそう、この人とは無理そう、みたいな。
「あっ、すみません。同じものでお返ししたほうがいいですよね」
申し訳なくなったのか、私の反応を見て気まずそうな表情を浮かべた。たしかに、私が渡したものよりもずいぶんとお高いものとして返ってきてしまったけれど、ここには悪意というものがないし、本当に気持ちとして渡してもらっているということが伝わる。
それは彼女が持つ空気感みたいなものかもしれない。言葉の端々で、丁寧さを感じられる。すかさず「嬉しいです」とバッグにしまわれてしまう前に受け取った。
「私のは安くて大容量なものだったので受け取っていいか迷ってしまって……でも、せっかくなので大事なときに使わせてもらいます」
「そんな、いつでも使ってください」
照れくさそうにする彼女に、親しみを覚えた。ここで名前が出せたらいいのだけど、やはり思い出せそうになかった。
「それにしても、二人して最終面接に進めるなんて本当によかったですね」絆創膏を受け取りながらそう言うと、彼女は「私は運のみなんですけど」と、肩をすくめた。
「こうして森さんや、ほかの方を前にすると、実力で選ばれてきたのだなということが痛いほどわかるといいますか。私は本当に、運頼りなところがあるので」
「そんなことないです。運はあるかもしれないですけど、みなさん実力ですから」
ここまで来るのに“ただの運”とは思いたくなかった。
就活での正解はほとんどない。会社の気分によって採用人数が変わることがあれば、面接官との波長が合うか合わないか、気に入られるかどうかで決まってしまう。数学のように決まった式があるわけではないからこそ、就活に悩む人は多く、私も頭を抱えてきた。
早く終わってくれと何度思ったことだろう。
「でも、ここってすごいですよね」彼女は続けた。「一次のとき、ちょっとびっくりしたんです。リモート参加の人もいるってことに」
「わかります。リモートの面接はありますけど、リモートとそうではない人が同じ面接の時間になるってところがおどろきですよね。ここがリモートワークを推奨していることもあって、面接をリモートでしてもらえるって心強いですけど」
「とはいえ、あのときみたいにトラブルがあると対処できそうにもないです」
回線が不安定になると、途中で離脱するということもある。そうなると、おのずと採用の文字は遠ざかっていくだろう。そうなるぐらいなら、ここまで足を運んで、直接面接してもらえたほうがいい。
「お互い内定がもらえるといいですよね」
本当ですよ、と返していると一番最初に戻ってきたのは、女性だった。花屋さんだ。花を扱う花屋と一緒だと覚えていたが、何よりも洗礼された身だしなみ、違和感のないメイク、そして整った顔もあってかよく覚えている。
なぜここにいるのだろうと思うほどの美しさを兼ね備え、さっきの自己PRでは彼女の良さが余すことなく伝わっていた。目が合うと、にこりと微笑まれた。
「ここのトイレ、すごい綺麗でしたよ。パウダールームが別にあって」
あ、とつい言葉が出てしまった。人と話すとき「あ」とやたらと付けやすい。特に彼女のような人を前にすると、なぜか妙に緊張してしまう。私自身が、花屋さんのような人とは無縁だったからだろう。気を付けていたつもりなのに、まさか花屋さんのような人から話しかけられるとは思わず戸惑ってしまった。
「やっぱり私も行っておけばよかったです」
「まだ間に合いますよ。時間も、うん、余裕がある」
こういう人は敬語とそうではないときのバランスが絶妙だ。人の懐に、ふわっと入れるような性格なのだろう。真似ができそうで、いざ自分がすると気味が悪かったりする。バランスが悪く、変に馴れ馴れしい人になってしまいそうで。憧れるのはいいが、だからといって同じことをしていいわけでもないなと高校生のときから思ってきていた。
「ええと、それなら」と「じゃあ」と切り出したのは同じタイミングだった。ここに花屋さんの声はない。私と、隣にいたカンボジアの人だ。彼女が立ち上がると、かさりと、何かが擦れる音が聞こえた。軽く足元を見てみたけど、何かが落ちた形跡はなかった。
「ちょっと行ってきます」
「はい、行ってらっしゃい」
つい行くタイミングを逃してしまう。意識してしまうと妙に行きたくなるのだから不思議だ。だからといって、「ちょっと私も」というのも、今度は花屋さんとは一緒にいたくないのだと捉えられてしまわないかと不安になる。そういうわけではない、でも、あえて言葉にするようなことでもない。
昔からこうだ。考えすぎると行動に移せない。
そのまま時間だけが過ぎていく。結果だけ見ると、何も動いていないだけの人間になる。
頭の中ではあれやこれやと選択肢を浮かべては悩んでいるのに、そんなことは周囲に伝わるはずもない。判断が遅いと、いつも自分に嫌気が差す。思い立ったら、それが正しいことではなかったとしても、後悔を減らす選択肢を取れるようになりたい。
花屋さんはカンボジアの人を見送りながら、「正直、ここまで来るとちょっとホッとしませんか」花屋さんが話題を作ってくれた。
「あ、そうですね。最終面接までいけたら内定確定みたいな噂を聞いたことがあって」
「ですよね。私もキャリアセンターの先輩に言われて、ちょっと調子に乗ったっていうか」
「乗りますよね、ここまで来れたんですから」
「こうなったら全員内定ってことにしてほしいですよね」
そんな話をしていると、一番最初に出て行った体格のいい男性が戻ってきた。なぜか首を傾げてスマホを見ている。「おかしいな」と呟く姿を見て花屋さんが声をかけた。
「どうかしたんですか?」
「ずっと圏外なんですよ。今日昼から予定あって、この調子だと間に合わなさそうだなと」
「ああ、他己紹介ですよね。ちょっと私も見てみます」
花屋さんは傍らに置いていた黒のバッグを自分の膝の上に置いた。上部にゴールドの英語が書かれている。もしかしてブランドものだろうか。就活にブランドものは悪目立ちしてしまうため避けたほうがいいとされていた。そのため、私はディスカウントショップに売られていた三千円代のものにした。ただただ金銭的余裕がなかったからに過ぎないけれど。
「うーん、今のところ私のスマホは電波拾ってますね」
一応私も確認してみたが圏外のマークはついていない。「私も電波あります」
「じゃあ俺だけか。なんでだろ」
そのまま、さっきのメールを確認する。やはり内定の文字は見間違いではなかった。だが、はっきりとした内定でもなかったのが事実だ。
内容は、内定をもらうには、という胡散臭いビジネス臭が香るものだった。就活用のアカウントも、やたらとこういったDMが多く届いていた。中には口座を登録するだけでお金が入ってくるといった詐欺もある。
その口座はなぜか作るとパスワードが求められ、送ってしまったが最後、乗っ取られてしまうという。こういった話は珍しくもない。それでもお金に困っているタイミングで、口座を作るだけでお金が入ってきますよなどと誘われてしまえば、ほんの軽い気持ちで作ってしまうのはわからなくもない。
やはり、ここで内定を勝ち取るしかないだろう。
そこまで不安になることもない。花屋さんが言っていたように、ここまできたら内定をもらったのも同然だ。ひとまずお金の心配をそこまでする必要もなくなるだろう。ここさえクリアできてしまえば、バイトを入れることもできる。内定がもらえれば。それだけで私の人生は豊かになり、そして余裕さえ生み出してくれる。内定があれば。
そんなことを考えていると、銀縁眼鏡の男性が戻ってきた。彼は雑談に入ることなく自分の席に座る。名前は憶えていないが、高学歴だとされる大学名を出していた。いかにも頭が良さそうな喋り方で、わかりやすかったが他人に隙を与えないような印象だった。
残り五分。まだ少し時間に余裕はある。
「やっぱりちょっと行ってきます」
花屋さんに声をかけると、どこに行くのかわかったようで「会議室出て右にありましたよ」と教えてくれた。どこまでも気遣いに溢れたような人だ。
会議室を出ると、廊下には厚みのあるクッションフロアが敷かれており、靴音がほとんど響かない。会議室を出た左斜め向かいにも部屋があり、外からは見えないもののそこに香田さんたちがいるのがわかった。どこまでも掃除が行き届いたオフィスは歩いているだけで気分がいい。
綺麗なオフィスというものに憧れがあった。だから、高望みをするつもりではないけれど、見た目の印象は大事にしていたし、場所もできればオフィス街がよかった。ランチは財布だけを持って近くのカフェで食べている自分を想像すると、つい笑みがこぼれてしまう。そんな未来を掴めそうになっていることが、ここで過ごす時間が伸びれば伸びるほど現実的になっていた。
ちょうどカンボジアの人とすれ違った。なにもアクションをしないのは気まずいので、軽く会釈をするだけの動作を同じタイミングでした。
花屋さんが言ったようにお手洗いとは別で隣にパウダールームがあった。覗いてみると、中には誰もいない。壁に備え付けられている鏡にはライトがついている。ああ、いいな。ここを知れば知るほど、内定が欲しくなる。
お手洗いを出ると、少し離れたところに何かが落ちていた。ちょうど香田さんたちがいる部屋の前だ。
目を凝らすと、それがビニール袋だということがわかる。さっきは落ちていただろうか。いや、落ちていたかもしれない。袋は透明だ。すると、香田さんが部屋から出てきて、お手洗いとは真逆の方向へと走っていくのが見えた。どことなく焦ったように見えたのは気のせいだろうか。
会議室に戻ったのは、休憩が終わる一分前だった。
花屋さんは鬼塚くんと雑談をしていた。スマホが圏外だったと話していたが解決したのだろうか。それにしても花屋さんは誰とでも話せる人らしい。男女関係なく、こういう場でも分け隔てなくコミュニケーションが取れるのは、企業に取っても欲しい人材だろう。
ここまで残ったのだから、それなりにふるいにかけられた結果だと思っていいはずだ。
今のところ、花屋さんぐらいしか最終選考に相応しい人はいないように思うけれど。同じように私も周りから思われているのだろう。カンボジアの人はスマホでしきりに文字を打っているようだった。使えるということは圏外ではないかもしれない。ならば鬼塚くんだけということなのだろうか。銀縁眼鏡の人は他人には干渉しませんというスタイルを今も貫いていた。
自分が座っていた椅子まで歩いていた時──
ピー、ガ、ガ、ガ。
人の会話ではない機械音が、なんの前触れもなく会議室に響いた。
「びっ……くりした。なんの音ですかね」よほど驚かされたのだろう。咄嗟に声が出なかったのか、花屋さんが周囲を見渡した。
「プリンターじゃないっすか。ほら、あそこの」鬼塚くんが壁に沿って置かれている業務用の大きな機械を指さした。「間違えてこっちに出しちゃったんですかね」
プリンターに近いのは銀縁眼鏡の人だったが動く気配がない。花屋さんが確認しに行くと、「あれ」と呟いた。
「紙は出てないみたいですね」
「もしかすると用紙切れだったりして」
「あとで香田さんに伝えましょうか」
そう話しながら、廊下を慌ただしそうに走って行った香田さんの背中を思い出した。話題にしようか一瞬悩んだが、やめておくことにした。
もしかすると選考に何か問題があったのかもしれない。そうだとしたら、あまりペラペラと触れるのもよくないだろう。
しばらくすると、廊下から足音が聞こえてくる。ちょうど十五分五十九秒だった。狙っていたのだろうかと思うほど、ギリギリ十五分だった。
会議室に入ってきた香田さんは、当たり前だが慌ただしそうにはしていなかった。最終面接時と同じような朗らかで全員を見渡した。
「みなさんお揃いですね。では、他己紹介に移りたいと思います」
そこから、他己紹介について簡単な説明がされる。「説明は字のごとくといったところですね。みなさんもご経験、もしくは聞いたことがあるかと思います。自己紹介ではなく、他人に自分を紹介してもらうというあれです」
当たり前の認識だと、誰もがうなずいていた。香田さんも安心する。
他己紹介のメリットは自分では気づかない強みを知ることだとされているし、コミュニケーションを取るという意味でもよく使われるものだった。
客観的な視点を取り入れることも大切だとされていて、事前にこの時間があることは知らされていた。
「これから他己紹介に必要なやり取りを一時間設けます。ご要望があればお伺いします」
一時間で十分だと誰もが思っていたのだろう。私は軽くうなずいてみせたが、ほかの人がどうだったかはわからない。こういうときは、あまり周りを気にしないほうがいい。
キョロキョロとしているだけで不格好だ。そんなことは、ここまで昇りつめてきた人間なら心得ているのだろう。おそらく、私以外も同じように考えていた人がほとんどだったはずだ。
「よさそうですね。では、やり方はお任せいたします」
そう言って香田さんが出て行こうとするのを、誰が引き止めるのだろうと様子見していた。今更になって、別にプリンターの件を伝えなくてもいいのではないかと思い始める。「すみません」と声をあげたのは鬼塚くんだった。
「さきほど、そちらのプリンターが作動していました。印刷物が出てくることはなかったですが、念のためご報告しておいたほうがよいかと」
はきはきと臆することなく言えてしまうのはひとつの才能だ。まして香田さんという自分よりも年齢が上の人の前でもきちんとした伝えた方ができることを素直に尊敬する。
「ご報告ありがとうございます。誤作動かもしれませんね、こちらでも声をかけておきます」
香田さんは特に不審がることはなく会議室を出て行った。ただ、鬼塚くんの評価がこれでわずかに上がったような気がした。やはり言っておくべきだった。なぜ私は一瞬「言わなくてもいい」と思ってしまったのだろう。
ほらやっぱり、私は頭で考えるだけで行動にはできない。とはいえ、鬼塚くんが言わなかったとしても、今度はその役割を花屋さんが担っていただろう。いずれにせよ、私ではなかったはずだ。
判断が遅いというだけの問題ではない気はするが、だからといって私のような人間はどこまでいってもこんな感じなんだろうなと思う。就活を始めてから自分のことを嫌うことが何十倍と増えた。別に今まで自分のことを好きだったわけではないが、だからといってこれほどまでに嫌悪感を抱くとも思っていなかった。
どうして私は、私なのだろう。
花屋さんのようにはなれなかったのだろう。
一体どんな違いがあるのか。強いていえば、同じ人間であるということだけだ。
「どんなこと話していきましょうか」
ここからの進行役は自然と花屋さんになっていた。不満に思う人は誰もいない。
「無難にガクチカでいきますか。その人のことを紹介する上では必要な情報が詰まってると思うんで」
そう提案したのは鬼塚くんだ。俺からいきますよ、とそのまま名乗り出た。
「鬼塚大樹です。学生時代はラクロス部に所属し、キャプテンやってました」
ああ、そうだ。ラグビーではなくラクロスだ。網がついた棒を持ち、走り抜ける鬼塚くん姿を想像する。
「全国大会に行ったりと、結構アクティブに動き回ってましたね。体を動かすのが好きなんで、時間を見つけては友達とスポーツするのが好きです。チームをまとめることは大変でしたけど、戦略を考えたり、仲間との連携を取ったりするのも楽しかったっすね」
私たち相手ということもあり、口調はかなり砕けていた。そのほうが、これからの人間もやりやすいだろう。場の雰囲気づくがうまいなと思う。この場の緊張感をあえてほぐそうとしてくれる役割も自然と担ってくれたのかもしれない。
「ラクロスってかっこいいですね」花屋さんが言った。「私も学生時代は運動したかったけど、イベント運営に忙しくてなかなかできなくて」
「ああ、まあ人それぞれありますよ。でもスポーツはいつからでも始められるんで、興味がある人は声かけてください。一通り知り合いはいるんで」
こういったリーダータイプは企業側も欲しいと思うだろう。最終選考に残された理由が見えてくる。
「終わったってことでいいですか」
そんな和やかな空気をぶった切ったのは銀縁眼鏡の人だった。どうぞ、と鬼塚くんが促す。
「長谷川 聡輔です。ゼミで経済学の研究をしていました。特にデータ解析に力を入れていて、いくつかのプロジェクトをリーダーとしてまとめた経験があります。趣味でプログラミングやロボット工作もしてました」
鬼塚くん同様に、っぽい、と思うような内容だった。彼が運動してましたと言っていたら驚いていたかもしれない。鬼塚くんに比べて、長谷川くんは身体の線が細い。そのことを別に気にしているわけではなさそうだし、どんなときも冷静でいる彼もまた、企業にとって欲しい人材に思える。
「もしかして機械とか得意だったり?」
持ち掛けたのは鬼塚くんだ。長谷川くんが乱暴に入っていかなければ、もう少し鬼塚くんの話題で盛り上がったはずだけれど、そんなことを気にしてもいないような口調だった。
「わかる範囲でなら」
「じゃあ俺のスマホがさっきから圏外なんすけど、原因とか分かったりします?」
まだ圏外だったらしい。長谷川くんは花屋さんと同じように鞄から自分のスマホを取り出して確認した。
「……俺は電波が届いていますね。一度電源を切ってはどうですか」
「試してみます」
鬼塚が電源を切っている間に、控えめな挙手があった。
「そしたら、次は私でもいいですか……?」
カンボジアの人だ。できれば早く緊張感から解放されたいと思っていたのだろう。鬼塚くん、長谷川くんが自分のガクチカを紹介している間、何度か呼吸を整えていた。
「春菜 かえでです。学生時代はボランティア活動をメインにしていて、ええと、カンボジアの子どもたちを支援する取り組みをしていました。あとは皆さんのスケジュール調整や、資金集めも任せてもらっていました」
そうだ、この話を聞いたことがある。このあとは「正直、大変なこともありましたけど」と続くはずだと思っていれば、案の定そうだった。
「やっぱりカンボジアの子どもたちが成長する姿を見ると、やってよかったなって思えて。そのときのことは、今の私にとってはかけがえのないもので、カンボジアに行けてよかったなと思います」
なぜこの人をカンボジアの人だと認識したか。そのままだ。やたらと「カンボジア」というワードを出していたから。緊張で伝えたい言葉を繰り返してしまうのかもしれない。私もできるだけ気を付けようとするのに、一番伝えたいという熱意だけが先行してしまって、その過ちになかなか気づけない。
こうして人の分析はできるのに、いざ自分のこととなると見えない。悪いところだらけのようなことは理解していても、それをどう修正していけばいいのかは不明だ。それなのに、人の志望動機や自己PRなんかを聞いていると、矛盾を見つけたり、改善点がどこなのか明確だったりする。ある意味、自分事とは思っていないところがいいんだろうか。
「麻月さんの話、すごく印象に残ってました」私が話すと、彼女は嬉しそうにこちらを見た。
「本当ですか?」
「一次の集団面接でもお話されてましたよね。ボランティア活動をしていただけでなく、現地にも行かれてたんだなと」
「自分の目で見てみたくて」
なるほど、控えめな印象はあったものの、熱意が伝わってくる。自分のやりたいことが明確にあるというのは就活においても強い。
「もしかして森さんと麻月さんは一次が一緒だったんですか?」
花屋さんが少し驚いたような顔を見せていた。私たちが会話をしていた理由も納得していたのかもしれない。そうです、とどちらかともなく言うと、「ここもですよね」と鬼塚くんが言った。
「花屋さんと俺は二次で一緒でしたよね。そのあと飲み会にも参加したりして」
そうか、だからやたらと会話が盛り上がっている印象があったのか。今日初めて会ったにしてはやたらと距離が近いと思っていた。物理的なものではなく、対話が。
「え、飲み会があったんですか……?」麻月さんは、二人の関係ではなく面接のあとに飲み会があったということに驚いているようだった。それもそうだ、面接が同じだった人間とその後飲み会に行くなんて流れを私はこれまで聞いたことがない。いや、知らないだけであったのか。ご飯を食べに行くぐらいなら聞いたことはあっても、私には経験がないから未知の世界だ。
それは麻月さんも同じだったようで、知らなかったです、とぽつり呟いた。だからといって飲み会があったとしても麻月さんは参加したのだろうか。ここにいるメンバーで飲み会に参加すると言ったら鬼塚くんと花屋さんぐらいしかいなさそうだ。長谷川くんはおそらく最初から断るだろう。飲み会に参加しているところが想像できない。これは偏見だろうか。
「とはいえ、あのとき参加してたメンバーで残ってるのは私と鬼塚さんだけみたいですけど」花屋さんが言うと鬼塚くんも「残れるなんてねえ」と盛り上げていた。
そもそも。ある程度親しくなった人間が、最終選考で二人も残っていることが異常だ。ほとんどの人間は落ちるというのに、花屋さんと鬼塚くんは競争を勝ち抜きここに座っている。
「結構いろいろ話しましたよね」
「酒が入っちゃったんで、なに話したかよく覚えてないっすけど」
初対面同士だと思ってしまったのは、おそらく他己紹介が始まるまで、二人が会話をしなかったからだろう。久しぶりです、という会話がどこかでされていたのか。それとも、今日はここまで一緒に来たとか。
それにしても、二人の打ち解け具合はここ数分で加速していた。おそらく、未来の同僚として見据えているのかもしれない。仲良くなっておくに越したことはない。ここまできてしまえば内定は確定しているのだから。
ここにいる全員が、もし同期になったら。それこそ飲み会を開催することもあるのだろう。同期だけで集まり、仕事の成功を話したり、時には愚痴をこぼしたりして、そうしてまた明日から頑張ろうと思えたりするのだろうか。まだ見ぬ未来はそう遠くない。
私もこの波に乗っておかないと取り残されてしまう。そんな焦りを抱いていると、花屋さんが「次は私がいきます」と可愛らしく手を挙げた。
「花屋 凛です。あ、別に実家が花屋とかそういうわけではないので期待を裏切ったらごめんなさい」
もしかすると定番の挨拶なのかもしれない。鬼塚くんが「それ聞きたかったんですよ」と適度な合いの手を入れた。「飲み会では、誰がご実家情報聞くかで戦争になってましたから」
つまり誰もが彼女との接点を望んだということだろう。同性であったとしても、花屋さんは魅力あふれるような人に見えるのだから、異性からするとまた別の魅力を感じただろう。
「名前負けしててちょっとお恥ずかしいんですけどね」と彼女は照れ笑いを浮かべながら自己紹介を始めた。
「学生時代で言うとSNS運用に力を入れてたんです。さっきもお話したので、またかよって思われるかもしれないんですけど、このセリフばかり練習してきたので大目に見てもらえたら嬉しいです。大学のサークルではイベント運営に関わってました。特に学園祭が一番大きなイベントで、リーダーとして企画や運営、広報まで全部こなしちゃう系の人間です。集客も結構SNSで呼びかけたりして」
実際、彼女の個人アカウントは一般人だというのに有名なインフルエンサーと同じような数のフォロワー数を抱えていた。それらを丁寧に一人ずつ見せていく彼女は「宣伝みたいになってすみません」と肩を竦めた。
「こんな感じなので、ちょっとここの力も借りたりして、学園祭では過去最多の来場者数を達成できたことは自慢だったりするので、こういうときの十八番として使ってます」
たしかに、香田さんたち向けの内容と同じだったところもあるが、それでも私たち向けのプレゼンであることは間違ないなかったし、なんといってもユーモアがあった。それだけで彼女の親しみやすさが遺憾なく発揮された時間でもある。
「飲み会でも噂になってましたよ」鬼塚くんが言った。「『あの花屋凛だ』みたいな感じで」
「いやいや、大袈裟です。というか盛り上げ上手な方しかいなかったので、変に持ち上げられて、ちょっと降りられなくなってましたから」それに、と花屋さんが続けた。「私、ただの大学生ですから有名人でもなんでもないんですよ」
「有名人ですよ」麻月さんが自分のスマホの画面を見せた。さっき花屋さんが見せてくれた自身のアカウントの画面だった。
「五十万人のフォロワーって簡単にはいかないですし」早速調べていたのだろう。早い。リサーチ力という意味でも即戦力になれそうだ。なんて採用する側でもないのに思ってしまう。実際はそうじゃないかもしれないけれど、ほかの人の何気ない行動が加点ポイントに見えてしまう。私は、どうだろう。私は、どこで加点されるような部分があるんだろう。
「たしかに、数だけ見るとちょっとびっくりしちゃいますよね」花屋さんはなおも謙虚な姿勢を貫いていた。
「そこまでいくのに、やっぱり日々の発信とか、フォロワーさんとのコミュニケーションは大事にしてました。あとは根気と継続も大事ですね。そこさえクリアできれば誰でもいけるんですけど」
その結果が五十万というフォロワー数に繋がっているのだから説得力がある。
「ちょっとその数を俺にも分けてほしいぐらいですよ」
「あれ、鬼塚くんもSNS活動してましたっけ」
「活動ってわけではないんですけど、ちょっと人脈が欲しいときってあるじゃないですか」
「私のフォロワーさんを変な勧誘しないでくださいね」
そんな掛け合いがあり、場は和んでいた。そうして「最後は森さんですね」と花屋さんからの華々しいバトンをもらうことになってしまった。
正直、彼女のあとではやりにくさがあるものの、表情に出すわけにはいかない。
「森 果帆です。学生時代でいうと、環境保護団体での活動に参加していました。詳しいことはさっき話したので、ざっくばらんでいいですかね」しっかり前置きを作っておく。私が人前で話せるようなものはこれぐらいしかない。「活動内容は、街のゴミ拾い活動がメインで、地域住民の方々との連携しながら掃除をするっていう……皆さんと比べると随分地味な紹介になってしまうんですが、個人的には目に見える成果を実感できることがよかったです」
「目に見える実感ですか?」そう聞いたのは意外にも鬼塚くんだった。これまで花屋さんの話にばかり興味があるとは思っていたけれど、何気に全員の話をきちんと聞いている。面倒見のいい兄がいれば、こんな感じなのだろうか。
そうなんです、と返しながら説明っぽくならないように心がける。
「たとえば海岸の清掃だったりすると、ビフォーアフターがわかりやすくて実感しやすいですね。達成というか、私たちの活動で、自然環境が改善されたかもしれないと思うと、無駄ではなかったんだなと思えるんです。油断すると家でサブスクばかり見てしまうので、明らかにちゃんとしたことに時間を使っているなと思えて自己肯定感が上がりやすかったりします」
ふふ、と花屋さんが笑ってくれる。この手の話は同性代なら共感してもらえるだろう。即興な部分はありつつも、この場に合わせた話しができているかと思えると自信がつく。
「実は私も参加したいと思ってたんです」花屋さんは微笑みを保ちながら言った。「友達がそのプロジェクトに関わってて、話を聞くたびにすごいなって思ってたんです」
友達が、ということについ身構えてしまう。大丈夫、興味を持ったというところだ。
「花屋さんとも活動できたらうれしかったですね」
「そう言ってもらえると私もうれしいです。それに、私も何か貢献できたらって思ってたんですけど、結局はSNSとかでしか支援できなかったので、森さんの話を聞くと憧れちゃいます」
憧れるなどと花屋さんに言ってもらうと、どこか有頂天になりがちだ。やっぱりこの話を選んで正解だった。これまでの面接でも「パンチがないね」と何度か言われていた。その度に、自分らしさというものを取り入れながら修正してきた内容だ。何度か面接でも話しているからか、淀みなく出ていくが、このメンバーで爪痕が残せたかと言われると厳しい。
全員が、私よりも優秀な人たちに見える。今までの面接では、誰かしらが「この人よりはマシかも」なんて思うような人間が一人や二人はいたのに。ここにいる人たちと戦えと言われたら、到底太刀打ちできそうにない。
「なんか、こうやってお互いのことを知るのってすごくいいですよね」花屋さんが感慨深い表情で続けた。「普段の面接だと、自分のことばっかり話して、他の人の話ってあまり聞けなくて」
「分かります。緊張して、自分が順番最後だともう頭が真っ白というか」麻月さんは何度か前髪を触っていた。おそらく癖なのだろう。そういえば、やたらと髪を触る人がいるなとどこかで思ったことがあったが、あれは麻月さんだったのか。
「いやあ、今日が一番リラックスして学生時代のこと話せた気がするっつーか」鬼塚くんに関しては、ここでなくても普段とあまり変わりがないように思えるけれど。
長谷川くんは自分のターンが終わってからというもの、口を開くことはなかった。一応、その場にいるという形だけは作られているが、誰も彼に話題を振ることはない。もう少し協調性をアピールしたほうがいいのではないかとこちらが思ったりもするが、落ちるのであればどうぞ落ちてほしい。ライバルは少ないほうがいい。
「これだけいろんな経験がある人たちが集まってると、お互いに刺激を受けますよね」そう話すと「分かります」と麻月さんが少し打ち解けたような様子で言った。
「みなさんの話聞いてたら、私のガクチカもっと磨いていきたいって思いました。とはいえ、もうこれが最終面接なんですけど……」
「全員が内定取れたら、絶対に楽しい職場になりそうだなあ」
鬼塚くんの言葉に、つい自分がここで入社したあとのことを考えてしまう。
パリッとしたスーツを着て、颯爽とオフィスを歩く自分。香田さんが身に着けていたような、あのブランドものの腕時計を装着する日はくるかもしれないし、そのころには優雅な一人暮らしもできているだろう。
今は実家を出ているというものの、自分一人だけの生計ではとてもじゃないが間に合わず、ここ数か月は就活が始まったことで、落ち着くまではと全額援助してもらっている。そんな自分ともおさらばできる日がくる。輝かしい未来が、もう少しで手に入りそうだということが今でも信じられない。
「同期として一緒に働けるって思えると、なんか不安が消えました」
「麻月さん、不安なんて吹き飛ばしていきましょうよ。今度、みんなで集まってご飯食べません?」
「いいですね……! どこかいいお店知ってますか?」
「私、サークルでも結構幹事任されることが多くて、いろいろ知ってるんですよ」
花屋さんの提案に、鬼塚くんが「あれ」と思い出したように声をあげた。
「この前の店も花屋さんが予約してくれたんじゃなかったっけ」
「あそこは知り合いの人がいて、ちょうど開けてくれたんです」
「お店の知り合いがいるとか、かっこいいですね」思ったことをそのまま伝えると「たまたまってだけで」と鼻につかない返しをされた。私だったらもう少し自慢げに話してしまうかもしれない。
「どんな料理がいいか言ってもらったら候補挙げますよ」
「俺はイタリアンとか好きだなあ」
「私もいいなと思いました。麻月さんとかどうですか?」
「あ、いいと思います」
「そしたら、ちょっと奮発しちゃいません?」
「わあ、それいいですね! お祝いも兼ねて」
「それじゃ、みんなで内定もらったら予約入れておきますね」と花屋さんが冗談交じりに言うと、全員が楽しそうに笑った。ただひとり、輪に入ろうとしない長谷川くんを除いて。
「ちなみに、長谷川くんはどんな料理が好きですか?」
そんな彼など私だったら放っておいてしまうのに、花屋さんは声をかけるという選択を取る。今まで、同じクラスの人が一人で行動していたら、つい輪に入れてしまうようなこともあったのだろうか。長谷川くんの瞳が若干動いた。
「強いて言えば和食です」
「ああ、そっちもいいですよね。和食はまた落ち着くし」
「ですが、あまり浮かれないほうがいいのではないですか」
これまでの空気を凍らせてしまうような勢いだった。築き上げようとしてきたものが、この人の言葉で崩されていく。少なくとも、ここから未来の同僚が生まれるかもしれないというのに。仲良くしておいて損はないはずだ。それなのに、どうしてこの人は輪を乱すようなことばかりをしてしまうのだろう。愛想ひとつさえ難しいのだろうか。
おいおい、と鬼塚さんが困惑しながらも笑みを浮かべる。
「別にこれぐらいいんじゃないっすか。それに、正直言って最終面接までいけたら内定確定みたいなところあるらしいんですよ」
内定確定。そうだ、私たちはほとんど内定がすぐ目の前にあるような立場だ。
よっぽどのやらかしをしなければ落ちることのほうが珍しいとさえされている。
この人は採用されたいわけではないのだろうか。どうしてここにいるのだろう。
「鬼塚くんも知ってたんだね。私もさっき森さんと話してたんですよね」花屋さんに振られて「あ、はい」とつい答えてしまった。だから、「あ」は要らないんだよ。自分に叱責していれば「おそらくないと思いますよ」と、またしても空気が読めない発言をする長谷川くん。
そうですね、などと返ってくるかと思っていたけれど、彼の答えは予想外のものだ。
「……ないって、どういう意味ですか」麻月さんが控えめに聞いた。
「そのままの意味です。全員が内定というわけにはいかないでしょう」
「あのさ、さっきからなんなの」いよいよ鬼塚くんの顔からも笑顔が消える。「ちょっと尖りたいみたいな感じ?」
「そう見えているのならそうでしょう。ただ、あまりにも愉快な人たちが揃っているなと感心していただけなので」
「愉快って」
険悪なムードとはまさにこのことだ。
長谷川くんさえいなければ、今頃楽しく雑談をしていたはずだった。
他己紹介だって褒め合うような形で披露して、全員で内定をもらう。それは理想と形といえる。こんな私でも「納得内定もらえた」と言えるような日がくるかもしれない。そんなことが現実になりかけている中で、この人だけが、やけにそれを許さない。
「あの──」言いかけたところで、コンコン、とノック音が響いた。すぐに香田さんが入っては、会議室を見渡した。和やかな空気から一変した異変を、香田さんは気に留めることなく「お疲れ様でした」と労いの言葉をかけてくれる。
「時間は足りましたかね」
本当ならば、もう少しそれぞれの話を聞いていたかった。他己紹介をするには情報が足りないようにも思う。その人の新しい一面みたいなものが見えたらポイントは高かったはずだ。
「それでは、他己紹介に移る前に、少しこちらからルールを追加させていただきます」
ルール、という言葉に引っかかりを覚えた。おかしなことを言われたわけではないのに、なぜか妙な胸騒ぎがしていた。
「みなさまには、匿名による他己紹介を行っていただきます」
香田さんの言葉に、会議室は静まり返った。匿名の部分が引っかかったのは、おそらくこの場にいる全員だっただろう。
互いを知ることが目的なのに、どうして匿名にする必要があるのか。
「今後は別室でみなさま待機していただきます。時間になりましたら係の者から案内がありますので、通された部屋で他己紹介を行っていただきます」
「え、あの……待機って、全員一緒ってことですか?」
「いえ。たとえば森さんでしたらA室、鬼塚さんでしたらB室と部屋が異なります。また順番も事前に告知することはございませんのでご了承ください」そして、とまるでここから先が最も重要だと言わんばかりに、香田さんは、一度全員を見渡してから、こう続けた。
「他己紹介をするお相手は、こちらから指定いたします」
これは、私が知っている他己紹介ではなかった。
説明を聞いても、独自のルールが設けられ、そしてそれは、私たちにとって青天の霹靂でもあった。なんだ、匿名の他己紹介って。
香田さんは、なおも説明を続けた。
「みなさまには他己紹介の最後に、おひとり推薦していただきます。他己紹介のお相手と推薦は別の方でも構いません。目的としましては、みなさまだからこそ知るその方の人間性と、そして誰を推薦するのか──この二点に重点を置きたいと考えています」
「ちょっと待ってください」
手を挙げたのは鬼塚くんだった。
「匿名の内容は、本人が知ることは可能なんですか?」
「いえ、ご本人様には伏せた情報となり、最後まで明かされることもございません。もちろん、ご自身の評価を知りたいという申し出もご遠慮いただきます」
「ありがとうございます。追加で質問いいですか」鬼塚くんは臆することなく二つ目の質問に入った。香田さんは「もちろん」と頷く。
「今回、推薦枠が用意されたご意図を伺ってもよろしいですか」
それは誰もが知りたがった情報のはずだ。鬼塚くん以外、意見を発することはなかったが、香田さんの答えを全員が待っていたような気がする。
「これはとても大事なところですね。みなさまにここでお伝えさせていただきますが、今回の内定枠はお一人となります」
「一名……ですか?」鬼塚くんの声が一瞬かすれた。他の参加者たちもざわついた。会議室内の空気が急に重くなったように感じたのは、私だけじゃない。
「はい、それぞれが素晴らしい成果を持つことは理解しておりますが、企業の現状を踏まえた決定です」と香田さんは淡々と説明を続けた。企業の現状とは言うが、本当だろうか。ここにいる五人、全員を採用するだけの余裕はあると思っていた。
「ですので、推薦には慎重さが求められます。ただし、ここで推薦された方が即座に内定となるわけではなく、推薦理由、そして匿名の他己紹介と照らし合わせて検討したいと考えています」
その言葉に、会議室の静けさがさらに増した。私は内心動揺していた。これまではライバルがいても、どこかで全員が一緒に受かる可能性があると思っていた。けれど、たった一人しか採用されないとなると、この他己紹介と推薦が一層重大なものに感じられる。
鬼塚くんは「ありがとうございます」と戸惑いながら口にしてからは、質問を重ねることはなかった。眉間にしわを寄せながら何かを考えている様子だ。
推薦枠は、選考の中でも大きな力を持つ。誰を推薦するか、そして誰に推薦されるかが、これからの結果を左右するだろう。それに、匿名の他己紹介。これは想像している以上に、恐ろしいものになるのではないか。
なぜなら、私たちの前だけで発表するわけではない。さっきのように和やかに自分たちのことを紹介しているような和気あいあいとした時間ではないだろう。匿名の他己紹介を行うのは、香田さんたちの前だけだ。そして、用意された推薦枠と、内定枠一名。
つまり、他己紹介も推薦も、すべてが選考に直結している
ここまでくればほぼ内定を勝ち取ったといってもいい。そう話していた未来が、一気に崩れていく。
「では、それを踏まえて、もう一度みなさまでお話をする機会を設けたいと思います。時間は先程と同じ一時間でどうでしょうか」
香田さんの問いかけに、全員が混乱していたけれど、反対するものはいなかった。
「問題ないようですね。では、お願いします」
それから香田さんは初めて会ったときと変わらない親しみやすそうな笑みで会議室を出て行った。
「なあ」
沈黙が流れていたが、それを破ったのは低い声だった。ここでそんな声を出すのは彼だけだろう。
「知ってたのか、このこと」
鬼塚くんは、長谷川くんを見ていた。「なにがです」と彼はこの状況には不釣り合いなほど余裕だった。
「内定が一人だって。さっき、浮かれないほうがいいって話してたのは、このことがわかってたからなんじゃねえのか」
口調が乱暴だ。香田さんの前とは別人としか思えない。
「答えとしては、知らなかった、が正しいです。ただ、よくよく考えればわかることではないですか。まさか本気で、この場にいる全員に内定が与えられるとでも思っていたんですか」
ありえないでしょう、と嘲笑うように長谷川くんは言った。その姿に怒りと、恥ずかしさが一気にこみ上げてくる。
「お前っ」
鬼塚くんが立ちあがったのを、花屋さんが「まあまあ」となだめる。
「とりあえず、事実がわかっただけでも良かったんじゃないかな。内定枠が一人だってことは確定したわけなんだからさ」
花屋さんが冷静でいてくれることが唯一の救いだった。けれど、それだけでは解決にならない。それは麻月さんも同じだったのだろう。
「……でも、これって最悪ですよね。香田さんの話では、私たちが内定枠の一人を決めるってことじゃないですか」
「そんなことは言ってなかったと思うけどな。あくまでも、検討するってだけで」
そう落ち着いた様子で花屋さんは話していたけれど、私も麻月さんの意見に同感だった。
「他己紹介の中身と推薦、これら二つを重要視すると言っていたので、やっぱり内定に繋がるという考えにはなると思います。言い方を変えると──」
「自分を選んでもらうか、それとも他者を蹴落とすかってところだろ」私が言いたかったこを鬼塚くんが拾った。
「……まあ、結構最悪だなとは、私も思ってるんですけどね」
さすがの花屋さんの笑みも、困惑が広がっていた。この場が混乱しないように、あえてポジティブな意見を口にしてくれていたのかもしれない。
「ここまできて、内定枠が一人とかなんだよそれ」
鬼塚くんが頭をかく。
「もし本当だとしたら」麻月さんが呟く。「全員で仲良くやってる場合じゃない、ってことなんでしょうか」
その言葉に、全員が一気に緊張感を増していく。仲良くやってる場合じゃない、か。ついさっきまでは、同僚になれるかもしれない、この波にのらないといけないなどと汗っていたというのに。
「そういうことだよ」と鬼塚くんが、苛立ちを隠せない様子で声を荒げた。「結局、俺たち全員ライバルなんだ。仲良く見せかけてるけど、最後に笑うのは一人だけだってことだろ?」
麻月さんは視線を落とした。「でも、どうしてこんなやり方を……最初からそう伝えてくれれば、もっと別の方法があったような気がするんです」
「それが向こうの狙いなんでしょう」長谷川くんが静かに口を開いた。「面接官たちは、僕たちがどうやってこの極限の状況を乗り切るか見ているんです。協力し合い、誰かを推薦するのか、それとも自分の利益だけを考えて動くのか」
その分析に、場の空気は一層重くなった。今までの穏やかな雰囲気は、まるで一瞬にして消え去ったかのようだ。自分のことしか考えない人間が誰なのか、お互いに探り合うように、全員の視線が交錯した。
「もう、時間はないぞ」と鬼塚くんが短く言う。「このまま続けるのか、それとも全員でこの馬鹿げた試験を辞退するか」
「ちょっと待ちませんか。さっきまで和やかに話してたのに、急にそんな話をされても……」
花屋さんが言いたいことはわかる。けれど、私たちの将来は全員が決して明るいわけではない。むしろ、ほとんどの人間がどん底に突き落とされてしまう。ここまできたのに、またやり直さなければいけない。それだけは避けたい。
「とりあえず、まずは落ち着いて話しをしませんか」花屋さんが訴えたとき、この場に不釣り合いな軽快な音が響いた。
ピー、と聞き覚えのある音が始まり、その後、ガ、ガ、ガと何かが動き出す音。それは、この場にいる全員なら聞き覚えのあるものだった。
「また……」
麻月さんが言った。
プリンターから近い長谷川くんが様子を見に行った。しかし何かを言うことはない。
「それ、誤作動があるって香田さんが言ってましたよね」
「いや」
長谷川くんは先程までなかった一枚の用紙をプリンターから取った。
「これは誤作動ではないと思います」
そこには──。
【ラクロス部ではマルチ勧誘が行われており、首謀者は当時のキャプテンだったとされている】
「……え、なにこれ」
全員が凍り付いた。
この場でラクロス部といえば、一人しかいない。
「いやいや、なんで俺を見るの」
鬼塚くんは困惑した表情を浮かべながら、周囲の視線を避けるように笑った。しかし、その声はどこか焦りがにじみ出ていた。
「そもそも、このプリンター調子が悪いとか言ってたし」
「調子が悪いことに結びつけるのはどうなんでしょうか」
焦ったような鬼塚くんとは対照的に、長谷川くんが眼鏡の縁を軽く持ち上げた。
「内容としては、鬼塚くんを示唆するようなものとして受け取ることはできます」
「いや、だからって俺はこんなことやってない。それにラクロス部でもこういった話は一度もなかった」
「確かめる術はありませんからね」長谷川くんの冷静な態度が、逆に鬼塚くんの焦りを煽っていた。こんなことを言われてしまえば苛立ちを覚えるだろう。
突然、険悪な空気が漂い始める。まるでこうなることが想定されていたみたいに。あの、と控えめに声をあげたのは麻月さんだった。
「調べたら……ネット記事で出てきて……ちょうど鬼塚くんが在籍されている期間と一致するのかなと思ったりで」
スマホの画面には、名前こそ伏せられていたものの、鬼塚くんが通っていた大学名と、マルチ勧誘に関わったとされるラクロス部が大々的に報じられている。言われてみれば、こんなニュースを過去で見たことがある。そのときは他人事だと思っていたが、その当事者が目の前にいるとなると話は別だ。
「だから……あ、圏外になっちゃいました」麻月さんは不審がるような表情を浮かべた。
これで二人目だ。妨害電波でも出ているのだろうか。
「この情報が出てきた以上は、無視ができないですね」
確信をついたとばかりに長谷川くんが結論付けた。
「はあ? いや、だからデマだって! 俺は知らなかった」
困惑が広がっていた。これから匿名による他己紹介が始まれば圧倒的に不利な状況にはなるだろう。
「……言っとくけど、真に受ける人間なんていないよな?」
唸るような、とても低い声だった。
「ここにいる全員が黙っていれば、俺の評価は変わらない。そもそも、これは嘘なんだから信じるほうが馬鹿げてると思うけど」
「でも、嘘だって証明もないですよね……?」
私の言葉に、鬼塚くんはゆっくりとこちらを見て、そして睨んだ。
「証明って……こんなのないでしょ、ふつうに考えて。俺が在籍してたから、事件に関わってるとか思われても」
「じゃあ、この事件のことは知ってたんですよね? ここまで騒がられていたら」
鬼塚くんはしばらく私を見ていたけれど、そのまま諦めるように目を閉じた。
「知ってる」
「……どうして、さっきはデマなんて」
「否定したくなるだろ、こんなときに、この情報が出てきたら。ただ、この事件のことは最後まで知らなかった。警察にも話してるから確認すればいい。俺は嵌められただけだ」
「嵌められたんですか」
今度は花屋さんが口を開いた。
「そうだよ。俺が部長に就任する前に、あの事件はすでに起きてた。俺が部長になった頃には、ラクロス部がマルチ勧誘の温床だっていう噂が広まってたんだ」
「ではなぜ、一度否定したんです」
長谷川くんが鋭く指摘する。それもそうだ。ついさっきまで、鬼塚くんはこんな話を聞いたことは一度もないと言いきっていた。それなのに、今では、マルチ勧誘が行われていたということは認めている。
「……だから言ってんだろ。ここまできたら、そういう過去も否定したくなるって」
誰よりも発言力があり、そして行動力に溢れていた人が、今は萎んだ風船のように小さく見えてしまう。
「でも俺は何も知らなかったし、関わってない。全部終わった後に知った。それが全てだ」
それだけ言うと、鬼塚くんは口を閉ざした。おそらく、これ以上喋ったとしても無意味だと判断したのだろう。おそらく、彼ではなくとも、ここにいる全員が彼の立場になれば同じことを思ったはずだ。
「……警察に話してるってことは、証明できる可能性はあるってことですね」と麻月さんが言った。そこに、花屋さんが「そうだと思います」と続けた。
「どちらにしても、この場ではすぐに確認することはできないですし。だから、今は鬼塚くんの話を信じませんか」
「ですが、こういう情報が出てきた以上、誰かが意図的に動いている可能性は否定できません」と長谷川が冷静に指摘した。「匿名の告発。プリンターの不審な動き。何かしらの仕組みが働いていると思ったほうがいいでしょう」
でも、誰かって、一体──。
駅のホームに座り、かかとより少し上にできた傷に塗り込んでから絆創膏を貼った。これで痛みがなくなるわけではないが、軽減はされる。応急処置程度のものだったが、何度も靴擦れができるためか、これが通常となった。履き慣れなかった新品のパンプスは、すでに細かな傷が入っていた。
電車が来るまでの数分間。ホームに立って並んでいたほうがいいとはわかっていても、今日に至るまでの疲労からか、今座れることを優先してしまう。電車では立つことになるかもしれないのに、その少しあとのことを考えられるほどの余裕がない。
スマホを取り出すと、友人のストーリーに【納得内定もらえた】という投稿があった。
つい数週間前は【ES一枚で私の良さなんてわかるわけねえだろ】と毒づいていたが、どうやらうまくいったらしい。納得、という言葉が引っかかったが、だからなんだという話だ。
内定をもらったという話を聞く度に、焦りや不安がないぜまになったような、どうしようもない感情が湧き上がってくる。
私の場合は周りよりも先に就活を始めたことが原因のひとつだった。自分よりも後から始めた人たちのほうが内定をもらい始めている。その現実から遠ざかるように、何枚もESと略されるエントリーシートを書いては企業に応募を続けた。
けれど、そんな生活も今日で終わるかもしれない。
手の中にあったスマホが僅かに震え出したのは電話を知らせる合図だった。表示されているのは母だ。もしもし、と出れば快活な声が聞こえてくる。
『今日が最終面接だったでしょ。ほら、あそこ、なんて名前だったかな。あれよ、パンみたいな名前のところ』
「ベーグル社。みたいじゃなくて、そのままだよ」
『そうそう、そこ。お母さん、会社の名前とかは知らなかったけど、同じパートさんで知ってる人いたんだわ。なんか、ものすごいところらしいね。娘が最終面接に残ってるって話をしたら果帆のことを褒めてたよ。競争率も高いんだってね。なんかパソコンの人たちを応援するみたいな会社らしいけど』
母は動画配信にはからっきし弱い。
ベーグル社。近年急成長を見せる企業と知られ、革新的なアイデアを持つ企業文化が特徴的だった。福利厚生も充実しており、社員同士の関係が良好であることが多くの就活生を惹きつける要因──とそれは上辺だけの理由だ。
ここにいる全員、破格の初任給に飛びついているとっても過言ではないだろう。しかも年に二回あるボーナスが、入社一年目では考えられないような金額であることも関係している。
若手社員の意欲を引き出すために、企業側がしっかりと評価していることが感じられ、どこよりも気合いを入れて挑んでいた。また、リモートワーク制度を推奨しているあたり、ここ以外にはもう考えられなかった。
事業内容はプラットフォームで成功するためのオンラインコースやワークショップを提供。内容には動画の編集、コンテンツの企画、SEO対策、マーケティング戦略などを含んだりと多岐にわたる。正直、大学時代にかじったことがある経験が功を奏し、結果的に最終までこぎつけることができた。
それらの話を以前、母にしたことはあったが「難しいところだね。やっていけそう?」などと返された。ほとんど理解できなかっただろう。母は高校を卒業してすぐに父と結婚をし、専業主婦を経て今は気ままにパートをしている。
就活などの経験はないためか、私がどれだけ大変だと嘆いても「内定さえもらっちゃえばいいんだから」と片付けてしまう。
その内定を勝ち取ることがどれだけ難しいか、わからない人と会話をするというのは今の私にとって心底嫌悪しかない。
『それでね、果帆のこと話してたら子どものときのことも思い出して。ほら、覚えてる? 小学生のときにお友達と喧嘩になってお母さんと謝りに行ったこと』
「……いつの話をしてるの」
『果帆ってば、意地張って謝れなかったでしょう。明日からこの子、学校に行けるのかなって心配だったけど、ちゃんと自分たちで仲直りしてたもんねえ』
昔の話になると長くなる。平気で一時間を取られてしまうだろう。
『まあ、果帆ならできるから。自分らしくやればいいのよ』
鼻で笑ってしまいそうだった。就活を始めてから自分のことなんてわからなくなり、自己PRや学生時代に力を入れたことなんかを聞かれる度に、自分という人間を作り上げてきた。
長所も短所もわからない。自分の魅力はなんですかと聞かれた面接もあったが、そんなものは教えてほしいぐらいだった。
母との電話は苦痛となり、電車がもうくるからと嘘をついて切った。まだ話したそうにしていた母は、おそらく娘がすごい企業に入れそうだという優越感にもう少し浸っていたかったのかもしれない。正直言って迷惑だった。
目の前でキャリーケースを引いた就活生が横切っていく。同じく黒のスーツを身に纏った女性だ。あの人も今からどこかの面接だろうか。同じような姿をした人を見ると、妙な親近感を覚える。ここまでどれだけの苦労があったか語ってみたい。
ベンチから立ち上がると靴擦れをしたところが痛んだ。その場しのぎを続けたところで根本的な解決にはつながらない。パンプスを買い替えればいいだけの話だけど、余計な出費は出したくない。就活費用の平均金額は約十万円前後とされている。交通費、被服費、宿泊、それに加えて飲食費から就活のための書籍などを揃えていくと、とてもじゃないがパンプス一足を買うことが躊躇われてしまう。
大丈夫、今日で最後になるかもしれない。それなら、このパンプスでもう少し耐えよう。
とある会議室に通されたのは最終選考に残った五人と、企業の経営陣が五人。左から事業部長、執行役員、社長、人事部二人。これまでにもほかの企業で面接を受けたことはあったが、最終面接ともなればこれだけの面接官がいるのかと正直怖気づいてしまいそうだった。それとも、ベーグル社の気合いがこうして現れているのか。どちらにせよ、ここで合否の判断が下されてしまう。
進行役を務めていたのは人事部の一人、香田さんだった。それぞれが名前と志望動機を話し終えると、ありがとうございました、と朗らかに微笑んだ。
「では、あとは事前にお知らせをしていた他己紹介ですね。その前に休憩を挟みましょうか」
十五分でどうでしょう、と香田さんは自身の腕時計を確認した。シンプルながらも洗礼されたデザインで、着こなしていた深いネイビーブルーのスーツにもよく似合っている。
いかにも仕事ができる人のようで、この人と一緒に働けたらどんなにいいだろうかと気分が高揚してしまう。それを隠しながら気を引き締めた。
自然と壁に設置されたスクリーンに視線が流れた。ついさっきまで流れていた映像は、今では会社の広告へと切り替わっている。企業理念は「つながりを創り、成長を支える」。
その言葉が流れてくるのはもう何度目だろうか。
ここに来るまでにも何度か頭に叩き込み、自分の志望動機と絡められるようにしたつもりだが、そこまで響いていなかったように思う。
ただ、そのときの反応だけで結果がわからないところがもどかしい。これまで受けてきた三十社の中では、ぜひ前向きに採用を検討したいと言ってもらったこともあった。
そう言われてしまえば少なからず期待してしまうものだが、大体はお祈りメールが届く。どうせ落とすなら、舞い上がらせないでほしい。就活生を弄んで楽しいのか。苛立ち、そうしてまた新しくエントリーシートを書いては、直近の説明会やインターンのスケジュールを確認する。こんな生活がもう何ヶ月と続いている。
大丈夫、ここまできたんだから。最終選考に残れるなんて初めてだ。ここで結果を残さないと。
最も危惧していたガクチカが終わったことで安心を覚えている一方で、私はまだ運に恵まれているほうなのだと知る機会でもあった。そもそも、ここまで残れたことが奇跡としか言いようがない。
香田さん以外が続々と会議室から出て行く。全員が私たちに「お疲れ様」と声をかけてくれる。なんといい人たちばかりなのだろう。これまで圧迫面接を受けた経験もあるからか、ベーグル社の人の良さというものをつくづく実感する。
「みなさん、あと少しですがリラックスしましょう」
最後に香田さんが出て行くと、どことなく張りつめていた緊張感が僅かにほぐれたように感じた。しばらく静寂が包まれる。十五分となるとお手洗いを済ませておけということだろう。しかし誰も立つことはない。
会議室は広く、正面がガラス張りだった。向かい側の企業が忙しなく働いている。身に纏っている服装が色鮮やかで、就活生の象徴となる黒のスーツを今すぐ脱ぎ捨ててしまいたくなる。
会議室には、ホワイトボード、プロジェクター、観葉植物、プリンター、パソコン、プロジェクター、あとはテーブルや椅子が置かれていた。
いまだに面接の空気が残る会議室で、一番最初に動いたのは扉に近い男性だった。たしか鬼塚と言っていた。体格が良く、学生時代はラグビーかなにかのスポーツをやっていたと話していた。それから今度は綺麗な栗色に染まった髪の女性が出て行き、続くように銀縁のメガネをかけた男性が出て行った。
残ったのは一つ椅子を挟んだ先にいる女性だけ。適度に時間を潰そう。ここでスマホを使うことは避けたほうがいいとは分かっていても、ついSNSをチェックしてしまう。私と同じように今日が最終選考だと呟いていたあの人はどうだったのだろう。今頃は終わっているかもしれない。
就活用のアカウントを作ってからは、あまり呟くことはせず、見る専門となっていた。どうやらまだ面接は続いているようで、私も残りの時間をなんとか耐えようと自分に鼓舞する。そのまま流れるようにメールをチェックする。
時折、急な連絡が入っていることもあれば、お祈りはされたけれど、もしかしたら、みたいな可能性があるのではないかと馬鹿みたいにまだ期待してしまう自分がいる。
内定がもらえれば、この地獄から抜け出せる。そのとき、気になるメールを見つけた。内定の文字が見えたような気がしたそのとき、「あの」と声をかけられた。残り十一分というところだった。
「一次の集団面接で一緒……でしたよね?」
一列に並んだ椅子で、左から二番目に座っていた女性が少し立って私を見ていた。一次と聞いて、そういえばここは一次の時から集団面接だったということを思い出す。
控えめな印象愛らしい笑顔で、黒い髪が肩上で切り揃えられていた。名前はなんだっけ。さっき聞いたはずなのに。顔はなんとなく覚えているぐらいだった。ただ、学生時代のエピソードでカンボジアの子どもたちの話をしていたことだけは覚えている。
そうでしたよね、と話を合わせながら思い出そうとするが、やはりカンボジア以上の情報が思い出せそうにない。とはいえ、今さら「お名前は」と聞くのも失礼だろう。
「あのとき、絆創膏をお借りして、……あ、一枚お返しします」
絆創膏?
言われてみれば、面接の前に絆創膏を自分ではない誰かに渡した記憶がある。律儀に一枚だけ絆創膏を取り出すと、そのまま渡された。
「ありがとうございました。また会えたらお返ししたいと思っていたんです」
「いや、そんな。たかが絆創膏一枚なので」
「本当に助かったんです」
そこまで感謝されるものだったのだろうか。私にとって絆創膏は、靴擦れの痛みを耐える代物でしかない。おそらく彼女にも似たような意味合いで渡したのだろうとは思うけど、ここまでありがたく思ってもらうと、この一枚を受け取るのは気が引ける。
そんな私を察してか「あ、あのお返ししたいだけなので」と念押しをされる。人との貸し借りはきちんと清算しないと気がすまない人なのかもしれない。ここは素直に受け取っておこう。
「ではお言葉に甘えて。ありがとうございます……って、これちょっといいやつじゃないですか」
一枚、百五十円ぐらいするものだ。
私が彼女に渡したのは百円ショップで買ったものの一枚だ。ちなみに六十枚も入っていたから、それに比べると高価なものだ。おそらく今の私なら絶対に手を伸ばすことはないであろう価格帯の一枚だった。
たかが絆創膏を買うことが、今の私にとっては痛手だ。彼女はそうではなかったのだろうか。こういう些細なところで金銭感覚の余裕を感じてしまう。別に何を買おうがその人の自由で、安いだけを重要視したのは私の問題だ。それなのに、この世は不公平だ、なんて思わないわけでもない。
同じ就活生であっても、財布やキーケースなどの小物がブランドものだったりすると、この人とは仲良くなれそうにないなと思ってしまう。私が、というよりも、私のような人間がこういう人たちと関わることは避けたいだろうなと思うからだ。
小物に気を遣う人は、やはり他人の小物も見ている。自分が気にしているところは、いくら「関係ない」と割り切っていたとしても目につくだろう。そうして、無意識な判断が瞬時に繰り広げられる。この人とは仲良くなれそう、この人とは無理そう、みたいな。
「あっ、すみません。同じものでお返ししたほうがいいですよね」
申し訳なくなったのか、私の反応を見て気まずそうな表情を浮かべた。たしかに、私が渡したものよりもずいぶんとお高いものとして返ってきてしまったけれど、ここには悪意というものがないし、本当に気持ちとして渡してもらっているということが伝わる。
それは彼女が持つ空気感みたいなものかもしれない。言葉の端々で、丁寧さを感じられる。すかさず「嬉しいです」とバッグにしまわれてしまう前に受け取った。
「私のは安くて大容量なものだったので受け取っていいか迷ってしまって……でも、せっかくなので大事なときに使わせてもらいます」
「そんな、いつでも使ってください」
照れくさそうにする彼女に、親しみを覚えた。ここで名前が出せたらいいのだけど、やはり思い出せそうになかった。
「それにしても、二人して最終面接に進めるなんて本当によかったですね」絆創膏を受け取りながらそう言うと、彼女は「私は運のみなんですけど」と、肩をすくめた。
「こうして森さんや、ほかの方を前にすると、実力で選ばれてきたのだなということが痛いほどわかるといいますか。私は本当に、運頼りなところがあるので」
「そんなことないです。運はあるかもしれないですけど、みなさん実力ですから」
ここまで来るのに“ただの運”とは思いたくなかった。
就活での正解はほとんどない。会社の気分によって採用人数が変わることがあれば、面接官との波長が合うか合わないか、気に入られるかどうかで決まってしまう。数学のように決まった式があるわけではないからこそ、就活に悩む人は多く、私も頭を抱えてきた。
早く終わってくれと何度思ったことだろう。
「でも、ここってすごいですよね」彼女は続けた。「一次のとき、ちょっとびっくりしたんです。リモート参加の人もいるってことに」
「わかります。リモートの面接はありますけど、リモートとそうではない人が同じ面接の時間になるってところがおどろきですよね。ここがリモートワークを推奨していることもあって、面接をリモートでしてもらえるって心強いですけど」
「とはいえ、あのときみたいにトラブルがあると対処できそうにもないです」
回線が不安定になると、途中で離脱するということもある。そうなると、おのずと採用の文字は遠ざかっていくだろう。そうなるぐらいなら、ここまで足を運んで、直接面接してもらえたほうがいい。
「お互い内定がもらえるといいですよね」
本当ですよ、と返していると一番最初に戻ってきたのは、女性だった。花屋さんだ。花を扱う花屋と一緒だと覚えていたが、何よりも洗礼された身だしなみ、違和感のないメイク、そして整った顔もあってかよく覚えている。
なぜここにいるのだろうと思うほどの美しさを兼ね備え、さっきの自己PRでは彼女の良さが余すことなく伝わっていた。目が合うと、にこりと微笑まれた。
「ここのトイレ、すごい綺麗でしたよ。パウダールームが別にあって」
あ、とつい言葉が出てしまった。人と話すとき「あ」とやたらと付けやすい。特に彼女のような人を前にすると、なぜか妙に緊張してしまう。私自身が、花屋さんのような人とは無縁だったからだろう。気を付けていたつもりなのに、まさか花屋さんのような人から話しかけられるとは思わず戸惑ってしまった。
「やっぱり私も行っておけばよかったです」
「まだ間に合いますよ。時間も、うん、余裕がある」
こういう人は敬語とそうではないときのバランスが絶妙だ。人の懐に、ふわっと入れるような性格なのだろう。真似ができそうで、いざ自分がすると気味が悪かったりする。バランスが悪く、変に馴れ馴れしい人になってしまいそうで。憧れるのはいいが、だからといって同じことをしていいわけでもないなと高校生のときから思ってきていた。
「ええと、それなら」と「じゃあ」と切り出したのは同じタイミングだった。ここに花屋さんの声はない。私と、隣にいたカンボジアの人だ。彼女が立ち上がると、かさりと、何かが擦れる音が聞こえた。軽く足元を見てみたけど、何かが落ちた形跡はなかった。
「ちょっと行ってきます」
「はい、行ってらっしゃい」
つい行くタイミングを逃してしまう。意識してしまうと妙に行きたくなるのだから不思議だ。だからといって、「ちょっと私も」というのも、今度は花屋さんとは一緒にいたくないのだと捉えられてしまわないかと不安になる。そういうわけではない、でも、あえて言葉にするようなことでもない。
昔からこうだ。考えすぎると行動に移せない。
そのまま時間だけが過ぎていく。結果だけ見ると、何も動いていないだけの人間になる。
頭の中ではあれやこれやと選択肢を浮かべては悩んでいるのに、そんなことは周囲に伝わるはずもない。判断が遅いと、いつも自分に嫌気が差す。思い立ったら、それが正しいことではなかったとしても、後悔を減らす選択肢を取れるようになりたい。
花屋さんはカンボジアの人を見送りながら、「正直、ここまで来るとちょっとホッとしませんか」花屋さんが話題を作ってくれた。
「あ、そうですね。最終面接までいけたら内定確定みたいな噂を聞いたことがあって」
「ですよね。私もキャリアセンターの先輩に言われて、ちょっと調子に乗ったっていうか」
「乗りますよね、ここまで来れたんですから」
「こうなったら全員内定ってことにしてほしいですよね」
そんな話をしていると、一番最初に出て行った体格のいい男性が戻ってきた。なぜか首を傾げてスマホを見ている。「おかしいな」と呟く姿を見て花屋さんが声をかけた。
「どうかしたんですか?」
「ずっと圏外なんですよ。今日昼から予定あって、この調子だと間に合わなさそうだなと」
「ああ、他己紹介ですよね。ちょっと私も見てみます」
花屋さんは傍らに置いていた黒のバッグを自分の膝の上に置いた。上部にゴールドの英語が書かれている。もしかしてブランドものだろうか。就活にブランドものは悪目立ちしてしまうため避けたほうがいいとされていた。そのため、私はディスカウントショップに売られていた三千円代のものにした。ただただ金銭的余裕がなかったからに過ぎないけれど。
「うーん、今のところ私のスマホは電波拾ってますね」
一応私も確認してみたが圏外のマークはついていない。「私も電波あります」
「じゃあ俺だけか。なんでだろ」
そのまま、さっきのメールを確認する。やはり内定の文字は見間違いではなかった。だが、はっきりとした内定でもなかったのが事実だ。
内容は、内定をもらうには、という胡散臭いビジネス臭が香るものだった。就活用のアカウントも、やたらとこういったDMが多く届いていた。中には口座を登録するだけでお金が入ってくるといった詐欺もある。
その口座はなぜか作るとパスワードが求められ、送ってしまったが最後、乗っ取られてしまうという。こういった話は珍しくもない。それでもお金に困っているタイミングで、口座を作るだけでお金が入ってきますよなどと誘われてしまえば、ほんの軽い気持ちで作ってしまうのはわからなくもない。
やはり、ここで内定を勝ち取るしかないだろう。
そこまで不安になることもない。花屋さんが言っていたように、ここまできたら内定をもらったのも同然だ。ひとまずお金の心配をそこまでする必要もなくなるだろう。ここさえクリアできてしまえば、バイトを入れることもできる。内定がもらえれば。それだけで私の人生は豊かになり、そして余裕さえ生み出してくれる。内定があれば。
そんなことを考えていると、銀縁眼鏡の男性が戻ってきた。彼は雑談に入ることなく自分の席に座る。名前は憶えていないが、高学歴だとされる大学名を出していた。いかにも頭が良さそうな喋り方で、わかりやすかったが他人に隙を与えないような印象だった。
残り五分。まだ少し時間に余裕はある。
「やっぱりちょっと行ってきます」
花屋さんに声をかけると、どこに行くのかわかったようで「会議室出て右にありましたよ」と教えてくれた。どこまでも気遣いに溢れたような人だ。
会議室を出ると、廊下には厚みのあるクッションフロアが敷かれており、靴音がほとんど響かない。会議室を出た左斜め向かいにも部屋があり、外からは見えないもののそこに香田さんたちがいるのがわかった。どこまでも掃除が行き届いたオフィスは歩いているだけで気分がいい。
綺麗なオフィスというものに憧れがあった。だから、高望みをするつもりではないけれど、見た目の印象は大事にしていたし、場所もできればオフィス街がよかった。ランチは財布だけを持って近くのカフェで食べている自分を想像すると、つい笑みがこぼれてしまう。そんな未来を掴めそうになっていることが、ここで過ごす時間が伸びれば伸びるほど現実的になっていた。
ちょうどカンボジアの人とすれ違った。なにもアクションをしないのは気まずいので、軽く会釈をするだけの動作を同じタイミングでした。
花屋さんが言ったようにお手洗いとは別で隣にパウダールームがあった。覗いてみると、中には誰もいない。壁に備え付けられている鏡にはライトがついている。ああ、いいな。ここを知れば知るほど、内定が欲しくなる。
お手洗いを出ると、少し離れたところに何かが落ちていた。ちょうど香田さんたちがいる部屋の前だ。
目を凝らすと、それがビニール袋だということがわかる。さっきは落ちていただろうか。いや、落ちていたかもしれない。袋は透明だ。すると、香田さんが部屋から出てきて、お手洗いとは真逆の方向へと走っていくのが見えた。どことなく焦ったように見えたのは気のせいだろうか。
会議室に戻ったのは、休憩が終わる一分前だった。
花屋さんは鬼塚くんと雑談をしていた。スマホが圏外だったと話していたが解決したのだろうか。それにしても花屋さんは誰とでも話せる人らしい。男女関係なく、こういう場でも分け隔てなくコミュニケーションが取れるのは、企業に取っても欲しい人材だろう。
ここまで残ったのだから、それなりにふるいにかけられた結果だと思っていいはずだ。
今のところ、花屋さんぐらいしか最終選考に相応しい人はいないように思うけれど。同じように私も周りから思われているのだろう。カンボジアの人はスマホでしきりに文字を打っているようだった。使えるということは圏外ではないかもしれない。ならば鬼塚くんだけということなのだろうか。銀縁眼鏡の人は他人には干渉しませんというスタイルを今も貫いていた。
自分が座っていた椅子まで歩いていた時──
ピー、ガ、ガ、ガ。
人の会話ではない機械音が、なんの前触れもなく会議室に響いた。
「びっ……くりした。なんの音ですかね」よほど驚かされたのだろう。咄嗟に声が出なかったのか、花屋さんが周囲を見渡した。
「プリンターじゃないっすか。ほら、あそこの」鬼塚くんが壁に沿って置かれている業務用の大きな機械を指さした。「間違えてこっちに出しちゃったんですかね」
プリンターに近いのは銀縁眼鏡の人だったが動く気配がない。花屋さんが確認しに行くと、「あれ」と呟いた。
「紙は出てないみたいですね」
「もしかすると用紙切れだったりして」
「あとで香田さんに伝えましょうか」
そう話しながら、廊下を慌ただしそうに走って行った香田さんの背中を思い出した。話題にしようか一瞬悩んだが、やめておくことにした。
もしかすると選考に何か問題があったのかもしれない。そうだとしたら、あまりペラペラと触れるのもよくないだろう。
しばらくすると、廊下から足音が聞こえてくる。ちょうど十五分五十九秒だった。狙っていたのだろうかと思うほど、ギリギリ十五分だった。
会議室に入ってきた香田さんは、当たり前だが慌ただしそうにはしていなかった。最終面接時と同じような朗らかで全員を見渡した。
「みなさんお揃いですね。では、他己紹介に移りたいと思います」
そこから、他己紹介について簡単な説明がされる。「説明は字のごとくといったところですね。みなさんもご経験、もしくは聞いたことがあるかと思います。自己紹介ではなく、他人に自分を紹介してもらうというあれです」
当たり前の認識だと、誰もがうなずいていた。香田さんも安心する。
他己紹介のメリットは自分では気づかない強みを知ることだとされているし、コミュニケーションを取るという意味でもよく使われるものだった。
客観的な視点を取り入れることも大切だとされていて、事前にこの時間があることは知らされていた。
「これから他己紹介に必要なやり取りを一時間設けます。ご要望があればお伺いします」
一時間で十分だと誰もが思っていたのだろう。私は軽くうなずいてみせたが、ほかの人がどうだったかはわからない。こういうときは、あまり周りを気にしないほうがいい。
キョロキョロとしているだけで不格好だ。そんなことは、ここまで昇りつめてきた人間なら心得ているのだろう。おそらく、私以外も同じように考えていた人がほとんどだったはずだ。
「よさそうですね。では、やり方はお任せいたします」
そう言って香田さんが出て行こうとするのを、誰が引き止めるのだろうと様子見していた。今更になって、別にプリンターの件を伝えなくてもいいのではないかと思い始める。「すみません」と声をあげたのは鬼塚くんだった。
「さきほど、そちらのプリンターが作動していました。印刷物が出てくることはなかったですが、念のためご報告しておいたほうがよいかと」
はきはきと臆することなく言えてしまうのはひとつの才能だ。まして香田さんという自分よりも年齢が上の人の前でもきちんとした伝えた方ができることを素直に尊敬する。
「ご報告ありがとうございます。誤作動かもしれませんね、こちらでも声をかけておきます」
香田さんは特に不審がることはなく会議室を出て行った。ただ、鬼塚くんの評価がこれでわずかに上がったような気がした。やはり言っておくべきだった。なぜ私は一瞬「言わなくてもいい」と思ってしまったのだろう。
ほらやっぱり、私は頭で考えるだけで行動にはできない。とはいえ、鬼塚くんが言わなかったとしても、今度はその役割を花屋さんが担っていただろう。いずれにせよ、私ではなかったはずだ。
判断が遅いというだけの問題ではない気はするが、だからといって私のような人間はどこまでいってもこんな感じなんだろうなと思う。就活を始めてから自分のことを嫌うことが何十倍と増えた。別に今まで自分のことを好きだったわけではないが、だからといってこれほどまでに嫌悪感を抱くとも思っていなかった。
どうして私は、私なのだろう。
花屋さんのようにはなれなかったのだろう。
一体どんな違いがあるのか。強いていえば、同じ人間であるということだけだ。
「どんなこと話していきましょうか」
ここからの進行役は自然と花屋さんになっていた。不満に思う人は誰もいない。
「無難にガクチカでいきますか。その人のことを紹介する上では必要な情報が詰まってると思うんで」
そう提案したのは鬼塚くんだ。俺からいきますよ、とそのまま名乗り出た。
「鬼塚大樹です。学生時代はラクロス部に所属し、キャプテンやってました」
ああ、そうだ。ラグビーではなくラクロスだ。網がついた棒を持ち、走り抜ける鬼塚くん姿を想像する。
「全国大会に行ったりと、結構アクティブに動き回ってましたね。体を動かすのが好きなんで、時間を見つけては友達とスポーツするのが好きです。チームをまとめることは大変でしたけど、戦略を考えたり、仲間との連携を取ったりするのも楽しかったっすね」
私たち相手ということもあり、口調はかなり砕けていた。そのほうが、これからの人間もやりやすいだろう。場の雰囲気づくがうまいなと思う。この場の緊張感をあえてほぐそうとしてくれる役割も自然と担ってくれたのかもしれない。
「ラクロスってかっこいいですね」花屋さんが言った。「私も学生時代は運動したかったけど、イベント運営に忙しくてなかなかできなくて」
「ああ、まあ人それぞれありますよ。でもスポーツはいつからでも始められるんで、興味がある人は声かけてください。一通り知り合いはいるんで」
こういったリーダータイプは企業側も欲しいと思うだろう。最終選考に残された理由が見えてくる。
「終わったってことでいいですか」
そんな和やかな空気をぶった切ったのは銀縁眼鏡の人だった。どうぞ、と鬼塚くんが促す。
「長谷川 聡輔です。ゼミで経済学の研究をしていました。特にデータ解析に力を入れていて、いくつかのプロジェクトをリーダーとしてまとめた経験があります。趣味でプログラミングやロボット工作もしてました」
鬼塚くん同様に、っぽい、と思うような内容だった。彼が運動してましたと言っていたら驚いていたかもしれない。鬼塚くんに比べて、長谷川くんは身体の線が細い。そのことを別に気にしているわけではなさそうだし、どんなときも冷静でいる彼もまた、企業にとって欲しい人材に思える。
「もしかして機械とか得意だったり?」
持ち掛けたのは鬼塚くんだ。長谷川くんが乱暴に入っていかなければ、もう少し鬼塚くんの話題で盛り上がったはずだけれど、そんなことを気にしてもいないような口調だった。
「わかる範囲でなら」
「じゃあ俺のスマホがさっきから圏外なんすけど、原因とか分かったりします?」
まだ圏外だったらしい。長谷川くんは花屋さんと同じように鞄から自分のスマホを取り出して確認した。
「……俺は電波が届いていますね。一度電源を切ってはどうですか」
「試してみます」
鬼塚が電源を切っている間に、控えめな挙手があった。
「そしたら、次は私でもいいですか……?」
カンボジアの人だ。できれば早く緊張感から解放されたいと思っていたのだろう。鬼塚くん、長谷川くんが自分のガクチカを紹介している間、何度か呼吸を整えていた。
「春菜 かえでです。学生時代はボランティア活動をメインにしていて、ええと、カンボジアの子どもたちを支援する取り組みをしていました。あとは皆さんのスケジュール調整や、資金集めも任せてもらっていました」
そうだ、この話を聞いたことがある。このあとは「正直、大変なこともありましたけど」と続くはずだと思っていれば、案の定そうだった。
「やっぱりカンボジアの子どもたちが成長する姿を見ると、やってよかったなって思えて。そのときのことは、今の私にとってはかけがえのないもので、カンボジアに行けてよかったなと思います」
なぜこの人をカンボジアの人だと認識したか。そのままだ。やたらと「カンボジア」というワードを出していたから。緊張で伝えたい言葉を繰り返してしまうのかもしれない。私もできるだけ気を付けようとするのに、一番伝えたいという熱意だけが先行してしまって、その過ちになかなか気づけない。
こうして人の分析はできるのに、いざ自分のこととなると見えない。悪いところだらけのようなことは理解していても、それをどう修正していけばいいのかは不明だ。それなのに、人の志望動機や自己PRなんかを聞いていると、矛盾を見つけたり、改善点がどこなのか明確だったりする。ある意味、自分事とは思っていないところがいいんだろうか。
「麻月さんの話、すごく印象に残ってました」私が話すと、彼女は嬉しそうにこちらを見た。
「本当ですか?」
「一次の集団面接でもお話されてましたよね。ボランティア活動をしていただけでなく、現地にも行かれてたんだなと」
「自分の目で見てみたくて」
なるほど、控えめな印象はあったものの、熱意が伝わってくる。自分のやりたいことが明確にあるというのは就活においても強い。
「もしかして森さんと麻月さんは一次が一緒だったんですか?」
花屋さんが少し驚いたような顔を見せていた。私たちが会話をしていた理由も納得していたのかもしれない。そうです、とどちらかともなく言うと、「ここもですよね」と鬼塚くんが言った。
「花屋さんと俺は二次で一緒でしたよね。そのあと飲み会にも参加したりして」
そうか、だからやたらと会話が盛り上がっている印象があったのか。今日初めて会ったにしてはやたらと距離が近いと思っていた。物理的なものではなく、対話が。
「え、飲み会があったんですか……?」麻月さんは、二人の関係ではなく面接のあとに飲み会があったということに驚いているようだった。それもそうだ、面接が同じだった人間とその後飲み会に行くなんて流れを私はこれまで聞いたことがない。いや、知らないだけであったのか。ご飯を食べに行くぐらいなら聞いたことはあっても、私には経験がないから未知の世界だ。
それは麻月さんも同じだったようで、知らなかったです、とぽつり呟いた。だからといって飲み会があったとしても麻月さんは参加したのだろうか。ここにいるメンバーで飲み会に参加すると言ったら鬼塚くんと花屋さんぐらいしかいなさそうだ。長谷川くんはおそらく最初から断るだろう。飲み会に参加しているところが想像できない。これは偏見だろうか。
「とはいえ、あのとき参加してたメンバーで残ってるのは私と鬼塚さんだけみたいですけど」花屋さんが言うと鬼塚くんも「残れるなんてねえ」と盛り上げていた。
そもそも。ある程度親しくなった人間が、最終選考で二人も残っていることが異常だ。ほとんどの人間は落ちるというのに、花屋さんと鬼塚くんは競争を勝ち抜きここに座っている。
「結構いろいろ話しましたよね」
「酒が入っちゃったんで、なに話したかよく覚えてないっすけど」
初対面同士だと思ってしまったのは、おそらく他己紹介が始まるまで、二人が会話をしなかったからだろう。久しぶりです、という会話がどこかでされていたのか。それとも、今日はここまで一緒に来たとか。
それにしても、二人の打ち解け具合はここ数分で加速していた。おそらく、未来の同僚として見据えているのかもしれない。仲良くなっておくに越したことはない。ここまできてしまえば内定は確定しているのだから。
ここにいる全員が、もし同期になったら。それこそ飲み会を開催することもあるのだろう。同期だけで集まり、仕事の成功を話したり、時には愚痴をこぼしたりして、そうしてまた明日から頑張ろうと思えたりするのだろうか。まだ見ぬ未来はそう遠くない。
私もこの波に乗っておかないと取り残されてしまう。そんな焦りを抱いていると、花屋さんが「次は私がいきます」と可愛らしく手を挙げた。
「花屋 凛です。あ、別に実家が花屋とかそういうわけではないので期待を裏切ったらごめんなさい」
もしかすると定番の挨拶なのかもしれない。鬼塚くんが「それ聞きたかったんですよ」と適度な合いの手を入れた。「飲み会では、誰がご実家情報聞くかで戦争になってましたから」
つまり誰もが彼女との接点を望んだということだろう。同性であったとしても、花屋さんは魅力あふれるような人に見えるのだから、異性からするとまた別の魅力を感じただろう。
「名前負けしててちょっとお恥ずかしいんですけどね」と彼女は照れ笑いを浮かべながら自己紹介を始めた。
「学生時代で言うとSNS運用に力を入れてたんです。さっきもお話したので、またかよって思われるかもしれないんですけど、このセリフばかり練習してきたので大目に見てもらえたら嬉しいです。大学のサークルではイベント運営に関わってました。特に学園祭が一番大きなイベントで、リーダーとして企画や運営、広報まで全部こなしちゃう系の人間です。集客も結構SNSで呼びかけたりして」
実際、彼女の個人アカウントは一般人だというのに有名なインフルエンサーと同じような数のフォロワー数を抱えていた。それらを丁寧に一人ずつ見せていく彼女は「宣伝みたいになってすみません」と肩を竦めた。
「こんな感じなので、ちょっとここの力も借りたりして、学園祭では過去最多の来場者数を達成できたことは自慢だったりするので、こういうときの十八番として使ってます」
たしかに、香田さんたち向けの内容と同じだったところもあるが、それでも私たち向けのプレゼンであることは間違ないなかったし、なんといってもユーモアがあった。それだけで彼女の親しみやすさが遺憾なく発揮された時間でもある。
「飲み会でも噂になってましたよ」鬼塚くんが言った。「『あの花屋凛だ』みたいな感じで」
「いやいや、大袈裟です。というか盛り上げ上手な方しかいなかったので、変に持ち上げられて、ちょっと降りられなくなってましたから」それに、と花屋さんが続けた。「私、ただの大学生ですから有名人でもなんでもないんですよ」
「有名人ですよ」麻月さんが自分のスマホの画面を見せた。さっき花屋さんが見せてくれた自身のアカウントの画面だった。
「五十万人のフォロワーって簡単にはいかないですし」早速調べていたのだろう。早い。リサーチ力という意味でも即戦力になれそうだ。なんて採用する側でもないのに思ってしまう。実際はそうじゃないかもしれないけれど、ほかの人の何気ない行動が加点ポイントに見えてしまう。私は、どうだろう。私は、どこで加点されるような部分があるんだろう。
「たしかに、数だけ見るとちょっとびっくりしちゃいますよね」花屋さんはなおも謙虚な姿勢を貫いていた。
「そこまでいくのに、やっぱり日々の発信とか、フォロワーさんとのコミュニケーションは大事にしてました。あとは根気と継続も大事ですね。そこさえクリアできれば誰でもいけるんですけど」
その結果が五十万というフォロワー数に繋がっているのだから説得力がある。
「ちょっとその数を俺にも分けてほしいぐらいですよ」
「あれ、鬼塚くんもSNS活動してましたっけ」
「活動ってわけではないんですけど、ちょっと人脈が欲しいときってあるじゃないですか」
「私のフォロワーさんを変な勧誘しないでくださいね」
そんな掛け合いがあり、場は和んでいた。そうして「最後は森さんですね」と花屋さんからの華々しいバトンをもらうことになってしまった。
正直、彼女のあとではやりにくさがあるものの、表情に出すわけにはいかない。
「森 果帆です。学生時代でいうと、環境保護団体での活動に参加していました。詳しいことはさっき話したので、ざっくばらんでいいですかね」しっかり前置きを作っておく。私が人前で話せるようなものはこれぐらいしかない。「活動内容は、街のゴミ拾い活動がメインで、地域住民の方々との連携しながら掃除をするっていう……皆さんと比べると随分地味な紹介になってしまうんですが、個人的には目に見える成果を実感できることがよかったです」
「目に見える実感ですか?」そう聞いたのは意外にも鬼塚くんだった。これまで花屋さんの話にばかり興味があるとは思っていたけれど、何気に全員の話をきちんと聞いている。面倒見のいい兄がいれば、こんな感じなのだろうか。
そうなんです、と返しながら説明っぽくならないように心がける。
「たとえば海岸の清掃だったりすると、ビフォーアフターがわかりやすくて実感しやすいですね。達成というか、私たちの活動で、自然環境が改善されたかもしれないと思うと、無駄ではなかったんだなと思えるんです。油断すると家でサブスクばかり見てしまうので、明らかにちゃんとしたことに時間を使っているなと思えて自己肯定感が上がりやすかったりします」
ふふ、と花屋さんが笑ってくれる。この手の話は同性代なら共感してもらえるだろう。即興な部分はありつつも、この場に合わせた話しができているかと思えると自信がつく。
「実は私も参加したいと思ってたんです」花屋さんは微笑みを保ちながら言った。「友達がそのプロジェクトに関わってて、話を聞くたびにすごいなって思ってたんです」
友達が、ということについ身構えてしまう。大丈夫、興味を持ったというところだ。
「花屋さんとも活動できたらうれしかったですね」
「そう言ってもらえると私もうれしいです。それに、私も何か貢献できたらって思ってたんですけど、結局はSNSとかでしか支援できなかったので、森さんの話を聞くと憧れちゃいます」
憧れるなどと花屋さんに言ってもらうと、どこか有頂天になりがちだ。やっぱりこの話を選んで正解だった。これまでの面接でも「パンチがないね」と何度か言われていた。その度に、自分らしさというものを取り入れながら修正してきた内容だ。何度か面接でも話しているからか、淀みなく出ていくが、このメンバーで爪痕が残せたかと言われると厳しい。
全員が、私よりも優秀な人たちに見える。今までの面接では、誰かしらが「この人よりはマシかも」なんて思うような人間が一人や二人はいたのに。ここにいる人たちと戦えと言われたら、到底太刀打ちできそうにない。
「なんか、こうやってお互いのことを知るのってすごくいいですよね」花屋さんが感慨深い表情で続けた。「普段の面接だと、自分のことばっかり話して、他の人の話ってあまり聞けなくて」
「分かります。緊張して、自分が順番最後だともう頭が真っ白というか」麻月さんは何度か前髪を触っていた。おそらく癖なのだろう。そういえば、やたらと髪を触る人がいるなとどこかで思ったことがあったが、あれは麻月さんだったのか。
「いやあ、今日が一番リラックスして学生時代のこと話せた気がするっつーか」鬼塚くんに関しては、ここでなくても普段とあまり変わりがないように思えるけれど。
長谷川くんは自分のターンが終わってからというもの、口を開くことはなかった。一応、その場にいるという形だけは作られているが、誰も彼に話題を振ることはない。もう少し協調性をアピールしたほうがいいのではないかとこちらが思ったりもするが、落ちるのであればどうぞ落ちてほしい。ライバルは少ないほうがいい。
「これだけいろんな経験がある人たちが集まってると、お互いに刺激を受けますよね」そう話すと「分かります」と麻月さんが少し打ち解けたような様子で言った。
「みなさんの話聞いてたら、私のガクチカもっと磨いていきたいって思いました。とはいえ、もうこれが最終面接なんですけど……」
「全員が内定取れたら、絶対に楽しい職場になりそうだなあ」
鬼塚くんの言葉に、つい自分がここで入社したあとのことを考えてしまう。
パリッとしたスーツを着て、颯爽とオフィスを歩く自分。香田さんが身に着けていたような、あのブランドものの腕時計を装着する日はくるかもしれないし、そのころには優雅な一人暮らしもできているだろう。
今は実家を出ているというものの、自分一人だけの生計ではとてもじゃないが間に合わず、ここ数か月は就活が始まったことで、落ち着くまではと全額援助してもらっている。そんな自分ともおさらばできる日がくる。輝かしい未来が、もう少しで手に入りそうだということが今でも信じられない。
「同期として一緒に働けるって思えると、なんか不安が消えました」
「麻月さん、不安なんて吹き飛ばしていきましょうよ。今度、みんなで集まってご飯食べません?」
「いいですね……! どこかいいお店知ってますか?」
「私、サークルでも結構幹事任されることが多くて、いろいろ知ってるんですよ」
花屋さんの提案に、鬼塚くんが「あれ」と思い出したように声をあげた。
「この前の店も花屋さんが予約してくれたんじゃなかったっけ」
「あそこは知り合いの人がいて、ちょうど開けてくれたんです」
「お店の知り合いがいるとか、かっこいいですね」思ったことをそのまま伝えると「たまたまってだけで」と鼻につかない返しをされた。私だったらもう少し自慢げに話してしまうかもしれない。
「どんな料理がいいか言ってもらったら候補挙げますよ」
「俺はイタリアンとか好きだなあ」
「私もいいなと思いました。麻月さんとかどうですか?」
「あ、いいと思います」
「そしたら、ちょっと奮発しちゃいません?」
「わあ、それいいですね! お祝いも兼ねて」
「それじゃ、みんなで内定もらったら予約入れておきますね」と花屋さんが冗談交じりに言うと、全員が楽しそうに笑った。ただひとり、輪に入ろうとしない長谷川くんを除いて。
「ちなみに、長谷川くんはどんな料理が好きですか?」
そんな彼など私だったら放っておいてしまうのに、花屋さんは声をかけるという選択を取る。今まで、同じクラスの人が一人で行動していたら、つい輪に入れてしまうようなこともあったのだろうか。長谷川くんの瞳が若干動いた。
「強いて言えば和食です」
「ああ、そっちもいいですよね。和食はまた落ち着くし」
「ですが、あまり浮かれないほうがいいのではないですか」
これまでの空気を凍らせてしまうような勢いだった。築き上げようとしてきたものが、この人の言葉で崩されていく。少なくとも、ここから未来の同僚が生まれるかもしれないというのに。仲良くしておいて損はないはずだ。それなのに、どうしてこの人は輪を乱すようなことばかりをしてしまうのだろう。愛想ひとつさえ難しいのだろうか。
おいおい、と鬼塚さんが困惑しながらも笑みを浮かべる。
「別にこれぐらいいんじゃないっすか。それに、正直言って最終面接までいけたら内定確定みたいなところあるらしいんですよ」
内定確定。そうだ、私たちはほとんど内定がすぐ目の前にあるような立場だ。
よっぽどのやらかしをしなければ落ちることのほうが珍しいとさえされている。
この人は採用されたいわけではないのだろうか。どうしてここにいるのだろう。
「鬼塚くんも知ってたんだね。私もさっき森さんと話してたんですよね」花屋さんに振られて「あ、はい」とつい答えてしまった。だから、「あ」は要らないんだよ。自分に叱責していれば「おそらくないと思いますよ」と、またしても空気が読めない発言をする長谷川くん。
そうですね、などと返ってくるかと思っていたけれど、彼の答えは予想外のものだ。
「……ないって、どういう意味ですか」麻月さんが控えめに聞いた。
「そのままの意味です。全員が内定というわけにはいかないでしょう」
「あのさ、さっきからなんなの」いよいよ鬼塚くんの顔からも笑顔が消える。「ちょっと尖りたいみたいな感じ?」
「そう見えているのならそうでしょう。ただ、あまりにも愉快な人たちが揃っているなと感心していただけなので」
「愉快って」
険悪なムードとはまさにこのことだ。
長谷川くんさえいなければ、今頃楽しく雑談をしていたはずだった。
他己紹介だって褒め合うような形で披露して、全員で内定をもらう。それは理想と形といえる。こんな私でも「納得内定もらえた」と言えるような日がくるかもしれない。そんなことが現実になりかけている中で、この人だけが、やけにそれを許さない。
「あの──」言いかけたところで、コンコン、とノック音が響いた。すぐに香田さんが入っては、会議室を見渡した。和やかな空気から一変した異変を、香田さんは気に留めることなく「お疲れ様でした」と労いの言葉をかけてくれる。
「時間は足りましたかね」
本当ならば、もう少しそれぞれの話を聞いていたかった。他己紹介をするには情報が足りないようにも思う。その人の新しい一面みたいなものが見えたらポイントは高かったはずだ。
「それでは、他己紹介に移る前に、少しこちらからルールを追加させていただきます」
ルール、という言葉に引っかかりを覚えた。おかしなことを言われたわけではないのに、なぜか妙な胸騒ぎがしていた。
「みなさまには、匿名による他己紹介を行っていただきます」
香田さんの言葉に、会議室は静まり返った。匿名の部分が引っかかったのは、おそらくこの場にいる全員だっただろう。
互いを知ることが目的なのに、どうして匿名にする必要があるのか。
「今後は別室でみなさま待機していただきます。時間になりましたら係の者から案内がありますので、通された部屋で他己紹介を行っていただきます」
「え、あの……待機って、全員一緒ってことですか?」
「いえ。たとえば森さんでしたらA室、鬼塚さんでしたらB室と部屋が異なります。また順番も事前に告知することはございませんのでご了承ください」そして、とまるでここから先が最も重要だと言わんばかりに、香田さんは、一度全員を見渡してから、こう続けた。
「他己紹介をするお相手は、こちらから指定いたします」
これは、私が知っている他己紹介ではなかった。
説明を聞いても、独自のルールが設けられ、そしてそれは、私たちにとって青天の霹靂でもあった。なんだ、匿名の他己紹介って。
香田さんは、なおも説明を続けた。
「みなさまには他己紹介の最後に、おひとり推薦していただきます。他己紹介のお相手と推薦は別の方でも構いません。目的としましては、みなさまだからこそ知るその方の人間性と、そして誰を推薦するのか──この二点に重点を置きたいと考えています」
「ちょっと待ってください」
手を挙げたのは鬼塚くんだった。
「匿名の内容は、本人が知ることは可能なんですか?」
「いえ、ご本人様には伏せた情報となり、最後まで明かされることもございません。もちろん、ご自身の評価を知りたいという申し出もご遠慮いただきます」
「ありがとうございます。追加で質問いいですか」鬼塚くんは臆することなく二つ目の質問に入った。香田さんは「もちろん」と頷く。
「今回、推薦枠が用意されたご意図を伺ってもよろしいですか」
それは誰もが知りたがった情報のはずだ。鬼塚くん以外、意見を発することはなかったが、香田さんの答えを全員が待っていたような気がする。
「これはとても大事なところですね。みなさまにここでお伝えさせていただきますが、今回の内定枠はお一人となります」
「一名……ですか?」鬼塚くんの声が一瞬かすれた。他の参加者たちもざわついた。会議室内の空気が急に重くなったように感じたのは、私だけじゃない。
「はい、それぞれが素晴らしい成果を持つことは理解しておりますが、企業の現状を踏まえた決定です」と香田さんは淡々と説明を続けた。企業の現状とは言うが、本当だろうか。ここにいる五人、全員を採用するだけの余裕はあると思っていた。
「ですので、推薦には慎重さが求められます。ただし、ここで推薦された方が即座に内定となるわけではなく、推薦理由、そして匿名の他己紹介と照らし合わせて検討したいと考えています」
その言葉に、会議室の静けさがさらに増した。私は内心動揺していた。これまではライバルがいても、どこかで全員が一緒に受かる可能性があると思っていた。けれど、たった一人しか採用されないとなると、この他己紹介と推薦が一層重大なものに感じられる。
鬼塚くんは「ありがとうございます」と戸惑いながら口にしてからは、質問を重ねることはなかった。眉間にしわを寄せながら何かを考えている様子だ。
推薦枠は、選考の中でも大きな力を持つ。誰を推薦するか、そして誰に推薦されるかが、これからの結果を左右するだろう。それに、匿名の他己紹介。これは想像している以上に、恐ろしいものになるのではないか。
なぜなら、私たちの前だけで発表するわけではない。さっきのように和やかに自分たちのことを紹介しているような和気あいあいとした時間ではないだろう。匿名の他己紹介を行うのは、香田さんたちの前だけだ。そして、用意された推薦枠と、内定枠一名。
つまり、他己紹介も推薦も、すべてが選考に直結している
ここまでくればほぼ内定を勝ち取ったといってもいい。そう話していた未来が、一気に崩れていく。
「では、それを踏まえて、もう一度みなさまでお話をする機会を設けたいと思います。時間は先程と同じ一時間でどうでしょうか」
香田さんの問いかけに、全員が混乱していたけれど、反対するものはいなかった。
「問題ないようですね。では、お願いします」
それから香田さんは初めて会ったときと変わらない親しみやすそうな笑みで会議室を出て行った。
「なあ」
沈黙が流れていたが、それを破ったのは低い声だった。ここでそんな声を出すのは彼だけだろう。
「知ってたのか、このこと」
鬼塚くんは、長谷川くんを見ていた。「なにがです」と彼はこの状況には不釣り合いなほど余裕だった。
「内定が一人だって。さっき、浮かれないほうがいいって話してたのは、このことがわかってたからなんじゃねえのか」
口調が乱暴だ。香田さんの前とは別人としか思えない。
「答えとしては、知らなかった、が正しいです。ただ、よくよく考えればわかることではないですか。まさか本気で、この場にいる全員に内定が与えられるとでも思っていたんですか」
ありえないでしょう、と嘲笑うように長谷川くんは言った。その姿に怒りと、恥ずかしさが一気にこみ上げてくる。
「お前っ」
鬼塚くんが立ちあがったのを、花屋さんが「まあまあ」となだめる。
「とりあえず、事実がわかっただけでも良かったんじゃないかな。内定枠が一人だってことは確定したわけなんだからさ」
花屋さんが冷静でいてくれることが唯一の救いだった。けれど、それだけでは解決にならない。それは麻月さんも同じだったのだろう。
「……でも、これって最悪ですよね。香田さんの話では、私たちが内定枠の一人を決めるってことじゃないですか」
「そんなことは言ってなかったと思うけどな。あくまでも、検討するってだけで」
そう落ち着いた様子で花屋さんは話していたけれど、私も麻月さんの意見に同感だった。
「他己紹介の中身と推薦、これら二つを重要視すると言っていたので、やっぱり内定に繋がるという考えにはなると思います。言い方を変えると──」
「自分を選んでもらうか、それとも他者を蹴落とすかってところだろ」私が言いたかったこを鬼塚くんが拾った。
「……まあ、結構最悪だなとは、私も思ってるんですけどね」
さすがの花屋さんの笑みも、困惑が広がっていた。この場が混乱しないように、あえてポジティブな意見を口にしてくれていたのかもしれない。
「ここまできて、内定枠が一人とかなんだよそれ」
鬼塚くんが頭をかく。
「もし本当だとしたら」麻月さんが呟く。「全員で仲良くやってる場合じゃない、ってことなんでしょうか」
その言葉に、全員が一気に緊張感を増していく。仲良くやってる場合じゃない、か。ついさっきまでは、同僚になれるかもしれない、この波にのらないといけないなどと汗っていたというのに。
「そういうことだよ」と鬼塚くんが、苛立ちを隠せない様子で声を荒げた。「結局、俺たち全員ライバルなんだ。仲良く見せかけてるけど、最後に笑うのは一人だけだってことだろ?」
麻月さんは視線を落とした。「でも、どうしてこんなやり方を……最初からそう伝えてくれれば、もっと別の方法があったような気がするんです」
「それが向こうの狙いなんでしょう」長谷川くんが静かに口を開いた。「面接官たちは、僕たちがどうやってこの極限の状況を乗り切るか見ているんです。協力し合い、誰かを推薦するのか、それとも自分の利益だけを考えて動くのか」
その分析に、場の空気は一層重くなった。今までの穏やかな雰囲気は、まるで一瞬にして消え去ったかのようだ。自分のことしか考えない人間が誰なのか、お互いに探り合うように、全員の視線が交錯した。
「もう、時間はないぞ」と鬼塚くんが短く言う。「このまま続けるのか、それとも全員でこの馬鹿げた試験を辞退するか」
「ちょっと待ちませんか。さっきまで和やかに話してたのに、急にそんな話をされても……」
花屋さんが言いたいことはわかる。けれど、私たちの将来は全員が決して明るいわけではない。むしろ、ほとんどの人間がどん底に突き落とされてしまう。ここまできたのに、またやり直さなければいけない。それだけは避けたい。
「とりあえず、まずは落ち着いて話しをしませんか」花屋さんが訴えたとき、この場に不釣り合いな軽快な音が響いた。
ピー、と聞き覚えのある音が始まり、その後、ガ、ガ、ガと何かが動き出す音。それは、この場にいる全員なら聞き覚えのあるものだった。
「また……」
麻月さんが言った。
プリンターから近い長谷川くんが様子を見に行った。しかし何かを言うことはない。
「それ、誤作動があるって香田さんが言ってましたよね」
「いや」
長谷川くんは先程までなかった一枚の用紙をプリンターから取った。
「これは誤作動ではないと思います」
そこには──。
【ラクロス部ではマルチ勧誘が行われており、首謀者は当時のキャプテンだったとされている】
「……え、なにこれ」
全員が凍り付いた。
この場でラクロス部といえば、一人しかいない。
「いやいや、なんで俺を見るの」
鬼塚くんは困惑した表情を浮かべながら、周囲の視線を避けるように笑った。しかし、その声はどこか焦りがにじみ出ていた。
「そもそも、このプリンター調子が悪いとか言ってたし」
「調子が悪いことに結びつけるのはどうなんでしょうか」
焦ったような鬼塚くんとは対照的に、長谷川くんが眼鏡の縁を軽く持ち上げた。
「内容としては、鬼塚くんを示唆するようなものとして受け取ることはできます」
「いや、だからって俺はこんなことやってない。それにラクロス部でもこういった話は一度もなかった」
「確かめる術はありませんからね」長谷川くんの冷静な態度が、逆に鬼塚くんの焦りを煽っていた。こんなことを言われてしまえば苛立ちを覚えるだろう。
突然、険悪な空気が漂い始める。まるでこうなることが想定されていたみたいに。あの、と控えめに声をあげたのは麻月さんだった。
「調べたら……ネット記事で出てきて……ちょうど鬼塚くんが在籍されている期間と一致するのかなと思ったりで」
スマホの画面には、名前こそ伏せられていたものの、鬼塚くんが通っていた大学名と、マルチ勧誘に関わったとされるラクロス部が大々的に報じられている。言われてみれば、こんなニュースを過去で見たことがある。そのときは他人事だと思っていたが、その当事者が目の前にいるとなると話は別だ。
「だから……あ、圏外になっちゃいました」麻月さんは不審がるような表情を浮かべた。
これで二人目だ。妨害電波でも出ているのだろうか。
「この情報が出てきた以上は、無視ができないですね」
確信をついたとばかりに長谷川くんが結論付けた。
「はあ? いや、だからデマだって! 俺は知らなかった」
困惑が広がっていた。これから匿名による他己紹介が始まれば圧倒的に不利な状況にはなるだろう。
「……言っとくけど、真に受ける人間なんていないよな?」
唸るような、とても低い声だった。
「ここにいる全員が黙っていれば、俺の評価は変わらない。そもそも、これは嘘なんだから信じるほうが馬鹿げてると思うけど」
「でも、嘘だって証明もないですよね……?」
私の言葉に、鬼塚くんはゆっくりとこちらを見て、そして睨んだ。
「証明って……こんなのないでしょ、ふつうに考えて。俺が在籍してたから、事件に関わってるとか思われても」
「じゃあ、この事件のことは知ってたんですよね? ここまで騒がられていたら」
鬼塚くんはしばらく私を見ていたけれど、そのまま諦めるように目を閉じた。
「知ってる」
「……どうして、さっきはデマなんて」
「否定したくなるだろ、こんなときに、この情報が出てきたら。ただ、この事件のことは最後まで知らなかった。警察にも話してるから確認すればいい。俺は嵌められただけだ」
「嵌められたんですか」
今度は花屋さんが口を開いた。
「そうだよ。俺が部長に就任する前に、あの事件はすでに起きてた。俺が部長になった頃には、ラクロス部がマルチ勧誘の温床だっていう噂が広まってたんだ」
「ではなぜ、一度否定したんです」
長谷川くんが鋭く指摘する。それもそうだ。ついさっきまで、鬼塚くんはこんな話を聞いたことは一度もないと言いきっていた。それなのに、今では、マルチ勧誘が行われていたということは認めている。
「……だから言ってんだろ。ここまできたら、そういう過去も否定したくなるって」
誰よりも発言力があり、そして行動力に溢れていた人が、今は萎んだ風船のように小さく見えてしまう。
「でも俺は何も知らなかったし、関わってない。全部終わった後に知った。それが全てだ」
それだけ言うと、鬼塚くんは口を閉ざした。おそらく、これ以上喋ったとしても無意味だと判断したのだろう。おそらく、彼ではなくとも、ここにいる全員が彼の立場になれば同じことを思ったはずだ。
「……警察に話してるってことは、証明できる可能性はあるってことですね」と麻月さんが言った。そこに、花屋さんが「そうだと思います」と続けた。
「どちらにしても、この場ではすぐに確認することはできないですし。だから、今は鬼塚くんの話を信じませんか」
「ですが、こういう情報が出てきた以上、誰かが意図的に動いている可能性は否定できません」と長谷川が冷静に指摘した。「匿名の告発。プリンターの不審な動き。何かしらの仕組みが働いていると思ったほうがいいでしょう」
でも、誰かって、一体──。