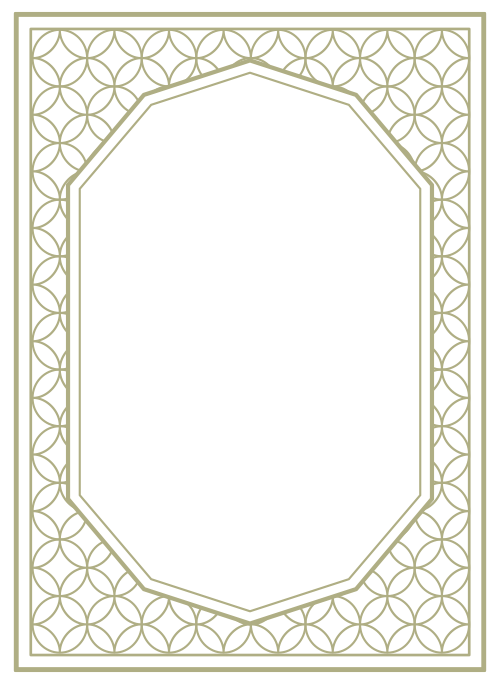「まさか連絡をもらえるなんて思わなかったよ」
そう言うと、麻月さんはあのときと変わらない笑みを見せてくれた。
「ずっとお会いしたかったので」
ベーグル社からほど近い喫茶店で待ち合わせしていた。お互いにリクルートスーツではなく私服だ。鮮やかな黄色のワンピースは麻月さんによく似合っていた。
「お互い、あまりいい別れ方はしなかったからね」
そうですね、と麻月さんが柔らかく微笑んだ。
「聞いたよ、麻月さんがベーグルの内定をもらったって」
「もらいました。私は、森さんを推薦したんですが」
「知ってる。あんなことがあって、まさか推薦してもらえたなんて思わなかったけど」
「します。私にとって森さんは、恩人ですから」
そんなことを、今でも言ってくれるのか。あれから一か月経つけれど、麻月さんは以前に増して自分の言葉に自信が持てたような印象がある。特に、私のことを恩人だと言いきってしまうその強さには。
「このまま懐かしい話に戻りたいところですが、先に済ませしょうか」
「うん」私は、切り出した。「犯人だね」
「やっぱりそうですよね。あのときの犯人が、最後まで不明のままでしたから」
きっとここに来るまでに、いろいろとシミュレーションをしてきてくれたのだろう。犯人という突飛な展開にも麻月さんは驚くことがなかった。
「森さんが一番最初に内定をもらったことは知っているんです。おそらく私だけかもしれないんですが」
それはベーグル社に入社できたからだろう。香田さんにあれからいろいろと聞いたのかもしれない。
「四名の推薦があったのは事実ですけど、それ以外にも森さんが採用された理由をお話したいです」
「遠慮したいけどね」
「話させてください。森さんは、全部の罪を被ったんですから。それはみなさんが知るべきですし、だからこそ内定が決まったんです」
そのことを、今日は一番に伝えたいと思ってくれていたのだろう。そして、あのときあったことをきちんと清算したいと誰よりも考えていたのだろう。
「森さんは最後まで悪役を務めていましたよね。そういう意味で、私は森さんを推薦したかったんです」
「そんなことない。みんなの秘密をばらしたのは私だから」
「そこまでが森さんの役割だったはずです」
「麻月さんの情報網ってどうなってるの?」
「自称情報屋ですから」
「なにそれ」
「私の黒歴史です」
じゃあ、と麻月さんは言った。
「森さんが話さなかった、もう一つの事実をお聞かせください」
──事実。それを話すとなれば、私たちは共通の認識を持たなければならない。わかったと、頷いて私は切り出した。
「六人目の候補者のことを思い出してほしいんだけど」
*
あの日、会議室に集められたのは私を含めて五人と──
「ええと……聞こえてますかね」
もう一人、高辻という男が参加していた。けれど彼の場合、私たちとは違っていた。
「すいません、僕だけリモートで。本来ならここに参加させてもらえるなんてありえない話なんですけど」
ベーグルの本社に呼ばれていた私たちと、物理的な理由によりリモートになった彼。
最終選考に残されているのが六名だと知ったのは、このときだった。
誰しもが、リモートの参加を許されていいのかと疑念を抱いたに違いない。けれど、面接官たちが当たり前のように高辻を受け入れ、受け答えをしていくものだから、その疑念はついに薄れていった。ああいう場とは恐ろしいもので、企業側に問題がないならそれでいいのだろうとなぜか納得してしまう。今思えば、彼という存在は最初からおかしかった。
「高辻さん、今日はよろしくお願いします」香田さんが一番に挨拶をした。面接官は基本的に香田さんが話すだけで、残りの四名はほとんど口を開くことはなかった。
高辻の顔は、プロジェクターによってスクリーンに映し出されていた。本人がどう見えているかはわからないが、私からすると公開処刑並みに恥ずかしいものだった。
「こちらこそ、よろしくお願いします」高辻はスクリーン越しに明るい笑顔を見せた。好青年という言葉がふさわしい。鬼塚くんとも長谷川くんともタイプが違っていた。
その後始まった最終選考で、香田さんから自己紹介をするように促され、一人ずつ答えていった。それぞれの経歴や、志望動機を話し、高辻の順番は最後に回った。簡単に言ってしまえば、あまり特別なことを言っていたようには思えない。私と同じように、どこか薄っぺらさを感じるようなものだったが、彼には自信というものが備わっていた。
高辻がリモートでいるというのは、少し特別な状況だったが、次第に慣れていった。むしろこの場にいなくとも、目の前の面接を乗り越えなければならないという共通の目的は一緒だった。
「さて、次にお話ししたいのは、これからの企業で必要な人材についてです。皆さんはどのようなスキルや資質が必要だと思いますか?」香田さんの問いに、すぐには答えが出なかった。真っ先に口を開いたのは高辻だった。
「私が思うに、チームでの協力や柔軟な対応力が重要だと思います。これからの時代、変化に適応できる能力が求められますし」
「僕もそう思います」鬼塚くんが続いた。「特に環境問題に取り組む上では、多様な視点を持って、さまざまなバックグラウンドを尊重しながら進めていくことが大切です」
花屋さんもそれに続くように、自分の考えを述べた。「自分の意見を持つことも大事にしながら、周囲の意見も尊重し合える環境を作ることが、組織全体の成長につながると思います」
香田さんを含めた面接官は、各々で別の表情を浮かべていた。
面接が進む中、突然スクリーンの映像が乱れ始めた。高辻の顔が一瞬消え、再度映し出された時には、彼の表情が緊張しているのが見て取れた。
「すいません、回線が不安定になったみたいで……」
「大丈夫ですか?」と香田さんが高辻に問いかける。高辻はパソコンの画面を叩きながら、回線が回復するのを待っている様子だった。
「大丈夫です。すぐに戻りますから」と高辻が答えた瞬間、画面がまたもや不安定に揺れ始める。私たちの間に不安な空気が流れる中、再び高辻の顔が画面に映った。
「申し訳ありませんが、少し私の方でトラブルが起きているようです。音声が聞こえづらいかもしれないですが」
リモートである以上、回線のトラブルは避けられない。そういった点では面接でもデメリットに働いてしまうだろう。社長が「だから言ったじゃないか」とこぼした。おそらく高辻のリモート参加を非難しているのだろう。そして社長は反対だった。
「わかりました。こちらの声が聞こえないようでしたら……とりあえずは回線が復旧するまでお待ちいただいてよろしいでしょうか」
はい、と高辻の声が歪んだものに聞こえた。映像だけではなく音声にも乱れが出ている。
「それでは、次の質問に移りましょう」と香田さんが高辻を気遣いながらも、選考を進めることにした。しかし、時間が経つにつれて、高辻の様子は変わっていった。最初のうちは、私たちの間で楽しい会話が続いていたが、やがて彼の表情は不安げなまま、回線が戻らないという事実が現実味を帯びてきた。
「大丈夫かな」質問が途切れたタイミングで花屋さんが呟いた。その言葉に、私たち全員が高辻を気遣う視線を交わす。スクリーンには、もう高辻の顔が長らく映っていない。
「高辻さん、大丈夫ですか?」香田さんが声をかけても、画面は静まり返っていた。彼の顔は再び映ることない。
「高辻さんの接続が戻らないようですね」と香田さんの隣に座っていたもう一人の人事部の女性が言った。「このままだと、選考を続けるのが難しいかもしれません」
もし高辻がこのまま接続できなかったら、選考から外れるのだろうか。
「高辻さん、接続が不安定なようですので、選考を続けることが難しいと思います。どうされますか?」その声さえも高辻に届いているのか不明だったが、数分後、高辻の声がかすかに聞こえた。「すみません、こちらの回線が不安定で選考を続けるのは難しいと思います。申し訳ありませんが、辞退させていただきます」
面接を辞退。
彼の顔が画面に戻らないことが、まさか選考の終わりを意味するとは思ってもみなかった。
「高辻くん、あのとき本当に消えたと思いますか?」
他己紹介が始まるまでの出来事を確認し合っていると、麻月さんが言った。
「……どういうこと?」
「実は、あとで調べてわかったんです。あの会議室に小型カメラがあったって」
「え」
「観葉植物があったの覚えてますか? そこに隠れるようにして置いてありました」
「そんな」
それは初耳だ。おそらく麻月さんにだけ伝えられた情報だったのだろう。
「高辻くんがリモートで参加していたので、私たちが気づかないうちに彼が全てを監視していた可能性があります。もしかしたら、私たちの会話や表情をリアルタイムで見ていたかもしれないです」
「いや、なんでそんなことを」
「リモートだから」麻月さんは続けた。「現場にいなくても、全てを見ていたかもしれません。しかも私たちは、高辻くんがスクリーンにいると信じて疑わなかった」
たしかに、スクリーンから高辻くんが消えて、その後はもういないものだと思っていた。
「選考を有利に進めるためだったのか、ただ単に私たちの反応を見て楽しんでいたのか、理由はわかりません。ただ、リモートというのは都合の良い隠れ蓑にはなったかと思います。私たちが感じてるよりも、ずっと簡単に情報を得ることができたはずですから」
そうして、あの暴露大会が始まった。
理由はなんだろうか。
「……自分が辞退したから、あんなことをしたって麻月さんは考えてたりする?」
「どうでしょう、さすがに自己中心的過ぎて引きますけど。それに、辞退することになったのは自分のせいで、そもそもリモートで参加したのが運の尽きってところはありますし」
だけど、と麻月さんは運ばれてきていたカップを手にした。
「高辻くんはどこまで計算していたのかは気になります」
「どこまで?」
「回線に不具合が起こることも想定して、その先にある辞退も見込んで、全員を破滅させようとしてたって説もあるんじゃないかと」
私たちが闘おうとしていた場所で、別の思惑が働いていたことはそこまで意外でもない。
「リモート参加は、最初からハンデを背負ってるように見えますから。もしそれが最初から仕組まれた“戦略”だったとしたら、どうなんだろうと」
「大がかりだなあ」
「ですよね」と麻月さんは静かに同意した。「でも、もし高辻くんが回線不具合も辞退も全て計算していたとしたら、私たちがこうして彼を疑い始めることすら、彼の計画の一部かもしれないですし。自分は潔白を装いながら、みんなが疑心暗鬼に陥るのを待つ。それから全員を精神的に追い詰め、内定を勝ち取ろうとしていた可能性もあります」
追い詰められ、終わってしまった。
けれど一人だけ、追い詰められることなく、終わった人もいる。
私たち全員がダメなら、自分に内定が回ってくると見越していたのかもしれない。
「人間って、極限状態に置かれたら何をするかわからないものですからね。まして就活の最終面接、全員がライバルという状況なら尚更です。少しでも有利になる手段を選びたいって思うのは、ある意味当然かと思います」
「……それに」麻月さんは小さな声で続けた。「観葉植物のカメラ、誰がそこに置いたのかなんて、私たちが知るはずもないですから。それでも今なら、リモートで参加してた人間が一番怪しいと思いませんか」
そう言われてみればそうだ。高辻くんがいなくなった時点で、私たちはもう五人だけで戦うのだと思っていた。最初から高辻という男が存在しなかったように話しは進み、最後まで彼の名前が出ることもなく終わっていた。誰からも紹介されることなく、消えていった人。
あの人は本当に高辻という男だったのだろうか。そもそも、リモートが許されていた時点で疑うべきだった。本当に、就活生だったのかどうか。
「高辻くんは私たちの顔と名前を知っています。秘密を調べることもできたはずです」
私たちが高辻をスクリーン越しで見ていたように、高辻もまた私たちが見えていた。私にDMを送ってきたのもおそらく高辻だったのだろう。そう片付けてしまうのはできる。結局のところ犯人はわからないままなのだから。
「一番は高辻くん本人に聞いてみるのが一番手っ取り早いんですが、連絡がつかなくて」
「え、連絡先を知ってるんですか?」
「情報屋ですから──というのはさすがに冗談ですが、香田さんに相談して、そのあたりは動いてみたりはしました。結局のところ意味はなかったんですが」
そんなことをしてくれていたのか。麻月さんの行動力に感心してしまう。
「ただ、正直、鬼塚くんはわかってたんじゃないかなと思うんです」
なぜかここで鬼塚くんが出てきた。
「どうして鬼塚くん?」
「あの日、私はすっかり忘れていましたけど、鬼塚くんは何回か高辻くんのことを思い出したと思うんです。何度かスクリーンを見ていましたし、もしかして犯人だと疑っていたのかもしれません。それに、香田さんからもちらっと話しを聞いたので」
他己紹介のときだろうか。そう訊ねると彼女は頷いた。
「基本的に他己紹介で聞いた話は他言しないことがルールでしたよね。ですが、高辻くんだと思われる箇所は例外ではないかと──無理やり取ってつけたようなニュアンスで教えてもらっただけんですけど。多分、私がしつこかったんだと思います」
麻月さんのしつこさは想像できない。そこまでして手に入れた情報とはなんだろうか。
「鬼塚くんは、私の他己紹介をすることになっていたそうです。内容はわかりませんでしたけど、最後になぜか私ではない人の話に触れたそうです」
「それが高辻くん?」
「その可能性はあります。“存在自体が嘘だったんじゃないか”みたいなことを言っていたそうです」
「そうだとしたら、鬼塚くんは高辻くんが犯人だってわかってたってことかな」
「やたらとパソコンを気にしていたように見えますし」
言われてみればそうだ。機械がどうとか何度か話題にしていた。
「高辻くんの存在が頭にはずっとあったとは思います。犯人が森さんってことにされてからは、そっちを信じたのかなとは感じてはいたんですが、香田さんに話してたのを聞いたら、高辻くん説を鬼塚くんは早い段階で持ってたんじゃないかと」
「そうだとしたらすごいね」
「すごいです。仲間思いなんでしょうね、鬼塚くんは。最後まで言いませんでしたけど、マルチ勧誘の事件には無関係だったみたいです」
「え、でもキャプテンがどうとか話しがあったよね?」
「副キャプテンの仕業が真相ってところですね。それが伝言ゲームのように伝わっていく中で副が取れてキャプテンになって、それが鬼塚くんで」
「主犯にされちゃったわけだ」
「それでも、誰が悪いとは言わなかったですよね。自分はやってない、そのことをだけを必死に伝えてた。誰も傷つけてない人だなと思いました」
「それを言うなら花屋さんもだし、麻月さんだって同じじゃないかな」
「ここで長谷川くんの名前が出てこないのがリアルですね」
「データ改善してるからね」
「改善して、開き直っちゃいましたから」
「反省の色を見せてくれてたらもうちょっと変わったんだけど」
「それでも名前が出たでしょうか」
「うーん、出なかったかもしれない」
「辛辣ですね」
「あんなことができるぐらいの神経だから、イカれてるんだろうなとは思う」
「開き直っちゃいましたね」
「私が悪かったのは事実で、そこを捻じ曲げたらいけないよ」
「──っていう話を、あの場にいた三人にも話していいですか」
そう提案されて「ん?」と声が出た。
「どういうこと?」
「森さんは真犯人じゃないよと」
「いやいや、もう真犯人でいいよ」
「だめですよ、高辻くんが真犯人なんですから」
「真犯人かどうかはわからないけどね」
「でもちゃんと言っておかないと、森さんがずっと犯人扱いのままです」
「そんなのいいよ」
別に犯人と思われていようが構わないのは事実だ。
それに、今さら感もある。
「私はみんなを売ることで内定を勝ち取ろうとしたんだから」
「ああ、そうだ。そろそろ真実を教えてくれませんか」麻月さんは、少し口角を上げた。「あのときも、ちょっと嘘をついてましたよね? 真相を話すとき」
「……真実を話したよ」
「いえいえ、プリンターの謎が解明されていません。どうして森さんがベーグル社のプリンターを動かすことができたのか。そして、高辻くんではない証拠も、そこでわかるんじゃないかと思っているんですから」
「麻月さんって執念深いよね」
「絆創膏一枚を今も大事に持ち歩いているぐらいですから」
そう言って、スマホのケースを取り外すと、私があげたあの絆創膏を出てきた。
「肌身離さずってこのことかな」
「私にとって、それだけ大事なものってことです」
*
香田さんに持ち掛けられたのは、なぜかメールでのことだった。
ちょうど十五分休憩が始まったところで【確実に内定枠を入手しませんか】という文言が飛び込んできたときには思わず目を疑った。
詐欺か。これはなんなんだ。それから麻月さんに声をかけられて思わず笑みを浮かべたが、頭の中でスパイになれと言われていることに理解が追いつかなかった。
これから届く文言を会議室で印刷するように。それが私に課せられた使命で、実行すれば内定がもらえるという。意味がわからないものだったが、内定がもらえるに越したことはなかった。
様子を見ていたけれど、私以外にあのメールをもらった人はいないようだった。
だから、もちろんみんなの秘密が高辻くんが送られてきたという説はない。高辻くんは可哀想だけれど、最後まで運がなかっただけの人だった。
プリンターの操作はほとんどスマホで十分で、香田さんから送られてきていたWi-FiルーターのSSIDとパスワードを入力すればいいだけ。なにも難しいことはなかった。
ただ、ここまでの流れが本当に起こっているのかを確認するために、プリンターを試しで動かしてみた。すぐにピーと反応する音が聞こえて中止を押した。
ああ、本当に私はスパイになっている。そんな馬鹿げたことを思っていたりもする。
プリンターが誤作動したと解釈してくれたときは本当に助かった。それに香田さんという協力者がいたから、みんなは特に怪しむことなく、それからのプリンターに怯えてくれた。
みんなの秘密が暴かれていく。けれど突発的に決まったこのゲームの終止符を考えていなかった。いや、考えようとしたけれど、考えられるだけの余裕はなかった。
その結果、最後に残ったのが犯人だと推理され、慌てて麻月さんと、自分の虚偽をプリントした。そのあとは私が犯人ということになったけれど、もうそれでよかった。
そう思っていることは事実だし、今さら蒸し返してどうこうしてやろうということもない。ただ、私はこれでいい。
*
パタンと、手帳を閉じた。
あの日あった出来事を振り返しながら、最後の言葉を思い出す。
【最後に結果で締める必要はあるけれど、それはこの手帳の最後に残しておくとする。】
あのときも、現時点で結果が出ていないからと濁したが、おそらく、結果が記されることはないのだろう。
私はもう、見えてなかった部分がもう見えているような気がする。
「次の方、どうぞ」
呼ばれて、ふうと深呼吸をする。ノートを鞄にしまう手が震えていた。何度経験をしても、このときばかりは慣れない。
足に力を入れて立ち上がると、わずかに靴擦れが痛んだ。心機一転の気持ちで新しいパンプスに買い替えたが、やはり靴擦れとは切っても切れない中らしい。おまけにストッキングは敗れて、慌ててコンビニで新調した。今度からは予備をきちんとストックしておいたほうがいい。
それでも、靴擦れの痛みは以前に比べてずいぶんとマシだ。この足も、そろそろこのパンプスに慣れてくれるだろう。そうでなければ困ってしまう。
私はまだまだ、自分と、社会と、戦っていかなければいけないんだから。
ライフフューチャー株式会社。個人や企業に向けたメンタルヘルス支援サービスを展開している企業で、社員やクライアントが抱えるストレスや心理的な課題を解決するためのカウンセリング、自己分析ワークショップ、そして成長支援プログラムを提供している。
社員数は三十人と決して多いわけではないし、福利厚生の充実度は大手企業には遠く及ばない。社会保険は完備されていたものの、通勤手当は上限があったり、賞与や昇給も期待できるかどうかは、会社の業績にかかっているらしい。
以前の私であれば、真っ先に排除していた候補先だろう。
握っていた少しお高めの絆創膏をジャケットのポケットに戻す。いつしかこれがお守りのように手放せなくなっている。麻月さんに話したら喜んでもらえるだろうか。私が彼女から聞いて嬉しかったように。
コンコンと控えめなノックをして、少し古びた木製の扉を押し開けた。先に広がっていたのは、四角いテーブルが一つだけ置かれた小さな会議室。部屋はこじんまりとしていて、窓から差し込む午後の日差しが、黄ばみがかった壁紙に柔らかく反射している。
空気は重たいわけではない。落ち着きすぎていて、少し緊張感を伴っているぐらいだ。部屋には一人だけ、面接官が座っている。背筋をピンと伸ばし、整然と並んだ書類を前に、私を見つめていた。
名前、それから求められるものを答えていく中で、ようやく最後にやってきたのは──
「学生時代に力を入れたことはなんですか?」
大丈夫、私は私のままでいい。
緊張を飲み込み、そして意思を伝えるように面接官──織田さんの目を見た。
「はい。私は、これまで自分の弱さを隠し続けてきました。
自分をよく見せたいがために、時には嘘をつくこともありました。しかし、そうした自分に正直になれない生き方が、最終的には自分自身を苦しめていることに気づいたんです。
これまで、さまざまな企業の面接に参加しましたが、特に困難だったのは、自分の弱さを認めることでした。最初は完璧であることに執着し、失敗を避けようとするあまり、あるとき大きなミスを犯してしまい、そのときに初めて周囲のサポートを受け入れることができました。
その経験から、私は弱さを隠すことよりも、それを認めて他者と協力することの大切さを学びました。結果として、チームとしての成果は大きくなり、自分一人では達成できなかった目標を超えることができました。
御社の企業理念である『誠実さを持って信頼を築き、共に成長する』という言葉に強く共感しています。
私の過去の経験を振り返ると、この理念は私自身が成長の過程で学んだことそのものであり、嘘ではなく正直さと誠実さを持って、チームやお客様との信頼関係を築くことが、長期的な成果に繋がると確信しています。
私は、御社でその理念を実現するため、まずは自分に正直に向き合い、チームメンバーやお客様と誠実に接し、信頼を得ることを大切にしていきます。そして、企業の一員として、共に成長しながらより良い成果を出していくことを目指します。
今では、自分に正直に向き合い、弱点を強みに変えることができるようになりました。
この経験を通して学んだのは、自己改善のためには他者との連携が不可欠であるということ。そして、何よりも大切なのは、どれだけ本当の自分に向き合えるかだと感じています。
この新たな姿勢で、御社の理念に貢献し、長期的に成長していける人材になりたいと考えています」
誠実に、それでも着実に。
私という人間を生きていこう。
どこかで私を必要としてくれる日のために。
そう言うと、麻月さんはあのときと変わらない笑みを見せてくれた。
「ずっとお会いしたかったので」
ベーグル社からほど近い喫茶店で待ち合わせしていた。お互いにリクルートスーツではなく私服だ。鮮やかな黄色のワンピースは麻月さんによく似合っていた。
「お互い、あまりいい別れ方はしなかったからね」
そうですね、と麻月さんが柔らかく微笑んだ。
「聞いたよ、麻月さんがベーグルの内定をもらったって」
「もらいました。私は、森さんを推薦したんですが」
「知ってる。あんなことがあって、まさか推薦してもらえたなんて思わなかったけど」
「します。私にとって森さんは、恩人ですから」
そんなことを、今でも言ってくれるのか。あれから一か月経つけれど、麻月さんは以前に増して自分の言葉に自信が持てたような印象がある。特に、私のことを恩人だと言いきってしまうその強さには。
「このまま懐かしい話に戻りたいところですが、先に済ませしょうか」
「うん」私は、切り出した。「犯人だね」
「やっぱりそうですよね。あのときの犯人が、最後まで不明のままでしたから」
きっとここに来るまでに、いろいろとシミュレーションをしてきてくれたのだろう。犯人という突飛な展開にも麻月さんは驚くことがなかった。
「森さんが一番最初に内定をもらったことは知っているんです。おそらく私だけかもしれないんですが」
それはベーグル社に入社できたからだろう。香田さんにあれからいろいろと聞いたのかもしれない。
「四名の推薦があったのは事実ですけど、それ以外にも森さんが採用された理由をお話したいです」
「遠慮したいけどね」
「話させてください。森さんは、全部の罪を被ったんですから。それはみなさんが知るべきですし、だからこそ内定が決まったんです」
そのことを、今日は一番に伝えたいと思ってくれていたのだろう。そして、あのときあったことをきちんと清算したいと誰よりも考えていたのだろう。
「森さんは最後まで悪役を務めていましたよね。そういう意味で、私は森さんを推薦したかったんです」
「そんなことない。みんなの秘密をばらしたのは私だから」
「そこまでが森さんの役割だったはずです」
「麻月さんの情報網ってどうなってるの?」
「自称情報屋ですから」
「なにそれ」
「私の黒歴史です」
じゃあ、と麻月さんは言った。
「森さんが話さなかった、もう一つの事実をお聞かせください」
──事実。それを話すとなれば、私たちは共通の認識を持たなければならない。わかったと、頷いて私は切り出した。
「六人目の候補者のことを思い出してほしいんだけど」
*
あの日、会議室に集められたのは私を含めて五人と──
「ええと……聞こえてますかね」
もう一人、高辻という男が参加していた。けれど彼の場合、私たちとは違っていた。
「すいません、僕だけリモートで。本来ならここに参加させてもらえるなんてありえない話なんですけど」
ベーグルの本社に呼ばれていた私たちと、物理的な理由によりリモートになった彼。
最終選考に残されているのが六名だと知ったのは、このときだった。
誰しもが、リモートの参加を許されていいのかと疑念を抱いたに違いない。けれど、面接官たちが当たり前のように高辻を受け入れ、受け答えをしていくものだから、その疑念はついに薄れていった。ああいう場とは恐ろしいもので、企業側に問題がないならそれでいいのだろうとなぜか納得してしまう。今思えば、彼という存在は最初からおかしかった。
「高辻さん、今日はよろしくお願いします」香田さんが一番に挨拶をした。面接官は基本的に香田さんが話すだけで、残りの四名はほとんど口を開くことはなかった。
高辻の顔は、プロジェクターによってスクリーンに映し出されていた。本人がどう見えているかはわからないが、私からすると公開処刑並みに恥ずかしいものだった。
「こちらこそ、よろしくお願いします」高辻はスクリーン越しに明るい笑顔を見せた。好青年という言葉がふさわしい。鬼塚くんとも長谷川くんともタイプが違っていた。
その後始まった最終選考で、香田さんから自己紹介をするように促され、一人ずつ答えていった。それぞれの経歴や、志望動機を話し、高辻の順番は最後に回った。簡単に言ってしまえば、あまり特別なことを言っていたようには思えない。私と同じように、どこか薄っぺらさを感じるようなものだったが、彼には自信というものが備わっていた。
高辻がリモートでいるというのは、少し特別な状況だったが、次第に慣れていった。むしろこの場にいなくとも、目の前の面接を乗り越えなければならないという共通の目的は一緒だった。
「さて、次にお話ししたいのは、これからの企業で必要な人材についてです。皆さんはどのようなスキルや資質が必要だと思いますか?」香田さんの問いに、すぐには答えが出なかった。真っ先に口を開いたのは高辻だった。
「私が思うに、チームでの協力や柔軟な対応力が重要だと思います。これからの時代、変化に適応できる能力が求められますし」
「僕もそう思います」鬼塚くんが続いた。「特に環境問題に取り組む上では、多様な視点を持って、さまざまなバックグラウンドを尊重しながら進めていくことが大切です」
花屋さんもそれに続くように、自分の考えを述べた。「自分の意見を持つことも大事にしながら、周囲の意見も尊重し合える環境を作ることが、組織全体の成長につながると思います」
香田さんを含めた面接官は、各々で別の表情を浮かべていた。
面接が進む中、突然スクリーンの映像が乱れ始めた。高辻の顔が一瞬消え、再度映し出された時には、彼の表情が緊張しているのが見て取れた。
「すいません、回線が不安定になったみたいで……」
「大丈夫ですか?」と香田さんが高辻に問いかける。高辻はパソコンの画面を叩きながら、回線が回復するのを待っている様子だった。
「大丈夫です。すぐに戻りますから」と高辻が答えた瞬間、画面がまたもや不安定に揺れ始める。私たちの間に不安な空気が流れる中、再び高辻の顔が画面に映った。
「申し訳ありませんが、少し私の方でトラブルが起きているようです。音声が聞こえづらいかもしれないですが」
リモートである以上、回線のトラブルは避けられない。そういった点では面接でもデメリットに働いてしまうだろう。社長が「だから言ったじゃないか」とこぼした。おそらく高辻のリモート参加を非難しているのだろう。そして社長は反対だった。
「わかりました。こちらの声が聞こえないようでしたら……とりあえずは回線が復旧するまでお待ちいただいてよろしいでしょうか」
はい、と高辻の声が歪んだものに聞こえた。映像だけではなく音声にも乱れが出ている。
「それでは、次の質問に移りましょう」と香田さんが高辻を気遣いながらも、選考を進めることにした。しかし、時間が経つにつれて、高辻の様子は変わっていった。最初のうちは、私たちの間で楽しい会話が続いていたが、やがて彼の表情は不安げなまま、回線が戻らないという事実が現実味を帯びてきた。
「大丈夫かな」質問が途切れたタイミングで花屋さんが呟いた。その言葉に、私たち全員が高辻を気遣う視線を交わす。スクリーンには、もう高辻の顔が長らく映っていない。
「高辻さん、大丈夫ですか?」香田さんが声をかけても、画面は静まり返っていた。彼の顔は再び映ることない。
「高辻さんの接続が戻らないようですね」と香田さんの隣に座っていたもう一人の人事部の女性が言った。「このままだと、選考を続けるのが難しいかもしれません」
もし高辻がこのまま接続できなかったら、選考から外れるのだろうか。
「高辻さん、接続が不安定なようですので、選考を続けることが難しいと思います。どうされますか?」その声さえも高辻に届いているのか不明だったが、数分後、高辻の声がかすかに聞こえた。「すみません、こちらの回線が不安定で選考を続けるのは難しいと思います。申し訳ありませんが、辞退させていただきます」
面接を辞退。
彼の顔が画面に戻らないことが、まさか選考の終わりを意味するとは思ってもみなかった。
「高辻くん、あのとき本当に消えたと思いますか?」
他己紹介が始まるまでの出来事を確認し合っていると、麻月さんが言った。
「……どういうこと?」
「実は、あとで調べてわかったんです。あの会議室に小型カメラがあったって」
「え」
「観葉植物があったの覚えてますか? そこに隠れるようにして置いてありました」
「そんな」
それは初耳だ。おそらく麻月さんにだけ伝えられた情報だったのだろう。
「高辻くんがリモートで参加していたので、私たちが気づかないうちに彼が全てを監視していた可能性があります。もしかしたら、私たちの会話や表情をリアルタイムで見ていたかもしれないです」
「いや、なんでそんなことを」
「リモートだから」麻月さんは続けた。「現場にいなくても、全てを見ていたかもしれません。しかも私たちは、高辻くんがスクリーンにいると信じて疑わなかった」
たしかに、スクリーンから高辻くんが消えて、その後はもういないものだと思っていた。
「選考を有利に進めるためだったのか、ただ単に私たちの反応を見て楽しんでいたのか、理由はわかりません。ただ、リモートというのは都合の良い隠れ蓑にはなったかと思います。私たちが感じてるよりも、ずっと簡単に情報を得ることができたはずですから」
そうして、あの暴露大会が始まった。
理由はなんだろうか。
「……自分が辞退したから、あんなことをしたって麻月さんは考えてたりする?」
「どうでしょう、さすがに自己中心的過ぎて引きますけど。それに、辞退することになったのは自分のせいで、そもそもリモートで参加したのが運の尽きってところはありますし」
だけど、と麻月さんは運ばれてきていたカップを手にした。
「高辻くんはどこまで計算していたのかは気になります」
「どこまで?」
「回線に不具合が起こることも想定して、その先にある辞退も見込んで、全員を破滅させようとしてたって説もあるんじゃないかと」
私たちが闘おうとしていた場所で、別の思惑が働いていたことはそこまで意外でもない。
「リモート参加は、最初からハンデを背負ってるように見えますから。もしそれが最初から仕組まれた“戦略”だったとしたら、どうなんだろうと」
「大がかりだなあ」
「ですよね」と麻月さんは静かに同意した。「でも、もし高辻くんが回線不具合も辞退も全て計算していたとしたら、私たちがこうして彼を疑い始めることすら、彼の計画の一部かもしれないですし。自分は潔白を装いながら、みんなが疑心暗鬼に陥るのを待つ。それから全員を精神的に追い詰め、内定を勝ち取ろうとしていた可能性もあります」
追い詰められ、終わってしまった。
けれど一人だけ、追い詰められることなく、終わった人もいる。
私たち全員がダメなら、自分に内定が回ってくると見越していたのかもしれない。
「人間って、極限状態に置かれたら何をするかわからないものですからね。まして就活の最終面接、全員がライバルという状況なら尚更です。少しでも有利になる手段を選びたいって思うのは、ある意味当然かと思います」
「……それに」麻月さんは小さな声で続けた。「観葉植物のカメラ、誰がそこに置いたのかなんて、私たちが知るはずもないですから。それでも今なら、リモートで参加してた人間が一番怪しいと思いませんか」
そう言われてみればそうだ。高辻くんがいなくなった時点で、私たちはもう五人だけで戦うのだと思っていた。最初から高辻という男が存在しなかったように話しは進み、最後まで彼の名前が出ることもなく終わっていた。誰からも紹介されることなく、消えていった人。
あの人は本当に高辻という男だったのだろうか。そもそも、リモートが許されていた時点で疑うべきだった。本当に、就活生だったのかどうか。
「高辻くんは私たちの顔と名前を知っています。秘密を調べることもできたはずです」
私たちが高辻をスクリーン越しで見ていたように、高辻もまた私たちが見えていた。私にDMを送ってきたのもおそらく高辻だったのだろう。そう片付けてしまうのはできる。結局のところ犯人はわからないままなのだから。
「一番は高辻くん本人に聞いてみるのが一番手っ取り早いんですが、連絡がつかなくて」
「え、連絡先を知ってるんですか?」
「情報屋ですから──というのはさすがに冗談ですが、香田さんに相談して、そのあたりは動いてみたりはしました。結局のところ意味はなかったんですが」
そんなことをしてくれていたのか。麻月さんの行動力に感心してしまう。
「ただ、正直、鬼塚くんはわかってたんじゃないかなと思うんです」
なぜかここで鬼塚くんが出てきた。
「どうして鬼塚くん?」
「あの日、私はすっかり忘れていましたけど、鬼塚くんは何回か高辻くんのことを思い出したと思うんです。何度かスクリーンを見ていましたし、もしかして犯人だと疑っていたのかもしれません。それに、香田さんからもちらっと話しを聞いたので」
他己紹介のときだろうか。そう訊ねると彼女は頷いた。
「基本的に他己紹介で聞いた話は他言しないことがルールでしたよね。ですが、高辻くんだと思われる箇所は例外ではないかと──無理やり取ってつけたようなニュアンスで教えてもらっただけんですけど。多分、私がしつこかったんだと思います」
麻月さんのしつこさは想像できない。そこまでして手に入れた情報とはなんだろうか。
「鬼塚くんは、私の他己紹介をすることになっていたそうです。内容はわかりませんでしたけど、最後になぜか私ではない人の話に触れたそうです」
「それが高辻くん?」
「その可能性はあります。“存在自体が嘘だったんじゃないか”みたいなことを言っていたそうです」
「そうだとしたら、鬼塚くんは高辻くんが犯人だってわかってたってことかな」
「やたらとパソコンを気にしていたように見えますし」
言われてみればそうだ。機械がどうとか何度か話題にしていた。
「高辻くんの存在が頭にはずっとあったとは思います。犯人が森さんってことにされてからは、そっちを信じたのかなとは感じてはいたんですが、香田さんに話してたのを聞いたら、高辻くん説を鬼塚くんは早い段階で持ってたんじゃないかと」
「そうだとしたらすごいね」
「すごいです。仲間思いなんでしょうね、鬼塚くんは。最後まで言いませんでしたけど、マルチ勧誘の事件には無関係だったみたいです」
「え、でもキャプテンがどうとか話しがあったよね?」
「副キャプテンの仕業が真相ってところですね。それが伝言ゲームのように伝わっていく中で副が取れてキャプテンになって、それが鬼塚くんで」
「主犯にされちゃったわけだ」
「それでも、誰が悪いとは言わなかったですよね。自分はやってない、そのことをだけを必死に伝えてた。誰も傷つけてない人だなと思いました」
「それを言うなら花屋さんもだし、麻月さんだって同じじゃないかな」
「ここで長谷川くんの名前が出てこないのがリアルですね」
「データ改善してるからね」
「改善して、開き直っちゃいましたから」
「反省の色を見せてくれてたらもうちょっと変わったんだけど」
「それでも名前が出たでしょうか」
「うーん、出なかったかもしれない」
「辛辣ですね」
「あんなことができるぐらいの神経だから、イカれてるんだろうなとは思う」
「開き直っちゃいましたね」
「私が悪かったのは事実で、そこを捻じ曲げたらいけないよ」
「──っていう話を、あの場にいた三人にも話していいですか」
そう提案されて「ん?」と声が出た。
「どういうこと?」
「森さんは真犯人じゃないよと」
「いやいや、もう真犯人でいいよ」
「だめですよ、高辻くんが真犯人なんですから」
「真犯人かどうかはわからないけどね」
「でもちゃんと言っておかないと、森さんがずっと犯人扱いのままです」
「そんなのいいよ」
別に犯人と思われていようが構わないのは事実だ。
それに、今さら感もある。
「私はみんなを売ることで内定を勝ち取ろうとしたんだから」
「ああ、そうだ。そろそろ真実を教えてくれませんか」麻月さんは、少し口角を上げた。「あのときも、ちょっと嘘をついてましたよね? 真相を話すとき」
「……真実を話したよ」
「いえいえ、プリンターの謎が解明されていません。どうして森さんがベーグル社のプリンターを動かすことができたのか。そして、高辻くんではない証拠も、そこでわかるんじゃないかと思っているんですから」
「麻月さんって執念深いよね」
「絆創膏一枚を今も大事に持ち歩いているぐらいですから」
そう言って、スマホのケースを取り外すと、私があげたあの絆創膏を出てきた。
「肌身離さずってこのことかな」
「私にとって、それだけ大事なものってことです」
*
香田さんに持ち掛けられたのは、なぜかメールでのことだった。
ちょうど十五分休憩が始まったところで【確実に内定枠を入手しませんか】という文言が飛び込んできたときには思わず目を疑った。
詐欺か。これはなんなんだ。それから麻月さんに声をかけられて思わず笑みを浮かべたが、頭の中でスパイになれと言われていることに理解が追いつかなかった。
これから届く文言を会議室で印刷するように。それが私に課せられた使命で、実行すれば内定がもらえるという。意味がわからないものだったが、内定がもらえるに越したことはなかった。
様子を見ていたけれど、私以外にあのメールをもらった人はいないようだった。
だから、もちろんみんなの秘密が高辻くんが送られてきたという説はない。高辻くんは可哀想だけれど、最後まで運がなかっただけの人だった。
プリンターの操作はほとんどスマホで十分で、香田さんから送られてきていたWi-FiルーターのSSIDとパスワードを入力すればいいだけ。なにも難しいことはなかった。
ただ、ここまでの流れが本当に起こっているのかを確認するために、プリンターを試しで動かしてみた。すぐにピーと反応する音が聞こえて中止を押した。
ああ、本当に私はスパイになっている。そんな馬鹿げたことを思っていたりもする。
プリンターが誤作動したと解釈してくれたときは本当に助かった。それに香田さんという協力者がいたから、みんなは特に怪しむことなく、それからのプリンターに怯えてくれた。
みんなの秘密が暴かれていく。けれど突発的に決まったこのゲームの終止符を考えていなかった。いや、考えようとしたけれど、考えられるだけの余裕はなかった。
その結果、最後に残ったのが犯人だと推理され、慌てて麻月さんと、自分の虚偽をプリントした。そのあとは私が犯人ということになったけれど、もうそれでよかった。
そう思っていることは事実だし、今さら蒸し返してどうこうしてやろうということもない。ただ、私はこれでいい。
*
パタンと、手帳を閉じた。
あの日あった出来事を振り返しながら、最後の言葉を思い出す。
【最後に結果で締める必要はあるけれど、それはこの手帳の最後に残しておくとする。】
あのときも、現時点で結果が出ていないからと濁したが、おそらく、結果が記されることはないのだろう。
私はもう、見えてなかった部分がもう見えているような気がする。
「次の方、どうぞ」
呼ばれて、ふうと深呼吸をする。ノートを鞄にしまう手が震えていた。何度経験をしても、このときばかりは慣れない。
足に力を入れて立ち上がると、わずかに靴擦れが痛んだ。心機一転の気持ちで新しいパンプスに買い替えたが、やはり靴擦れとは切っても切れない中らしい。おまけにストッキングは敗れて、慌ててコンビニで新調した。今度からは予備をきちんとストックしておいたほうがいい。
それでも、靴擦れの痛みは以前に比べてずいぶんとマシだ。この足も、そろそろこのパンプスに慣れてくれるだろう。そうでなければ困ってしまう。
私はまだまだ、自分と、社会と、戦っていかなければいけないんだから。
ライフフューチャー株式会社。個人や企業に向けたメンタルヘルス支援サービスを展開している企業で、社員やクライアントが抱えるストレスや心理的な課題を解決するためのカウンセリング、自己分析ワークショップ、そして成長支援プログラムを提供している。
社員数は三十人と決して多いわけではないし、福利厚生の充実度は大手企業には遠く及ばない。社会保険は完備されていたものの、通勤手当は上限があったり、賞与や昇給も期待できるかどうかは、会社の業績にかかっているらしい。
以前の私であれば、真っ先に排除していた候補先だろう。
握っていた少しお高めの絆創膏をジャケットのポケットに戻す。いつしかこれがお守りのように手放せなくなっている。麻月さんに話したら喜んでもらえるだろうか。私が彼女から聞いて嬉しかったように。
コンコンと控えめなノックをして、少し古びた木製の扉を押し開けた。先に広がっていたのは、四角いテーブルが一つだけ置かれた小さな会議室。部屋はこじんまりとしていて、窓から差し込む午後の日差しが、黄ばみがかった壁紙に柔らかく反射している。
空気は重たいわけではない。落ち着きすぎていて、少し緊張感を伴っているぐらいだ。部屋には一人だけ、面接官が座っている。背筋をピンと伸ばし、整然と並んだ書類を前に、私を見つめていた。
名前、それから求められるものを答えていく中で、ようやく最後にやってきたのは──
「学生時代に力を入れたことはなんですか?」
大丈夫、私は私のままでいい。
緊張を飲み込み、そして意思を伝えるように面接官──織田さんの目を見た。
「はい。私は、これまで自分の弱さを隠し続けてきました。
自分をよく見せたいがために、時には嘘をつくこともありました。しかし、そうした自分に正直になれない生き方が、最終的には自分自身を苦しめていることに気づいたんです。
これまで、さまざまな企業の面接に参加しましたが、特に困難だったのは、自分の弱さを認めることでした。最初は完璧であることに執着し、失敗を避けようとするあまり、あるとき大きなミスを犯してしまい、そのときに初めて周囲のサポートを受け入れることができました。
その経験から、私は弱さを隠すことよりも、それを認めて他者と協力することの大切さを学びました。結果として、チームとしての成果は大きくなり、自分一人では達成できなかった目標を超えることができました。
御社の企業理念である『誠実さを持って信頼を築き、共に成長する』という言葉に強く共感しています。
私の過去の経験を振り返ると、この理念は私自身が成長の過程で学んだことそのものであり、嘘ではなく正直さと誠実さを持って、チームやお客様との信頼関係を築くことが、長期的な成果に繋がると確信しています。
私は、御社でその理念を実現するため、まずは自分に正直に向き合い、チームメンバーやお客様と誠実に接し、信頼を得ることを大切にしていきます。そして、企業の一員として、共に成長しながらより良い成果を出していくことを目指します。
今では、自分に正直に向き合い、弱点を強みに変えることができるようになりました。
この経験を通して学んだのは、自己改善のためには他者との連携が不可欠であるということ。そして、何よりも大切なのは、どれだけ本当の自分に向き合えるかだと感じています。
この新たな姿勢で、御社の理念に貢献し、長期的に成長していける人材になりたいと考えています」
誠実に、それでも着実に。
私という人間を生きていこう。
どこかで私を必要としてくれる日のために。