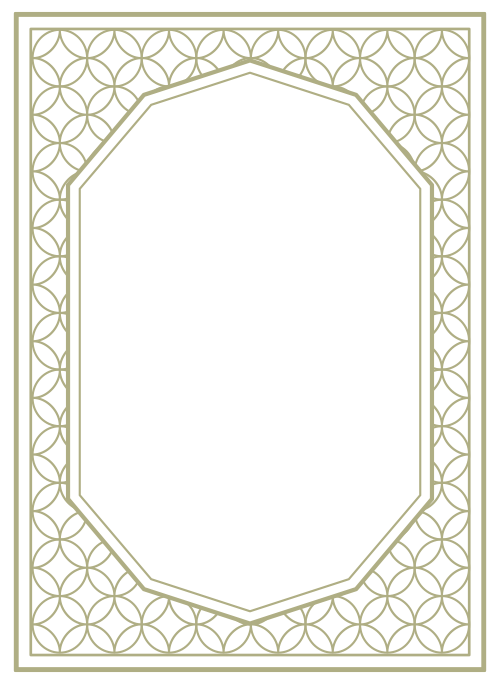麻月さんは力が尽きたように、その場から動かなくなってしまった。
今どんなことを考えているんだろう。自分の罪と、これからどう向き合っていくのだろう。
「あのさ」口を開いたのは花屋さんだった。「ずっと思ってるっていうか、考えてることがあって」
彼女は少し言いずらそうな表情を浮かべたあと、申し訳なさそうに私を見た。
「今回の犯人、森さんだったんじゃないかなって思ってるの」
「……え?」
突然落とされた爆弾に、まともに息が吸えなかった。
今、犯人と言われたのだろうか。
冗談を言われているのかと思ったが、この空気で言われるような内容でもない。リアクションが取れなかった。ずいぶんと間抜けな顔をしていたと思う。花屋さんは、まだ私を見ている。鬼塚くんも長谷川くんも私を見ている。少し遅れて、麻月さんも私を見た。ワンテンポ遅れて花屋さんの声が届いていたのかもしれない。
そんなことを冷静に思いながら、変に発言をしないようにした。
「正直、どこからが森さんの仕業かわからないんだけど」
発言権を持つ人の力とは強い。まるでそれが全て真実のように聞こえてしまう。いいな、私にもこういう力があったらよかったのに。
足が痛い。そうだ、靴擦れ。あれ、ずっと治らないんだよなあ。もう履きたくないと思うのに、まるでパンプスの呪いでもかかったようにこの痛みを我慢しなければならない。
「プリンターは、森さんだったんじゃないかなって」
「どうして……私が」
「一番最初にプリンターを見たからだよ」
この人は、本当によく周りを見ている。
「誤作動があったとき、私はどこから音が出たのかすぐにはわからなかった。プリンターだって知ったのは鬼塚くんが教えてくれたけど、それより前に森さんはプリンターを見てたよね」
「……いや、あの音はわかるよ」
「そうかもしれない。あれはプリンターだって、すぐに判断できた人もいる。だから森さんはそうだったんだって思うようにしてたの。だけど、スマホで操作できたのは、やっぱり森さんだけなんだよ」
「言いがかりだよ、そんなの」
「森さん以外が、圏外だったとしても?」
反論しようとしたけれど、すぐには出ていかなかった。
なぜ、こんなことを言われているのだろう。
「鬼塚くんのスマホが圏外だったって話があったよね。あのときは、もう私も圏外だったの。電波があるって嘘をついたのは、香田さんにそうお願いをされていたからだよ」
香田さん。お願い。私が知らないところで、何が交わされていたのだろうか。
「長谷川くんも同じ。私たちがお願いされたのは、一番最初の十五分休憩のとき。廊下で香田さんに呼び止められて、そう答えるように指示を受けたの。どうしてだったのかはゲームが始まるまではわからなかったけど、私たち三人は麻月さんと森さんを疑ってた」
あのときから、香田さんによる計画は始まっていた──?
「だけど途中で、麻月さんから圏外の話が出た。あのタイミングで圏外だってことは、あとは森さんからの発言を待つしかないって思っていたけど、唯一、圏外にならなかったんじゃない?」
スマホを取り出し、確認することが最善なのだろう。けれど、そうできなかった。
「……確信が持ててたわけじゃなかった。特定の人間のスマホを圏外にできるのか、それを調べたくてもスマホが使えないし」
「待って。花屋さんはスマホが使えていたよね? 私たちにフォロワー数がわかるアカウントのページを見せてくれて」
「あれはスクショだよ。リアルタイムのものじゃない」
「……いやいや」
でも、それ以上はなにも出てこなかった。
「だから何って話かもしれない。森さんだけが圏外じゃないから、犯人にしようと思ってるわけでもない。ただ、それ以外でも引っかかったことはあったの」
もう顔が上げられない。立ち振る舞いの正解が見つからない。
「森さんって、何もかもが嘘だよね?」
──嘘。
「情報として正しいのは、名前ぐらいなんじゃないかな。そもそも、森果歩って人間、ちゃんと実在してるよね?」
なんでこんなことになってるんだっけ。
私って、ちゃんとここにいるよね?
「森さんって、本当に私たちと同じ就活生?」
疑いの目が鋭く向けられていた。花屋さんだけではなく、鬼塚くんと長谷川くん、それから麻月さん。
「私たちに話してくれたガクチカ、あれって森さんの経験ではないでしょ」
私の嘘。
それはどこから始まっているんだろう。
少なくとも、就活において、本当の自分なんてどこにもいなかった。
「だって、森さんが話してくれた内容、そっくりそのまま私の友達だったから」
「え」
「似てるどころの話じゃない。個人的にどう思っていたか、それさえも全く同じなんて、そんなの偶然にしては怖いよ」
これまでいくつもの面接を通ってきた。
その度に、他人のガクチカを盗んできた。面接官が食いついたり、好感度を見せていたりすれば、次の面接で使った。私の学生時代、ただただ与えられた授業を受けるだけの日々で、頑張ったことなんてなにもなかったから。
人よりも優れているところもなければ、誇れるような話もない。
私は、ただこの歳になるまで生きていきたような人間で、こういう場で話せるようなものなんて何ひとつ持ち合わせてはないんだから。それなら、嘘で自分を作っていくしかない。他人の話を盗むしかない。
「どうしてそんなことしたの? 全部嘘なんでしょ?」
「……嘘をつくことって、そんな悪いこと?」
ここは、そういう場でしょう?
本音で話してる人なんていない。
働きたくもないのに「ここで働きたいです」と自信満々に語って。
別に第一志望でもないのに「ここ以外考えられません」みたいに偽って。
ただ内定が欲しい。それだけのために、就活は存在しているように思えて仕方がない。
本当の自分をさらけ出して戦っているなんて、一体どれだけの割合でいるというのだろう。どう考えても、そんな人間は存在しないはずだ。
就活は戦争で、他人を蹴落としながら勝ち進んでいかなければならない。
常に選ばれなければいけない。
評価をされ、お祈りメールがくれば自分の存在価値を否定されたような気分になり、それでもまたボロボロになりながら立ち向かっていく。
価値のない自分という人間を、価値のある自分にしていく作業。
それが、そんなに悪いことだろうか。
花屋さんは左右に首を振った。
「嘘をついたことを責めてるんじゃない。私も嘘ついてたし。でも、ゼロからイチにするのはよくないと思う。それに、私がわからなかったら、そのまま突き通すつもりだったよね?」
嘘だった。他人の時間だった。それが、一体なんだと言うのだろう。
「イチを膨らませるのはいいと思う。でも、ゼロをイチにするって結構罪なことだと思うし、まして赤の他人の経験だとしたら、それは立派な罪だよ」
「罪?」
「森さんは経験してないでしょ? 人の経験を奪ったらだめだよ」
そうすることでしか、勝ちあがれなかった私は、どうしたらよかったのだろうか。
「嘘を評価されて、嬉しいの?」
「嬉しくないよ。でも、しょうがないじゃん」
開き直っていくしか、私は自分が保てなかった。
どう考えても、私が悪いことはわかって、正しいか正しくないかで言えば、それはハッキリと正しくないと判断ができる。それでも、本当の自分なんて一体どこにいた?
「そうやって嘘で固めて、他人を蹴落としていくのは楽しかった?」
「あの……本当に森さんが犯人なんですか?」麻月さんは信じられないと言いたげに問いかけた。誰に求めているのかわからないが、少なくとも私本人に向けられたものではない。
ほかの誰かに「違うよ」と言ってほしかったのかもしれない。私が言う「違う」と、他人が言う「違う」には大きな差がある。信憑性の問題だ。私の話ではあるのに、私の意見はどうでもいい。黙っていれば、長谷川くんがすっと息を吸った。
「そうなんじゃないですか。ほかにいなさそうですし」
「今までの話を聞いてたら、そうなんだろうな」確信はないけど、と鬼塚くんが続けた。
ここにいる全員、私が犯人だと思っている。
それなら、もうそれでいい。
真実がどうだとか、そんなことを話すつもりはない。
だって、半分は本当だ。
でも半分でも、当てはまることがあれば、それはもう全部なのと一緒。
「人の秘密を暴くってスリルがあって面白いと思う」花屋さんは、もう親しみのある笑みを向けてはくれなかった。代わりに、冷たく鋭い瞳がこちらを見据えている。視線が突き刺さる。「しかも匿名だったらなおさら」
「……どうして、こんなことを思いついたんですか?」麻月さんが私を不安そうに見つめる。
「どうしてって、納得してもらえるような答えはないよ」
「納得できなくても、理解は……したいです」
「それは麻月さんのエゴだよ。そこに巻き込まないでほしい」
「巻き込まないでって……森さんがやったことは、誰かが傷つくことで、それこそ森さんのゲームに私たちは巻き込まれているんですよ」
それもそうか。「ごめんなさい」と素直に謝れば「そいうことじゃなくて」と麻月さんはもどかしそうに前髪を触った。意思の通じない何かを前にしているような顔だ。
「でも」これ以上は言わないほうがいいとわかっていても、ずっと我慢していたことがポロポロと溢れていく。「誰かが傷つくようなことをしたつもりはないよ」
「はあ?」
鬼塚くんが飛び掛かってきそうだったけれど、不思議と怖いとは思わなかった。
「結果的に誰かが傷ついたかもしれない。でも、それは私が直接傷つけたわけじゃないよ。私がやったのは、ただみんなの秘密を明るみに出しただけ。みんな、自分の過去を隠してただけでしょ? それで誰が傷ついたの? 自分だけなんじゃないの? 自分がしてきた行動を隠していたのは、自分たち自身の選択だったんだよ。私はただ、みんなが作った仮面を壊しただけなんだから」
「そんな言い訳、誰が信じるんだよ!」鬼塚くんは私に向かって一歩踏み出してきたが、その瞬間、花屋さんが彼の腕を掴んだ。
「やめて、鬼塚くん」花屋さんの声は低く、冷静だった。彼女はゆっくりと鬼塚くんの目を見つめながら、さらに言葉を続けた。「このままじゃ、彼女の思うつぼだよ」
「……どういうことだよ」鬼塚くんは苛立ちを隠せないまま、花屋さんの手を振りほどいた。
「森さんは最初からこれを計画していた。私たちの弱点を見つけて、それを利用することで、自分が優位に立てるようにしていたんだよ。だから、今こうして私たちを挑発してる」花屋さんの目は鋭く光っていた。「私たちが感情的になって、彼女を責めれば責めるほど、彼女の思い通りになる。今だって、鬼塚くんは彼女のペースに乗せられている」
「まあ、たしかに花屋さんの言う通りかもしれないね。人の秘密を暴くって、スリルがあって面白いとは感じてた」
「でも、どうしてそんなことをするんですか?」麻月さんが震える声で問いかけた。「どうして、そんなに人の秘密を暴いて楽しんでるんですか?」
「楽しんでる……?」私は少し考え込んだ。「そう見えるかもしれないけど、私がやってるのはただのゲームじゃなかった。私にとって必要なこと。みんなが自分の秘密を隠して、それを守ろうと必死になるのを見ると……なんていうか、安心した」
「……それ、どういう意味ですか?」麻月さんが戸惑いながら尋ねた。
「簡単だよ」私は答えた。「私はずっと、何も持たずに生きてきた。誇れることも、就活で勝ち抜いていくための存在価値も。だから、みんなみたいに優秀そうな人が、秘密を持っていることがわかれば、安心できた。それさえ壊してしまえば、何も持っていない私だけが、勝ち残れる世界があるって思えたから」
その言葉に、場の空気は一層重くなった。誰もが自分の胸の内に秘めていたものを思い出し、そしてその秘密が暴かれる恐怖を感じていた。
「本当に森さんが仕組んだんですか? この状況……匿名の他己紹介だっていう仕掛けも」
「さすがにそれは違うって言いたいけど、信じてもらえるかは別の話だよね」でも、と笑みがこぼれる。「本当はみんな、誰かの秘密を知りたいと思ってたはずだよ」
私と目を合わせてくれる人は誰もいない。
「プリンターから自分の秘密じゃない、他人の秘密が出てくることを楽しみにしていた人もいるんじゃないかな。むしろ、ほとんどそうだったんじゃない?」
「お前と一緒にすんなよ」
鬼塚くんの声には、いつになく強い怒りがこもっていた。彼の目はまっすぐ私を見据え、冷たい怒りが渦巻いているのが感じ取れた。でも、その一言にはどこか焦りも含まれているように思えた。自分の内心が図星を突かれたのではないかという不安が、彼を動揺させているのだろう。
「本当に? 鬼塚くんだって、誰かの秘密を知りたいと思ったこと、少しでもあったんじゃないかな。誰かの失敗や、隠していたことが暴かれる瞬間を見て、ちょっとだけ安心してたとか」
「そんなこと、あるわけないだろ!」鬼塚くんは声を荒げたけど、その表情はどこか引きつっているようにも見えた。
「でも、もしそれが本当だったとしても、恥ずかしいことじゃないよ。だって、みんなそうなんだから。人の秘密を知りたがるのは、自然なこと。自分の方が少し優位に立てるような気がして安心できるし、他人のミスが自分の苦しさを和らげてくれるんだよ」
その瞬間、誰もが黙り込んだ。部屋の中には不安と沈黙が漂い、誰も私と目を合わせようとしない。プリンターから出てくる他人の秘密を心のどこかで期待していた自分に、今気づいたのかもしれない。
「それが……人間だよね?」私は続けた。「誰かの過ちや秘密を知ることで、自分が少しだけ安心する。自分も同じような失敗をするかもしれないけど、他人が先に失敗してくれたら、なんだかホッとするでしょ?」
麻月さんが震える声で口を開いた。「でも、それを利用するのは間違ってる……」
「間違ってる?」私はその言葉に少し笑ってしまった。「じゃあ、何が正しいんだろう? 私はただ、みんなが見て見ぬふりをしていた事実を表に出しただけ。誰もが心の中で思っていたことを、私は行動に移しただけだよ」
麻月さんは答えることができず、ただ俯いていた。彼女の指先が震えているのが見えた。
「結局さ、みんな自分のことしか考えてないんだよ。隠し続けていたものを、ただ外に出しただけ。それがたまたま、みんなの秘密だったってだけ」
私はそう言いながら、部屋の中を見渡した。鬼塚くんも、花屋さんも、麻月さんも、長谷川くんも、視線を伏せていた。それが、私にとっての答えだった。
「私のことを責めたいなら、ちゃんと私を見て言えばいいのに。自分も同じことを考えてたから、何も言い返せない?」
「黙れ……」鬼塚くんが低い声で呟いた。「黙れって言ったんだよ!」鬼塚くんが叫び、私に向かって一歩踏み出した。「お前が何を言っても、俺たちはお前とは違う!」
それはそうだろう。彼と私ではまるで違う。
「たとえ俺が一瞬でも、誰かの秘密を知りたいと思ったとしても、それは間違いだった。俺はそんな自分を恥じるよ。でも、お前みたいにそれを利用して人を傷つけることはしない!」
人を傷つける。私の行為は本当に人を傷つけてた?
「俺たちは、お前と同じじゃない」鬼塚くんは強く言い放った。「お前が他人の秘密を暴いて楽しんでいる間にも、俺たちは違う道を選ぶ。人を信じて、信頼し合って生きていくんだ」
「こんなことが起きて、それでも人を信じるの?」
「信じるよ。お前みたいな人間ばかりじゃない」
「ねえ、偽善者ごっこはやめようよ。みんな、自分の中で押し殺していた感情や秘密を、私が引き出されて、信用なんてできないでしょ。自分の秘密がバレたことで、パニックになったのはみんな自身のせいでもあるんだから、私だけを責める理由にもならない」
「言い訳にしか聞こえないですね」と、長谷川くんが静かに言った。「確かに、誰だって完璧なわけではないですし、隠したいことの一つや二つはあるでしょう。それでも、わざわざそれを暴いて他人を傷つける権利なんて、誰にもないんですよ」
「権利?」私は小さく笑った。「そもそも、みんなが正しいことだけをして生きてきたわけじゃないよね。だからこそ隠してたんじゃない? 私はただ、その隠された部分を引き出しただけ。それが事実なら、責めるべきは自分たちの過去でしょ?」
「そんなの詭弁だ」鬼塚くんが低く言った。「お前は俺たちを操って、自分だけが楽しんでたんだろ」
「そう思うなら、それでもいい。でも、私がしたことって、ただ他人の嘘を暴いただけ。私の行動で傷ついたなら、それはその嘘をついた自分のせいじゃない?」
「お前、ほんとにそう思ってんのか?」鬼塚くんの声は、驚きと怒りが入り混じったものだった。「本気で自分が正しいと思ってんのか?」
私は少し黙って、彼を見つめた。彼らの反応は予想通りだったけど、鬼塚くんの問いに答える言葉は、すぐには出てこなかった。
「正しいかどうか……それは、私にもわからないよ」と、私はやっと口を開いた。
「森さんってさ、嘘をつきすぎて、もう本当の自分がわからなくなっちゃってるんじゃない?」花屋さんに聞かれ、首を傾げた。
「……わからなくなってる?」私は静かに繰り返した。その言葉が妙に胸に響いた。「そんなこと、ないよ」
「そうかな」花屋さんは一歩近づき、私を真っ直ぐに見つめた。「ずっと周りの嘘を暴いて、それを楽しんでた。でも、それって結局、森さん自身も何かから逃げてるんじゃないの? 自分が何者なのか、どうしたいのかってことを」
「それ、まるで私が自分のことを見失ってるみたいに聞こえるね」
「だって、そうじゃない?」花屋さんの声は揺るがない。「最初は嘘を暴くことで自分を守ってたんだろうけど、気づいたら、その嘘に自分も飲み込まれてるんじゃないかって思う。嘘をつきすぎて、本当の森さんがどこにいるのか、もう誰にもわからないっていうか……森さん自身にも、わからないんじゃないの?」
「そんなことないよ」私は繰り返したが、自分の声がどこか揺れているのがわかった。こんなことは予想していなかったはずなのに、彼女の言葉が心に引っかかって離れない。
「私は、自分が何をしているかちゃんとわかってる。私が暴いたのは、みんなの嘘であって、私自身は嘘なんか」
「本当に?」花屋さんが優しく言葉を挟んだ。「森さんは、自分が一番嘘をついてるってこと、わかってるんだよね。他人の嘘を暴いてきたけど、本当は自分のことを隠すために、ずっと嘘をついてきたんだよ」
「それは……違うよ」私はかろうじて言ったが、自分でも説得力がないことを感じていた。「私はただ、みんなが隠してる真実を暴いただけで……」
「でも、なんでそんなことをしたんですか?」麻月さんが、小さな声で続けた。「森さんは自分が傷つくのが怖くて、みんなの秘密を暴くことで自分を守って」
「……違う」私は首を振った。「私はみんなを守ろうとしてたんだよ。みんなが嘘をついて生きてるから、その嘘が暴かれたら傷つくってわかってた。だから今のうちに……」
「本当にそうですか?」長谷川くんが口を挟んだ。「それなら、なんでこんなにみんなを傷つけたんです。誰も守られてなんかいない。むしろ、傷つけられただけじゃないですか」
「それは……」
私は言葉に詰まった。何を言っても、彼らの視線が痛いほど鋭く感じられる。私は本当に、自分のことを守ろうとしていただけなのだろうか。
「自分の中で本当の自分がわからなくなって、他人を傷つけることでしか自分を保てなくなってたんじゃない?」花屋さんの声が、再び鋭く私に突き刺さる。
「……わからない」私はついに口を開いた。「本当に、わからない」
その言葉が、自分でも信じられないほど本音だった。ずっと、嘘をつき続けてきた私。それがどれほど自分に影響していたのか、気づかないふりをしてきたのかもしれない。
「わからないよ。ねえ、長谷川くん」
彼の名前を呼ぶと、その肩がびくりと震えた。
「麻月さんのときに言ってたことをそのままお返しするけど、私って最初から犯人だって思ってた? こんなことする人間だってわかってた?」
「……わからないですよ、そんなこと」
「それなら、裏切られることもあって当然で、他人を蹴落とすのも当然でしょう」
「だから人を信用しないのか。言っとくけど、そういうお前の勝手な信念で、人を傷つけていいわけがないからな」鬼塚くんの指摘は鋭かった。
「どういうこと?」
「お前が他人を信用しなくても、誰かはお前のことを信用する。こんなことがあっても、それでもお前のことを信用している人間はいるかもしれない」
「いないでしょ、そんなの」
「──います」
そう、か細く聞こえた。誰、なんて思うはずもない。
「私は、信じたいです。森さんのこと、上辺だけじゃなくて、ちゃんと」
「……なんで? 私、こんなことしたのに、信じてもらえるような人間じゃないよ」
「人間だから、です」
麻月さんは、頼りない声で、それでも力いっぱい私に何かを伝えようとしてくれていた。
「人間だから、失敗するし、人間だから他人を傷つけます。でも、生きてたら当たり前のことじゃないですか。そんなことを経験していない人なんて誰もいません」
「……麻月さんは、私のせいで秘密が暴かれたんだよ?」
「だからなんですか。私は、森さんに傷つけられてばかりでもないです。助けてもらったこともあります」
「助けたって……私、嘘ばかりついてきたのに」
「その嘘に、助けてもらったんですよ」麻月さんは、私に一枚の絆創膏を差し出した。彼女がくれたものとは別の──私が渡した安物の絆創膏。
「森さんは忘れてしまっているかもしれませんが、私、本当はあの日、死のうと思ってたんです」
あの日。それがいつのことだったか思い出せない。けれど、なぜか、駅のホームで座り込んでいた彼女のことが想像できた。
「就活で失敗ばかりして、こんな毎日を過ごすのが嫌になって……でも内定をもらわないと終わらないから必死で耐えてきて。でも、ふっと電池が切れたみたいに、もう心がしんどすぎて、辛くなっちゃって。そんなとき、森さんが声をかけてくれたんです」
──大丈夫ですか。私は、そう言った気がする。
「まさか、私が今から死のうなんて思っていないような顔でした。それもそうですよね、ただ地べたに座り込んでる変な人で、ほかの人たちは見て見ぬふりだったり、遠目で様子を見てたりで、私なんかこの世界にいるのかいないのか、よくわからない存在で」
──もしかして靴擦れですか。そう、続けた気がする。
「靴擦れじゃないけど、死にたいんですとは言えなかったから、気付いたら頷いてました。どこも痛かったわけじゃなかったんですけど、でも、なんかどうしようもなく泣きたくて」
──絆創膏貼るといいですよ。知ってたらすみません。そう、言ったような気もする。
「それからリップクリームの話をしてくれたんです。塗るといいですよって。全然、安いやつでいいですからって。さすがに自分のを差し出すのは遠慮してくれたんですよね、自分で足に使ってるものだから。せめてもの気持ちで絆創膏を渡してくれたのかなと思ったら、なんかその優しさで、死にたかった気持ちが少し和らぎました」
──就活ですか。そう言った。
「就活ってきついですよね、辛いですよねってそのあと話してくれて。でも、どうにかなりますよって森さんが言ってくれたんです。今のところ内定ゼロですけど、なんとかやってますって笑いながら話してくれて。失敗の話とかいろいろしてくれて」
でも、それは。
「嘘でしたよね、あの失敗の話。少し前にネットで見た失敗談と似たようなものばかりで。だけど、私を励まそうとしてくれているのはわかって、うれしかったんです。それが嘘でも、私にとっては、生きるために必要な嘘でした。立ち上がるために大事なことだったんです」
そんなつもりじゃなかった。私は、麻月さんの名前や、その出来事すら忘れてしまっているような人間だ。
「嘘をつくことが、いいって言いたいわけじゃないんですけど……ただ、森さんの嘘が、悪いものばかりじゃなかったって知ってるんです。だから、森さんの悪いところだけを責めたくない。……私だって失敗ばかりです。高校時代なんて、もう思い出すだけで死にたいです。なんであんなことできてたんだろうって思うようなことをたくさんしてきて、変わりたい気持ちだけはずっとあって。でも、そういうところを含めて自分で、どこまでいっても間違いだらけの人生かもしれないけど、そういうのを抱えながら、私はこの絆創膏と生きていきたいです」
たかが、と思っていたその絆創膏が、誰かにとっては大事なものになっていて。少なくとも麻月さんにとって、私の嘘は傷つけられたものではないと言ってくれて。そういう優しさが、今はどうしようもなく泣きそうになる。
「話してくれませんか? 森さんに何があって、こういうことをすることになったのか」
聞かれて、私は素直に打ち明けるつもりでいたことが不思議だった。こんなの、ずっと黙っておこうと思っていたのに。
十五分の休憩が与えられ、私たちはそれぞれの時間を過ごしていた。残り数分といったところでお手洗いに立ち、人事部の人たちが集まる部屋の前をわざと通った。「内定枠は一人にしましょう」そう聞こえて、はっとした。全員が受かるわけではない。
廊下に落ちていたビニール袋に気付いたのはこのときだった。私の前に誰かいた。かさり、と音がすることで中にいた人たちに勘付かれた。「誰かに聞かれたんじゃないか」という声に、すぐさま真逆にあったトイレまでダッシュで向かった。すぐに隠れ、そこから廊下を覗いてみると、香田さんが慌てたように走っていったのが見えた。その様子を見て、これは本当なんだと思った。
それからは、とにかく自分が生き残れるようになればいいと思った。
ここで受かりたいというよりも、もう二度と就活はしたくないという思いのほうが強かった。また最初から、振り出しになることだけは避けたかった。そのためには、四人を蹴落とす必要がある。
四人の秘密を握ることは困難を極めた。当然、あの短時間で全員分の過去を調べ上げることなどできるはずもない。
メールが届いたのはそのときだった。
SNSのDM。相手は捨て垢のようだった。全員分の秘密を知りたくないですか。一番最初にそう書かれていた。そのあとは、告発した通りの内容が続いていた。
とにかく時間がなかった。これを使うことが罠なんじゃないかと思わないわけでもなかった。それでも、私は秘密を使うことを選んだ。もし、一週間、一か月と時間があればこのメールは無視していたかもしれない。
時間がないことをカバーするには、やはりこれを使うしかなかった。
このゲームが始まったとき、私は奇妙な安堵感を覚えたんだと思う。ルールはシンプル。誰かを欺き、他人を犠牲にして、自分だけが勝ち残ればいい。就職活動みたいに、自分の価値を証明しなければならない競争じゃない。むしろ、他人の弱点を突いて、自分が優位に立てる競争だった。
このゲームなら、私でも勝てるかもしれない。そう思った。
最初は軽い気持ちだった。匿名で誰かの秘密を暴くなんて、どうせ大したことじゃないと思ってた。みんな隠し事の一つや二つ、あるものだと思っていたから。ちょっとした秘密を暴露して、少しだけ優位に立てればいい。それだけで、私の不安が少しでも和らぐなら、やる価値があると思った。
でも、気づいたら私はその快感に溺れていた。他人の秘密を知り、それを暴くことで、彼らの動揺や恐怖を見るのが楽しくて仕方なかった。私が見下していた優秀な人たちが、私の手のひらの上で踊らされる。その瞬間だけ、私は彼らよりも優位に立てた気がした。
最初に鬼塚くんのラクロス部の過去を暴いたとき、彼の焦った顔を見て、私は確信した。誰でも、どんなに立派な人間でも、過去には触れられたくない秘密がある。それを暴けば、誰でも動揺する。
次は花屋さん。SNSで人気を博していた彼女の転落ぶりは凄まじかった。探せばぼろぼろと秘密が出てきそうだったし、何より、花屋さんに勝てたと思ってしまった。
花屋さんのような人でも秘密はある。何も持っていない私のほうがマシなのではないかと思うほどに。
次にターゲットにしたのは長谷川くんだった。彼は冷静沈着で、いつも論理的に物事を処理するタイプだった。でも、彼にも弱点があった。動揺するかと思っていた反応は違ったけれど、やはりこの人も完璧ではなかった。それはそれで安心できた。
誰も完璧じゃない。みんな何かを隠している。
麻月さんのNPO活動に関する告発文が出たときも、彼女は戸惑っていた。彼女の活動に軽蔑するような内容が含まれていたと知られたとき、周囲の冷たい視線に晒されていたのがわかった。この場にいる誰もが彼女を信じていた分、その裏切りはより大きな衝撃を与えた。
みんな、隠してることがある。それが暴かれるのが怖い。
そうして、おどろくほど順調に進んでいった。正直、鬼塚くんだけの秘密を使うつもりだった。全員分を使うことは気が引けた。彼には申し訳ないけど、犠牲になってもらおう。そこで場が荒れてくれたらいいと思っていた。
けれど、花屋さんまで、長谷川くんまでと、どんどん欲が出てしまった。最終的に全員分の告発をすることは想定していなかった。
あの秘密を送ってきたのは、ここにいる誰かだとは思っていたけど、誰なのかは最後までわからなかった。ただ、ひとつだけ言えるのは、私が残れる選択はないということ。
今どんなことを考えているんだろう。自分の罪と、これからどう向き合っていくのだろう。
「あのさ」口を開いたのは花屋さんだった。「ずっと思ってるっていうか、考えてることがあって」
彼女は少し言いずらそうな表情を浮かべたあと、申し訳なさそうに私を見た。
「今回の犯人、森さんだったんじゃないかなって思ってるの」
「……え?」
突然落とされた爆弾に、まともに息が吸えなかった。
今、犯人と言われたのだろうか。
冗談を言われているのかと思ったが、この空気で言われるような内容でもない。リアクションが取れなかった。ずいぶんと間抜けな顔をしていたと思う。花屋さんは、まだ私を見ている。鬼塚くんも長谷川くんも私を見ている。少し遅れて、麻月さんも私を見た。ワンテンポ遅れて花屋さんの声が届いていたのかもしれない。
そんなことを冷静に思いながら、変に発言をしないようにした。
「正直、どこからが森さんの仕業かわからないんだけど」
発言権を持つ人の力とは強い。まるでそれが全て真実のように聞こえてしまう。いいな、私にもこういう力があったらよかったのに。
足が痛い。そうだ、靴擦れ。あれ、ずっと治らないんだよなあ。もう履きたくないと思うのに、まるでパンプスの呪いでもかかったようにこの痛みを我慢しなければならない。
「プリンターは、森さんだったんじゃないかなって」
「どうして……私が」
「一番最初にプリンターを見たからだよ」
この人は、本当によく周りを見ている。
「誤作動があったとき、私はどこから音が出たのかすぐにはわからなかった。プリンターだって知ったのは鬼塚くんが教えてくれたけど、それより前に森さんはプリンターを見てたよね」
「……いや、あの音はわかるよ」
「そうかもしれない。あれはプリンターだって、すぐに判断できた人もいる。だから森さんはそうだったんだって思うようにしてたの。だけど、スマホで操作できたのは、やっぱり森さんだけなんだよ」
「言いがかりだよ、そんなの」
「森さん以外が、圏外だったとしても?」
反論しようとしたけれど、すぐには出ていかなかった。
なぜ、こんなことを言われているのだろう。
「鬼塚くんのスマホが圏外だったって話があったよね。あのときは、もう私も圏外だったの。電波があるって嘘をついたのは、香田さんにそうお願いをされていたからだよ」
香田さん。お願い。私が知らないところで、何が交わされていたのだろうか。
「長谷川くんも同じ。私たちがお願いされたのは、一番最初の十五分休憩のとき。廊下で香田さんに呼び止められて、そう答えるように指示を受けたの。どうしてだったのかはゲームが始まるまではわからなかったけど、私たち三人は麻月さんと森さんを疑ってた」
あのときから、香田さんによる計画は始まっていた──?
「だけど途中で、麻月さんから圏外の話が出た。あのタイミングで圏外だってことは、あとは森さんからの発言を待つしかないって思っていたけど、唯一、圏外にならなかったんじゃない?」
スマホを取り出し、確認することが最善なのだろう。けれど、そうできなかった。
「……確信が持ててたわけじゃなかった。特定の人間のスマホを圏外にできるのか、それを調べたくてもスマホが使えないし」
「待って。花屋さんはスマホが使えていたよね? 私たちにフォロワー数がわかるアカウントのページを見せてくれて」
「あれはスクショだよ。リアルタイムのものじゃない」
「……いやいや」
でも、それ以上はなにも出てこなかった。
「だから何って話かもしれない。森さんだけが圏外じゃないから、犯人にしようと思ってるわけでもない。ただ、それ以外でも引っかかったことはあったの」
もう顔が上げられない。立ち振る舞いの正解が見つからない。
「森さんって、何もかもが嘘だよね?」
──嘘。
「情報として正しいのは、名前ぐらいなんじゃないかな。そもそも、森果歩って人間、ちゃんと実在してるよね?」
なんでこんなことになってるんだっけ。
私って、ちゃんとここにいるよね?
「森さんって、本当に私たちと同じ就活生?」
疑いの目が鋭く向けられていた。花屋さんだけではなく、鬼塚くんと長谷川くん、それから麻月さん。
「私たちに話してくれたガクチカ、あれって森さんの経験ではないでしょ」
私の嘘。
それはどこから始まっているんだろう。
少なくとも、就活において、本当の自分なんてどこにもいなかった。
「だって、森さんが話してくれた内容、そっくりそのまま私の友達だったから」
「え」
「似てるどころの話じゃない。個人的にどう思っていたか、それさえも全く同じなんて、そんなの偶然にしては怖いよ」
これまでいくつもの面接を通ってきた。
その度に、他人のガクチカを盗んできた。面接官が食いついたり、好感度を見せていたりすれば、次の面接で使った。私の学生時代、ただただ与えられた授業を受けるだけの日々で、頑張ったことなんてなにもなかったから。
人よりも優れているところもなければ、誇れるような話もない。
私は、ただこの歳になるまで生きていきたような人間で、こういう場で話せるようなものなんて何ひとつ持ち合わせてはないんだから。それなら、嘘で自分を作っていくしかない。他人の話を盗むしかない。
「どうしてそんなことしたの? 全部嘘なんでしょ?」
「……嘘をつくことって、そんな悪いこと?」
ここは、そういう場でしょう?
本音で話してる人なんていない。
働きたくもないのに「ここで働きたいです」と自信満々に語って。
別に第一志望でもないのに「ここ以外考えられません」みたいに偽って。
ただ内定が欲しい。それだけのために、就活は存在しているように思えて仕方がない。
本当の自分をさらけ出して戦っているなんて、一体どれだけの割合でいるというのだろう。どう考えても、そんな人間は存在しないはずだ。
就活は戦争で、他人を蹴落としながら勝ち進んでいかなければならない。
常に選ばれなければいけない。
評価をされ、お祈りメールがくれば自分の存在価値を否定されたような気分になり、それでもまたボロボロになりながら立ち向かっていく。
価値のない自分という人間を、価値のある自分にしていく作業。
それが、そんなに悪いことだろうか。
花屋さんは左右に首を振った。
「嘘をついたことを責めてるんじゃない。私も嘘ついてたし。でも、ゼロからイチにするのはよくないと思う。それに、私がわからなかったら、そのまま突き通すつもりだったよね?」
嘘だった。他人の時間だった。それが、一体なんだと言うのだろう。
「イチを膨らませるのはいいと思う。でも、ゼロをイチにするって結構罪なことだと思うし、まして赤の他人の経験だとしたら、それは立派な罪だよ」
「罪?」
「森さんは経験してないでしょ? 人の経験を奪ったらだめだよ」
そうすることでしか、勝ちあがれなかった私は、どうしたらよかったのだろうか。
「嘘を評価されて、嬉しいの?」
「嬉しくないよ。でも、しょうがないじゃん」
開き直っていくしか、私は自分が保てなかった。
どう考えても、私が悪いことはわかって、正しいか正しくないかで言えば、それはハッキリと正しくないと判断ができる。それでも、本当の自分なんて一体どこにいた?
「そうやって嘘で固めて、他人を蹴落としていくのは楽しかった?」
「あの……本当に森さんが犯人なんですか?」麻月さんは信じられないと言いたげに問いかけた。誰に求めているのかわからないが、少なくとも私本人に向けられたものではない。
ほかの誰かに「違うよ」と言ってほしかったのかもしれない。私が言う「違う」と、他人が言う「違う」には大きな差がある。信憑性の問題だ。私の話ではあるのに、私の意見はどうでもいい。黙っていれば、長谷川くんがすっと息を吸った。
「そうなんじゃないですか。ほかにいなさそうですし」
「今までの話を聞いてたら、そうなんだろうな」確信はないけど、と鬼塚くんが続けた。
ここにいる全員、私が犯人だと思っている。
それなら、もうそれでいい。
真実がどうだとか、そんなことを話すつもりはない。
だって、半分は本当だ。
でも半分でも、当てはまることがあれば、それはもう全部なのと一緒。
「人の秘密を暴くってスリルがあって面白いと思う」花屋さんは、もう親しみのある笑みを向けてはくれなかった。代わりに、冷たく鋭い瞳がこちらを見据えている。視線が突き刺さる。「しかも匿名だったらなおさら」
「……どうして、こんなことを思いついたんですか?」麻月さんが私を不安そうに見つめる。
「どうしてって、納得してもらえるような答えはないよ」
「納得できなくても、理解は……したいです」
「それは麻月さんのエゴだよ。そこに巻き込まないでほしい」
「巻き込まないでって……森さんがやったことは、誰かが傷つくことで、それこそ森さんのゲームに私たちは巻き込まれているんですよ」
それもそうか。「ごめんなさい」と素直に謝れば「そいうことじゃなくて」と麻月さんはもどかしそうに前髪を触った。意思の通じない何かを前にしているような顔だ。
「でも」これ以上は言わないほうがいいとわかっていても、ずっと我慢していたことがポロポロと溢れていく。「誰かが傷つくようなことをしたつもりはないよ」
「はあ?」
鬼塚くんが飛び掛かってきそうだったけれど、不思議と怖いとは思わなかった。
「結果的に誰かが傷ついたかもしれない。でも、それは私が直接傷つけたわけじゃないよ。私がやったのは、ただみんなの秘密を明るみに出しただけ。みんな、自分の過去を隠してただけでしょ? それで誰が傷ついたの? 自分だけなんじゃないの? 自分がしてきた行動を隠していたのは、自分たち自身の選択だったんだよ。私はただ、みんなが作った仮面を壊しただけなんだから」
「そんな言い訳、誰が信じるんだよ!」鬼塚くんは私に向かって一歩踏み出してきたが、その瞬間、花屋さんが彼の腕を掴んだ。
「やめて、鬼塚くん」花屋さんの声は低く、冷静だった。彼女はゆっくりと鬼塚くんの目を見つめながら、さらに言葉を続けた。「このままじゃ、彼女の思うつぼだよ」
「……どういうことだよ」鬼塚くんは苛立ちを隠せないまま、花屋さんの手を振りほどいた。
「森さんは最初からこれを計画していた。私たちの弱点を見つけて、それを利用することで、自分が優位に立てるようにしていたんだよ。だから、今こうして私たちを挑発してる」花屋さんの目は鋭く光っていた。「私たちが感情的になって、彼女を責めれば責めるほど、彼女の思い通りになる。今だって、鬼塚くんは彼女のペースに乗せられている」
「まあ、たしかに花屋さんの言う通りかもしれないね。人の秘密を暴くって、スリルがあって面白いとは感じてた」
「でも、どうしてそんなことをするんですか?」麻月さんが震える声で問いかけた。「どうして、そんなに人の秘密を暴いて楽しんでるんですか?」
「楽しんでる……?」私は少し考え込んだ。「そう見えるかもしれないけど、私がやってるのはただのゲームじゃなかった。私にとって必要なこと。みんなが自分の秘密を隠して、それを守ろうと必死になるのを見ると……なんていうか、安心した」
「……それ、どういう意味ですか?」麻月さんが戸惑いながら尋ねた。
「簡単だよ」私は答えた。「私はずっと、何も持たずに生きてきた。誇れることも、就活で勝ち抜いていくための存在価値も。だから、みんなみたいに優秀そうな人が、秘密を持っていることがわかれば、安心できた。それさえ壊してしまえば、何も持っていない私だけが、勝ち残れる世界があるって思えたから」
その言葉に、場の空気は一層重くなった。誰もが自分の胸の内に秘めていたものを思い出し、そしてその秘密が暴かれる恐怖を感じていた。
「本当に森さんが仕組んだんですか? この状況……匿名の他己紹介だっていう仕掛けも」
「さすがにそれは違うって言いたいけど、信じてもらえるかは別の話だよね」でも、と笑みがこぼれる。「本当はみんな、誰かの秘密を知りたいと思ってたはずだよ」
私と目を合わせてくれる人は誰もいない。
「プリンターから自分の秘密じゃない、他人の秘密が出てくることを楽しみにしていた人もいるんじゃないかな。むしろ、ほとんどそうだったんじゃない?」
「お前と一緒にすんなよ」
鬼塚くんの声には、いつになく強い怒りがこもっていた。彼の目はまっすぐ私を見据え、冷たい怒りが渦巻いているのが感じ取れた。でも、その一言にはどこか焦りも含まれているように思えた。自分の内心が図星を突かれたのではないかという不安が、彼を動揺させているのだろう。
「本当に? 鬼塚くんだって、誰かの秘密を知りたいと思ったこと、少しでもあったんじゃないかな。誰かの失敗や、隠していたことが暴かれる瞬間を見て、ちょっとだけ安心してたとか」
「そんなこと、あるわけないだろ!」鬼塚くんは声を荒げたけど、その表情はどこか引きつっているようにも見えた。
「でも、もしそれが本当だったとしても、恥ずかしいことじゃないよ。だって、みんなそうなんだから。人の秘密を知りたがるのは、自然なこと。自分の方が少し優位に立てるような気がして安心できるし、他人のミスが自分の苦しさを和らげてくれるんだよ」
その瞬間、誰もが黙り込んだ。部屋の中には不安と沈黙が漂い、誰も私と目を合わせようとしない。プリンターから出てくる他人の秘密を心のどこかで期待していた自分に、今気づいたのかもしれない。
「それが……人間だよね?」私は続けた。「誰かの過ちや秘密を知ることで、自分が少しだけ安心する。自分も同じような失敗をするかもしれないけど、他人が先に失敗してくれたら、なんだかホッとするでしょ?」
麻月さんが震える声で口を開いた。「でも、それを利用するのは間違ってる……」
「間違ってる?」私はその言葉に少し笑ってしまった。「じゃあ、何が正しいんだろう? 私はただ、みんなが見て見ぬふりをしていた事実を表に出しただけ。誰もが心の中で思っていたことを、私は行動に移しただけだよ」
麻月さんは答えることができず、ただ俯いていた。彼女の指先が震えているのが見えた。
「結局さ、みんな自分のことしか考えてないんだよ。隠し続けていたものを、ただ外に出しただけ。それがたまたま、みんなの秘密だったってだけ」
私はそう言いながら、部屋の中を見渡した。鬼塚くんも、花屋さんも、麻月さんも、長谷川くんも、視線を伏せていた。それが、私にとっての答えだった。
「私のことを責めたいなら、ちゃんと私を見て言えばいいのに。自分も同じことを考えてたから、何も言い返せない?」
「黙れ……」鬼塚くんが低い声で呟いた。「黙れって言ったんだよ!」鬼塚くんが叫び、私に向かって一歩踏み出した。「お前が何を言っても、俺たちはお前とは違う!」
それはそうだろう。彼と私ではまるで違う。
「たとえ俺が一瞬でも、誰かの秘密を知りたいと思ったとしても、それは間違いだった。俺はそんな自分を恥じるよ。でも、お前みたいにそれを利用して人を傷つけることはしない!」
人を傷つける。私の行為は本当に人を傷つけてた?
「俺たちは、お前と同じじゃない」鬼塚くんは強く言い放った。「お前が他人の秘密を暴いて楽しんでいる間にも、俺たちは違う道を選ぶ。人を信じて、信頼し合って生きていくんだ」
「こんなことが起きて、それでも人を信じるの?」
「信じるよ。お前みたいな人間ばかりじゃない」
「ねえ、偽善者ごっこはやめようよ。みんな、自分の中で押し殺していた感情や秘密を、私が引き出されて、信用なんてできないでしょ。自分の秘密がバレたことで、パニックになったのはみんな自身のせいでもあるんだから、私だけを責める理由にもならない」
「言い訳にしか聞こえないですね」と、長谷川くんが静かに言った。「確かに、誰だって完璧なわけではないですし、隠したいことの一つや二つはあるでしょう。それでも、わざわざそれを暴いて他人を傷つける権利なんて、誰にもないんですよ」
「権利?」私は小さく笑った。「そもそも、みんなが正しいことだけをして生きてきたわけじゃないよね。だからこそ隠してたんじゃない? 私はただ、その隠された部分を引き出しただけ。それが事実なら、責めるべきは自分たちの過去でしょ?」
「そんなの詭弁だ」鬼塚くんが低く言った。「お前は俺たちを操って、自分だけが楽しんでたんだろ」
「そう思うなら、それでもいい。でも、私がしたことって、ただ他人の嘘を暴いただけ。私の行動で傷ついたなら、それはその嘘をついた自分のせいじゃない?」
「お前、ほんとにそう思ってんのか?」鬼塚くんの声は、驚きと怒りが入り混じったものだった。「本気で自分が正しいと思ってんのか?」
私は少し黙って、彼を見つめた。彼らの反応は予想通りだったけど、鬼塚くんの問いに答える言葉は、すぐには出てこなかった。
「正しいかどうか……それは、私にもわからないよ」と、私はやっと口を開いた。
「森さんってさ、嘘をつきすぎて、もう本当の自分がわからなくなっちゃってるんじゃない?」花屋さんに聞かれ、首を傾げた。
「……わからなくなってる?」私は静かに繰り返した。その言葉が妙に胸に響いた。「そんなこと、ないよ」
「そうかな」花屋さんは一歩近づき、私を真っ直ぐに見つめた。「ずっと周りの嘘を暴いて、それを楽しんでた。でも、それって結局、森さん自身も何かから逃げてるんじゃないの? 自分が何者なのか、どうしたいのかってことを」
「それ、まるで私が自分のことを見失ってるみたいに聞こえるね」
「だって、そうじゃない?」花屋さんの声は揺るがない。「最初は嘘を暴くことで自分を守ってたんだろうけど、気づいたら、その嘘に自分も飲み込まれてるんじゃないかって思う。嘘をつきすぎて、本当の森さんがどこにいるのか、もう誰にもわからないっていうか……森さん自身にも、わからないんじゃないの?」
「そんなことないよ」私は繰り返したが、自分の声がどこか揺れているのがわかった。こんなことは予想していなかったはずなのに、彼女の言葉が心に引っかかって離れない。
「私は、自分が何をしているかちゃんとわかってる。私が暴いたのは、みんなの嘘であって、私自身は嘘なんか」
「本当に?」花屋さんが優しく言葉を挟んだ。「森さんは、自分が一番嘘をついてるってこと、わかってるんだよね。他人の嘘を暴いてきたけど、本当は自分のことを隠すために、ずっと嘘をついてきたんだよ」
「それは……違うよ」私はかろうじて言ったが、自分でも説得力がないことを感じていた。「私はただ、みんなが隠してる真実を暴いただけで……」
「でも、なんでそんなことをしたんですか?」麻月さんが、小さな声で続けた。「森さんは自分が傷つくのが怖くて、みんなの秘密を暴くことで自分を守って」
「……違う」私は首を振った。「私はみんなを守ろうとしてたんだよ。みんなが嘘をついて生きてるから、その嘘が暴かれたら傷つくってわかってた。だから今のうちに……」
「本当にそうですか?」長谷川くんが口を挟んだ。「それなら、なんでこんなにみんなを傷つけたんです。誰も守られてなんかいない。むしろ、傷つけられただけじゃないですか」
「それは……」
私は言葉に詰まった。何を言っても、彼らの視線が痛いほど鋭く感じられる。私は本当に、自分のことを守ろうとしていただけなのだろうか。
「自分の中で本当の自分がわからなくなって、他人を傷つけることでしか自分を保てなくなってたんじゃない?」花屋さんの声が、再び鋭く私に突き刺さる。
「……わからない」私はついに口を開いた。「本当に、わからない」
その言葉が、自分でも信じられないほど本音だった。ずっと、嘘をつき続けてきた私。それがどれほど自分に影響していたのか、気づかないふりをしてきたのかもしれない。
「わからないよ。ねえ、長谷川くん」
彼の名前を呼ぶと、その肩がびくりと震えた。
「麻月さんのときに言ってたことをそのままお返しするけど、私って最初から犯人だって思ってた? こんなことする人間だってわかってた?」
「……わからないですよ、そんなこと」
「それなら、裏切られることもあって当然で、他人を蹴落とすのも当然でしょう」
「だから人を信用しないのか。言っとくけど、そういうお前の勝手な信念で、人を傷つけていいわけがないからな」鬼塚くんの指摘は鋭かった。
「どういうこと?」
「お前が他人を信用しなくても、誰かはお前のことを信用する。こんなことがあっても、それでもお前のことを信用している人間はいるかもしれない」
「いないでしょ、そんなの」
「──います」
そう、か細く聞こえた。誰、なんて思うはずもない。
「私は、信じたいです。森さんのこと、上辺だけじゃなくて、ちゃんと」
「……なんで? 私、こんなことしたのに、信じてもらえるような人間じゃないよ」
「人間だから、です」
麻月さんは、頼りない声で、それでも力いっぱい私に何かを伝えようとしてくれていた。
「人間だから、失敗するし、人間だから他人を傷つけます。でも、生きてたら当たり前のことじゃないですか。そんなことを経験していない人なんて誰もいません」
「……麻月さんは、私のせいで秘密が暴かれたんだよ?」
「だからなんですか。私は、森さんに傷つけられてばかりでもないです。助けてもらったこともあります」
「助けたって……私、嘘ばかりついてきたのに」
「その嘘に、助けてもらったんですよ」麻月さんは、私に一枚の絆創膏を差し出した。彼女がくれたものとは別の──私が渡した安物の絆創膏。
「森さんは忘れてしまっているかもしれませんが、私、本当はあの日、死のうと思ってたんです」
あの日。それがいつのことだったか思い出せない。けれど、なぜか、駅のホームで座り込んでいた彼女のことが想像できた。
「就活で失敗ばかりして、こんな毎日を過ごすのが嫌になって……でも内定をもらわないと終わらないから必死で耐えてきて。でも、ふっと電池が切れたみたいに、もう心がしんどすぎて、辛くなっちゃって。そんなとき、森さんが声をかけてくれたんです」
──大丈夫ですか。私は、そう言った気がする。
「まさか、私が今から死のうなんて思っていないような顔でした。それもそうですよね、ただ地べたに座り込んでる変な人で、ほかの人たちは見て見ぬふりだったり、遠目で様子を見てたりで、私なんかこの世界にいるのかいないのか、よくわからない存在で」
──もしかして靴擦れですか。そう、続けた気がする。
「靴擦れじゃないけど、死にたいんですとは言えなかったから、気付いたら頷いてました。どこも痛かったわけじゃなかったんですけど、でも、なんかどうしようもなく泣きたくて」
──絆創膏貼るといいですよ。知ってたらすみません。そう、言ったような気もする。
「それからリップクリームの話をしてくれたんです。塗るといいですよって。全然、安いやつでいいですからって。さすがに自分のを差し出すのは遠慮してくれたんですよね、自分で足に使ってるものだから。せめてもの気持ちで絆創膏を渡してくれたのかなと思ったら、なんかその優しさで、死にたかった気持ちが少し和らぎました」
──就活ですか。そう言った。
「就活ってきついですよね、辛いですよねってそのあと話してくれて。でも、どうにかなりますよって森さんが言ってくれたんです。今のところ内定ゼロですけど、なんとかやってますって笑いながら話してくれて。失敗の話とかいろいろしてくれて」
でも、それは。
「嘘でしたよね、あの失敗の話。少し前にネットで見た失敗談と似たようなものばかりで。だけど、私を励まそうとしてくれているのはわかって、うれしかったんです。それが嘘でも、私にとっては、生きるために必要な嘘でした。立ち上がるために大事なことだったんです」
そんなつもりじゃなかった。私は、麻月さんの名前や、その出来事すら忘れてしまっているような人間だ。
「嘘をつくことが、いいって言いたいわけじゃないんですけど……ただ、森さんの嘘が、悪いものばかりじゃなかったって知ってるんです。だから、森さんの悪いところだけを責めたくない。……私だって失敗ばかりです。高校時代なんて、もう思い出すだけで死にたいです。なんであんなことできてたんだろうって思うようなことをたくさんしてきて、変わりたい気持ちだけはずっとあって。でも、そういうところを含めて自分で、どこまでいっても間違いだらけの人生かもしれないけど、そういうのを抱えながら、私はこの絆創膏と生きていきたいです」
たかが、と思っていたその絆創膏が、誰かにとっては大事なものになっていて。少なくとも麻月さんにとって、私の嘘は傷つけられたものではないと言ってくれて。そういう優しさが、今はどうしようもなく泣きそうになる。
「話してくれませんか? 森さんに何があって、こういうことをすることになったのか」
聞かれて、私は素直に打ち明けるつもりでいたことが不思議だった。こんなの、ずっと黙っておこうと思っていたのに。
十五分の休憩が与えられ、私たちはそれぞれの時間を過ごしていた。残り数分といったところでお手洗いに立ち、人事部の人たちが集まる部屋の前をわざと通った。「内定枠は一人にしましょう」そう聞こえて、はっとした。全員が受かるわけではない。
廊下に落ちていたビニール袋に気付いたのはこのときだった。私の前に誰かいた。かさり、と音がすることで中にいた人たちに勘付かれた。「誰かに聞かれたんじゃないか」という声に、すぐさま真逆にあったトイレまでダッシュで向かった。すぐに隠れ、そこから廊下を覗いてみると、香田さんが慌てたように走っていったのが見えた。その様子を見て、これは本当なんだと思った。
それからは、とにかく自分が生き残れるようになればいいと思った。
ここで受かりたいというよりも、もう二度と就活はしたくないという思いのほうが強かった。また最初から、振り出しになることだけは避けたかった。そのためには、四人を蹴落とす必要がある。
四人の秘密を握ることは困難を極めた。当然、あの短時間で全員分の過去を調べ上げることなどできるはずもない。
メールが届いたのはそのときだった。
SNSのDM。相手は捨て垢のようだった。全員分の秘密を知りたくないですか。一番最初にそう書かれていた。そのあとは、告発した通りの内容が続いていた。
とにかく時間がなかった。これを使うことが罠なんじゃないかと思わないわけでもなかった。それでも、私は秘密を使うことを選んだ。もし、一週間、一か月と時間があればこのメールは無視していたかもしれない。
時間がないことをカバーするには、やはりこれを使うしかなかった。
このゲームが始まったとき、私は奇妙な安堵感を覚えたんだと思う。ルールはシンプル。誰かを欺き、他人を犠牲にして、自分だけが勝ち残ればいい。就職活動みたいに、自分の価値を証明しなければならない競争じゃない。むしろ、他人の弱点を突いて、自分が優位に立てる競争だった。
このゲームなら、私でも勝てるかもしれない。そう思った。
最初は軽い気持ちだった。匿名で誰かの秘密を暴くなんて、どうせ大したことじゃないと思ってた。みんな隠し事の一つや二つ、あるものだと思っていたから。ちょっとした秘密を暴露して、少しだけ優位に立てればいい。それだけで、私の不安が少しでも和らぐなら、やる価値があると思った。
でも、気づいたら私はその快感に溺れていた。他人の秘密を知り、それを暴くことで、彼らの動揺や恐怖を見るのが楽しくて仕方なかった。私が見下していた優秀な人たちが、私の手のひらの上で踊らされる。その瞬間だけ、私は彼らよりも優位に立てた気がした。
最初に鬼塚くんのラクロス部の過去を暴いたとき、彼の焦った顔を見て、私は確信した。誰でも、どんなに立派な人間でも、過去には触れられたくない秘密がある。それを暴けば、誰でも動揺する。
次は花屋さん。SNSで人気を博していた彼女の転落ぶりは凄まじかった。探せばぼろぼろと秘密が出てきそうだったし、何より、花屋さんに勝てたと思ってしまった。
花屋さんのような人でも秘密はある。何も持っていない私のほうがマシなのではないかと思うほどに。
次にターゲットにしたのは長谷川くんだった。彼は冷静沈着で、いつも論理的に物事を処理するタイプだった。でも、彼にも弱点があった。動揺するかと思っていた反応は違ったけれど、やはりこの人も完璧ではなかった。それはそれで安心できた。
誰も完璧じゃない。みんな何かを隠している。
麻月さんのNPO活動に関する告発文が出たときも、彼女は戸惑っていた。彼女の活動に軽蔑するような内容が含まれていたと知られたとき、周囲の冷たい視線に晒されていたのがわかった。この場にいる誰もが彼女を信じていた分、その裏切りはより大きな衝撃を与えた。
みんな、隠してることがある。それが暴かれるのが怖い。
そうして、おどろくほど順調に進んでいった。正直、鬼塚くんだけの秘密を使うつもりだった。全員分を使うことは気が引けた。彼には申し訳ないけど、犠牲になってもらおう。そこで場が荒れてくれたらいいと思っていた。
けれど、花屋さんまで、長谷川くんまでと、どんどん欲が出てしまった。最終的に全員分の告発をすることは想定していなかった。
あの秘密を送ってきたのは、ここにいる誰かだとは思っていたけど、誰なのかは最後までわからなかった。ただ、ひとつだけ言えるのは、私が残れる選択はないということ。