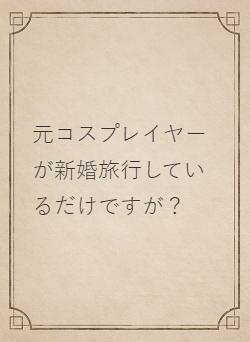・
・【11 アホみたいだ】
・
来る時は前触れも無い。
自殺室に一人の女子生徒が入ってきて、早々こんなことを叫んだ。
「やっと死ねる! やったぁっ! 死の臭気吸って死ぬぞぉ!」
僕と同様、噂を真に受けている生徒だ。
自殺室は部屋中が血みどろ、生臭い匂いが充満し、入ったと同時に死の臭気に当てられて死んでしまうという噂を。
さらに言えば僕と、そして溝渕さんとも一緒だ。
彼女は死にたい人だ。
やっぱり僕の時と同様、自殺室は真っ白い部屋のままだった。
本当にこの人も死にたいんだ。
死にたくない人は死んで、死にたい人は死ねない部屋、自殺室。
さて、これからどうするか。
僕は溝渕さんのほうを見た。
すると溝渕さんはいつものようにアゴのあたりを触りながら、
《後から自殺室に変化が起きるかもしれないから、もう少し様子を見ていよう》
ちなみに僕と溝渕さんの会話は、こっちで念じない限り、彼女には聞こえないし、僕たちの姿も見えない。
前回ちょっとイレギュラーがあったけども、今回はどうやら大丈夫らしい。
いや大丈夫という言い方もおかしいけども。
そんな自分の脳内のことよりも、僕は溝渕さんに聞きたいことを聞くことにした。
《それって、もしかすると僕の時も溝渕さんはそうしていたということですか? 変わるかもしれないから》
《あぁ、そうだ。部屋はたまに途中で変化することがあるんだ。だから最初は様子を見るといい》
僕と溝渕さんの会話は聞こえない。
彼女は一人で喋っている。
「あれぇっ? 全然クサくないばかりか、むしろ良い香りぐらいな感じだぁっ? どういうことだろう?」
小首を傾げながら、キョロキョロしている。
でも焦っている感じはしない。
なんとなく全てを受け入れて、じゃあどうするかということを建設的に考えているような表情だ。
《何だか僕の時と似ていますね》
《そうだね、似ているね》
僕は溝渕さんのGOを待つ。
溝渕さんのほうがずっと詳しいので、自ら動いたりはしない。
自ら動いたところで好転するとは思えないから。
「舌でも噛みきるか……いやゴムか! 急にアタシの舌がゴムになったわ! もはや冬用のタイヤだわっ!」
何か一人でツッコんでいる……お笑いが好きな女子なのかな。
ノリがちょっとおかしい。
でも死にたいんだろう。
死にたい人間がこんなノリで生きている?
ちょっと考えられないけども、この自殺室という空間への信用はそれなりにあるので、バグとかではないのだろうな。
《これはもう出ていいみたいだね》
溝渕さんがそう言ったので、僕は頷き、溝渕さんと共に念じて、彼女の前に現れた。
「死神か! 男二人の死神か! 珍しいな! 鎌持て! 鎌ぁっ!」
そう何かハイテンションに、むしろちょっと嬉しそうにツッコんできた彼女。
何が楽しいんだろうと思いつつ、僕は喋りだした。
「いや僕たちは死神じゃないんだ。この自殺室で死にたくても死ねない人間なんだ。一応生きている」
溝渕さんもそれに同調しながら、
「この自殺室は死にたくない人は自殺して、死にたい人は死ねない部屋なんだ。君の言動をさっきから見ていたんだが、死にたい人だろう? そんな感覚じゃ、一生死ねないよ」
この言葉に対してどんな反応を見せるのかと思っていると、彼女は凍えるようなポーズをしながら、
「マジかっ? 何それ寒っ! そのギャグ寒っ! 冬用のタイヤじゃん! 寒すぎて冬用のタイヤじゃん!」
と言った。
何なんだこの人と思いながら、僕はちょっと呆れながら、
「いや本当にそうで、ギャグじゃないんだ……あと、何か、君、すごい饒舌だね……」
すると彼女は、口から声を出していることをアピールする手の動きをしながら、
「そうそう口が滑って滑ってたまらないよ! ……って! こちとら冬用のタイヤだから滑らないんだよ!」
と何だかノリツッコミをしているような感じ。
僕は何だか嫌な汗が止まらない。
背筋に汗が伝った。
溝渕さんは耳のあたりを掻きながら、
「死にたいのに、そんなに明るい人って珍しいな」
それに対して彼女はやたらデカい声で、
「死は解放! 現世からの解放! だから尊いことじゃん! あー! 死にてぇっ!」
あまりの変な”アレ”さに戸惑っていると、彼女は僕のほうを見て、
「オマエもそう思うだろ! なぁっ!」
と言ってきたので、目を逸らした。
するとすぐさま彼女は場所を動いてきて、僕の目の前に立ってきて、
「聞いているんだよ! 答えろよ! そういう無視とか絶対ダメだからな! 信号無視禁止!」
「いや君は信号じゃないでしょ。信号だったら無視しないけども」
「私は一番元気な! ヒマワリのような黄色信号!」
「確かにヒマワリは黄色だけども、信号にとっての黄色は一番元気とは言い難いよ」
思ったことをついそのまま口にすると、彼女は嬉しそうに手を叩きながら、
「良いツッコミじゃん! じゃあこっからアタシがボケね! 君はツッコミ! よろしくなっ!」
「そんな漫才の役目みたいなことを言われても。僕は普通に喋るだけだから」
「それでいい! 普通が一番ツッコミに向いているからなぁ! あとそこのあんちゃんは客な! オーラが無いから!」
そう言いながら溝渕さんのことを指差した彼女。
いやいや溝渕さんこそすごい人なんだけども。
この自殺室の役目を全て網羅している、オーラが一番ある大人の人なんだけども。
まあそういうことを説明するかと思って口を開いたところで、それを追い越すように彼女が、
「はいどうも! よろしくお願いします!」
と言い始めたので、すぐさま僕は、
「だからそんな漫才のスタートみたいなことを言われてもっ」
と言うと、彼女は親指を立ててグッドマークを出しながら、
「いいね! そういうツッコミじゃんじゃん頂戴!」
そう快活に笑った。
この人、本当に死にたいのか?
死にたいという気持ちと笑いって真逆なんじゃないか?
もしそれが同居しているということは、本当に狂っている人だ。
狂っているからこそ裁きようの無いという感じだ。
この人はマジで早く死んでくれないかな。
どんな悪いことをしてきた人よりも、何だかそう思ってしまう自分がいて。
もう嫌だ。
こんな人とずっと一緒なんて本当に無理だ。
死にたい。
あぁ、ダメだ。またこの言葉が僕を押し潰してきた。あの鉄槌のように、ゆっくり、ゆっくり、僕の脳内を圧迫していく、ダメだ、もうダメだ、死にたい、ちょっと思うことは、ちょっとだけ思うことは、人のことを死んでしまえと思ってしまったことへの自己嫌悪だ、光莉を助けたかったと思って、でもそれ以外の人は死んでも良くてなんて、光莉が喜ぶはずがないのに、ダメだ、死んでしまえばいいんだ、僕なんてすぐに死んでしまえばいいんだ、死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいいし死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいいし、僕なんて、君なんて言うの? ん?
「君なんて言うの? 自己紹介もそう言えばまだだったね! こりゃ失礼! 漫才はここでブレーキ!」
話し掛けられていたのか……そうか、えっと、答えないと……と自分の言葉を探っていると、それより先に彼女が、
「いや何か疲れているみたいだし、すぐに喋りださなくてもいいよ。アタシはかなりの美人だから待てるほう!」
かなりの美人だから待てるほう。
よく分かんないけども、まあ本当に待っているみたいだし、いいか。
でもそれならそっちから自己紹介してもいいのに。
何だか自分が決めた道は曲げない人みたいだ。
こっち側が、僕たち側が先に自己紹介するもんと決めつけているみたいだ。
一体何なんだ、この人。
まあこういう人なんだと思って、もう認めるしかない。
喧嘩しても多分仕方ないし、一緒に居づらくなるだけだから。
よしっ、平穏な思考回路が戻ってきた。
これなら大丈夫だ。
喋りだそう。
「……これから君とは長い付き合いになりそうだね。僕は田中信太、よろしく」
僕がそう言うと、それに続けて溝渕さんも、
「俺は溝渕弥勒だ、よろしく」
それに対して彼女は何か考えるような表情をしながら、
「田中信太……溝渕弥勒……」
えっ、もしやこの人、溝渕さんの過去を知っている……?
僕は少々ドキドキしながら彼女の次の言葉を待っていると、
「いや溝渕弥勒は全く知らないけども、田中信太ってSクラスなのに自殺室行きになった田中信太ぁっ? はー! アンタ死にたかったんだ! だからわざとテストで手を抜いたんだぁっ! アタシと一緒じゃん!」
「あっ、溝渕さんのことは知らないんだ……」
「いやもう全く知らない! 誰このあんちゃん!」
そう言って何故か少し軽蔑しているような”しっしっ”というアクションをとった彼女。
いやそういう動きは冗談でも失礼だろ、と思っていると、溝渕さんは冷静に、
「まあ俺のことは置いといて、君もわざとテストで手を抜いたわけか」
確かにそのことは気になる。
彼女の返答は、
「そうそう! 何かもういいかなって思って! 未練なんもねぇし! あっ、アタシは深山陽菜(はるな)、陽菜でいいよ! 信太! ……えっと、まあ、あんちゃんを呼び捨てで呼ぶほどあれじゃないんで、弥勒さんね! これでいいでしょ!」
そう言って、えっへんというような偉そうな顔をした陽菜。
腰に手を当てて、お腹を前に突きだして、動きがいちいちコミカルだ。
でもやっぱり違和感がある。
まずそれを聞いてみなければ、
「陽菜は死ねないと分かっても、そんなに落ち込んだりしないんだね」
それに対しては間髪入れず、
「いや落ち込んでるよ! タイヤを溝にハメて動かなくなった人くらい落ち込んでるよ! でももうこうなったらしょうがねぇじゃん! だからよろしくってことよ!」
そう言ってコロコロと鈴の音のように笑う陽菜。
何でこんな明るい人が死のうと思ったのだろうか。
いやでも、もしかしたらこんな明るい人ほど、この学校では死にたくなるのかもしれない。
僕は違うけども。
陽菜は大笑いしながら、
「そっか、そっかぁっ! 死ねねぇのか! あーぁ! どうなんだろうなぁっ! あー、死にてぇっ!」
本当に一体どうなるのだろうか。
未来が見えないし、もう未来なんて無い状態だし。
死ねる時って、くるのかな……。
それに。
「死ねる術の開発とかしねぇとダメかなぁっ!」
こんなテンションがおかしな人と一緒にいるなんて苦痛だ。
より死にたくて、死ねないよ。
「なぁっ!」
そう言ってまた僕のほうを見てきた陽菜。
あんまり僕に関わらないでほしい。
「信太! 聞いてるのか! なぁっ、みたいな文末の時は同い年のオマエに言ってるんだぞ!」
「いやでも、うん、あの、この空間は、馴れ合っても仕方無いからさ、それぞれで生きていこうよ」
「何だよ! 死にてぇ仲間じゃん! どうせなら一緒に死のうぜ! 同い年なんだしな!」
こんな口の悪い女子とは一緒に死にたくない、あっ、今の死にたくないという気持ちで死ねるか?
いや全然何もこの自殺室に変化は無いか、そりゃそうか、この程度じゃダメか。
でも。
「じゃあどっちが死ねる術を先に開発できるか勝負な!」
そう叫んで口角を上げた陽菜。
……僕は結構この人と一緒に死にたくない気持ちあるんだけどな。
「曲げたことの無い方向に指を曲げてみるか!」
僕があんなことを考えている時も陽菜は何かすごいバカげたことを言っている。
というかそもそもこの人、この学校に入学できるくらいの頭を持ち合わせているのか?
とか思ったその時だった。
自殺室に、白い空間に大きな音が響いた。
《《《ボキィッ!》》》
僕はすぐさま音の鳴ったほうを見ると、指が曲がってはいけない方向に曲がった陽菜がいた。
「あっ、折れた」
そう言った陽菜。
僕は正直ここにきて一番ゾォワァッとしてしまった。
躊躇無く自分の指を折るなんて誰もできなかったこと。
いやまあ指が折れたところで死ねないだろうから、試していなかったことでもあるし、奈々江さんは最終的に自ら自殺できた。
が、奈々江さんもそんなすぐに、といった感じでは無かった。
でもこの陽菜は何の確証も無い状態で、すぐさま自分の指を曲げたのだ。
なんという唐突感。
この向こう見ずなところが、完全に死にたいヤツのソレだと思ってしまった。
僕は陽菜のほうをワナワナしながら、震えて見ていると、指が何事も無かったように、平常時の位置に戻り、陽菜は、
「おっ、勝手に治った。面白い空間じゃん。指折るボケし放題じゃん。何か痛みも無かったし」
と言い放ったので、僕はつい声を出した。
「何言っているんだよ……指折るボケとか止めなよ……何しているんだよ、陽菜は……」
「ほら、いろいろ試さないと。死ねるかもしれないじゃん。基本的にはトライ&エラーだろ」
「そうかもしれないけども、この空間はずっと死にたい人は死ねなくて」
「まあ弥勒さんを見れば分かるよ、多分ここの生徒だったんでしょ。でもあれだな、成長はするんだな」
そう言われた時に僕はハッとした。
確かに溝渕さんは成長している。つまり老いている。
全く何も変わらない空間ではないんだ。
なんでこのことに気付かなかったのだろうか。
いやいや気付いたところで何もすることはない。
変わらないんだ。
この空間は何をしても変わらないんだ。
もう諦めないといけないんだ。
でもこの彼女は、陽菜は、全て新鮮な思いで一からいろんなことをし始めているし、多分これからもしていくに違いない。
その度にきっと、僕は、諦めたほうがいいと思うんだろうな。
もう全てを受け入れて、死ぬ時を待つしかない、と。
でも溝渕さんのことを見ていると、やっぱり死ぬ時なんて来ないのかな。
またダメだ、死にたい思いが止まらなくなってきた、死にたいんだ、止まらないんだ、止まらないのに止まっているんだ、ずっと停滞しているんだ、手痛いんだ、死にたいんだ、死ねないんだ、死にたい、ダメだ、また死にたいだけが襲ってきた、いくら襲われても死ねないのに、死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたいぃぃいいいいいいいいい?
「またその顔になった。つまんないから。つまんないともっと死にたくなるだろ。それじゃダメなんじゃないのか?」
気付いた時には陽菜が僕の頬を思い切りつまんで引っ張っていた。
というか今は触れられる状態なのか。
いやまあこうなってしまった同士はそもそも触れ合えたのかもしれないけども、そう言えば僕、溝渕さんに意図的に触ろうとしたことないな。
僕と陽菜は目が合ったタイミングで、陽菜は僕の頬を引っ張ることを止めた。
陽菜は長い溜息をしてから、
「死ねない同士楽しくしようぜ! ほら! 楽しくしたら生きたいと思うかもしれないだろ! そうしたら死ねるじゃん! ラッキー!」
そう言って笑った陽菜。
確かにそうか、確かにそうかもしれない。
楽しければ生きたくなって死ねるかもしれない。
じゃあ、
「分かった。できるだけ陽菜の言うことは無視しないようにするよ。少なくても陽菜が楽しくなるように努力する。そうしたら陽菜だけは死ねるかもしれないもんね」
「そこはwin-winでいこうぜ! 信太も楽しくなって死ぬんだぜ! あと観客の弥勒さん! アンタのことも笑わせてやるからよぉ!」
そう言って溝渕さんのほうを見ると、溝渕さんは体育座りしながらも、こっちを見て手を振りながら、
「期待しているよ」
と言葉短くそう言った。
でも不快に思っているといった感じでは無かった。
むしろちょっとした変化を受け入れ、楽しみにしているようだった。
そうだ、溝渕さんだってそうなんだ。
この状況を楽しめば死ねるんだ。
そうだ、だからだ。
だから溝渕さんは死神役なんてやっているんだ。
穏やかに人が死ぬところを見ることができれば、死にたい気持ちを抑えられるかもしれない、と。
溝渕さんも陽菜も、平穏に生きたいと思っているんだ。
なんとか変化を望んでいるんだ。
でも僕はすぐに考えてしまうんだ。
変わろうとしても今さら変われないって。
どこか無理だと蓋をしてしまうんだ。
無理だ。
無理なんだ。
もう無理なんだ。
無理難題なんだ。
そもそも溝渕さんの死神役もそんなうまくいっていないじゃないか。
僕がいるせいか?
僕がいるせいで逆に悪いほうへ入っていっているのか?
いやいや溝渕さんもここまでお兄さんになるほど、ここにいるじゃないか。
僕のせいじゃない僕のせいじゃない、あぁ、ダメだ、こう考えたらまた堕ちてしまう。
何なんだ、僕は。
一体どうすればいいんだ。
どうしても無駄なんだろうな。
・【11 アホみたいだ】
・
来る時は前触れも無い。
自殺室に一人の女子生徒が入ってきて、早々こんなことを叫んだ。
「やっと死ねる! やったぁっ! 死の臭気吸って死ぬぞぉ!」
僕と同様、噂を真に受けている生徒だ。
自殺室は部屋中が血みどろ、生臭い匂いが充満し、入ったと同時に死の臭気に当てられて死んでしまうという噂を。
さらに言えば僕と、そして溝渕さんとも一緒だ。
彼女は死にたい人だ。
やっぱり僕の時と同様、自殺室は真っ白い部屋のままだった。
本当にこの人も死にたいんだ。
死にたくない人は死んで、死にたい人は死ねない部屋、自殺室。
さて、これからどうするか。
僕は溝渕さんのほうを見た。
すると溝渕さんはいつものようにアゴのあたりを触りながら、
《後から自殺室に変化が起きるかもしれないから、もう少し様子を見ていよう》
ちなみに僕と溝渕さんの会話は、こっちで念じない限り、彼女には聞こえないし、僕たちの姿も見えない。
前回ちょっとイレギュラーがあったけども、今回はどうやら大丈夫らしい。
いや大丈夫という言い方もおかしいけども。
そんな自分の脳内のことよりも、僕は溝渕さんに聞きたいことを聞くことにした。
《それって、もしかすると僕の時も溝渕さんはそうしていたということですか? 変わるかもしれないから》
《あぁ、そうだ。部屋はたまに途中で変化することがあるんだ。だから最初は様子を見るといい》
僕と溝渕さんの会話は聞こえない。
彼女は一人で喋っている。
「あれぇっ? 全然クサくないばかりか、むしろ良い香りぐらいな感じだぁっ? どういうことだろう?」
小首を傾げながら、キョロキョロしている。
でも焦っている感じはしない。
なんとなく全てを受け入れて、じゃあどうするかということを建設的に考えているような表情だ。
《何だか僕の時と似ていますね》
《そうだね、似ているね》
僕は溝渕さんのGOを待つ。
溝渕さんのほうがずっと詳しいので、自ら動いたりはしない。
自ら動いたところで好転するとは思えないから。
「舌でも噛みきるか……いやゴムか! 急にアタシの舌がゴムになったわ! もはや冬用のタイヤだわっ!」
何か一人でツッコんでいる……お笑いが好きな女子なのかな。
ノリがちょっとおかしい。
でも死にたいんだろう。
死にたい人間がこんなノリで生きている?
ちょっと考えられないけども、この自殺室という空間への信用はそれなりにあるので、バグとかではないのだろうな。
《これはもう出ていいみたいだね》
溝渕さんがそう言ったので、僕は頷き、溝渕さんと共に念じて、彼女の前に現れた。
「死神か! 男二人の死神か! 珍しいな! 鎌持て! 鎌ぁっ!」
そう何かハイテンションに、むしろちょっと嬉しそうにツッコんできた彼女。
何が楽しいんだろうと思いつつ、僕は喋りだした。
「いや僕たちは死神じゃないんだ。この自殺室で死にたくても死ねない人間なんだ。一応生きている」
溝渕さんもそれに同調しながら、
「この自殺室は死にたくない人は自殺して、死にたい人は死ねない部屋なんだ。君の言動をさっきから見ていたんだが、死にたい人だろう? そんな感覚じゃ、一生死ねないよ」
この言葉に対してどんな反応を見せるのかと思っていると、彼女は凍えるようなポーズをしながら、
「マジかっ? 何それ寒っ! そのギャグ寒っ! 冬用のタイヤじゃん! 寒すぎて冬用のタイヤじゃん!」
と言った。
何なんだこの人と思いながら、僕はちょっと呆れながら、
「いや本当にそうで、ギャグじゃないんだ……あと、何か、君、すごい饒舌だね……」
すると彼女は、口から声を出していることをアピールする手の動きをしながら、
「そうそう口が滑って滑ってたまらないよ! ……って! こちとら冬用のタイヤだから滑らないんだよ!」
と何だかノリツッコミをしているような感じ。
僕は何だか嫌な汗が止まらない。
背筋に汗が伝った。
溝渕さんは耳のあたりを掻きながら、
「死にたいのに、そんなに明るい人って珍しいな」
それに対して彼女はやたらデカい声で、
「死は解放! 現世からの解放! だから尊いことじゃん! あー! 死にてぇっ!」
あまりの変な”アレ”さに戸惑っていると、彼女は僕のほうを見て、
「オマエもそう思うだろ! なぁっ!」
と言ってきたので、目を逸らした。
するとすぐさま彼女は場所を動いてきて、僕の目の前に立ってきて、
「聞いているんだよ! 答えろよ! そういう無視とか絶対ダメだからな! 信号無視禁止!」
「いや君は信号じゃないでしょ。信号だったら無視しないけども」
「私は一番元気な! ヒマワリのような黄色信号!」
「確かにヒマワリは黄色だけども、信号にとっての黄色は一番元気とは言い難いよ」
思ったことをついそのまま口にすると、彼女は嬉しそうに手を叩きながら、
「良いツッコミじゃん! じゃあこっからアタシがボケね! 君はツッコミ! よろしくなっ!」
「そんな漫才の役目みたいなことを言われても。僕は普通に喋るだけだから」
「それでいい! 普通が一番ツッコミに向いているからなぁ! あとそこのあんちゃんは客な! オーラが無いから!」
そう言いながら溝渕さんのことを指差した彼女。
いやいや溝渕さんこそすごい人なんだけども。
この自殺室の役目を全て網羅している、オーラが一番ある大人の人なんだけども。
まあそういうことを説明するかと思って口を開いたところで、それを追い越すように彼女が、
「はいどうも! よろしくお願いします!」
と言い始めたので、すぐさま僕は、
「だからそんな漫才のスタートみたいなことを言われてもっ」
と言うと、彼女は親指を立ててグッドマークを出しながら、
「いいね! そういうツッコミじゃんじゃん頂戴!」
そう快活に笑った。
この人、本当に死にたいのか?
死にたいという気持ちと笑いって真逆なんじゃないか?
もしそれが同居しているということは、本当に狂っている人だ。
狂っているからこそ裁きようの無いという感じだ。
この人はマジで早く死んでくれないかな。
どんな悪いことをしてきた人よりも、何だかそう思ってしまう自分がいて。
もう嫌だ。
こんな人とずっと一緒なんて本当に無理だ。
死にたい。
あぁ、ダメだ。またこの言葉が僕を押し潰してきた。あの鉄槌のように、ゆっくり、ゆっくり、僕の脳内を圧迫していく、ダメだ、もうダメだ、死にたい、ちょっと思うことは、ちょっとだけ思うことは、人のことを死んでしまえと思ってしまったことへの自己嫌悪だ、光莉を助けたかったと思って、でもそれ以外の人は死んでも良くてなんて、光莉が喜ぶはずがないのに、ダメだ、死んでしまえばいいんだ、僕なんてすぐに死んでしまえばいいんだ、死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいいし死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいい死ねばいいし、僕なんて、君なんて言うの? ん?
「君なんて言うの? 自己紹介もそう言えばまだだったね! こりゃ失礼! 漫才はここでブレーキ!」
話し掛けられていたのか……そうか、えっと、答えないと……と自分の言葉を探っていると、それより先に彼女が、
「いや何か疲れているみたいだし、すぐに喋りださなくてもいいよ。アタシはかなりの美人だから待てるほう!」
かなりの美人だから待てるほう。
よく分かんないけども、まあ本当に待っているみたいだし、いいか。
でもそれならそっちから自己紹介してもいいのに。
何だか自分が決めた道は曲げない人みたいだ。
こっち側が、僕たち側が先に自己紹介するもんと決めつけているみたいだ。
一体何なんだ、この人。
まあこういう人なんだと思って、もう認めるしかない。
喧嘩しても多分仕方ないし、一緒に居づらくなるだけだから。
よしっ、平穏な思考回路が戻ってきた。
これなら大丈夫だ。
喋りだそう。
「……これから君とは長い付き合いになりそうだね。僕は田中信太、よろしく」
僕がそう言うと、それに続けて溝渕さんも、
「俺は溝渕弥勒だ、よろしく」
それに対して彼女は何か考えるような表情をしながら、
「田中信太……溝渕弥勒……」
えっ、もしやこの人、溝渕さんの過去を知っている……?
僕は少々ドキドキしながら彼女の次の言葉を待っていると、
「いや溝渕弥勒は全く知らないけども、田中信太ってSクラスなのに自殺室行きになった田中信太ぁっ? はー! アンタ死にたかったんだ! だからわざとテストで手を抜いたんだぁっ! アタシと一緒じゃん!」
「あっ、溝渕さんのことは知らないんだ……」
「いやもう全く知らない! 誰このあんちゃん!」
そう言って何故か少し軽蔑しているような”しっしっ”というアクションをとった彼女。
いやそういう動きは冗談でも失礼だろ、と思っていると、溝渕さんは冷静に、
「まあ俺のことは置いといて、君もわざとテストで手を抜いたわけか」
確かにそのことは気になる。
彼女の返答は、
「そうそう! 何かもういいかなって思って! 未練なんもねぇし! あっ、アタシは深山陽菜(はるな)、陽菜でいいよ! 信太! ……えっと、まあ、あんちゃんを呼び捨てで呼ぶほどあれじゃないんで、弥勒さんね! これでいいでしょ!」
そう言って、えっへんというような偉そうな顔をした陽菜。
腰に手を当てて、お腹を前に突きだして、動きがいちいちコミカルだ。
でもやっぱり違和感がある。
まずそれを聞いてみなければ、
「陽菜は死ねないと分かっても、そんなに落ち込んだりしないんだね」
それに対しては間髪入れず、
「いや落ち込んでるよ! タイヤを溝にハメて動かなくなった人くらい落ち込んでるよ! でももうこうなったらしょうがねぇじゃん! だからよろしくってことよ!」
そう言ってコロコロと鈴の音のように笑う陽菜。
何でこんな明るい人が死のうと思ったのだろうか。
いやでも、もしかしたらこんな明るい人ほど、この学校では死にたくなるのかもしれない。
僕は違うけども。
陽菜は大笑いしながら、
「そっか、そっかぁっ! 死ねねぇのか! あーぁ! どうなんだろうなぁっ! あー、死にてぇっ!」
本当に一体どうなるのだろうか。
未来が見えないし、もう未来なんて無い状態だし。
死ねる時って、くるのかな……。
それに。
「死ねる術の開発とかしねぇとダメかなぁっ!」
こんなテンションがおかしな人と一緒にいるなんて苦痛だ。
より死にたくて、死ねないよ。
「なぁっ!」
そう言ってまた僕のほうを見てきた陽菜。
あんまり僕に関わらないでほしい。
「信太! 聞いてるのか! なぁっ、みたいな文末の時は同い年のオマエに言ってるんだぞ!」
「いやでも、うん、あの、この空間は、馴れ合っても仕方無いからさ、それぞれで生きていこうよ」
「何だよ! 死にてぇ仲間じゃん! どうせなら一緒に死のうぜ! 同い年なんだしな!」
こんな口の悪い女子とは一緒に死にたくない、あっ、今の死にたくないという気持ちで死ねるか?
いや全然何もこの自殺室に変化は無いか、そりゃそうか、この程度じゃダメか。
でも。
「じゃあどっちが死ねる術を先に開発できるか勝負な!」
そう叫んで口角を上げた陽菜。
……僕は結構この人と一緒に死にたくない気持ちあるんだけどな。
「曲げたことの無い方向に指を曲げてみるか!」
僕があんなことを考えている時も陽菜は何かすごいバカげたことを言っている。
というかそもそもこの人、この学校に入学できるくらいの頭を持ち合わせているのか?
とか思ったその時だった。
自殺室に、白い空間に大きな音が響いた。
《《《ボキィッ!》》》
僕はすぐさま音の鳴ったほうを見ると、指が曲がってはいけない方向に曲がった陽菜がいた。
「あっ、折れた」
そう言った陽菜。
僕は正直ここにきて一番ゾォワァッとしてしまった。
躊躇無く自分の指を折るなんて誰もできなかったこと。
いやまあ指が折れたところで死ねないだろうから、試していなかったことでもあるし、奈々江さんは最終的に自ら自殺できた。
が、奈々江さんもそんなすぐに、といった感じでは無かった。
でもこの陽菜は何の確証も無い状態で、すぐさま自分の指を曲げたのだ。
なんという唐突感。
この向こう見ずなところが、完全に死にたいヤツのソレだと思ってしまった。
僕は陽菜のほうをワナワナしながら、震えて見ていると、指が何事も無かったように、平常時の位置に戻り、陽菜は、
「おっ、勝手に治った。面白い空間じゃん。指折るボケし放題じゃん。何か痛みも無かったし」
と言い放ったので、僕はつい声を出した。
「何言っているんだよ……指折るボケとか止めなよ……何しているんだよ、陽菜は……」
「ほら、いろいろ試さないと。死ねるかもしれないじゃん。基本的にはトライ&エラーだろ」
「そうかもしれないけども、この空間はずっと死にたい人は死ねなくて」
「まあ弥勒さんを見れば分かるよ、多分ここの生徒だったんでしょ。でもあれだな、成長はするんだな」
そう言われた時に僕はハッとした。
確かに溝渕さんは成長している。つまり老いている。
全く何も変わらない空間ではないんだ。
なんでこのことに気付かなかったのだろうか。
いやいや気付いたところで何もすることはない。
変わらないんだ。
この空間は何をしても変わらないんだ。
もう諦めないといけないんだ。
でもこの彼女は、陽菜は、全て新鮮な思いで一からいろんなことをし始めているし、多分これからもしていくに違いない。
その度にきっと、僕は、諦めたほうがいいと思うんだろうな。
もう全てを受け入れて、死ぬ時を待つしかない、と。
でも溝渕さんのことを見ていると、やっぱり死ぬ時なんて来ないのかな。
またダメだ、死にたい思いが止まらなくなってきた、死にたいんだ、止まらないんだ、止まらないのに止まっているんだ、ずっと停滞しているんだ、手痛いんだ、死にたいんだ、死ねないんだ、死にたい、ダメだ、また死にたいだけが襲ってきた、いくら襲われても死ねないのに、死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたいぃぃいいいいいいいいい?
「またその顔になった。つまんないから。つまんないともっと死にたくなるだろ。それじゃダメなんじゃないのか?」
気付いた時には陽菜が僕の頬を思い切りつまんで引っ張っていた。
というか今は触れられる状態なのか。
いやまあこうなってしまった同士はそもそも触れ合えたのかもしれないけども、そう言えば僕、溝渕さんに意図的に触ろうとしたことないな。
僕と陽菜は目が合ったタイミングで、陽菜は僕の頬を引っ張ることを止めた。
陽菜は長い溜息をしてから、
「死ねない同士楽しくしようぜ! ほら! 楽しくしたら生きたいと思うかもしれないだろ! そうしたら死ねるじゃん! ラッキー!」
そう言って笑った陽菜。
確かにそうか、確かにそうかもしれない。
楽しければ生きたくなって死ねるかもしれない。
じゃあ、
「分かった。できるだけ陽菜の言うことは無視しないようにするよ。少なくても陽菜が楽しくなるように努力する。そうしたら陽菜だけは死ねるかもしれないもんね」
「そこはwin-winでいこうぜ! 信太も楽しくなって死ぬんだぜ! あと観客の弥勒さん! アンタのことも笑わせてやるからよぉ!」
そう言って溝渕さんのほうを見ると、溝渕さんは体育座りしながらも、こっちを見て手を振りながら、
「期待しているよ」
と言葉短くそう言った。
でも不快に思っているといった感じでは無かった。
むしろちょっとした変化を受け入れ、楽しみにしているようだった。
そうだ、溝渕さんだってそうなんだ。
この状況を楽しめば死ねるんだ。
そうだ、だからだ。
だから溝渕さんは死神役なんてやっているんだ。
穏やかに人が死ぬところを見ることができれば、死にたい気持ちを抑えられるかもしれない、と。
溝渕さんも陽菜も、平穏に生きたいと思っているんだ。
なんとか変化を望んでいるんだ。
でも僕はすぐに考えてしまうんだ。
変わろうとしても今さら変われないって。
どこか無理だと蓋をしてしまうんだ。
無理だ。
無理なんだ。
もう無理なんだ。
無理難題なんだ。
そもそも溝渕さんの死神役もそんなうまくいっていないじゃないか。
僕がいるせいか?
僕がいるせいで逆に悪いほうへ入っていっているのか?
いやいや溝渕さんもここまでお兄さんになるほど、ここにいるじゃないか。
僕のせいじゃない僕のせいじゃない、あぁ、ダメだ、こう考えたらまた堕ちてしまう。
何なんだ、僕は。
一体どうすればいいんだ。
どうしても無駄なんだろうな。