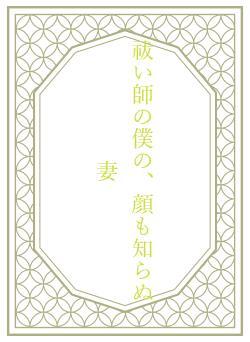「…そういえば、どうして俺がイチくんを“イチくん”って呼ぶと思う?」
「え、苗字も名前も、イチって読めるからじゃないんですか?」
「まぁ、それもあるけど…」
先輩は不意に僕の膝裏に右腕、腰に左手を添えて僕を抱き上げる。
急なことで、「わぁっ!?」なんて素っ頓狂な声を出してしまった。
先輩はその声に笑みを深めて、そのまま元々僕が居たベッドに座って、僕を膝の上に乗せる。
先輩よりは背も小さいし、太っているというわけではないけれど、この歳になってこうも軽々と持ち上げられると、ちょっと複雑な気分だ。
そんな僕をよそに、いつの間にかおでこを合わせられて、ゼロ距離で目線を交わす。
「イチっていうのは、1番の1。俺にとってイチくんは、1番の奇跡だから。…だから君をイチくんって呼ぶたびに俺は、君に告白してるつもりだったんだ」
「っ、え…」
先輩の言葉を少しづつ理解していくのに合わせて、顔が熱くなるのが分かる。
「そ、そんな、こと言われたら…」
これから先、イチくんと呼ばれる度に意識してしまうではないか。
「ず、ずるい…っ」
「ふふっ、うん。俺はね、イチくんのことが大好きだから、これらもずっと君をイチくんって呼び続けるよ」
ーーどんなに時が経とうと、1番の奇跡が変わることはないから。