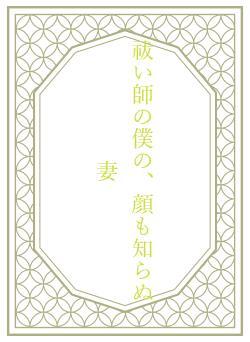誰もいないと思っていたのにまさか他でもない先輩に見られていたのかと、とても恥ずかしい。
けど、僕にとってはなんてことはない所も、波瀬先輩には良く見えていたのなら、それは素直に嬉しい。
「まだあるよ。
何もないところでよく躓いたりする意外とドジな所も、その後誰も見てなかったか確認して恥ずかしそうにしてるのも好きだし。
花が枯れた時の悲しんだ顔は、俺まで胸が痛くなって、全力で抱きしめたいって思った」
「も、もういいです…っ」
「ダメだよ。好きがちゃんと伝わるまでは、やめないよ俺は」
「もう、十分伝わりましたからっ」
本当に止めないといつまでも続きそうで、自分に幾つも言えるほどの魅力はないのは分かっているが、先輩の目があまりにも本気だから。
いつの間にかベッドから立ち上がり、数歩歩いて未だベッドに座る僕の前に片膝をついた先輩は上目遣いで僕を見る。
先輩の目に映る僕は真っ赤で、泣きそうな顔をしているに違いない。
「ねぇ、俺はずっとイチくんが好きだったんだよ。それ、ちゃんと伝わった?」
「つ、伝わりました…」
「なら、イチくんの答えを教えて…?」