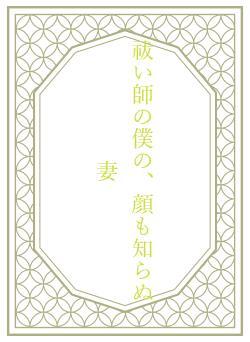途中から、先輩の言葉から、目から、何も逸らせなくなってしまった。
一つ一つが、自分に突き刺さるようで。
痛いのに、心が軽くなっていくような感覚。
「俺がイチくんに出会って恋をしたのも、今この瞬間も好きになり続けてるのも、奇跡だと俺は勝手に思ってるよ」
「っ…、なんでっ、なんで僕なんですか…?」
言っている内に段々と声が小さくなっていく。
今起こっていることが信じられなくて、でも信じたくて。
実際、好きになられるような要素も、場面もなかったはずのに。
ただ時々、校内で会って少し言葉を交わして、からかわれて、それだけだったのに。
「最初はただの興味だったんだけどね。自分と同じ匂いがするのに、それを無理やり抑え込んで息がし辛そうな感じがして。
でも無意識に目で追っていくうちに、誰も見ていないところで花に話しかけながら、楽しそうに水をやるところとか。
綺麗に花が咲いたら、本当に嬉しそうに破顔するところ、
神社の野良猫と毛だらけになりながら遊んでるところ。
そんな顔もするんだって、いつか自分にもそれが向けられたらいいなって思ったんだ」