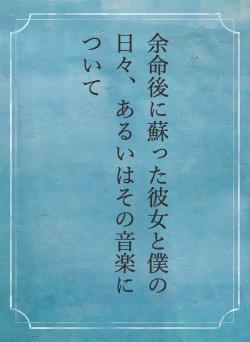双子の妹の夏芽がクリップで留めた紙束を弓ちゃんから貰ってタイトルを読み上げる
『人を 殺さば』。
ぐさり! と
やって みたし
人を ころさば
こころよからん
「これ、なんかいいと思う! ねえ弓ちゃん、これにしたら? 常美もそう思わない?」
二限の終わり、三限の始まる前、夏芽と私は僅かな十分の間でも話したくてこうして羽根虫が蜘蛛の網に絡められるように窓側の弓ちゃんの席に来ていた。書き残された黒板の白い文字を次の数学のために今日の日直が綺麗に消していく。
「そりゃあんたが朗読するならいいかもしれないけど、実際やるのは弓ちゃんだからね」
そう言いながら座る弓ちゃんの反応をそっと伺う。案外と弓ちゃんはこういう過激な方が気に入ったりするのだろうか。
教室の騒がしさに混じって消えてしまいそうな弓ちゃんの声に夏芽と私はきき耳を立てる。
「夏芽ちゃんらしいね」
うーむ、弓ちゃんの人間観が相変わらずわからん。
私は笑うと糸のように細くなるその目を横に見ながら腕を組む。
弓ちゃんとは対照的に妹の声は耳を塞いでいてもきこえてきそうだ。夏芽はプリントアウトされた紙束を捲りながら言った。
「うーむ、なんかこの人暗くない?」
弓ちゃんは夏芽の率直な言葉を優しく包み込むように言う。
「たしかに詩人のなかにはだいぶ欝っぽい感じの人ってたくさんいるけど、この人はどうかなあ。でも、たしかにそういう死を見つめる目線みたいなものはあったのかも。この人の場合、若くして病気になって結局二十九歳で死んじゃったみたいだから。ってこれ先生の受け売りだけど」
「他の作家とかにしないの? このヤギシゲキチで決定?」
弓ちゃんは夏芽の間違いを訂正しなかった。それを優しいと言うのか言わないのかは私にはわからなかった。夏芽サン「シゲキチ」じゃなくて「ジュウキチ」ダヨ。
「うん、やっぱり朔太郎とかは人気があって先輩がやることになってるの。一年は一人一人先生に作家を選ばれてそれをやるの」
「へー、なんかちょっと運動部みたいだね」
「そうかも」
「あ、これなんかよさそう」夏芽がヤギシゲキチを朗読する。『無造作な 雲』という題だ。
無造作な くも、
あのくものあたりへ 死にたい
「シゲキチ、死なないで」
やっぱ暗いわ、この人、と夏芽はやはり正直に呟いた。
ふふ、それは常ちゃんっぽいね。え、どういうこと、弓ちゃん?
「どうかな。どれがいいと思う? ジュウキチは残っている詩集が少ないから選びやすいねって先輩達は言うんだけど、短いのが多くて朗読することも考えたら結構選ぶのが難しくて」
夏芽が『貧しき信徒』のプリントアウトを弓ちゃんの机に返して、もう一束プリントアウトを捲る。そちらは『秋の瞳』という詩集らしい。
「そうだねえ、これなんか一行だけなんだね、『おもひ』か、ふむふむ」
かへるべきである ともおもわれる
「どこにだよ。でもこんな風に一行だけでも詩なんだねえ。なんか短歌とかみたい」
「影響はあるのかもしれないね。ある程度の長さがあるやつもあるんだけど、でもジュウキチは、ただ一言だけ深呼吸するみたいに、自分の奥の何かを見つめて、それが装飾もなく言葉になっているところが私は読んでいて好き。だから朗読のためだけに長いのを選ぶのもどうかなあって」
「飾らない素朴さが良いってことですな、ほう」
そういうことかな。弓ちゃんが照れ臭そうに言う。それをまん丸とした目でパチパチと音をたてるように夏芽が見つめた。
私は改めてプリントアウトを眺める。まだインクの独特な匂いが残っている。私は弓ちゃんに伝えた。
「いいんじゃないかな、短いのでも、かっこいいよ。文芸部は軽音楽部のあとでしょ、激しく盛り上がったあとに弓ちゃんの声で『かへるべきである ともおもわれる』って一言静かな感じで体育館に響いたらなんかいいと思う」
「それでほんとにみんな帰っちゃったりして。文芸部のあとには最後にピアノ部の発表もあるんですけど」
「ピアノ部の発表はそれでいいんじゃない? ダンス部の発表は最初に終わってるしね」
「常ちゃんはバレエ?」
弓ちゃんは私にどこかしら期待を持つようにきいた。
「やるとしたらね。おばあちゃん、来るからね。バレエ以外やったら卒倒しそう」
「そっか、幼稚舎から続けてるって言ってたもんね」
「といっても、文化祭の出演は有志だから私はでないけど」
「え、なんで?」
そこに夏芽がトウっと叫んで弓ちゃんと私の間に手刀を切って割り込んだ。
「ソンナコトヨリお二人サン。待ちにマッタ、テストオワリノ海ノコトナンデスガ」
なんでロボットみたいなの? 弓ちゃんが笑って言う。トクニ意味はアリマセン。
私は二人の会話を眺める。夏芽はバレエの話が嫌いだ。おばあちゃんのことは考えるのも嫌なのだろう。高等部に転入して二ヶ月の弓ちゃんはそれを知らない。二人は嬉しそうに海水浴に持っていくものを相談している。私は二人の話題に入り直そうと身を乗り出すと、黒板の上のスピーカーが三限の開始を教室の喧騒に告げた。
「じゃあ弓ちゃん、絶対ベッドのやつ持ってきてね」
いちばん席が遠い夏芽がそう言って席に帰っていった。「ベッドのやつ」ってなんだろう? そういえば、と最後に私は弓ちゃんに質問をした。弓ちゃんは答える代わりに紙束からプリントアウトを一枚渡してくれた。私が席に着くと同時に葉子先生が入ってきた。危ない、危ない。
「ちゃんと皆さんチャイムが鳴り終わるまでに席に着きましたか。それでは前回の公約数の求め方から始めましょう。公約数の計算は来週の中間テストでは必ず出ますからね」
葉子先生はそう言って黒板に二つの数字の組み合わせを書いていく。私は本人に気づかれないように夏芽を盗み見て、それから弓ちゃんと目を合わせる。夏芽がこの時間だけ大きな目を開いて授業に集中できるのは何も数学だけが得意科目だからというわけだけではない。恋は学業に資するのである。
それから私はさっき弓ちゃんに貰ったプリントアウトを葉子先生に見つからないようにこっそり眺める。
私はきいた。弓ちゃんがいちばん好きなのはこの詩集のなかだとどれなの?
私は右端に書かれたタイトルを目で拾う『あめの 日』。
しろい きのこ
きいろい きのこ
あめの日
しづかな日
きのこ……、たしかに弓ちゃんっぽいかも。私は森の大樹の陰でひっそりと生える濡れた傘に触れるようにその机の下の言葉を指でなぞった。
紗枝はどうしているだろう。
印字された言葉を撫でているとそんなことがなぜか不意に頭にうかんだ。
❋
「それじゃあ二人とも勝手に水着買いに行っちゃダメだからね」
放課後、夏芽は弓ちゃんと私を昇降口の校舎玄関まで見送ると、そう言い残して部活のため隣校舎の音楽室まで走っていった。
なぜあんな落ち着きのない子に育ったのか。私は双子とは何かについて深く考えさせられずにはいられなかった。私は下駄箱から靴を取り出して溜息を吐きながら足を入れた。
痛っ、気づけば自然と口から漏れていた。
「大丈夫?」
弓ちゃんも履き替えて心配そうに私に言った。
「うん、全然、大丈夫」
おばあちゃんにこっそり内緒で買ったスニーカーのせいだった。高等部になってローファーを履くのが自由になり思い切って買ったの だが、インソールがずれて少し痛くなっていた。
「やっぱりバレエやってるとそうなっちゃうの?」
弓ちゃんは鞄からバンソウコウを取り出して渡してくれた。
「ありがとう。ソックスを厚手に変えたら全然大丈夫だと思うから」
私は靴下を捲って貼ると弓ちゃんにお礼を言った。
「これはバレエとは関係ないかな、たぶんふつうに靴擦れ」
「そっか、海行くまでに治るといいね」
暑さに勘違いした初夏の蝉はもう鳴き始めていた。校舎を出ても夏至の太陽はまだ放課後の世界から降りることができず空に釘付けされている。葉桜の木漏れ日を弓ちゃんが愛おしそうに見つめる。私はそんな弓ちゃんを見ていると心が跳ねた。不意に泣きたくなる。
いっそ神様に何もかも正直に打ち明けたい。そんな気分がした。
「常ちゃん、今日レッスンはお休みなの? ダンス部は?」
「レッスンは休み。部活は、今日はいいかな」
ズル休みだ。弓ちゃんはクスクス笑う。
「文芸部も今日は休みだったよね」
うん、と弓ちゃんの声が歌うようにきこえる。私は思い切って弓ちゃんに提案した。
「ねえ弓ちゃん、天国にいちばん近い場所に行かない?」
「天国?」
「うん、ニューカレドニアだよ。神様に会いに行くんだよ」
❋
私は駅前まで来ると目印にしている潰れたタバコ屋さんから路地に入った。そして目当てのビルの裏口まで来ると、外付け非常階段の入り口に架けられた立ち入りを禁ずるためのチェーンをためらわずに下から潜った。
「常ちゃん、勝手に入ったら怒られちゃうよ」
弓ちゃんは慌てて後ろから私の手を引っ張った。
私は弓ちゃんを安心させようと笑いかけた。
「大丈夫、ここ、うちの家のビルだから。駅前のビルはだいたいうちなんだ」
それから弓ちゃんも潜れるようにチェーンを片手で持ち上げた。
一段一段赤錆びている踏み板を音をさせながら上がると、ここも相当古くなったな、と私は思う。
最初に夏芽と勝手に入って、お父さん達に絶対に子供だけで入るなと怒られて、それからまた自分達だけでこっそり入るようになったのはいつだったけ。そういえばお父さんとおばあちゃんは私達を叱ったけど、お母さんは何も言わなかったなあ。まあ、お母さんは私達にはいつもそうだけど。
いいんじゃないですか、お義母さん、夏芽一人だけならピアノを続けても。だから、きっとあのときも援護射撃のつもりなど一切なかったのだろう。単純に言い争う夏芽とおばあちゃんがうるさかっただけだ。その証拠にお母さんは特に考えもせずにこう言ったものだ。バレエの方は常美に続けてもらえばお義母さんの義理は果たせるでしょ。私は階段の最後の一段を踏みつけるようにスニーカーの足を下ろした。
お姉ちゃんはほんとにそれでいいの?
踏み板が鳴る音にあの日リビングに響いた妹の泣き声が私の頭で混じった気がした。
屋上にたどりついた。私はよろよろと屋上の中央に彷徨って大きく仰向けに寝転がった。
高い場所から見える雲は西からの力でゆっくりと移動していった。あんまりにも晴れているものだから、うるせー、晴れてるぞー! と思い切り叫びたいような気持ちがした。気づけば登り疲れた弓ちゃんも隣で仰向けになっている。
このビルの屋上を「ニューカレドニア」と名づけたのは夏芽だった。天国に近いからって。天国は意外と低い場所にあるものだ。
「弓ちゃん、うちの学校は慣れた? 弓ちゃんの中学ってうちの県から遠かったんでしょ? 友達と離れて寂しかったりしない?」
「どうかなあ、私、小学校のころから引っ越し多かったし、前の中学も三年のときに入ったから、卒業って言われてもなんか不思議な感じだったんだよね。私、みんなと仲良くなるまで時間かかるタイプみたいで最後もちょっと時間足りなかったかも」
「そうなんだ」
でも弓ちゃんの声は暗くなかった。むしろ少し弾んでいたかもしれない。私はその理由がわかっていた。弓ちゃん自身はその理由がわかっているのだろうか。
「あ、でも夏芽ちゃんと常ちゃんみたいな子は初めて。二人といるのほんとにたのしい」
夏芽ちゃんは太陽みたいな人だね。
隣の弓ちゃんがどんな表情か私にはわからなかった。きっといつものように目を糸のように笑っているのだと思った。
「あ、常ちゃん見て、月だよ」
お月様は昼でもちゃんといるんだねえ。弓ちゃんはそう言って水色の舞台に夜から紛れ込んだ上弦の星を見つける。あのくものあたりへ、死んでいきたい、か。
私は目を瞑った。少し眠たいような気がした。屋上の風は子守唄だった。私は寝ぼけているように呟いた。
「私、なんだか弓ちゃんといると怖い」
どうして。弓ちゃんの声はすぐ隣にいるのに遠くきこえた。
どこか遠い場所から、でも、すごく近くから。不思議な感じがした。
「中等部のときに紗江って子がいたのね。私達みたいに内部進学せずに県外の高校に行ったんだけど、一緒にバレエのレッスンも受けてたんだ。紗枝は、」
「うん」
弓ちゃんの声もどこか眠そうだった。
「紗江は、」
額に汗が滲んだ。
弓ちゃんは何も言わない、私が話すのを待っている。
紗江は、
紗江は、
私は懸命に彼女を語る言葉を探す。なぜだろう、どうしてだろう。どうしても彼女を弓ちゃんに伝える言葉がなかった。三年間、あれほど話したのに。こんな短い時間で忘れるはずないのに。どうして紗江を語る言葉が出てこないのだろう。
代わりに影のように頭に響くのは卒業舞踏会の前日に教室で言われたことだった。
常美は痛いよ。
どういうこと? 紗江の言っていることの意味がわからなかった。同じ時間を幾度も過ごしたのに私は紗江のことを何もわかっていなかった。最後の最後にそう宣告されたようだった。私は紗江のことがわからなかった。結局その言葉の真意もきけないまま別れてしまった。
私は今日までその言葉の意味をずっと考えていた。でもやっぱりわからなかった。
どうしても紗江について語る言葉がなかった。
それはたまらなく、たまらなく恥ずかしいことのように思えた。代わりに口を衝いて出たのは自分のことだった。
「私、バレエ好きじゃないし、向いてない」
弓ちゃんは何も言わず隣で寝転ぶ私の手を掴んでくれた。握り返すと小さな手はすっぽりと私のなかに収まった。その手を掴んでいると私の意識は懐かしくてここよりももっと大きくて広いところに落ちていくようだった。常ちゃん、私ね、弓ちゃんは落ちていく私に言葉を渡してくれる。
「思い出せなかったり、見失ったりすることはあっても、本当に失くしたりはできないと思うんだ」
それから、私を眠らせるように囁いた。
「海、たのしみだね」
❋
海開きにはまだ一週間だけ早かった。海岸には私達以外誰もいなくて、迎えてくれたのは浜辺のシオマネキだけだった。それでも六月最後の日にして気温は30℃以上、梅雨はとっくに過ぎ去り真夏日だった。
乾いた砂浜から濡れた場所に入ると踵が沈んで靴擦れは少し染みた。親指の間には海水が流れ込んできて私達の足裏を洗う。冷たさに隣の弓ちゃんが目隠しされた箱の中のものを触ったみたいに肩をビクッと震わせて私の二の腕を掴んだ。私達は思わず身を縮めて波打ち際で立ち止まってしまった。打ち寄せる波はそれから光が滑ったようなしゃらしゃらとした音をさせて引いていく。
ひとり前を行っていた夏芽はうっかり氷を呑み込んだ猫みたいにパチッと目を開き硬直していた。それから三秒ほど静止すると、う ああああああ、と叫んで海に駆けた。
「あははは、夏芽ちゃん……」
すると隣の弓ちゃんも何かのスイッチが入ったように、きゃーっと叫んで夏芽のもとに駆け寄っていった。え、どうしたの、二人とも。ちょっと待って私をおいていかないで。
弓ちゃんと私は海面が腰まで浸かる高さにいた夏芽に追い付いて二人で背中からのしかかった。育ち盛りの女子二人の体重を育ち盛りの女子一人で支えきれるわけもなく、育ち盛りの私達三人はそのまま浅い海中に転んだ。海面に顔がつくときに野蛮な塩の匂いが私達を包んだ。
はーっと夏芽が海中から立ち上がって、大きく深呼吸して叫んだ。
「しょっぺー!」
「海だからね」
弓ちゃんは叫ぶ夏芽に言った。
❋
それから私達は持ってきたビーチボールや浮き輪で遊び、弓ちゃんの「ベッドのやつ」を奪い合って三人ではしゃいだ。
ひとまず前半戦は終了と私達は浜辺へ引き返すと砂に腰を降ろして、電車に乗る前に買っておいたコンビニのおにぎりを食べることにした。
静かな海だった。私達三人の声以外誰もきこえない。ぼーっとしているとまるで無人島にいるような気分がしてくる。
わたしのまちがひだった
わたしのまちがひだった
こうして 草にすわれば それがわかる
草じゃなくて砂浜だけどね、弓ちゃんがイタズラっぽく付け加えた。
「シゲキチ?」
「うん。『草に すわる』ってやつ」
「シゲキチよ、君はいったい何を間違えたの……」
「夏芽にはわからないかもね」
私は梅干しをお茶で呑み込んで軽口をたたいた。
「妹にはお姉ちゃんのわからないことがわかるんですう」
「お姉ちゃんには妹のわからないことがわかるんですう」
弓ちゃんはまだ食べきれていないおかかを片手に笑う。それから「いいなあ、私も常ちゃんと夏芽ちゃんの妹だったらなあ」と言った。
「泣かせることを言うねえ。大丈夫、弓ちゃんは私の可愛いリトルシスターだよ」
弓ちゃんが夏芽の言葉を笑って受け止めたあとに言う。
「二人は双子なんだよね?」
「そうだよ、顔も性格も全然似てないけどね。よかった!」
「ほんと、似てなくてよかった!」
「ねえ夏芽ちゃんは最初から『常美』なの? それとも最初は『お姉ちゃん』だったの?」
夏芽と私は一瞬目を合わせる。どちらが応えようか。でも双子にテレパシーがあるわけじゃない。結局夏芽が答えを口にする。
「それはねえ、今年の四月から常美は『常美』なの。お姉ちゃんは中等部修了をもって私が引導を渡して『お姉ちゃん』を引退させました。もう姉妹揃って同じ道を行くこともないしね」
「え、それどういうことなの?」
「お姉ちゃんと私はね、実はバレエ以外に前からピアノもやってたの。でも、オ・ト・ナの事情で私はピアノ、常美はバレエに別れてしまったのです。ああ、さようなら、かつてのピアニストお姉ちゃん、永遠なーれー」
「大人の事情って何?」
弓ちゃんが私の顔を覗き込んだ。
目の前の少女の小さな肩から身体の中心へ濡れた髪が垂れた。
「ごめん、もしかして、きいてほしくないこときいちゃった?」
私は笑った。「大丈夫、そんなことないよ」
うそ、ほんとは自分がピアノやりたかったくせに。夏芽が笑っていないのは一瞬だった。
夏芽は弓ちゃんに「あ、ねえねえ、師匠きいて!」と波に負けないように大きな声で言った。夏芽は私達から顔を逸らして口にした。
つまらないから
明るい陽のなかにたってなみだを流していた。
「『涙』かな?」
弓ちゃんが夏芽に問いかけた。夏芽は弓ちゃんの言葉を返さず繰り返し続ける波を見た。焼けた肌は海水で濡れて、頬の水滴が日射しを吸い込んで瞬いた。夏芽自身が燃える恒
星みたいだった。本当に、双子ってなんなんだろう。
どうして夏芽はこうなんだろう。
夏芽は弓ちゃんと私の方を振り返った。
「なんか覚えちゃった。シゲキチ、つまらないから、暇つぶしで泣くとかやばいね。むしろポジティブな気さえしてきた!」
笑わそうとしたのかもしれない。でも波が重なって弓ちゃんと私は笑うタイミングを見逃してしまった。弓ちゃんは夏芽に話しかけた。その声はいつものとおり落ち着いていた。
「ねえ、夏芽ちゃん」
弓ちゃんが妹をそう呼びかける。
「夏芽ちゃんって葉子先生が好きなんだよね」
弓ちゃんはじっと夏芽を見つめる。私はそれを見つめる。
波は変わらずしゃらしゃらと砂を響かせ鳴らし続ける。
夏芽は応えた。
「うん、私は葉子先生が好きだよ」
静かな海だった。
定規で引いたような線の向こう側から打ち寄せる波音をこの先ずっと私は忘れないような気がした。
弓ちゃんは笑った。「そっか」
それから手元の砂浜を握りしめて、夏芽に投げつけた。えいっ。
「わあ、弓ちゃんなにすんの」
えいっ。えいっ。弓ちゃんは構わずに夏芽に砂を投げ続ける。きらきら光る砂が星を流し広げるみたいに夏芽に向かって飛んでいく。 私も一緒になって夏芽に投げつけた。「ちょっと、ちょっと二人ともやめて」
夏芽は立ちあがって海の方へ砂から逃げていく。弓ちゃんと私も立ち上がって、夏の雪合戦みたいにそれでも夏芽を追いかける。笑って、笑って、ずっと夏芽を追いかけ続ける。
それから海のなかで私達はまた転んだ。転んだ拍子に私の頭に海月が乗って弓ちゃんと夏芽は水平線の向こうまで届くくらい爆笑した。
海月はぽちゃんと水面に沈んだ。
やっぱり妹じゃ嫌かな。
弓ちゃんが波間でそう囁くのをきいたのは私だけだったのだろうか。
❋
散々遊んで、六時を過ぎるとさすがに水温も下がって肌寒くなった。私達は誰が言うでもなく、岸に上がり、それから制服に着替えた。タオルで水滴を拭き取って乾いた服に袖を通すと皮膚が少しチリチリする気がした。
誰かが「あーあ、テストなんて返ってこなくていいのになあ」とぼやいた。それに誰かが「今日出た問いの三問ってこれであってる?」と返して答え合わせを始めた。でも、私達のうちの結局誰も正解を知らず、結果は来週のおたのしみということになった。
最後に水着を海水が漏れないように二重にビニール袋で包んで無理やり詰め込んだ。濡れた水着の入ったかばんは行きよりも確実に重たくなっていた。
それから海岸沿いを三人で歩いた。突堤を見つけて三人で先まで行って、もう今日の当番は終了とばかりに海の底に帰っていこうとする太陽に向けて私達のうちの一人がバカヤローと叫んだ。それから恥ずかしそうに振り返って、一度やってみたかったの、と笑った。私達のうちの二人がいくらなんでもベタすぎと笑い返した。
私達は電車までまだ時間はあるからといいかげんなことを言って突堤のコンクリートに腰を降ろした。太陽はあんまりにも大きくて、あんまりにも真っ赤で、それを何にたとえればいいのかわからなかった。花のような? トマトのような? それはただ何にもたとえにならずにこの一瞬だけがあって、そして確実に巨大なその円は下降していっていたのだ。腰を降ろした私達はなんとなく膝を抱えて三角座りをした。
私は陽のなかに座る二人を見た。本当に私の大好きな二人。私は二人を見ていると紗枝のことを思い出した。紗枝は少し弓ちゃんに似ていた。そう、きっと。でもいまは弓ちゃんが紗江に似ているような気がする。
「なっちゃん」
弓ちゃんが夏芽をそう呼ぶ声がした。それから私のことも。「常ちゃん」
「今日、たのしかったね」
私は夕焼けで姿を変えていく海を見る。海面の波はそれぞれの場所で広がって影響を与えながら一瞬たりとも同じ形にはならない。
電信柱よりも高い海鳥が沖へ滑るように光のなかを越えていく。
私、文化祭で朗読するのこれにしようと思うの。弓ちゃんは静かに暗唱する。
夏芽が、シゲキチ珍しくポジティブじゃん、と笑った。『太陽』という題だった。
日をまともに見ているだけで
うれしいと思っているときがある
私は指先で目をこすった。でも手には海水の塩分が残っていて私の眼球を刺激した。底が擦り減った足元のスニーカーが滲んでいく。私は立ちあがった。この気持ちが瞳の雨になってかたちになる前に。
赤い煌めきが舞台を充たしている。護岸ブロックに波が打ち寄せるこの些細な舞台で私は二人の観客のためだけに踊る。トゥーシューズでないから長くルルヴェは保てない。それでも僅かな時間だけほんの少し爪先が背を高くしてくれる。両腕をのばしてピルエット。もう少し身体を大きく動かしてグラン・ピルエット。スカートが暖かい風を孕んで一緒に踊ってくれる。
好きじゃなくても、向いてなくても、それでもきっと。
それでもきっと。
本当に、二人だけに見せる一瞬の舞台。
私は気が済むと二人の観客の前に立って礼をした。
観客からは拍手ではなく抗議の声が上がった。
「お姉ちゃんが泣くなんてずるい」
誰かがそう言った。海が鳴っているような洟声だった。
「ずるくない」
風が涙を撫でる。でもそこにはやっぱり塩分が混じっていて、ますます私と妹を泣かせる。止まらない時間に成って涙は流れ続ける。弓ちゃんだって泣いている。「痛いね」弓ちゃんが言った。私は応える。
「うん、痛い」
それから弓ちゃんは目を糸のようにして笑ってくれる。
「でも、私、常ちゃんの踊り好きだよ」
塩が痛い。
海が痛い。
風が痛い。
光が痛い。
何よりもこの一瞬が痛かった。私達は痛かった。
私達は気が済むまで三人で痛い、痛いと泣き続けた。あんまり泣いたものだから目が腫れて顔は洟でぐしゃぐしゃになった。
それから私達は立ちあがって突堤から岸へ歩いた。「夏休みになったら、また来ようね。それから秋は山の方に行ってみよう。冬になったら……」誰かが何かに抵抗するようにそう言って手を繋いだ。
でもどれだけ抵抗しても背後の太陽は暮れてゆく時を一瞬たりともごまかそうとしなかった。そしてまた水槽の舞台に月が浮かび始める。
二人の冷えた指先は体温を取り戻そうと脈を強く拍っていた。きっと私も。
私は繋いだ両端の手に力を籠める。
そう。あのとき紗江は。私は流れ続ける暖かな血液を感じる。
この時間のことを言っていたんだ。
私はもう一度繋いだ手に力を籠める。
「大丈夫」
弓ちゃんが私にそう言った。
「きっと失くなったりなんかしないから」
それから私達は夜が来て暗転するまでにお互いの手を離した。
了
『人を 殺さば』。
ぐさり! と
やって みたし
人を ころさば
こころよからん
「これ、なんかいいと思う! ねえ弓ちゃん、これにしたら? 常美もそう思わない?」
二限の終わり、三限の始まる前、夏芽と私は僅かな十分の間でも話したくてこうして羽根虫が蜘蛛の網に絡められるように窓側の弓ちゃんの席に来ていた。書き残された黒板の白い文字を次の数学のために今日の日直が綺麗に消していく。
「そりゃあんたが朗読するならいいかもしれないけど、実際やるのは弓ちゃんだからね」
そう言いながら座る弓ちゃんの反応をそっと伺う。案外と弓ちゃんはこういう過激な方が気に入ったりするのだろうか。
教室の騒がしさに混じって消えてしまいそうな弓ちゃんの声に夏芽と私はきき耳を立てる。
「夏芽ちゃんらしいね」
うーむ、弓ちゃんの人間観が相変わらずわからん。
私は笑うと糸のように細くなるその目を横に見ながら腕を組む。
弓ちゃんとは対照的に妹の声は耳を塞いでいてもきこえてきそうだ。夏芽はプリントアウトされた紙束を捲りながら言った。
「うーむ、なんかこの人暗くない?」
弓ちゃんは夏芽の率直な言葉を優しく包み込むように言う。
「たしかに詩人のなかにはだいぶ欝っぽい感じの人ってたくさんいるけど、この人はどうかなあ。でも、たしかにそういう死を見つめる目線みたいなものはあったのかも。この人の場合、若くして病気になって結局二十九歳で死んじゃったみたいだから。ってこれ先生の受け売りだけど」
「他の作家とかにしないの? このヤギシゲキチで決定?」
弓ちゃんは夏芽の間違いを訂正しなかった。それを優しいと言うのか言わないのかは私にはわからなかった。夏芽サン「シゲキチ」じゃなくて「ジュウキチ」ダヨ。
「うん、やっぱり朔太郎とかは人気があって先輩がやることになってるの。一年は一人一人先生に作家を選ばれてそれをやるの」
「へー、なんかちょっと運動部みたいだね」
「そうかも」
「あ、これなんかよさそう」夏芽がヤギシゲキチを朗読する。『無造作な 雲』という題だ。
無造作な くも、
あのくものあたりへ 死にたい
「シゲキチ、死なないで」
やっぱ暗いわ、この人、と夏芽はやはり正直に呟いた。
ふふ、それは常ちゃんっぽいね。え、どういうこと、弓ちゃん?
「どうかな。どれがいいと思う? ジュウキチは残っている詩集が少ないから選びやすいねって先輩達は言うんだけど、短いのが多くて朗読することも考えたら結構選ぶのが難しくて」
夏芽が『貧しき信徒』のプリントアウトを弓ちゃんの机に返して、もう一束プリントアウトを捲る。そちらは『秋の瞳』という詩集らしい。
「そうだねえ、これなんか一行だけなんだね、『おもひ』か、ふむふむ」
かへるべきである ともおもわれる
「どこにだよ。でもこんな風に一行だけでも詩なんだねえ。なんか短歌とかみたい」
「影響はあるのかもしれないね。ある程度の長さがあるやつもあるんだけど、でもジュウキチは、ただ一言だけ深呼吸するみたいに、自分の奥の何かを見つめて、それが装飾もなく言葉になっているところが私は読んでいて好き。だから朗読のためだけに長いのを選ぶのもどうかなあって」
「飾らない素朴さが良いってことですな、ほう」
そういうことかな。弓ちゃんが照れ臭そうに言う。それをまん丸とした目でパチパチと音をたてるように夏芽が見つめた。
私は改めてプリントアウトを眺める。まだインクの独特な匂いが残っている。私は弓ちゃんに伝えた。
「いいんじゃないかな、短いのでも、かっこいいよ。文芸部は軽音楽部のあとでしょ、激しく盛り上がったあとに弓ちゃんの声で『かへるべきである ともおもわれる』って一言静かな感じで体育館に響いたらなんかいいと思う」
「それでほんとにみんな帰っちゃったりして。文芸部のあとには最後にピアノ部の発表もあるんですけど」
「ピアノ部の発表はそれでいいんじゃない? ダンス部の発表は最初に終わってるしね」
「常ちゃんはバレエ?」
弓ちゃんは私にどこかしら期待を持つようにきいた。
「やるとしたらね。おばあちゃん、来るからね。バレエ以外やったら卒倒しそう」
「そっか、幼稚舎から続けてるって言ってたもんね」
「といっても、文化祭の出演は有志だから私はでないけど」
「え、なんで?」
そこに夏芽がトウっと叫んで弓ちゃんと私の間に手刀を切って割り込んだ。
「ソンナコトヨリお二人サン。待ちにマッタ、テストオワリノ海ノコトナンデスガ」
なんでロボットみたいなの? 弓ちゃんが笑って言う。トクニ意味はアリマセン。
私は二人の会話を眺める。夏芽はバレエの話が嫌いだ。おばあちゃんのことは考えるのも嫌なのだろう。高等部に転入して二ヶ月の弓ちゃんはそれを知らない。二人は嬉しそうに海水浴に持っていくものを相談している。私は二人の話題に入り直そうと身を乗り出すと、黒板の上のスピーカーが三限の開始を教室の喧騒に告げた。
「じゃあ弓ちゃん、絶対ベッドのやつ持ってきてね」
いちばん席が遠い夏芽がそう言って席に帰っていった。「ベッドのやつ」ってなんだろう? そういえば、と最後に私は弓ちゃんに質問をした。弓ちゃんは答える代わりに紙束からプリントアウトを一枚渡してくれた。私が席に着くと同時に葉子先生が入ってきた。危ない、危ない。
「ちゃんと皆さんチャイムが鳴り終わるまでに席に着きましたか。それでは前回の公約数の求め方から始めましょう。公約数の計算は来週の中間テストでは必ず出ますからね」
葉子先生はそう言って黒板に二つの数字の組み合わせを書いていく。私は本人に気づかれないように夏芽を盗み見て、それから弓ちゃんと目を合わせる。夏芽がこの時間だけ大きな目を開いて授業に集中できるのは何も数学だけが得意科目だからというわけだけではない。恋は学業に資するのである。
それから私はさっき弓ちゃんに貰ったプリントアウトを葉子先生に見つからないようにこっそり眺める。
私はきいた。弓ちゃんがいちばん好きなのはこの詩集のなかだとどれなの?
私は右端に書かれたタイトルを目で拾う『あめの 日』。
しろい きのこ
きいろい きのこ
あめの日
しづかな日
きのこ……、たしかに弓ちゃんっぽいかも。私は森の大樹の陰でひっそりと生える濡れた傘に触れるようにその机の下の言葉を指でなぞった。
紗枝はどうしているだろう。
印字された言葉を撫でているとそんなことがなぜか不意に頭にうかんだ。
❋
「それじゃあ二人とも勝手に水着買いに行っちゃダメだからね」
放課後、夏芽は弓ちゃんと私を昇降口の校舎玄関まで見送ると、そう言い残して部活のため隣校舎の音楽室まで走っていった。
なぜあんな落ち着きのない子に育ったのか。私は双子とは何かについて深く考えさせられずにはいられなかった。私は下駄箱から靴を取り出して溜息を吐きながら足を入れた。
痛っ、気づけば自然と口から漏れていた。
「大丈夫?」
弓ちゃんも履き替えて心配そうに私に言った。
「うん、全然、大丈夫」
おばあちゃんにこっそり内緒で買ったスニーカーのせいだった。高等部になってローファーを履くのが自由になり思い切って買ったの だが、インソールがずれて少し痛くなっていた。
「やっぱりバレエやってるとそうなっちゃうの?」
弓ちゃんは鞄からバンソウコウを取り出して渡してくれた。
「ありがとう。ソックスを厚手に変えたら全然大丈夫だと思うから」
私は靴下を捲って貼ると弓ちゃんにお礼を言った。
「これはバレエとは関係ないかな、たぶんふつうに靴擦れ」
「そっか、海行くまでに治るといいね」
暑さに勘違いした初夏の蝉はもう鳴き始めていた。校舎を出ても夏至の太陽はまだ放課後の世界から降りることができず空に釘付けされている。葉桜の木漏れ日を弓ちゃんが愛おしそうに見つめる。私はそんな弓ちゃんを見ていると心が跳ねた。不意に泣きたくなる。
いっそ神様に何もかも正直に打ち明けたい。そんな気分がした。
「常ちゃん、今日レッスンはお休みなの? ダンス部は?」
「レッスンは休み。部活は、今日はいいかな」
ズル休みだ。弓ちゃんはクスクス笑う。
「文芸部も今日は休みだったよね」
うん、と弓ちゃんの声が歌うようにきこえる。私は思い切って弓ちゃんに提案した。
「ねえ弓ちゃん、天国にいちばん近い場所に行かない?」
「天国?」
「うん、ニューカレドニアだよ。神様に会いに行くんだよ」
❋
私は駅前まで来ると目印にしている潰れたタバコ屋さんから路地に入った。そして目当てのビルの裏口まで来ると、外付け非常階段の入り口に架けられた立ち入りを禁ずるためのチェーンをためらわずに下から潜った。
「常ちゃん、勝手に入ったら怒られちゃうよ」
弓ちゃんは慌てて後ろから私の手を引っ張った。
私は弓ちゃんを安心させようと笑いかけた。
「大丈夫、ここ、うちの家のビルだから。駅前のビルはだいたいうちなんだ」
それから弓ちゃんも潜れるようにチェーンを片手で持ち上げた。
一段一段赤錆びている踏み板を音をさせながら上がると、ここも相当古くなったな、と私は思う。
最初に夏芽と勝手に入って、お父さん達に絶対に子供だけで入るなと怒られて、それからまた自分達だけでこっそり入るようになったのはいつだったけ。そういえばお父さんとおばあちゃんは私達を叱ったけど、お母さんは何も言わなかったなあ。まあ、お母さんは私達にはいつもそうだけど。
いいんじゃないですか、お義母さん、夏芽一人だけならピアノを続けても。だから、きっとあのときも援護射撃のつもりなど一切なかったのだろう。単純に言い争う夏芽とおばあちゃんがうるさかっただけだ。その証拠にお母さんは特に考えもせずにこう言ったものだ。バレエの方は常美に続けてもらえばお義母さんの義理は果たせるでしょ。私は階段の最後の一段を踏みつけるようにスニーカーの足を下ろした。
お姉ちゃんはほんとにそれでいいの?
踏み板が鳴る音にあの日リビングに響いた妹の泣き声が私の頭で混じった気がした。
屋上にたどりついた。私はよろよろと屋上の中央に彷徨って大きく仰向けに寝転がった。
高い場所から見える雲は西からの力でゆっくりと移動していった。あんまりにも晴れているものだから、うるせー、晴れてるぞー! と思い切り叫びたいような気持ちがした。気づけば登り疲れた弓ちゃんも隣で仰向けになっている。
このビルの屋上を「ニューカレドニア」と名づけたのは夏芽だった。天国に近いからって。天国は意外と低い場所にあるものだ。
「弓ちゃん、うちの学校は慣れた? 弓ちゃんの中学ってうちの県から遠かったんでしょ? 友達と離れて寂しかったりしない?」
「どうかなあ、私、小学校のころから引っ越し多かったし、前の中学も三年のときに入ったから、卒業って言われてもなんか不思議な感じだったんだよね。私、みんなと仲良くなるまで時間かかるタイプみたいで最後もちょっと時間足りなかったかも」
「そうなんだ」
でも弓ちゃんの声は暗くなかった。むしろ少し弾んでいたかもしれない。私はその理由がわかっていた。弓ちゃん自身はその理由がわかっているのだろうか。
「あ、でも夏芽ちゃんと常ちゃんみたいな子は初めて。二人といるのほんとにたのしい」
夏芽ちゃんは太陽みたいな人だね。
隣の弓ちゃんがどんな表情か私にはわからなかった。きっといつものように目を糸のように笑っているのだと思った。
「あ、常ちゃん見て、月だよ」
お月様は昼でもちゃんといるんだねえ。弓ちゃんはそう言って水色の舞台に夜から紛れ込んだ上弦の星を見つける。あのくものあたりへ、死んでいきたい、か。
私は目を瞑った。少し眠たいような気がした。屋上の風は子守唄だった。私は寝ぼけているように呟いた。
「私、なんだか弓ちゃんといると怖い」
どうして。弓ちゃんの声はすぐ隣にいるのに遠くきこえた。
どこか遠い場所から、でも、すごく近くから。不思議な感じがした。
「中等部のときに紗江って子がいたのね。私達みたいに内部進学せずに県外の高校に行ったんだけど、一緒にバレエのレッスンも受けてたんだ。紗枝は、」
「うん」
弓ちゃんの声もどこか眠そうだった。
「紗江は、」
額に汗が滲んだ。
弓ちゃんは何も言わない、私が話すのを待っている。
紗江は、
紗江は、
私は懸命に彼女を語る言葉を探す。なぜだろう、どうしてだろう。どうしても彼女を弓ちゃんに伝える言葉がなかった。三年間、あれほど話したのに。こんな短い時間で忘れるはずないのに。どうして紗江を語る言葉が出てこないのだろう。
代わりに影のように頭に響くのは卒業舞踏会の前日に教室で言われたことだった。
常美は痛いよ。
どういうこと? 紗江の言っていることの意味がわからなかった。同じ時間を幾度も過ごしたのに私は紗江のことを何もわかっていなかった。最後の最後にそう宣告されたようだった。私は紗江のことがわからなかった。結局その言葉の真意もきけないまま別れてしまった。
私は今日までその言葉の意味をずっと考えていた。でもやっぱりわからなかった。
どうしても紗江について語る言葉がなかった。
それはたまらなく、たまらなく恥ずかしいことのように思えた。代わりに口を衝いて出たのは自分のことだった。
「私、バレエ好きじゃないし、向いてない」
弓ちゃんは何も言わず隣で寝転ぶ私の手を掴んでくれた。握り返すと小さな手はすっぽりと私のなかに収まった。その手を掴んでいると私の意識は懐かしくてここよりももっと大きくて広いところに落ちていくようだった。常ちゃん、私ね、弓ちゃんは落ちていく私に言葉を渡してくれる。
「思い出せなかったり、見失ったりすることはあっても、本当に失くしたりはできないと思うんだ」
それから、私を眠らせるように囁いた。
「海、たのしみだね」
❋
海開きにはまだ一週間だけ早かった。海岸には私達以外誰もいなくて、迎えてくれたのは浜辺のシオマネキだけだった。それでも六月最後の日にして気温は30℃以上、梅雨はとっくに過ぎ去り真夏日だった。
乾いた砂浜から濡れた場所に入ると踵が沈んで靴擦れは少し染みた。親指の間には海水が流れ込んできて私達の足裏を洗う。冷たさに隣の弓ちゃんが目隠しされた箱の中のものを触ったみたいに肩をビクッと震わせて私の二の腕を掴んだ。私達は思わず身を縮めて波打ち際で立ち止まってしまった。打ち寄せる波はそれから光が滑ったようなしゃらしゃらとした音をさせて引いていく。
ひとり前を行っていた夏芽はうっかり氷を呑み込んだ猫みたいにパチッと目を開き硬直していた。それから三秒ほど静止すると、う ああああああ、と叫んで海に駆けた。
「あははは、夏芽ちゃん……」
すると隣の弓ちゃんも何かのスイッチが入ったように、きゃーっと叫んで夏芽のもとに駆け寄っていった。え、どうしたの、二人とも。ちょっと待って私をおいていかないで。
弓ちゃんと私は海面が腰まで浸かる高さにいた夏芽に追い付いて二人で背中からのしかかった。育ち盛りの女子二人の体重を育ち盛りの女子一人で支えきれるわけもなく、育ち盛りの私達三人はそのまま浅い海中に転んだ。海面に顔がつくときに野蛮な塩の匂いが私達を包んだ。
はーっと夏芽が海中から立ち上がって、大きく深呼吸して叫んだ。
「しょっぺー!」
「海だからね」
弓ちゃんは叫ぶ夏芽に言った。
❋
それから私達は持ってきたビーチボールや浮き輪で遊び、弓ちゃんの「ベッドのやつ」を奪い合って三人ではしゃいだ。
ひとまず前半戦は終了と私達は浜辺へ引き返すと砂に腰を降ろして、電車に乗る前に買っておいたコンビニのおにぎりを食べることにした。
静かな海だった。私達三人の声以外誰もきこえない。ぼーっとしているとまるで無人島にいるような気分がしてくる。
わたしのまちがひだった
わたしのまちがひだった
こうして 草にすわれば それがわかる
草じゃなくて砂浜だけどね、弓ちゃんがイタズラっぽく付け加えた。
「シゲキチ?」
「うん。『草に すわる』ってやつ」
「シゲキチよ、君はいったい何を間違えたの……」
「夏芽にはわからないかもね」
私は梅干しをお茶で呑み込んで軽口をたたいた。
「妹にはお姉ちゃんのわからないことがわかるんですう」
「お姉ちゃんには妹のわからないことがわかるんですう」
弓ちゃんはまだ食べきれていないおかかを片手に笑う。それから「いいなあ、私も常ちゃんと夏芽ちゃんの妹だったらなあ」と言った。
「泣かせることを言うねえ。大丈夫、弓ちゃんは私の可愛いリトルシスターだよ」
弓ちゃんが夏芽の言葉を笑って受け止めたあとに言う。
「二人は双子なんだよね?」
「そうだよ、顔も性格も全然似てないけどね。よかった!」
「ほんと、似てなくてよかった!」
「ねえ夏芽ちゃんは最初から『常美』なの? それとも最初は『お姉ちゃん』だったの?」
夏芽と私は一瞬目を合わせる。どちらが応えようか。でも双子にテレパシーがあるわけじゃない。結局夏芽が答えを口にする。
「それはねえ、今年の四月から常美は『常美』なの。お姉ちゃんは中等部修了をもって私が引導を渡して『お姉ちゃん』を引退させました。もう姉妹揃って同じ道を行くこともないしね」
「え、それどういうことなの?」
「お姉ちゃんと私はね、実はバレエ以外に前からピアノもやってたの。でも、オ・ト・ナの事情で私はピアノ、常美はバレエに別れてしまったのです。ああ、さようなら、かつてのピアニストお姉ちゃん、永遠なーれー」
「大人の事情って何?」
弓ちゃんが私の顔を覗き込んだ。
目の前の少女の小さな肩から身体の中心へ濡れた髪が垂れた。
「ごめん、もしかして、きいてほしくないこときいちゃった?」
私は笑った。「大丈夫、そんなことないよ」
うそ、ほんとは自分がピアノやりたかったくせに。夏芽が笑っていないのは一瞬だった。
夏芽は弓ちゃんに「あ、ねえねえ、師匠きいて!」と波に負けないように大きな声で言った。夏芽は私達から顔を逸らして口にした。
つまらないから
明るい陽のなかにたってなみだを流していた。
「『涙』かな?」
弓ちゃんが夏芽に問いかけた。夏芽は弓ちゃんの言葉を返さず繰り返し続ける波を見た。焼けた肌は海水で濡れて、頬の水滴が日射しを吸い込んで瞬いた。夏芽自身が燃える恒
星みたいだった。本当に、双子ってなんなんだろう。
どうして夏芽はこうなんだろう。
夏芽は弓ちゃんと私の方を振り返った。
「なんか覚えちゃった。シゲキチ、つまらないから、暇つぶしで泣くとかやばいね。むしろポジティブな気さえしてきた!」
笑わそうとしたのかもしれない。でも波が重なって弓ちゃんと私は笑うタイミングを見逃してしまった。弓ちゃんは夏芽に話しかけた。その声はいつものとおり落ち着いていた。
「ねえ、夏芽ちゃん」
弓ちゃんが妹をそう呼びかける。
「夏芽ちゃんって葉子先生が好きなんだよね」
弓ちゃんはじっと夏芽を見つめる。私はそれを見つめる。
波は変わらずしゃらしゃらと砂を響かせ鳴らし続ける。
夏芽は応えた。
「うん、私は葉子先生が好きだよ」
静かな海だった。
定規で引いたような線の向こう側から打ち寄せる波音をこの先ずっと私は忘れないような気がした。
弓ちゃんは笑った。「そっか」
それから手元の砂浜を握りしめて、夏芽に投げつけた。えいっ。
「わあ、弓ちゃんなにすんの」
えいっ。えいっ。弓ちゃんは構わずに夏芽に砂を投げ続ける。きらきら光る砂が星を流し広げるみたいに夏芽に向かって飛んでいく。 私も一緒になって夏芽に投げつけた。「ちょっと、ちょっと二人ともやめて」
夏芽は立ちあがって海の方へ砂から逃げていく。弓ちゃんと私も立ち上がって、夏の雪合戦みたいにそれでも夏芽を追いかける。笑って、笑って、ずっと夏芽を追いかけ続ける。
それから海のなかで私達はまた転んだ。転んだ拍子に私の頭に海月が乗って弓ちゃんと夏芽は水平線の向こうまで届くくらい爆笑した。
海月はぽちゃんと水面に沈んだ。
やっぱり妹じゃ嫌かな。
弓ちゃんが波間でそう囁くのをきいたのは私だけだったのだろうか。
❋
散々遊んで、六時を過ぎるとさすがに水温も下がって肌寒くなった。私達は誰が言うでもなく、岸に上がり、それから制服に着替えた。タオルで水滴を拭き取って乾いた服に袖を通すと皮膚が少しチリチリする気がした。
誰かが「あーあ、テストなんて返ってこなくていいのになあ」とぼやいた。それに誰かが「今日出た問いの三問ってこれであってる?」と返して答え合わせを始めた。でも、私達のうちの結局誰も正解を知らず、結果は来週のおたのしみということになった。
最後に水着を海水が漏れないように二重にビニール袋で包んで無理やり詰め込んだ。濡れた水着の入ったかばんは行きよりも確実に重たくなっていた。
それから海岸沿いを三人で歩いた。突堤を見つけて三人で先まで行って、もう今日の当番は終了とばかりに海の底に帰っていこうとする太陽に向けて私達のうちの一人がバカヤローと叫んだ。それから恥ずかしそうに振り返って、一度やってみたかったの、と笑った。私達のうちの二人がいくらなんでもベタすぎと笑い返した。
私達は電車までまだ時間はあるからといいかげんなことを言って突堤のコンクリートに腰を降ろした。太陽はあんまりにも大きくて、あんまりにも真っ赤で、それを何にたとえればいいのかわからなかった。花のような? トマトのような? それはただ何にもたとえにならずにこの一瞬だけがあって、そして確実に巨大なその円は下降していっていたのだ。腰を降ろした私達はなんとなく膝を抱えて三角座りをした。
私は陽のなかに座る二人を見た。本当に私の大好きな二人。私は二人を見ていると紗枝のことを思い出した。紗枝は少し弓ちゃんに似ていた。そう、きっと。でもいまは弓ちゃんが紗江に似ているような気がする。
「なっちゃん」
弓ちゃんが夏芽をそう呼ぶ声がした。それから私のことも。「常ちゃん」
「今日、たのしかったね」
私は夕焼けで姿を変えていく海を見る。海面の波はそれぞれの場所で広がって影響を与えながら一瞬たりとも同じ形にはならない。
電信柱よりも高い海鳥が沖へ滑るように光のなかを越えていく。
私、文化祭で朗読するのこれにしようと思うの。弓ちゃんは静かに暗唱する。
夏芽が、シゲキチ珍しくポジティブじゃん、と笑った。『太陽』という題だった。
日をまともに見ているだけで
うれしいと思っているときがある
私は指先で目をこすった。でも手には海水の塩分が残っていて私の眼球を刺激した。底が擦り減った足元のスニーカーが滲んでいく。私は立ちあがった。この気持ちが瞳の雨になってかたちになる前に。
赤い煌めきが舞台を充たしている。護岸ブロックに波が打ち寄せるこの些細な舞台で私は二人の観客のためだけに踊る。トゥーシューズでないから長くルルヴェは保てない。それでも僅かな時間だけほんの少し爪先が背を高くしてくれる。両腕をのばしてピルエット。もう少し身体を大きく動かしてグラン・ピルエット。スカートが暖かい風を孕んで一緒に踊ってくれる。
好きじゃなくても、向いてなくても、それでもきっと。
それでもきっと。
本当に、二人だけに見せる一瞬の舞台。
私は気が済むと二人の観客の前に立って礼をした。
観客からは拍手ではなく抗議の声が上がった。
「お姉ちゃんが泣くなんてずるい」
誰かがそう言った。海が鳴っているような洟声だった。
「ずるくない」
風が涙を撫でる。でもそこにはやっぱり塩分が混じっていて、ますます私と妹を泣かせる。止まらない時間に成って涙は流れ続ける。弓ちゃんだって泣いている。「痛いね」弓ちゃんが言った。私は応える。
「うん、痛い」
それから弓ちゃんは目を糸のようにして笑ってくれる。
「でも、私、常ちゃんの踊り好きだよ」
塩が痛い。
海が痛い。
風が痛い。
光が痛い。
何よりもこの一瞬が痛かった。私達は痛かった。
私達は気が済むまで三人で痛い、痛いと泣き続けた。あんまり泣いたものだから目が腫れて顔は洟でぐしゃぐしゃになった。
それから私達は立ちあがって突堤から岸へ歩いた。「夏休みになったら、また来ようね。それから秋は山の方に行ってみよう。冬になったら……」誰かが何かに抵抗するようにそう言って手を繋いだ。
でもどれだけ抵抗しても背後の太陽は暮れてゆく時を一瞬たりともごまかそうとしなかった。そしてまた水槽の舞台に月が浮かび始める。
二人の冷えた指先は体温を取り戻そうと脈を強く拍っていた。きっと私も。
私は繋いだ両端の手に力を籠める。
そう。あのとき紗江は。私は流れ続ける暖かな血液を感じる。
この時間のことを言っていたんだ。
私はもう一度繋いだ手に力を籠める。
「大丈夫」
弓ちゃんが私にそう言った。
「きっと失くなったりなんかしないから」
それから私達は夜が来て暗転するまでにお互いの手を離した。
了