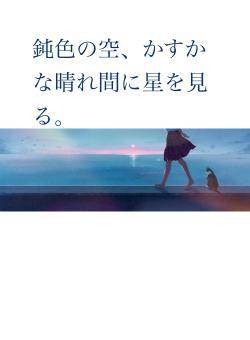あたしは可愛い。
一歩外に出れば、みんながちやほやしてくれる。
あたしが頼めば、男子はなんでもやってくれる。
だからあたしは高いところにあるものは取らないし、重いものだって持たない。
それについて文句を言うガヤはいるけど、べつに気にしない。だってそれでなんの問題もなく生きていけてるんだから、かまわないじゃない。
それに、文句を言うのはだいたい女。どうせみんな、可愛いあたしに嫉妬してるだけ。妬まずにはいられないだけ。あたしが可愛いから。羨ましいから。
街を歩けば、男子だけじゃなくて女子だってちらちら見てくる。
あたしは可愛い。
だからあたしは、だれにも媚びない。そんなことしなくても、あたしは愛される。愛されるに相応しい女だから。
***
高校二年の春、あたしはすごく久しぶりに、女子から声をかけられた。
朝野みやび。
美人でスタイルが良くて、一年のときから目立っていた子だ。他人に興味のないあたしでも、知っていた。
「あのね、私ね、美月ちゃんが赤ちゃんを泣き止ませてるの見て、すごく感動したんだ!」
「えー……ありがとう」
……気持ち悪い。なに知り合いでもないひとのこと見てんの。ストーカーかよ。
きらいなタイプだ。
彼女からは、清潔な匂いがぷんぷんしていた。
きっと、すごくいい子なのだろう。
可愛くて、性格も良くて、皆から愛されてきた。
愛されて育ったから、他人を疑わない。ちょっと意外な一面を見ただけで、あたしのことを、困ってるひとに手を差し伸べられる心優しい女の子だと誤解する。
それがあたしのすべてなわけがないのに。
あたしは善人なんかじゃない。
バスのなかであたしがあの親子に声をかけたのは、そんなきれいな理由からじゃない。
***
風船がパンッと割れたような音がして、あたしは目を覚ました。
周囲を見ると、満員のバスのなか。何度か瞬きをするあいだに周囲の空気を感じ、今が放課後で、じぶんが帰宅途中であったことを思い出す。
寝ぼけて遠のいていた音が、波のように押し寄せてくる。
前のほうから、赤ちゃんの声が聞こえる。
見ると、小さな赤ちゃんを抱っこした若い母親が優先席近くに座っていた。風船が割れた音だと思ったのは、赤ちゃんの泣き声だったようだ。
母親が泣き止まない赤ちゃんをあやすために立ち上がると、空いた席にすかさず近くにいたおばさんが座った。
となりに座っていたおじさんが、聞こえよがしのため息を吐く。背後から、「うるせえなぁ」という呟きが聞こえてくる。
目眩がする。
降りろよ、という乗客からの見えない圧に、母親はどんどん萎縮していく。
母親の緊張が赤ちゃんにも伝わったのか、赤ちゃんは泣き止むどころかさらに大きな声で泣き始めた。
べつに、どうだっていい。
……どうだっていいけれど、泣き声は、苦手。
母親を、思い出すから。
『あんたなんて、産まなきゃよかった』
耳元で声がした、気がした。
あたしの母親は、あたしが中学になるかならないかくらいのときに男を作って出ていった。
悲しくはなかった。むしろ、心からほっとした。それまで、さんざんいじめられてきたから。
機嫌が悪いと、殴られ蹴られは当たり前。口ごたえどころか睨んだだけでご飯も抜きにされる。ひどいときは、服を剥かれて熱湯をかけられた。
いわゆる虐待というやつである。
おかげであたしの胸元には、大きな火傷の痕がある。故にいつもパーカーで隠し、バイトのときはチョーカーネックのドレス一択。痕がバレないように。
まぁ、贔屓の客にはわざと見せて、感情を煽ったりもするけれど。
でも、オッサンは騙せても、たぶん、同級生はムリ。特に女子は、たぶんこういうものを見たら、あたしを格好の餌にする。女子はそういう、醜い生き物。だからあたしは、基本的に学校では肌を隠している。
あたしは、今でもまだ、ふとしたときにPTSDに襲われたりする。トリガーになるのはだいたい、子どもの泣き声、女の金切り声、オジサンの怒鳴り声。
あんな店で働いてるあたしだけど、べつに男が好きってわけじゃない。お金に困ってるわけでもない。もっとべつの理由。
あたしは、子どもの泣き声も母親もきらいだけど、オッサンがいちばんきらい。
あたしに手を上げてきたのは、母親だけじゃなかった。母親が出ていってからは、父親にも手をあげられてきたから。
大きな手で頭を掴まれて、何度も、何度も……。
吐き気がする。
……いやなことを思い出した。気持ち悪い。頭痛い。
あたしはカバンのポケットから痛み止めを取り出し、二粒口のなかに入れた。薬を飲み込んで、目を瞑る。しかし、動悸は収まらない。
……ダメだ。まだ足りない。
あたしはさらに三粒、痛み止めを飲み込んだ。
少しづつ意識が朦朧としてくる。不安が薄れていく。
ほっとして、気が緩んだその拍子に、手の力も緩んでしまったようだ。鞄が手から滑り落ちた。
床に落ちた瞬間、なかで乾いた音がした。鞄を開けてなかを見ると、小袋のお菓子が入っていた。
なにこれ。
少し考えて、あぁ、そうだ、と思い出す。
『――月宮って甘いもの好き?』
今朝、学校でとなりの席の男子と、そんな会話をした。その子から、お菓子をもらったのだった。くれた男子の名前は知らない。たしか、遠足も同じグループだった気がするけど、キョーミないから覚えてない。
お菓子の袋を取り出し、バスの前方を見る。
まぁ、車内にゴミ箱なんてないか。
学校のゴミ箱に捨ててくるつもりだったのに、すっかり忘れていた。
あたしは基本、他人からもらったものは食べない。
昔、母親が作ったカレーのなかに割れたガラスを入れたことがあったから。あのときは最悪だった。口の粘膜があちこち切れて、数日、いや、一週間くらいは、口のなかになにも入れられなかった。
あれ以来、あたしはじぶんで作ったものしか食べられなくなった。
だけど、くれるというものを突き返すのも、理由を話すのも面倒だから言わない。笑顔で受け取る。そして、あとで捨てる。そのほうが楽だから。
しかし、女子はそれをよく思わないらしい。
『うーわ。また男子に媚び売ってるよ』
『よくやるよねぇ』
『マジ男好きだよねー』
は? なんで? くれるっていうものをもらっただけで、なんであたしが責められなくちゃならないの? じぶんがもらえないからってあたしに当たるな。
『ないわー』
こっちのセリフだし。つーか、羨ましがってんの見え見えなのよ。悔しかったらあんたも男に笑って見せれば? それで男がその気になるかどうかは知らないけど。
『亜子ちゃんもみやびちゃんも優しいよね』
どこが?
淡島亜子も、朝野みやびもただの偽善者。
弱い者にいい顔をして、ただいい子のふりをしたいだけ。そのあとの責任はなにひとつとらない。あれのどこが優しいわけ?
『私はいっしょに行動するとかムリだわー』
いやいや、こっちから願い下げですけど。なに言ってんの?
『亜子ちゃんの彼氏とったってきいたよ』
そうだよ? だってひとの男奪うのって気持ち良いから。ただし、奪った男はすぐ捨てる。あたしは、捨てられる人間にだけはぜったいにならない。
『えーマジ? ヤバ』
はいはい。知ってます。あたしはクズ。ヤバい人間です。だからどうした。ほっといて。
裏アカだの一軍だの、だれかがだれかの彼氏とっただの。
どいつもこいつもバカばっか。
だったら聞くけど、女友だちなんか作ってなにになるの?
集まったところで、ただ悪口言いあってるだけじゃん。それのなにが楽しいわけ?
男とったっていうけど、あたしからアプローチしたわけじゃないし。つーかこの世の半分が男なんだから、次に行けばいいじゃん。なんでみんなそんなくだらないものに執着するわけ?
バカみたい。バッカみたい。
少し気分が落ち着いて、あたしは周囲を見る。となりの座席のおじさんがいらいらしていた。
舌打ち、ため息。貧乏揺すり。
明らかに、親子に圧をかけている。
あぁ、もう。うるさい。うるさい、うるさい!
子どもじゃないんだから、いらいらを外に出さないでよ。ここはあんたらの家じゃないのよ!
おじさんのとなりに座っているおじさんもまた、いらいらし始める。
周囲の空気に、泣きわめく赤ちゃんをあやしていた母親の顔から、ゆっくりと表情が消えていく。その光景に、あたしはもう顔もろくに覚えていないはずの母親のことを思い出した。
『あんたさえいなければ……』
疲れ切った、悪魔のような母親の声が耳朶を叩く。
あたしを責める声。
なんで?
あたしは悪くない。勝手に産んだのはあんたじゃない。それなのに、なんでそんな顔するの。なんでそんな目であたしを見るの。
赤ちゃんをあやす声から、覇気が失われていく。
『あんたみたいな醜い生き物、産まなきゃよかった!』
あたしは醜くなんてない。ちゃんと見て! ほら、あたしはこんなに可愛い。
母親はとうとうあやすのをやめて俯いた。
あたしはその姿をじっと見つめる。
バカみたい。じぶんで産むことを選んだくせに。
「…………」
そんな目で赤ちゃんを見ないでよ。この子は悪くないじゃない。悪いのはあんた。その子を産んだあんたがぜんぶ悪い。責任転嫁するな。
叫び出したくなる衝動をなんとか抑えて、あたしは席から立ち上がった。
親子の前で立ち止まると、あたしに気付いた母親が顔を上げる。
文句を言われるとでも思ったのだろうか。母親はあたしと目が合うと、弱々しい声で「ごめんなさい」と口にした。
ムカつく。それはなにに対しての謝罪?
あんたが謝るべきはあたしじゃない。あんたの腕のなかにいるこの子だ。
あたしは母親の謝罪を無視して、鞄からお菓子を取り出した。赤ちゃんの前でくしゃくしゃと音を鳴らす。
前、テレビかネットか忘れたけれど、こうすると赤ちゃんが泣き止むと聞いたことがあったのだ。
半信半疑だったが、赤ちゃんは本当に泣き止んだ。あの情報は、どうやらうそではなかったらしい。
赤ちゃんはあっという間に泣き止んで、しばらくぼけっとしたあと、きゃらきゃらとご機嫌そうに笑い出した。
可愛い。
笑っている赤ちゃんは、とても可愛らしい顔をしている。
「ありがとうございます」
母親は、今にも零れ落ちそうなほど大きな雫を目に溜めて、あたしを見上げていた。それを見て、初めて気付いた。
お母さん、若……。
赤ちゃんを抱いていたのは、思ったより若い女性だった。目元のクマがひどいせいで老けて見えたけれど、まだ二十代前半くらいに見える。きっとあたしと五、六歳ほどしか変わらないだろう。
「……すごくいい子ですね」
最後、あたしは母親にそう言った。
あれは、母親のためじゃない。子どものために言ったのだ。
「これ、よかったらどうぞ」
あたしはお菓子を母親に差し出す。ちょうど最寄り駅についたので、あたしはそのままバスを降りた。
どうか、勘違いしないで。この子は敵じゃない。この子に憎むような眼差しを向けないで。そう祈りながら。
あのときの行動は、あたしにとって、今はどこにいるかも分からない母親への、精一杯の反発だった。
***
「――ごめん、巻き込んだね」
あたしは、すぐとなりで俯いていたみやびちゃんに言う。するとみやびちゃんはわずかに顔を上げて、あたしを見て微笑んだ。
「ううん……」
みやびちゃんの笑顔は引きつっていた。
「無理して笑わなくていいんじゃない。ショックだったんでしょ」
あたしは、生まれてこのかた友だちなんていたことはない。だから、これが慰めになっているのかは分からなかった。だが、どうやら、あたしが励ましたつもりだということは、伝わったらしい。
「……茉莉奈ちゃんは優しいね」
ぽつりと呟くみやびちゃんに、あたしは冷笑した。
「どこが? あたし、みやびちゃんと淡島さんの関係ぶち壊した本人だけど?」
「それはそうだけど……でも、私を置いていこうとしたのって、私に気遣ってくれたんだよね?」
「…………」
残念ながら、私がみやびちゃんを置いていった理由は違う。
だが、本当にみやびちゃんは美しいひとだ。まるで、物語に出てくる本物のお姫さまみたいだと思う。でも、彼女がお姫さまなら、あたしはなに?
あたしはみやびちゃんを見ていられず、彼女から目を逸らした。
どうやったら、彼女のような心の持ちかたができるんだろう。
「ねぇ、ちょっとだけ話できるかな?」
「……え」
「大事な話だから、場所変えよう? こっち来て」
みやびちゃんが、パーカー越しにあたしの手を掴んで歩き出す。彼女にしては、いささか強引だ。
みやびちゃんに手を引かれながら、あたしは周囲を見る。
ギャラリーがあたしたちを取り囲んでいた。無遠慮にカメラを向けてくるひともいる。まぁ、あれだけ派手に言い合ったのだから仕方ない。
それにしても、かなり大騒ぎになってしまった。これはあとから呼び出しを喰らいそうだ。
明日、学校で担任に呼び出されてくどくどと説教されるじぶんの姿を想像すると、うんざりした。
あたしたちはひとだかりを抜け、すぐ近くに乗り場があった観覧車に乗り込んだ。
パーク内のアトラクションはどれも人気だが、観覧車だけは並ばずスムーズに乗ることができるのだとみやびちゃんは言う。
「詳しいんだね」
「うん。家族で何回か来てるから」
「へぇ……」
向かい合って座ると、みやびちゃんは気まずさからか、ずっと窓の外を眺めていた。
あたしはこっそり、彼女の横顔を盗み見る。落ち着かないのかまつ毛が微かに震えているが、その横顔は場違いなまでに完璧で、まるで美術館の絵画でも見ているような錯覚を覚えた。
「……ねぇ、みやびちゃんちって、三人家族だったよね。仲良いの?」
あたしの問いに、みやびちゃんが振り向いた。
「え? あ……」
その眼差しは左右に揺れて、困惑しているように見えた。
「……うん、まぁ、仲良いよ」
「ふぅん。そうなんだ」
「茉莉奈ちゃんちは……」
言いかけて、声が途切れた。あたしが虐待されていたという淡島亜子の話を思い出したのだろう。
「……ごめん」
「いいよ。べつに」
「…………」
「…………」
話題が浮かばず、あたしはぼんやりと外の景色を眺める。
パークの向こうには、海が見えた。太陽に照らされた水面がきらきらしていて、美しい。
「……あのさ、茉莉奈ちゃんは私のこと、どう思う?」
あたしは黙って彼女を見る。みやびちゃんはあたしと目が合うと、自信なさげに俯いた。
「なに? いきなり」
「茉莉奈ちゃん、いつもひとりでいたから、ひとりが好きだったかなって。もしそうだったら、いろいろ誘ったりして、その……ごめんね」
出た。自己反省からの独りよがりな謝罪。
いい子に限って、こういうことをヘーキでする。
こういうとき、あたしは心のなかでいつも思う。
そのセリフ、どんなつもりで言ってるの?
まぁ、聞かなくてもおおよそのことは分かるけれど。
結局みやびちゃんは、『そんなことないよ。私はみやびちゃんのことが大好きだよ』と、そう言ってほしいだけなのだ。
そして、あたしがそう言ってくれるって無意識に確信している。愛されている自信があるから、こっちが気を遣ってそのセリフを吐いてるって気付かない。
「……べつに、迷惑ではなかったよ」
ほかの子だったらうんざりして無視するところだけれど、あたしは、彼女の望む答えを投げてあげる。
気だるく、窓際に頬杖をつきながらではあるけれど。それでも今回ばかりは、あたしの答えと彼女の望む答えが一致していると、みやびちゃんと過ごすことには意義があったと、そう確信しているから。
もちろん、これまであたしは、友だちなんていらないと思っていたし、今でもそう思っていることに変わりはないが。
「本当?」
「もしかして、今のが大事な話?」
もしそうなら、なんてくだらない大事な話だろう。
「いや……」
みやびちゃんの目が泳ぐ。
「違うの?」
話があるならさっさとしてほしい。観覧車はもうすぐ頂上に差し掛かる。
「……その、私ってさ……ぶっちゃけ女子からはきらわれるタイプかなって思って」
「……そう?」
むしろ好かれまくっている気がするが。
「昔からあんま、空気? みたいなのが読めなかったし」
それは仕方ない。見た目がいいから、多少ワガママでも許されてきたのだろうから。
「私さ、友だちがいなかったことってないんだ。新学期はみんなどきどきするっていうけど、いつもみんなのほうから声かけてくれるから、すぐ友だちもできるし。……だから私、亜子が言ってたいじめとかは経験なくて。亜子の気持ちは、理解できない」
そりゃそうだろう。彼女ほどの美貌があれば、男も女も関係なくみんな親しくなりたがる。興味を持つ。
人間は所詮、美しいものが好きだ。あくまで美しいもの、だが。美しいと可愛いは違う。
あたしは、前に落ちていた髪を乱雑にうしろ側に払った。
「いいんじゃない。いじめられないに越したことないじゃん」
「本当にそうかな……」
みやびちゃんが俯く。一瞬見えたその表情は、不満そうだった。
「私に声をかけてくれるひとはみんな優しい。けど、本当に私を友だちって思ってくれてるのかなって思うの」
これは長くなりそうだ。この子はいったい、あと何周観覧車を回るつもりだろう。
「……他人なんだから、多少気を遣うのはふつうだと思うけど」
子どもじゃあるまいし、気を遣わないほうがおかしい。あたしはそう思う。でも、彼女はそれが気に食わないらしい。
「私ね、小学校からずーっと仲良い子って、ひとりもいないんだ。クラスが変わって、学校が変わったら、友だち関係もそこでおしまいっていうことが多くて。兄妹もいなくてひとりっ子だし……」
ふうん、とあたしは相槌を打つ。
というか、それなら私もいないけど。それってそんなにおかしいこと? 気にしたこともなかった。
「昨年、仲良くなった子がいたんだ。アニメが好きで、大人しい感じの子。でも、私の周りに派手な子たちが集まるようになったら、どんどん疎遠になっていって」
「ふぅん、そう」
相手の子の気持ちは、分からないでもない。みやびちゃんは目立つから、陰キャは近寄り難いのだろう。
「その子にね、言われたの。他の子たちに目をつけられたくないから、もう話しかけないでって。クラスのなかで必死に居場所を守ってる彼女と私は、違うんだって言われた」
みやびちゃんはとうとう、ガラス玉のような目から、ぽろぽろと涙を流し始めた。マジか。
「私だけ大好きでも、ぜんぜんうまくいかない。だから、今年こそはちゃんとした友だちがほしいって思ったの。本当は、亜子の本音は気付いてたよ。でも、これから向き合っていけば、ちゃんと仲良くなれるかもって……そう思ったんだ」
みやびちゃんが俯く。
あたしはそれを見て、バカだなぁと思う。そんなもの、本人の意図は関係ない。
だって、彼女は生まれた瞬間から凡人ではないのだから。
それが、どれだけ彼女に息苦しさを与えているのかは私には分からない。だが、とにかくみやびちゃんのせいではないし、みやびちゃんにはどうしようもできないことだった。
さて、なんて言おう?
あたしは、ひとりが好き。あんたの気持ちを汲んで、ずっといっしょにいてあげるっていうのはできないし、したくない。
それは彼女も分かっているはずだ。だからこそさっきの謝罪があったのだから。
それなら、彼女はいったい、あたしになにを言わせたいのだろう。彼女の目を見つめ、じっと考える。……が、まぁ、考えたところで分かるはずもなく。
ふっと、さっきのみやびちゃんの言葉がよみがえった。
『――これから向き合っていけば、ちゃんと仲良くなれるかもって』
あぁ、そういうことか。
あたしはようやく自覚した。なぜ、ここにいるのかを。
あたしは、彼女を殺すためにここにいるのだ。あたしの役目は、彼女を殺すことだった。彼女も、それを望んでた。
「……たぶん、それが間違ってるんじゃない」
みやびちゃんが涙を拭っていた手を止める。
「そもそも向き合うってこと自体、間違ってる。向き合ったって無駄。あたしたちは分かり合えない」
あたしが彼女にできることは、ほかならぬ現実を突きつけること。そして絶望させることだ。
「なんで? ちゃんと思ってることを口にすれば、すれ違ったりしなくなると思うんだけど」
そうかもしれない。でもそれは、きれいな本音を聞けたときの話。ひとの本音は、だいたい黒くて汚いものだ。そんなものを四方から真正面にぶつけられたら、よりよい人間関係なんてまず作れないだろう。
「淡島さんはべつに、みやびちゃんを騙そうとしたとか、好きじゃなかったとか、そうじゃない。ただ、本音を見せたくても見せらんなかっただけ」
みやびちゃんは少しのあいだ黙り込んで、しかし首を傾げた。
「……だからなんで? 分かんないよ。見せられないってことは、私を信じてくれてないってこと?」
違う。あたしは首を横に振る。
これは、信じる信じないの話ではないのだ。
「じぶんに自信がないの。だから、みやびちゃんにきらわれたくなくて、本当の姿を見せられない。みやびちゃんは、生まれたときから愛されて、ずっと受け入れられてきたから分からないだろうけど」
最後のひとことに、みやびちゃんが黙り込む。
彼女は、愛されている。
みやびちゃんは、学校という場所に恐怖を抱いたことがない。だから、他人の評価に恐れがない。淡島さんの劣等感の本質に気付けない。
「……じゃあ、私は、どうしたらいいの?」
みやびちゃんは項垂れるように言った。
「どうもなにも、どうしようもないよ。だってあたしたちは赤の他人。みやびちゃんは淡島さんじゃない。淡島さんの気持ちは、一生分からないんだから」
「そんな……」
「だってないんでしょ? いじめられたこと」
被せるように言うと、彼女はしゅんと怒られた子犬のように黙り込んだ。
「ない……けど。でも、それじゃあ友だちなんて一生できないことになっちゃうじゃん」
「そうだね」
「そうだね、って」
あぁ、鬱陶しい。
「あたしたちは、育ってきた環境もタイプもぜんぜん違うんだよ。分かり合おうとするほうが無謀だって」
「そんなことないよ。私は……!」
しつこいな。
これは、やんわり伝えただけでは納得してくれなさそうだ。あたしは仕方なく、トドメを刺してあげることにした。
「じゃあ言うけど、淡島さんに本心教えてって言ったとしてよ。たとえばみやびちゃんの悪口が呆れるほど出てきたとしても、みやびちゃんは、本音を言ってくれてありがとう、あなたの気持ちは分かったから、これからはちゃんとした友だちになろーって思えるわけ?」
みやびちゃんが息を呑む。
「ひとの生きかたを否定して、じぶんの生きかたを見せつけるのは簡単だよ。けど、じぶんの気持ちを優先させるってことは、彼女の生きかたを曲げさせるってこと。それに責任をとらなきゃいけないってことだよ。淡島さんと友だちになりたいなら、みやびちゃんは、彼女のぜんぶを受け入れなきゃいけない。最後まで、見捨てることなく。たとえ彼女がどんなにクズだったとしても。なぜなら、踏み込んだのはじぶん自身なんだから」
みんな、それができないから、ある程度の仮面を被って、テキトーに生きている。相手に合わせて、本音を呑み込んで。そのほうが楽だから。
「それにさ、みやびちゃんってあたしたちにずっと遠慮して、本音見せてなかったでしょ? 本音を見せてくれないひとに、相手が心なんて開くわけないじゃん」
ダメ押しにもう一撃くらわせると、みやびちゃんは黙り込んでしまった。俯いて、唇を噛み締めている。
あーぁ。泣くかな。
やめてほしい。まるであたしがいじめているみたい。
やっぱりニガテだ。こういう、無自覚にじぶんの正しさを訴えてくる清潔な子。
俯く彼女を見て、改めて思った。
それからしばらく、あたしたちは無言のまま外の景色を眺めていた。
ほどなくして、ゴンドラが地上に到着する。
あたしはみやびちゃんより先に降りて、そのまま歩き出す。
さて、これからどうしようか、と思っていると、みやびちゃんが「ねぇ」と声をかけてきた。
「茉莉奈ちゃんは、だれのことも受け入れたくないからひとりでいるの?」
足が止まる。
「ごめん、でも、ずっと気になってたんだ。茉莉奈ちゃんって、本当は男の子のこともあんまり好きじゃないでしょ?」
あたしは振り向く。
「……なんで?」
「なんとなく」
「まぁね。ひとりは気楽だし」
男は暴力的だし、女は面倒。
あたしは赤の他人にじぶんを見せたいとか知ってもらいたいなんて思わないし、どこの馬の骨とも分からない他人を受け入れるつもりもない。
友だちを作るのは義務じゃない。だったらあたしはいらない。
男もそう。適当に相手をしてやって、飽きたら捨てる。捨てられる前に捨てる。それでじゅうぶん、暇は潰せる。
そう、あたしはみやびちゃんに告げる。
「……そっか」
そう言うと、みやびちゃんは笑った。そして、おもむろにあたしの手を掴んだ。
「なに?」
あたしは眉を寄せて、みやびちゃんを見上げる。みやびちゃんは、じっとあたしを見下ろしていた。
「大事な話があるって言ったけど、今してもいいかな?」
「え……う、うん」
驚きつつも頷く。大事な話とは、さっきの友だち関係の悩みではなかったのか。それならば、さっきのはなしはなんだったのだ。
「私ね、ずーっと前から、茉莉奈ちゃんに聞きたいことがあったんだ」
「……なに?」
なんとなく、いやな予感がした。そしてそれは、当たっていた。
「――茉莉奈ちゃんって、私のパパとどーゆう関係?」
私の視界の端にあったジェットコースターが、カラフルな悲鳴とともに頂上から真っ逆さまに落ちていった。
***
「……なんのこと?」
数秒後、ジェットコースターの悲鳴が引くのを待ってから、私はそう返した。
「私ね、前に見たことあるんだ。泉町商店街のバス停の前で、茉莉奈ちゃんとパパが腕組んで歩いてるとこ」
「…………」
みやびちゃんはそう言って、スマホ画面を見せてくる。画面には、薄暗くなった街の風景が切り取られている。ネオンの下で、華やかな化粧をした女がオッサンと腕を組んで歩く姿が写っていた。紛れもなく、あたしだ。
「……えーなに、このオッサン、みやびちゃんのパパなの? 似てないね?」
あたしは努めて冷静に、そう返す。
「……そっか。あくまで知りませんでした、を貫き通すつもりなんだ」
みやびちゃんは、一度悲しげにまつ毛を震わせて、すっと表情を消した。次の瞬間、彼女の顔には、乾いた笑みが浮かんでいた。
正直、彼女については引くぐらい純粋だと思っていたのだが、どうやらあたしが間違っていたらしい。こんな顔もできるのか、と変なところで感心してしまう。
「でも、そんな演技しなくていいよ。私、知ってるから。茉莉奈ちゃんが私に復讐しようとしてること」
ねぇ、と、みやびちゃんがあたしに顔を寄せてきた。
「私のお母さんって、茉莉奈ちゃんのママなんだよね?」
「…………」
「ね?」
ダメ押しのようにもう一度訊ねられ、あたしは笑った。
「なぁんだ、つまんない」
あたしはゆっくりと瞬きをして、目を開ける。
「そうだよ。あたしを捨てた女が、みやびちゃんの新しいママ」
その瞬間、ごくっと彼女の喉が鳴った。
「ってことはあたしたち、血は繋がってないけど姉妹ってことになるのかな?」
あたしはわざと呑気に笑ってやる。
「ねぇ、みやびちゃん。どこから知りたい?」
これは、あたしとみやびちゃんの物語だ。
あたしはずっと、母親の行方を探していた。
あたしを捨てた母親を。
理由は、ほかでもない復讐のため。
あたしはずっと、復讐するために生きている。
母親を見つけたのは昨年の冬のことだった。あろうことか、場所は学校。
うちの高校は、冬になると学年問わず三者面談がある。一年のとき、三組だったあたしは、担任と二者面談をした。保護者代わりである叔父に日時と時間を伝えたものの、当日、来なかったからだ。そんなことだろうとは思っていたから、前もって担任教師にも伝えていたし、あたしも担任教師も、特段対応に慌てることはなく、ふつうに二者面談が始まって、終わった。
母親と再会したのは、二者面談が終わって、廊下に出たときだ。といっても、あたしが一方的に見かけただけだが。
二組で同じく行われていた面談の風景がちらりと目に入った。面談をしていたのは知らない女子だったけれど、きれいな横顔だなと思って、そのまま眺めていた。そして、自然な流れでその子の母親を見た瞬間、あたしは凍りついた。
見知らぬ女子生徒と親密そうに肩を並べて、担任教師に愛想のいい笑みを向けていたのは、他ならぬあたしの母親だったのだ。
母親は、再婚していた。新しい夫には連れ子がいて、それが、みやびだったのだ。
再婚したことについては、なんとも思わなかった。母親が男を作って出ていったことも、あたしより男を取るひとであることもいやというほど知っていたから。
だけど、あたしは知らなかった。
母親が、だれか知らない女の母親でいることを。あたしと同じ歳の少女の保護者となっていることを。
あたしを捨てた女が、血の繋がりもない女の、保護者面をしている?
ふざけんな。
「待って」
そこで、真実を語っていたあたしを、みやびちゃんが遮った。
「捨てたって……違うよ。お母さんはただ、茉莉奈ちゃんのお父さんと離婚しただけでしょ? 親権がお父さんになっただけでしょ?」
そう、消え入りそうな声で、あたしに反論する。
「は?」
笑っちゃう。
「あんた、淡島亜子の話聞いてた? あたし、虐待されてたんだよ?」
あたしは苛立ちを露わにしながら、パーカーの首元をぐっと下げる。
まだ少しひんやりとした春の空気が、優しくあたしの肌を撫でていく。
みやびちゃんの目には、痕が映っているはずだ。あたしがあの女につけられた、凄惨な火傷の痕が。
みやびちゃんはあたしの胸元を見て眉を寄せ、顔を背けた。
「そうやって汚いものから目を逸らすの、あんたもあの女と同じね」
挑発すると、みやびちゃんのこめかみがぴくりと動く。そして、ゆっくり、あたしへ視線を戻した。
そうよ。ちゃんと見なさいよ。あたしは、あんたの母親にこの痕をつけられたんだよ。
「ねぇ、みやびちゃん。あたしね、許せなかったの」
変わり果てた母の姿が、許せなかった。
あたしのことは愛さなかった女が、みやびちゃんを愛しているなんて。男にしか興味なかった女が、幸せな家庭の中心にいるなんて。
「だからね、今年、みやびちゃんと同じクラスになったときは、運命だと思ったよ。ようやく神さまも、あたしを愛する気になってくれたんだってね」
あたしはうっそりと笑う。一方でみやびちゃんは、どんどん青ざめていく。
「……じゃあ、私と仲良くしてくれたのは、ぜんぶ復讐のためだったってこと……?」
あたしは笑顔で頷く。
「うん、そう」
あたしはあたしの目的のために、みやびちゃんと友だちのふりを続けた。
淡島亜子に嫉妬されてることは気付いていたけど、そんなこと、どーだってよかった。あたしのなかでの最優先事項は、朝野みやびの家庭をぶち壊すこと。ただそれだけ。
「あのね、いいこと教えてあげる。みやびちゃんのパパとうちの母親はね、ガールズバーで出会ってるんだよ。ちなみに、あたしが今働いてるとこ」
みやびちゃんが驚きの表情を見せる。
絶望してる絶望してる。そうだよね。まさか、そんな場所で両親が出会っていたなんて思わなかったよね。かわいそー。
でも、男女なんてそんなものなんだよ。あんたは夢見すぎ。もっとしっかり現実を見たほうがいい。この腐った世界の現実を。
「あたしの母親はクズだったけど、調べてみたら、みやびちゃんのパパもなかなかクズだよねー。女好きで、浮気性で。ウケる」
「……それで、茉莉奈ちゃんは最終的にどうするつもりだったの」
はぐらかそうか、最後まで暴露するか。少し考えてから、あたしはまた話し出す。
「みやびちゃんはさぁ、なんであたしがラパンでバイトしてたと思う?」
質問を投げられると思っていなかったのだろう。みやびちゃんの瞳が困惑気味に左右に揺れた。
「……お母さんが、働いてたから……?」
「惜しい!」
「じゃあなによ」
みやびちゃんが感情的に聞き返す。
「あんたの大好きなパパが通ってるからだよ」
「……パパ?」
「そう」
今日のあたしの喉は絶好調のようで、のど飴も舐めていないのに滑らかに滑ってくれる。
「あんたのパパが通ってたから、あたしは年齢を偽ってラパンでバイトを始めた。あんたのパパに近づくためにね。にしても、男って若い女が好きだよねぇ。あんたのパパ、すぐにあたしのこと気に入ってくれたよ。じぶんの奥さんの子どもとも知らないでさ」
私はふぅ、と息をつくと、前髪をかきあげた。みやびちゃんは呆然としたまま、微動だにしない。
「そのうちホテルに行って、既成事実でも作ってから、あの女のこと、あたしのこと、ぜんぶぶちまけてやるつもりだった。それで、ホテルでの写真をあの女に見せつけてやるつもりだったのにさ」
失敗した。淡島亜子のせいで。
あたしはスマホを見る。担任教師からの着信が、十件以上入っていた。おそらく、あたしと淡島亜子が起こした炎上騒ぎを聞きつけたのだろう。
教師たちがあの炎上動画を見ているとすれば、あたしのバイト先についても、学校側に露見していることになる。すぐにバイトもクビになることだろう。
残念ながら、あたしの復讐劇はここで幕を閉じる。
ちょっと想定外ではあるものの、あたしの心は案外スッキリしていた。みやびちゃんのパパがクズってことを、みやびちゃんに暴露できたからだろうか。
「……さて。話は以上。どう? これで満足?」
あたしはみやびちゃんに問いかける。
みやびちゃんはしばらく顔を伏せていた。泣いているのだろうか、と思ったが、違った。
「……うん。満足」
顔を上げた彼女は、口角を上げて笑っていた。不気味なほど上機嫌に。
「……なに、笑ってるわけ?」
目の前のみやびちゃんがいつもの彼女と別人のように思えて、背中を変な汗が伝う。
「ごめんね。茉莉奈ちゃんの本音が聞けたから嬉しくて」
「は……?」
「ねぇ、私、ちゃんと聞いたよ。茉莉奈ちゃんの本音。聞いたから、友だちになってくれるよね?」
なにを言い出すのかと思えば。
「……あんた、バカ? 今の話聞いてた? あたし、あんたんちをぶち壊そうとしてたのよ?」
間違いなく、今の暴露のあとでする話ではない。この子、頭がおかしいんじゃない?
「分かってるよ。でも、実を言うと私、ずっときらいだったの、お母さんのこと。香水臭いし、派手好きだし、イタイっていうか。でもパパが選んだひとだからって思って、我慢してた」
ホントはお母さんなんて呼びたくなかったし、お弁当も食べたくなかったんだよね。
みやびちゃんは可愛らしく笑いながら、あたしに言う。
これが、彼女の本音。
なんでだろう。あんな女、今さらどうだっていいし、だいっきらいなのに、なんか、みやびちゃんがムカつく。
あたしはみやびちゃんから目を逸らす。
その瞬間顔に影が落ち、あたしは顔を上げた。すぐ目の前に、みやびちゃんの美しい顔がある。みやびちゃんは笑顔であたしに言った。
「ね、私もちゃんと本音を言ったよ。これって、私も茉莉奈ちゃんも、お互いのために生きかたを曲げたってことだよね? つまり、お互い責任を取らないとってことだよね?」
「は……?」
本音? 責任? いったいなんの話?
訊こうとしたとき、みやびちゃんが静かに言った。
「だから、なってくれるよね? 私の、ほんとの友だちに」
「みやびちゃ……」
あたしが彼女の名前を呼び終わる前に、手を掴まれた。今にも鼻先が触れそうなほどの距離で、みやびちゃんの瞳があたしを射抜く。みやびちゃんは目を見開き、あたしを凝視している。
「茉莉奈ちゃんは私のぜんぶを受け入れなきゃいけない。最後まで、見捨てることなく。たとえ私がどんなにクズだったとしても。なぜなら、踏み込んだのは茉莉奈ちゃん自身だから」
「…………」
ようやくみやびちゃんの意図に気付く。彼女は意趣返しをして、あたしを縛りつけようとしていた。
これはいささか、想定外だ。彼女がここまで友だちというものに固執するとは思わなかった。呆れてもはや、ため息しか出てこない。
「…………あんたって、淡島亜子以上に変わってるよね」
「そう?」
満面の笑みが非常にうざい。というより、怖い。
「ねぇ、今から茉莉奈って呼んでもいい?」
「どーぞご自由に」
テキトーにあしらうと、みやびちゃんがあたしの腕に絡みついた。
「茉莉奈も、私のことみやびって呼んでよ!」
「ハイハイ」
「ハイハイって、ねぇ。今、呼んでよ」
しつこい。
無視しようとしたら、みやびちゃんがあたしの腕を振り回し始める。ウザいし痛い。
ハイハイ、言えばいいのね。
「……みやび」
仕方なく呼んであげると、みやびは顔をくしゃっとしてみせた。名前を呼んだだけなのに、なんでこんなに嬉しそうなのかしら。この子、彼氏できたらヤンデレになるタイプかも。
あたしは将来みやびの恋人となるであろうひとにご愁傷さま、と心の内で唱えた。
「よし! じゃあ仲直りも済んだところで、そろそろ亜子のこと探しに行く?」
よし、の意味も、じゃあ、の意味も分からないが、まぁいい。
「行けば?」
どうぞご勝手に。あたしには関係ない。
「行けばって……違うよ? 茉莉奈も行くんだよ?」
「いやいや……なんであたしが」
あたしはみやびに強引に絡められていた手をやんわり外し、距離をとる。歩幅一歩分ほど空いた。
そのまま、あたしは彼女から離れようと試みるが、なにしろ、リーチが違う。呆気なく距離は縮められ、再びみやびに腕を掴まれてしまった。
「だって茉莉奈、私のことはきらいだったかもしれないけど、亜子のことはべつにきらいじゃなかったでしょ?」
「はぁ? なに言ってんの。だいっきらいだし、あんなやつ」
この子はさっきの大喧嘩を見ていなかったのだろうか? それとも忘れた?
思いっきり吐き捨てると、みやびはふふっと笑った。
「そんなことないよ。だって、きらいならふつう隼くんと別れさせたりしないでしょ」
あたしはぎろりとみやびを睨む。
「なんの話?」
みやびは、私は知ってるよ、みたいなドヤ顔を向けてくる。
「茉莉奈ってなんだかんだ、優しいよね」
あたしはみやびから目を逸らした。
あぁ、もう。鬱陶しい。
あたしは懲りずに絡みついてくるみやびを引き剥がしながら、うんざりと言う。
「……あたしはただ、あの子があまりにも良い子ちゃんぶってるから、その面の皮を剥がしてやりたくなっただけ」
「ウソだ。茉莉奈は亜子のこと、本当は結構大好きだよね?」
「バカなの?」
有り得ない。あんな自己中。勝手にひとの秘密バラしやがって。あー思い出したら腹立ってきた。
睨みつけると、みやびはふと真剣な顔つきになった。
「……ねぇ、茉莉奈。私、茉莉奈に言われて、考えたよ。それでなんとなく分かった。私、これまで友だちに不満を抱くのっていけないことだと思ってた。でも、違うよね。好きでも不満のひとつくらい、あっていいんだよね」
「そりゃそうでしょ。相手のぜんぶを好きじゃなかったら、好きって言えないとでも思ってたの?」
「バカだね、私」
「そうだねー」
話していたら、あたしたちの前方にいたキャラクターの着ぐるみと目が合ったような気がした。それはやはり間違いではなかったようで、キャラクターはコミカルな動きであたしたちに近づいてくる。
キャラクターはあたしのところまで来ると、おもむろに黄色の風船を差し出してきた。いらない。無視していたら、みやびちゃんがあたしを小突いたあと、笑顔で受け取った。
「……だれかを妬んだり憎んだりすることは、当たり前の感情だよ」
そもそも、不満がないほうが異常だと私は思う。友だちなんて所詮他人だ。合わない部分は必ずある。もちろんそれは、友だちに限った話ではないけれど。
「私、茉莉奈が私にしたこと、許せないし許さない。でも……私がもし、茉莉奈の立場だったら、同じことをすると思う。だから私、そう思うことを許したい。じぶんにも、相手にも」
だからこれは、妥協とかじゃない。ぜんぜん違う。
そして、みやびは力強く言った。
「私は、亜子のことも茉莉奈のこともだいっきらいだけど、そこそこ好きだよ。少なくとも、クラスのなかでは、いちばん好き」
息を呑む。
だいっきらい。
間違いない彼女の本音。
でも、
そこそこ好き。
これもきっと、彼女の本音だ。
みやびがあたしの手をとる。つくづく、彼女はあたしに触れるのが好きみたいだ。
「ねぇ、茉莉奈はこれからどうする?」
私は、少し考えてから、
「……任せる」
そう返すと、みやびはにっこりと笑った。
可愛い。そうだ、そういえばこの子は可愛いんだった。メンタルが強過ぎて、忘れてたけど。
「……ま、さすがはあの女の娘ってことね」
小さく呟くと、みやびが振り返った。
「茉莉奈もね」
ドヤ顔で、そう返された。
可愛くてメンタル鋼で、さらに地獄耳? こわ。