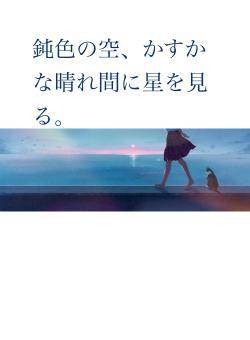私はたぶん、ひとよりも恵まれた人間なのだと思う。
両親は再婚で、私とお母さんは血が繋がっていないけれど、それでも可愛がってもらってる。
学校でも、私はいつだってクラスのなかでいちばん人気のグループに入れてもらえた。
もちろん、いじめられたことなんて一度もないし、なんなら友だちの作りかたも知らない。だって、男女問わずみんなのほうから話しかけてきてくれるから。
男の子に好きって言ってもらったことも、何度もある。
みんな基本的にすごく優しくて、気を遣ってくれる。
……でも、ときどき、みんなの笑顔が仮面に思えるときがある。
みんな、私の前では笑顔だけど、うしろを向いたとき、本当に笑っているのだろうか、って。
もしかしたら本当はぜんぜん笑ってなんていなくて、それどころか本音すら打ち明けてくれていないんじゃないか、って。
私に本音を言ってくれてる子って、今までどれくらいいたのかな……。
***
「――ねぇねぇ。よかったら、連絡先交換しない?」
高校二年の春。
私は、新学期いちばんに声をかけてくれた、うしろの席の女子と友だちになった。
彼女は名前を淡島亜子ちゃんといって、華やかな子だ。
長い髪の毛先はコテで丁寧に内巻にしていて、ちょっといい匂いがするから、香水もつけているらしい。
休み時間はよくファッション誌を読んでいて、お弁当はいつも小さめ。
放課後、どこかに寄り道してなにかを食べようってなったとき、いつも半分こしない? って言ってくる。
少食できらきらした可愛いもの好きの、ザ・女の子みたいな感じの子だ。
「ねーみやび、今日部活?」
放課後、先生が教室を出ていくと同時に、うしろの席の亜子が私の肩を叩いた。
「ううん、今日は休み」
振り返って答えると、亜子の顔がパッと明るさを増す。
「なら、ちょっと寄り道していかない?」
「いいよいいよ、どこ行く?」
私は笑顔で返事をする。
「私今金欠で、できればカフェあたりがいいんだけど……どう?」
亜子がうかがうような視線を私に向ける。
亜子はたまに、私の顔色を気にするような態度をとる。そしてそれは、私にだけではなくて、ほかの子たちに対しても同じ。
なにかに怯えてるみたいに、というか、すべてのひとと一線を置いているような、そんな感じ。
行先は私に決めてほしいってことなのかな?
ただ気を遣っているだけなのか、それともほかの理由があるのか。亜子は特に、本音が見えないときがある。
本音を言えるほどの関係に、私たちはまだなれていないということなのかもしれないけれど。
心のなかでほんの少し寂しさを感じながらも、私は笑顔で頷いた。
「じゃあ私、スタバ飲みたいな!」
「いいね! じゃあスタバ行こ!」
「やったー!」
亜子は、どうして私に声をかけてくれたのだろう。
やっぱり、外見が大きいのかな。
少し複雑だけど、そのおかげで亜子と友だちになれたのなら、喜ぶべきなのだろう。
スタバに入り、フラペチーノを注文して空いている席に座る。その間、話が途切れることはなかった。
「最近なににハマってる?」
「曲はなに聞く?」
「アイドルとか好き?」
亜子は聞き上手のようで、続けざまに質問をくれた。
「えっとねー……」
次第に話が盛り上がってきて、笑い声が大きくなっていく。ふととなりの席の女性と目が合い、私たちが今いる場所がカフェであることを思い出した。慌てて我に返り、声を抑えて訊ねる。
「ねぇ、亜子ってさ、一年のときはだれと仲良かったの?」
さっきから私ばっかり話してしまっている気がして、今度は私から亜子に話を振る。
亜子は少し気恥ずかしそうにはにかんで、話し出す。
「知ってるかなー? 市野桃果っていう子なんだけど、今は七組で」
七組といえば、たしか、一年のときに仲が良かった綾とみこと同じクラスだ。
「知ってる知ってる! 昨年の後夜祭でバンドしてた子だよね? 軽音部の」
明るいロング髪の、人前に立つのが大好きといった感じの子だ。たしか一年の後夜祭で、先輩たちとバンドを組んで歌っていた。中学も違うし、話したこともないけれど、顔ぐらいは知っている。
「あーそうそう。もうあのバンドは解散しちゃったらしいんだけどね」
「え? そうなの?」
驚いて顔を上げると、亜子は若干呆れた口調で言った。
「桃果、あのバンドのギターの先輩と付き合ってたんだけど、別れたらあっさり退部してサッカー部の男子と付き合ってるよ」
「そ、そうなんだ……すごいね」
高校生になると、周りはどんどん大人になっていく。
だれかとだれかが付き合ったとか、別れたとか。私にはまだ未知の世界だ。
話の流れで、亜子の彼氏の名前を聞いたときは驚いた。
遠山隼。
サッカー部でイケメンだとよく噂になっているひと。私自身、同じクラスになったこともないし、彼について詳しいわけではない。
ただ、告白されたことが一度だけあった。
私に告白してきたのは、たしか一年の冬休み直前の頃。同時期にとなりのクラスの女子も告られたとか騒いでいたから、あぁそういうひとなんだなぁと思って、断った。
特別視されることはきらい。だけど、軽視されるのもいや。
「亜子は……彼のどこが好きなの?」
「えー……」
亜子が恥ずかしそうに笑う。
噂のこともあって、私は正直なことを言うと、彼に良い印象は持っていなかった。
しかも、よくよく話を聞けば、亜子が告られたのも同時期だとか。
亜子の様子をうかがうけれど、彼女はその噂については知らないようだ。前半クラスで噂になっていただけで、全クラスまで広まってはいないのだろう。
言うか言うまいか悩むが、亜子の様子を見るかぎり、幸せそうに見える。始まりはどうあれ、当人同士が幸せなら、私がとやかくいうことではない。もし言うにしても、もう少し関係ができてからのほうがきっといい。
私は彼の噂について、黙っておくことにした。
「だって隼くん、かっこよくない? 人気者だし」
「かっこいい……?」
「うん!」
その言葉はまるで、じぶんへ向けられた刃のように、私の心臓を突き刺した。
かっこいいとか、人気者とか。そんな理由? そんな理由で、恋ってするものなの?
じゃあ、これまで私に告白してきた男の子たちはやっぱりみんな、私の外見だけで……。
「ねぇ、みやびは彼氏いないの?」
亜子から問われ、私は顔を上げる。
「私? いないいない。私、恋とかしたことないし」
苦笑混じりに答えると、亜子が前のめりになる。
「そうなの? でもすごい告白されるんじゃない?」
「んー……ぶっちゃけ、今はあんまり恋愛に興味ないんだよね」
本心だった。私はあまり、恋愛にいいイメージを持っていない。
だれかに好きって言ってもらうことはあるけど、そういうとき、いつも相手は私の顔を見ている。
その目を見て思う。
このひとは、もし私が事故に遭って顔がぐちゃぐちゃになったとしても、好きだよと言ってくれるのだろうか、って。
私の顔は変わらない。これ以上良くもならないし、悪くもならない。なのだから、そんなこと考えたって意味がない。頭では分かってる。だけど、どうしても考えてしまう。
私の価値って、なに?
顔を褒められるたび、人格を否定されている気になる。
終わりのない負のループにはまりかけて、私は思考を掻き消すようにスマホを開いた。ふと、ホーム画面の左下にあるアプリアイコンに目が止まる。
『チップス』。
試しに素性を隠して始めてみたSNSだ。でも、ほとんど起動させていない。フォロワーがいないのだ。いくら呟いても、フォローしても、フォロワーは増えなかった。
私の呟きは、つまらないんだろう。
私は、ビジュアルがなければだれの目にも止まらない。だれにも相手にされない。
じぶんでも自覚してる。だって、不特定多数のひとたちに向かって、なにを話せばいいかなんて分からない。話すことなんてない。
なんでみんな、楽しそうにこんなものをやるんだろう? 承認欲求? 分からない。理解できない。
となると、みんなが欲しがる承認欲求というものが、私にはないのだろうか。
私は考える。
……違う。
たぶん私は、SNSがなくても、承認欲求が既に満たされてしまっているのだ。
フォロワーがいなくても、現実では人気者だから。みんなに愛されているから。
だから私には、SNSなんて必要ない。いいねなんてそんなもの、ぜんぜんほしくない。
私はそんな小細工しなくても愛されるから。鬱陶しいと感じるくらいに愛されているから。
「ねぇ、みやびってチップスやってる?」
「えっ?」
「チップス。知らない? 最近人気のアプリなんだけど」
亜子はじぶんのスマホを翳して、チップスのアイコンを見せてくる。
「あー……」
私はじぶんのスマホを見る。視界に入るのは、アカウントを作っただけで放置しているチップスのアイコン。やっている、と言おうかどうか、悩む。
でも結局、私はスマホ画面を暗くした。
「ううん。私、そういうの分からなくてやってないんだ」
「そっかぁ」
私は、他人のことが信用できない。
ただし、普段からひとが信用できない、というわけではない。
信用できないのは、私のことを好きと言ってくるひとのことだけ。失礼な話かもしれないが、私にぜんぜん興味ありません、っていうひとのほうがひととして信頼できる気さえしている。
女の子同士でいると、だいたい恋バナが始まる。
恋バナ自体は好きだけど、じぶんに話を振られるのは苦手。
こういうとき、恋愛に対して否定的なことを呟くと、必ずと言っていいほど「もったいない」と言われるから。
なんでもったいないんだろう。
可愛かったら、彼氏がいないといけないの?
恋愛って、そういうものなの?
亜子との会話中、つい声のトーンが下がってしまった。いけない、と思い直す。気を悪くしてしまったかもしれない。
微妙な空気が流れて、亜子が慌てて笑顔を作る。
「あっ、そういえばさ、ずっと気になってたんだけど、みやびって髪つやつやだよね! シャンプーなに使ってるの?」
察しがいい。亜子は気遣い上手のようだ。ありがたい反面、申し訳なさを感じる。
話しながら、亜子はしきりにフラペチーノのストローをかじっていた。くせなのだろうか。
「――そういえばみやびって、昨年は二組だったって言ってたけど」
「うん」
「みやびはだれと仲良かったの?」
「あー……えっと」
何気なく問われて、私は曖昧に笑う。
脳裏に数人の女子の顔がちらつく。だけど、そのうちのだれの名前も言う気にはならなかった。
「……昨年は特別仲いい子はいなかったんだ。なんていうか、一年のクラスはみんなでわいわいって感じだったから」
言いながら、目を伏せる。
本当は、違った。ひとりだけ、友だちだと思っている子がいた。けれど、それも結局思っていたのは私だけ。だから、厳密には友だちとは呼べないのかもしれない。だから、言わない。
かつてあの子に言われた言葉が蘇る。
『――学校では、あんまり私に話しかけないで』
胃のあたりがぎゅっとした。
「あー……あるよねぇ、そういうクラス。いいなぁ。うちのとこは結構ギスギスだったからさ」
「そうなの?」
「うん。いつも気を張ってるかんじだったよ。いじめとまではいかなかったけど、グループのなかでのいざこざも多くて」と亜子は苦笑する。
そうなんだ、と返しながら、少しだけ亜子に親近感を感じる。だから、訊ねてみた。
「ねぇ……亜子って、アニメとか見る?」
「えー? なに急に。見ないけど。え、うそもしかしてみやび見るの? 意外すぎるんだけど!」
なんとなくいやな言いかたに聞こえたのは、気のせいだろうか。ちょっと小バカにしたような。
その反応に、あぁ、やっぱりこの子もか、と私は軽く幻滅する。
「……見ないけど」
本当は好きだけど、たぶんそういう答えは、この子は望んでない。
「あは、だよねぇ。だってアニメってオタクが見るものでしょ。アニメ好きとか言ったら、絶対クラスでハブられるわ」
「…………だね」
やっぱり、私の感覚は合っていたみたい。
もし、私がアニメを好きだとぶっちゃけたら、亜子はなんて言うのだろう。
私のことを、どう思うんだろう……?
「まぁでも、みやびはそんな悩みとは無縁そうだよね~」
そんなことない。……そんなことないよ。
友だち関係では、私だってたくさん悩んだ。今だって、ちょっと悩んでる。
……でも、亜子の言うとおり、私はひとより恵まれているという自覚がある。
直接バカにされたり、ものを隠されたりしたこともない。だから、そんなことは思っちゃいけない。
「あは。そうかも」
私は顔に笑みを貼り付けて、亜子の言葉を聞き流す。
「亜子はさ、桃果ちゃんとは今も仲良いの?」
「あー……」
微妙な反応が返ってきて、おや、と思う。
亜子はどこか気まずそうに頬をかきながら、言った。
「ううん。廊下で会えば話す程度かな。今はもう個人的にメッセとかはぜんぜんしてない。お互い、クラスに新しい友だちいるしね」
「ふぅん、そうなんだ?」
「ん」
じっと見ていると、亜子が私から目を逸らした。その視線の流れを見つめながら、思う。
フラペチーノを飲む亜子は笑顔だったけれど、その笑顔はどこか引き攣っているように思えた。
――なにか悩みでもあるのかな。
相談に乗りたいけれど、まだ知り合って日が浅いから、遠慮しているのかもしれない。もしくは、私には話しにくいことかも。
……今はまだ、聞くべきじゃないかな。言いたくないことを無理に聞くのもよくないし。
そうだ。今日は亜子から放課後デートに誘ってくれたから、今度は私から誘ってみたらどうだろう。
今はまだ無理でも、この先もお昼を一緒に食べて、放課後寄り道したり、勉強会したり、休みの日に映画とかデパートにいっしょに行ったりして、少しづつでも仲良くなっていけば、いつかは本音で話してくれるようになるだろうか。
たまに喧嘩して、お互い泣きながら仲直りしたりできるだろうか。
亜子と私のあいだにある見えない壁を、いつか壊せたらいい。
そしていつか、亜子と心から笑い合える友だちになれたらいい。
そう思いながら、私は指先でつまんだストローを口に持っていった。
***
亜子と別れて、駅前のバス停に立っていると、バスの到着時刻である五時四十二分きっかりにバスがやってきた。
バスに乗り込むと、車内は仕事帰りの大人たちで混み合っていた。
運良く空いていた後方の座席に座り、カバンを膝の上に置く。ひと息ついてから、車内を見渡した。
乗客のなかには、既に学校を経由していたからか、ちらほら同じ星蘭高校の制服を着た学生がいた。
そのなかのひとりに、引き寄せられるように視線がいった。
赤いパーカーを着た女の子だ。
――月宮茉莉奈。
話したことはないが、同じ学校の生徒だ。
肩につかないくらいの髪は緩く巻かれていて、スカートから覗く足は陶磁器のように白く細い。
学校でもそうだが、彼女は外部のひと混みのなかでもかなり目を引く容姿をしている。
家が同じ方向なのか、よくバスでいっしょになる。
氷のように冷たい眼差しをした、人形めいた女の子。スマホも見ず、居眠りもせず、ただじっとどこか一点を凝視している。
彼女は、いつ見ても異質だった。
バスが発進する。バス停をふたつ過ぎたところで、茉莉奈ちゃんが停車ボタンを押した。
『次は、泉町商店街前。泉町商店街前。次、止まります』
茉莉奈ちゃんは、私を一度も見ることなく、バスを降りていった。
「あ、おかえり、みやびちゃん」
家に帰ると、お母さんが笑顔で迎えてくれた。香辛料のにおいがする。今日はカレーらしい。
「ただいま。今日は仕事もういいの?」
お母さんはいつも仕事が忙しく、夜遅くまで帰ってこない。こんな早く家にいるのは珍しい。
「だって今日は、みやびちゃんの二年生記念日なんだもの! それで、新しいクラスはどうだった?」
「うん! 仲良い子できたよ」
笑顔で答えると、お母さんはホッとしたように微笑む。
私は、お母さんと血が繋がっていない。
お母さんは、もともと他人だったけれど、パパと再婚したことで私の『お母さん』になった。
血は繋がっていなくても、お母さんは優しいし、ちゃんと私のことを可愛がってくれる。
どんなに忙しくても必ずお弁当を作ってくれるし、服もたくさん買ってきてくれる。本当は、お昼は購買のパンでじゅうぶんだし、買ってきてくれる服も私の好みじゃないけど、お母さんが母親としてこうしたいって、そう言うから。
べつにいやなわけじゃないけど、たまにはコンビニとか、購買のものも食べてみたい。
なんて、言えないから、私はまたうそをつく。
「今日もお弁当美味しかったよ、ありがとう」
私は笑顔で空になったお弁当箱を差し出す。お母さんは嬉しそうに受け取った。
***
「――じゃあ今日は、来週末の遠足で行動するグループを決めていきます」
教卓に立った学級委員が、遠足の話を進めていく。
行先はテーマパークだ。
グループかぁ……。
亜子とは一緒になれるだろうから、残りはあと四人。
亜子はだれを誘うだろう。
私は、窓際で笑い合っている子たちを見る。ちょっと派手めなバスケ部の女子だ。ちょうど四人。誘うならあの辺かもしれない。
あの子たちのことを詳しくは知らない。けれど、いつも大きな声で周囲に気を遣わずに話していたりして、なんとなく苦手だった。
あの子たちを誘うなら……。
ちらり、と窓のほうを見る。そこには、すごく可愛らしい容姿をした女子がいた。
――月宮茉莉奈ちゃん。
今、いちばん気になってる女子。私はあの子を誘いたい。
小動物のようにくりくりと大きく、しっとりと濡れたような瞳。小柄なわりに、いつも大きめのパーカーをブラウスの上から着ていて、いわゆる萌え袖が印象的な女子だ。
その印象から、ふわふわした子なのかなと思いきや、意外と違う。
茉莉奈ちゃんはいつも男子といた。
とにかく男子とばかりいるから、女子からは男好きだと思われて、ちょっとだけきらわれているみたいだ。
だからたぶん、彼女をグループに誘う女子はいないだろう。
「ねね、亜子! 私、あの子と話してみたいんだけど」
思い切って亜子に頼んでみると、彼女の表情がわずかに強ばった。
……だよね。そういう顔になると思ってた。
でも、違うんだよ。
私は知っている。
茉莉奈ちゃんは本当は、すごく優しい子。
私は知っている。彼女の優しさを。
私は毎日、茉莉奈ちゃんと同じバスに乗って通学している。
朝はいつもいっしょ。下校のときも、たまに遭遇することがある。
クラスが同じというわけでもなかったし、彼女の噂はさんざん聞いていたから、となりの席に座っても話しかけるということはしなかった。私も噂を鵜呑みにしていたから。
彼女への印象が変わったのは、一年の最終日の放課後のできごとがきっかけだった。
バスのなかで、赤ちゃんが大泣きした。
周りにいた人たちは迷惑そうに赤ちゃんや母親を見ては、あからさまにため息をついたり、不快感を顔に出していた。
小さな舌打ちを皮切りに、いやな空気が漂い始める。
彼らの反応も、分からなくはない。でも、相手は赤ちゃんなんだから仕方ないじゃない。生まれたての子が、ときや場所を選んで泣けるわけはないんだから。
『うるせーなぁ……』
『さっさと泣き止ませろよ』
ボソッと吐かれる心ない言葉たちに、私は両手を強く握り込む。
どうしてみんな、こんなことで苛立つのだろう。
どうしてもっと、優しくできないのだろう。
私たちにだって、あの子のように小さい頃があったのに。
どうにもならないことを責めるような空気がいやで俯いていると、だれかが立ち上がった。
少しだけ顔を上げると、視界の端で見慣れた制服がちらついた。
赤いパーカーに、深緑と紺のチェックのスカート。同じ学校の子だ、と彼女の姿を目で追って、ハッとした。
立ち上がったのは、彼女だった。月宮茉莉奈。
茉莉奈ちゃんは、まっすぐ赤ちゃんを抱く母親の席へと向かっていく。
最初、私は茉莉奈ちゃんがお母さんに文句でも言うつもりかとはらはらした。が、そうではなかった。
茉莉奈ちゃんはおもむろに、鞄から小袋のお菓子を取り出した。そして、赤ちゃんのそばでかしゃかしゃと袋を握りつぶすように擦って、音を鳴らし始めた。
なにしてるんだろう……?
じっとその様子を眺めていると、それまで泣いていた赤ちゃんが不思議と泣き止んだ。まるで魔法のようだった。
赤ちゃんはぽかんとした顔で、茉莉奈ちゃんの手元を見ている。そのうち、笑い始めた。
わっ……すごい! あんなに泣いていたのに。
感心していると、
『あ……ありがとうございます』
と、赤ちゃんの母親が茉莉奈ちゃんに礼を言う。すると、茉莉奈ちゃんはこう返した。
『すごくいい子ですね、この子』
母親は泣きそうな顔をして、茉莉奈ちゃんにもう一度礼を言った。
赤ちゃんに微笑みかける茉莉奈ちゃんの横顔は、とても美しかった。
それ以来、私は茉莉奈ちゃんを見かけると、目で追うようになった。
そして、いくつか分かったことがある。
茉莉奈ちゃんの待ち受けがもふもふの猫の画像であること。その猫の動画をよく見ていること。アニメのキャラクターのキーホルダーをバッグに付けていること。
どんな男子とも、分け隔てなく接していること。
みんなの言う彼女だけが彼女の姿では、決してない。
そのことを私は知っている。
茉莉奈ちゃんは、不思議な子だ。
聞こえよがしに不名誉な噂をされても、なにも言い返さない。
けれど、決してやけになることなく、じぶんがこうしたいと思った行動をする。いざってときは、思ったことを言う。
噂が違うなら、きっといやなはずなのに。
否定したくならないのかな?
私が彼女と同じ立場なら、どうするだろう。
茉莉奈ちゃんのように、だれも分かってくれないのなら、ひとりでいればいいやってなれるだろうか。それでも毎日学校に来られるだろうか。
いや、おそらく無理だろう。
だれかが目の前で困っていても、周りの視線を気にして、見て見ぬふりをしてしまう私に、彼女のような強さはない。
知りたい。彼女のことをもっと。
大丈夫。
亜子はいい子だし察しがいいから、亜子もきっと、茉莉奈ちゃんと話せば分かってくれるはずだ。
***
一年のとき、私には水沼果歩ちゃんという仲のいい女子がいた。
同じクラスで、たまたま入学時の席がとなり同士になって自然と仲良くなったのだ。
果歩ちゃんは素朴な感じの子で、アニメや動物が大好きだった。
スマホで画像を開きながら、私にアニメの良さやあらすじを熱弁してくれた。
果歩ちゃんと過ごす毎日は、亜子といるときのような華やかさはなかったけれど、とても穏やかで、楽しかった。
なにより果歩ちゃんが、じぶんの好きなものを私と共有してくれようとしていることが嬉しかった。
――でも。
入学して一ヶ月が過ぎ、次第にクラスメイトたちと打ち解け始めてくると、果歩ちゃんはだんだん、私よりもほかの子と過ごすようになった。
理由はたぶん、私のそばに少し派手めの男女が集まってくるようになったからだ。
いわゆる『陽キャ』とか、『一軍』と呼ばれる子たち。
彼らといるのがいやなわけではないけれど、恋愛のことにあまり興味がない私は、話についていけない。
果歩ちゃんは教室の隅っこのほうで、少し地味な雰囲気の女子たち数人で固まって過ごすようになっていた。
私のことなんて忘れたみたいに、楽しげに笑っている。
寂しくて、羨ましかった。
私もあのなかに混ざりたいな、と思った。
タイミングを見て何度か声をかけようと思ったけれど、上手く噛み合わない。
果歩ちゃんは私を、どこか避けているようだった。
そんなある日、トイレの前でたまたま果歩ちゃんと出くわした。
「果歩ちゃん!」
嬉しくなって、果歩ちゃんの肩を軽く叩きながら声をかけたら、果歩ちゃんは飛び上がって驚いた。果歩ちゃんは振り向いて私を見ると、ホッと息を吐いた。
「あ……なんだ、みやびちゃんか」
果歩ちゃんの笑顔は引き攣っている。
微妙な空気を感じながらも、きっと気のせいだと心の違和感に気付かないふりをした。
だって、果歩ちゃんはいい子だ。
そう思って、私は話を続けた。
「ねぇねぇ、あのね、前に話してくれたアニメ見たよ! すごく面白かった」
「あー……ありがとう」
果歩ちゃんの反応は、やはりあまりよくない。大丈夫。考えすぎ。気にしない。
「それでさ、またなにかオススメのアニメとかあったら……」
私が話しているあいだも、果歩ちゃんはなにかを気にするように視線を泳がせている。さすがに、その視線を無視することはできなかった。
「……どうかしたの?」
話題を中断させて小さな声で訊ねると、果歩ちゃんがようやく私を見た。
「……あ、ねぇ、みやびちゃんって、今ひとり?」
「え?」
私は不思議に思いながら、首を横に振る。
「……ううん。綾たちとトイレに来たとこだけど」
「あ……そ、そうなんだ」
すると、果歩ちゃんは言いにくそうにしながらも、控えめな口調で私に言う。
「……あのね、私、綾ちゃんのこと少し苦手で……」
「え……そうだったの」
知らなかった。これまで、そうとは知らずに綾たちの前で話しかけていたから、よそよそしくされてしまったのか。
「だからできれば、学校ではあんまり私に話しかけないでほしいの」
果歩ちゃんはそう言いながらも、頻りに私の背後を気にしている。
私のほうは、少しスッキリしていた。果歩ちゃんとの距離ができてしまったことに対しての明確な理由が分かったからだ。
「……もしかして、私が綾と仲良いから? だから最近私のこと避けてたの?」
「うん……だから、ごめんね」
果歩ちゃんが申し訳なさそうに俯く。
「ぜんぜんいいよ、そんなの。むしろ、原因がはっきりしてホッとした」
私がきらわれたのかと思っていたが、そうではなかった。
良かった。
私は胸を撫で下ろしつつ、
「でも綾、いい子だよ。明るいし。なんで苦手なの?」
何気なく、訊ねた。でも、果歩ちゃんの反応を見て、言わなきゃ良かった、と心から後悔した。
「それは、相手がみやびちゃんだからだよ。綾ちゃんって、私たちみたいな陰キャのことすごくバカにしてるんだよ。アニメとか見てる奴キモいって、陰口言うの」
だから、あんまり関わりたくないの。
そう言って、果歩ちゃんは俯いた。
「それは……たまたまじゃない?」
べつに、綾をかばうつもりで言った、とかではない。むしろ、果歩ちゃんを励ましたつもりだった。
だけど私の選んだ言葉は、間違いだったようだ。果歩ちゃんの顔を見て、そう気付いた。
「……たまたま?」
「そうだよ。私はそんなことないと思うけどな……あ、そうだ。この前果歩ちゃんから勧められたアニメ、綾に教えたけど、面白かったって言ってたし」
「だからそれは、みやびちゃんみたいな可愛い子が勧めたからでしょ! 私、綾ちゃんとは同じ中学だったけど、ずっと陰口を言われてきたんだよ! いじめられてきたの!」
果歩ちゃんは睨むように私を見上げた。
「みやびちゃんはさ、可愛いし、スタイルもいいし優しいから、努力なんかしなくても学校にいくらでも居場所があるじゃん。だけど私たちは、綾ちゃんみたいな子たちにきらわれたら終わりなの! ああいう子たちの目に入らないように、息を潜めて生きてかなきゃいけないの。その苦労、みやびちゃんには分からないでしょ!」
お願いだから、もう私に話しかけないで!
果歩ちゃんはそう言い捨てて、逃げるように教室に戻っていった。取り残された私は、そのままその場で立ち尽くす。
「……なにそれ」
私には、分からない?
分からないよ。分からない。じゃあ、私はどうしたらよかった?
ただ果歩ちゃんとアニメの話をしたかっただけなのに。楽しかったことを伝えたかっただけなのに。
みんな、なにも分かってない。なんで私が勝ち組みたいに言うの?
「……私にだって、苦労くらいあるよ」
だって。みんな私がこの顔じゃなかったら、どうせ私に声なんかかけてくれなかったでしょ?
勝手に決め付けてるのは、そっちだっていっしょじゃん。
……私がこの顔じゃなかったら、きっと私には価値はない。
だって私は、みんなにとってステータスを上げるアイテムのようなものなんだもの。
私をそばに置いておけば、陽キャになれる。だからみんな、私を求める。
私はただ笑っておけばいい。それ以外はだれも求めていないんだから。
分かったよ。私は私の役目をしておけばいいんでしょ。
「みやび、おまたせー」
私は、笑っていればいい。
「もう、綾もみこも遅いよー」
「ごめんってー。ねぇ、それよりさ、さっきみやび、水沼に絡まれてなかった?」
水沼とは、果歩ちゃんの苗字だ。
「あぁ。なんかさー、いきなりアニメの話されたんだけど、私意味分かんなくて。無視しちゃった」
笑え、私。笑って、お願い。
引き攣りそうになる顔に言い聞かせる。
「うわ、マジ? やばー。あいつマジキモいよね」
「だよね~」
どうしてだろう。
綾たちといればいるほど、性格が悪くなっていく気がする。じぶんが腐敗していく気がする。
さっき見た、果歩ちゃんの泣きそうな顔が、脳裏をよぎる。
ずきずきと心が痛い。けれど、私はそれに気付かないふりをする。
だって、果歩ちゃんの言葉で傷付いたのは、私もだもん。だから、この胸の痛みはたぶんお互いさま。
「さっき男子たちとも話してたんだけどさー、今日カラオケ行きたくない?」
「あー……」
男子とカラオケ。あんまり好きじゃない。
私の反応を察してか、綾が私の腕に絡みついてくる。
「私さ、今竹元くんのこと狙ってて。竹元くん、みやびが来るなら来るって言ってくれたんだよ。だからさ、付き合ってくれるよね?」
いつもこうだ。私はだれかを釣るためのエサ。
でも、仕方ない。青春なんて、そんなものだ。
「ね、みやびも行こ?」
ダメ押しのように確認される。
「もちろん!」
なんにも知らないふりをして笑いながら、私は心のなかで果歩ちゃんに問いかけた。
ねぇ、果歩ちゃん。息を潜めているのは、果歩ちゃんだけじゃないよ。
陰口ぐらい、だれだって言われる。
さっき、トイレのなかで綾とみこが私の陰口を言っていたことを、私は知っている。