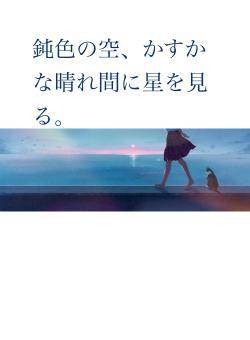「じゃあ今日は、来週末の遠足で行動するグループを決めていきます」
進級して二週間。
新一年生も無事入学し、新学期の高揚感も薄れてきた四月下旬。
朝のホームルームは、毎年恒例の遠足のグループ決めだった。
行先は毎年同じで、国内有数のテーマパークだ。基本、丸一日自由行動になる。
昨年は桃果とふたりで回ったが、今年はもちろんみやびと回るつもりだ。
「じゃあ今年は六人グループを作ってね」
学級委員の指示に、教室中から不満が噴出する。
「なんで六人確定?」
「一応親睦を深めるのが目的だから」
「えー」
――六人か……。
とりあえずみやびだけは確保しなくちゃと、私は前の席のみやびの背中をつんとつついた。みやびが振り向く。
「みやび、いっしょまわろ」
「うん! まわろまわろ!」
残りはあと四人。
妥当なのは、バスケ部で固まってる体育会系女子のグループかな。ひとり気が強そうな子がいるけど、陰キャグループを誘うよりはマシだろう。
「ねぇみやび……」
あの子たちを誘おうよ、と言う前に、みやびが私の腕に手を絡めてきた。
「ねね、亜子! 私、あの子と話してみたいんだけど」
「え?」
みやびが視線を送っているのは、私のすぐとなりのの席で気だるげに居眠りをしている女子。
――月宮茉莉奈。
よりによって、あの性悪オンナ。
え、なに。聞き間違い?
だって、フツーに有り得ないでしょ。だって、月宮さんは女子不人気ランキングでダントツ一位の女子。まぁ、私調べだけど。でもぜったいそう。
みやびは噂のことを知らないのだろうか。だから雰囲気で良さげだと勘違いして誘った?
私も噂の真偽は知らないけれど、そんなことは問題じゃない。そういう噂が広まっていること自体が問題なのだ。噂が広まるということは、人望がないということ。人望がない人間といっしょにいれば、目立つ。いっしょにいるだけで、同じカテゴリの人間だと思われる。冗談じゃない。
とにかく、月宮茉莉奈は女子からいちばんきらわれるタイプの女子であることに間違いない。彼女にかかわって得はない。悪い意味で目立つだけだ。
しかし、みやびは私の意見なんて聞かず、ちょっと浮かれた様子で月宮さんへ声をかけていた。
「ねぇねぇ、茉莉奈ちゃん」
白々とした視線を送ってみるも、気付く気配はなし。
バカみたい。なにがそんなに嬉しいんだろう。今、あんたが声をかけようとしてるのは、この教室に存在する人間地雷なんだけど?
みやびの横顔を見つめながら、私は小さくため息を漏らした。
みやびって、こういうところがある。
生まれながらに陽キャだからか、察しが悪いというか、空気が読めない感じ?
決して悪い子ではないけれど、これまで遠慮とは無縁の人生だったんだろうなってことをふつうに言う。私はこんなに気遣ってやってるのに。
みやびに声をかけられた月宮さんは、気だるげに身体を起こした。目元がほんのり赤い。本当に寝ていたような顔だ。
「おはよ。えっと……朝野さんだっけ?」
肩上くらいまでの焦げ茶色の髪は緩く巻かれていて、少し垂れた目尻とブラウスの上から着た大きめの赤いパーカーが、どこか小動物のような雰囲気がある女子だ。
アヒル口の唇は淡いリップでぽってりしていて、いかにも男子を意識しています、って感じ。それだというのに、表情は引くぐらい冷たいから異質だ。
「なに?」
出た。お決まりの、愛想の欠片もない声。声のトーンや表情、態度から、これまでだれにも気を遣ってきませんでした、ってにおいがぷんぷんする。
「遠足のグループなんだけどさ、茉莉奈ちゃんがよかったら、私たちといっしょに回らない?」
あーぁ。言っちゃった。
周囲を見ると、他の女子たちは遠巻きに呆れた視線を送っていた。
みやびはぜんぜん気付いていないようだけれど。
月宮さんは数秒ほどぼんやりと瞬きを繰り返してから、
「……まぁ、いいけど。メンバーって、朝野さんとあとだれ?」
「亜子だよ」
月宮さんが、みやびから私へ視線を向ける。私は慌てて笑みを作った。
「あ、でもね、もちろん月宮さんがよければだよ! 無理にとは言わないから」
心のなかで、どうか断ってくれますように、と強く祈る。正直、彼女とはいっしょに回りたくない。
下手に彼女と仲良くしているところを見せて、彼女をよく思っていない女子たちの反感を買いたくないし、それに――月宮さんは女子にきらわれるくらいには、整った顔立ちをしている。
顔がいい子を近くに置きすぎても逆に悪目立ちするし、私が浮く。
陽キャはみやびだけで十分だ。
察してくれと思いながら言ったら、ちょっと変な言いかたになってしまった。
「よければ、ねぇ」
月宮さんは、パーカーで隠れた手の甲に頬杖をついたまま、口角を上げた。私を見上げながら、ふふん、といった感じで。いやな予感。
「いいよ」
ほらきた。
「ほんと!?」
みやびの顔に花が咲く。
「うん。どうせひとりだったし」
うわぁ。
「やった! これであと三人だね、亜子!」
みやびが嬉しそうに振り向く。
……マジか。
「だね」と笑顔を返す。
最悪だ。
ふぅーと長く息を吐いた。
だって、息を吐き続けていないと、みやびに文句を言いたくなる衝動を抑えられなくなりそうで。
……だって。だってさ。
あと三人、どうするの。この子がいたら、確実に女子は入らないよ。男子とパーク回るとか、私、ぜったいいやなんだけど。というか男子だって、もうほとんどグループ組み終わってるし、残ってるのがだれかなんて、見なくても分かる。陰キャとヤバい奴。私がいちばんきらいなひとたちだよ。なんでもっと要領よくまわり見れないの? 私はこんなに考えてるのに……!
「……亜子? どうしたの?」
みやびが私の顔を覗き込んでくる。ハッとした。
「あっ、ごめん! いや、なんでもないよ。それよりあと三人どうしようね」
「みんなもう決まっちゃってるのかなー?」
みやびがきょろきょろと周囲を見る。
「うん……そうっぽいねー」
当たり前じゃん。こういうのは早い者勝ちなんだから、迅速に動かなきゃならないんだよ。バカなの?
顔で笑いながら、心のなかで毒を吐く。
「なぁ、まだメンバー決まってないとこあるー? 俺ら三人余ってるんだけどー」
前のほうから声がして、振り向く。
げ、と思った。
手を挙げていたのは、学級委員の安藤くんだった。安藤くんの近くには、陰キャ代表の敷島くんと、超マイペースの本村くんがいる。案の定、残っていたのは最悪なひとたちばっかだった。
「私たち残ってる! ちょうど三人」
みやびが手を挙げる。
「じゃあ俺たちで組もーぜ」
「うん。よろしく」
決まったグループメンバーを見て、私は絶望した。みやびはいいとして、他のメンバーは最悪だ。
月宮さんは女子のきらいな女子ワースト一位だし、安藤くんも真面目過ぎて融通が効かなくて話もつまらない。敷島くんは暗いし声も小さくてなに話してるのかよく分からないし、本村くんにいたっては、グループ行動すらまともにできるのか怪しいところだ。
――あーぁ。遠足なんてなくなればいいのにな。
放課後、電車が来る時間まで、私は教室に残っていた。
教室内には数人のクラスメイトたちが残っている。そのなかにみやびもいたけれど、今はあまり話す気分じゃなくて、私はひとり、自席でスマホをいじっていた。
そろそろ帰ろうかなと思っていたとき、机をとんとんと叩かれた。
顔を上げると、みやびがこちらを向いていた。どこかうかがうような眼差しで、私を見ている。
「ん? どしたの、みやび」
スマホの画面を暗くして、改めてみやびを見た。
「あの……なんか今日、ごめんね」
みやびは視線を迷わせながら、私に謝った。
「えっ? なになに? 急に」
あのことだと察するけど、気付かないふり。
「いや……なんとなくなんだけど、亜子ってもしかして、茉莉奈ちゃんのこと苦手だったかなって。それなのに私、勝手に誘っちゃったから……」
そうね。後悔する頭があるなら先に聞こうよ、ソレ。というかソレ、今さら言ってどーなんの? そういう態度が陽キャなんだって自覚してる?
これは本音。もちろん言わない。
私はいい子の仮面を貼り付ける。
「なんだ、そんなこと気にしてたの? ぜんぜんいいよ。私も月宮さんと話してみたかったし」
思っていることと正反対の言葉を返すと、みやびはホッとしたような顔をした。
「でも、ちょっと意外だったな。みやび、月宮さんのこと気になってたの?」
いつものように笑顔で返すと、みやびはそこを聞かれたことが嬉しかったのか、可愛らしく笑った。
「うん! 実はね……」
みやびは嬉しそうに声を弾ませながら、月宮さんの話を始めた。
「茉莉奈ちゃんとは、帰り道が同じ方向らしくて、ときどきバスで一緒になってたんだ」
「そうだったんだ?」
どーでもいい。と、思いつつも笑顔で相槌を打つと、それでね、とみやびが話を続ける。
「ちょうどこの前も同じバスになったことがあったんだけど、そのとき近くにいた赤ちゃんが大泣きしちゃって」
「赤ちゃん?」
なんでいきなり赤ちゃん?
私は眉を寄せた。
「そう。それでね、赤ちゃんのとなりに座ってたおじさんがすごく感じ悪い態度をお母さんにしてたの。お母さん、すごくまわりに気を遣って謝っててさ……すごくはらはらしてたんだけど。そしたら茉莉奈ちゃんがいきなりその親子に近付いてって、赤ちゃんのことあやし始めたんだよね」
「へぇ……」
「おかげで、赤ちゃんも泣き止んで、雰囲気も軽くなったんだ。それ見たらさ、うわあって思って! すごくいい子だなーって」
当時のことを思い返すように話すみやびは、聖母のように優しい眼差しをしている。
「茉莉奈ちゃんの噂は知ってたよ。だけど、私が見た茉莉奈ちゃんは噂の感じとぜんぜん違った。だから一度話してみたいなって思ったんだ」
私は咄嗟に唇を引き結んだ。でないと、思い切り暴言を吐いてしまいそうだった。
もし私がその場にいたとして、どう思っただろう。たぶん、彼女のそういう行為を見たとしても、ポイント稼ぎだ、くらいにしか思わなかっただろう。
だって、本心なんて分からない。同じバスに気になってる男子がいたからじぶんをよく見せようとしただけかもしれないし、単に子どもがうるさかっただけかもしれない。その行動の本音が、親切心であるとは限らない。
でも、みやびはそうは考えない。いいことをしているひとは、ぜったいいいひと。そういうふうに信じて疑わない。そのひとの過去とか、そのひとの目的とか、そんなことはまるで考えない。
「……みやびって、本当にいい子だよね」
反吐が出るくらい。
「えっ……そ、そんなことないよ」
視界の端に、照れるみやびが映る。
可愛いなぁ、相変わらず。どんな切り取りかたをしても、みやびは可愛い。その上心まで清らかだなんて。
あーもう。ホント、うんざりする。
「……あるよ。……私、みやびと友だちになれてよかった」
ちょっと淡々とした口調になっちゃった気がするけど、大丈夫だっただろうか?
今の私は、上手く笑えていただろうか。
「えーなにそれ、超嬉しい」
みやびは本当に優しい。優しくて、余裕がある。だからこそ、周囲のちょっとした優しさにも気付けるのだろう。
これまで、一軍でいじめてきた子たちの恨めしげな顔がよぎる。
私は……じぶんを守るだけで精一杯だった。
私はこれまで、一度だってだれかから声をかけられたことはない。興味を持つのは、いつも私から。私から声をかけなきゃ、だれも私を見ようとはしてくれなかった。
それは私が、可愛くもなくて、素直でもなくて、いいひとでもないから。
……なにそれ。そんなの、月宮さんだっていっしょじゃん。
ひとの挨拶無視するし、小バカにしたような顔で笑ってくるし、ヤな奴じゃん。なんでそんな奴がみやびに興味を持たれて、私が我慢しなきゃなんないの?
机の下、膝の上に置いていた手をぎゅっと握り込んだ。
なんか……。
バカみたい。
ひどく惨めな気分になる。
「茉莉奈ちゃんってさ、いろんな噂があるけど、実際あんま喋ってるとこ見ないじゃん? もしかしたらその噂とかも勝手なもので、本当の茉莉奈ちゃんは違うんじゃないかなって思うんだよね」
可愛くて性格もいいみやび。
どうして、私はみやびじゃないんだろう。
どうして私は、こんなに性格が悪いんだろう。
「……みやびは優しいね」
私は、みやびの顔を見ることができない。
「遠足、楽しみだね」
私は俯いたまま言った。
「うん!」
みやびの弾んだ声が返ってくる。
「じゃあ私、今日は寄るとこあるから先帰るね」
「うん、バイバイ」
お腹のあたりがキリキリする。
私はみやびと別れたあと、トイレに逃げ込んだ。胃の中身がせり上がってくるような感覚に襲われる。
気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。
たまらずスマホを取り出す。
『バッカみたい。なんなのマジで。おまえのわがまま付き合ってる私の身にもなれよ』
投稿。
『いい子ぶっちゃって、こっちはいい迷惑なんだよ』
投稿。
『あの子、人間地雷って言われてんの知らないのかな?』
投稿。
『人間地雷にじぶんから向かってくとか自殺行為じゃん。マジで草』
投稿。
『つーかなに? あのぶかぶかパーカー。男子意識してるの見え見えなんだけど』
投稿、投稿、投稿。
声に出しながら裏アカに悪口を吐き出しまくるけれど、いくら吐いても、込み上げた吐き気は止まらない。
「あぁっ! もう!!」
ふと、目に入った水道近くにあったゴミ箱を、腹いせに思い切り蹴り上げる。大きな音を立てて、豪快に中身が散らばった。
しばらくそのまま、トイレのタイルの上に散乱したゴミを見下ろす。
きったな……。
ゴミをそのままにして、蛇口を捻り、手を洗う。
鏡のなかのじぶんを見る。髪が乱れていた。手を拭き、前髪をかきあげて、息を吐く。そうしてから、手櫛で髪を整え直した。
もう一度鏡を確認する。可愛い私がいる。ちゃんとまつ毛が上がって、唇がつやつやした、可愛い私が。
よかった。少しだけ心が落ち着いた。
帰ろ、と思ったときだった。トイレの個室のドアが開いた。
キィ、と不気味な音を立ててゆっくりと開くそのドアに、私は青ざめる。
しまった。ひとがいるかもなんて考えもしなかった。音がしなかったから、てっきりだれもいないと思ったのに。
ヤバい。顔を見られる前に逃げなきゃ。
私は走ってトイレを飛び出した。
***
翌日、ホームルームの時間。
今日は、遠足の当日の日程について、グループで話し合うように、ということだった。グループごとに集まり、予定を決めていく。
「女子はなにに乗りたいとかある?」
安堂くんが当たり前のように仕切り出す。ウザいし私はこういう男きらいだけど、まあ話を進めてくれるからありがたい。
「あっ、私、落ちる系は苦手。早いだけとかなら平気なんだけど……」
すかさずみやびが言う。対して、「私はべつになんでも平気」と、月宮さん。
「淡島さんは?」
安堂くんが私を見る。ぼうっとしていた私は、ハッと笑みを作った。
「あ、うん! 私は絶叫系もお化け屋敷も大丈夫だよ!」
「へぇ、意外! そーゆうのダメなひとかと思ってた」
「えーなにそれ。ぜんぜんそんなことないよ!」
勝手にイメージつけんな、と心のなかで悪態をつく。
お化けとかいるわけないし、怖がる意味が分からない。つーか、同級生のほうがよっぽど怖いじゃん。いじめで毎年何人死んでると思ってんの?
こいつら頭悪いなぁと思いつつ、私はのんびり髪をいじる。
「私、この水のなか行くやつ乗りたいなー」
みやびが可愛く言うと、安堂くんは笑顔で了承する。
「いいよ。じゃあまずパーク入ったらここ行こっか」
「ほんと!? ありがとう!」
素直に喜ぶみやびと、その向かい側で照れる安堂くん。
男ってバカだなぁ。こんな笑顔にころっと騙されて。
哀れんでいると、視線を感じた。となりからだ。見ると、月宮さんが私を見ていた。私は笑顔を向ける。目を逸らされるかと思ったが、彼女は私を凝視したまま動かなかった。憎たらしい。
「どうしたの? 月宮さん」
わざと大きな声で言うと、彼女はようやく身じろぎをする。
「べつに?」
鼻で笑いながら、月宮さんが私から目を逸らす。なんとも優雅に、ゆっくりと。
「月宮さんも、なにか乗りたいのないの? せっかく行くんだから、一個くらい希望言ったほうがいいよ」
ムカつくから、わざと言ってやった。もちろん笑顔で。
「私べつに、アトラクションとかキョーミないし。そういうふうに進めるってことは、あんたのほうこそ乗りたいのあるんでしょ? 痩せ我慢してないで、さっさと言ったら?」
笑顔のまま固まる。
月宮茉莉奈って、なんでこんなに感じ悪いわけ?
「えー……はは。バレてた? えっとね、私も実はひとつ行きたいところがあって〜」
ムカつくから、私は笑顔のまま、
「でも、私はどちらかというと、パレードのほうが好きなんだよね」
と返して締めた。
「あ、いいね! パレードは私も見たい!」
みやびが乗っかる。
「だよね!」
「女子ってパレード好きだよね。月宮さんもパレード好きなの?」
ふたりで盛り上がっていると、安堂くんはなぜか月宮さんに話を振った。こいつ、さっきから女子としか話してない。案外女好き?
「私はそーゆうの、ぜんぜん興味ない」
「あ……そうなんだ」
ぴしゃりと言った月宮さんに、安堂くんはぎこちなく苦笑した。
話題に困っているようだったので、私は笑顔で助け舟を出す。安堂くんのことはどーでもいいけど、こういう細やかな気遣いは周囲の印象的にポイントアップになるから。
「じゃあ当日いっしょに見ようよ。きっと感動するから!」
ふん、と月宮さんが笑う。
「まぁいいけど」
「ありがとう」
なんで私が礼を言わなきゃいけないのかぜんっぜん分からないが、一応言っておく。
正直私だってパレードなんて、ぜんぜんこれっぽっちもキョーミない。
ただ、キョーミを持つほうが当たり前だからそうしているだけ。そのほうが正しいから。
女の子らしいから。
みんなに好かれやすいから。
ただ。それだけ。
バカみたい?
分かってる、そんなこと。
毎日一時間かけて化粧して、放課後と休日はバイトして。
それでなにを得られるかといえば、そのとき限りの一軍の居場所。ただそれだけ。
一軍だの二軍だのでクラスメイトを区別する意味が分からないし、そういう話をフツーにしてる一軍の連中たちもただのバカ。
だけど、学校はそのバカみたいなシステムで成り立っている。だから私たちは、どんなにバカげていると思っていても、それに抗うことはできない。
武器を持って、下の人間を殺して、殺して、上に立つ。
そうすることでしか、学校で居場所を見つけることはできないから。
――イタイ子。ぼっち。陰キャ。
そうだよ、私はそれくらい価値がない人間。分かってる。自惚れてなんかいない。
だからこうして毎日頑張ってる。私はバカじゃない。
その日の放課後、日直の日誌を届けるため、私はひとり職員室へ向かっていた。
「にしても、隼ってほんとクズだよなー」
ふと、空き教室から知っている声が聞こえてきて、足を止める。
「んなことねーだろ」
知っている声に、心臓が大きく音を立てる。
――隼くん?
おそるおそる、空き教室のなかを覗く。そこには、隼くんとほかのサッカー部の部員たちが残って話していた。私は慌ててドアの影に隠れる。口を手で覆い、息を潜める。
「今日はどーすんの? また自慢のカノジョ召喚すんの?」
「当たり前じゃん。もうすぐ俺の誕生日だし、なに買ってもらおっかなー」
「お前、カノジョにたかりすぎじゃね?」
「なに言ってんだよ、そのための彼女だろ?」
「うわ、サイテーだこの男」
「悔しかったらお前も作ればいーじゃん」
胸に抱いていた日誌をぎゅっと握る。と、そのとき。スマホが振動した。開くと、隼くんからだった。
『今日放課後どっか行かない? 亜子に会いたいよ』
よく言う。ただ利用しているだけのくせに。
隼くんが私といるのは、私の金払いがいいから。分かっている。べつに気にしない。私だって隼くんのステータスにしかキョーミないし、お互いさまだ。
『分かった! 日直の仕事が終わったら、そっちのクラス行くね!』
悩んだのは数秒。すぐに私の指先はそう打ち込んで、送信していた。
『楽しみにしてる!』
送信してすぐ、返事が来る。直後、教室から響いてくる冷笑は間違いなく私に向けられたものだった。
私は聞こえないふりをして回れ右をする。すると、目の前に月宮さんがいた。私は、びっくりして思わず「げ」と声が出てしまった。いつからいたんだろう。
「入らないの?」
月宮さんがわざとらしく私に聞く。空き教室を覗きながら。
「私は、日直でたまたまここ通っただけだから。月宮さんは、今帰り?」
「…………」
月宮さんはゆっくりとした瞬きとともに私から目を逸らす。
無視ですか。そうですか。
「……えーっとじゃあ、私は職員室に行くから、また明日ね」
そう言って月宮さんのとなりをすり抜けようとした瞬間、
「あんたさ、あれでいいわけ?」
振り向くが、月宮さんは私のことなんて見ていない。空き教室で騒ぐ隼くんたちへ視線を向けたまま。あれで、というのは、彼氏が隼くんでいいわけ? という意味のようだ。
「今の会話聞こえてたでしょ? あんた、金ヅルにされてるじゃん」
んなの、知ってるっつーの。
心のなかでは思うけれど、顔には笑みを貼り付けた
まま。
「ああいうふうに盛り上がるのって、男子あるあるじゃない? 私はべつに気にしないよ」
つーか、いちいち言わせんな。
月宮さんが失笑する。まるで私を小バカにするように。
「それってさぁ、相手のこと好きじゃないって言ってるようなもんだよね」
は?
笑顔が引き攣る。
「そんなこと……」
「ま、べつに私には関係ないからいいけど」
月宮さんはそう言って、スタスタと行ってしまった。
私はその背中を睨みつけた。
じぶんからふっかけてきといて、なんなの。マジでムカつく。
私は日誌を強く抱き締めながら、その背中にあっかんべーっと舌を出した。
月宮茉莉奈。ほんと、ヤなヤツだ。