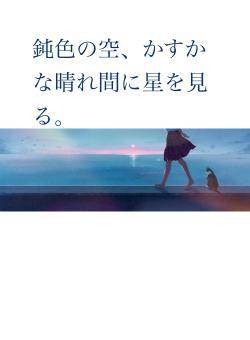「あっ、亜子ーっ!! こっちこっち! もうクラス割表出てるよ!」
朝、いつもより少し早く家を出て学校に行くと、昇降口横の掲示板の前にひとだかりができていた。
ひとだかりのなかで、一年のときに同じクラスだった市野桃果が、私に向かって大きく手を振っている。
「桃果、おはよ!」
私は桃果に駆け寄りながら、表を見上げる。が、ひとの頭が邪魔でよく見えない。これだから低身長はもう。
私の身長があと五センチ高ければ、もっと見栄えがして目立てるのに。
「桃果は何組だった?」
「私は七組だった!」
「えー、私何組だろう。ぜんぜん見えないよ〜……」
背伸びをして、クラス割表を見ているふりをする。だって、どうせ見えないから。
すると、桃果は仕方ないなぁと身を乗り出す。
「あっ、亜子は一組じゃない?」
「えっ、ほんと?」
「うん。ほら」
言われて、私は今度こそちゃんと一組の表を見る。七クラス分の表のなかからじぶんの名前を探すのは面倒だけど、一クラスの表だけ見るなら楽ちんだ。
一組の上から二番目に、たしかに私の名前がある。じぶんの名前を確認したあと、そのままほかの名前を見てみるけれど、一年のとき同じクラスだった子はひとりも見当たらない。
「うわぁ、友だちできるかな〜」
朝から少し重い気分になりながら、桃果と昇降口で上履きに履き替え、階段を昇る。
「私も。亜子と同じクラスがよかったな〜」
「ま、仕方ないよ。だってうちらの高校、七クラスもあるんだし」
一年のときに仲が良かった子とまた同じクラスになれるなんて、最初から思っていなかった。というか、考えたくもなかった。桃果とまた一年いっしょだなんて。
桃果は典型的ないじめっ子気質で、他人に当たりが強かった。もう一年同じクラスだとか言われたら、たぶん私の印象も悪くなっていたと思う。申し訳ないけど、彼女とはもう遊ぶことはないだろう。
「それでも奇跡を願うもんじゃん? あっ、てか隼くんは?」
隼くん、というのは私の彼氏だ。サッカー部に所属していて、爽やかな見た目から結構女子人気のある同級生である。
「あー……そういえば」
言われてスマホを見たちょうどそのとき、メッセージが届いた。隼くんからだ。
『おはよ! もうクラス割見た?』
見たよ、一組だった。隼くんは?
それっぽいメッセージを返し、スマホをしまう。隼くんが何組だろうが、正直べつにどうでもいい。
「隼くん?」
「うん。何組だったかって」
「朝からラブラブねぇ」
「ふふ」と笑っておく。
否定はするもんじゃない。無駄に話が続いちゃうから。
異性の話は、ほどよく切り上げるのが鉄則。
たとえじぶんから始めたわけではなくても、話しすぎると惚気けてると思われて悪印象を与えるからだ。
知ってる?
彼氏も、友だちも、親の仕事も、この社会ではぜんぶがステータス。私の価値を上げるもの。
桃果と一年間いっしょにいたのは、一軍に属するため。隼くんと付き合っているのは、みんなが羨むひとを彼氏にすれば、私の可愛さが保証されると思ったから。ただそれだけ。
階段を昇り切ったところで、私は桃果と笑顔で別れる。
あー笑顔疲れた。
固まった表情筋を解しながら、私はひとり新しい教室に向かった。
桜がちらほらと咲き始めた四月のはじめ。
私が通う星蘭高校は、今日から新学期が始まる。
新一年生が入ってくるのは今週末だから、それまでは新三年生と新二年生だけだ。
新しい教室に入る。なんだか少し落ち着かないし、見慣れない。といっても、造りは一年のときと特別なにも変わらないはずなのだが。
「おはよー!」
「おはよ、よろしくね~」
「やった、今年は同じクラス!」
「お昼いっしょ食べよ!」
あちこちから聞こえてくる新学期特有の挨拶。
黒板に貼られた座席表でじぶんの席を確認して、自席につく。
新学期は、出席番号順に座席を決められることが多い。私の席は窓際の前から二番目だった。
近くには、まだだれもいない。
私は、今のうちにクラスメイトたちの観察を始める。
窓際で楽しそうに話す女子の三人組。もさっとした黒髪を三つ編みにした地味なタイプの女子と、長い髪を低めの位置でひとつ縛りにした子、それからボブの女の子だ。
みんないい子そうだけど、ないな。
おそらく、あの子たちは三軍だろう。声をかけるのはあとからでよさそうだ。
ほかの子に目を向ける。
明らかに文化部っぽい子や、清潔感がなく声が低めのあそこら辺も陰キャっぽいからパス。
となると……今教室にいる子たちはみんな二軍以下。ぜんぜん、良さげな子がいない。
うわ、このクラスってもしかしてハズレ?
一軍キャラが多すぎて険悪ムードになるのはごめんだけど、いなさすぎるのも困る。
参ったな。
だれと仲良くなろうかと考えていると、がたんと前の席の椅子が引かれた。顔を上げると、すらりとした長身の美少女が立っていた。
お人形さんのような顔立ちに思わず見惚れていると、目が合った。
「おはよう。私、朝野みやび。ねぇ、淡島さん……だよね? よろしくね?」
座席表を確認したときにでも知ったのだろう。彼女は私の苗字を呼び、控えめに微笑んだ。
「あ……うん、よろしく」
彼女は私が挨拶を返すと、再びにこりと微笑んで、席に着いた。
華奢な背中を見つめながら、うわぁと思う。
この子は、間違いなく一軍だろうな。
長い髪はよく手入れされていてツヤツヤだし、色白でスタイルもいい。雰囲気も良さげだし、友だちになるならこういう子がいちばんだ。
スマホのメッセージアプリを開き、私はその背中に手を伸ばした。
「ねぇねぇ」
声をかけると、スマホをいじっていたらしい朝野さんが振り向く。耳にかかっていた長い髪が、振り向いた拍子にさらりと垂れる。ほんのりとシャンプーの香りがした。
「よかったら、連絡先交換しない?」
いつもの笑顔を張り付けて訊ねると、朝野さんは嬉しそうに表情を綻ばせた。
「え、ほんと? 嬉しい!」
机を挟み、お互いスマホを操作する。メッセージアプリに彼女の名前が追加されたのを確認して、私は顔を上げた。
「ねぇ、みやびちゃんって呼んでいい?」
「ふつーにみやびでいいよ。私も亜子って呼んでいい?」
「うん! よろしくね、みやび!」
よかった。これでまた一年、私は一軍にいられる。
***
新学期は、緊張する。
だって、なにがなんでも友だちを作らなきゃいけないから。
しかも、ただ作るだけじゃダメ。
これからの一年間のことを考えて、なるべくきらきらした子と仲良くなって、一軍に入るのだ。
学校という特殊な社会でやっていくには、とにかく一軍に入ること。
それ以外にはない。万が一、一軍から省かれてしまったら、その時点で学校は地獄になる。
一軍に入るには、華やかな容姿と女子に好かれることが必須。
女の目は厳しい。
つまり、デブは論外。清潔感がないのもダメ。
けばくならない程度のメイクをして、男女関係なく愛想を良くして、なんなら陰キャにも優しい顔をする。
ただし、仲良くはしない。
決して陰キャとの一線は越えないようにうまく振る舞うのだ。
威圧的にはならないように、でも、なめられないように。
勉強ができないとバカにされるから、勉強だってちゃんとして、部活も陽キャ認定されるようなきらきらしたメジャーな運動部に入らないといけない。
彼氏はいたほうがいいけれど、男とばっかいるのはダメ。基本、女子のなかで生きて、たまに彼氏に会いに行く。そうしないと、女子にきらわれるから。
いちばんに優先するのは、女子のグループで浮かないこと。でないとハブかれる。
だけど、肝心な女子同士のグループに居場所を作るのは難しい。
口を開けばだれかの悪口。なにが面白いのかも分からないオチのない話をだらだらとして、最終的には『分かる〜』連呼の共感パーティ。
居心地がいいわけでもないグループに入って、気を遣って、顔色をうかがって。
じぶんの言動が、行動が、相手にどう見られているかを過剰に意識して。
バカみたい、とじぶんでも思うけれど、仕方ない。
それが『女子』。それが、『青春』。
青春青春ってみんな言うけど、青春なんて、本当はきらきらなんてまったくしてない。
言い換えれば、青春とはデスゲームである。
勝ち残りのデスゲーム。情けも容赦もない、負けたら即死のデスゲーム。
大袈裟じゃなく、本当にそんな感じの場所。
だから私は、今日も「うふふ」と笑ってうそをつく。
青春を生き抜くために――。
***
新学期一日目は、始業式のあと簡単な自己紹介をして終了した。
自己紹介。友だちを選別する上でとてつもなく重要なイベントのひとつである。
教卓に立ったときの視線、クラスメイトたちの反応、醸し出される雰囲気、その他多くの情報で、本人がどういう立ち位置にいるか、一発で分かるからだ。
この子はお調子者で、みんなにバカにされているけれど、きらわれないタイプのムードメーカーだとか、逆に、この子はクラスで浮いてこそいないけれど、あんまり好かれてはいないな、とか。
全員の自己紹介を聞いて、確信した。
みやびと友だちになったのは、大正解。
みやびが教卓に立った瞬間、空気が変わった。
基本、女子も男子も関係なく、ひとは端正な顔のひとには興味を抱くものだ。
ちょっと可愛い、とかだと同性は対抗心が芽生えてギクシャクしがちだけど、みやびの場合はそうはならない。彼女の容姿もスタイルも、圧倒的だから。
宝石が埋め込まれたような澄んだ瞳。雪のように白い肌に通った鼻筋。ほんのり桃色を帯びた薄い唇にあざとさは感じない。
同性受けの悪いアイドル顔じゃない。同性受けが圧倒的なモデル顔。よっぽど性格が悪いとか、男好き、とかでなければ万人受けする容姿。
やっぱり、私は正しかった。
放課後になると、案の定、みやびのまわりにはクラスのほとんどの女子が集まっていた。私は遠慮せず、中心にいるみやびに声をかける。
「みーやび!」
一瞬、教室内のすべての音が消える。
みやびと、みやびを取り囲んでいた女子数人が振り向いた。いくつもの目玉が一斉に私を見る。けれど、私が見るのはみやびだけ。
「ねぇ、いっしょに帰らない?」
笑顔で言うと、みやびはパッと嬉しそうに頷く。
「うん! 帰る!」
だれも、私も、とは来なかった。まだ一日目だから、みやびと仲良くしたいとは思いつつもまだ様子を見ている状態なのだろう。
バカだなぁ。既に出遅れてるのに。
もうみやびは渡さない。
学校を出た私たちは、駅前のスタバに入った。私からみやびを誘ったのだ。
もう少し話さない? って。
みやびを探ってるのは、私もいっしょ。
ただし、みんなの前ではぜったいやらない。
教室で私は常に、私がみやびのいちばんの友だちです、アピールをする。もちろんそれは、みやびに対してではなく、クラスメイトに対してだ。そう見せることで、ほかの子は私とみやびに近寄りづらくなる。
「ねぇ、みやびってさぁ、一年のとき何組だったの?」
私は笑顔でキャラメルフラペチーノを飲むみやびに話しかける。
「私? 私は二組だったよ」
二組か。二組に知り合い、だれかいたかな。考えながら、私もストローに口をつけた。どろりとした重い液体が、ゆっくり口のなかを侵食していく。
「亜子は?」
同じように問われ、私は笑みを作り直す。
「私は五組。仲良かった子と離れちゃってさぁ……実は今日、めちゃくちゃ不安だったんだよね。だけどこうしてみやびと友だちになれて、ほんとによかったよ〜」
「えー嬉しい!」
みやびが照れくさそうにはにかむ。私もさらに笑顔になる。良かった、この子、ちょろそう。内心ほくそ笑む。
不安を吐露して、相手への依存をチラつかせる。こうすれば、だいたい相手は気を良くする。上下関係が生まれるからだ。みやびが上で、私が下。べつにかまわない。それで一軍にいられるなら、私はいくらでも媚びへつらう。だって、一軍の底辺のさらにその下には、二軍、三軍がいる。それより上に、私はいる。
「え〜嬉しい。私もだよ。新学期ってめちゃくちゃ緊張するよね!」
「分かる〜。しかも今週末実力テストじゃん。私数学がめちゃくちゃ苦手で……」
「えーじゃあさ、今度ふたりで勉強会する? よかったら教えるよ!」
「ほんと? するする! 助かる〜!」
ほらね? 相手が下だと分かった途端、会話が弾み出す。人間って浅ましい。
でも、みやびはマシなほうだ。彼女の見下しは、無意識だから。
桃果のほうが、もっとあからさまだった。わざとそういう言葉を選んで、攻撃していた。
たとえば、じぶんと違う意見が出ると、鼻で笑う感じ。まわりの話なんて聞かないし、その割になんの特技もない口だけ女。彼女の言動は、とにかく引くことが多くて、いっしょにいるこっちが恥ずかしくなることもあった。
「そうだ、昨年の写真とかないの? 見せてよ」
「いいよー!」
小一時間話してみると、さらにみやびの性格が分かってきた。
みやびはいい子だった。優しくて、素直で明るい。容姿だけじゃなく、心も美人。私とは大違い。
私は、カフェの窓ガラスに映ったじぶんを見つめる。
アイプチして、まつ毛はマスカラで盛って、眉毛もバッチリ描いてる。
化粧をとったら、ブスとまでは言わないけどいたってふつうの顔。印象なんて残らない、平凡な人間。おまけに中身は真っ黒ときた。
ガラス越しに、みやびを見る。みやびは私の視線に気付かずに、呑気にフラペチーノの味わっていた。
みやびのように、もし私が素でこの可愛さだったなら、こんな性格悪くはならなかっただろう。なんて思ってから、その考えを振り払う。
そんなことない。私だって負けてない。
だって、彼氏がいるし。男はバカだから、みんなこの顔に騙される。騙されてくれるんだから、いいのだ。これで。
私は、隼くんの前ですっぴんになったことがない。これからもなるつもりはない。
素を見せるとかぜったいムリだし、それに、わざわざ夢を壊すことないじゃん。
私は窓ガラスに映ったじぶんを睨みつけ、ふん、と息を吐いた。
そういえば隼くんからメッセージが来てるかも、と思ってスマホを開く。
「一年のときの友だち?」
みやびが訊ねてきた。私は首を振る。
「んーん、彼氏だよ」
「えっ! 亜子、彼氏いるの!?」
みやびのテンションが今日イチ上がる。
「えーっ、何組? 私知ってるかな!?」
どうやら、みやびは私に彼氏がいることを知らなかったらしい。少しは噂になってることを期待してたけど、みやびは私のこと知らなかったみたいだし、そっち系には疎いのかもしれない。
「どうだろ……サッカー部の遠山隼っていうんだけど」
「あっ、あー……知ってるよ!」
みやびは、一瞬なにかを考えるように視線を動かした。若干笑顔が痙攣した気がするけど、考えすぎだろうか。
「あれ。もしかして、知り合いだった?」
気になって訊ねると、みやびは笑って首を振る。
「あっ、いや、ぜんぜん。ちょっとカッコいいなーって思ってただけだよ」
「……そうかな? 付き合ったばっかりなんだけどね」
みやびも隼くんをカッコいいと思っていたらしい。やっぱり、隼くんの告白を受けたのは正解だった。
「ねぇ、どっちから告ったの!?」
ずいぶん前のめりに聞いてくる。みやびはミーハーなのか、恋バナが好きなようだ。
「隼くんのほうからだよ。一年のとき、同じクラスで」
「やばーい! 亜子、めっちゃ青春してるじゃん」
「そんなことないよ」
ほらね。やっぱりみんな言う。こういうのが、青春だって。
きらきらした男の子と付き合ったり、放課後にカフェで友だちと笑い合う。それが青春。
大人たちも、こういう話をすると必ずと言っていいほど『青春だねぇ』と言う。バカげてるって、だれも思わないのが不思議。
まぁ、それをだれも疑問に思わないおかげで、私も青春しているふりができているわけだけど。
「ねぇ、みやびは彼氏いないの?」
みやびの男関係を聞くなら今しかないと、私は思い切って切り出した。
「私? いないいない。私、恋とかしたことないし……」
困ったように笑いながら、みやびが言う。意外だ。
「そうなの? でも、すごい告白されるんじゃない?」
「んー……ぶっちゃけ、今はあんまり恋愛に興味ないんだよね」
「みやびって学校でも特に垢抜けてるし、ぜったい彼氏いると思ってたけどな」
「あーそれねぇ」
みやびは苦笑して、頬杖をついた。前から思ってたんだけどさぁ、と話し出す。
「女の子が可愛くなるとさ、彼氏できた? とかいうひといるじゃん? 正直、ああいうのもなんだかなーって思う。世のなか、だれかのために可愛くなりたいってひとばっかりじゃないと思うから」
「あー……分かるー……」
正直、ぜんぜん意味分かんない。
「せっかく美人なのに、もったいないとかもよく聞くけど、あれも言われるとムカつかない?」
「それなー」
なに言ってんだろ、この子。
みやびの言っている言葉の意味はイマイチよく分かんなかったから、適当に流しておく。
そもそも私は、他人の恋愛遍歴なんてぜんぜんキョーミない。でも、話題になるし、相手を知ることもできるからとりあえず聞く。
そして、話を聞いたら大袈裟にならない程度に褒めて、羨ましがっておくのだ。
そうすれば、選ばれるから。
なにに?
決まってる。一軍のメンバーに、だ。
選ばれるには、相手に話をさせることがいちばんだ。それで、じぶんの話は聞かれるまでしない。だいたいのひとが、話を聞くより話をするほうが好きだから。
青春は、弱肉強食。強い者が弱い者を選ぶ。そして、選ばれた者だけが、生き残る。
私は強者にはなれない。だから、選ばれる弱者になる。
弱者であることを認めて、強者に媚びへつらうのだ。
簡単だ、と思うかもしれない。たしかに単純だし、簡単。だけど、楽ではない。
努力して可愛くなって、さらに思うようになった。
この世界は腐ってる、と。
「あっ、そういえばさ、ずっと気になってたんだけど、みやびって髪つやつやだよね! シャンプーなに使ってるの?」
「えーなにいきなり」
うまく話題を変えて、軌道修正。
「私今さぁ、髪でめちゃくちゃ悩んでて。アイロンのせいで枝毛ヤバいんだよ」
「あー分かる! でもしないわけにいかないもんねぇ」
「そうなんだよー」
「私もね、けっこう悩んでたんだけど、最近いいやつ見つけたんだよねー」
「えっほんと? 教えてよ!」
「いいよ! これなんだけど……」
みやびがスマホを見せてくる。
つまらない。ぜんぜんキョーミのない話。だけど、最高に盛り上がったフリをして、私の新学期一日目の放課後は幕を閉じた。
身だしなみも、相手が喜ぶ会話も、ぜんぶ義務。
私が一軍でいるためには、そういう努力は必須事項なのだ。
バカみたい。
心のなかで、もうひとりのじぶんが言う。
でも、知らんぷりをする。
いつもどおり、ドリンクといっしょに、本音は呑み込む。だけど、甘ったるいフラペチーノでは、喉につまったそれはぜんぜん滑り落ちてはいかなかった。
――だから、私は発散する。
私は、みやびと別れたあと、学校から少し離れた場所にある公園に入った。
スマホを開き、最近中高生のあいだで人気のSNS『チップス』というアプリを開く。
すぐに画面が切り替わって、本アカのアイコンが出てくる。重なるようにして、本アカのアイコンのうしろにもうひとつアイコンがある。私はそれをタップした。すると、きらきらした桜貝のアイコンから一転、口がチャックになったピエロのアイコンが出てきた。
これは、私のもうひとつのアカウント。いわゆる裏アカである。
『今日はクソだるい学校初日。陰キャしかいないと思ってたけど、ひとり良さげなの発見。ただし、美人だけどバカそう笑』
投稿ボタンをタップすると、爆弾のイラストが出てくる。導火線に火がつき、読み込むほど線が燃えていく。そして、投稿が完了すると同時に爆弾が爆発する。
一連の流れを何気なく見つめる。無事、投稿できた。私は続ける。
『バカって見てるだけで落ち着く。マジ面白い』
投稿。
スマホに打ち込みながら、つぶやきが口からこぼれていく。ようやく吐き出せる。喉に詰まっていた異物が、どんどん出ていく。
はー。
少しづつ、呼吸が楽になっていく。
大丈夫。口にしたって問題ない。どうせここには、私しかいないのだから。
私はベンチに座り、裏アカでストレスを吐き出し続ける。新学期でストレスを溜め込んでいたぶん、指先に力がこもる。
『つーか学校に行く意味。ぶっちゃけ教師の授業って、塾より分かりづらい』
投稿。
『担任、三十代なのに禿げてて草』
投稿。
『キモ過ぎて泣ける』
投稿。
じぶんでもよく分からない不満をぶちまけてから、スマホをベンチに放り投げる。今日はいつも以上に気を遣ったから疲れた。もういいや。もう、文字を打つことすら面倒くさい。
錆だらけの遊具から目を逸らすと、その先にあるのは真っ青な空。憎らしいほど美しい。
ここは、公園といっても手入れがまったくされていないのか、雑草が生え放題。そのため、近所の子どもたちはまったく寄り付かない。
まぁ、そのほうが私は助かるけど。
おかげで私はこの公園に入り浸り、裏アカで愚痴を発散することができている。
『でもま、あの子とべつのクラスになったし、マジでそれだけは幸せか笑』
ピコン、と通知音がして、コメントが届く。
『きらいな子と離れられたんだ! 良かったですね』
『分かります! 私もクラス替えきらいだけどきらいな子と離れられたことだけはマジで嬉しかった記憶ある笑』
コメントをくれるのは、顔も性別も年齢もぜんぜん知らないひとたち。ネットでしか繋がらないひと。私の素顔を知らないひと。私がブスだってことを知らないから、こんな私でもマウントを取れる。
ネットのひとたちは、たくさんのいいねをくれる。私の投稿に反応してくれるし、ちやほやしてくれる。だから絡む。
『ありがとうございます〜。マジでよかったです笑』
私が一日のなかで唯一安らげるのは、SNSで愚痴っているときだけだった。
こうして刺だらけの言葉を吐いていれば、じぶんが棘を突き刺している側なのだと実感できるから。棘を突き刺される側ではないと、確信できるから。
とどのつまり、安心できるのだ。もう、あの頃の私ではないと。
***
私の心臓には、未だにいくつもの棘が突き刺さっている。
私の心臓に棘を刺したのは、小学校の同級生だった。
三ノ輪茜、山口美香、金森真奈。
今もどこかで生きているだろう彼女たちのことを、私は一生忘れないだろう。
舞台は、机や椅子、それぞれの線の境が曖昧に思えるほど、ぼんやりとした教室の一角。視界はぼんやりしているくせに、彼女たちの声だけは鮮明に響く。
『おいおい、牛乳瓶盗んだのだれだよー』
『ほんとー、返してやりなよー』
当時私は、視力が悪かったにもかかわらず、裸眼で過ごしていた。理由は、眼鏡をかけているとからかわれたからだ。
私はもともと、牛乳瓶の底のような分厚いレンズの眼鏡をかけていた。でも、クラスメイトたちが眼鏡をかけた私を執拗にからかってきたから、眼鏡をかけることをやめたのだ。だからといって、いじめは止まなかったが。
窓際から、再び大きな声が響く。
『ねぇなんか臭くなーい?』
『デブがいるからじゃん? デブってマジで公害だよねぇ』
『やだぁ』
『美香ひどーい』
私がいじめられていた理由は、容姿だった。私の場合は、太っていてさらに眼鏡をかけていたから。
性格とかじゃなく、そういう理由で、私はクラスメイトたちからいじめを受けていた。
班行動では必ず『臭いからこっちくんな』と言われ、給食の机もくっつけさせてもらえなくて、いつもひとりで食べていた。放課後の掃除の時間も、みんな私から離れて喋っているだけで、掃除なんてしやしない。教科書にはマジックで消えない落書きをされて、上履きは学校の池に投げ捨てられていたこともある。
そして、昼休みになると響く冷笑。
いじめの主犯は女子三人だったけれど、私がターゲットだと分かると、私を排除する雰囲気はすぐにクラス中に拡散されていった。
次第に、ほかの女子たちもじぶんまで巻き込まれたらたまらないと私を無視するようになって、担任の先生もいじめには気付いていただろうけれど見て見ぬふりをした。
いじめは、小学校を卒業するまで続いた。
中学校に入ると同時に、私はイメチェンすることを決意し、たくさん勉強した。
くせ毛だった髪はアイロンでまっすぐにして、怖かったけどピアスも開けた。なめられないように。
ダイエットのために食べたいものを我慢して、毎日運動をするようになった。おかげで、人並みくらいまで痩せることができた。痩せたら、周囲の女子がちょっとだけ優しくなった。
痩せたことで、わずかに声も高くなった。そのおかげか、声を出すことも怖くなくなった。低い声よりも高い声のほうが、みんなに好かれることが分かった。
部活はテニス部に入って、怖かったけどじぶんから声をかけて友だちを作っていった。
そのうち、なんとなくコツを掴んだ。
とりあえず幸せなフリをして笑って、たまに自虐をして。
だれかの悪口が始まったら、合わせる。いっしょに悪口を言って笑い、仲良しの子がいじめを始めたらそれに乗っかる。そうすることで、ターゲットになるのを避けた。
ぜんぶ、いじめられないため。
そうして、今のクソつまらない私が完成した。
でも、仕方ない。だって青春そのものがクソなんだから。
***
翌日、教室に入ると、私のとなりの席に知らない女子が座っていた。昨日の始業式にはいなかった子だ。机に伏せっているため、顔は分からない。
窓際にいた女子数人が、ちらちらと彼女を見ている。
――月宮サン、同じクラスだったんだね。サイアク……。
だれかのささやき声が聴こえた。
月宮茉莉奈。知ってる。
彼女の噂は一年のときから聞いていた。有名だった。男癖が最悪とかで。
しかも性格もキツくて、だから女子からはかなりきらわれている。
私が席に着くと、音に反応したのか、それまで伏せていた月宮さんがむくりと身体を起こした。
目が合う。私は笑顔を向けた。彼女がどれだけ女子にきらわれていようと、私は優しくする。私のために。
「私、となりの席の淡島亜子。よろしくね」
笑顔で声をかけるが、月宮さんは私を一瞥するだけでまた顔を伏せてしまった。つまり無視された。名乗りもしない。なにこいつ。
まるで、あのときの彼女たちと同じ態度。
胸にどろっとしたものが落ちる。貼り付けていた笑顔が引き攣るのを感じて、私は月宮さんから目を逸らした。
感じわる、と思っていると、みやびが登校してきた。
「亜子、おはよ!」
みやびは私と目が合うなり、笑顔で挨拶をしてくれる。
「みやびおはよ〜! 昨日はありがとね!」
私は、いつもの話し声より少しだけトーンアップさせて、挨拶を返す。
「うーうん、ぜんぜん! また行こうね!」
「行く〜!」
大丈夫。私には、みやびがいる。
ざわめくじぶんの心に言い聞かせ、私はみやびとの会話に花を咲かせる。しばらく話していると、担任が入ってきた。
「はーいじゃあ席ついて。今日はまず教材配るよー」
新しい教科書が配られる。それぞれ白紙のページがないか確認したり、名前を書いたりしているなか、となりの席の月宮さんは呑気に眠っている。
「おーい月宮、起きろ~」
先生が呆れ気味に、寝ている彼女を名指しする。
ちらりととなりを見る。
それでも起きない月宮さんに、先生がとうとうため息をつく。
「だれか起こせ~」
私は仕方なく、月宮さんの机を控えめに叩く。話しかけたくなんてなかったけれど、仕方がない。
「ねぇ、起きて」
「……んー」
月宮さんがようやく起き上がる。もちろん、私のほうはちらりとも見ない。
「月宮。初日から居眠りは印象悪いぞー」
「失礼しました〜」
先生に注意されてなお、月宮さんはマイペースに机に頬杖をついて、目を閉じていた。
だいたいの子は、曖昧な理由でいじめの標的になる子が多い。だけど、さすがにこの子はきらわれるのも分かる気がする。
空気が読めていないし、ひとの迷惑も考えてない。
あまり関わらないようにしよう、と思いながら、私は手元に視線を戻した。
***
こんな私でも、異性にはそれなりに興味がある。
隼くんとは、高一のときに仲良くなった。仲良しだった桃果と同中だった繋がりで。
優しいし、明るいし、なによりイケメンだし、みんなが大好きなサッカー部。
一年のとき、ほとんどのクラスメイトの女子が彼を見ていた。だから、それとなく桃果に彼女の存在を聞いた。
――いないけど、競争率高そうだし、やめておいたら?
そう言われて、逆に燃えた。
たぶん、桃果も隼くんのことが好きだったんだと思う。なんとなく分かってた。だけど気付かないふりをした。だって、桃果より私のほうが可愛い。外面もいいし、隼くんのなかのポイントも高い気がする。
メッセージアプリのIDを交換してからは、放課後も毎日メッセージを交換した。あっという間に桃果より仲良くなって、最終的に冬休みに入る直前くらいで隼くんのほうから告白してくれて、今に至る。
桃果に対してはちょっと罪悪感がないわけではないけれど、でも隼くんが選んだのは私なんだから仕方ない。
「なぁ、なんか腹減らない?」
「え? そう?」
放課後、珍しく部活がない隼くんとふたりで帰っていると、彼が言った。どこか寄っていこう、という誘いである。
こういうとき、彼は決まって食べ放題の店を選択する。せっかくのデートだからおしゃれなカフェに行こうとか、そんなことは一切考えてくれない。彼はいつもじぶんのお腹を満たすことだけを考える。
正直、私はそんなにお腹は減っていない。 お金もないし、それに今日は早く帰りたい。
だけど、隼くんがそう言うなら付き合うしかない。機嫌を損ねられても困るから。
「じゃあ、どっか寄ってく? たまにはカフェとか……」
先回りして安い店を提案したつもりなのに、隼くんは笑顔で私の言葉に被せてきた。
「俺、あそこ行ってみたいんだよね。駅ナカのしゃぶしゃぶ食べ放題! 最近できたじゃん!」
「食べ放題かぁ……」
そんなにお腹減っていないし、食べられる気がしない。でも、隼くんは食べたいらしい。
「……いや?」
隼くんが私の顔を覗き込む。
「亜子がいやならやめとくけどさ」
急に声のトーンが下がる。だから、私は慌てて、
「ううん、いいよ!」
と頷いた。お財布の中身を思い出しながら。だって、隼くんはいつもお金を出さない。
そこに関して思うところはあるけれど、でも、それでも私と付き合ってくれているから、私はなにも言わない。
隼くんにとって私は金ヅル。
でも、それは私も同じ。
私にとって隼くんは、一軍でいるためのステータス。それ以外にはなにもない。
隼くんの価値が上がることは、私の価値が上がること。だから、どんなわがままも受け入れてあげる。
プレゼントもあげる。隼くんからもらったことはないけど、それでもあれがほしいと言われたら、頑張って買うしかない。
なんかおかしい、と心のなかのじぶんが言うのは気のせい。
だってこれは、彼女である私の義務なのだから。