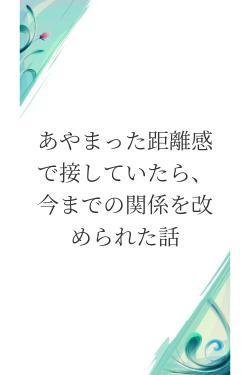「ネコを飼いましょう」
その一言から、全ては始まった。
◇
とある住宅街から外れた一軒家に、三人の女性が集まり、かれこれ半年の間シェアハウスしている。
メンバーは、
①比嘉 まさ美(30歳)
仕事:調剤薬局の事務
趣味:引きこもり
②華原 モエナ(23歳)
仕事:美容学校の専門学生
趣味:美容オタク
③五十嵐 朋子(45歳)
仕事:医薬品メーカーの営業
趣味:猫を吸う
の三人で、職種は多種多様――にも関わらず、たまたま休日が一緒になった今日(こんじつ)。最年長の朋子から、大々的な提案がなされた。
「ネコを飼いましょう」
現在、朝の九時。
各々が気怠い体を起こし、部屋から這い出た時間。
〝自身の提案に必ず許可をもらうべく〟、〝あまり脳が覚醒しきっていないこの瞬間〟を、わざわざ朋子は狙った。
しかし二人のシェアハウスメンバーの攻落は、一筋縄ではいかない。
「ネコを飼いたいって、本気なんですか?」
薬局事務員・黒髪ボブのまさ美は、全員分のトーストを焼く準備をしながら眉間にシワを寄せる。
「一番家にいない人がソレ言っちゃうって、ヤバ」
学生・茶髪ロングのモエナはあざ笑うように、片方の口角を上げる。彼女が手にしているのはスマホ。いつか朋子が「スマホの見過ぎよ」と注意したが「ニュース見てるんで」と一蹴された。
もちろん、モエナのウソである。
騙されたことを根に持っている朋子は「話を聞く時間!」と、モエナのスマホを容赦なくスリープする。
「あー、ちょっとー。今日の美容トレンドを検索してたのに」
「美容は一日にしてならず。急に降って湧いたトレンドが、女性を美しくすると思ってるの?」
「ソレ、朋さんにブーメランじゃなーい?」
「ゔ……」
黒髪ショート・朋子は医薬品メーカーで働く営業部。医薬品と言えば、病院や薬局に薬を売る事で有名だが、朋子の会社は美容にも精通している。美容液から始まりサプリに至るまで、幅広い品ぞろえを誇っている。
そんな朋子の会社の商品を使い、効果の程を宣伝しているのがモエナだ。モエナはいわゆる「契約」をしていて、朋子の会社の新商品を試しては感想を述べる動画を、定期的にアップしている。
「この前の新商品も悪くなかったけどさぁ〝三日間で変わる!〟はさすがに誇大広告だよ。モエナが実感したのは、四日目の朝かな」
「それは三日間の範疇じゃないの?」
「え~じゃあ朋さん、四日目の朝からデートが入ってる子の美容はどうでもいいの~?その日のために気合いを入れる子が、少しでも時短でキレイになろうとする気持ちを無下にするんだ~?」
「ぐぅ……」
ザ・正論。
新商品・nyai(ニャイ)を〝三日間で変わる!〟のキャッチコピーにした理由は「急いでキレイになりたい女の人へ」とターゲットを絞った上での事だ。本末転倒な発言をしてしまい、朋子は唸りながら自戒する。
「一応確認なんだけど、四日目で効果が出たとか、動画の中で……」
「言うわけないじゃん。それに、まだアップしてないし」
「良かった。急いで改良するから、そのままアップしないでちょうだい」
スマホのロックを解除しながら「っていうか朋さんも動画確認したじゃん」と三日前のことを言われ、朋子は急いで記憶を呼び覚ます。
「それにしても、なんでネコを飼うんですか?だって朋子さん、休みの日はいつもネコカフェに行ってるじゃないですか」
「そんで、すっからかんで帰ってくるんだよねー」
まさ美とモエナの発言後、トーストが焼きあがる音が室内に響く。するとひんやり秋めく温度を中和するように、トーストの湯気が空間に充満した。
香ばしく、それでいて甘い匂い。
力の入った頭が弛緩していく感覚。
心地いい空間に、朋子は思わずほっこりした。だが、熱々のトーストに触れた瞬間――目が覚め、現実にもどる。
「だから、それよ。それ」
机上にバターが出ていないことに気付き、冷蔵庫に向かいながら朋子は反論する。
「お金がね、いくらあっても足りないのよ。そして時間もない」
長方形のバターをポンとテーブルに置いた後。ケトルの湯が沸いたので、慣れた手つきで傾ける。コップの底には、これから気合をいれるためにコーヒーの粉末をしたためた。
途中、コップの水面がハネ、黒い点がキッチン台を汚す。ちょうど通りがかったまさ美が「……」と、黒いシミを見て固まった。まさ美の「とある性格」を知っている朋子は息を呑む。
「あーあ。汚れた瞬間を、一番見られたくない人に見られちゃった」
「いいから。早く拭いてください。落ちなくなります」
「心の汚れは、昨日の晩酌で綺麗さっぱり落ちたわよ?」
「そういうのいいから、チャキチャキ手を動かしてください」
「ちぇ〜」
キレイに拭き終えたのを見届け、まさ美は何事もなかったように席へ戻る。その背中に、朋子のため息がぶつかる。
「そのキレイ好き、なんとかならないの?」
「性分なので」
「キレイ好きなのに、よくシェアハウスに住もうと思ったわね……」
「どうかーん」
二人の攻撃も意に介さないまさ美は、「そんな事より」と、右手でバターナイフを握る。
「ネコちゃんの話はどうなったんですか?」
「あぁ、そうそう。だから、ネコちゃんに会いに行くためのお金と時間を時短すべく、いっそ家にお招きしようって話よ」
朋子が言い終わると、「あ~」と二人。
理由は分かった。だけど賛同しかねる――という声色だ。
「さっきも言ったけど、朋さんが一番家にいないじゃん」
「ネコ買うにも、お金と時間がかかるって知ってます?」
コーヒーカップ片手に、朋子も椅子に座る。短い髪は既にキレイに整えられており、化粧もバッチリだ。全ては新しい同居人・ネコちゃんをお迎えに行くため――といっても、雲行きは怪しさを増すばかり。負けじと朋子も反論する。
「生き物を飼うんだもの。お金と時間がかかるのは、もちろん知ってるわ。
だから今日から、一つの命を大事に育んでいきましょうって話よね?」
「いえ、まだその段階じゃないです」
「メンバーの許可取ってくだサーイ」
「ぐぐ……」
二人の思わぬ反応に、朋子は唸る。ネコを飼いたい理由には納得してくれたのに、どうしてこうも拒否されるのか。
「まさ美はキレイ好きだから、ネコが嫌なの?家が汚れると思ってる?」
「キレイ好きうんぬんかんぬんの前に、私ミニマリストなんです」
「……それが?」
「もし災害が起きて、どこかへ避難するってなった時。自分の荷物だけで手いっぱいじゃないですか?」
「んん?」予期せぬ話題に、朋子は再び唸る。
「そこにプラスしてネコとネコの荷物までなんて、無理です。もし避難所にネコを連れていけなかったらどうするんですか?荷が重すぎます」
「なるほど~。両手に持ちきれない荷物になった場合とか、ネコも一緒に避難できなかった場合のことも考えないといけないのかぁ……あ?」
突如、モエナのスマホから音が流れる。「広告ウザ」と舌打ちした最年少メンバーを見て、朋子はため息を吐いた。
「まさ美が重度の心配性って知ってたけど……想像以上だわ」
「むしろ想像してくださいよ。命が増えるのが、どういう事かを。時間よりお金より、必要なのは覚悟ですよ」
バターをトーストに塗るまさ美。決まった角度でナイフが滑り、均等に塗られていく。
淡々とした動きだけど、つい見入ってしまう。一切の無駄がなく、更には余白もなく。トーストが服を着るように色を変えていくのは、見ていて飽きない。
「まさ美って、しっかり端までバターを塗るわよね」
「味がないところが嫌いなんです」
「私は冷める方が嫌だから、適当にバターを塗ったら、すぐ食べちゃうのよね」
「あれ、本当に意味がわからないでふ」
サクッとトーストを頬張りながら、まさ美。
「朋子さんって、バターを〝塗る〟んじゃなくて〝置いて〟ますよね?
ただ、そこに、置くだけですよね?
真ん中に、ポトンって」
「それが?」
「バターのついてる部分が少な過ぎませんか?」
「トーストが熱いから、自然に溶けていくのよ。私はシーソーみたいにユラユラ動かしてればいいんだから、楽なもんでしょ?」
「つっても朋さん、いつも溶け切る前に完食じゃん。トーストの真ん中の方で、いっつもバター噛んでるじゃん」
「あらモエちゃん知らないの?固まったバターの美味しさを」
どやさ、と口角を上げるも、二人は頭を横に振る。
「歯につくし、嫌いー」
「バターは溶けてナンボです。
っていうか、そもそもですよ。そもそも」
その時、トーストを半分ほど食べたまさ美が、バターの油で艶めく唇を動かす。
「バターの塗り方なんて、そんなに何種類もあるものですか?ここにいる三人だけでも、見事に塗り方がバラバラじゃないですか」
まさ美の一言に、モエナと朋子は顔を見合わせる。「そう言えば」と言っている辺り、今まで注目したことはないようだ。
「確かに。モエちゃんに至っては〝塗らない〟もんね。
バターなしのトーストって美味しいの?味がないと嫌じゃない?」
「それ、バターがどれほど美容に悪影響か知らない人が言うセリフだよ~」
トーストを片手で持ちながら、サクサク食べ進めるモエナ。
しかしスマホを見ていた視線は、突如、大人二人へ移る。
「っていうか私がバターを塗らないのは、それが〝私のしたい事〟だからだよ」
一点の曇りなく、堂々と言い切るモエナに、大人二人の目が点になる。
「なんかモエちゃん……カッコイイわね」
「どこが?」
「カッコイイです。私も見習いたいです」
「だから、どこが?」
自分のどこがカッコイイか分かっていないモエナ。だが、大人二人は違った。朋子とまさ美は、互いに見合って、どちらともなくカップを顔の高さまで掲げる。
――チン。
「こわ、大人こわ!今のどこに乾杯する要素あったの?」
「いや、それ言ったらモエちゃん二十歳越えてるし、あなたも大人だけどね?
でも、なんていうかね。いいな~って思ったのよ」
「……乾杯が?」
「違う。モエちゃんが」
モエナは気づいてないが、自分の意見をハッキリ言う力強い姿に、朋子とまさ美は圧倒された。「これが若さか」と、自身の年齢に動揺しながら。
だが、モエナへの驚きは序章に過ぎない。
「ちなみに私、お昼も食べてないよ。カロリー過多だから」
「へえぇ!?」
「美への徹底ぶりがスゴイですね……」
――ギロリ。
二人に、モエナの強烈な視線が刺さる。
「人と違うことしてるって、そんなに変?」
「変じゃないけど、ビックリしたわね」
「だってお腹すくよね?」と大人二人が視線を交わす間に、モエナはスマホをテーブルに置く。モエナがスマホを手放す=本気モード突入の合図だ。
「私、日本人って本当に嫌いなんだよねー」
「え、DNAから否定するの?」
「どこまで遡ればOKが出るんですかねぇ?微生物?」
若干楽しんでいる二人に、モエナは「そうやってすぐ子供扱いする」と苦言を呈す。
「日本人って、マジで同調意識すごいじゃん?右を向いたら右、下を向いたら下。同じ方向を向いてない人は、すぐ後ろ指さされるんだよ」
「まぁ、それが民主主義だからねぇ」
「主義じゃなく、主張の話してんの」
トーストを食べ終わり、モエナは手をはたく。
パンパン!――いつもより力がこもった音を聞いて気まずくなったまさ美は、頭からもう一度バターを塗り直す。
どんどん厚みを増すバター。
呼応するように、モエナの語気もクレッシェンドに増していく。
「私がお昼をとらないと、学校で〝なにあの子〟って目で見られる。確かに珍しいだろうけど、だからと言って、 何で型にはまらないといけないわけ?
同じ学校にいるから?
同じ勉強しているから?
全部みんなと同じだと、みんなと同じでいることが当たり前って〝錯覚〟するんだよね。だから輪から外れると、揃って皆が指をさす」
すぅーーーーーーー……。
「めんどくさー!!!!」
ドンッと、迫力ある一声。
ビックリしてバターを塗る手を止めたまさ美に対し、朋子は「よっ、モエナ屋!」と合いの手を入れる。伊達に飲み会で盛り上げ役を務めていない。
「っていうことで、私がバターを塗らないのもお昼を食べないのも、私がしたいことだからです。以上」
続けて「ごちそうさまでした」と手を合わせる。そのまま食器の片づけをしていると、重厚感あるため息が、まさ美の口から洩れた。
「あぁ、ビックリした……。だけど、すごい分かります……」
どうやら、さきほどのモエナの発言。まさ美も思うところがあるらしい。一言呟いたきり、いつもより厚みがかったトーストを、暗い顔で咀嚼した。
「……」
「……」
「……でさ」
場の空気を読んだ最年長の朋子が、トーストをシーソーしながら、食器を洗うモエナの背中に語り掛ける。
「モエちゃんの悩み、分かるわ。みんなと同じだと、絶対〝競争〟が生まれるのよね。私はノルマ慣れして平気だけど、人によってはすっごいしんどいはずよ」
「さすが朋さん、営業の鏡」
「どうも。その道二十年です」
キラリ。瞳をかっぴらいた朋子の、なんと迫力あること。ただでさえ暗い顔のまさ美が「やっぱ営業ってノルマあるんだ」と更に顔を青くする。
「ようは、虫と同じなんだよね。たくさんの虫を虫かごに入れると争いが起こるじゃん?
人間も一緒。同じ境遇にいる人と同じ状態でないといけないって刷り込みが入って、〝追いつけ追い越せ〟の競争心が生まれるんだよ」
「私負けず嫌いだから、競争になった時〝私が一番になってやる〟って燃えるのよね。だから私にとって競争心はプラスに働くけど……モエちゃん・まさ美ちゃんの性格だと、確かにしんどいわよね」
「鋼のメンタルかよ、朋さん」とモエナ。
「競争心って、基本的に蹴落とし合いじゃん?自分を高めるものって、何もないじゃん?私は一分一秒でも、自分のために時間を使いたいんだよね」
「要するに、自分のやりたい事をやってるだけなのに、部外者が口を挟むなってことね?」
「そう!」
ガチャン、とシンクの中でお皿がぶつかる音が響く。割らないでよ、と朋子が祈りを込めた横で、同じように。まさ美も不安げに、モエナの背中を見つめた。
「男関係にしてもそう。
〝そんなに可愛くなってどうするの?そんなに男ほしいの?〟っていう女子。
〝俺、お前となら付き合ってもいいんだけど……〟って斜に構えてる男子。
一言だけ言わせて……
男なんて毛ほど興味ないんだよー!!
私が興味あるのは自分!自分の美だけなの!」
「よ、モエナ屋!」
全てぶちまけてスッキリしたのか、手を拭き終わり、モエナは静かに着席する。そして、未だ青い顔をしているまさ美を気遣った。
「ねぇまさ美さん、バターの重みでトーストが曲がってるよ?どした?」
「いや……今、モエナちゃんが吐き出した愚痴の中に、私がいたなって……」
「あー。確かにまさ美さん、自分を持ってなさそうだよね。〝その他大勢の中〟にいそう」
「ぐぁ……」
「こら、モエちゃん。トドメ刺さないの」
モエナの衝撃発言に、まさ美はついにトーストを皿に戻す。
「モエナちゃんは、ちゃんと自分のことを考えてるんですね……強くて羨ましい」
「このシェアハウスでいちばん権力あるまさ美様が、何を言うのよ」
「私が恐慌政治してるみたいな言い方、やめてくださいよ」
「いやね」と、続けてまさ美様。
「私って起伏のない平坦な人生送ってるじゃないですか。でも朋さんもモエナちゃんも仕事や私生活が順調で……だから二人を見ると焦るんです」
「順調?そんなことないわよ?」
「昨日〝業績がうなぎ登り〟って言ったの、しっかり聞きましたよ」
「あらら」
気まずさから逃げるように、朋子は残り僅かになったコーヒーを喉に送る。
ミルクも砂糖もないシンプルなソレは、口に入れると芳醇な香りが弾け、心地よく体に沈んでいく。インスタントコーヒー、侮れない。
すると「私ね」と、まさ美。
「本当に焦ってるんですよ。私より年上の人も年下の人もキラキラ輝いて……私一人、置いていかれたような気がして。
私は朋子さんみたいに社会人として成果を上げてるわけじゃないし、モエナちゃんみたいに学生と動画配信を兼業もできないし……」
「朋さんは会社で働いて正真正銘スゴイけど、私は好きなことしてるだけだよー?」
「好きなことを見つけてるだけでも、スゴイことなんです」
「そうなんだ」と、多趣味の二人は驚く。
当のまさ美は、休日になると部屋に引きこもり、一日出て来ない日もある。部屋で悠々自適に過ごしているかと思いきや、夜中に「はぁ」とベッドの上でため息をついているのだ。
「私も二人みたいにキラキラしたい。やりがいを見つけたい。毎日パソコンと向き合う事務職は私に合っていて天職ですが……たまに〝このままでいいのかな〟って思っちゃうんですよ。休日も、パソコンと睨めっこしてる間は楽しいですが、一日の終わりに〝今日も何もしなかったな〟って虚しくなるんですよ」
「どデカ重い悩みきたじゃん、コレ……」
胃のあたりをさすりながら、モエナは苦笑を浮かべる。
だけど何か思いついたのか、いきなりスマホを操作し始めた。暗に「お前の悩みなど興味ない」と言われたみたいで、まさ美の視線が下がる下がる。
「モエナちゃんにとって私の悩みはスマホ以下ですよね、そうですよね……」
「そんなんイイからさ、まさ美さん……
マジカルキュンキュン、プインプイン。って言ってみて?」
「あ゙!?」
まさ美の本性が垣間見えた後、モエナにノった朋子が「晩ご飯おごってあげるから」と囁く。
「ぐ……っ」薄給のまさ美からすると「おごり」は喉から手が出るほどほしいワードで……ついに覚悟を決め、両手を握り締めた。
「ま……、マジカルキュンキュン、プインプイン!」
「はい、録音OK~」
「録音!なんで!?」
意に介さないモエナは、さっそく再生する。
『ま……、マジカルキュンキュン、プインプイン!』
「わ~!!」
断末魔が響いた後、「もう私を土に還して……」とまさ美がテーブルに突っ伏す。さすがの朋子も、同情の視線を送った。
「ちょ、なんですか朋さん、その目は……。
違う違う。精神攻撃したんじゃなくて、提案したいの!
まさ美さん、私の動画でVチューバーとして出ない?かわいい声だなって、ずっと思ってたんだよね。もちろん収益が出た場合は、お支払いしますよぉ~?」
手をお金の形にクイッと曲げたモエナを、腕のすき間からまさ美が覗き見る。
「Vチューバ―……?」
「声はバレちゃうんだけど、顔はバレないの。可愛いアバターを作って、意のままに動かすことが出来るよ」
「え?、ん??」
二人のハテナだらけの脳内を察したモエナは「コレコレ」と、人気Vチューバーの動画を再生する。見ると確かにアバターが動いているだけで、実写はなし。「本当に声だけなんですね」と、まさ美は前のめりになる。
「動画編集は、今まで通り私がやります。私が渡した台本通り、まさ美さんは喋ってくれればOKです。慣れてきたら、台本なしで。どうかな?まさ美さんの新たな趣味になるかもよ?」
「え、でも急には……」
「まさ美さんはバター塗る時みたいに、慎重すぎるんだって。初めて挑戦することに〝ここまで手間暇かけたんだからOK〟ってラインは存在しないよ?」
「つまりモエナちゃんみたいに、バターなしでも堂々としていればいいって事ですか?」
「そーそー」
「……」
まさ美は、グッと下唇を噛む。そしてトーストを食べる時に手に付いてしまったバターを、チラリと見る。そして、想像する。
もしかしたら食後にバターのついていない手を見るのは、自分が思っている以上に嬉しくて、幸せなことかもしれない――と。
「……なるほど」まさ美にしてはいつもより大胆な想像は、頭に浮かぶモヤを、少しだけ晴らした。
「ちょっと、やってみたい……かも」
「えー!マジ?」
「ま、まじです」
まさ美の目がキラキラ輝いたのを見て、モエナは「よし」と、見えない所でガッツポーズを出す。その横で、朋子が「なるほど」と、モエナのパソコンから視線を逸らした。
「動画が伸びれば伸びる程、収入も上がるのね。10~20分の動画を定期的に上げれば、登録者も増えるかしら?」
「あ、朋さんは管理してくれる感じ?助かる~、マネージャー」
朋子は「任せなさい」と、胸を叩く。
「営業は、どうすれば数字が上がるか、どうすれば自分を知ってもらえるかを研究するプロよ。全てのエビデンスは、私に詰まってる!」
「か、カッコイです。朋さん……っ」
モエナも拍手を送りながら「ヤバ!団結感あってシェアハウスって感じするー!」とテンションを上げる。
朋子は早速、自分のスマホを操作した。
「Vチューバーたるもの、マスコットが必要だと思うのよ。動画の説明を代わりにしてくれたりとか、マスコットならではの役割が、色々あるでしょ?」
「今の短時間で、どれだけの動画見たの?朋さん」
「でさ、ここから本題よ。
我らのマスコットは、
この子でいこうと思います!」
ババン!と、スマホの画面に現れたのは……某ペットショップ屋のネコ。
この画面を見て、今まで朋子の手のひらに踊らされていたのだと、二人はやっと知る。
言うなれば、まさ美とモエナは、トーストの真ん中に置かれたバター。それを自分の思うがままに、シーソーのごとく傾けていたのが朋子だ。
「朋さん、ちょ、これは卑怯だって」
「……そこに話を戻すんですか?」
「これだから若者は」と朋子はどや顔をキめる。
「この物語が感慨無量なサクセスストーリーだと思ったら大間違いよ」
「え、違うんですか?」
スンと暗い顔をしたまさ美を見て「いや、そうでもあるけどね?」とすぐ覆す朋子。
しかし、やはりネコには並々ならぬ思いがあるらしい。「どうしても譲れない」と、とある名言を持ち出した。
「あの偉人も言ってたじゃない。
〝時間よりお金より、必要なのは覚悟ですよ〟って」
「それ偉人じゃなくて、ついさっき私が言った言葉ですね?」
「あは、そうだっけ?」
まさ美のピクつくこめかみを見ながら「でもさ」と、朋子は席を立つ。
「まさ美ちゃんは、さっき覚悟を決めたでしょ?Vチューバ―やってみたいって、ちゃんと声に出せてたじゃない」
「確かに、そうですけど……」
「だから私も思ったの、覚悟を決めなきゃねって。
可愛いネコちゃんをお迎えするために……
あなた達と、とことん話し合う覚悟を決めたわ」
「うゎ……」
「げ!朋さん〝ネコちゃんを飼うために〟って内容で、パワポ作ろうとしてる!」
カウンターにある朋子のパソコンを覗き見たモエナは戦慄を覚える。同じくまさ美も、ここまでになった朋子が、何をどうしたって意見を曲げない人であると知っているだけに、ため息がとまらない。
闘志を燃やした朋子がお皿を洗っている間、二人のシンキングタイムがスタートする。
「まさ美さん、どうする?アレ、絶対めんどうくさいパターンだって」
「何もしない休日も嫌だけど、興味ないパワポを見る休日も嫌です……」
そこで、二人は苦渋の決断を下す。
「とりあえず……」
「ペットショップ屋に、行くだけですよ?」
もちろん、この言葉を聞いて朋子の口角が上がったのは言うまでもない。
財布にカードが入っている事をしっかり確認し、いざ。
「じゃあ各々支度をして、三十分後に集合ね!」
◇
「あ、……え、ちょっと!ちょっと!!」
「始まった」
「始まったわね」
ズズと、紅茶とコーヒーを飲むモエナと朋子の横で、まさ美が声にならない声を上げた。
「すぐ近くの駅で推しが撮影しているらしいので、行ってきます!」
ウキウキした顔で、素早く身支度をし玄関から飛び出したのは、まさ美。「いってらっしゃい」と振り向きざまに見たまさ美のキラキラした横顔に、朋子は口に弧を描く。
「ねぇ、だーれがさぁ、こんな事になるって予想できたかしら?」
「いや、きっと誰も予想出来なかったね。まさか、まさ美さんに〝動画配信者の推し〟が出来るなんてさ」
そう。
事の発端は、あの日、三人で会議した日まで遡る。
モエナに「Vチューバ―担当ね」と頼まれたまさ美は、真面目な性格から「Vチューバ―たるや」を学ぶために、動画を視聴し漁っていた。
そこで虜になったのが、イケメンなアバターを使う動画配信者。名前を【ゆしりん】。アバターの容姿はもちろんのこと、声を始めご本人に至るまでイケメンで、まさ美はチャンネル登録だけでなく、SNSまでフォローし、引きこもりから追っかけを謳歌する推し活人生へと変貌を遂げたのだ。
「三十年間悩んでいた無趣味が、まさか、こんなにあっけなく開花するとは思わなかったよね」
「本当~。干物みたいな顔をしていたのに、今じゃ水を得た魚よ?すごい変化よ?」
「肌にも潤いが戻ったよねぇ、水だけに」
【ゆしりん】が「綺麗な子が好き」という情報を得てから、まさ美の美への探求心は一気に開花した。モエナから美の講座を受けるのはもちろんのこと、朋子の会社が販売する商品を買うなど、まさに「三日間でキレイになれる」を謳うnyai(ニャイ)の理想モデル様様なのだ。
「あたし、この数日で、あんなに変わる人を初めて見た」
「まさ美はのめり込むと、とことんって感じだからねぇ。
ね~?ニャイ。あとで写真撮影と、声を録音させてね~動画で使うから」
「ニャッ」
ニャイ――と呼ばれたのは、朋子の腕の中にいる真っ白な子猫。
そう、メンバーの皆でペットショップ屋に行ったあの日。朋子はついに、ネコをお迎えすることに成功したのだ。けれど、出会いはペットショップではない。目的地へ向かう道すがら、出会ったのだ。
道の端っこで一人さ迷っていたニャイは、か細い声でニャーニャー泣いていた。しかし、待てど暮らせど、親猫は来ない。きっと一人なんだと悟った三人は、道の真ん中で緊急会議を開いた。
『とりあえず〝ネコを飼えるか否か〟、大家さんに聞いてみるわね』
『ちがうちがう』
『話が早い早い』
二人の静止を聞いた朋子は、寸でのところで通話ボタンを押す手を止める。次に見せたのは「これから雨が降ります」という天気予報の画面。
『この小ささで、これから雨に打たれて……可哀そうにね』
『だーかーらぁ』
『そういうのを卑怯っていうんですよ……』
ガクンと二人が項垂れたのを見て、朋子は口角を上げる。そして「大家さんに電話してくる」と、ルンルンで通話を開始した。
朋子の話し方を聞くに、どうやら「ペットOK」の許可が出たと踏んだ二人。これからの事に、各々が覚悟を決めた。
『まさ美さん、あたし家に戻るね』
『え、どうしてですか?』
『ネコちゃん来るなら、部屋を片付けておかないとじゃん?』
『なるほど……じゃあ、飼う道具も一式必要ですね。私は、そっちの係ですか?』
『そういうことー。さすが、話が分かる』
『もう半年の付き合いですから』
そこへニッコニコの笑みで、朋子が戻って来る。「OKだって~!」とやっぱりの返答に、二人は開き直った。
『じゃあモエナちゃんと朋子さんは、家へ戻ってください。私が一式買ってくるので』
『まさ美ちゃん、ネコちゃん飼っていいの!?』
『朋さんは聞かないって分かってますから』
『や~ん、さすがお友達!あ、じゃあ待って!』
ネコを片手に、朋子は自身の財布をまさ美に差し出す。そして、お札をとるよう促した。
『今日はネコちゃんお迎え祝いだから、パーッと買ってきてね!道具を揃えるくらいのお金なら、現金で足りると思うから!』
『任せてください』
お札をシッカリ握ったまさ美は、そのままペットショップ屋へ急ぐ。そうして、その日からメンバー四人のシェアハウスが始まったのだ。
――という経緯があり。
ネコことニャイが、シェアハウスに住み始めて三日。初日こそオドオドしていたものの、朋子の溺愛に陥落したのか、今ではニャイ自ら顔を摺り寄せる。朋子は、赤ちゃん言葉で迎えた。
「あ~かわいいでちゅねぇ、ニャイは最高でちゅねぇ」
ニャイ――この名前に、モエナが片方の眉を上げる。
「よく自分の会社の商品名をつけようと思ったよね」
「ぴったりじゃない?ニャイって」
「そうだけど、名前を呼ぶ度に仕事のこと思い出して嫌じゃない?」
「別に?嫌じゃニャイ」
「……そう言えばこの人、鋼メンタルだった」
「んふふ~」
朋子がネコを可愛がる横で、モエナはパソコンを操作する。昨日撮った動画をアップするため、長い長い編集作業をしているのだ。
「昨日、まさ美ちゃんと二回目の撮影したんだっけ?」
「自分の存在を推しに認知してもらおうと、まさ美さんったら一気に火が付いてさ。今まで聞いたことない〝きゅるるんな声〟を、出し惜しみなく披露してくれたよ」
初期の「マジカルキュンキュン、プインプイン」が嘘みたいだよね――と。緊張でカタコトになった、あの日のまさ美を再生する。
「でも、モエちゃんもまさ美ちゃんと一緒に、【ゆしりん】の動画見てるんでしょ?〝モエナちゃんがいつも一緒に見てくれるんです〟って、すごい嬉しがってたわよ?」
「酌だけど【ゆしりん】って、すごい動画編集が上手いんだよねぇ。飽きないから、いつも最後まで見ちゃうの」
「最初はイヤイヤなのに?」
「最後はアハハ、みたいなね」
同じ配信者として、すごい嫉妬するんだよね、とモエナ。
「自分の糧にするために、歯を食いしばって見てる」
「推しを見てキラキラするまさ美と、敵を見て歯をギリギリさせるモエナ……」
想像したのか、朋子はプッと吹き出す。もちろんモエナの眉間にシワが寄ったのは、言うまでもない。
「趣味も推しも、一瞬で爆誕させるまさ美さん。
四日でキレイになる商品を、三日に縮めさせちゃう朋さん。
どっちもバケモノだわ。っていうか朋さんって営業だよね?なんで企画にも開発にも関わってんの?」
「そこは二十年の貫禄が、横にも縦にも斜めにも道を切り開いてるのよ」
「引っ張りだこってワケか、羨ましい~。ねー、ニャイ?」
モエナが呼びかけると、ニャイが「ニャ」と返事をする。編集に飽きたモエナが、おもちゃの猫じゃらしを取り出した。
朋子の腕を飛び出し、猫じゃらしを追って右へ左へ移動するニャイ。その姿を見て「まるで私みたい」と、モエナが呟く。
「モエちゃん、人生って右往左往するものなのよ?」
「なんのこと?ニャイの可愛さが、私ソックリって言っただけだよ?」
「あっそ」
カシュッとビールのプルタブを、奥へ押しやる朋子。今日は休日で、お昼から飲んでも許される貴重な日だ。
「あ~美味しいー!
そういえば、沖縄で飲んだビールも美味しかったわねぇ」
「あぁ……あの〝歓迎会と称した、ただ欲望のままに行動したプチ弾丸旅行〟のことね」
「こら。言い方、言い方」
そう。実は、このメンバーで二泊三日の沖縄旅行をしたことがある。
シェアハウスに住み始めた順番は、朋子、まさ美、モエナ――最後の入居者、モエナが引っ越してきた当日。仕事で大口顧客を獲得し、テンションがハイになっていた朋子が「旅行に行こう!」と、急きょ三人分の飛行機チケットを手に入れたのだ。
「初対面の人と旅行に行って、しかも泊まりだなんて。あんなの男子がやったら訴訟もんだよ」
「女同士だから問題なかったでしょ?」
「一般常識は問われるけどね」
「んふふ~。ニャイも一緒に来れたら良かったのにね~」
既に猫じゃらしをゲットしたニャイは、仰向けになったりうつ伏せになったりと、無邪気にじゃれている。その姿を見て、沖縄で見た〝とある風景〟をモエナは思い出す。
「そういえば、ネコ、いたよね。変なおじさんに連れて行かれた、カフェの先で」
「あぁ、タクシーの!」
タクシーの運転手を「変なおじさん」呼ばわりするとは――朋子は苦笑を浮かべる。
「モエちゃんが足が痛い~って泣いてたら、おじさんが〝格安だよ〟って、色々連れて行ってくれたのよね」
「泣いてないから。っていうか、何の警戒心もなく車に乗るんだもん。私からしたら、二人の方が信じられなかったよ」
「警戒って……タクシーに警戒してどうするの」
「私、この容姿のせいで男には苦労してるんだよね。だから全ての男を警戒してる。といういきさつがあって、女性限定のこのシェアハウスに来ましたー」
そういえば女性限定だったな、と朋子は思い出す。ニャイは……よかった、女の子だ。
「モエちゃんがココに来た理由、初めて知ったわ。若い子なのに、どうして今時のシェアハウスに住まないのかなって不思議だったのよ」
「今時のシェアハウスって、百人規模の男女混合のアレだよね?いや、もう絶ーッ対イヤ。男女の色恋に興味ないんだよね。私が興味あるのは、」
「「「私の美だけだから」」」
朋子、モエナ、そして帰宅したまさ美の声が重なる。まさか声が揃うとは思わなかったモエナは「これはこれでキモイね」と、忌憚ないコメントをした。
「おかえり~まさ美ちゃん。どうだった?」
「心が洗われました。インタビューしていたので、つつがなく受けてきました」
「インタビュー受けたの!? メンタル強!」
「でも……っ」
まさ美は肩を震わせる。
「推しと会えるどころか、直接話が出来るなんて……感無量すぎて号泣しちゃって、一言も喋れませんでした」
たぶん私のシーンは全カットです――と落ち込むまさ美の目の前に、朋子がビールを置く。ニャイも、足元にすり寄った。
「ニャイ、慰めてくれるんですか……」
泣きながら、まさ美はニャイを抱き上げる。――小さくも温かな存在に癒される。まるで自分が、トーストの上で溶けるバターになった気分だ。
「そういえば、沖縄でも泣いてたわよね。まさ美ちゃん」
「え、沖縄?」
椅子に座って、ビールのプルタブを開けるまさ美。缶を近づけた朋子と、無言の乾杯を交わす。その横でモエナが「そんな事あったねー」と、パンドラの蓋を開けた。
「タクシーのおじさんが、〝沖縄の有名な歌を歌ってあげるよ〟ってさ。三味線で披露してくれた時、助手席にいたまさ美さん号泣だったじゃん」
「え、そうでしたっけ?」
「覚えてないの?号泣したのに!?」
モエナの大きな声に驚いたニャイが、ネコタワーに逃げ込む。「あ、ごめんニャイ」と、モエナにしては珍しく謝った。どうやらモエナは、人よりも動物に対しての方が素直に謝れるらしい。
「沖縄でタクシーのおじさんに会ったことまでは覚えてますが……私、泣いてました?」
「号泣だったよ。その姿を、私と朋さんがドン引きした目で後部座席から見てたんだよ」
「え、私を笑っていたんですか?」
「むしろ何かツライことあったのかな?って心配してたよ」
モエナがツッコミを入れると、朋子が小さな拍手を送る。
「モエちゃん、引っ越して早々沖縄に連れて行かれたのに、もうメンバーのことを心配してくれていたの?優しい子ね」
「もちろん自分の心配もしたよ?こんなメンバーの中で生活して大丈夫なのかな?って」
「やだ~モエちゃん!大丈夫に決まってるでしょ」
「そ、そうですよ!大船に乗ったつもりで楽しんでくださいっ」
ビール片手にほろ酔い気分の朋子。
インタビューを引きずり、再び泣き出すまさ美。
二人を見て、モエナはため息をついた。埒が明かない、と再び動画の編集に戻る。
「あ、まさ美さん、コレ見て」
ちょいちょい、とモエナがまさ美を呼ぶ。まさ美がパソコンを覗きこむと……
≪こんにちはー、【ゆしりん】でーす。早速ですが今日は、街灯インタビューを行います≫
「さっきの撮影、もう動画アップしたんだー。編集する暇なかったろうし、全シーン採用されてるんじゃない?」
「ってことは、号泣した私が写るってことですか?」
「且つ、推しと二人のツーショット!」
「うわぁ!家宝にします……っ!」
グビグビ、ビールを喉の奥へ送るまさ美。パソコンの前には、いつの間にやら朋子、モエナ、まさ美、そしてニャイの全員が集まっていた。
≪今日はどちらから来たんですかー?≫
≪う、ううう、ゆしりん~……!≫
≪おっと新手の反応!名付けて、号泣!≫
「めっちゃいじられてるじゃん」
「これはこれで〝オイシイ〟って事なのよね?」
「私、推しの取れ高に貢献できてるんですか?」
≪っていうか君、俺が見てるVチューバ―の声とすごい似てるね。その子のこと最近知ったんだけどさ、良い声なんだよ~≫
≪うぅ、ゆすりん~≫
≪ちょっと?推す名前が違うから!≫
「「「……」」」
ん?
三人+一匹は、顔を見合わせる。
「気のせいじゃなければ、【ゆしりん】が私たちの動画を見てる?」
「最近しったVチューバ―って……私のことですか!?」
「え~!やだ【ゆしりん】サイコーじゃん!」
決めた!私もまさ美と一緒に【ゆしりん】を推す!――と朋子。
いつもはツッコミを入れるモエナも、これには何度も頷いた。
「私の動画でしょうか?って非公開メッセ送るね!
してもいいよね!?ってかするから!
上手くいけば、【ゆしりん】とコラボできるかもしれないよ!」
っていうか、Vチューバ―って中の人がいない設定が鉄板なんだけどね!と、チクリと【ゆしりん】の発言にダメ出しをした後。モエナは素早く手を動かした。三秒後には「送った!」と、ガッツポーズをきめる。
「推しに認知されてるって……現実ですか!?」
「ゆ・し・りん!イ・ケ・メン!」
「コ・ラ・ボ!コ・ラ・ボ!」
カシュッと、二本目のビールを開ける朋子。この場を空気を悟ったニャイも、どこか嬉しそうに三人を見上げる。
あまりの感動に力の抜けたまさ美が、その場に座り込む。すかさずニャイが、太ももの上にやってきた。
「私……キレイ好きって言ったじゃないですか」
「ん?あぁ、ごめん。ニャイもらうわね?」
遠回しに、ニャイを遠ざけてくれと言ったのかと。気を利かせた朋子は、ニャイを抱き上げようとする。だけど、まさ美がニャイを撫でる方が早かった。
「私は確かにキレイ好きです。でも一人で住むのは嫌だったんです。誰かと交流を図りたかった。誰かと過ごせば、今までの自分から脱却できる気がして……」
優しい手つきで撫でられ、ニャイは目を細める。そんなニャイを見て、まさ美も、涙の浮かぶ瞳をキュッと細めた。
「勇気を出して良かった。一歩踏み出してよかった。推しが出来たし、友達もできました」
「え~そんな可愛いこと言ってくれるのー!まさ美ちゃーん!」
「バターの新しい塗り方も知れたしね、って言わせるなバカー。私こういう空気に弱いんだよ~っ」
泣いたら目が腫れるじゃん、と。こんな時まで自分の美に反するものへ厳しいモエナが、実は優しいと知っているまさ美は……涙をこぼしながら、思い切り笑みを浮かべる。
「どんなバターの塗り方も、楽しくて面白くて、幸せなんですね。ここに住んでいなきゃ私、自分の塗り方が一番だって妄信し続けていました」
「色んな味や人生を楽しめるのが、シェアハウスのいいところよね」
「じゃあ、とりあえず……」
モエナが、自分の分のビールを持って来た。珍しいことに、飲むらしい。
「今後もよろしくって事で、乾杯いこーよー」
「いいわねぇ、モエちゃん!さいこー!」
モエナがプルタブを押しやり、炭酸が細かな粒となり四方へ散る。「ヤバ」と、モエナは綺麗好きのまさ美へ視線を送るが、本人は何のその。
今までのまさ美なら「すぐ拭いてください」と言っていたが――不思議と、まさ美の目には、炭酸の粒が光って見えるのだ。キラキラと、輝いて見えるのだ。
そして、その粒が教えてくれる。
この生き方が、私の幸せなのだと――
「これからも私の推し共々、よろしくお願いします」
「〝私の〟じゃなくて、〝私たちの推し〟ね!」
「且つ、配信者同士〝ライバル〟としてッ」
「「「カンパーイ!」」」
【 完 】