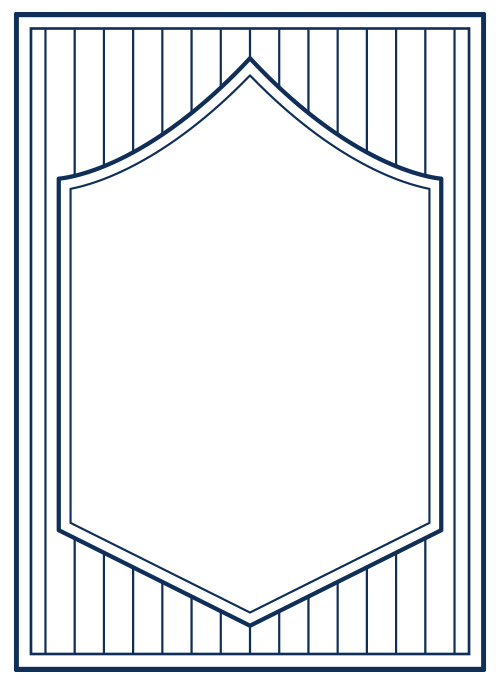第五章 魂に紡がれゆく謳
一
「小夜、今日お茶しない?」
朝、校門の前で一緒になった清美が言った。
「清美、懲りないね」
「雷は同じ場所に二度落ちないって言うじゃん」
清美は笑いながら言った。
いつもながら呆れるほどポジティブだ。
清美が知らないだけで二度目がかすったんだよ。
とは言わないでおいた。
小夜が清美にスマホを返した二日後だった。
小夜がスマホを持っていたことについては、学校の玄関で拾った、と説明した。
靴を履き替えようとして屈んだときに落としたというのは不自然ではないと考えたのだ。
清美にスマホのことをなんと言うかは柊矢と相談して決めた。
これまでと同じようにお茶したりすると言うことも。
スマホに関しては、知らない間に盗られていたことで怯えさせてもいけないと言うことで、本当のことは黙っていた。
沙陽が清美のスマホを奪えたと言うことは付き合いを絶ったからと言って狙おうと思えば狙える。
それなら清美と付き合うのをやめるのは沙陽の思惑通りになるだけだから、今まで通りでいいだろう、と言うことになった。
勿論、清美に迷惑をかけないように十分な配慮をする。
とはいえ清美は二度と誘ってくれないかもしれないと半分覚悟していた。
何しろ命の危険にさらされたのだ。
あのとき、もし刺されていたら清美は死んでいたかもしれない。
金輪際近付きたくないと思われても仕方ない。
それを清美に言うと、
「小夜、ひっどーい。あたしがそんなに薄情だと思ってたの?」
「そう言うわけじゃないんだけど」
「あんなのに屈したら、あの連中の思う壺じゃん。あたし、そういうの嫌だもん」
と言う答えが返ってきた。
柊矢に電話して清美とのお茶の許可をもらうと、いつもの店に向かった。
「清美、またコーヒー頼むの?」
「うん。今じゃ毎朝お父さんと一緒に飲んでるんだ」
「そうなんだ」
小夜はちょっぴり敗北を感じた。
自分も頼むつもりではいるが清美のように美味しいとは思えないのだ。
店に入ると既に柊矢が来ていた。
二人は注文をして柊矢から離れたところに座った。
「柊矢さんの側の席が空いてたら一緒に話せたのに」
清美が残念そうに言った。
「清美ってば、柊矢さんの好みは大人の女性だよ」
清美は子供ではないが、まだ大人でもない。
「好きになっちゃえば好みなんか関係ないじゃん」
確かに、清美の好きになる芸能人のタイプには一貫性がない。
最初がいのっち(お母さんの好きな情報番組を一緒に見て好きになったらしい)で、次に好きになったのが草刈正雄(大河ドラマでファンになったそうだ)。その後がマイケル・J・フォックス(難病にも負けずにドラマに出演してるのを見て感動したのだとか)。
基準が全く分からない。
もうちょっと統一性を持とうよ、と思うが、本人曰く、中身が良ければ外見なんかどうでもいい、と言うことらしい。
「小夜、今日もコーヒーにチャレンジするんだ」
「早く飲めるようになりたいもん」
二人はひとしきりお喋りをすると小夜が夕食の支度をする時間になったので別れた。
柊矢が清美を送ろうかと申し出たのだが、買い物をして帰りたいから、と言って断られた。
車に乗ると、
「無理してコーヒーなんか飲むことないだろ」
柊矢が言った。
「べ、別に無理してるわけじゃ……」
柊矢さん、見てたんだ。
小夜は頬を染めて俯いた。
紙コップからは中身は分からなかったはずだが小夜が飲む度に顔をしかめるのを見て察したのだろう。
飲めるようになるまで隠しておこうと思ったのに。
でも、なんで皆こんなに苦いものが好きなんだろう。
それを言うならお酒もそうだ。
まだ祖父が生きてた頃、お酒を一口だけ飲もうとしたことがあったが、あまりの不味さに吐き出してしまった。
あの後、口の中が気持ち悪くてオレンジジュースをがぶ飲みした。
柊矢も少しだがお酒を嗜む。
台所には高そうな酒の瓶が何本か置いてある。
大人になると味覚が変わるのかな。
それならもう高校生なのだから大人の味覚が分かっても良さそうなものなのに。
二十歳になったとき、柊矢さんと一緒にお酒が飲めたらいいな。
そのときムーシカが聴こえてきた。
沙陽の歌声だ。
やはり一人で歌っている。
「森が出た」
バックミラーを見た柊矢が言った。
小夜が振り返ると確かに出ていた。
足の付け根が熱くなった気がしてポケットに手を入れるとクレーイスが熱を発していた。
出してみるとクレーイスは内側から輝いていた。
クレーイスから溢れてくるのは、あの封印のムーシカだ。
クレーイスはムーシケーの意志を伝えている。
そしてムーシケーの意志は森の眠りだ。
柊矢の方を見ると彼は前を向いたまま頷いた。
小夜はクレーイスを握って封印のムーシカを歌い始めた。すぐに斉唱や重唱の歌声が重なり、沙陽の声はかき消された。
森が嫌がってるのがクレーイスを通して伝わってくる。
ごめんね、ムーサの森。
憧れでもある、あの旋律の森が嫌がることをするのは胸が痛かった。
でも、これはムーシケーの意志だ。
そして自分の役目はムーシケーの意志をムーシカで伝えること。
森はすぐに消えた。
封印のムーシカが終わると他のムーソポイオスが別のムーシカを歌い始めた。
「どうして、ムーシケーは森の意志に反してまで凍り付かせようとしているんでしょう」
小夜が呟いた。
「理由はあるんだろうが、俺達には分からんな」
起きたい森と、眠りたい惑星。
いつか、何故なのか分かる日が来るのだろうか。
「夕食の買い物していくだろ」
確かに冷蔵庫には何もない。
「はい」
柊矢は明治通りと大久保通りの角にある駐車場に入った。
沙陽は忌々しげに今まで森があったところを睨んだ。
とことんまで邪魔するつもりなのね。
あの小娘さえいなければ……。
柊矢に未練がある沙陽の憎しみは小夜に向かった。
今は火事で天涯孤独になったあの娘に同情しているだけだ。
ムーシコスならあの森の良さが分からないわけがない。
なのに柊矢もあの子も他のムーシコスも、森の目覚めに協力しないどころか積極的に眠らせようとしている。
どうして、よりによってあの娘がクレーイス・エコーなのか。
クレーイス・エコーは自分ではなかったのか。
昔、柊矢に別れを切り出されたときムーサの森が現れて自分を招いた。
それまでにも森は何度も見てきたが足を踏み入れたのは初めてだった。
そのとき惑星全体が旋律で凍り付いていることを知った。
大地や水、草や樹々、それらに手を触れると様々な旋律が聴こえてきた。
この旋律が全て溶け出して惑星中を覆ったらどれだけ素晴らしいだろう。
ここだけではない。
惑星全てが旋律で凍り付いてるのだ。
それらが一斉に旋律を奏で始めたら。
実際、昔この惑星は旋律で溢れ、ムーシコスはその中で暮らしていたのだ。
ならば、この惑星の旋律が溶ければまた同じように暮らせるはずだ。
沙陽はその想像に心を奪われた。
だが沙陽はクレーイス・エコーから外された。
ムーシケーは沙陽に惑星が素晴らしい旋律に覆われていることを見せつけて魅了した後で拒絶した。
もしも自分がクレーイス・エコーのままだったら、どんな手を使ってでも封印を解いて旋律の溶けた森に帰ったのに。
沙陽はなんとしてもムーサの森に、ムーシケーに帰りたかった。
あの幻想的な森が溶け出した旋律に包まれたら……。
きっと美しい旋律が惑星を包み込み、帰還したムーシコスの歌と演奏が大地に満ちるだろう。
沙陽は目を閉じて、その場面を想像した。
その場には柊矢もいた。だが、その腕には小夜が縋り付いていた。
沙陽は目を開いた。
あくまでも邪魔をするのなら、こちらにだって考えがある。
あの森も、柊矢も、両方手に入れてみせる。
一
「小夜、今日お茶しない?」
朝、校門の前で一緒になった清美が言った。
「清美、懲りないね」
「雷は同じ場所に二度落ちないって言うじゃん」
清美は笑いながら言った。
いつもながら呆れるほどポジティブだ。
清美が知らないだけで二度目がかすったんだよ。
とは言わないでおいた。
小夜が清美にスマホを返した二日後だった。
小夜がスマホを持っていたことについては、学校の玄関で拾った、と説明した。
靴を履き替えようとして屈んだときに落としたというのは不自然ではないと考えたのだ。
清美にスマホのことをなんと言うかは柊矢と相談して決めた。
これまでと同じようにお茶したりすると言うことも。
スマホに関しては、知らない間に盗られていたことで怯えさせてもいけないと言うことで、本当のことは黙っていた。
沙陽が清美のスマホを奪えたと言うことは付き合いを絶ったからと言って狙おうと思えば狙える。
それなら清美と付き合うのをやめるのは沙陽の思惑通りになるだけだから、今まで通りでいいだろう、と言うことになった。
勿論、清美に迷惑をかけないように十分な配慮をする。
とはいえ清美は二度と誘ってくれないかもしれないと半分覚悟していた。
何しろ命の危険にさらされたのだ。
あのとき、もし刺されていたら清美は死んでいたかもしれない。
金輪際近付きたくないと思われても仕方ない。
それを清美に言うと、
「小夜、ひっどーい。あたしがそんなに薄情だと思ってたの?」
「そう言うわけじゃないんだけど」
「あんなのに屈したら、あの連中の思う壺じゃん。あたし、そういうの嫌だもん」
と言う答えが返ってきた。
柊矢に電話して清美とのお茶の許可をもらうと、いつもの店に向かった。
「清美、またコーヒー頼むの?」
「うん。今じゃ毎朝お父さんと一緒に飲んでるんだ」
「そうなんだ」
小夜はちょっぴり敗北を感じた。
自分も頼むつもりではいるが清美のように美味しいとは思えないのだ。
店に入ると既に柊矢が来ていた。
二人は注文をして柊矢から離れたところに座った。
「柊矢さんの側の席が空いてたら一緒に話せたのに」
清美が残念そうに言った。
「清美ってば、柊矢さんの好みは大人の女性だよ」
清美は子供ではないが、まだ大人でもない。
「好きになっちゃえば好みなんか関係ないじゃん」
確かに、清美の好きになる芸能人のタイプには一貫性がない。
最初がいのっち(お母さんの好きな情報番組を一緒に見て好きになったらしい)で、次に好きになったのが草刈正雄(大河ドラマでファンになったそうだ)。その後がマイケル・J・フォックス(難病にも負けずにドラマに出演してるのを見て感動したのだとか)。
基準が全く分からない。
もうちょっと統一性を持とうよ、と思うが、本人曰く、中身が良ければ外見なんかどうでもいい、と言うことらしい。
「小夜、今日もコーヒーにチャレンジするんだ」
「早く飲めるようになりたいもん」
二人はひとしきりお喋りをすると小夜が夕食の支度をする時間になったので別れた。
柊矢が清美を送ろうかと申し出たのだが、買い物をして帰りたいから、と言って断られた。
車に乗ると、
「無理してコーヒーなんか飲むことないだろ」
柊矢が言った。
「べ、別に無理してるわけじゃ……」
柊矢さん、見てたんだ。
小夜は頬を染めて俯いた。
紙コップからは中身は分からなかったはずだが小夜が飲む度に顔をしかめるのを見て察したのだろう。
飲めるようになるまで隠しておこうと思ったのに。
でも、なんで皆こんなに苦いものが好きなんだろう。
それを言うならお酒もそうだ。
まだ祖父が生きてた頃、お酒を一口だけ飲もうとしたことがあったが、あまりの不味さに吐き出してしまった。
あの後、口の中が気持ち悪くてオレンジジュースをがぶ飲みした。
柊矢も少しだがお酒を嗜む。
台所には高そうな酒の瓶が何本か置いてある。
大人になると味覚が変わるのかな。
それならもう高校生なのだから大人の味覚が分かっても良さそうなものなのに。
二十歳になったとき、柊矢さんと一緒にお酒が飲めたらいいな。
そのときムーシカが聴こえてきた。
沙陽の歌声だ。
やはり一人で歌っている。
「森が出た」
バックミラーを見た柊矢が言った。
小夜が振り返ると確かに出ていた。
足の付け根が熱くなった気がしてポケットに手を入れるとクレーイスが熱を発していた。
出してみるとクレーイスは内側から輝いていた。
クレーイスから溢れてくるのは、あの封印のムーシカだ。
クレーイスはムーシケーの意志を伝えている。
そしてムーシケーの意志は森の眠りだ。
柊矢の方を見ると彼は前を向いたまま頷いた。
小夜はクレーイスを握って封印のムーシカを歌い始めた。すぐに斉唱や重唱の歌声が重なり、沙陽の声はかき消された。
森が嫌がってるのがクレーイスを通して伝わってくる。
ごめんね、ムーサの森。
憧れでもある、あの旋律の森が嫌がることをするのは胸が痛かった。
でも、これはムーシケーの意志だ。
そして自分の役目はムーシケーの意志をムーシカで伝えること。
森はすぐに消えた。
封印のムーシカが終わると他のムーソポイオスが別のムーシカを歌い始めた。
「どうして、ムーシケーは森の意志に反してまで凍り付かせようとしているんでしょう」
小夜が呟いた。
「理由はあるんだろうが、俺達には分からんな」
起きたい森と、眠りたい惑星。
いつか、何故なのか分かる日が来るのだろうか。
「夕食の買い物していくだろ」
確かに冷蔵庫には何もない。
「はい」
柊矢は明治通りと大久保通りの角にある駐車場に入った。
沙陽は忌々しげに今まで森があったところを睨んだ。
とことんまで邪魔するつもりなのね。
あの小娘さえいなければ……。
柊矢に未練がある沙陽の憎しみは小夜に向かった。
今は火事で天涯孤独になったあの娘に同情しているだけだ。
ムーシコスならあの森の良さが分からないわけがない。
なのに柊矢もあの子も他のムーシコスも、森の目覚めに協力しないどころか積極的に眠らせようとしている。
どうして、よりによってあの娘がクレーイス・エコーなのか。
クレーイス・エコーは自分ではなかったのか。
昔、柊矢に別れを切り出されたときムーサの森が現れて自分を招いた。
それまでにも森は何度も見てきたが足を踏み入れたのは初めてだった。
そのとき惑星全体が旋律で凍り付いていることを知った。
大地や水、草や樹々、それらに手を触れると様々な旋律が聴こえてきた。
この旋律が全て溶け出して惑星中を覆ったらどれだけ素晴らしいだろう。
ここだけではない。
惑星全てが旋律で凍り付いてるのだ。
それらが一斉に旋律を奏で始めたら。
実際、昔この惑星は旋律で溢れ、ムーシコスはその中で暮らしていたのだ。
ならば、この惑星の旋律が溶ければまた同じように暮らせるはずだ。
沙陽はその想像に心を奪われた。
だが沙陽はクレーイス・エコーから外された。
ムーシケーは沙陽に惑星が素晴らしい旋律に覆われていることを見せつけて魅了した後で拒絶した。
もしも自分がクレーイス・エコーのままだったら、どんな手を使ってでも封印を解いて旋律の溶けた森に帰ったのに。
沙陽はなんとしてもムーサの森に、ムーシケーに帰りたかった。
あの幻想的な森が溶け出した旋律に包まれたら……。
きっと美しい旋律が惑星を包み込み、帰還したムーシコスの歌と演奏が大地に満ちるだろう。
沙陽は目を閉じて、その場面を想像した。
その場には柊矢もいた。だが、その腕には小夜が縋り付いていた。
沙陽は目を開いた。
あくまでも邪魔をするのなら、こちらにだって考えがある。
あの森も、柊矢も、両方手に入れてみせる。