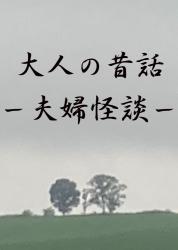八重山から戻った次の朝、僕はいつも通りに学校に登校した。その日の放課後には担任の先生に相談に行くつもりだった。父には既にいじめのことは打ち明けていて、早々に三者面談をしてもらおうという話になっていた。
しかし、事態は思わぬ方向に向かうことになった。
その朝、僕が後ろのドアから教室に入ると、前の方にはただならぬ気配が漂っていた。最前列の席に座る祐子の机の前に不動とその取り巻きが並んでいた。
「もう一度チャンスをやる。これさえ書けば昨日のことは忘れてやるよ」
不動はなにか薄くて四角いものを祐子に突きつけていた。
「いくらなんでも、私、そんなことまでしたくない」
祐子は机に突っ伏した。
「お前も、あいつと同じ目に合いたいのか。お前ら、もう別れたんだろ。だったら、いいじゃねえか」
不動は更に迫った。
「そんなの関係ない。いくらなんでも、こんなの酷すぎるよ」
祐子は泣き出しそうだった。
近づいてみると四角いものの正体が分かった。それは色紙だった。そこには僕の冥福を祈るクラスメートの言葉が並んでいた。いわゆるお葬式ごっこという奴だった。
「さっさと書けって言ってるだろう」
しかし、事態は思わぬ方向に向かうことになった。
その朝、僕が後ろのドアから教室に入ると、前の方にはただならぬ気配が漂っていた。最前列の席に座る祐子の机の前に不動とその取り巻きが並んでいた。
「もう一度チャンスをやる。これさえ書けば昨日のことは忘れてやるよ」
不動はなにか薄くて四角いものを祐子に突きつけていた。
「いくらなんでも、私、そんなことまでしたくない」
祐子は机に突っ伏した。
「お前も、あいつと同じ目に合いたいのか。お前ら、もう別れたんだろ。だったら、いいじゃねえか」
不動は更に迫った。
「そんなの関係ない。いくらなんでも、こんなの酷すぎるよ」
祐子は泣き出しそうだった。
近づいてみると四角いものの正体が分かった。それは色紙だった。そこには僕の冥福を祈るクラスメートの言葉が並んでいた。いわゆるお葬式ごっこという奴だった。
「さっさと書けって言ってるだろう」