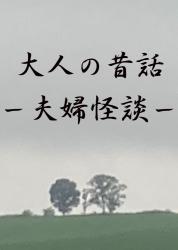それから、どうやって空港に着いたのか僕にはほとんど記憶が無かった。荷物を預ける前に、僕はベンチに座り膝の上で三線のケースを開いてみた。奈々さんの香りがするような気がした。それから、宿の食堂で、庭で、そしてカイジ浜で、三線を弾く奈々さんの面影が浮かんだ。
同時に、すぐにでも竹富に帰りたい、奈々さんに会いたいという気持ちが心の中で大きく渦を巻き始めた。僕はケースを閉じて空港の出口に歩き出そうとした。
その時、もう一人の僕が僕を止めた。
『それは奈々さんがしてくれたことへの裏切りだ。そんなお前を奈々さんは受け止めてはくれないぞ』
その通りだった。
僕は三線のケースを閉じ、それを両手で強く握り締めた。そして歯を食いしばって竹富に帰りたいという思いを無理やりねじ伏せた。
その時、ケースの中の三線が聴いたことのない沖縄風のメロディーを奏でたような気がした。しかし、それは僕の頭の中で生まれたメロディーが奈々さんの三線の音を求めただけなのだとすぐに気が付いた。
子供っぽいと言われた「夏のような日」に代わる七文字の言葉が自然にメロディーに重なった。歌が全てできたわけではなかった。しかし、全く手がついていなかった三番の最後のフレーズが出来上がっていた。
平成十九年一月二十日
今はもう返らない幻の夏