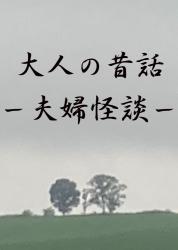朝が来ると、奈々さんはそれまでのことが嘘だったみたいに、ただの宿のスタッフに戻っていた。朝食をテーブルに並べているところを見たきりで、その後、奈々さんは全く僕の前に姿を現さなかった。
仕方なく、僕は残された時間でもう一度島を巡ってみることにした。しかし、奈々さんと訪れたどの場所も一人で行くと寂しさが募るばかりだった。
午後、いよいよ、のむら荘を発つ時間になった。僕は談話スペースで車が来るのを待っていた。義男さんが車を門の前に付けて僕を呼んだ。
「山崎さん、じゃあ行きましょうか」
すると、裏手から急いで駆けてくる足音が聞こえた。やってきたのは奈々さんだった。
「義男さん、私が行きます」
「そうかい、じゃあ、よろしく。山崎さん、また来てくださいね」
「はい、必ず来ます。お父様にもよろしくお伝えください」
「はい。では、お気をつけて」
義男さんはそう言うと去っていった。
「行きましょうか」
奈々さんが僕に声を掛けた。
「はい」
僕がリュックを肩に掛けて車の後部に回ると奈々さんがハッチを開けてくれた。僕はそこに自分のリュックを置いた。なぜかそこには奈々さんの三線のケースも置かれていた。
奈々さんは一昨日とは違って、二列目ではなく助手席のドアを開けていた。僕が乗り込むと、奈々さんは運転席に回ってエンジンを掛けた。車が動き出すと、たまらなく切ない思いがこみ上げてきた。陳腐極まりない表現だが、正に夢のような竹富での二泊三日だった。そして、僕は不快極まりない現実に戻ろうとしていた。