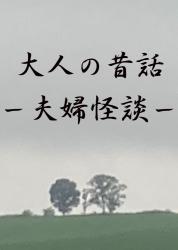「純君」
奈々さんは僕の方を向いてまっすぐに僕を見つめていた。
「君、本当に話したいこと、まだ何も話していないんじゃない?」
「え?」
僕は心の中を見抜かれた気がした。
「君、十六歳でしょ。まだ子供なんだよ。私はもう立派な大人。だから、甘えてもいいんだよ」
心臓の鼓動が一気に速くなった。
「溜まっているもの、全部、南の島で吐き出しちゃいなさい」
奈々さんが僕の手を取った。
「おいで、私の部屋に」
奈々さんは僕の手を引いて歩き始めた。僕はまるで母親に手を引かれて歩く幼子のように、されるがまま奈々さんの部屋に連れて行かれた。
それから、僕は夜明けまで奈々さんの部屋で過ごした。