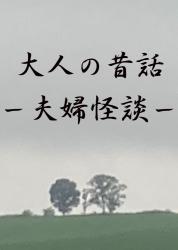対岸の西表と小浜には小さな明かりも見えたが、僕たちが歩く桟橋は闇に包まれていた。懐中電灯があっても先に進むのはかなり怖かった。もし、左右どちらかの海に落ちたら、真っ暗な海の底に引きずりこまれて二度と陸に戻ることはできないような気がした。
実際には桟橋の左右は満潮でも十分に足が着く程度の深さしかなかったので、そんなことになるわけがないことは分かりきっていた。しかし、それでもなお、そういう恐怖を拭い去ることができなかった。
当然ながら、星もない真冬の桟橋に、僕たち以外に人はいなかった。やがて僕たちは無人の桟橋の一番先までたどり着いた。
「純君、こっち側に来て」
奈々さんは桟橋の右側の縁に立った。僕は言われた通り奈々さんの右隣に並んだ。
「懐中電灯を消して」
言われたとおりにすると僕たちは完全な闇に囲まれた。僕は不意に背筋が寒くなった。
「どうしたの?怖いのかしら?」
「別に怖くなんてないです」
僕は見栄を張った。
「わ!」
奈々さんが急に僕を突き飛ばすふりをした。
「おお!」
僕は少しのけぞってしまった。まんまと嵌められて少し悔しかった。
実際には桟橋の左右は満潮でも十分に足が着く程度の深さしかなかったので、そんなことになるわけがないことは分かりきっていた。しかし、それでもなお、そういう恐怖を拭い去ることができなかった。
当然ながら、星もない真冬の桟橋に、僕たち以外に人はいなかった。やがて僕たちは無人の桟橋の一番先までたどり着いた。
「純君、こっち側に来て」
奈々さんは桟橋の右側の縁に立った。僕は言われた通り奈々さんの右隣に並んだ。
「懐中電灯を消して」
言われたとおりにすると僕たちは完全な闇に囲まれた。僕は不意に背筋が寒くなった。
「どうしたの?怖いのかしら?」
「別に怖くなんてないです」
僕は見栄を張った。
「わ!」
奈々さんが急に僕を突き飛ばすふりをした。
「おお!」
僕は少しのけぞってしまった。まんまと嵌められて少し悔しかった。