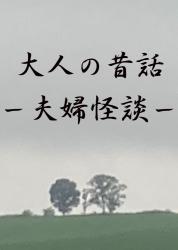僕がそう言うと奈々さんはまた呆れたような口調で話し始めた。
「純君、歌詞は君の日記じゃないのよ。現実である必要なんか無いの。多くの人が共感できる美しい物語であるべきなのよ。もちろん作り手の純君の思いが欠片も残っていない歌詞を書いたら、良い歌詞にはならないと思うけどね。だから自分だけの思いは、こっそりと少しだけ忍ばせるようにするのよ」
奈々さんの話には説得力があった。
「分かりました。自分の思いが完全に消えない範囲で、現実と虚構の折り合いを上手くつければいいわけですね?」
「そういうことね。ああ、ごめんね。でも、これは私の持論だから、他の人は私とは全く違うことを言うかもしれないわね。大体において、物語性はほとんどなくて抽象的だけど素晴らしい歌詞を書いている人は沢山いるものね。残念だけど、私にはそういう歌詞の書き方は教えられない。でもとりあえず、この歌はそういう方向性で作ってみて。たくさん歌を作って色々な人の意見を聞いているうちに純君自身の持ち味は自然に出てくると思うから」
「はい。頑張ってみます」
僕の言葉に小さく微笑むと奈々さんはまたメモ帳をのぞき込んだ。
「純君、歌詞は君の日記じゃないのよ。現実である必要なんか無いの。多くの人が共感できる美しい物語であるべきなのよ。もちろん作り手の純君の思いが欠片も残っていない歌詞を書いたら、良い歌詞にはならないと思うけどね。だから自分だけの思いは、こっそりと少しだけ忍ばせるようにするのよ」
奈々さんの話には説得力があった。
「分かりました。自分の思いが完全に消えない範囲で、現実と虚構の折り合いを上手くつければいいわけですね?」
「そういうことね。ああ、ごめんね。でも、これは私の持論だから、他の人は私とは全く違うことを言うかもしれないわね。大体において、物語性はほとんどなくて抽象的だけど素晴らしい歌詞を書いている人は沢山いるものね。残念だけど、私にはそういう歌詞の書き方は教えられない。でもとりあえず、この歌はそういう方向性で作ってみて。たくさん歌を作って色々な人の意見を聞いているうちに純君自身の持ち味は自然に出てくると思うから」
「はい。頑張ってみます」
僕の言葉に小さく微笑むと奈々さんはまたメモ帳をのぞき込んだ。