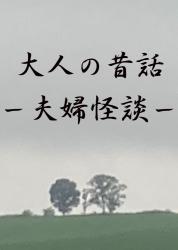面白くないと言われても、僕はただ途方に暮れるだけだった。
「どうすればいいんでしょう?」
「それは自分で考えなさい。純君の歌なんだから」
このまま突き放されては溺れてしまいそうだった。僕は藁をもすがる思いで懇願した。
「じゃあ、何かヒントをもらえませんか?」
「そうね、『夏のような日』はあまりにも子供っぽい表現だし、もっと簡潔でインパクトのある言葉に変えるの。純君は真冬の大都会から、まるで別世界のようなこの島に来たわけでしょう。しかも、島の人さえめったに経験しない夏みたいな日を体験した。だから、そういう非現実的な雰囲気を伝えられるような七文字の言葉を探すのよ。もしかしたら、それは歌のタイトルにできるかもしれない」
「すごいアドバイスですね。やっぱり奈々さんは・・・」
「何、何が言いたいの?」
奈々さんが怖い顔をした。
「いえ、何でもないです」
やはり、僕は無視されたくなかった。
「あと、二番の星の砂のくだりだけど、男女の立場を逆転させた方が良いわね。女の子が探し当てた砂を男がもらうのはロマンチックじゃないでしょ」
「でも、それは現実じゃないし」
「どうすればいいんでしょう?」
「それは自分で考えなさい。純君の歌なんだから」
このまま突き放されては溺れてしまいそうだった。僕は藁をもすがる思いで懇願した。
「じゃあ、何かヒントをもらえませんか?」
「そうね、『夏のような日』はあまりにも子供っぽい表現だし、もっと簡潔でインパクトのある言葉に変えるの。純君は真冬の大都会から、まるで別世界のようなこの島に来たわけでしょう。しかも、島の人さえめったに経験しない夏みたいな日を体験した。だから、そういう非現実的な雰囲気を伝えられるような七文字の言葉を探すのよ。もしかしたら、それは歌のタイトルにできるかもしれない」
「すごいアドバイスですね。やっぱり奈々さんは・・・」
「何、何が言いたいの?」
奈々さんが怖い顔をした。
「いえ、何でもないです」
やはり、僕は無視されたくなかった。
「あと、二番の星の砂のくだりだけど、男女の立場を逆転させた方が良いわね。女の子が探し当てた砂を男がもらうのはロマンチックじゃないでしょ」
「でも、それは現実じゃないし」