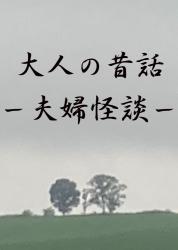言いかけて口をつぐんだ。奈々さんに無視されたくはなかった。僕は手元にあったメモ帳を開いて奈々さんに差し出した。奈々さんは僕の隣に腰を下して真剣に僕の書いた歌詞に目を通した。
「う~ん、純君、今までに歌詞を書いたことあったの?」
「いえ、初めてです」
「まあ、初めてにしては、とても良いと思うわ。元号まで日付が入っている歌なんて斬新だと思うわ。どうして、こんなにご丁寧に日付を入れたの?」
「いえ、たぶん僕にとって歴史的な日付になるだろうと思ったので」
「純君は大袈裟な表現が多いね」
「いえ、ちっとも大袈裟じゃありません」
僕の確信を他所に、奈々さんは少々呆れたような顔で講評を続けた。
「まあ、いいわ。それは別として、問題点がいくつかあるから言っておくわ」
「どこでしょうか?」
何を言われるのだろうかと僕は身構えた。
「そうね。一番、二番の最後に出てくる『夏のような日』という表現はもっと別の言い方にするべきだと思うわ」
「どういうことですか?」
僕にはそうすべき理由がわからなかった。
「つまりね、日常会話みたいな表現では歌詞としては面白くないということ」
「う~ん、純君、今までに歌詞を書いたことあったの?」
「いえ、初めてです」
「まあ、初めてにしては、とても良いと思うわ。元号まで日付が入っている歌なんて斬新だと思うわ。どうして、こんなにご丁寧に日付を入れたの?」
「いえ、たぶん僕にとって歴史的な日付になるだろうと思ったので」
「純君は大袈裟な表現が多いね」
「いえ、ちっとも大袈裟じゃありません」
僕の確信を他所に、奈々さんは少々呆れたような顔で講評を続けた。
「まあ、いいわ。それは別として、問題点がいくつかあるから言っておくわ」
「どこでしょうか?」
何を言われるのだろうかと僕は身構えた。
「そうね。一番、二番の最後に出てくる『夏のような日』という表現はもっと別の言い方にするべきだと思うわ」
「どういうことですか?」
僕にはそうすべき理由がわからなかった。
「つまりね、日常会話みたいな表現では歌詞としては面白くないということ」