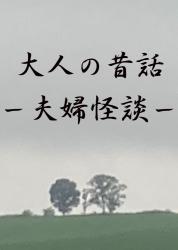「どうだった?」
奈々さんに問われて、ようやく僕は我に返った。
「なんというか、言葉にできないくらい良い歌でした」
「大袈裟ね。でも気に入ってくれたなら良かったわ」
奈々さんが嬉しそうに笑った次の瞬間に、僕は今まで誰にも言わずに秘めていた望みをあっさりと口にしていた。
「実は、僕もいつかオリジナルソングを作りたいと思っていたんです。こんな歌が作れたらいいなと思いました」
「こんな後ろ向きの歌は、ウィスキーをストレートで飲むような人生終わってる奴が作るものよ。純君は、もっと明るい歌を作りなさい」
奈々さんは少し寂し気に笑った。視線は僕ではなく遠くに向いていた。
そんな奈々さんの横顔を見ていたら、どうしても奈々さんから教えを請いたいと思った。
「あの、奈々さん、僕にも歌の作り方を教えてくれませんか?前からいつかは作ってみたいと思っていたんですけど、回りには作っている人がいなかったから、なんかきっかけがなくて」
「いいわよ、じゃあ、とりあえず今日のことを歌詞にしてみて。夜までの宿題よ」
「奈々さん、なんだか先生みたいな口ぶりですね」
「そんなことないと思うけど」
奈々さんの顔が少し曇った。
「もしかして、竹富に来る前は先生をしてたとか?」
僕の言葉を聞いて奈々さんの表情が一気に厳しくなった。
「純君、こんど今みたいなこと言ったら二度と口聞かないから」
奈々さんは冗談めかして言ったが、その言葉は冗談ではないような気がした。
「待って下さい。奈々さんにまで無視されたら、僕、生きていけませんよ」
「純君って、もしかして周りから無視されてるの?」
図星だったが、そうは言えなかった。
「いえ、そんなことありません。なんというか『言葉の綾』っていうか」
「まあ、いいわ。とにかく書いてみて」
奈々さんは少しあきれ気味に言うと三線を片付け始めた。