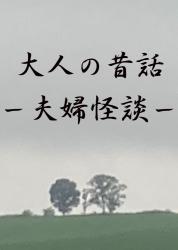夏のような日差しが降っていたが、僕たちのいる木陰は湿気もなく実に快適だった。奈々さんから顔を背けているうちに、僕はいつの間にか眠りに落ちていた。
目を覚ますと、奈々さんが僕の顔をのぞき込んでいた。
「良く寝てたね。でも、女の子を放っておいて爆睡したりすると振られちゃうよ」
「心配しなくても、もう振られてますよ。いや、捨てられたというか」
「もしかして、それでこの島に来たわけ?」
確かにそれは理由の一部ではあったが、そうは言えなかった。
「違いますよ。そうじゃありません」
「そうよね、昭和生まれの私と違って、純君は平成生まれだからね」
少し気になる一言だった。
「ええ!私と違って?まさか奈々さん、そういう理由でここに来たんですか?」
「純君、女性にそんなこと聞いていいと思ってるの?」
奈々さんは怖い顔をした。
「ごめんなさい、忘れてください」
「馬鹿ね、冗談よ。そんなロマンチックな理由じゃないわよ」
目を覚ますと、奈々さんが僕の顔をのぞき込んでいた。
「良く寝てたね。でも、女の子を放っておいて爆睡したりすると振られちゃうよ」
「心配しなくても、もう振られてますよ。いや、捨てられたというか」
「もしかして、それでこの島に来たわけ?」
確かにそれは理由の一部ではあったが、そうは言えなかった。
「違いますよ。そうじゃありません」
「そうよね、昭和生まれの私と違って、純君は平成生まれだからね」
少し気になる一言だった。
「ええ!私と違って?まさか奈々さん、そういう理由でここに来たんですか?」
「純君、女性にそんなこと聞いていいと思ってるの?」
奈々さんは怖い顔をした。
「ごめんなさい、忘れてください」
「馬鹿ね、冗談よ。そんなロマンチックな理由じゃないわよ」