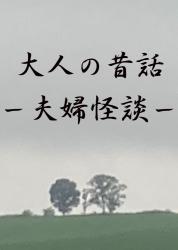奈々さんは右手に進むと、木陰の方に歩き出した。まるで座ってくださいと言わんばかりに木陰に横たわる流木を目指していた。僕は黙って奈々さんについていった。
「まずは、のんびりしようね」
奈々さんは流木の上に三線のケースを置き、トートバッグからブルーシートを取り出すと、それを広げて流木の前に敷いた。そして、すぐに三線のケースをシートの端の方に移動させた。それからトートバッグを畳んで、持ってきたタオルと共に枕代わりにすると、シートの上に横になった。僕が固まっていると、奈々さんに言われた。
「何やってんの。純君も隣で横になりなよ。気分がいいよ」
「ああ、はい、じゃあ」
僕はためらいがちに奈々さんの隣で横になった。真昼間とはいえ、人前で女性の隣に寝転んでいるのは十六歳の僕には余りにも照れくさかった。一度は奈々さんの方に目を向けたが、やはり目のやり場に困った。仕方なく、僕は奈々さんとは反対側の海に視線を向けた。その先にはコンドイ浜の白砂が細い砂州のように沖に向かっているのが見えた。
「まずは、のんびりしようね」
奈々さんは流木の上に三線のケースを置き、トートバッグからブルーシートを取り出すと、それを広げて流木の前に敷いた。そして、すぐに三線のケースをシートの端の方に移動させた。それからトートバッグを畳んで、持ってきたタオルと共に枕代わりにすると、シートの上に横になった。僕が固まっていると、奈々さんに言われた。
「何やってんの。純君も隣で横になりなよ。気分がいいよ」
「ああ、はい、じゃあ」
僕はためらいがちに奈々さんの隣で横になった。真昼間とはいえ、人前で女性の隣に寝転んでいるのは十六歳の僕には余りにも照れくさかった。一度は奈々さんの方に目を向けたが、やはり目のやり場に困った。仕方なく、僕は奈々さんとは反対側の海に視線を向けた。その先にはコンドイ浜の白砂が細い砂州のように沖に向かっているのが見えた。