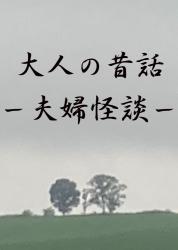車が揺れると、時々、奈々さんの肩が僕の肩に触れた。奈々さんの髪からは甘い香りがした。黒い石垣、赤瓦の家、ハイビスカスの紅に、ブーゲンビリアの赤紫、そして、時おり覗いてみる奈々さんの横顔。感じるものの全てが愛おしかった。ゆっくりと進む水牛車の速度と反比例して、都会でのことが猛スピードで遠くなっていった。
「じゃあ、一度宿に戻ろうか」
水牛車を降りた後、奈々さんは宿の方に自転車を漕ぎだした。宿に着くと、奈々さんは談話スペースにある扇風機の電源を入れた。戦闘機のプロペラのような大型の扇風機が轟音を立てた。
「ちょっと休んだら、次はカイジ浜に行こうね」
僕たちはテーブルを挟んで向かい合って座ると、扇風機が送ってくる風を浴びた。
「真冬に扇風機回すなんて、ここに来て初めてだな」
奈々さんが呆れたように呟いた。
僕はそれにありきたりの言葉を返した。
「地球温暖化の影響ですかね?」
「さあ、分からないけど、本当に夏みたいね」
「そうですね。でも昨日までみたいな天気じゃなくて嬉しいです。やっと南の島に来たっていう実感が湧きました。来た甲斐がありました」
「そう、良かったわね」
「じゃあ、一度宿に戻ろうか」
水牛車を降りた後、奈々さんは宿の方に自転車を漕ぎだした。宿に着くと、奈々さんは談話スペースにある扇風機の電源を入れた。戦闘機のプロペラのような大型の扇風機が轟音を立てた。
「ちょっと休んだら、次はカイジ浜に行こうね」
僕たちはテーブルを挟んで向かい合って座ると、扇風機が送ってくる風を浴びた。
「真冬に扇風機回すなんて、ここに来て初めてだな」
奈々さんが呆れたように呟いた。
僕はそれにありきたりの言葉を返した。
「地球温暖化の影響ですかね?」
「さあ、分からないけど、本当に夏みたいね」
「そうですね。でも昨日までみたいな天気じゃなくて嬉しいです。やっと南の島に来たっていう実感が湧きました。来た甲斐がありました」
「そう、良かったわね」