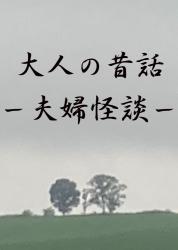翌朝、気分よく目が覚めたが外はまだ暗かった。真冬なのに加えて、日本の最西端に近い竹富では日の出が東京よりもかなり遅かった。
太陽が顔を出した頃に、まだ静まり返ったままの宿の門外に出てみた。オジイの奥さんらしき女性が白砂の道を竹箒で掃き清めていた。
天気も良く、真冬だというのに寒さはまったく感じられなかった。それはまるで夏の高原で迎えるような清々しい朝だった。
朝食後、僕は談話スペースでガイドブックを見ながら少し途方にくれていた。竹富をどこからどう回ろうか、何も決まっていなかったからだ。
いつの間にか気温がすごく上がっていた。昨日までが嘘のように空が晴れ、夏と言って良いほどの天気になっていた。奇跡的な陽気だと僕は思った。
しかし、奇跡はそれに留まらなかった。奈々さんは食堂の建物の裏手からやって来ると、まるで僕の心を見透かしたように言った。
「純君、島を案内してあげるから、ついてきて。ああ、今日は夏みたいに暑いからTシャツに短パンで十分だよ」
まったく予想もしていなかった展開に、僕は一瞬、自分の耳を疑った。奈々さんはTシャツにハーフパンツという夏らしい服装をしていた。シャツとパンツから伸びた長い手足が妙に眩しかった。
「じゃあ、僕、寝巻き代わりに持ってきたシャツと短パンに着替えてきます」
「早くしてね。なごみの塔が混んじゃうから」
僕は慌てて部屋に戻り着替えをした。部屋を出て靴を履こうとしたら、奈々さんに止められた。
「靴なんかじゃなくて、サンダルにしたほうがいいわよ。ちょっと待ってね」
奈々さんは敷地の奥の方からビーチサンダルを持ってきてくれた。
「はい、これ履いて」
「ありがとうございます」
僕は靴下を脱いで部屋の中に放り込むと用意してもらったサンダルを履いた。
「じゃあ、自転車で行こうね。自転車は駐車場の奥にあるから、ついてきて」
「はい」