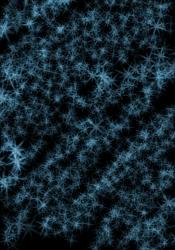瞼を開けると、真っ白な天井が見えた。
「菜穂!」
声がしたほうに向くと、お母さんとお父さんがいた。
病気を初めて知った日の事を夢で見て目が覚めた今、頭の中を整理するのに少し時間がかかった。
そうか、私は倒れて……。
お母さんが立ち上がりナースコールを押して看護士さんに私が目を覚ましたことを伝えている。ふとお父さんと目が合う。
「大丈夫か、菜穂」
「……お父さん仕事は?」
「抜けてきた。樹くんが家に連絡してきたそうだよ」
「……樹は?」
お母さんは看護士さんに話し終わると、座ってもう一度私を見た。
「樹くんはここに来てる。今ね、気を使って私たちの飲み物を買いに行った」
「そう、なんだ」
「学校に救急車がきた。先生がね、待っててって樹くんに言ったらしいんだけど、強引に乗ってきたみたいね」
「そう……」
お母さんは椅子に座ったまま、俯く。
「ねえ菜穂。お母さん、さっき樹くんに菜穂のこと聞かれたけど、菜穂は自分で話したいと思うからって言わなかった」
「……うん、ありがとう」
「できそう?」
「……そうだね」
少し俯きながら私はそう答える。
……覚悟を決めなきゃならないと思った。
上半身をゆっくり起こして辺りを見回す。この病室が個室だということに、ようやく私は気づいた。そこへ病院の先生と看護士さんがやってきた。
「菜穂ちゃん、胸の音聴かせてもらっていい?」
「はい」
先生は聴診器を私の体にあて診断を始めた。診断はすぐに終わる。
「手術したから痛みがあると思うけど、徐々にひいていくよ。飲食は四時間控えてね」
「はい」
「菜穂ちゃん。ちょっとお父さんとお母さんとお話ししてきてもいい?」
私は頷いた。先生を先頭にお父さんとお母さんと看護士さんが病室を出ていく。一人になって窓の外を見ていると少しして、ペットボトルを何本か抱えた樹が一人で戻ってきた。
「菜穂」
樹ははっとして、私に駆け寄る。
「樹」
「大丈夫?」
「うん」
樹はベッドの隣にある机の上にペットボトルを置くと私の前に来て、優しく頭を撫でてくれた。それに、ほっとしてしまう。
「おじさんとおばさんは?」
「病院の先生と話しに行った」
「そうなんだ」
「……ごめんね、樹」
樹は軽く首を振った。
「何か飲む?」
樹はペットボトルを指差した。
「ごめん。手術後はだめだって」
樹は頷いた。
樹は椅子を近くまで持ってきて、私の側に座った。
「なぁ菜穂。俺聞きたいことがあるんだけど」
「うん」
「あのさ……」
樹は少し俯いて目線をそらしてから、もう一度私を見た。
「菜穂は、病気なの?」
分かっていたのにも関わらず、聞かれて私はどきっとした。樹は話を続ける。
「ここに来る救急車の中で林原先生が言ってた。この子は心臓が悪いって。それを聞いて嘘だろって思ったんだけど……本当なの?」
林原先生が詳細を知っているのは、もしものために、あらかじめお母さんが伝えていたからだ。そうか……樹は聞いてしまったのかと思った。手を握りしめて樹と目を合わせた。
「本当だよ」
私は静かに伝えた。
「いつから?」
樹は怒っていない。 ただ少し寂しそうな顔をしている。 それでも落ち着いた声で私にそう聞いた。
「……うん」
私は俯いた。言葉がすぐ声に出ない。樹は真っ直ぐこっちをみているのに樹とまともに目が合わせられずにいた。
「菜穂」
名前を呼ばれても視線を上げられない。落ち着いてと自分に言い聞かせて、口を開く。
「生まれつき……かな。でも最初は自覚がなくて、症状が出始めたのは小学四年生くらい……かな」
「生まれつき……」
樹は驚きを隠せずにいる。樹のその反応を聞いて、私はまた口を閉じた。
「待って、小学四年から症状があるの? 嘘だろ?」
あきらかに樹は動揺している。
「……ごめんね」
樹は私を見て一瞬黙りこんだが、首を振った。
「ううん……何で気づかないかな。俺、菜穂のこと見てたと思ってたのに、見れてなかったんだな」
「そんなことないよ」
「ずっと一人で何も言わずに背負ってたの?」
「え……?」
「菜穂は泣き虫なのにさ」
突然樹がそんなことをいい、私は困惑した。
「いつの話してるの? 私はもう泣き虫じゃないよ」
否定すると、樹は真剣な表情でまっすぐ私を見る。
「菜穂、治るんだよな?」
私は樹を見たが、やっぱり目をそらす。
「菜穂」
言いにくい。言った後が怖い。でも言わなければいけない。感情的になってはいけないと心を静めて、私は樹を見た。
「ごめんね、樹。治らないかもしれない」
「……え?」
「頻繁ではないけど、定期的に症状が続いてるの……樹が知らないだけで」
「菜穂……」
「病院も結構変わってるし治すのが難しいみたい。だからね樹……だから」
私は俯いて手を握りしめている。……言え、私。
「大丈夫、菜穂。俺、側にいるからさ。病気は治してあげられないけど、ちゃんといるから」
黙ってしまった私を、樹は心配そうに見つめながらも、優しくそう言ってくれる。
「……ありがとう」
けど、そうじゃない。
そうではないのだ。
「ごめんね樹。もう大丈夫なの」
「え?」
「私はもう大丈夫」
「大丈夫?」
「分かったでしょ? 樹、私がね、樹のこと応援してあげられるのは……ここまでなんだ」
「え?」
樹は驚いてこっちを見る。私も今度は目をそらさないようにしようと、樹を見た。
「樹には病気のこと内緒にしてたけど、意識を失って倒れたのは初めてなの。これからさらに悪化するかもしれない。樹は私と一緒にいるとね、負担がかかってくるよ」
「負担? 何言ってんだ菜穂」
「あのね、勝手なこと言うけど私は……」
続きを言おうと思ったのに、瞬時に声に出てこなくて、私は一度口をぎゅっと閉じてからまた開く。
「私は、樹とさよならがしたいんだ」
「……え?」
「ずっとそうしたいと思っていたんだ」
樹は黙りこんだ。その瞳は悲しげでも驚いてるわけでも怒ってるわけでもなくて、ただまっすぐ、こっちをみている。樹の言葉を待って聞くつもりだったのに、この沈黙が耐えられなくて、また私が話し始める。
「本当はもっと早く言いたかったのに、時間がたつと言いにくくなっちゃって。こういう機会じゃないと言えないもん。本当に……樹に言えて、良かったよ」
想像よりもやや早口で話してしまった。樹は表情があまり変わってない。
「さよならってどういう意味? もう俺に会いたくないってこと?」
「うん」
「何で? いきなりすぎるよ」
そう言った樹の声は、落ち着いていた。
「そうだね。樹にとってはいきなりだよね。でも私にとってはそうじゃないんだ」
「俺は負担になんて思わない。菜穂に病気があっても絶対に」
私は樹に目を合わせないまま、首を振る。
「だめなの、樹」
「何が」
「……だめなの」
樹は椅子から立ち上がった。そして私の手を握って、少しだけ私に顔を近づけた。思わず樹を見る。樹はまっすぐ私を見たままだ。
「なあ菜穂。聞いていい?」
「……うん」
「さよならしたいは本当に……菜穂が、俺に言いたかったことなの?」
私はそれを聞いて驚いたが、すぐに気持ちを落ち着けて
「うん」
と答える。
「何で嘘つくの?」
「嘘なんてついてないよ」
「本当に言いたいことまだ言ってないだろ。……雑音が聞こえる」
「雑音? 何それ……」
「何かまだ隠してるだろ? ……結局菜穂は何が言いたいんだよ」
「隠してない」
「言えよ、菜穂」
「隠してないってば!」
もうここまできてしまったら、自然にとか時間をかけてなんて、無理なんだ。
「何で、菜穂は俺に言ってくれないんだよ!」
樹は先程よりも強く、私の手を握る。私はその手を……思いっきり振り払った。
「分かった。隠してること言う。私はね、私は……」
「……何」
「私は樹のことが、嫌いなんだよ」
「……は?」
「ずっと嫌いだったの。うっとうしかった。ずっと話を合わせてあげてたの分からない?
もう限界なの。早く私の側から消えて」
それを聞くと、樹は口を一度ぎゅっと閉じてた。そして私を静かに見た。
「……そう。菜穂の決意はよく分かったよ。さよならっていうならさよならする。でもそれと一緒に菜穂が応援してくれた俺のシンガーソングライターの夢も、さよならだ。来週のオーディションも受けない」
「な、何言って……」
「もうそれは菜穂には関係のないことだよな?」
「……」
「菜穂はさよならするんだろ、俺と」
「樹……」
「勝手にしろよ!」
樹はそう言って、病室を出ていってしまった。
「いつ……」
追いかけようと思った。けどすぐに思いとどまる。
止める権利がどこにあるというのだろう。
樹が出ていった扉を見ていた。
……私は勝手だ。無茶苦茶だよね。
「樹……」
……嫌なこと言ってごめんね。
少しの間、扉を見た後になんとなく窓の外を見ようとして、さっき樹が買ってきてくれたペットボトルが目に入った。それに手を伸ばして、一つ手に取る。その飲み物のラベルをぼんやりと見ていたら、何だか悲しくなってきて、私は、そのラベルから目を離して、天井を見た。
「私が悲しんでるのは、違うよね」
そう呟いたその時、お母さんとお父さんが戻ってきて、私は目線を移した。
「あれ、樹くんと林原先生まだ来てない?」
お母さんはそう言い、少し辺りを見回す。
「先生は学校に電話してるって。樹は……帰ったよ」
そういうと、お母さんは驚いていた。
「帰っちゃったの? 樹くん用事でもできたの?」
「う、うん……」
「そっか……」
お母さんは何故か少し俯いたが、私に近づき、椅子には座らずに立ったまま私を見た。
「ねえ菜穂。いきなりだけどね、今から病院移ろうか?」
「病院を、移る?」
「うん。竹川幹也《たけかわみきや》っていう先生がね菜穂の病気のことに詳しいんだって。その先生、海外から帰ってくるみたいで。見てもらわない?」
「え……でも、その病院どこにあるの?」
「ここからね……車で八時間くらいかかる」
「は、八時間!?」
「うん。そのまま入院するから、学校にもしばらく行けないんだけど……」
「え……?」
その言葉に戸惑いながら、私はお母さんの後ろにいるお父さんを見る。
「……菜穂の思いは色々あるだろうけど、行こう、菜穂」
お父さんはいつもと表情が、あまり変わらないものの、静かに私にそう言った。
頭の中が混乱する。色々なことが過って全然追いつけない。けどすぐに思った。
ここで何を思っても、何を言っても……行かなきゃいけない。
「……うん、行く」
返事をすると、お母さんもお父さんもほっとしていた。
「樹くんに病院移ること直接言えれば良かったね」
お母さんは、少し寂しそうな顔をして、そっと私に言う。
「……いいんだ」
私は、静かに首を振る。
……ちょうどいいではないか。
これで無理矢理にでも樹と離れておけば、樹は私のことなんて忘れて、負担になることなく夢に向かって行けることだろう。
私は覚悟していた。ずっと。
だから大丈夫。
……だけど出来ることなら、本当はもっと穏やかにさよならがしたかった。
こんなあっけない感じで、喧嘩して終わりたくはなかった。
私はそっと目を閉じる。
私がそうしたんだ。
私が今、この道を選んだ。
もう樹とは連絡しない。
……青山や小絵にも連絡しない。
病院の場所も伝えずに、みんなここに。置いていくんだ。
「菜穂?」
お母さんが、私に心配そうに声をかける。
簡単に人の縁を切り、自分のことを大切にしてくれた人たちをあっさり捨てて、恨まれるのか、呆れられるのか、分からないけど……。
後で取り返せないようなことを今からする。
私は手を強く握る。
「菜穂?」
「……大丈夫」
私は目を開けて顔をあげて、お母さんとお父さんを見た。
私は今日さよならをする。
「……準備して、行こう」
大切な君と、大切な仲間と突然に、永遠の……さよならを。