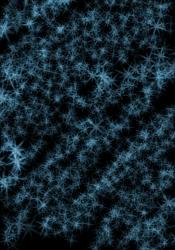あれは小学四年生の私。
ピアノの前に座る樹の横で、私はむっとしていた。
「菜穂、全然違う! ラの音はもう少し高いの!」
「ラはこれだもん。あってるもん」
「違う!」
「違わない! ラの音はこれ!」
「菜穂!」
樹に怒鳴られてさらにむっとしたが、私の目から次第にぽろぽろと涙が落ちる。
「樹が怒った……」
「ごめん……けどずれてる!」
申し訳なさそうに謝ってはくれたが、樹は食い下がらなかった。他のことに関しては違うのに、音楽が入ると彼は少し厳しいのだ。
「知らないよ、私は樹みたいに歌とか興味ないもん! 今日はもうやらない!」
「……菜穂は泣き虫だな」
「練習もう一緒にしない!」
泣きながら怒って、顔を背けた私を見て、樹はじっと私を見た後、何故か少しきょとんとした。
「なぁ菜穂」
「何?」
樹と目線を合わせずに私は情けない声を出して返事をした。これ以上泣かないように強がって涙を拭いた。
「菜穂ってさ、帰らないよな」
「え、帰ってほしいの?」
ぴたっと涙が止まり、かなりショックを受けて私は樹を見た。樹は首を横に振る。
「違う。でも普通嫌だったら怒って帰るだろ。菜穂は怒るけど帰らないなって」
私は少し俯いた。
「……だって練習は付き合いたくないけど、樹とは一緒にいたいもん」
樹は椅子から降りて立ち上がる。そしてそっと私の頭を撫でてくれた。
私は目線を上に向けた。
「ごめんな。もう今日は練習はやめる」
「本当?」
「うん。あと、いつもありがとな」
樹が笑ってくれたのが嬉しくて、私にもだんだん笑顔が戻る。そしてこう言った。
「今日は無理だけど、樹がどーしてもっていうならこれからも私は練習付き合ってあげる。だって、樹はシンガーソングライターになりたいんだよね? そのための練習だもんね」
「菜穂は優しいな。一人で練習しろとか言わないんだ?」
「樹はいつも一人で頑張って練習してるよ。でも、それが大変だから私を巻き込んでくるんでしょ?」
何の気なしに言った私の言葉を聞き、樹は少し吹き出すように笑った。
「お見通しだな」
「……うん」
何故少し笑ったのか、分からないままでいると、樹が
「今からゲームする?」
と言うので、私は頷く。
「する。羊を育成するやつがいい」
「あれか。人気ないゲームなんだよ。地味だし」
「いいの。いつきって名前つけるんだ」
「俺は羊か」
「うん」
「まぁ、やるか」
「うん!」
樹がゲームをセットして始める。
一人用のゲームだというのに、私が操作しながら樹が育成の方法など話して、何故か二人とも盛り上がって時間が過ぎていく。
ゲームと関係ない他愛もない話もたくさんした。
あっという間に夕食の時間が近づいてきたので、ゲームをやめて、私は家に帰ることにした。
樹は玄関まで送りに来てくれる。
「樹またね」
「帰り道で泣くなよ。菜穂はすぐ泣くから」
「泣かないよ。それに今日泣いたのは樹のせいだからね」
「……ごめんな!」
今度はあっさりと謝った樹を見て、少し笑ってしまった。
「またね」
手を振って、私は家を出た。私は歩いて隣の自分の家の玄関を開ける。
「ふふ」
ゲームをやったからなのか、樹と話したからなのか、何だか楽しくなって、玄関先で一人で笑みをこぼした。それがだんだん自分でも少し恥ずかしくなってきて、照れながら、私は靴を脱いだ。
「ただいま」
一階のリビングに行くと、ソファーに座りながらお母さんは、はっとしてこっちを見た。
「あ、菜穂……」
「ただいま。あれ、ご飯は?」
いつもなら机の上にある夕食が、その日はなかった。
「え!?」
驚いたお母さんは、慌てて壁時計を確認していた。
「……忘れた」
「え?」
そんなことあるのかと、私は目を丸めてしまう。
お母さんは、何故か何も言わないまま私をじっと見た。
「……どうしたの?」
「菜穂、ちょっとここ座って」
そう言うので疑問に思いながらも、ソファーの側にきて、隣に座って、お母さんを見上げた。
「菜穂、あのね……話があるの。菜穂はショックを受けると思う。それでも聞いてくれる?」
「ショック? 何? ……聞く」
戸惑いながらも、私はまっすぐお母さんを見た。お母さんは口を固く閉じてから、もう一度ゆっくりと開く。
「あのね、菜穂は明日から入院することになったの」
「え? 私が入院するの?」
「うん」
「私、どこか悪いの?」
「うん」
「どこが悪いの?」
「大丈夫。手術すれば治るよ。治る……」
お母さんは泣いていた。
「ごめんね……お母さんがしっかりしなきゃならないのに……」
私はその時入院すると聞いたことよりも、お母さんの初めて見る姿を目の当たりにして心配になった。そっとソファーから降りて、近くにあったティッシュの箱を持ってまた戻った。
「泣かないでお母さん」
「うん」
ティッシュを出して涙を拭くお母さんを見て、私は口を開く。
「あのね、大丈夫だよ」
「え……?」
お母さんは、顔を上げて私をみた。
「大丈夫だよお母さん。私はそんな弱くないよ」
一人で納得したように頷き、少し考えてからまた口を開く。
「でもね、樹には言わないで」
「樹くん……?」
「樹は私のこと心配したら弱くなる。樹はシンガーソングライターになるの。入院の事聞いたら絶対心配して夢を投げ出しちゃうかもしれない。樹はそういうところがあるの。だから言わないで」
私はその時、必死だった。
「樹にはばれないようにして。入院すること何とかごまかして」