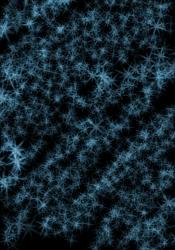「樹は英語できていいな」
「できないよ」
「話せなくても英語を聞き取ったり文章は読めるよね?」
「あ、それはできる」
はっとする樹に、私はため息をついた。
「レベルが違いすぎて私は泣ける。次の英語の授業が不安」
私が口を尖らせると、樹はまた少しだけ振り向く。
「なら菜穂。帰り道で英語勉強するか」
「帰り道で?」
「うん。ちなみに空は英語でSkyね」
「スカイ」
「今日の授業の文章なら、俺覚えてるから自転車に乗りながらでも復習できるよ」
「え……?」
……まじかよ、樹。凄い記憶力だと私は驚く。
「お願いします」
「いいよ」
こうして帰り道の英語の勉強会が始まった。
学校の授業とは違い、分からないところは気軽に樹に聞けて、雑談を挟むことで集中ができた。英語の勉強会は思った以上に楽しかった。
「樹は先生になれるね」
と言うと、樹は少し笑いながらも眉を寄せ
「それは褒めすぎ」
と謙遜した。 話をしていると自転車はあっという間に家の前に着いた。私は自転車を降りる。樹は自転車に乗ったまま、ハンドルに両ひじを軽くつけて、私を見た。
「なぁ菜穂」
「ん?」
私は隣にいる樹を見た。
「来週の英語の文章、今から翻訳するの?」
「うん。今樹に英語を教えてもらったから、やる気が出た」
「でも翻訳できるの?」
「んー……」
「俺、教えようか?」
と言うので私は驚いた。
「本当!?」
「いいよ。じゃあ俺の家来る?」
「行く!」
テンションが上がったまま答えた。が、少し考えて私は、はっとした。
「い……かない」
と言い、急いで首を横に振ると、樹は私を見て笑った。
「えらい。覚えてたな」
口ごもる私を何故か満足そうに見た樹は、その場で自転車を降りて
「じゃあな」
と言い残し、自分の家の門の扉を開けた。
「ちょ、なんなの?」
私はさらに口をつぐみ、樹なんか知らんと思いながら、自分の家の門を開ける。庭に自転車を止め、自転車から降りて鞄の中から家の鍵を探した。火曜日と木曜日は樹のお母さんと入れ違いで私のお母さんがパートの日なので、家の鍵は閉まっている。
「鍵……あった!」
鍵を取り出し、家の扉に鍵を差し込んだ時に
「菜穂ー」
と樹の声がして振り向く。自転車を置いてきた樹が私の家の門の前に立っていた。私は樹を見て、入れた家の鍵を引き抜き、もう一度門に近づき、門の扉を開けた。
「何ー?」
私が声をかけると樹が私の側に来て、右手に隠し持っていたノートを私に差し出した。
「ん? 何これ」
私はノートを見て、樹を見る。
「英語のノート。次の英語の授業でやる文章、実は翻訳してあるんだよね」
「ええ! 樹やるの早いね」
「まあね」
「貸してくれるの?」
樹を見ると、樹は静かに頷いた。
「ありがとう! 本当は一人でやれるか不安だったんだよね」
持っていた家の鍵を制服の胸ポケットにしまいノートに視線を映して受け取ろうとすると、樹は何故かノートを手から離さなかった。軽く引っ張ったが、やはり強くノートの端を握ったまま離さない。仕方なく私は手の力を緩める。意地悪だと思いながらも、少し笑ってしまった。
「ちょっと何なの、樹」
顔をあげると樹の顔が近くにあって、私の唇に何かが触れた。
時が止まったようにぼんやりとしてしまって、突然胸が高鳴る。私はようやく状況を理解した。触れた感触がゆっくりと離れていくと私は樹を見た。樹は私を見ると優しく微笑んで、ほんの少し離れたと思ったらまたゆっくりと私に近づき、両腕を開いて私を温かく包み込んだ。私は狭い空間の中で温かさに包まれながら、樹を見上げた。
「……何か安心した。いつもそうやって反応してくれたら嬉しいのに」
樹にそう言われて、急に顔が暑くなっていくのを感じた。
恥ずかしくなって、表情を隠すように私は俯きながらも、樹の胸の当たりを片手で軽く叩き、声を振り絞った。
「ね、ねぇ」
「……何?」
抱き締められたまま内心焦っている私と違い、樹の声はとても落ち着いている。
「私、約束守ったよ……樹の部屋行かなかったよ!」
「油断大敵、だな?」
「な……」
そう言うと樹は私からゆっくり離れ、俯く私と目線を合わせた。
「……はい」
樹は再び、英語のノートを私に差し出す。それにかなり動揺しながらも落ち着けと自分に言い聞かせて、無言のままノートを受け取った。
「……明日は」
「え……?」
「明日は置いていくなよ、俺のこと」
まっすぐに見る目線を避けられないまま、私は黙りこんだ。その目が揺らぐことなく優しくこっちを見るので戸惑いながらも、私は頷いてしまった。私が一回ゆっくりと頷くと、樹もゆっくりと頷いた。
「……じゃあ、またな」
樹は私に目線を合わせたまま微笑み、私の頭をぽんぽんと優しく叩くと、姿勢を戻して門を出ていった。
樹が見えなくなって、私は立ち尽くしたまま、混乱する頭の中を解決しようと考え始める。
どうしようもなく恥ずかしくなって首を横に振り、私は玄関の扉を開けた。開けて中に入ると、自分でもおかしいくらいに足の力が一瞬で抜けた。手の甲で軽く口を押さえた。
「ちょっと……」
ノートで顔を隠しながらあれは樹だった? なんて分かりきったことを心の中で投げかけている。その場から少し動けずにいた。
「……落ち着かなきゃ」
深呼吸をして、私は思いきって立ち上がる。二階の自分の部屋へと向かった。
ふと手に持ったままの樹に貸してもらったノートを広げないままぼんやり眺めてそのスペースに置いた。ぼんやりしていたら落ち着くと思ったのに、熱が一向に覚めない。
「落ち着け……」
私は目を閉じる。静かに鼻唄を歌い始めた。あのCMの曲を最初から少しスローペースで。心を落ち着かせるために。
『遠くまで行ける靴を履いて
あの流れ星を見に行こう』
歌うのを途中で止めて、顔をあげて窓の外を見た。
隣の家からピアノの音が聞こえてきた。
偶然にも私の鼻唄と同じだったその曲は、私の今歌っていた部分と見事に重なっていた。
タイトルも歌手名も分からないその曲。ピアノのメロディーは、樹がいつも鼻唄で歌っているとおりだ。ピアノを耳コピして弾けることにも驚いた。本来のCM曲はこれであっているのかは分からないけど、私にとってこの曲は大切な思い出の曲。
キスなんてしておいてすぐにピアノを弾ける樹が何だか憎らしくも感じるが、心が落ち着いてくる。
「……ねえ、樹は好きになる人を間違えてるよ」
頬杖を軽くついて、私はもう一度目を閉じた。
「でもね……」
目を閉じると、ピアノの前に座る樹の横顔が見えた。横顔を見ている私の方をふと見た樹はそっと微笑んでいる。その時に幼い頃のピアノを習い始めた時の樹の姿が重なっていた。
「大好き。私は樹のことが、大好き」
呟いたら少し泣きそうになって、私はすぐに笑顔を無理矢理作った。
――
次の日の朝。制服に着替えて鞄を持ち玄関を出ようとすると、一階の廊下で私のお父さん、澤田尚哉《さわだしょうや》と目が合った。
「菜穂元気?」
お父さんは仕事でいつも帰りが遅く、だいたい朝は早い時が多い。
私が出かける時には、いつもだといなかったり寝ていたりする。家族だと言うのにお父さんを寝る姿以外でちゃんと見たのは二週間ぶりだった。
「元気だよ」
「ならいいけど。気を付けてな」
お父さんはいつものように私に明るく話しかけて、笑顔を浮かべている。
「うん、行ってきます」
そこへお母さんが慌ててやって来た。
「菜穂、お弁当忘れてるよ!」
「あ」
「うっかりして。はい」
お母さんから、お弁当の入ったランチバックを受けとり、鞄の中に入れる。
「行ってきます」
「菜穂、勉強しっかりな」
「いってらっしゃい」
お父さんとお母さんに笑顔で見送られながら、私は玄関を出た。
玄関を出ると、自転車に乗った樹と目があった。ちょうど私の家の門の前まで来たみたいだった。
「菜穂、おはよう」
いつも通りの樹に、私はほっとした。
「おはよう。待ってね、今自転車を……」
「菜穂」
「ん?」
「自転車の鍵貸して」
そう言われて庭に止めている自転車から、視線を移して門の前にいる樹の方を見る。
「え、何で?」
「いいから」
私は首を傾げて鞄の中から自転車の鍵を取り出すと、門を開けて樹に渡した。樹はその鍵を私から受けとると、すぐに自分の制服の胸ポケットに入れた。
「あ、泥棒!」
「早く後ろ乗らないと行っちゃうよ」
「返してよ」
「嫌だ。今日はニケツで行くの!」
樹がわざと子供っぽく言うので、私は笑った。
「何その言い方は」
「早く乗って」
自転車に乗った樹が振り向いて何だか楽しそうに私を待っているので、私も少しその表情につられてしまった。私は樹の後ろに大人しく乗ることにした。
私が後ろに乗り、樹が自転車を漕ぎ、前進する。スピードが徐々に上がってくると、ふんわりと暖かく心地よい風が流れてきた。
「今日は何かいい感じの気温だよね」
「そうだよな」
いつものように樹の腰の両サイドの服を軽く掴みながら、私は少し目を閉じた。
「なぁ、菜穂」
「んー?」
私は目を閉じたままで、風を感じ、自転車の音を聞きながら樹に返事をする。
「昨日聞こえた? ピアノ」
「え……」
私は目を開ける。
「CM曲弾いたんだけど、聞いてた?」
私は昨日のことを思いだし、頷いた。
「うん、聞いてた。私はやっぱりあの曲が一番好き」
と言うと樹は
「そっか」
と自転車をこぎながら、一瞬こっちを振り向いて笑っていた。
「いつもはヘッドホンしながらピアノ弾いてるのに珍しいね」
「菜穂に聴こえるように弾いてた」
「そうなの? 何で?」
「いや、何か菜穂が歌ってる気がしたから」
私はそれを聞いて驚く。
「まあ、そんなことあったら奇跡だよな」
あははと笑う樹の背中を見た。
「奇跡起きてたよ」
「ん?」
「私、歌ってたもん」
「まじ!?」
「うん」
「嬉しいかも」
樹はご機嫌に鼻唄を歌い出した。私も笑顔が溢れた。
「……そういえば樹。来週のオーディションの曲、何にするか決まった?」
「迷ってるんだよね」
「オーディションはオリジナル曲なの?」
「カバーでもいいって聞いてるよ」
「どっちでやるか悩みどころだね」
「うん。楽しみ」
「オーディションが?」
「不安はあるけど、それ以上夢叶うかもしれない」
私はそれを聞いて嬉しくなった。そして樹は強いなって思った。
「頑張れ樹。応援しか出来ないけど」
樹はそっと笑った。
「……十分だよ」
自転車は信号にさしかかった。赤信号になって、樹は自転車を緩やかに止めた。
「そういえば、菜穂。昨日英語の勉強した?」
樹にそう聞かれて出来るわけないと心の中で突っ込んだ。樹が英語のノート貸してくれた時にあんなことするから、頭から離れず、正直それどころじゃなかった。
「いや……」
「空は覚えた?」
「そーら!」
「……おい、まじか」
樹に呆れられ、私は笑う。
「嘘だよ。スカイだよね?」
「良かった。菜穂は忘れっぽいから本気にした」
「えへへ」
樹が私に振り向いた時、待っていた信号はもうすぐ青になるところだった。樹はハンドルを握り前方に視線を戻した。その時だった。私の視界が突然ぐらりと歪み、どくんと大きく鼓動がして、胸に激しい痛みが襲ってきた。
信号が青になり、自転車は進む。視界が揺れ、胸が苦しくなる。原因は……分かっていた。叫びたい気持ちを必死に我慢し、私はとっさに樹に強くしがみついた。樹は一瞬びくっとして走行しながら少しだけ振り返る。
「菜穂?」
樹が少し振り返り、私は樹に見えないように顔を隠して、荒くなりそうな呼吸と痛む胸を必死に押さえた。
「ん?」
樹は私の様子に疑問を抱きながらも前を見たが、緩やかに自転車の速度を落とし始めた。……まずい、このままでは樹が自転車を止めて完全に振り返ってしまう。そうしたらばれてしまう、樹にずっと隠していたことが。だから私は願った。振り返らないで、気づかれたくない、見られたくない、樹の邪魔になりたくない。どうか……おさまって。でもその気持ちとは裏腹に、樹の自転車は止まった。
「菜穂、どうかした?」
まずい、振り返る。私は目を閉じて顔を隠したまま懸命に声を出した。
「樹……!」
「え?」
「樹の自転車のかごに変な虫がいる!」
「虫?」
樹はこちらに振り返ろうとしたが、すぐに前方を見た。
「どこ?」
「怖い……!」
「え、いる?」
樹は自転車のかごを見ている。その時、願いが通じたのか、私の張り裂けそうな胸の痛みは何とかすぐにおさまってくれた。顔を上げるとまだ少し視界がぼんやりしたが、私はほっと息をはいた。
「なぁ、いないよ」
樹が振り返り、私を見た。私はもう一度息を吐き、自転車のかごを見た。
「本当だ。もういないね」
私が笑うと、樹が首をかしげる。ぼやけた視界ももとに戻り、樹に抱きついていた私はいつものように樹の服の裾に持ち直し、手をグーにして片手をあげた。
「出発」
樹は不思議に思いながらも、自転車のペダルをこぎはじめる。
「変なの」
そう呟く樹に、私は笑ってごまかす。
「どんな虫がいたわけ?」
「えーっとね……丸くて青くて……」
「そんな虫いるの?」
「……ねー? もうびっくり」
「菜穂って普段は虫怖がるタイプじゃないのにな」
「……ごめんね、樹」
私がそう言うと、樹は前を向きながら
「んー? 別にいいよ」
と言った。
「できないよ」
「話せなくても英語を聞き取ったり文章は読めるよね?」
「あ、それはできる」
はっとする樹に、私はため息をついた。
「レベルが違いすぎて私は泣ける。次の英語の授業が不安」
私が口を尖らせると、樹はまた少しだけ振り向く。
「なら菜穂。帰り道で英語勉強するか」
「帰り道で?」
「うん。ちなみに空は英語でSkyね」
「スカイ」
「今日の授業の文章なら、俺覚えてるから自転車に乗りながらでも復習できるよ」
「え……?」
……まじかよ、樹。凄い記憶力だと私は驚く。
「お願いします」
「いいよ」
こうして帰り道の英語の勉強会が始まった。
学校の授業とは違い、分からないところは気軽に樹に聞けて、雑談を挟むことで集中ができた。英語の勉強会は思った以上に楽しかった。
「樹は先生になれるね」
と言うと、樹は少し笑いながらも眉を寄せ
「それは褒めすぎ」
と謙遜した。 話をしていると自転車はあっという間に家の前に着いた。私は自転車を降りる。樹は自転車に乗ったまま、ハンドルに両ひじを軽くつけて、私を見た。
「なぁ菜穂」
「ん?」
私は隣にいる樹を見た。
「来週の英語の文章、今から翻訳するの?」
「うん。今樹に英語を教えてもらったから、やる気が出た」
「でも翻訳できるの?」
「んー……」
「俺、教えようか?」
と言うので私は驚いた。
「本当!?」
「いいよ。じゃあ俺の家来る?」
「行く!」
テンションが上がったまま答えた。が、少し考えて私は、はっとした。
「い……かない」
と言い、急いで首を横に振ると、樹は私を見て笑った。
「えらい。覚えてたな」
口ごもる私を何故か満足そうに見た樹は、その場で自転車を降りて
「じゃあな」
と言い残し、自分の家の門の扉を開けた。
「ちょ、なんなの?」
私はさらに口をつぐみ、樹なんか知らんと思いながら、自分の家の門を開ける。庭に自転車を止め、自転車から降りて鞄の中から家の鍵を探した。火曜日と木曜日は樹のお母さんと入れ違いで私のお母さんがパートの日なので、家の鍵は閉まっている。
「鍵……あった!」
鍵を取り出し、家の扉に鍵を差し込んだ時に
「菜穂ー」
と樹の声がして振り向く。自転車を置いてきた樹が私の家の門の前に立っていた。私は樹を見て、入れた家の鍵を引き抜き、もう一度門に近づき、門の扉を開けた。
「何ー?」
私が声をかけると樹が私の側に来て、右手に隠し持っていたノートを私に差し出した。
「ん? 何これ」
私はノートを見て、樹を見る。
「英語のノート。次の英語の授業でやる文章、実は翻訳してあるんだよね」
「ええ! 樹やるの早いね」
「まあね」
「貸してくれるの?」
樹を見ると、樹は静かに頷いた。
「ありがとう! 本当は一人でやれるか不安だったんだよね」
持っていた家の鍵を制服の胸ポケットにしまいノートに視線を映して受け取ろうとすると、樹は何故かノートを手から離さなかった。軽く引っ張ったが、やはり強くノートの端を握ったまま離さない。仕方なく私は手の力を緩める。意地悪だと思いながらも、少し笑ってしまった。
「ちょっと何なの、樹」
顔をあげると樹の顔が近くにあって、私の唇に何かが触れた。
時が止まったようにぼんやりとしてしまって、突然胸が高鳴る。私はようやく状況を理解した。触れた感触がゆっくりと離れていくと私は樹を見た。樹は私を見ると優しく微笑んで、ほんの少し離れたと思ったらまたゆっくりと私に近づき、両腕を開いて私を温かく包み込んだ。私は狭い空間の中で温かさに包まれながら、樹を見上げた。
「……何か安心した。いつもそうやって反応してくれたら嬉しいのに」
樹にそう言われて、急に顔が暑くなっていくのを感じた。
恥ずかしくなって、表情を隠すように私は俯きながらも、樹の胸の当たりを片手で軽く叩き、声を振り絞った。
「ね、ねぇ」
「……何?」
抱き締められたまま内心焦っている私と違い、樹の声はとても落ち着いている。
「私、約束守ったよ……樹の部屋行かなかったよ!」
「油断大敵、だな?」
「な……」
そう言うと樹は私からゆっくり離れ、俯く私と目線を合わせた。
「……はい」
樹は再び、英語のノートを私に差し出す。それにかなり動揺しながらも落ち着けと自分に言い聞かせて、無言のままノートを受け取った。
「……明日は」
「え……?」
「明日は置いていくなよ、俺のこと」
まっすぐに見る目線を避けられないまま、私は黙りこんだ。その目が揺らぐことなく優しくこっちを見るので戸惑いながらも、私は頷いてしまった。私が一回ゆっくりと頷くと、樹もゆっくりと頷いた。
「……じゃあ、またな」
樹は私に目線を合わせたまま微笑み、私の頭をぽんぽんと優しく叩くと、姿勢を戻して門を出ていった。
樹が見えなくなって、私は立ち尽くしたまま、混乱する頭の中を解決しようと考え始める。
どうしようもなく恥ずかしくなって首を横に振り、私は玄関の扉を開けた。開けて中に入ると、自分でもおかしいくらいに足の力が一瞬で抜けた。手の甲で軽く口を押さえた。
「ちょっと……」
ノートで顔を隠しながらあれは樹だった? なんて分かりきったことを心の中で投げかけている。その場から少し動けずにいた。
「……落ち着かなきゃ」
深呼吸をして、私は思いきって立ち上がる。二階の自分の部屋へと向かった。
ふと手に持ったままの樹に貸してもらったノートを広げないままぼんやり眺めてそのスペースに置いた。ぼんやりしていたら落ち着くと思ったのに、熱が一向に覚めない。
「落ち着け……」
私は目を閉じる。静かに鼻唄を歌い始めた。あのCMの曲を最初から少しスローペースで。心を落ち着かせるために。
『遠くまで行ける靴を履いて
あの流れ星を見に行こう』
歌うのを途中で止めて、顔をあげて窓の外を見た。
隣の家からピアノの音が聞こえてきた。
偶然にも私の鼻唄と同じだったその曲は、私の今歌っていた部分と見事に重なっていた。
タイトルも歌手名も分からないその曲。ピアノのメロディーは、樹がいつも鼻唄で歌っているとおりだ。ピアノを耳コピして弾けることにも驚いた。本来のCM曲はこれであっているのかは分からないけど、私にとってこの曲は大切な思い出の曲。
キスなんてしておいてすぐにピアノを弾ける樹が何だか憎らしくも感じるが、心が落ち着いてくる。
「……ねえ、樹は好きになる人を間違えてるよ」
頬杖を軽くついて、私はもう一度目を閉じた。
「でもね……」
目を閉じると、ピアノの前に座る樹の横顔が見えた。横顔を見ている私の方をふと見た樹はそっと微笑んでいる。その時に幼い頃のピアノを習い始めた時の樹の姿が重なっていた。
「大好き。私は樹のことが、大好き」
呟いたら少し泣きそうになって、私はすぐに笑顔を無理矢理作った。
――
次の日の朝。制服に着替えて鞄を持ち玄関を出ようとすると、一階の廊下で私のお父さん、澤田尚哉《さわだしょうや》と目が合った。
「菜穂元気?」
お父さんは仕事でいつも帰りが遅く、だいたい朝は早い時が多い。
私が出かける時には、いつもだといなかったり寝ていたりする。家族だと言うのにお父さんを寝る姿以外でちゃんと見たのは二週間ぶりだった。
「元気だよ」
「ならいいけど。気を付けてな」
お父さんはいつものように私に明るく話しかけて、笑顔を浮かべている。
「うん、行ってきます」
そこへお母さんが慌ててやって来た。
「菜穂、お弁当忘れてるよ!」
「あ」
「うっかりして。はい」
お母さんから、お弁当の入ったランチバックを受けとり、鞄の中に入れる。
「行ってきます」
「菜穂、勉強しっかりな」
「いってらっしゃい」
お父さんとお母さんに笑顔で見送られながら、私は玄関を出た。
玄関を出ると、自転車に乗った樹と目があった。ちょうど私の家の門の前まで来たみたいだった。
「菜穂、おはよう」
いつも通りの樹に、私はほっとした。
「おはよう。待ってね、今自転車を……」
「菜穂」
「ん?」
「自転車の鍵貸して」
そう言われて庭に止めている自転車から、視線を移して門の前にいる樹の方を見る。
「え、何で?」
「いいから」
私は首を傾げて鞄の中から自転車の鍵を取り出すと、門を開けて樹に渡した。樹はその鍵を私から受けとると、すぐに自分の制服の胸ポケットに入れた。
「あ、泥棒!」
「早く後ろ乗らないと行っちゃうよ」
「返してよ」
「嫌だ。今日はニケツで行くの!」
樹がわざと子供っぽく言うので、私は笑った。
「何その言い方は」
「早く乗って」
自転車に乗った樹が振り向いて何だか楽しそうに私を待っているので、私も少しその表情につられてしまった。私は樹の後ろに大人しく乗ることにした。
私が後ろに乗り、樹が自転車を漕ぎ、前進する。スピードが徐々に上がってくると、ふんわりと暖かく心地よい風が流れてきた。
「今日は何かいい感じの気温だよね」
「そうだよな」
いつものように樹の腰の両サイドの服を軽く掴みながら、私は少し目を閉じた。
「なぁ、菜穂」
「んー?」
私は目を閉じたままで、風を感じ、自転車の音を聞きながら樹に返事をする。
「昨日聞こえた? ピアノ」
「え……」
私は目を開ける。
「CM曲弾いたんだけど、聞いてた?」
私は昨日のことを思いだし、頷いた。
「うん、聞いてた。私はやっぱりあの曲が一番好き」
と言うと樹は
「そっか」
と自転車をこぎながら、一瞬こっちを振り向いて笑っていた。
「いつもはヘッドホンしながらピアノ弾いてるのに珍しいね」
「菜穂に聴こえるように弾いてた」
「そうなの? 何で?」
「いや、何か菜穂が歌ってる気がしたから」
私はそれを聞いて驚く。
「まあ、そんなことあったら奇跡だよな」
あははと笑う樹の背中を見た。
「奇跡起きてたよ」
「ん?」
「私、歌ってたもん」
「まじ!?」
「うん」
「嬉しいかも」
樹はご機嫌に鼻唄を歌い出した。私も笑顔が溢れた。
「……そういえば樹。来週のオーディションの曲、何にするか決まった?」
「迷ってるんだよね」
「オーディションはオリジナル曲なの?」
「カバーでもいいって聞いてるよ」
「どっちでやるか悩みどころだね」
「うん。楽しみ」
「オーディションが?」
「不安はあるけど、それ以上夢叶うかもしれない」
私はそれを聞いて嬉しくなった。そして樹は強いなって思った。
「頑張れ樹。応援しか出来ないけど」
樹はそっと笑った。
「……十分だよ」
自転車は信号にさしかかった。赤信号になって、樹は自転車を緩やかに止めた。
「そういえば、菜穂。昨日英語の勉強した?」
樹にそう聞かれて出来るわけないと心の中で突っ込んだ。樹が英語のノート貸してくれた時にあんなことするから、頭から離れず、正直それどころじゃなかった。
「いや……」
「空は覚えた?」
「そーら!」
「……おい、まじか」
樹に呆れられ、私は笑う。
「嘘だよ。スカイだよね?」
「良かった。菜穂は忘れっぽいから本気にした」
「えへへ」
樹が私に振り向いた時、待っていた信号はもうすぐ青になるところだった。樹はハンドルを握り前方に視線を戻した。その時だった。私の視界が突然ぐらりと歪み、どくんと大きく鼓動がして、胸に激しい痛みが襲ってきた。
信号が青になり、自転車は進む。視界が揺れ、胸が苦しくなる。原因は……分かっていた。叫びたい気持ちを必死に我慢し、私はとっさに樹に強くしがみついた。樹は一瞬びくっとして走行しながら少しだけ振り返る。
「菜穂?」
樹が少し振り返り、私は樹に見えないように顔を隠して、荒くなりそうな呼吸と痛む胸を必死に押さえた。
「ん?」
樹は私の様子に疑問を抱きながらも前を見たが、緩やかに自転車の速度を落とし始めた。……まずい、このままでは樹が自転車を止めて完全に振り返ってしまう。そうしたらばれてしまう、樹にずっと隠していたことが。だから私は願った。振り返らないで、気づかれたくない、見られたくない、樹の邪魔になりたくない。どうか……おさまって。でもその気持ちとは裏腹に、樹の自転車は止まった。
「菜穂、どうかした?」
まずい、振り返る。私は目を閉じて顔を隠したまま懸命に声を出した。
「樹……!」
「え?」
「樹の自転車のかごに変な虫がいる!」
「虫?」
樹はこちらに振り返ろうとしたが、すぐに前方を見た。
「どこ?」
「怖い……!」
「え、いる?」
樹は自転車のかごを見ている。その時、願いが通じたのか、私の張り裂けそうな胸の痛みは何とかすぐにおさまってくれた。顔を上げるとまだ少し視界がぼんやりしたが、私はほっと息をはいた。
「なぁ、いないよ」
樹が振り返り、私を見た。私はもう一度息を吐き、自転車のかごを見た。
「本当だ。もういないね」
私が笑うと、樹が首をかしげる。ぼやけた視界ももとに戻り、樹に抱きついていた私はいつものように樹の服の裾に持ち直し、手をグーにして片手をあげた。
「出発」
樹は不思議に思いながらも、自転車のペダルをこぎはじめる。
「変なの」
そう呟く樹に、私は笑ってごまかす。
「どんな虫がいたわけ?」
「えーっとね……丸くて青くて……」
「そんな虫いるの?」
「……ねー? もうびっくり」
「菜穂って普段は虫怖がるタイプじゃないのにな」
「……ごめんね、樹」
私がそう言うと、樹は前を向きながら
「んー? 別にいいよ」
と言った。