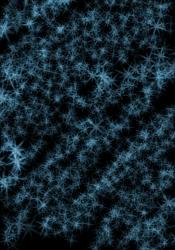青山と樹は教材室にやってきた。
「移動させるのは教壇の隣にある箱に入った譜面台と、あとは……」
樹は青山を横で見てて、ふと目をそらすように前を向く。
「なあ、青山」
「んー?」
青山は紙から目を離さず、樹にそれなりの返事をする。
「本当に、ありがとな」
青山はその紙から目を離して樹を見た。
「何だよ。樹の実力で勝ち取ったんだろ?」
青山は平然と言う。
「青山が言ってくれたから、俺はあの舞台に立ったんだ」
「ま、俺のおかげも一理あるか……なんて。あれは樹の実力だろ」
「そうかな……」
「そうだよ。それより樹、菜穂ちゃんと何かあった?」
青山は唐突に話を変え、樹は少し驚いて青山を見る。
「……何で?」
「お前らいつも一緒に登校してるだろ? 今日は別々じゃん」
「そうだ、な……」
樹は言葉に詰まる。
「俺、電車で菜穂ちゃんと会ったもん。昨日菜穂ちゃんが俺に対する悪口ばかりのメールをよこしてさ、『何これ!?』って聞いたら『気持ちを吐き出す場所がほしくて』って言われて……絶対俺じゃなくて、樹のせいだろ」
青山を見て、樹は少し笑みを浮かべているが目を伏せた。
「青山」
「何?」
樹はため息をついた。
「俺、青山になりたいかもしれない」
「は? 何それ」
青山は一瞬きょとんとしてから、少し笑って樹を見る。でも樹の顔は少し深刻そうだったので、青山の笑顔はすぐ消えた。
「菜穂は青山には気持ちを吐き出せるみたいだからさ。……いいな、青山は」
「樹のこと大切にしてるから言えないってこともあるんだよ、きっと」
「言ってほしいよ。俺、小さい頃から菜穂の側にいるのに……」
目を伏せる樹を見て、青山は一瞬慌てたがすぐ冷静になる。
「何情けないこと言ってるんだよ。言っとくけど樹が俺になったら菜穂ちゃんには絶対好かれなくなるからな? 菜穂ちゃんが好きなのは俺じゃないんだから」
「うーん」
「どうしたんだよ、樹らしくない。そんな落ち込んで」
樹はそ少し考え込んだ後、青山に目を合わさないままそっと口を開いた。
「なあ、青山。こんな話知ってる?」
「ん?」
「プロのボーカリストって言うのはさ、歌うだけでその人の性格、考えてる気持ちが一瞬で見抜けるんだ」
「え?」
「歌のテンポや、感情の込めかた、発声の癖なんかでさ」
「へぇ……何か占い師みたいだな」
青山は、俯いた樹のほうを見たまま答える。
「昔、ボーカル教室の先生に教えてもらったんだ。俺は素人だし全然分からなかったけど、俺にも少しずつ先生の言っていた意味が分かるようになってきたんだ」
「へぇ……凄いなそれは」
「菜穂には今、二つの雑音が聞こえる」
「雑音?」
青山は、眉を寄せた。
「一つは大きくて、何か最近菜穂は俺を避けてるみたいだからそれが理由と分かるけど……もう一つは」
「もう一つは?」
「何かは分からないけど小さくて、思えば昔からあった雑音、かな」
「大きな雑音と小さな雑音?」
「気になってるんだ。中学の卒業式前くらいから」
「そうなのか?」
「うん。本当はさ俺、中学の卒業式に菜穂に告白するつもりだったんだ。でもその頃から雑音がだんだんと分かるようになって。菜穂は理由はよく分からないけど俺から離れようとしてる、きっと、俺はフラれてるんだって告白する前に気づいたんだよね」
「そんな、考えすぎじゃない?」
「たまたま高校の進路が同じだったし、告白は保留にしてまた距離を縮めていけばいいって思ってたんだけど、一つの雑音が大きくなるし、小さな雑音の正体も分からない。俺さ何か今、余裕がないんだよね」
「樹?」
「菜穂がだんだん離れていっていなくなりそうで……怖い」
樹はふいに片手で、自分の視界を塞いだ。
青山は樹の様子に焦ったが、樹の不安を煽らないように、何とかその表情が出ないように押さえ込んだ。
「な、何言ってんだよ。菜穂ちゃんはいなくならないよ。普段は分かりにくいけど、樹のこと好きだもん」
「そうかな……」
「そうだよ。もうどうしたんだよお前は」
「だってさ」
「一緒に登校してこなかったぐらいで、そんな落ち込むな」
「そういうわけじゃ、ないけど……」
「今はオーディション決まったことでも喜んどけよ、な?」
青山に諭され、樹は顔をあげ、ゆっくり頷いた。
「……そうだよな。ごめん」
「いいよ。その分譜面台運んでもらうから。言っとくけどあれ想像以上に重いから覚悟した方がいいよ」
青山が譜面台をさしながら笑うと、樹もそっと微笑む。
もちろん今の私にはそんな二人の話を知るはずもなかった。