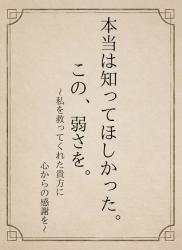「ちっ、姉貴のせいで注目の的じゃねーかよ。マジで最悪。だから家から出たくねぇんだよ」
俺は大きく舌打ちをしながら姉貴と客の女たちを睨みつける。
「ごめんよ、弟。なんも考えてなかった……」
「あ゙? アホなんじゃねえの。……はぁ、もういいよ。姉貴が満足するまで付き合えばいいんだろ」
姉貴の申し訳なさそうな声に、俺は大きくため息をつくと執事が案内した椅子に座った。
革張りの豪華な一人掛けソファに体が沈み込む。
「いや、これいいかも。ふかふか」
予想外な心地よさに俺はボフボフとソファを叩く。
「ふふっ。それは良かったです。ご注文がお決まりになりましたらお呼びください。お嬢様、旦那様。……では」
反応したのは姉貴ではなく、俺たちを案内した執事だった。
その声に聞き覚えがあり、反射的に顔をあげる。
が、彼はもうこちらに背を向けていた。
その背中への既視感。
いつも、この背中越しに黒板を見る。
「……鷹司?」
俺は大きく舌打ちをしながら姉貴と客の女たちを睨みつける。
「ごめんよ、弟。なんも考えてなかった……」
「あ゙? アホなんじゃねえの。……はぁ、もういいよ。姉貴が満足するまで付き合えばいいんだろ」
姉貴の申し訳なさそうな声に、俺は大きくため息をつくと執事が案内した椅子に座った。
革張りの豪華な一人掛けソファに体が沈み込む。
「いや、これいいかも。ふかふか」
予想外な心地よさに俺はボフボフとソファを叩く。
「ふふっ。それは良かったです。ご注文がお決まりになりましたらお呼びください。お嬢様、旦那様。……では」
反応したのは姉貴ではなく、俺たちを案内した執事だった。
その声に聞き覚えがあり、反射的に顔をあげる。
が、彼はもうこちらに背を向けていた。
その背中への既視感。
いつも、この背中越しに黒板を見る。
「……鷹司?」