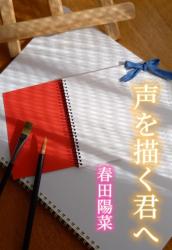「朔いいなー。あの夏帆先輩の恋人だもんな」
「え、演劇の話だろ!」
稽古終わりの帰り道、同じ演劇部の泰生が僕の平凡な日常を一瞬で滅ぼすような爆弾発言をしたので、慌てて否定した。僕は周囲を見渡し、誰かに聞き耳を立てられていないかを確認する。幸い、夏休み真っ只中ということもあり、高校の正門付近の横断歩道に人影はなく、僕は命拾いした。
目の前の信号が青点灯から点滅し始めたので、自転車のブレーキをかける。
「誰かに誤解されるような言い方するなよ」
「ごめんごめん。でもどんな徳を積んだら夏帆先輩の恋人役に抜擢されるんだよ!」
泰生が嘆くのもやむを得ない。
夏帆先輩は演劇部の部長で、演劇部の心臓ともいえる存在だ。圧倒的な演技力とカリスマ性を持っていて、見る人を魅了する。部内だけでなく、校内でも人気の先輩だ。
僕は夏帆先輩に初めて会った日のことをよく覚えている。1年前、高校に入学して間もない僕は、部活動紹介の際に体育館で披露された演劇部の舞台演劇を見た。全体的に演劇のレベルが高くて、僕は瞬きも惜しいくらい夢中になった。
その中でも一際目を惹く人がいた。それが夏帆先輩だった。自信に満ち溢れた演技と見る人を惹きつける華やかなオーラがあって、目が離せなかった。僕はあっという間に虜になった。僕もあの人と同じ舞台に立ちたいって、そう思ったんだ。後輩想いで、僕たち一人一人に寄り添った指導をしてくれた。そんな夏帆先輩だからこそ、僕とありもしない噂が流れるのは避けたい。
「しかも朔、主役じゃん。嬉しくないのか?」
「今日の稽古だって上手くできなかったし、不安だよ。ミスばっかりで顧問に怒鳴られたし、夏帆先輩にも迷惑かけた」
「まだ稽古始まったばっかりじゃん!主役が弱気になるなよ。俺も頑張るからさ」
泰生のこういうところに僕は救われてきた。見た目はチャラいけど、根は真面目で芯が強い。大雑把だけど楽観的でなんだかんだ憎めない。そんな泰生の期待を裏切りたくない。
今、僕がやるべきことは……。
「おーい、朔!青信号だぞ」
気づけば、すでに泰生が横断歩道を渡っていた。
「ごめん泰生。今日ちょっと寄るところあるから、じゃあな!」
「おい、どこ行くんだよ!朔!」
突拍子のない僕の行動に戸惑う泰生を置き去りにして、僕はペダルを踏んだ。
このままじゃダメだ。今の僕に主役は務まらない。夏帆先輩と並んでも見劣りしないくらいもっと稽古しないと。僕は息を切らしながら、全力で自転車を漕ぎ回した。
***
追い詰められた時、一人になれる場所を探して殻にこもるのが、昔からある僕の悪い癖だ。疲れ果て、真夏の暑さから逃げるように、僕は高架下の陰に身を潜めた。どこからか聞こえる蝉の声も目の前を流れる河川から聴こえるせせらぎも風情があって心地良い。休憩がてら僕はすぐ側の河川敷に腰かけ、ペットボトルの天然水を勢い良く飲んだ。トートバッグの中に入れていた水は生温くなっていて、微々たる不快感を覚えた。気を取り直して、僕はトートバッグから台本を取り出し、配役が記されたページを開く。
『王子ーーー長谷川朔
姫ーーー早瀬夏帆』
僕は、この配役の並びがやけに落差があるように感じた。
9月の文化祭で披露する舞台演劇向けて、僕たち演劇部は夏休み中も稽古に励んでいる。
披露する作品は『巡逢』というフランスが舞台となった恋愛物語だ。フランスの王子と姫が運命的な出逢いを果たし、2人は逢瀬を重ね、やがて恋に落ちる。しかし、悲惨な運命が2人を引き裂き、2人は異国の地で暮らすこととなる。不遇な状況に陥りながらも、いつかまた出逢えると信じて時を経る。そして10年後、2人は奇跡的な再会を果たし、無事に結ばれることとなる。どんなに居場所が離れていても、心さえ繋がっていれば、神は2人を巡り逢わせる。多岐に渡って人を愛することの希望と2人の一途な想いを描いた純愛物語だ。
つい先日、脚本家兼監督の顧問から配役が発表された。
「今回の主役は長谷川朔だ」
顧問がそう言うと、部室内がざわついた。一番衝撃を受けたのは僕だった。僕は演劇部に入部して初めて、主役に抜擢されたのだ。文化祭で披露する演劇は、3年生の先輩方にとっての集大成だ。失敗できないプレッシャーが僕を襲う。僕の心は、主役を演じることの重圧にすでに押しつぶされそうだった。
その日の夜、血眼で台本を読み終え、僕は恋愛感情を理解することに苦しんだ。僕の恋愛経験の乏しさが、作品の世界観への没入を妨げていると痛感した。そもそも僕が王子なんて柄じゃない。本来、文化祭の舞台演劇の主役は、この舞台演劇を最後に引退する3年生が務めるのが主流だ。先輩方の中にもっと適任な人がいたはずじゃないか。僕は心に溜まった不安を押し出すようにため息をついて、今日の稽古でやったシーンのページを開く。
今日、僕がどうしても言えなかった台詞がある。
『僕はきっと、貴方に出逢うために生まれてきたのです』
姫に一目惚れした王子が初めて姫にかけた言葉だ。恋に酔いしれた王子の口説き文句に虫酸が走る。自信家で積極的な王子の人物像は、僕と対照的であると感じた。
「僕は……きっと……きっと……!」
ダメだ。人気のない場所でも、羞恥心が勝って台詞に感情が乗せられない。自身の現状に失望し、僕は俯くことしかできなかった。
「私に逢うために生まれてきたんだよね?」
不意に耳元で鈴の転がるような声がして、僕は顔を上げた。視界の隅に華やかな黄色いスカートが映って、ゆっくりと視線を上に向ける。
一瞬、思考が停止した。
「夏帆先輩!?」
「ふふっ。自主練?えらいね」
夏帆先輩は僕の隣に腰かけ、頬に手を添えてほほえんだ。制服とは違う白い襟シャツに黄色いスカートといった見慣れない姿に僕は動揺を隠せなかった。まっすぐに僕を見つめる瞳に胸の奥が鼓動する。
「な、なんでここにいるんですか」
「それはこっちの台詞だよ。こんなところにずっといたら熱中症になっちゃうよ。朔くん顔赤いよ?」
夏帆先輩は僕の顔を見るなり、困り眉で笑った。鏡を見なくても分かるくらい、顔が火照っている感覚がある。夏の暑さのせいだけじゃない気がするけど……。
「良かったらうちのバイト先においでよ。カフェだから冷房きいてるし、スイーツも沢山あるよ!」
夏帆先輩は両手を胸の前でパンっと鳴らし、名案を閃いたといわんばかりに活気よく提案した。
「……いいんですか?っていうか、夏帆先輩バイトしてるんですね」
「うん。高1の秋くらいからね。もうすぐ休憩終わるからもう戻らないと。ここからすぐ近くだし、案内するよ!」
「お願いします」
僕はもはや、夏帆先輩の提案に乗る以外の選択肢は無かった。それにしても、学業に加えて部活とバイトを両立してるなんてすごいな。泰生には気の毒だが、夏帆先輩の新たな一面を知ることができて、僕は少しばかりの優越感に浸った。
***
入り口の自動ドアが開き、店内に足を一歩踏み入れた瞬間、ひんやりとした空間に身を包まれた。店内は白を貴重としたシンプルな壁紙に温かみのある木製の家具が設置されていて、落ち着いた雰囲気の洋楽がかかっていた。ケーキ屋とカフェが併設されていて、様々なスイーツやお菓子が販売されていた。ショーケースには旬の果物を用いたケーキやタルト、プリンやマカロンっといた色とりどりのスイーツが並べられていた。高貴な雰囲気のお召し物を纏ったマダムたちのお茶会やお姉様方による女子会が開かれていて、僕の場違い感を痛感した。夏帆先輩に誘われなければ、一生訪れることはなかったであろう場所だ。稽古終わりで汗だくなうえ、Tシャツにスウェットパンツというラフな格好がこの雰囲気で悪目立ちしないか心配になった。
「こちらにどうぞ」
夏帆先輩は窓際のカウンター席に案内してくれた。
「えっと……じゃあ、アイスカフェオレください」
「かしこまりました!」
部活の先輩、後輩という関係でありながらも、夏帆先輩は僕を客として接してくれた。
僕はカウンター席の端っこに座り、窓から見える景色に言葉を失った。目の前に広がる河川敷は若草が生い茂っていて、風に吹かれるままに自由になびいている。その動きが連鎖し、美しい波紋のように若草を揺るがす。河川は静止画と見紛うほどに沈静に流れているが、太陽の陽射しを反射し、自然の輝きを帯びていた。自然豊かなこの街の景色をこの席から一望することができた。穴場スポットを見つけたようで、僕は密かに得をした気分になった。ひと通り景色を堪能した後、僕は注文したアイスカフェオレが来るまで再び『巡逢』の台本に目を通していた。
「お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ」
「ありがとうございます。……えっ?」
僕の目の前にはアイスカフェオレと小皿に盛られた2つのマカロンが置かれた。
「私からの気持ちだよ。受け取って」
「ありがとうございます。いただきます」
「ごゆっくりどうぞ」
僕は夏帆先輩のお言葉に甘えることにした。まず、アイスカフェオレで喉の渇きを潤した。コーヒーの苦味とミルクの甘さのバランスが程良く、冷たさがより一層美味しさを際立てていた。僕はマカロンを手に取り、一口齧った。外側の生地はサクサクしているが、中のクリームは濃厚で、食感にバリエーションがある。ただ甘いだけではなく、味に深みのあるスイーツだと思った。あまりマカロンを食べたことがなかったので、一つでも満足感が大きかった。マカロンは高級なスイーツという印象があったので、もう一つはゆっくり味わって食べた。
僕は夏帆先輩が働くこのカフェで小さな幸せなひとときを過ごした。
***
「朔くん!」
帰宅しようと自転車のロックを解除すると、夏帆先輩がちょうど裏口から出てきた。バイト終わりなのだろう。先程まで着ていたカフェの制服姿とは違い、清楚な雰囲気を醸し出す涼しげな水色のワンピースに着がえていた。何気に、夏帆先輩の私服を見るのは初めてかもしれない。夏休み中の演劇部の稽古は私服登校が認められているが、夏帆先輩は「夏の制服着れるのもあと少しだから」と、名残惜しそうに制服を着用していた。
「夏帆先輩、お疲れ様です。マカロン美味しかったです」
「喜んでもらえて良かった!朔くん帰り道こっち?途中まで一緒に帰ろうよ」
「はい」
僕は自転車を手で押しながら夏帆先輩の隣を歩いた。一つ返事で了承したものの、この非日常的な状況に僕は戸惑う。何か僕から話題を振った方がいいのだろうか……。
夏帆先輩は「夏は日が暮れるのが遅いねー」と、独り言とも捉えられるようなことを呟いていた。僕は夏帆先輩の呟きに適度に相槌を打っていた。
「朔くん、一人で抱え込んじゃダメだよ?演劇はみんなで作り上げるものなんだから」
そんな僕を見兼ねたのか、不意に図星を突かれた。どうやら、僕の考えていることは夏帆先輩にはお見通しらしい。正直、僕はこの状況下でも演劇のことで頭がいっぱいだった。
「……すみません。演劇との向き合い方が分からなくなって、迷走してました」
昔から自分の感情を伝えることが苦手だった。他人の顔色を窺って、周りの目を気にしてばかりだった。
そんな自分を変えてくれたのが演劇だった。自分の魂を役に憑依させることで、感情を自由に表現することができたからだ。でも今の僕は、演劇と向き合うことを避けてしまっている。
「なんか……昔の私みたい」
「えっ?」
言葉の意味が理解できず、思わず聞き返した。いつもより低い夏帆先輩の声に違和感を覚える。
「感情が色づく瞬間、知ってる?」
「知りたいです!」
僕は間を空けずに答えた。
紛うことなき僕の本心だった。
「じゃあ私のスパルタ指導に耐えるべし!明日の18時、高架下に集合ね」
「えっ?」
「ってことでよろしくね!また明日!」
「ちょっ、夏帆先輩!?」
夏帆先輩は清々しい表情で駆け出し、颯爽と帰路に続く橋を渡って行ってしまった。どうやら僕に拒否権はないらしい。僕の声は夏帆先輩の耳に届くことなく、夏の暑さに溶けてしまったようだ。夏帆先輩の背中を目で追うことしかできない僕は、やり場のない虚しさを覚えた。
***
「長谷川朔!!声が小さい!!」
「す、すみません!」
部室に顧問の怒鳴り声が響き渡る。演者だけでなく、大道具や衣装を作っている部員たちの視線が自然と僕に集まる。その視線の圧に僕は今にも逃げ出したい気分だった。
「声のボリュームは自信の度量と比例している。お前はもっと稽古量を積むべきだ」
「はい……」
「声が小さい!!」
「はい!!」
結局、今日の稽古も顧問の怒鳴り声で終わりを告げた。稽古中は僕にとって精神修行の時間になりつつある。稽古が終わると毎度の如く、全身から力が抜けていくようにその場に崩れ落ちてしまう。そんな僕の様子を見兼ねて、泰生が励ましに来る。僕は泰生が横にいてもなお立ち直れずにいた。
「まあそう落ち込むなって。そんだけ朔に期待されてんだよ。……で、昨日はどこに行ったんだよ」
「ちょっといろいろあって……」
泰生に知られると色々と面倒なことになると悟り、僕は言葉を濁した。
「LINEしても未読無視だし、気になって気になって、夜しか眠れなかったんだからな!」
「眠れてるのかよ」
「ぐっすりだよ!」
僕と泰生の不毛な会話の中、足早に部室を出ていこうとする夏帆先輩と目が合った。夏帆先輩は去り際に小さく手を振って部室を後にした。
今日もバイトなのかな……。
ズボンのポケットに入れていたスマホが振動し、僕は画面を確認する。
『今日の18時に高架下集合でよろしく!『巡逢』の台本持ってきてね』
と、夏帆先輩からのLINEが一件送られていた。どうやら演劇部のグループラインから僕を追加し、連絡したようだ。にわかに信じがたいけど、昨日の出来事は夢ではなかったみたいだ。昨日夏帆先輩が言っていたスパルタ指導とは、やはり舞台演劇の『巡逢』のことだったのか。僕は腹を括り『了解です』と返信した。
***
僕は夏帆先輩との約束通り、18時にあの河川敷まで自転車で向かっていた。夏は日が長く、この時間帯でもまだ明るさを保っていた。しかし、暑さは昼と比べると少し和らいでいるように感じた。
予定時刻より五分早いが、高架下にはすでに夏帆先輩の姿が見えた。今日は白いTシャツにジーンズというカジュアルな格好をしている。
「夏帆先輩。遅れてすみません」
「朔くん!早いね」
「夏帆先輩こそ」
僕はすぐ側に自転車をとめ、夏帆先輩のもとへ駆け寄った。
「昨日言ってた、感情が色づく瞬間って……」
僕がそう尋ねると、夏帆先輩は瞳を輝かせた。
「私は舞台でその瞬間に出逢って、演劇がもっと好きになったの。上手く言葉にできないけど、感情が輝きを帯びて溢れ出すというか……。例えるなら、恋に落ちた時の感情に似てる気がする」
恋愛経験のない僕には、あまりイメージが掴めなかったけれど、僕もその瞬間に出逢ってみたいと思った。
「朔くんは、誰かを好きになったことある?」
「恋愛的な意味では、ほとんどありません……」
僕は17年の人生を振り返る。僕は不思議と誰かに恋愛感情を抱くことがなかった。たまに仲の良い女友達から告白されることはあったけど、友達だと思っていた相手からの好意を受け入れることができず、断ってしまった。恋愛に発展することで、今までの関係性に戻れなくなることを避けたかった。しかし今思えば、僕は相手の気持ちと向き合うことから逃げていただけなのかもしれない。僕はこのまま、恋を知らないまま大人になっていくのだろうか。
「まあ、何事にも経験は大事だよ!」
夏帆先輩は僕の背中を押すような声で言った。
「じゃあ今日は8ページ目からやろうか」
「はい。夏帆先輩、台本持ってきてないんですか?」
「台詞はもう全部覚えてるよ。あとは身体に叩き込むから」
「……流石です」
さりげなく格の違いを見せつけられ、僕は自分の未熟さを改めて痛感した。
この日から夏帆先輩によるスパルタ指導が始まった。
***
『僕たちの出逢いが運命ならば、きっとまた何処かで巡り逢えるでしょう。その際は、極上の愛の言葉を添えてお迎えに上がります』
愛してやまない姫と引き裂かれる運命に陥った王子が別れ際にかけた言葉。いつかまた出逢う日を夢見る王子の希望が込められているが、どこか哀愁を感じる。『巡逢』にとって非常に重要な台詞であるのに、僕はこのもどかしさを表現することに苦戦していた。
「言葉にはね、一つ一つ違った輪郭を持ってるの。そこに声色や間の取り方を加えて、表現の幅を広げるんだよ」
「なるほど……!」
夏帆先輩のアドバイスを忘れないように、僕は台本に赤ペンで『声色』『間の取り方』と書き足し、額の汗を拭った。
あれから毎日、18時から2時間ほどこの河川敷で、夏帆先輩と演劇の稽古をするのが僕の夏休みの日課となっていた。多忙な日々を送っている夏帆先輩の2時間を僕に費やしてくれているのだから、僕は不安を感じる暇もないくらい、演劇と向き合う日々を送っていた。
「朔くんの演技は、まだ内に秘めてる感じがする。でも、心の内にある確かな情熱を感じるんだ」
「殻にこもってしまう悪い癖があるのは、自覚しています……」
もともと僕が持っている気質や性格が、役への感情移入を妨げているような気がする。上手くやりたいという気持ちは人一倍持っているのに。
「顧問はそれを見抜いてるんじゃないかな。きっと、朔くんの殻を破った演技を望んでるんだよ」
いつか、この殻を破る時が来るのだろうか。
僕は自分自身に問いかける。
殻を破るためにも、一つ一つを着実にこなしていくしかない。結果は後からついてくるものだと信じている。
「大丈夫?休憩する?」
「いや、まだやれます」
「ふふっ。そう言うと思ったよ」
夏帆先輩は「そうこなくっちゃ」と言わんばかりの強気な笑みを浮かべていた。まるで、僕のスイッチの入れ方を熟知しているようだった。
「朔くんのことを知れば知るほど、輝きが見えてくる。伸びしろがある人だと、教えがいがあるよ」
夏帆先輩のその言葉は、僕に希望を与えてくれた。
***
来る日も来る日も、僕らは稽古を重ねた。
「だいぶ台詞に感情が乗るようになってきたね」
「本当ですか!?ありがとうございます!」
「うん!あとは頭だけじゃなくて、身体に覚えさせると、もっと良くなると思うよ」
「はい!」
あまり自覚はないけど、客観的に見て成長を感じているのなら良かった。それに、夏帆先輩から少しだけ認められた気がして嬉しかった。
「じゃあちょっと休憩しよっか。演劇は結構体力使うし、水分補給大事だよ」
そう言うと夏帆先輩は高架下の陰に腰かけ、天然水のペットボトルを飲んだ。僕は顔から首筋を伝う汗をタオルで拭き、天然水のペットボトルを飲んだ。渇いた喉に天然水が染み渡り、微かな幸福感を覚えた。稽古終わりに飲む水が一番美味いことを僕は改めて実感した。
僕も高架下の陰に腰かけ、僅かに髪を揺らす夏風に涼んでいた。
「夏帆先輩が演劇をする上で、心がけてることは何ですか?」
僕はふと、気になっていたことを聞いてみた。夏帆先輩はどんな想いを抱えて演劇と向き合っているのか、ずっと知りたかった。
「うーん……。独りよがりの演技をしないことかな」
夏帆先輩は珍しく少し曇った表情をしていたので、なんだか申し訳なくなった。
「実は……演劇部を辞めようと思った時期もあったんだ。顧問に独りよがりの演技をするなって言われて、どうすればいいか分からなくなったの」
僕が演劇との向き合い方が分からなくなっていた時に「昔の私みたい」と言っていたのは、そういう意味だったのか。夏帆先輩も僕と同じような悩みを抱えていたことに驚いた。
「期待されてたから、もっと上手くなりたくてずっと一人で練習してた。でも、演劇はみんなで作り上げるものだから、一人だけ上手くても意味なかったの。だからこうして、同じ志を持つ人と一緒に稽古できることが幸せなんだ」
" 同じ志を持つ人 "と言った時に夏帆先輩と目が合った。この稽古の時間を幸せだと思ってくれているのは正直、嬉しい。でも素直に喜べなかった。もしかしたら、部員の僕たちが夏帆先輩に抱いていた期待や信頼が重荷に感じていたのではないだろうか。そんなことを考えていたら、僕は合槌を打つタイミングを逃してしまい、しばらく聞き役に徹することにした。
「高1の文化祭で披露した舞台演劇が終わってから部活に行かなくなって、あのカフェでバイト始めたんだ。そしたら店長に『貴方は人を惹きつける華やかなオーラがあるね』って褒められたの!素の私を認められた気がして、すごく嬉しかったんだ」
夏帆先輩はバイトの話になると、だんだんと笑顔になっていった。
「演劇から離れたくてバイトを始めたのに、気づいたら演劇のことばっかり考えちゃうの。やっぱり私、演劇が好きなんだなって改めて分かったんだ。だからまた演劇部で頑張るって決めたの。復帰して初の舞台演劇で" 感情が色づく瞬間 "に出逢ったんだ。その瞬間、私が今まで演劇と向き合ってきた時間は無駄じゃなかったんだって思ったの」
「無駄じゃないですよ!僕は夏帆先輩がいたから、演劇部に入ろうと思ったんです。貴方が居てくれたから、僕は演劇の楽しさを知ることができました」
しばらく聞き役に徹していた僕が食い気味で話し始めたので、夏帆先輩は目を丸くして、驚いた様子だった。突発的な行動や言動をしてしまうのも僕の悪い癖かもしれない。でも全部、僕の本心だった。
「ありがとう。朔くんにそう言ってもらえて良かった!もっと早く朔くんに会えてたら良かったな。でも、私の人生でそんな風に思える人に出会えて良かった」
夏帆先輩は満開の向日葵のような笑顔を僕に向けた。僕の言葉は想像以上に夏帆先輩の心に響いたようだった。僕は照れくささを隠すために別の話題を振ることにした。
「夏帆先輩って、やっぱり演劇の道に進むんですか?」
「うん。東京で本格的に演劇を学びたいな」
夢を語る夏帆先輩の瞳は希望に満ちていた。
「そうですか……。頑張ってください。応援してます」
「ありがとう。部活引退してもたまに顔出すよ」
「いつでも待ってます」
夏帆先輩と同じ舞台に立てるのも今回で最後か……。分かっていたはずだけど、限られた日々に僕は胸が締めつけられたような痛みを覚えた。いつまでもこうやって、当たり前みたいに夏帆先輩と過ごせたら良かったのに。
***
「ごめん朔くん!遅れた!」
「大丈夫ですよ。バイトお疲れ様です」
何らかの理由でバイトが長引いたのか、夏帆先輩は約束の時間より30分ほど遅れて来た。僕はその間、顧問や夏帆先輩に指摘された箇所を見直し、台本に赤ペンで書き込んだり、付箋を貼ったりしていた。僕の台本は、どのページを開いてもびっしりと書き込みが施されている。台本が稽古量を表しているようで、僕にとってのモチベーションだった。
「じゃあ今日はダンスの復習からしよっか。動きを客観的に見るのも大事だから、後で見返せるように動画を撮っておこう」
「了解です。画角調節するんでちょっと待ってください」
僕はあらかじめ用意していた三脚にスマホを取りつけ、画面の中の夏帆先輩の全身が映るように画角を調節する。
「良い感じにできました」
「ありがとう。じゃあ私が音楽流すね」
「お願いします」
夏帆先輩の方のスマホで音楽を流し、三脚の側に置いた。
僕は左手で夏帆先輩の右手を取り、背中に右手を回して抱き寄せる。これが社交ダンスの基本姿勢だ。ダンスの稽古は物理的な距離の近さに毎度、動揺する。
「ちゃんと支えててね」
「は、はい」
3拍子の音楽に合わせて、円を描くように回転する。足並みを揃え、男女の体格差を活かした振り付けで美しさを表現する。
「朔くん、ちゃんと瞳見て」
僕は一瞬だけ、夏帆先輩と目を合わせた。夏帆先輩は少し悪戯な笑みを浮かべていた。僕はそれ以上目を合わせられなかった。平常心を保つのに精一杯で、目を合わせられない僕をからかっているのだろうか。夏帆先輩の笑顔も甘い言葉も全部演技って分かってるのに、どうしてこんなに胸が高鳴るんだろう。せめて演劇の時だけでも夏帆先輩の視線を独り占めできたらいいのに。
「ふふっ。朔くんの動きなんかぎこちないね」
「夏帆先輩だって、途中でこけそうになってるじゃないですか」
「バレたか」
撮影した動画を見返しながら、夏帆先輩と小競り合いを繰り広げていた。一つの画面を二人で見るために隣並びで座っているため、自然と夏帆先輩との距離が近くなる。夏帆先輩の髪が僕の肩に触れていて、どうにも落ち着かない。まあ、こんなに意識しているのも僕だけなんだろうけど。
ヒューーー……、ドーーーン。
「あ、朔くん見て!花火!」
「おー……。綺麗ですね」
このあたりで夏祭りが開催されているのだろう。演劇のことしか頭になかった僕は、夏祭りの存在など忘れていた。まさか、夏帆先輩と花火を見ることができるなんて思わなかった。夜空に打ち上がる花火も良いけれど、目の前の河川の水面に反射して映る花火は朧げで、どこか儚くて、美しかった。
夏帆先輩は花火に夢中にな様子で、分かりやすくテンションが上がっていた。そんな夏帆先輩の姿につられて、僕も心が舞い上がる。
普段見せない夏帆先輩のあどけない姿に僕の胸が密かにときめく。
こんな時間がずっと続けばいいのに。
夜空に打ち上がってーーー咲く。
また打ち上がってーーー咲く。
その一瞬の煌めきを夏帆先輩の隣で見届ける。
上手く言葉にできないけど、僕にとって永遠に感じた瞬間だった。
***
「おー!朔、かっけぇ!まじで王子じゃん」
「ありがとう」
ついに本番当日。舞台衣装に着がえ、髪のセットまで終えた僕は、舞台の中心で演劇のイメージトレーニングをしていた。泰生の無邪気なリアクションに自然と僕の口角が上がる。
途端に舞台袖から男女問わずの黄色い声が上がった。声のする方へ僕と泰生が目を向けると、青いドレス姿に身を纏う夏帆先輩の姿があった。いつもおろしている髪は後ろで一つにまとめていて、より清楚な雰囲気を醸し出していた。華奢な体型にふんわりとしたドレスがよく似合っていて、僕は夏帆先輩に見惚れてしばらく目が離せなかった。
「夏帆先輩……美しい……」
泰生は心臓を射抜かれたように悶えていて、僕と同様にすでに心を奪われている様子だった。泰生は姫の城に仕える執事役なので、黒のタキシードを身に纏っている。いつも毛先を遊ばせている髪型の泰生だが、今日は硬派な印象を与える執事ヘアスタイルだった。
「泰生もかっこいいよ。イケてる」
「えー!やっぱり!?さすがに今日の俺のビジュアル満点だよね」
「お、おう」
泰生の切り替えの早さに若干、動揺した。見た目は変わっていても、中身は変わらない泰生の姿が可笑しかった。僕も泰生のマインドを見習いたいものだ。
「今回の舞台で名脇役になってやるよ。朔の主役も喰っちゃうかも」
「喰われねぇよ」
泰生は「キャー!朔かっこいいー!」と、わざとらしく無駄に甲高い声で言いながら舞台脇にはけていった。相変わらずの調子の奴だけど、泰生のおかげで緊張が和らいだ気がする。
「第50回、水瀬高校演劇部による舞台演劇『巡逢』の開演まで今しばらくお待ちください」
体育館及び校舎全体にアナウンスが流れる。
僕は一旦舞台脇にはけ、夏帆先輩のもとまで駆け寄った。
「いよいよですね」
「最高の舞台にしようよ」
「はい!」
僕と夏帆先輩は舞台の成功を誓い合った。
開演のブザーがなる。
観客の声が一瞬のうちに静まり、舞台に緊張感が走る。その緊張感から来る震えさえも、僕の心を突き動かすエネルギーに変える。少しずつ、僕の魂が役に憑依していく感覚に陥った。
幕が開け、僕に眩しいスポットライトが当たる。数えきれないほどの観客の視線を浴びる。もうすでに、僕の魂は完全に役に憑依していた。
***
演劇もついに終盤。
10年越しにフランスの時計塔の前で偶然、姫と再会するシーンだ。
恋焦がれた姫と目が合い、すれ違う。心の中に仕舞っていた感情がざわめき始める。僕が振り返り、姫の名前を呼ぼうとしたその瞬間、何の弾みかは分からないが、ステージ上に設置されていた3メートルに及ぶ時計塔が徐々に傾き始め、今にも姫の真上に転倒しそうだった。
「危ない!!」
僕は瞬時に姫を抱き寄せた。咄嗟の行動に体勢を崩し、僕らはステージ上に勢いよく倒れこんでしまったが、僕は両腕で姫の頭を覆うようにして守った。姫の背後で時計塔が転倒し、会場に鈍い衝撃音が響き渡る。なんとか、間一髪のところで姫を窮地から救うことができたようだ。だが、その異様な光景に観客がざわつき始める。
「姫、お怪我はありませんか?」
僕は即座に立ち上がり、姫に手を差し伸ばしたが、自分の声に違和感を覚えた。僕の声は観客のざわめきに掻き消され、姫に届いていない様子だった。
倒れた衝撃により、マイクが故障してしまったのだろうか。
どうしよう……。
終盤とはいえ、まだ僕の台詞は残っている。
想定外のハプニングにより、絶望的な状況に追い込まれた僕は、焦燥に駆られた。
憑依していた魂が役からどんどんすり抜け、舞台では封印していたはずの僕の本性が暴き出す。
一体、僕はどうすればいいんだ……。
いっそのこと、このまま夏帆先輩と一緒にこの場から逃げてしまいたい。
そんな考えが脳裏によぎった瞬間、差し伸べていた僕の手に温もりを感じた。僕のそばに座っていた夏帆先輩は僕の手をそっと握って、笑った。
そうだ、この人だ。
演劇の楽しさを教えてくれたのも演劇と向き合う姿勢を教えてくれたのもこの人なんだ。
僕にとって永遠の憧れで、かけがえのない人。
こうして、憧れの人と一緒の舞台に立つことができて幸せなんだ。
だからもう逃げたくない。
最高の舞台にするって約束したから。
僕は覚悟を決めた。
ハプニングさえ粋な演出に変えてやる。
「僕はこの瞬間をずっと、待ち侘びていました。」
僕の芯のある声が観客のざわめきを沈静化させる。
「貴方を想う気持ちは、永遠に変わりません」
静寂に包まれた会場に僕の声が響き渡る。
マイクが機能しないなら、声を張るしかない。
「僕は貴方が好きです」
それは僕の本心であり、僕なりの極上の愛の言葉だった。
王子じゃない、ありのままの僕の言葉。
姫じゃない、ありのままの君に贈るモノローグ。
観客にも僕の声が届いたのか、客席からは鼓膜を破るほどの歓声と拍手が沸き上がった。
フィナーレの音楽が流れ始める。
「僕と踊りませんか?」
僕はその場に跪き、再び手を差し伸べた。この台詞と動作は台本にはない僕のアドリブであったが、夏帆先輩はすぐに対応し、僕の手を取った。
「はい。喜んで」
その様子を見た観客たちは再び歓声を上げた。
10年の時を経て再会し、喜びの舞のワルツを踊る。僕は夏帆先輩と手を繋ぎ、支えるように背中に手を回した。流れる音楽に身を任せ、夏帆先輩と軽快に足並みを揃える。踊りは完全に身体に染みついていた。
「夏帆先輩、僕の瞳見て」
マイクが故障して、観客に聞こえないのをいいことに僕は夏帆先輩に悪戯を仕掛けた。珍しく動揺している夏帆先輩に僕は嬉しくなった。夏帆先輩は恥じらうように下唇を噛み、「もう……!」と言わんばかりの表情だった。
こんなに大勢の人に見られているのに、僕たちにしか分からないやり取りをしているのが可笑しくて、僕と夏帆先輩はどちらからともなく笑い合った。演技では表現できない自然な笑顔でいられた気がする。
ワルツを踊り終え、観客に目を向けたその瞬間、僕の視界は眩しく彩られた。
観客から贈られる拍手や笑顔は輝きを帯びていて、胸が熱くなった。今なら、なんでもできそうな気がした。
これが" 感情が色づく瞬間 "というのだろうか。
その一瞬の煌めきはきっと色褪せることなく、僕の未来を照らす道導となるだろう。
カーテンコールを終えて、『巡逢』の幕を閉じた。
最後に僕が舞台脇にはけると、顧問を先頭に部員全員が僕を迎えていた。
「よくやった……!」
顧問の声は少し震えていて、涙ぐんでいるように見えた。顧問からの初めてのお褒めの言葉に僕は目頭が熱くなった。そして僕は初めて、顧問の口角が上がっているところを見た。
***
演劇部での打ち上げが終わった帰り、思ったよりも遅い時間になってしまったため、僕は演劇部代表として夏帆先輩を家まで送ることになった。
3年生の先輩方や泰生から「今日は全部持ってけ、主役!」と主役イジリをされた。正直、悪い気はしなかった。
「それにしても、朔くんが本番でアドリブをするなんて驚いたよ」
「すみません。ちょっと調子に乗っちゃって……。でも、夏帆先輩が僕のアドリブに合わせてフォローしてくれたから、なんとか最後までやり遂げることができました。本当にありがとうございました」
「こちらこそ、ありがとう。良い意味で忘れられない演劇になったよ」
夏帆先輩とこんなふうに話せるのもこれが最後になるんだろうな……。僕は限られた時間を名残惜しく思い、一歩一歩を踏みしめるように歩いた。そのたびに僕は抱えきれないほどの淋しさに襲われる。
「じゃあ……私の家ここだから。わざわざ送ってくれてありがとう」
僕の想いも虚しく、あっという間に夏帆先輩の家に到着した。まだ、夏帆先輩に伝えてないことがある。
「僕、今日の舞台で分かった気がするんです。夏帆先輩が言ってた、感情が色づく瞬間を……」
「うん。伝わってきたよ。あきらかに顔つきが違ったもん。高校最後の舞台演劇で朔くんの殻を破った演技が見れて嬉しかった!」
夏帆先輩のまっすぐな言葉に僕は胸を打たれた。いつも僕に向き合ってくれたから、僕も夏帆先輩と向き合うべきだ。
そして、自分の気持ちとも。僕はもう自分の気持ちから逃げたりしない。
「あのモノローグはアドリブだけど、僕の本心ですよ。僕は、貴方だけの主人公になりたいです」
僕は夏帆先輩の瞳をまっすぐに見つめた。この感情を伝えないままでは、僕は絶対後悔する。
『巡逢』を演じきった僕たちなら、きっと何処かでまた巡り逢える。そんな希望を僕は抱いてた。
「今くらい、格好つけさせてくださいよ」
「ずっと……格好良いじゃないですか……」
予想していなかった返答に僕は耳まで熱が行き渡る感覚に襲われた。慣れないことを口にしたせいで、僕の羞恥心はもう限界だ。
「なんで夏帆先輩まで敬語なんすか」
「だ、だって……」
照れ隠しのつもりなのか、夏帆先輩は両手で顔を覆っていた。初めて見る夏帆先輩の様子に僕の胸の奥がくすぐられる。素の夏帆先輩にもう一歩、歩み寄れた気がして嬉しかった。
「恋人役じゃなくて、本当の恋人になってもいいの?」
戸惑いながら聞く夏帆先輩を僕は抱きしめた。
それが僕の答えだった。
ああ、そうか。やっと分かった。
僕の心に芽生えたこの感情の名前が。
「僕は夏帆先輩が好きです」
僕には初めての感覚だった。
この感情を"恋"と言うのなら、僕の心が最も煌めいているのは、今この瞬間かもしれない。
「え、演劇の話だろ!」
稽古終わりの帰り道、同じ演劇部の泰生が僕の平凡な日常を一瞬で滅ぼすような爆弾発言をしたので、慌てて否定した。僕は周囲を見渡し、誰かに聞き耳を立てられていないかを確認する。幸い、夏休み真っ只中ということもあり、高校の正門付近の横断歩道に人影はなく、僕は命拾いした。
目の前の信号が青点灯から点滅し始めたので、自転車のブレーキをかける。
「誰かに誤解されるような言い方するなよ」
「ごめんごめん。でもどんな徳を積んだら夏帆先輩の恋人役に抜擢されるんだよ!」
泰生が嘆くのもやむを得ない。
夏帆先輩は演劇部の部長で、演劇部の心臓ともいえる存在だ。圧倒的な演技力とカリスマ性を持っていて、見る人を魅了する。部内だけでなく、校内でも人気の先輩だ。
僕は夏帆先輩に初めて会った日のことをよく覚えている。1年前、高校に入学して間もない僕は、部活動紹介の際に体育館で披露された演劇部の舞台演劇を見た。全体的に演劇のレベルが高くて、僕は瞬きも惜しいくらい夢中になった。
その中でも一際目を惹く人がいた。それが夏帆先輩だった。自信に満ち溢れた演技と見る人を惹きつける華やかなオーラがあって、目が離せなかった。僕はあっという間に虜になった。僕もあの人と同じ舞台に立ちたいって、そう思ったんだ。後輩想いで、僕たち一人一人に寄り添った指導をしてくれた。そんな夏帆先輩だからこそ、僕とありもしない噂が流れるのは避けたい。
「しかも朔、主役じゃん。嬉しくないのか?」
「今日の稽古だって上手くできなかったし、不安だよ。ミスばっかりで顧問に怒鳴られたし、夏帆先輩にも迷惑かけた」
「まだ稽古始まったばっかりじゃん!主役が弱気になるなよ。俺も頑張るからさ」
泰生のこういうところに僕は救われてきた。見た目はチャラいけど、根は真面目で芯が強い。大雑把だけど楽観的でなんだかんだ憎めない。そんな泰生の期待を裏切りたくない。
今、僕がやるべきことは……。
「おーい、朔!青信号だぞ」
気づけば、すでに泰生が横断歩道を渡っていた。
「ごめん泰生。今日ちょっと寄るところあるから、じゃあな!」
「おい、どこ行くんだよ!朔!」
突拍子のない僕の行動に戸惑う泰生を置き去りにして、僕はペダルを踏んだ。
このままじゃダメだ。今の僕に主役は務まらない。夏帆先輩と並んでも見劣りしないくらいもっと稽古しないと。僕は息を切らしながら、全力で自転車を漕ぎ回した。
***
追い詰められた時、一人になれる場所を探して殻にこもるのが、昔からある僕の悪い癖だ。疲れ果て、真夏の暑さから逃げるように、僕は高架下の陰に身を潜めた。どこからか聞こえる蝉の声も目の前を流れる河川から聴こえるせせらぎも風情があって心地良い。休憩がてら僕はすぐ側の河川敷に腰かけ、ペットボトルの天然水を勢い良く飲んだ。トートバッグの中に入れていた水は生温くなっていて、微々たる不快感を覚えた。気を取り直して、僕はトートバッグから台本を取り出し、配役が記されたページを開く。
『王子ーーー長谷川朔
姫ーーー早瀬夏帆』
僕は、この配役の並びがやけに落差があるように感じた。
9月の文化祭で披露する舞台演劇向けて、僕たち演劇部は夏休み中も稽古に励んでいる。
披露する作品は『巡逢』というフランスが舞台となった恋愛物語だ。フランスの王子と姫が運命的な出逢いを果たし、2人は逢瀬を重ね、やがて恋に落ちる。しかし、悲惨な運命が2人を引き裂き、2人は異国の地で暮らすこととなる。不遇な状況に陥りながらも、いつかまた出逢えると信じて時を経る。そして10年後、2人は奇跡的な再会を果たし、無事に結ばれることとなる。どんなに居場所が離れていても、心さえ繋がっていれば、神は2人を巡り逢わせる。多岐に渡って人を愛することの希望と2人の一途な想いを描いた純愛物語だ。
つい先日、脚本家兼監督の顧問から配役が発表された。
「今回の主役は長谷川朔だ」
顧問がそう言うと、部室内がざわついた。一番衝撃を受けたのは僕だった。僕は演劇部に入部して初めて、主役に抜擢されたのだ。文化祭で披露する演劇は、3年生の先輩方にとっての集大成だ。失敗できないプレッシャーが僕を襲う。僕の心は、主役を演じることの重圧にすでに押しつぶされそうだった。
その日の夜、血眼で台本を読み終え、僕は恋愛感情を理解することに苦しんだ。僕の恋愛経験の乏しさが、作品の世界観への没入を妨げていると痛感した。そもそも僕が王子なんて柄じゃない。本来、文化祭の舞台演劇の主役は、この舞台演劇を最後に引退する3年生が務めるのが主流だ。先輩方の中にもっと適任な人がいたはずじゃないか。僕は心に溜まった不安を押し出すようにため息をついて、今日の稽古でやったシーンのページを開く。
今日、僕がどうしても言えなかった台詞がある。
『僕はきっと、貴方に出逢うために生まれてきたのです』
姫に一目惚れした王子が初めて姫にかけた言葉だ。恋に酔いしれた王子の口説き文句に虫酸が走る。自信家で積極的な王子の人物像は、僕と対照的であると感じた。
「僕は……きっと……きっと……!」
ダメだ。人気のない場所でも、羞恥心が勝って台詞に感情が乗せられない。自身の現状に失望し、僕は俯くことしかできなかった。
「私に逢うために生まれてきたんだよね?」
不意に耳元で鈴の転がるような声がして、僕は顔を上げた。視界の隅に華やかな黄色いスカートが映って、ゆっくりと視線を上に向ける。
一瞬、思考が停止した。
「夏帆先輩!?」
「ふふっ。自主練?えらいね」
夏帆先輩は僕の隣に腰かけ、頬に手を添えてほほえんだ。制服とは違う白い襟シャツに黄色いスカートといった見慣れない姿に僕は動揺を隠せなかった。まっすぐに僕を見つめる瞳に胸の奥が鼓動する。
「な、なんでここにいるんですか」
「それはこっちの台詞だよ。こんなところにずっといたら熱中症になっちゃうよ。朔くん顔赤いよ?」
夏帆先輩は僕の顔を見るなり、困り眉で笑った。鏡を見なくても分かるくらい、顔が火照っている感覚がある。夏の暑さのせいだけじゃない気がするけど……。
「良かったらうちのバイト先においでよ。カフェだから冷房きいてるし、スイーツも沢山あるよ!」
夏帆先輩は両手を胸の前でパンっと鳴らし、名案を閃いたといわんばかりに活気よく提案した。
「……いいんですか?っていうか、夏帆先輩バイトしてるんですね」
「うん。高1の秋くらいからね。もうすぐ休憩終わるからもう戻らないと。ここからすぐ近くだし、案内するよ!」
「お願いします」
僕はもはや、夏帆先輩の提案に乗る以外の選択肢は無かった。それにしても、学業に加えて部活とバイトを両立してるなんてすごいな。泰生には気の毒だが、夏帆先輩の新たな一面を知ることができて、僕は少しばかりの優越感に浸った。
***
入り口の自動ドアが開き、店内に足を一歩踏み入れた瞬間、ひんやりとした空間に身を包まれた。店内は白を貴重としたシンプルな壁紙に温かみのある木製の家具が設置されていて、落ち着いた雰囲気の洋楽がかかっていた。ケーキ屋とカフェが併設されていて、様々なスイーツやお菓子が販売されていた。ショーケースには旬の果物を用いたケーキやタルト、プリンやマカロンっといた色とりどりのスイーツが並べられていた。高貴な雰囲気のお召し物を纏ったマダムたちのお茶会やお姉様方による女子会が開かれていて、僕の場違い感を痛感した。夏帆先輩に誘われなければ、一生訪れることはなかったであろう場所だ。稽古終わりで汗だくなうえ、Tシャツにスウェットパンツというラフな格好がこの雰囲気で悪目立ちしないか心配になった。
「こちらにどうぞ」
夏帆先輩は窓際のカウンター席に案内してくれた。
「えっと……じゃあ、アイスカフェオレください」
「かしこまりました!」
部活の先輩、後輩という関係でありながらも、夏帆先輩は僕を客として接してくれた。
僕はカウンター席の端っこに座り、窓から見える景色に言葉を失った。目の前に広がる河川敷は若草が生い茂っていて、風に吹かれるままに自由になびいている。その動きが連鎖し、美しい波紋のように若草を揺るがす。河川は静止画と見紛うほどに沈静に流れているが、太陽の陽射しを反射し、自然の輝きを帯びていた。自然豊かなこの街の景色をこの席から一望することができた。穴場スポットを見つけたようで、僕は密かに得をした気分になった。ひと通り景色を堪能した後、僕は注文したアイスカフェオレが来るまで再び『巡逢』の台本に目を通していた。
「お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ」
「ありがとうございます。……えっ?」
僕の目の前にはアイスカフェオレと小皿に盛られた2つのマカロンが置かれた。
「私からの気持ちだよ。受け取って」
「ありがとうございます。いただきます」
「ごゆっくりどうぞ」
僕は夏帆先輩のお言葉に甘えることにした。まず、アイスカフェオレで喉の渇きを潤した。コーヒーの苦味とミルクの甘さのバランスが程良く、冷たさがより一層美味しさを際立てていた。僕はマカロンを手に取り、一口齧った。外側の生地はサクサクしているが、中のクリームは濃厚で、食感にバリエーションがある。ただ甘いだけではなく、味に深みのあるスイーツだと思った。あまりマカロンを食べたことがなかったので、一つでも満足感が大きかった。マカロンは高級なスイーツという印象があったので、もう一つはゆっくり味わって食べた。
僕は夏帆先輩が働くこのカフェで小さな幸せなひとときを過ごした。
***
「朔くん!」
帰宅しようと自転車のロックを解除すると、夏帆先輩がちょうど裏口から出てきた。バイト終わりなのだろう。先程まで着ていたカフェの制服姿とは違い、清楚な雰囲気を醸し出す涼しげな水色のワンピースに着がえていた。何気に、夏帆先輩の私服を見るのは初めてかもしれない。夏休み中の演劇部の稽古は私服登校が認められているが、夏帆先輩は「夏の制服着れるのもあと少しだから」と、名残惜しそうに制服を着用していた。
「夏帆先輩、お疲れ様です。マカロン美味しかったです」
「喜んでもらえて良かった!朔くん帰り道こっち?途中まで一緒に帰ろうよ」
「はい」
僕は自転車を手で押しながら夏帆先輩の隣を歩いた。一つ返事で了承したものの、この非日常的な状況に僕は戸惑う。何か僕から話題を振った方がいいのだろうか……。
夏帆先輩は「夏は日が暮れるのが遅いねー」と、独り言とも捉えられるようなことを呟いていた。僕は夏帆先輩の呟きに適度に相槌を打っていた。
「朔くん、一人で抱え込んじゃダメだよ?演劇はみんなで作り上げるものなんだから」
そんな僕を見兼ねたのか、不意に図星を突かれた。どうやら、僕の考えていることは夏帆先輩にはお見通しらしい。正直、僕はこの状況下でも演劇のことで頭がいっぱいだった。
「……すみません。演劇との向き合い方が分からなくなって、迷走してました」
昔から自分の感情を伝えることが苦手だった。他人の顔色を窺って、周りの目を気にしてばかりだった。
そんな自分を変えてくれたのが演劇だった。自分の魂を役に憑依させることで、感情を自由に表現することができたからだ。でも今の僕は、演劇と向き合うことを避けてしまっている。
「なんか……昔の私みたい」
「えっ?」
言葉の意味が理解できず、思わず聞き返した。いつもより低い夏帆先輩の声に違和感を覚える。
「感情が色づく瞬間、知ってる?」
「知りたいです!」
僕は間を空けずに答えた。
紛うことなき僕の本心だった。
「じゃあ私のスパルタ指導に耐えるべし!明日の18時、高架下に集合ね」
「えっ?」
「ってことでよろしくね!また明日!」
「ちょっ、夏帆先輩!?」
夏帆先輩は清々しい表情で駆け出し、颯爽と帰路に続く橋を渡って行ってしまった。どうやら僕に拒否権はないらしい。僕の声は夏帆先輩の耳に届くことなく、夏の暑さに溶けてしまったようだ。夏帆先輩の背中を目で追うことしかできない僕は、やり場のない虚しさを覚えた。
***
「長谷川朔!!声が小さい!!」
「す、すみません!」
部室に顧問の怒鳴り声が響き渡る。演者だけでなく、大道具や衣装を作っている部員たちの視線が自然と僕に集まる。その視線の圧に僕は今にも逃げ出したい気分だった。
「声のボリュームは自信の度量と比例している。お前はもっと稽古量を積むべきだ」
「はい……」
「声が小さい!!」
「はい!!」
結局、今日の稽古も顧問の怒鳴り声で終わりを告げた。稽古中は僕にとって精神修行の時間になりつつある。稽古が終わると毎度の如く、全身から力が抜けていくようにその場に崩れ落ちてしまう。そんな僕の様子を見兼ねて、泰生が励ましに来る。僕は泰生が横にいてもなお立ち直れずにいた。
「まあそう落ち込むなって。そんだけ朔に期待されてんだよ。……で、昨日はどこに行ったんだよ」
「ちょっといろいろあって……」
泰生に知られると色々と面倒なことになると悟り、僕は言葉を濁した。
「LINEしても未読無視だし、気になって気になって、夜しか眠れなかったんだからな!」
「眠れてるのかよ」
「ぐっすりだよ!」
僕と泰生の不毛な会話の中、足早に部室を出ていこうとする夏帆先輩と目が合った。夏帆先輩は去り際に小さく手を振って部室を後にした。
今日もバイトなのかな……。
ズボンのポケットに入れていたスマホが振動し、僕は画面を確認する。
『今日の18時に高架下集合でよろしく!『巡逢』の台本持ってきてね』
と、夏帆先輩からのLINEが一件送られていた。どうやら演劇部のグループラインから僕を追加し、連絡したようだ。にわかに信じがたいけど、昨日の出来事は夢ではなかったみたいだ。昨日夏帆先輩が言っていたスパルタ指導とは、やはり舞台演劇の『巡逢』のことだったのか。僕は腹を括り『了解です』と返信した。
***
僕は夏帆先輩との約束通り、18時にあの河川敷まで自転車で向かっていた。夏は日が長く、この時間帯でもまだ明るさを保っていた。しかし、暑さは昼と比べると少し和らいでいるように感じた。
予定時刻より五分早いが、高架下にはすでに夏帆先輩の姿が見えた。今日は白いTシャツにジーンズというカジュアルな格好をしている。
「夏帆先輩。遅れてすみません」
「朔くん!早いね」
「夏帆先輩こそ」
僕はすぐ側に自転車をとめ、夏帆先輩のもとへ駆け寄った。
「昨日言ってた、感情が色づく瞬間って……」
僕がそう尋ねると、夏帆先輩は瞳を輝かせた。
「私は舞台でその瞬間に出逢って、演劇がもっと好きになったの。上手く言葉にできないけど、感情が輝きを帯びて溢れ出すというか……。例えるなら、恋に落ちた時の感情に似てる気がする」
恋愛経験のない僕には、あまりイメージが掴めなかったけれど、僕もその瞬間に出逢ってみたいと思った。
「朔くんは、誰かを好きになったことある?」
「恋愛的な意味では、ほとんどありません……」
僕は17年の人生を振り返る。僕は不思議と誰かに恋愛感情を抱くことがなかった。たまに仲の良い女友達から告白されることはあったけど、友達だと思っていた相手からの好意を受け入れることができず、断ってしまった。恋愛に発展することで、今までの関係性に戻れなくなることを避けたかった。しかし今思えば、僕は相手の気持ちと向き合うことから逃げていただけなのかもしれない。僕はこのまま、恋を知らないまま大人になっていくのだろうか。
「まあ、何事にも経験は大事だよ!」
夏帆先輩は僕の背中を押すような声で言った。
「じゃあ今日は8ページ目からやろうか」
「はい。夏帆先輩、台本持ってきてないんですか?」
「台詞はもう全部覚えてるよ。あとは身体に叩き込むから」
「……流石です」
さりげなく格の違いを見せつけられ、僕は自分の未熟さを改めて痛感した。
この日から夏帆先輩によるスパルタ指導が始まった。
***
『僕たちの出逢いが運命ならば、きっとまた何処かで巡り逢えるでしょう。その際は、極上の愛の言葉を添えてお迎えに上がります』
愛してやまない姫と引き裂かれる運命に陥った王子が別れ際にかけた言葉。いつかまた出逢う日を夢見る王子の希望が込められているが、どこか哀愁を感じる。『巡逢』にとって非常に重要な台詞であるのに、僕はこのもどかしさを表現することに苦戦していた。
「言葉にはね、一つ一つ違った輪郭を持ってるの。そこに声色や間の取り方を加えて、表現の幅を広げるんだよ」
「なるほど……!」
夏帆先輩のアドバイスを忘れないように、僕は台本に赤ペンで『声色』『間の取り方』と書き足し、額の汗を拭った。
あれから毎日、18時から2時間ほどこの河川敷で、夏帆先輩と演劇の稽古をするのが僕の夏休みの日課となっていた。多忙な日々を送っている夏帆先輩の2時間を僕に費やしてくれているのだから、僕は不安を感じる暇もないくらい、演劇と向き合う日々を送っていた。
「朔くんの演技は、まだ内に秘めてる感じがする。でも、心の内にある確かな情熱を感じるんだ」
「殻にこもってしまう悪い癖があるのは、自覚しています……」
もともと僕が持っている気質や性格が、役への感情移入を妨げているような気がする。上手くやりたいという気持ちは人一倍持っているのに。
「顧問はそれを見抜いてるんじゃないかな。きっと、朔くんの殻を破った演技を望んでるんだよ」
いつか、この殻を破る時が来るのだろうか。
僕は自分自身に問いかける。
殻を破るためにも、一つ一つを着実にこなしていくしかない。結果は後からついてくるものだと信じている。
「大丈夫?休憩する?」
「いや、まだやれます」
「ふふっ。そう言うと思ったよ」
夏帆先輩は「そうこなくっちゃ」と言わんばかりの強気な笑みを浮かべていた。まるで、僕のスイッチの入れ方を熟知しているようだった。
「朔くんのことを知れば知るほど、輝きが見えてくる。伸びしろがある人だと、教えがいがあるよ」
夏帆先輩のその言葉は、僕に希望を与えてくれた。
***
来る日も来る日も、僕らは稽古を重ねた。
「だいぶ台詞に感情が乗るようになってきたね」
「本当ですか!?ありがとうございます!」
「うん!あとは頭だけじゃなくて、身体に覚えさせると、もっと良くなると思うよ」
「はい!」
あまり自覚はないけど、客観的に見て成長を感じているのなら良かった。それに、夏帆先輩から少しだけ認められた気がして嬉しかった。
「じゃあちょっと休憩しよっか。演劇は結構体力使うし、水分補給大事だよ」
そう言うと夏帆先輩は高架下の陰に腰かけ、天然水のペットボトルを飲んだ。僕は顔から首筋を伝う汗をタオルで拭き、天然水のペットボトルを飲んだ。渇いた喉に天然水が染み渡り、微かな幸福感を覚えた。稽古終わりに飲む水が一番美味いことを僕は改めて実感した。
僕も高架下の陰に腰かけ、僅かに髪を揺らす夏風に涼んでいた。
「夏帆先輩が演劇をする上で、心がけてることは何ですか?」
僕はふと、気になっていたことを聞いてみた。夏帆先輩はどんな想いを抱えて演劇と向き合っているのか、ずっと知りたかった。
「うーん……。独りよがりの演技をしないことかな」
夏帆先輩は珍しく少し曇った表情をしていたので、なんだか申し訳なくなった。
「実は……演劇部を辞めようと思った時期もあったんだ。顧問に独りよがりの演技をするなって言われて、どうすればいいか分からなくなったの」
僕が演劇との向き合い方が分からなくなっていた時に「昔の私みたい」と言っていたのは、そういう意味だったのか。夏帆先輩も僕と同じような悩みを抱えていたことに驚いた。
「期待されてたから、もっと上手くなりたくてずっと一人で練習してた。でも、演劇はみんなで作り上げるものだから、一人だけ上手くても意味なかったの。だからこうして、同じ志を持つ人と一緒に稽古できることが幸せなんだ」
" 同じ志を持つ人 "と言った時に夏帆先輩と目が合った。この稽古の時間を幸せだと思ってくれているのは正直、嬉しい。でも素直に喜べなかった。もしかしたら、部員の僕たちが夏帆先輩に抱いていた期待や信頼が重荷に感じていたのではないだろうか。そんなことを考えていたら、僕は合槌を打つタイミングを逃してしまい、しばらく聞き役に徹することにした。
「高1の文化祭で披露した舞台演劇が終わってから部活に行かなくなって、あのカフェでバイト始めたんだ。そしたら店長に『貴方は人を惹きつける華やかなオーラがあるね』って褒められたの!素の私を認められた気がして、すごく嬉しかったんだ」
夏帆先輩はバイトの話になると、だんだんと笑顔になっていった。
「演劇から離れたくてバイトを始めたのに、気づいたら演劇のことばっかり考えちゃうの。やっぱり私、演劇が好きなんだなって改めて分かったんだ。だからまた演劇部で頑張るって決めたの。復帰して初の舞台演劇で" 感情が色づく瞬間 "に出逢ったんだ。その瞬間、私が今まで演劇と向き合ってきた時間は無駄じゃなかったんだって思ったの」
「無駄じゃないですよ!僕は夏帆先輩がいたから、演劇部に入ろうと思ったんです。貴方が居てくれたから、僕は演劇の楽しさを知ることができました」
しばらく聞き役に徹していた僕が食い気味で話し始めたので、夏帆先輩は目を丸くして、驚いた様子だった。突発的な行動や言動をしてしまうのも僕の悪い癖かもしれない。でも全部、僕の本心だった。
「ありがとう。朔くんにそう言ってもらえて良かった!もっと早く朔くんに会えてたら良かったな。でも、私の人生でそんな風に思える人に出会えて良かった」
夏帆先輩は満開の向日葵のような笑顔を僕に向けた。僕の言葉は想像以上に夏帆先輩の心に響いたようだった。僕は照れくささを隠すために別の話題を振ることにした。
「夏帆先輩って、やっぱり演劇の道に進むんですか?」
「うん。東京で本格的に演劇を学びたいな」
夢を語る夏帆先輩の瞳は希望に満ちていた。
「そうですか……。頑張ってください。応援してます」
「ありがとう。部活引退してもたまに顔出すよ」
「いつでも待ってます」
夏帆先輩と同じ舞台に立てるのも今回で最後か……。分かっていたはずだけど、限られた日々に僕は胸が締めつけられたような痛みを覚えた。いつまでもこうやって、当たり前みたいに夏帆先輩と過ごせたら良かったのに。
***
「ごめん朔くん!遅れた!」
「大丈夫ですよ。バイトお疲れ様です」
何らかの理由でバイトが長引いたのか、夏帆先輩は約束の時間より30分ほど遅れて来た。僕はその間、顧問や夏帆先輩に指摘された箇所を見直し、台本に赤ペンで書き込んだり、付箋を貼ったりしていた。僕の台本は、どのページを開いてもびっしりと書き込みが施されている。台本が稽古量を表しているようで、僕にとってのモチベーションだった。
「じゃあ今日はダンスの復習からしよっか。動きを客観的に見るのも大事だから、後で見返せるように動画を撮っておこう」
「了解です。画角調節するんでちょっと待ってください」
僕はあらかじめ用意していた三脚にスマホを取りつけ、画面の中の夏帆先輩の全身が映るように画角を調節する。
「良い感じにできました」
「ありがとう。じゃあ私が音楽流すね」
「お願いします」
夏帆先輩の方のスマホで音楽を流し、三脚の側に置いた。
僕は左手で夏帆先輩の右手を取り、背中に右手を回して抱き寄せる。これが社交ダンスの基本姿勢だ。ダンスの稽古は物理的な距離の近さに毎度、動揺する。
「ちゃんと支えててね」
「は、はい」
3拍子の音楽に合わせて、円を描くように回転する。足並みを揃え、男女の体格差を活かした振り付けで美しさを表現する。
「朔くん、ちゃんと瞳見て」
僕は一瞬だけ、夏帆先輩と目を合わせた。夏帆先輩は少し悪戯な笑みを浮かべていた。僕はそれ以上目を合わせられなかった。平常心を保つのに精一杯で、目を合わせられない僕をからかっているのだろうか。夏帆先輩の笑顔も甘い言葉も全部演技って分かってるのに、どうしてこんなに胸が高鳴るんだろう。せめて演劇の時だけでも夏帆先輩の視線を独り占めできたらいいのに。
「ふふっ。朔くんの動きなんかぎこちないね」
「夏帆先輩だって、途中でこけそうになってるじゃないですか」
「バレたか」
撮影した動画を見返しながら、夏帆先輩と小競り合いを繰り広げていた。一つの画面を二人で見るために隣並びで座っているため、自然と夏帆先輩との距離が近くなる。夏帆先輩の髪が僕の肩に触れていて、どうにも落ち着かない。まあ、こんなに意識しているのも僕だけなんだろうけど。
ヒューーー……、ドーーーン。
「あ、朔くん見て!花火!」
「おー……。綺麗ですね」
このあたりで夏祭りが開催されているのだろう。演劇のことしか頭になかった僕は、夏祭りの存在など忘れていた。まさか、夏帆先輩と花火を見ることができるなんて思わなかった。夜空に打ち上がる花火も良いけれど、目の前の河川の水面に反射して映る花火は朧げで、どこか儚くて、美しかった。
夏帆先輩は花火に夢中にな様子で、分かりやすくテンションが上がっていた。そんな夏帆先輩の姿につられて、僕も心が舞い上がる。
普段見せない夏帆先輩のあどけない姿に僕の胸が密かにときめく。
こんな時間がずっと続けばいいのに。
夜空に打ち上がってーーー咲く。
また打ち上がってーーー咲く。
その一瞬の煌めきを夏帆先輩の隣で見届ける。
上手く言葉にできないけど、僕にとって永遠に感じた瞬間だった。
***
「おー!朔、かっけぇ!まじで王子じゃん」
「ありがとう」
ついに本番当日。舞台衣装に着がえ、髪のセットまで終えた僕は、舞台の中心で演劇のイメージトレーニングをしていた。泰生の無邪気なリアクションに自然と僕の口角が上がる。
途端に舞台袖から男女問わずの黄色い声が上がった。声のする方へ僕と泰生が目を向けると、青いドレス姿に身を纏う夏帆先輩の姿があった。いつもおろしている髪は後ろで一つにまとめていて、より清楚な雰囲気を醸し出していた。華奢な体型にふんわりとしたドレスがよく似合っていて、僕は夏帆先輩に見惚れてしばらく目が離せなかった。
「夏帆先輩……美しい……」
泰生は心臓を射抜かれたように悶えていて、僕と同様にすでに心を奪われている様子だった。泰生は姫の城に仕える執事役なので、黒のタキシードを身に纏っている。いつも毛先を遊ばせている髪型の泰生だが、今日は硬派な印象を与える執事ヘアスタイルだった。
「泰生もかっこいいよ。イケてる」
「えー!やっぱり!?さすがに今日の俺のビジュアル満点だよね」
「お、おう」
泰生の切り替えの早さに若干、動揺した。見た目は変わっていても、中身は変わらない泰生の姿が可笑しかった。僕も泰生のマインドを見習いたいものだ。
「今回の舞台で名脇役になってやるよ。朔の主役も喰っちゃうかも」
「喰われねぇよ」
泰生は「キャー!朔かっこいいー!」と、わざとらしく無駄に甲高い声で言いながら舞台脇にはけていった。相変わらずの調子の奴だけど、泰生のおかげで緊張が和らいだ気がする。
「第50回、水瀬高校演劇部による舞台演劇『巡逢』の開演まで今しばらくお待ちください」
体育館及び校舎全体にアナウンスが流れる。
僕は一旦舞台脇にはけ、夏帆先輩のもとまで駆け寄った。
「いよいよですね」
「最高の舞台にしようよ」
「はい!」
僕と夏帆先輩は舞台の成功を誓い合った。
開演のブザーがなる。
観客の声が一瞬のうちに静まり、舞台に緊張感が走る。その緊張感から来る震えさえも、僕の心を突き動かすエネルギーに変える。少しずつ、僕の魂が役に憑依していく感覚に陥った。
幕が開け、僕に眩しいスポットライトが当たる。数えきれないほどの観客の視線を浴びる。もうすでに、僕の魂は完全に役に憑依していた。
***
演劇もついに終盤。
10年越しにフランスの時計塔の前で偶然、姫と再会するシーンだ。
恋焦がれた姫と目が合い、すれ違う。心の中に仕舞っていた感情がざわめき始める。僕が振り返り、姫の名前を呼ぼうとしたその瞬間、何の弾みかは分からないが、ステージ上に設置されていた3メートルに及ぶ時計塔が徐々に傾き始め、今にも姫の真上に転倒しそうだった。
「危ない!!」
僕は瞬時に姫を抱き寄せた。咄嗟の行動に体勢を崩し、僕らはステージ上に勢いよく倒れこんでしまったが、僕は両腕で姫の頭を覆うようにして守った。姫の背後で時計塔が転倒し、会場に鈍い衝撃音が響き渡る。なんとか、間一髪のところで姫を窮地から救うことができたようだ。だが、その異様な光景に観客がざわつき始める。
「姫、お怪我はありませんか?」
僕は即座に立ち上がり、姫に手を差し伸ばしたが、自分の声に違和感を覚えた。僕の声は観客のざわめきに掻き消され、姫に届いていない様子だった。
倒れた衝撃により、マイクが故障してしまったのだろうか。
どうしよう……。
終盤とはいえ、まだ僕の台詞は残っている。
想定外のハプニングにより、絶望的な状況に追い込まれた僕は、焦燥に駆られた。
憑依していた魂が役からどんどんすり抜け、舞台では封印していたはずの僕の本性が暴き出す。
一体、僕はどうすればいいんだ……。
いっそのこと、このまま夏帆先輩と一緒にこの場から逃げてしまいたい。
そんな考えが脳裏によぎった瞬間、差し伸べていた僕の手に温もりを感じた。僕のそばに座っていた夏帆先輩は僕の手をそっと握って、笑った。
そうだ、この人だ。
演劇の楽しさを教えてくれたのも演劇と向き合う姿勢を教えてくれたのもこの人なんだ。
僕にとって永遠の憧れで、かけがえのない人。
こうして、憧れの人と一緒の舞台に立つことができて幸せなんだ。
だからもう逃げたくない。
最高の舞台にするって約束したから。
僕は覚悟を決めた。
ハプニングさえ粋な演出に変えてやる。
「僕はこの瞬間をずっと、待ち侘びていました。」
僕の芯のある声が観客のざわめきを沈静化させる。
「貴方を想う気持ちは、永遠に変わりません」
静寂に包まれた会場に僕の声が響き渡る。
マイクが機能しないなら、声を張るしかない。
「僕は貴方が好きです」
それは僕の本心であり、僕なりの極上の愛の言葉だった。
王子じゃない、ありのままの僕の言葉。
姫じゃない、ありのままの君に贈るモノローグ。
観客にも僕の声が届いたのか、客席からは鼓膜を破るほどの歓声と拍手が沸き上がった。
フィナーレの音楽が流れ始める。
「僕と踊りませんか?」
僕はその場に跪き、再び手を差し伸べた。この台詞と動作は台本にはない僕のアドリブであったが、夏帆先輩はすぐに対応し、僕の手を取った。
「はい。喜んで」
その様子を見た観客たちは再び歓声を上げた。
10年の時を経て再会し、喜びの舞のワルツを踊る。僕は夏帆先輩と手を繋ぎ、支えるように背中に手を回した。流れる音楽に身を任せ、夏帆先輩と軽快に足並みを揃える。踊りは完全に身体に染みついていた。
「夏帆先輩、僕の瞳見て」
マイクが故障して、観客に聞こえないのをいいことに僕は夏帆先輩に悪戯を仕掛けた。珍しく動揺している夏帆先輩に僕は嬉しくなった。夏帆先輩は恥じらうように下唇を噛み、「もう……!」と言わんばかりの表情だった。
こんなに大勢の人に見られているのに、僕たちにしか分からないやり取りをしているのが可笑しくて、僕と夏帆先輩はどちらからともなく笑い合った。演技では表現できない自然な笑顔でいられた気がする。
ワルツを踊り終え、観客に目を向けたその瞬間、僕の視界は眩しく彩られた。
観客から贈られる拍手や笑顔は輝きを帯びていて、胸が熱くなった。今なら、なんでもできそうな気がした。
これが" 感情が色づく瞬間 "というのだろうか。
その一瞬の煌めきはきっと色褪せることなく、僕の未来を照らす道導となるだろう。
カーテンコールを終えて、『巡逢』の幕を閉じた。
最後に僕が舞台脇にはけると、顧問を先頭に部員全員が僕を迎えていた。
「よくやった……!」
顧問の声は少し震えていて、涙ぐんでいるように見えた。顧問からの初めてのお褒めの言葉に僕は目頭が熱くなった。そして僕は初めて、顧問の口角が上がっているところを見た。
***
演劇部での打ち上げが終わった帰り、思ったよりも遅い時間になってしまったため、僕は演劇部代表として夏帆先輩を家まで送ることになった。
3年生の先輩方や泰生から「今日は全部持ってけ、主役!」と主役イジリをされた。正直、悪い気はしなかった。
「それにしても、朔くんが本番でアドリブをするなんて驚いたよ」
「すみません。ちょっと調子に乗っちゃって……。でも、夏帆先輩が僕のアドリブに合わせてフォローしてくれたから、なんとか最後までやり遂げることができました。本当にありがとうございました」
「こちらこそ、ありがとう。良い意味で忘れられない演劇になったよ」
夏帆先輩とこんなふうに話せるのもこれが最後になるんだろうな……。僕は限られた時間を名残惜しく思い、一歩一歩を踏みしめるように歩いた。そのたびに僕は抱えきれないほどの淋しさに襲われる。
「じゃあ……私の家ここだから。わざわざ送ってくれてありがとう」
僕の想いも虚しく、あっという間に夏帆先輩の家に到着した。まだ、夏帆先輩に伝えてないことがある。
「僕、今日の舞台で分かった気がするんです。夏帆先輩が言ってた、感情が色づく瞬間を……」
「うん。伝わってきたよ。あきらかに顔つきが違ったもん。高校最後の舞台演劇で朔くんの殻を破った演技が見れて嬉しかった!」
夏帆先輩のまっすぐな言葉に僕は胸を打たれた。いつも僕に向き合ってくれたから、僕も夏帆先輩と向き合うべきだ。
そして、自分の気持ちとも。僕はもう自分の気持ちから逃げたりしない。
「あのモノローグはアドリブだけど、僕の本心ですよ。僕は、貴方だけの主人公になりたいです」
僕は夏帆先輩の瞳をまっすぐに見つめた。この感情を伝えないままでは、僕は絶対後悔する。
『巡逢』を演じきった僕たちなら、きっと何処かでまた巡り逢える。そんな希望を僕は抱いてた。
「今くらい、格好つけさせてくださいよ」
「ずっと……格好良いじゃないですか……」
予想していなかった返答に僕は耳まで熱が行き渡る感覚に襲われた。慣れないことを口にしたせいで、僕の羞恥心はもう限界だ。
「なんで夏帆先輩まで敬語なんすか」
「だ、だって……」
照れ隠しのつもりなのか、夏帆先輩は両手で顔を覆っていた。初めて見る夏帆先輩の様子に僕の胸の奥がくすぐられる。素の夏帆先輩にもう一歩、歩み寄れた気がして嬉しかった。
「恋人役じゃなくて、本当の恋人になってもいいの?」
戸惑いながら聞く夏帆先輩を僕は抱きしめた。
それが僕の答えだった。
ああ、そうか。やっと分かった。
僕の心に芽生えたこの感情の名前が。
「僕は夏帆先輩が好きです」
僕には初めての感覚だった。
この感情を"恋"と言うのなら、僕の心が最も煌めいているのは、今この瞬間かもしれない。