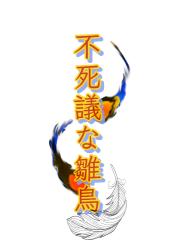* * *
4月。遅咲きの桜を眺めながらキャンパスを歩く。同じ方向に向かって歩く新入生に混じり、僕も同じ歩幅で歩いていく。
僕は無事に大学に入学できた。両親が行方不明ではあるが、入学はもう決まっていたことだ。手続き関連に多少の手間はあったものの大学側は便宜を図ってくれた。不思議なもので、世の中は独りになっても諸々の制度でなんとか生きていけるらしい。国というのはよく出来ているんだなと、そう思った。
「……」
はらりと落ちる桜を見ながらあの夜のことを思い返す。
あれから10日ほどが経った。ある程度の社会的な制度に守られた今、あの時ほどの強烈な孤独感はなくなったと言える。むしろもっと早く行政のお世話になっていればとも思うくらいだ。
そうは言ってもこうやって前を向けたのも彼女の存在があったからこそ。出会えなかったらきっとまだ夜の街を彷徨っていたかもしれない。彼女には感謝しかないが、1つ心残りがあった。
「…感謝し忘れちゃったんだよな」
誰に言うでもなく呟く。春風に乗って言葉が消えた。あの日は気が動転していたのか、不思議なことばかりだったからなのか、彼女にきちんとありがとうと伝えられていなかった。
だからこそもう一度会えたらなと思う。
──
─
そんなことを考えながら歩いていたら食堂に着いた。お昼時の食堂は人でごったがえしている。談笑に花を咲かせる同じ大学生たちを横目に食券の券売機に並んだ。
元々そこまで社交的な性格ではないので、未だに友人と呼べる人はできなかった。手続き諸々もあったせいか、スタートダッシュは失敗気味だ。少し話す程度の人はいるが、これが所謂よっ友と呼ばれる関係性だろうか。少しずつ都会に慣れ、人にも慣れていきたい。
「……」
彼女、マリーさんは今どうしているだろうか。年齢は20歳だと言っていた。1つ上だが学生ではないと思う。お店のオーナーをやっているくらいだし。そういえばお店の場所すら聞けていなかったな…。
あれから眠れない日々は相変わらず続いているものの、同じ夜を過ごしている彼女を思うと、気が落ちることはなかった。似た境遇の人がいるというだけで心が楽になったような気がする。
「──なぁ、知ってるか?」
「ん?」
ボーッとそんなことを考えていると、僕の前に並ぶ男性2人組の会話が聞こえてきた。
「新宿辺りにあるお店の噂なんだが」
「ほぅ」
「なんでもな、願いが叶う喫茶店があるらしい」
「なんだそれ」
「あくまで噂なんだけど、例えば大切な失せ物が見つかったり、昔好きだった人に会えたり、そのお店に訪れる前に考えていた願い事が叶うっていうお店なんだよ」
悪いと思いながらも聞き耳を立てる。願いが叶うお店…?ふとあの日起こった出来事を思い出した。
あの日警官に追われていた時、願うことなら誰かに自分を肯定して欲しいと願った。そう思った瞬間、僕の名をピタリと当てたマリーさんと出会い、独りぼっちじゃないと思えた。願いと呼べるかわからない感情ではあったが、たしかにあの瞬間僕は自分が肯定された気がしたんだ。
「夜遅くまでやっているらしい。美味しいデザートと飲み物が飲めるお店なんだってさ」
「それが本当なら随分怪しいお店だな。…というかなんで新宿の夜の店を知ってるんだよ」
「あー…まぁバイト先でな、聞いたって感じだ」
夜遅くまでやってる喫茶店…。新宿付近では夜やってるお店自体は珍しくない。あの後調べたが、パフェが食べられる店もあるくらいだ。
だけど今聞いた話がどうにも全く関係のないことだとは思えなかった。願うが叶う、美味しいデザートの喫茶店…。
「歯切れ悪いな。叶えたい願いでもあるの?」
「…そうだな、妹の──」
「あ、あの……」
「え?」
気がつけば僕は2人に話しかけていた。いてもたってもいられなくなり、口を衝いて出たような感じ。自分でも驚いた。
「あっ…その話、詳しく聞かせてくれない?」
驚きとともに、胸が高鳴っているのを感じた。
──
─
「…お兄さん、お遊びどうですか?」
キャッチの人が街ゆく人に声をかける。この光景を見るのもなんだか久しぶりな気がした。
その日の夜、僕はまた新宿に来ていた。どうせ家にいても眠れないので、少しでも可能性のある行動をした方がいい。そう思ったからだ。
「……」
煌びやかな夜の街を独り歩く。若干ストーカーっぽい気がしなくもないなと、今更ながらに思ってきた。そんな思考を歩きながらかき消す。もう一度会いたいのは、あの日の感謝をきちんと伝えるためだ…。それにお店をやっているならなにも変なことはないはず。僕は頭を振りながら自分に言い聞かせた。
「…ここは」
歌舞伎町を過ぎたあたりの裏路地に着く。僕が初めてマリーさんと会った場所だ。何か手掛かりがあるかもと思い訪れてみたが、当然なにもない。近くに喫茶店がある様子もなかった。
僕はまたゆるりと歩き始める。
結局、券売機で話しかけた2人の学生からは有力な情報を得られていない。
なんでも、噂では叶えたい願いをぼーっとしながら歩いていたら辿り着いたというような感じらしい。明確な場所はないに等しかった。その願いというのもかなり強い想いを抱えていた人が多いそうだ。
叶えたい願いなど、僕にはいくつもある。こんな邪推が見つからない要因なのかもしれない。
「……あっ」
そうこうしてるうちに、夜がいっそう更けていっているのに気がついた。時間を見ると深夜を回っている。
ふと顔を上げれば、見た事のある小道に足を踏み入れていた。あの日彼女と会話をした四季の路という遊歩道。それなりの距離を歩いていたようだ。
「……」
しばらく進むとあの日僕らが会話した場所に着く。無意識のうちに彼女と会えた軌跡を辿っている自分がいた。
「…馬鹿馬鹿しくなってきた」
ふと思ったのだが、願いを叶える深夜の喫茶店とマリーさんとの間に関係があるというのも根拠がない。それも僕がなんとなく思っただけだ。彼女がそこにいる保証などどこにもない。
願いが叶うというのも信憑性に欠ける。震災で天涯孤独になるという起こりえない経験をしている僕が言うのもなんだが、現実味が薄すぎることだ。
「もう一回だけ…ちゃんと会えたらいいな」
僕はただ感謝が伝えたい、それだけだ。宛もなく歩くより聞き込み回った方が早いかもしれない。彼女はいい意味で目立つ人だし、人の多い新宿なら知っている人もいるだろう。歌舞伎町の方で聞き込みを…そう思い辺りを見回す。
「…あれ?」
しんとした夜の空気が身を包む。遊歩道には人っ子一人いなかった。この前話していた時はこんなに静かではなかった。深夜だがそれなりの人数が歩いていたはず。それが今日は誰もいなかった。
「……」
来た道を戻る。新宿にいるのはたしかなのだが、人気をほとんど感じなかった。眩い灯りは見えるが、歩く道は仄暗い。この道、こんなに暗かったっけ?
傍らに生える木の模様が笑っているように見えた。
「……」
ひたすらに歩いて戻る。しかし、歩けども歩けども、大通りに出ることができない。なんだか不自然なほど長く歩いている気がする。
孤独感に苛まれ、少し不安になってきた。
「…あ、あれ?」
まさか迷子?田舎者なので新宿は訪れ慣れていない場所だが、まさか一本道で迷子になるなんて…。焦って小走りになる。
「あっ、よかったぁ…」
しばらく歩いた数m先、遊歩道の終わりが見えてきた。ホッと一安心からか声が漏れる。僕は小道から逃げるように抜ける。すると──
「……ここは?」
大通りかと思って出た先は雑居ビルが立ち並ぶ路地裏の一本道だった。こんなところから小路に入っただろうか…?
ビルに遮られた月明かりを元手にキョロキョロと辺りを見回す。まさに建物の裏側が並ぶだけで目立つものは何もない。まだ迷ってるのかもと歩きながら思った矢先、ビルとビルの間に小さな建物を見つけた。
「……」
雑居ビルの間に挟まるようにできた小さな建物。
自動車1台がギリギリ入れる程度のビルとの間に、挟まるように存在していた。よくわからないパイプや換気扇しか見えないビルの裏が密集した道に、あまりそぐわない外観をしている。まるで1本の木のような建物。2階建て程度だろうか。御伽噺に出てくる木の小屋のようにも見える。
中央には扉があり、A4ノートサイズほどのこれまた木でできた看板が吊るされている。
「マ…ル…チェン?」
その木の看板には『Märchen』と書かれてあった。読めない…英語じゃないけど──
「……あっ。これ、ドイツ語?」
パッとスマホで調べる。メルヘンと読むようだ。
それよりもドイツ語という部分にピンとくる。もしかして──
「……」
期待を胸に僕は扉に手をかけた。
──
─
扉を開けるとそこは喫茶店になっていた。中に入った1番の感想は意外と広い、だった。
入口のすぐ近くにL字型のバーカウンターがあり、カウンターの後ろの棚にはコーヒーメーカーやティーポット、洋風なグラスやカップが立ち並ぶ。カウンターの向かいには2人用のテーブルと椅子のセットが、奥に向かうように2つ並んでいた。
「……」
入った瞬間から流れるフワッとした甘い香り。室内なのに空気は澄んでいて、まるで森の中にでもいるかのようだった。緑と茶色を基調とした内装の作りをしているせいもあるだろうか。店内にBGMはかかっていないが、小鳥の囀りすら聞こえてきそうなほど穏やかな空間。
小物は洒落たものが多い。カウンターの上には林檎の形をした陶器の角砂糖入れに、キラキラした雪の結晶が舞うスノードーム。
息を飲むほどオシャレなお店だが、店員の姿は見えない。
「……」
そう思い改めて見回すと、カウンターの奥に裏手に繋がっているであろう小さな扉があった。
「…あの──」
少し声を張り上げて扉に声をかけた瞬間、ガチャリと扉が開いた。
「ごめんなさい、お菓子焼いてて!いらっしゃいま──」
白雪のような白い肌、夜空のような真っ黒な艶髪。甘い香りとともに、バタバタと扉から出てきたのは、僕が探していた人だった。
「…ど、どうも」
「驚いたぁ…!魁人くん、こんばんは」
「マリーさん、こんばんは。覚えててくれたんですか?」
「当たり前じゃない。忘れるわけないわ。ささ、とにかく座って座って?」
ふふふっとあの日と同じ笑顔で笑いながら、カウンターの席へ誘う。
意外というほどでもないが、こうやってまた出会えたことに多少の驚きはあった。まさか本当に出会えるとは思っていなかったからだ。純粋な嬉しいという気持ちが芽生える。そしてさらに、覚えてくれていたこともその嬉しさに拍車をかけた。
「…でもよくここがわかったね?」
「あ、実は──」
カウンターの椅子に座るのとほぼ同時に、そう尋ねてくる彼女に言葉を返そうとして言い淀む。
「……」
「実は?」
実はマリーさんにもう一度会いたくて探していました、なんて言えるわけなかった。
いや、もちろん会えたこと自体は嬉しいのだが、たった一度会っただけの関係であるにも関わらず、お店まで突き止めようとしていたという事実はやはり少々よろしくない。ストーカーっぽいという考えは消したはずだが言葉にするとそれ以外の何者でもなかった。
「えーっと…」
「ん?」
そんなこととは露知らず、彼女は小首を傾げる。
「あー…願い事…そう、願い事です」
「願い事?」
「えぇ、願い事の叶う喫茶店というのが噂になっていてそれを探していて」
「あー!」
誤魔化そうと思って口に出た言葉で回答する。彼女と関係があるかもと思って探していたが、嘘はついていない。きっかけは間違いなくそれだったわけだし…とにかくストーカーで通報されるのを避けるのを優先した。
「あの噂ね、はいはい」
「知ってるのですか?」
「えぇ、もちろん。たぶんうちのお店のことだしね」
「あ、ここのお店がそう呼ばれてるのですか」
「つい数週間前くらいからかなぁ…そう呼ばれるようになったわね」
彼女は手近にあったグラスを拭きながらそう答える。僕の妄想に近い推測は正しかったようで、マリーさんのお店が噂の喫茶店だった。
「美味しいデザートと飲み物のお店だとは聞いていて」
「それでもしかしたらと思って探してくれたの?」
「はい…あっ。いや…違います。ストーカーとかでは…」
「ふふふっ、墓穴掘ってるよ」
「あっ、いや…」
心でも読まれたかのように誘導されて呆気なく喋ってしまった。前話した時もそうだが、彼女といると心の内が自然と出てしまう。
「安心して?それだけじゃストーカーだなんて思わないわ」
「本当ですか?」
「だってあれだけ話をしたんだもの。また会えて嬉しいくらいよ」
「よ、よかった…」
安堵し、一息つく。店内を包む甘い香りが心地いい。
「そういえばあれから眠れているかしら?」
「いえ…それは変わらずです。でも前より気持ちは楽になりました」
「気持ちが楽に?」
「はい。マリーさんも眠れていない日を過してるのかなと思うと、独りじゃなくなったような気がして」
「そう、それは素直に嬉しいわ。悪夢はまだ?」
「それは…はい」
不眠症は治っていないし、悪夢も見る。嫌な汗をかいて起きるのも変わらないが、それは仕方のないことだった。
「そう…やっぱりつらいよね。願い事の叶う喫茶店を探してたって聞いたけど、願い事はそれ?」
「…どうでしょう。もちろん眠れるようにもなりたいですが、それよりも独りじゃないと思いたいんだと思います。今あるつらいことは全部、孤独感から起きてることな気がするので」
眠れるようになりたいとか、母が最期に何を言おうとしていたのかとか、そういうのが気になってしまうのは全て今を独りで生きているからという孤独感だ。強烈ではなくなったものの、心の奥底に住み着いて離れない気がしている。
「独りじゃない…かぁ」
「…すみません、また自分のことを話してしまって」
「いいのよ、聞いたのは私だし。でもそうねぇ…」
彼女は優しくそう答え、その後なにかを考えるような仕草を見せた。
「魁人くん、東京に来てまだ日が浅いでしょ?」
「はい」
「生活とかどうしてるの?金銭面とか」
「あ、それはなんとかやりくりしてます。行方不明の遺産関係とか特殊な申請はありましたが…」
「そうなんだ、ひとまずよかったよ」
「とはいえ、必要最低限に留めておこうかなと。取り急ぎバイトはしないとなとは思ってます」
まだ家族が死亡したと決まったわけではし、見つかるかもしれないと考えてのことだ。そうなるとかなり生活は厳しい。
「…んー、そしたらさ。うちでバイトしない?」
「え?」
彼女がそう持ちかけてきた。
「バイト先決まってるの?」
「いえ、それはまだ…」
「それなら丁度いいかなって。夜の人手が欲しいかなーとは思ってたの」
彼女が手をパンッと手を合わせて笑みを向ける。
「渡りに船ではありますが…いいのですか?」
「もちろんよ?」
「でも、なんだか悪いです」
気が引けるわけではないが、少し甘えすぎな気もした。こうして会えただけでも嬉しいのに、生活面まで気にかけてくれるとは…。貰ってばかりで何も返せていない。
「まぁまぁ。それなら面接しましょ?それから雇うか考えるわ」
しかしそんな僕の気負いなどお構いなしに話を進めてきた。意外と強引なところもあるんだなと思った。
「はい、じゃあよろしくお願いします」
「あ…よろしくお願いします」
そう思いつつも、形式ばって礼をされてしまったのでこちらも礼で返す。
「ではお名前は──ってこれは知ってるからいっか。出身も…知ってるしいいわね」
「…そうですね」
考えながら話しているが、面接で聞かれるような内容など彼女は知りえている。…これ、意味あるのだろうか。
「んー、じゃあ学歴?どこの高校を卒業しましたか?」
「…えーっと、実は高校卒業したかと言われると怪しいです」
「え?でも大学生でしょ?」
「はい、それはそうですが…。卒業証明はあるんですけど、卒業式に出られてないので」
「あっ…地元に帰れてないから?」
「そうです。高校もあの惨事の中で卒業式やったのかも微妙ですけど…」
昔のことを話すと触れなくてはならないことだ。災害の話というのはどこにでもつきまとうものなのだと実感した。
「ごめん、そんなつもりじゃ…」
「いえ、僕も不幸話をするつもりではなかったので…すみません」
「あぁ、謝らないで!」
「いえ…」
「…ごめん」
互いにそんなつもりなどなく、謝り合う。少し空気が重たくなる。店内を満たす甘い香りもなんだか悲しげになった気がした。
「…い、今の質問はやっぱなしで!そしたら…うーんとね……」
あたふたした彼女は、ブツブツとああでもないこうでもないと質問を選び始める。そんな姿を見て、申し訳ない気持ちに拍車をかけた。
「…上手くいかないものね。本当はね、ただ魁人くんに独りじゃないと思って欲しいだけなの」
「え?」
「なんとかしてあげたいなって思ったの。私も夜が怖いから」
「依然そうお話されてましたよね…」
「うん。私もね、悪い夢を見たことがあるの。長い長い、永遠に終わらないんじゃないかって思うほどの悪夢」
「……」
彼女は少し遠い顔をして、苦しそうにそう吐き出した。
「あの日、起きたら何もかもなくなってるんじゃないかなんて、魁人くんが私と同じこと感じているから驚いた。そしてその気持ちが痛いほどわかった」
ギュッと胸に手を当てる。彼女の着ていたウェイター服に皺ができる。それだけでいかに苦しかったことかわかった。僕も…同じだからだ。
「魁人くんが私と同じ境遇だから…私はこうして働くことで気を紛らわしてて、だから魁人くんもどうかなって」
そう言って彼女が苦笑いをする。
「結局、私のそんなエゴで嫌なことを思い出させちゃったのが、なんだか情けないわ」
「そ、そんな卑下しないでください。僕はこうして話してるだけで十分助かってます」
空元気と思われてもいい。そんな思いで努めて明るく答える。実際、彼女に僕のことで暗い顔はして欲しくなかった。
「…すみません、本当は単純に遠慮していただけです。僕は十分救われたので、これ以上甘えてもいいのかと思って」
「そんなの気にしなくていいのに。私が魁人くんのことを気にかけたいと思ったからそうしてるだけ。これもある意味でエゴなの」
そういえば、僕を助けてくれた時も彼女はそうしたいからそうしたといった風だった。現に僕のことは何一つ知らなかったわけだし。そんな風にまっすぐ生きている姿は羨ましい上に、憧れすら感じる。
僕と彼女は似ている。僕と同じで眠れなくて、僕と同じでこっちに来て日が浅い。そんな根幹に関わるようなことが同じなのだから、共感し合うのは必然でもある。
だから──
「あ…明日からでいいですか?」
「え?」
「今日は、一応お客さんとしてきてるので。明日から精一杯働かせてください」
そう言って僕は立ち上がり、ぺこりと頭を下げた。
境遇の似ている彼女と一緒にいたい。エゴだろうが、わがままだろうが、甘えだろうが。僕も彼女と同じように、したいようにしてみたいと思った。
「いいの?」
「お願いしたいくらいでした。夜は長いですし、お手伝いさせてください」
「…ほぼお客さん来ないけどいい?」
「喫茶店でのバイトは初めてなので構いません」
「時給安いよ?」
「……お金じゃないですから」
「今ちょっと考えたね?」
「そんなことないです」
綺麗なミディアムヘアを揺らしてむくれる彼女を少し面白いと思った。いつの間にか夜のような暗い雰囲気は消えていた。
「あ、そしたら就職祝いに焼いてたお菓子をあげる」
彼女は唐突にそう言うと裏手に小走りで戻って行った。どことなく小躍りしているような足取りだった。
きっと接客業とはいえ夜に独りで寂しかったんだろうな。僕もそうだったからわかる。そういえば、他に従業員はいるのだろうか?後で聞いてみよう。
「おまたせ」
ミトンを嵌めた両手で持っていたのは、鮮やかな亜麻色のタルトのようなもの。
「…これなんですか?」
「タルトタタンっていうの。林檎を敷きつめたタルトよ」
甘い香りの正体はこれだった。森のような見た目の喫茶店に、これまた華やかなタルトが置かれる。それはどこか懐かしい香りがした。
「そういえばこの前もアップルパイでしたよね?林檎のお菓子が得意なのですか?」
「…そうね、林檎はよく使うわ」
僕の質問に、彼女はふっと微笑みながら答えた。それは微かに、なにかを誤魔化すような笑みにも見えた。
彼女はそんな表情を見せながらも、手際よくタルト生地を切り分ける。手馴れている。さすがは喫茶店のオーナーだ。
「ささっ、食べて食べて!美味しくできたつもりよ」
「…ではいただきます」
そう言って頬張り、歯で噛むとサクッと音を立ててタルト生地が崩れる。甘い香りがよりいっそう口の中に強く広がり、バターのコクと林檎の甘酸っぱさが美味しさを際立たせた。
「……」
そしてなにより、心の中が暖かい気持ちになった。以前もそうだったが、彼女の作るデザートは美味しさだけでなく心にまで染み渡る。優しすぎる彼女の心が詰まってるのか…不思議な気持ちになった。まるで魔法のようだ。
「…どう?」
「すごく美味しいです」
「よかった」
彼女が笑う。暖色照明に照らされた笑顔はとても素敵だった。
「そういえば、他に従業員の方はいるのですか?」
「ううん、私一人よ」
「え、よく経営できてましたね」
「これでも敏腕オーナーだからね」
なんてことはない会話。眠れない夜も悪くないなと思った。
「あっ…」
「ん?」
「また、忘れてました」
「なにを?」
そう言って僕は立ち上がる。彼女といると気持ちが楽になるが、今日はこれを伝えに来たんだ。
「この前は夜明けまで一緒にいてくれてありがとうございました。本当に…本当に助かりました」
「…ふふ、どういたしまして」
伝え忘れた感謝。ぺこりと頭を下げると、彼女が月明かりのように微笑んだ。2度目になる偶然の夜はゆったりと流れていった。
4月。遅咲きの桜を眺めながらキャンパスを歩く。同じ方向に向かって歩く新入生に混じり、僕も同じ歩幅で歩いていく。
僕は無事に大学に入学できた。両親が行方不明ではあるが、入学はもう決まっていたことだ。手続き関連に多少の手間はあったものの大学側は便宜を図ってくれた。不思議なもので、世の中は独りになっても諸々の制度でなんとか生きていけるらしい。国というのはよく出来ているんだなと、そう思った。
「……」
はらりと落ちる桜を見ながらあの夜のことを思い返す。
あれから10日ほどが経った。ある程度の社会的な制度に守られた今、あの時ほどの強烈な孤独感はなくなったと言える。むしろもっと早く行政のお世話になっていればとも思うくらいだ。
そうは言ってもこうやって前を向けたのも彼女の存在があったからこそ。出会えなかったらきっとまだ夜の街を彷徨っていたかもしれない。彼女には感謝しかないが、1つ心残りがあった。
「…感謝し忘れちゃったんだよな」
誰に言うでもなく呟く。春風に乗って言葉が消えた。あの日は気が動転していたのか、不思議なことばかりだったからなのか、彼女にきちんとありがとうと伝えられていなかった。
だからこそもう一度会えたらなと思う。
──
─
そんなことを考えながら歩いていたら食堂に着いた。お昼時の食堂は人でごったがえしている。談笑に花を咲かせる同じ大学生たちを横目に食券の券売機に並んだ。
元々そこまで社交的な性格ではないので、未だに友人と呼べる人はできなかった。手続き諸々もあったせいか、スタートダッシュは失敗気味だ。少し話す程度の人はいるが、これが所謂よっ友と呼ばれる関係性だろうか。少しずつ都会に慣れ、人にも慣れていきたい。
「……」
彼女、マリーさんは今どうしているだろうか。年齢は20歳だと言っていた。1つ上だが学生ではないと思う。お店のオーナーをやっているくらいだし。そういえばお店の場所すら聞けていなかったな…。
あれから眠れない日々は相変わらず続いているものの、同じ夜を過ごしている彼女を思うと、気が落ちることはなかった。似た境遇の人がいるというだけで心が楽になったような気がする。
「──なぁ、知ってるか?」
「ん?」
ボーッとそんなことを考えていると、僕の前に並ぶ男性2人組の会話が聞こえてきた。
「新宿辺りにあるお店の噂なんだが」
「ほぅ」
「なんでもな、願いが叶う喫茶店があるらしい」
「なんだそれ」
「あくまで噂なんだけど、例えば大切な失せ物が見つかったり、昔好きだった人に会えたり、そのお店に訪れる前に考えていた願い事が叶うっていうお店なんだよ」
悪いと思いながらも聞き耳を立てる。願いが叶うお店…?ふとあの日起こった出来事を思い出した。
あの日警官に追われていた時、願うことなら誰かに自分を肯定して欲しいと願った。そう思った瞬間、僕の名をピタリと当てたマリーさんと出会い、独りぼっちじゃないと思えた。願いと呼べるかわからない感情ではあったが、たしかにあの瞬間僕は自分が肯定された気がしたんだ。
「夜遅くまでやっているらしい。美味しいデザートと飲み物が飲めるお店なんだってさ」
「それが本当なら随分怪しいお店だな。…というかなんで新宿の夜の店を知ってるんだよ」
「あー…まぁバイト先でな、聞いたって感じだ」
夜遅くまでやってる喫茶店…。新宿付近では夜やってるお店自体は珍しくない。あの後調べたが、パフェが食べられる店もあるくらいだ。
だけど今聞いた話がどうにも全く関係のないことだとは思えなかった。願うが叶う、美味しいデザートの喫茶店…。
「歯切れ悪いな。叶えたい願いでもあるの?」
「…そうだな、妹の──」
「あ、あの……」
「え?」
気がつけば僕は2人に話しかけていた。いてもたってもいられなくなり、口を衝いて出たような感じ。自分でも驚いた。
「あっ…その話、詳しく聞かせてくれない?」
驚きとともに、胸が高鳴っているのを感じた。
──
─
「…お兄さん、お遊びどうですか?」
キャッチの人が街ゆく人に声をかける。この光景を見るのもなんだか久しぶりな気がした。
その日の夜、僕はまた新宿に来ていた。どうせ家にいても眠れないので、少しでも可能性のある行動をした方がいい。そう思ったからだ。
「……」
煌びやかな夜の街を独り歩く。若干ストーカーっぽい気がしなくもないなと、今更ながらに思ってきた。そんな思考を歩きながらかき消す。もう一度会いたいのは、あの日の感謝をきちんと伝えるためだ…。それにお店をやっているならなにも変なことはないはず。僕は頭を振りながら自分に言い聞かせた。
「…ここは」
歌舞伎町を過ぎたあたりの裏路地に着く。僕が初めてマリーさんと会った場所だ。何か手掛かりがあるかもと思い訪れてみたが、当然なにもない。近くに喫茶店がある様子もなかった。
僕はまたゆるりと歩き始める。
結局、券売機で話しかけた2人の学生からは有力な情報を得られていない。
なんでも、噂では叶えたい願いをぼーっとしながら歩いていたら辿り着いたというような感じらしい。明確な場所はないに等しかった。その願いというのもかなり強い想いを抱えていた人が多いそうだ。
叶えたい願いなど、僕にはいくつもある。こんな邪推が見つからない要因なのかもしれない。
「……あっ」
そうこうしてるうちに、夜がいっそう更けていっているのに気がついた。時間を見ると深夜を回っている。
ふと顔を上げれば、見た事のある小道に足を踏み入れていた。あの日彼女と会話をした四季の路という遊歩道。それなりの距離を歩いていたようだ。
「……」
しばらく進むとあの日僕らが会話した場所に着く。無意識のうちに彼女と会えた軌跡を辿っている自分がいた。
「…馬鹿馬鹿しくなってきた」
ふと思ったのだが、願いを叶える深夜の喫茶店とマリーさんとの間に関係があるというのも根拠がない。それも僕がなんとなく思っただけだ。彼女がそこにいる保証などどこにもない。
願いが叶うというのも信憑性に欠ける。震災で天涯孤独になるという起こりえない経験をしている僕が言うのもなんだが、現実味が薄すぎることだ。
「もう一回だけ…ちゃんと会えたらいいな」
僕はただ感謝が伝えたい、それだけだ。宛もなく歩くより聞き込み回った方が早いかもしれない。彼女はいい意味で目立つ人だし、人の多い新宿なら知っている人もいるだろう。歌舞伎町の方で聞き込みを…そう思い辺りを見回す。
「…あれ?」
しんとした夜の空気が身を包む。遊歩道には人っ子一人いなかった。この前話していた時はこんなに静かではなかった。深夜だがそれなりの人数が歩いていたはず。それが今日は誰もいなかった。
「……」
来た道を戻る。新宿にいるのはたしかなのだが、人気をほとんど感じなかった。眩い灯りは見えるが、歩く道は仄暗い。この道、こんなに暗かったっけ?
傍らに生える木の模様が笑っているように見えた。
「……」
ひたすらに歩いて戻る。しかし、歩けども歩けども、大通りに出ることができない。なんだか不自然なほど長く歩いている気がする。
孤独感に苛まれ、少し不安になってきた。
「…あ、あれ?」
まさか迷子?田舎者なので新宿は訪れ慣れていない場所だが、まさか一本道で迷子になるなんて…。焦って小走りになる。
「あっ、よかったぁ…」
しばらく歩いた数m先、遊歩道の終わりが見えてきた。ホッと一安心からか声が漏れる。僕は小道から逃げるように抜ける。すると──
「……ここは?」
大通りかと思って出た先は雑居ビルが立ち並ぶ路地裏の一本道だった。こんなところから小路に入っただろうか…?
ビルに遮られた月明かりを元手にキョロキョロと辺りを見回す。まさに建物の裏側が並ぶだけで目立つものは何もない。まだ迷ってるのかもと歩きながら思った矢先、ビルとビルの間に小さな建物を見つけた。
「……」
雑居ビルの間に挟まるようにできた小さな建物。
自動車1台がギリギリ入れる程度のビルとの間に、挟まるように存在していた。よくわからないパイプや換気扇しか見えないビルの裏が密集した道に、あまりそぐわない外観をしている。まるで1本の木のような建物。2階建て程度だろうか。御伽噺に出てくる木の小屋のようにも見える。
中央には扉があり、A4ノートサイズほどのこれまた木でできた看板が吊るされている。
「マ…ル…チェン?」
その木の看板には『Märchen』と書かれてあった。読めない…英語じゃないけど──
「……あっ。これ、ドイツ語?」
パッとスマホで調べる。メルヘンと読むようだ。
それよりもドイツ語という部分にピンとくる。もしかして──
「……」
期待を胸に僕は扉に手をかけた。
──
─
扉を開けるとそこは喫茶店になっていた。中に入った1番の感想は意外と広い、だった。
入口のすぐ近くにL字型のバーカウンターがあり、カウンターの後ろの棚にはコーヒーメーカーやティーポット、洋風なグラスやカップが立ち並ぶ。カウンターの向かいには2人用のテーブルと椅子のセットが、奥に向かうように2つ並んでいた。
「……」
入った瞬間から流れるフワッとした甘い香り。室内なのに空気は澄んでいて、まるで森の中にでもいるかのようだった。緑と茶色を基調とした内装の作りをしているせいもあるだろうか。店内にBGMはかかっていないが、小鳥の囀りすら聞こえてきそうなほど穏やかな空間。
小物は洒落たものが多い。カウンターの上には林檎の形をした陶器の角砂糖入れに、キラキラした雪の結晶が舞うスノードーム。
息を飲むほどオシャレなお店だが、店員の姿は見えない。
「……」
そう思い改めて見回すと、カウンターの奥に裏手に繋がっているであろう小さな扉があった。
「…あの──」
少し声を張り上げて扉に声をかけた瞬間、ガチャリと扉が開いた。
「ごめんなさい、お菓子焼いてて!いらっしゃいま──」
白雪のような白い肌、夜空のような真っ黒な艶髪。甘い香りとともに、バタバタと扉から出てきたのは、僕が探していた人だった。
「…ど、どうも」
「驚いたぁ…!魁人くん、こんばんは」
「マリーさん、こんばんは。覚えててくれたんですか?」
「当たり前じゃない。忘れるわけないわ。ささ、とにかく座って座って?」
ふふふっとあの日と同じ笑顔で笑いながら、カウンターの席へ誘う。
意外というほどでもないが、こうやってまた出会えたことに多少の驚きはあった。まさか本当に出会えるとは思っていなかったからだ。純粋な嬉しいという気持ちが芽生える。そしてさらに、覚えてくれていたこともその嬉しさに拍車をかけた。
「…でもよくここがわかったね?」
「あ、実は──」
カウンターの椅子に座るのとほぼ同時に、そう尋ねてくる彼女に言葉を返そうとして言い淀む。
「……」
「実は?」
実はマリーさんにもう一度会いたくて探していました、なんて言えるわけなかった。
いや、もちろん会えたこと自体は嬉しいのだが、たった一度会っただけの関係であるにも関わらず、お店まで突き止めようとしていたという事実はやはり少々よろしくない。ストーカーっぽいという考えは消したはずだが言葉にするとそれ以外の何者でもなかった。
「えーっと…」
「ん?」
そんなこととは露知らず、彼女は小首を傾げる。
「あー…願い事…そう、願い事です」
「願い事?」
「えぇ、願い事の叶う喫茶店というのが噂になっていてそれを探していて」
「あー!」
誤魔化そうと思って口に出た言葉で回答する。彼女と関係があるかもと思って探していたが、嘘はついていない。きっかけは間違いなくそれだったわけだし…とにかくストーカーで通報されるのを避けるのを優先した。
「あの噂ね、はいはい」
「知ってるのですか?」
「えぇ、もちろん。たぶんうちのお店のことだしね」
「あ、ここのお店がそう呼ばれてるのですか」
「つい数週間前くらいからかなぁ…そう呼ばれるようになったわね」
彼女は手近にあったグラスを拭きながらそう答える。僕の妄想に近い推測は正しかったようで、マリーさんのお店が噂の喫茶店だった。
「美味しいデザートと飲み物のお店だとは聞いていて」
「それでもしかしたらと思って探してくれたの?」
「はい…あっ。いや…違います。ストーカーとかでは…」
「ふふふっ、墓穴掘ってるよ」
「あっ、いや…」
心でも読まれたかのように誘導されて呆気なく喋ってしまった。前話した時もそうだが、彼女といると心の内が自然と出てしまう。
「安心して?それだけじゃストーカーだなんて思わないわ」
「本当ですか?」
「だってあれだけ話をしたんだもの。また会えて嬉しいくらいよ」
「よ、よかった…」
安堵し、一息つく。店内を包む甘い香りが心地いい。
「そういえばあれから眠れているかしら?」
「いえ…それは変わらずです。でも前より気持ちは楽になりました」
「気持ちが楽に?」
「はい。マリーさんも眠れていない日を過してるのかなと思うと、独りじゃなくなったような気がして」
「そう、それは素直に嬉しいわ。悪夢はまだ?」
「それは…はい」
不眠症は治っていないし、悪夢も見る。嫌な汗をかいて起きるのも変わらないが、それは仕方のないことだった。
「そう…やっぱりつらいよね。願い事の叶う喫茶店を探してたって聞いたけど、願い事はそれ?」
「…どうでしょう。もちろん眠れるようにもなりたいですが、それよりも独りじゃないと思いたいんだと思います。今あるつらいことは全部、孤独感から起きてることな気がするので」
眠れるようになりたいとか、母が最期に何を言おうとしていたのかとか、そういうのが気になってしまうのは全て今を独りで生きているからという孤独感だ。強烈ではなくなったものの、心の奥底に住み着いて離れない気がしている。
「独りじゃない…かぁ」
「…すみません、また自分のことを話してしまって」
「いいのよ、聞いたのは私だし。でもそうねぇ…」
彼女は優しくそう答え、その後なにかを考えるような仕草を見せた。
「魁人くん、東京に来てまだ日が浅いでしょ?」
「はい」
「生活とかどうしてるの?金銭面とか」
「あ、それはなんとかやりくりしてます。行方不明の遺産関係とか特殊な申請はありましたが…」
「そうなんだ、ひとまずよかったよ」
「とはいえ、必要最低限に留めておこうかなと。取り急ぎバイトはしないとなとは思ってます」
まだ家族が死亡したと決まったわけではし、見つかるかもしれないと考えてのことだ。そうなるとかなり生活は厳しい。
「…んー、そしたらさ。うちでバイトしない?」
「え?」
彼女がそう持ちかけてきた。
「バイト先決まってるの?」
「いえ、それはまだ…」
「それなら丁度いいかなって。夜の人手が欲しいかなーとは思ってたの」
彼女が手をパンッと手を合わせて笑みを向ける。
「渡りに船ではありますが…いいのですか?」
「もちろんよ?」
「でも、なんだか悪いです」
気が引けるわけではないが、少し甘えすぎな気もした。こうして会えただけでも嬉しいのに、生活面まで気にかけてくれるとは…。貰ってばかりで何も返せていない。
「まぁまぁ。それなら面接しましょ?それから雇うか考えるわ」
しかしそんな僕の気負いなどお構いなしに話を進めてきた。意外と強引なところもあるんだなと思った。
「はい、じゃあよろしくお願いします」
「あ…よろしくお願いします」
そう思いつつも、形式ばって礼をされてしまったのでこちらも礼で返す。
「ではお名前は──ってこれは知ってるからいっか。出身も…知ってるしいいわね」
「…そうですね」
考えながら話しているが、面接で聞かれるような内容など彼女は知りえている。…これ、意味あるのだろうか。
「んー、じゃあ学歴?どこの高校を卒業しましたか?」
「…えーっと、実は高校卒業したかと言われると怪しいです」
「え?でも大学生でしょ?」
「はい、それはそうですが…。卒業証明はあるんですけど、卒業式に出られてないので」
「あっ…地元に帰れてないから?」
「そうです。高校もあの惨事の中で卒業式やったのかも微妙ですけど…」
昔のことを話すと触れなくてはならないことだ。災害の話というのはどこにでもつきまとうものなのだと実感した。
「ごめん、そんなつもりじゃ…」
「いえ、僕も不幸話をするつもりではなかったので…すみません」
「あぁ、謝らないで!」
「いえ…」
「…ごめん」
互いにそんなつもりなどなく、謝り合う。少し空気が重たくなる。店内を満たす甘い香りもなんだか悲しげになった気がした。
「…い、今の質問はやっぱなしで!そしたら…うーんとね……」
あたふたした彼女は、ブツブツとああでもないこうでもないと質問を選び始める。そんな姿を見て、申し訳ない気持ちに拍車をかけた。
「…上手くいかないものね。本当はね、ただ魁人くんに独りじゃないと思って欲しいだけなの」
「え?」
「なんとかしてあげたいなって思ったの。私も夜が怖いから」
「依然そうお話されてましたよね…」
「うん。私もね、悪い夢を見たことがあるの。長い長い、永遠に終わらないんじゃないかって思うほどの悪夢」
「……」
彼女は少し遠い顔をして、苦しそうにそう吐き出した。
「あの日、起きたら何もかもなくなってるんじゃないかなんて、魁人くんが私と同じこと感じているから驚いた。そしてその気持ちが痛いほどわかった」
ギュッと胸に手を当てる。彼女の着ていたウェイター服に皺ができる。それだけでいかに苦しかったことかわかった。僕も…同じだからだ。
「魁人くんが私と同じ境遇だから…私はこうして働くことで気を紛らわしてて、だから魁人くんもどうかなって」
そう言って彼女が苦笑いをする。
「結局、私のそんなエゴで嫌なことを思い出させちゃったのが、なんだか情けないわ」
「そ、そんな卑下しないでください。僕はこうして話してるだけで十分助かってます」
空元気と思われてもいい。そんな思いで努めて明るく答える。実際、彼女に僕のことで暗い顔はして欲しくなかった。
「…すみません、本当は単純に遠慮していただけです。僕は十分救われたので、これ以上甘えてもいいのかと思って」
「そんなの気にしなくていいのに。私が魁人くんのことを気にかけたいと思ったからそうしてるだけ。これもある意味でエゴなの」
そういえば、僕を助けてくれた時も彼女はそうしたいからそうしたといった風だった。現に僕のことは何一つ知らなかったわけだし。そんな風にまっすぐ生きている姿は羨ましい上に、憧れすら感じる。
僕と彼女は似ている。僕と同じで眠れなくて、僕と同じでこっちに来て日が浅い。そんな根幹に関わるようなことが同じなのだから、共感し合うのは必然でもある。
だから──
「あ…明日からでいいですか?」
「え?」
「今日は、一応お客さんとしてきてるので。明日から精一杯働かせてください」
そう言って僕は立ち上がり、ぺこりと頭を下げた。
境遇の似ている彼女と一緒にいたい。エゴだろうが、わがままだろうが、甘えだろうが。僕も彼女と同じように、したいようにしてみたいと思った。
「いいの?」
「お願いしたいくらいでした。夜は長いですし、お手伝いさせてください」
「…ほぼお客さん来ないけどいい?」
「喫茶店でのバイトは初めてなので構いません」
「時給安いよ?」
「……お金じゃないですから」
「今ちょっと考えたね?」
「そんなことないです」
綺麗なミディアムヘアを揺らしてむくれる彼女を少し面白いと思った。いつの間にか夜のような暗い雰囲気は消えていた。
「あ、そしたら就職祝いに焼いてたお菓子をあげる」
彼女は唐突にそう言うと裏手に小走りで戻って行った。どことなく小躍りしているような足取りだった。
きっと接客業とはいえ夜に独りで寂しかったんだろうな。僕もそうだったからわかる。そういえば、他に従業員はいるのだろうか?後で聞いてみよう。
「おまたせ」
ミトンを嵌めた両手で持っていたのは、鮮やかな亜麻色のタルトのようなもの。
「…これなんですか?」
「タルトタタンっていうの。林檎を敷きつめたタルトよ」
甘い香りの正体はこれだった。森のような見た目の喫茶店に、これまた華やかなタルトが置かれる。それはどこか懐かしい香りがした。
「そういえばこの前もアップルパイでしたよね?林檎のお菓子が得意なのですか?」
「…そうね、林檎はよく使うわ」
僕の質問に、彼女はふっと微笑みながら答えた。それは微かに、なにかを誤魔化すような笑みにも見えた。
彼女はそんな表情を見せながらも、手際よくタルト生地を切り分ける。手馴れている。さすがは喫茶店のオーナーだ。
「ささっ、食べて食べて!美味しくできたつもりよ」
「…ではいただきます」
そう言って頬張り、歯で噛むとサクッと音を立ててタルト生地が崩れる。甘い香りがよりいっそう口の中に強く広がり、バターのコクと林檎の甘酸っぱさが美味しさを際立たせた。
「……」
そしてなにより、心の中が暖かい気持ちになった。以前もそうだったが、彼女の作るデザートは美味しさだけでなく心にまで染み渡る。優しすぎる彼女の心が詰まってるのか…不思議な気持ちになった。まるで魔法のようだ。
「…どう?」
「すごく美味しいです」
「よかった」
彼女が笑う。暖色照明に照らされた笑顔はとても素敵だった。
「そういえば、他に従業員の方はいるのですか?」
「ううん、私一人よ」
「え、よく経営できてましたね」
「これでも敏腕オーナーだからね」
なんてことはない会話。眠れない夜も悪くないなと思った。
「あっ…」
「ん?」
「また、忘れてました」
「なにを?」
そう言って僕は立ち上がる。彼女といると気持ちが楽になるが、今日はこれを伝えに来たんだ。
「この前は夜明けまで一緒にいてくれてありがとうございました。本当に…本当に助かりました」
「…ふふ、どういたしまして」
伝え忘れた感謝。ぺこりと頭を下げると、彼女が月明かりのように微笑んだ。2度目になる偶然の夜はゆったりと流れていった。