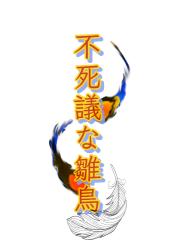* * *
木漏れ日照らす森の奥底。私は独り、座り込んでいた。目の前の惨状を目の当たりにして力が抜けてしまった。
崩れた木材、壊れた家財、割れた姿鏡。住んでいたはずの家は瓦礫へと成り果てていた。ぐちゃぐちゃになって腐った原型のない林檎菓子に蠅が集る。世話していた数名の孤児もいない。その目に映る全て、私が長く長く眠っていたことを表していた。
なにもない。誰もいない。そこにあるのはこの世界に独りぼっちになった、真新しい赤いドレスを着飾った…哀れな『魔女』と呼ばれた女、ただ一人。
「なんてこと…」
なんて言ったらよいのかわからないこの状況に、脳が勝手に声を漏らした。
あぁ、やっと…やっと目覚めたというのに…。
幾星霜待ちわびた夜明け、暗い暗い夢の底にいたほうが、幾分かましだったのかもしれない。
「……」
しかし涙すら出なかった。当たり前だ。流す涙など当の昔に枯れ果てていたのだから。感情なく、ただただ呆然と視界に映るかつて私の家だった残骸を見つめるのみ。
「……」
肌寒い風が通り抜ける。今は春か秋か、もしかしたら冬かもしれない。
照らしている木漏れ日は、朝日のようにも昼下がりのようにも思えた。いったい何時なのかもわからない。
また一つ、風がサァッと私の頬を撫でて消えていった。
──
─
「…なぁ、あんた!」
幾許の時をそうしていただろうか。突然、驚いたような声色で話かけられた。誰か来た気配すら気が付かなかった。
「…そんなところでなにしてるんだ?もうすぐ冬になるぞ」
見たことの無い服装に、見たことのない木筒のようなものを下げている。銃というやつだろうか。
「この辺じゃ見かけない顔だな。それに綺麗な黒髪だ。あんた日本人か?」
そう言って私の元へ来て手を差し伸べる。
「身寄りがないのか?冬になったら極寒だぞ」
ボーッと差し伸べられた手を見つめる。
「……綺麗な黒髪?」
彼の言葉を反芻する。刹那、はるか昔の虐げられた記憶が蘇る。
『忌々しい黒髪…なんで生まれてきたのかしら』
『近寄るな、魔女め!』
ここにいる男は私を見て否定しなかった。よく見ると彼の髪も、まるで夜のような黒色をしていた。
「立てるか?近くに俺の小屋がある。冬くらいは越させてやるから…とにかく暖を取りに来い」
虚ろな目をしたまま、私はそう言う彼の手を取った。
「……ありがとう」
私はこくりと頷き、立ち上がる。久しく触れてこなかった人の優しさに、思わず涙が頬を伝った。
「……日本」
涙を浮かべたまま、再び、反芻する。アジアの国だ。それくらいは知っている。
この黒髪が忌々しいと思われない…そんな国なのだろうか。
天涯孤独。きっと私の覚えているものは何もかもなくなった世界で、私は生きることができるだろうか…。また…王子様に出会えるだろうか…。
頬を撫でる秋風を受けながら、私はそう思った。
木漏れ日照らす森の奥底。私は独り、座り込んでいた。目の前の惨状を目の当たりにして力が抜けてしまった。
崩れた木材、壊れた家財、割れた姿鏡。住んでいたはずの家は瓦礫へと成り果てていた。ぐちゃぐちゃになって腐った原型のない林檎菓子に蠅が集る。世話していた数名の孤児もいない。その目に映る全て、私が長く長く眠っていたことを表していた。
なにもない。誰もいない。そこにあるのはこの世界に独りぼっちになった、真新しい赤いドレスを着飾った…哀れな『魔女』と呼ばれた女、ただ一人。
「なんてこと…」
なんて言ったらよいのかわからないこの状況に、脳が勝手に声を漏らした。
あぁ、やっと…やっと目覚めたというのに…。
幾星霜待ちわびた夜明け、暗い暗い夢の底にいたほうが、幾分かましだったのかもしれない。
「……」
しかし涙すら出なかった。当たり前だ。流す涙など当の昔に枯れ果てていたのだから。感情なく、ただただ呆然と視界に映るかつて私の家だった残骸を見つめるのみ。
「……」
肌寒い風が通り抜ける。今は春か秋か、もしかしたら冬かもしれない。
照らしている木漏れ日は、朝日のようにも昼下がりのようにも思えた。いったい何時なのかもわからない。
また一つ、風がサァッと私の頬を撫でて消えていった。
──
─
「…なぁ、あんた!」
幾許の時をそうしていただろうか。突然、驚いたような声色で話かけられた。誰か来た気配すら気が付かなかった。
「…そんなところでなにしてるんだ?もうすぐ冬になるぞ」
見たことの無い服装に、見たことのない木筒のようなものを下げている。銃というやつだろうか。
「この辺じゃ見かけない顔だな。それに綺麗な黒髪だ。あんた日本人か?」
そう言って私の元へ来て手を差し伸べる。
「身寄りがないのか?冬になったら極寒だぞ」
ボーッと差し伸べられた手を見つめる。
「……綺麗な黒髪?」
彼の言葉を反芻する。刹那、はるか昔の虐げられた記憶が蘇る。
『忌々しい黒髪…なんで生まれてきたのかしら』
『近寄るな、魔女め!』
ここにいる男は私を見て否定しなかった。よく見ると彼の髪も、まるで夜のような黒色をしていた。
「立てるか?近くに俺の小屋がある。冬くらいは越させてやるから…とにかく暖を取りに来い」
虚ろな目をしたまま、私はそう言う彼の手を取った。
「……ありがとう」
私はこくりと頷き、立ち上がる。久しく触れてこなかった人の優しさに、思わず涙が頬を伝った。
「……日本」
涙を浮かべたまま、再び、反芻する。アジアの国だ。それくらいは知っている。
この黒髪が忌々しいと思われない…そんな国なのだろうか。
天涯孤独。きっと私の覚えているものは何もかもなくなった世界で、私は生きることができるだろうか…。また…王子様に出会えるだろうか…。
頬を撫でる秋風を受けながら、私はそう思った。