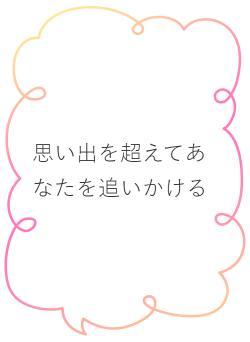高校の同級生の結婚式の帰り道、本格的な夏の訪れを控える六月の夜空の下は生ぬるく、披露宴と二次会で飲んで騒いだ後の火照ってべたついた体は、早くシャワーを浴びたいと私の足を宿泊するホテルへと急がせる。
五人の仲良しグループのうち一人が結婚した。未だに独身なのは私ともう一人だけ。
高校は女子校だったため高校時代は皆男の影はなし。彼氏なんてできる気がしないから五人でルームシェアでもして助け合って生きていこうか、三十歳まで独身だったらそうしよう、もうその線で考えたい。そんなことを言っていた三人が二十七歳から二十八歳になるこの一年の間に相次いで結婚した。私以外に残った一人も彼氏と同棲しており、もうすぐ結婚しそうとのことだ。
四月は中学の同級生、五月は大学の同級生の式があった。祝儀は一回三万円で三ヶ月の間に合計九万円。五月と今回の六月の式は遠方だったため交通費と宿泊費もかかっている。二次会の費用もそれなりに。合計十五万円くらいはこれらの結婚式関連だけで使っただろうか。まあ、二十八歳正社員、都会でも田舎でもない地方都市で彼氏もおらず独身実家暮らし、趣味は読書と散歩と動画視聴程度の私には、悲しいことにこれくらいのお金をすぐに出せるほどの貯金がある。
「詩穂ならすぐに彼氏できるよ。頑張って!」
東京で彼氏と同棲しており、家賃やその他諸々でお金が大変と嘆いていた幼稚園からの付き合いの雅美に言われた言葉を思い出しながら自分の恋愛遍歴を振り返る。
幼稚園の年長の頃、同じ組の和樹君と将来結婚する約束をした。以上、終わり。我ながらむなしくなる。
ちなみに和樹君は小学校に上がる前に遠くに引っ越してしまったのでその後は何もない。
幼稚園の頃は男友達もたくさんいたはずだが、小学生になると男子が苦手になってしまった。
大声で叫び、女子のスカートをめくり、休み時間には運動が苦手な私を強引に外でのドッジボールに誘い、教室内で殴り合いの喧嘩をして流れ弾の拳を私に食らわせ、そんな男子たちが何年生のときもクラスにいたおかげで男子と関わりを持つことを諦めてしまっていた。女子校だった高校はもちろん、共学の中学でも大学でも男子とはほとんど会話をしていない。
別に男性恐怖症というほどのものではないとは思っている。お父さんや男の先生、男の店員さんとは普通に会話できるのだ。だがそれは親子、教師と生徒、店員と客という関係があるからということは気がついている。
ただの男と女という特定の名前がつかない関係になると急に話ができなくなる。そんな私に恋愛なんて無理だ。
それでも、いつか王子様みたいな男性が目の前に現れて、私の手を取ってくれることを夢見ている。高貴で純真で愛情深く、私を絶対に守ってくれる人が目の前に現れるのを待ち続け、二十八歳になった。
「はぁ……」
いけない、ため息つくと幸せ逃げるよ、と一番最初に大学の同級生と結婚した由貴に二次会の時に言われたのだった。もともと幸せなんて持ってないから逃げないよ、と冗談半分で言い返してみたら、そうじゃなくてため息をついているような人のところに幸せはよってきてくれないってこと、と返されて納得した。
だったら息を吸えば幸せがよってきてくれるのか。
寂しさと酔いで判断力やら羞恥心が欠落しかけていた私は、丁字路の曲がり角の手前で立ち止まって目をつむり大きく両手を広げて深呼吸をしてみた。私の地元よりも発展しているからか少しだけ埃っぽい匂いとじめっとした空気、近くの焼鳥屋さんから漂ってくる美味しそうな匂いがする。かぐわしいタレの匂いと肉が焼ける匂いは食欲をそそる。
皆待っている人がいるからと終電前に解散になったため正直飲み足りなかったし、行ってしまうか。明日も仕事は休みだしありだな。でもその前にもう一回匂いを堪能しておくか。
そう思って今度は鼻をメインに深呼吸してみる。
その瞬間、私の視界の右端に大きな赤い塊が現れ鼻から通ってくるはずの焼鳥のいい匂いは何かの花のような甘く芳醇な香りにかき消された。
「わっ、何? げほっ、ごほっ」
嫌いな香りではないが予想とは異なる強烈なにおいを不意打ち的に嗅がされたため、私はむせて咳き込みながら地面に膝と手をついてしまった。スマホや財布が入った小さな鞄も地面に投げ出される。
「あ、す、すみません」
微かに上ずった声が耳に響く。咳が治まり立ち上がり声の主の方を向くと、そこには数えきれないほどの本数でできたバラの花束から顔をのぞかせる男性が立っていた。
身長は成人女性の平均ほどの私よりは少し大きいが、百七十センチはないくらい。きっちりとした黒いスーツに似合わない童顔で、一見すると女性とも見間違えるくらいに綺麗な肌が近くの建物の光の中ではっきりと浮かび上がっている。私が一目で男性だと思ったのは着ているスーツのおかげであり、今の時代それはただの偏見で実は女性なのかもしれない。
「本当にすみません。こんなにでかい花束持っていたから前が見づらくて。体は大丈夫ですか?」
「い、いえ。びっくりしただけで体はなんともありません。私の方こそ変なところで突っ立ってたから……そ、それでは」
鞄を拾って彼(彼女?)が来た方向へ歩き出す。
あの人は何故あんなに大きなバラの花束を抱えていたのだろうか。しかもこんな夜中に。
もしかしてこれから彼女の家に行ってプロポーズするつもりなのだろうか。あんなにたくさんのバラの花束を渡すなんて本当に王子様みたい。顔も整っていて優しそうで髪もサラサラで、私だったら絶対にオーケーしちゃうだろう。
ああ羨ましい。
ああいう人とお近づきになって、少女漫画もしくは恋愛ドラマみたいな恋がしたかった。男性が得意ではない私もあんな感じの人だったら多分大丈夫だ。現にさっきもきちんと受け答えできていた。
どんな人がこれからあの人のプロポーズを受けるのだろう。というかそもそもあの人何歳くらいなのだろう。下手すれば高校生にも見えるけど服装や時間を考えたらさすがに社会人だろうし、二十代前半といったところだろうか。二十八歳の私と比べると少し若いか、いや、学生時代ならともかく社会人ならこれくらいの差は珍しくない。
どんな仕事をしているのだろうか。華奢な体からして肉体労働系ではなさそう。営業の仕事だったらお金持ちのマダム相手にかなり稼げそうだ。女子校の先生とかだったら生徒にめちゃくちゃモテそう。モデル、は身長が高くないから難しそうだが俳優なら中学生役もできて重宝されそう。いっそのことアイドルでもいい。
趣味はなんだろうか。音楽はクラシックとか聞いていて欲しい。スポーツならテニスかフットサルとかが似合うかな。でも男性としてはあの小さい体でバスケが上手かったら萌える。お姉さんとかいて少女漫画を読んでいたりするのもいい。
彼への妄想が止まらない。もう二度と関わることのない彼に思いをはせてしまうのはきっと彼が私が求めていた王子様そのものだったから。こんな出会いを欲していたから。
確かに息を吸ったら幸せがよってきた。でもそれは私ではない誰かにとっての幸せで、今までため息をついていた分の効果で私からは逃げていってしまったのだ。
またため息をつこうとしてなんとか思いとどまり、無理やり息を吸って歩いてきた道を意味もなく振り返る。彼はあのまままっすぐ進んだはずだから後ろ姿が見えるはず。
だが、見えたのは後ろ姿ではなかった。
「あの! これ!」
振り返った私の視界にあったのはバラの花束を抱えたまま一生懸命に走る彼の姿だった。花束を抱えていない方の手には小さな紙切れが握られていて、その手を大きく振りながら私を呼んでいる。
バラの花びらを数枚散らしながら彼は立ち止まる私の目の前まで駆け寄ってくる。何が起きているのか、起ころうとしているのか理解できなかった。
「はぁ、はぁ。すみません、これ。あなたのではないですか?」
息を切らしながら彼が私に紙切れを差し出す。今日出席した結婚披露宴の席次表だった。鞄を落としたときに中からこぼれ落ちてしまったのだろう。
「あ、そ、そうです。すみません。わざわざありがとうございます」
「いえ。僕のせいで落としてしまったんですから、届けるのは当然です……結婚式だったんですか?」
「はい。高校の同級生で、先を越されちゃいました。私は相手すらいないのに」
何を言っているんだ私は。これからプロポーズをしようとしている人に独身彼氏なしをアピールしてどうする。
今までこんなことをしたことは一度もない。ずっと王子様を待っていたから自分から仕掛けるなんて考えたこともなかった。こんなことをするのは彼が魅力的過ぎるからだ。
「あの、ありがとうございます。えっと、が、頑張ってください!」
これ以上彼と一緒にいると叶わない気持ちに心を潰されてしまいそうになる。そう思って、彼と彼のお相手の幸せを最大限願って、エールを送った。
「え?」
彼はきょとんとして私を見ている。
「え? そのバラ、てっきりプロポーズでもされるのかなって」
「ああ、これですか」
彼は今にも泣きだしそうな顔で抱えた花束を見つめる。
「もうすでにプロポーズしたんですよ。一時間くらい前に、これを渡して結婚してくださいって言ったんです」
「……それが今あなたの手にあるってことは」
「はい。そういうことです」
ほんの少し涙を浮かべて彼は微笑む。
ぐーっという間抜けな音が二人の間に響き渡った。
「三十まで独身だったらルームシェアして皆で一緒に暮らそうって約束してたんですよ? それなのに三人は結婚してもう一人も同棲中で結婚秒読み。私だけ独身彼氏なしの実家暮らし。ひどくないですか?」
「それは、つらいですね」
「でしょう? 伊藤さんなら分かってくれると思ってました!」
伊藤と名乗った彼と私はいい匂いを振りまいて私を誘惑していた焼鳥屋さんにいた。
伊藤さんはプロポーズ失敗のショックで夕食をとっていなかったらしい。他の客が少ない店内で、四人掛けのテーブル席に向き合って座りタレのかかった焼鳥を二人でつまんだ。
私は自分でも不思議なくらいに不思議と伊藤さんに心を許していて、これまでの人生の鬱憤をお酒の力を借りてぶつけている。濃い目のハイボールが今日のお供だ。
「男って野蛮な人しかいないって思ってずっと避けてて、いつか理想の王子様みたいな人が現れてくれるんじゃないかって夢見てて、気がついたらもう二十八ですよ」
「まだそんなに悲観する年齢ではないと思いますよ」
「それは、そうですけど。周りの皆が結婚し始めてて、未だに彼氏すらできたことがないのはやばいなって……」
「今まで一人も、ですか?」
「そうですよ! 恋愛経験なんて幼稚園の頃に同じ組の男の子と結婚するって約束したくらいです! その子は小学生になる前に引っ越してどこかに行っちゃいましたけど! おかしいですよね。どうぞ笑ってください!」
「……それは、誰にでもそういう経験はあると思いますよ。気にすることでは――」
「彼氏いなかったことのフォローにはなってないですよー!」
私は何をやっているのだろう。珍しくちょっといいなと思った男性を逆ナンまがいに飲みに誘って、彼氏がいない愚痴を吐き出して、しかも相手はプロポーズに失敗した上に振られて傷心中。今までの私だったら考えられない行動に、自分でも制御が効かない。
「……伊藤さんはどうなんですか? 彼女さんと何があってこうなったんですか?」
だからこんな失礼なことでも口から漏れだすのを止められない。
伊藤さんは隣の椅子に置いたバラの花束を一瞥して、どこか吹っ切れたように爽やかに微笑んだ。
「彼女とは一年間交際していました。今日がちょうど交際一年目の記念日で、僕は初めてのデートで行った海の見える公園に彼女を呼び出したんです」
土地勘の薄くどこかを理解していない私に気がついた伊藤さんはスマホで写真を見せてくれた。行ったことはないがドラマのロケが行われたりやデートスポットとして人気の有名な場所だった。
「彼女も私も大事な話があるって言って、僕と彼女は同じ気持ちなんだって思って嬉しくて、この花束を用意して向かったんです」
「それ、何本あるんですか?」
「百八本です」
「えっと……」
バラは色だけでなく花束の本数でも花言葉が違ったはずだ。
「結婚してくださいっていう意味です。でも、断られて振られました。別れて欲しいって。それが彼女の大事な話だったんです」
「……どうして?」
「僕は優しすぎる、だそうです」
伊藤さんは再びにこりと微笑みを私に向ける。
「どうして?」
「いや、だから優しすぎるから……」
「なんで優しいと駄目なんですか? 意味が分かりません!」
優しいなんて最高じゃないか! 顔はもちろん良いし、一年付き合った彼女が優しいと言うならそれも本当のことだろう。そんな人と別れたいだなんて理解できなかった。
「私が――」
伊藤さんと結婚したいくらいなのに。その言葉を発する勇気は、お酒の力を借りても出なかった。
「私は優しい人がいいです……」
「世の中の女性はそういう人ばかりではないようです。彼女曰く僕は刺激が足りないそうです。僕は彼女のことが好きでしたけど、彼女は心のどこかで物足りなさを感じていたみたいです」
「難しいですね、恋愛って」
「そうですね」
伊藤さんはタレのかかったモモ肉の焼鳥を数個串に付いたまま食べ、残りを橋で皿の上に落とした。口の周りを汚さないため、異性の前でできるだけ上品に食べるためだろう。そして別の箸を持って私の分の焼鳥も串から外そうかと尋ねる。そんな小さな気遣いが素敵だと思う。
気遣いに甘えることにした私は作業に勤しむ伊藤さんの顔を見つめた。見れば見るほど綺麗な顔をしていて、外見も顔も整った伊藤さんを振った女の人の気が知れない。
「あの、失礼ですけど伊藤さんっておいくつなんですか?」
「二十八ですよ。斎藤さんと同い年です」
「嘘、同い年? 嘘でしょ? ていうかなんで私の歳知ってるんですか? 言いましたっけ?」
「すみません。披露宴の席次表を拾った時少し見てしまって、新婦の方のプロフィールを見て僕と同い年だということに気がついて、斎藤さんは新婦の方と高校の同級生だとおっしゃったので」
バツが悪そうに頭をかく伊藤さん。とても二十八歳には見えない爽やかで幼い顔をしている。
「下の名前は詩穂さんでよろしいですか? 確か出席者に斎藤さんはお二人いらっしゃいましたが、新婦高校時代友人となっていたのは詩穂さん。職場先輩となっていたのが恵美子さんでしたね」
「は、はい。す、すごいですね」
そんなに覚えるほどじっくり見たのだろうか。いや、丁字路で別れてから伊藤さんが私に声をかけるまでそんなに長い時間はかかっていないはずだ。
「あ、すみません。昔から名簿とか座席表を見て人の名前を覚えるのが得意なんです。子供の頃は父親の仕事の都合で転校を繰り返していたので、早く皆の名前を覚えようとして」
「転校ですか? どれくらいしたんですか?」
「小学校に入る前に一回。小学三年生の途中で二回目。六年生になる直前に三回目。中二で四回目。高一で五回目、ですかね。大学生になって一人暮らしを始めたくらいから父親は異動のない役職に就いて、仕方がないとはいえタイミングが悪いですね。大学の友達とは今も付き合いがありますけど、中学や高校の友達とはそれっきりですね」
「そっかぁ。転校生って友達いっぱい増えるしちやほやされるからちょっと羨ましかったけど、困ることも多いんですね」
「そうですね。好きな女の子がいても、たとえ両想いでも諦めざるをえないですから」
「えー? そういう経験あったんですか? 両想いなのに転校のせいで離れ離れになっちゃったっていう経験」
伊藤さんはもう何度目か分からない微笑みを私に向けた。
「ありますよ。僕も斎藤さんと同じように、幼稚園の頃結婚の約束をした女の子がいましたから」
「へぇ。どんな子だったんですか?」
「そうですね……」
昔を懐かしむように伊藤さんは目を閉じた。しばらくして目を開けると、私の顔を見つめながら語り出す。そんなに見つめられると恥ずかしい。私はハイボールを流し込み、照れて赤くなった顔を誤魔化した。
「優しくて、可愛くて、友達が多い子でした。いつか王子様と結婚するんだって言ってて、僕が王子様になるって言ったら、それなら結婚しようって約束したんです」
まるで私みたいだ。いや、優しいとか可愛いはともかくとして、幼稚園の頃は友達は多かったしその頃から王子様に憧れていたのも事実だ。
「でも、結局その子には何も言わないまま小学校に入る前に引っ越してしまいました。幼稚園児だった僕は色々と気が回らなかった。だからバチが当たったんですよ。あの約束を放置して他の女性と結婚しようとしたから」
「そんな……幼稚園の時の約束なんて」
「その約束があったから人に優しくしようと気をつけたし、もともと童顔なのはありますけど、肌とか髪もケアをちゃんとして外見にも気をつけて、スポーツもして体も鍛えました。王子様になりたかったんですよ、僕は」
伊藤さんは真剣な目で私を見つめている。とても少し前にプロポーズに失敗して振られた人とは思えないくらいに情熱的な目だ。
伊藤という苗字を記憶の中から探すが該当者が多すぎて絞り切れない。でも、かすかに残った記憶の中にそれはいた。和樹君の苗字は確か伊藤だった。
斎藤の私と伊藤の和樹君。似たような苗字が幼稚園児だった私たちにはなんだか面白くて、それがきっかけで仲良くなった。
顔の面影はない。幼稚園の時点で童顔だなんて分かるはずもない。優しいとか気遣いができるとかそんなことも覚えていない。ただ一緒にいると楽しくかったから好きだった。
「和樹君……」
「奇跡だと思った。振られて公園でしばらくぼーっとして、トボトボ帰ろうと歩いていたら、詩穂ちゃんになんとなく似ている女性と出会って、でもそんな偶然はないって思っていた。でも、披露宴の席次表に斎藤詩穂と篠田雅美の名前を見つけた。同じ幼稚園だった二人の名前があるなら間違いないって思って追いかけたんだ。いつの間にか彼女に振られた悲しみよりも詩穂ちゃんと再会できた喜びで泣きそうになっていた」
ずっと空っぽだった心の隙間が埋まっていくような感覚がする。私の二十八年の人生の中で経験したことがない恋という概念が注ぎ込まれていく。二十三年も前の恋とも呼べない何かが私に恋をもたらした。
もし和樹君が私に「付き合って欲しい」と言ってくれたら私は了承する。「結婚してください」と言いながら傍らに置いたバラの花束をくれたら和樹君を抱きしめて、今すぐに仲良しグループのメンバーを呼び出して宴会を始めるだろう。
でも、和樹君から次の言葉はない。
それはそうだ。和樹君はついさっき彼女と別れたばかり。そんなにすぐに他の女性に乗り換えるような軽い男ではない。
だから、私が言わなければならない。
他の女性にプロポーズした事実も受け入れて、過去の約束はそれとして、今の和樹君が好きだと。結婚を前提に付き合って欲しい、と。
「あの、和樹君……」
言え。言うんだ。チャンスなんてこれきりだ。
興奮と緊張で体が、顔が、頭が熱くなる。グラグラと視界が揺れて気持ち悪い。
「詩穂ちゃん? ……詩穂ちゃん!」
私は飲み過ぎたようだ。
朦朧とする意識の中、私は和樹君の肩を借りて歩いた。
言った覚えはないがどうやら言ったらしく、私が宿泊するホテルのロビーにあるソファーに座らされた。
「大丈夫? 詩穂ちゃん」
生ぬるい夜風に当たり、水を飲ませてもらい、少しはましになった私に和樹君が優しく声をかける。こんなんでは告白どころではない。やはり私には恋なんて向いていない。
「チェックインは済ましてあるってフロントの人に聞いたよ。部屋、一人で行ける?」
「うん」
「……それじゃあ、俺は」
「待って」
この場を去ろうとする和樹君の手を掴んだ。自分の目に涙が浮かんでいるのが分かる。和樹君は困ったような目で私を見ている。
「詩穂ちゃん、俺は……彼女に振らればかりなんだ。そんな俺が……」
高貴で純真で愛情深い彼が困っている。
「ごめん」
私の手を振りほどき、和樹君はホテルから出て行ってしまった。
私は呆然とそれを見送る。
私はため息をつき過ぎたのだ。幸せが逃げて行ってしまった。
和樹君が持っていた花束から落ちたバラの花びらを拾い上げて、最後に大きく息を吸ってみた。なんて往生際の悪いことだ。
幸せはよって来なかったがバラの香りがした。
鞄を開けると八本のバラの花束と、連絡先の書いてある紙切れが入っていた。
涙は大粒となってホテルのロビーの床を濡らした。
五人の仲良しグループのうち一人が結婚した。未だに独身なのは私ともう一人だけ。
高校は女子校だったため高校時代は皆男の影はなし。彼氏なんてできる気がしないから五人でルームシェアでもして助け合って生きていこうか、三十歳まで独身だったらそうしよう、もうその線で考えたい。そんなことを言っていた三人が二十七歳から二十八歳になるこの一年の間に相次いで結婚した。私以外に残った一人も彼氏と同棲しており、もうすぐ結婚しそうとのことだ。
四月は中学の同級生、五月は大学の同級生の式があった。祝儀は一回三万円で三ヶ月の間に合計九万円。五月と今回の六月の式は遠方だったため交通費と宿泊費もかかっている。二次会の費用もそれなりに。合計十五万円くらいはこれらの結婚式関連だけで使っただろうか。まあ、二十八歳正社員、都会でも田舎でもない地方都市で彼氏もおらず独身実家暮らし、趣味は読書と散歩と動画視聴程度の私には、悲しいことにこれくらいのお金をすぐに出せるほどの貯金がある。
「詩穂ならすぐに彼氏できるよ。頑張って!」
東京で彼氏と同棲しており、家賃やその他諸々でお金が大変と嘆いていた幼稚園からの付き合いの雅美に言われた言葉を思い出しながら自分の恋愛遍歴を振り返る。
幼稚園の年長の頃、同じ組の和樹君と将来結婚する約束をした。以上、終わり。我ながらむなしくなる。
ちなみに和樹君は小学校に上がる前に遠くに引っ越してしまったのでその後は何もない。
幼稚園の頃は男友達もたくさんいたはずだが、小学生になると男子が苦手になってしまった。
大声で叫び、女子のスカートをめくり、休み時間には運動が苦手な私を強引に外でのドッジボールに誘い、教室内で殴り合いの喧嘩をして流れ弾の拳を私に食らわせ、そんな男子たちが何年生のときもクラスにいたおかげで男子と関わりを持つことを諦めてしまっていた。女子校だった高校はもちろん、共学の中学でも大学でも男子とはほとんど会話をしていない。
別に男性恐怖症というほどのものではないとは思っている。お父さんや男の先生、男の店員さんとは普通に会話できるのだ。だがそれは親子、教師と生徒、店員と客という関係があるからということは気がついている。
ただの男と女という特定の名前がつかない関係になると急に話ができなくなる。そんな私に恋愛なんて無理だ。
それでも、いつか王子様みたいな男性が目の前に現れて、私の手を取ってくれることを夢見ている。高貴で純真で愛情深く、私を絶対に守ってくれる人が目の前に現れるのを待ち続け、二十八歳になった。
「はぁ……」
いけない、ため息つくと幸せ逃げるよ、と一番最初に大学の同級生と結婚した由貴に二次会の時に言われたのだった。もともと幸せなんて持ってないから逃げないよ、と冗談半分で言い返してみたら、そうじゃなくてため息をついているような人のところに幸せはよってきてくれないってこと、と返されて納得した。
だったら息を吸えば幸せがよってきてくれるのか。
寂しさと酔いで判断力やら羞恥心が欠落しかけていた私は、丁字路の曲がり角の手前で立ち止まって目をつむり大きく両手を広げて深呼吸をしてみた。私の地元よりも発展しているからか少しだけ埃っぽい匂いとじめっとした空気、近くの焼鳥屋さんから漂ってくる美味しそうな匂いがする。かぐわしいタレの匂いと肉が焼ける匂いは食欲をそそる。
皆待っている人がいるからと終電前に解散になったため正直飲み足りなかったし、行ってしまうか。明日も仕事は休みだしありだな。でもその前にもう一回匂いを堪能しておくか。
そう思って今度は鼻をメインに深呼吸してみる。
その瞬間、私の視界の右端に大きな赤い塊が現れ鼻から通ってくるはずの焼鳥のいい匂いは何かの花のような甘く芳醇な香りにかき消された。
「わっ、何? げほっ、ごほっ」
嫌いな香りではないが予想とは異なる強烈なにおいを不意打ち的に嗅がされたため、私はむせて咳き込みながら地面に膝と手をついてしまった。スマホや財布が入った小さな鞄も地面に投げ出される。
「あ、す、すみません」
微かに上ずった声が耳に響く。咳が治まり立ち上がり声の主の方を向くと、そこには数えきれないほどの本数でできたバラの花束から顔をのぞかせる男性が立っていた。
身長は成人女性の平均ほどの私よりは少し大きいが、百七十センチはないくらい。きっちりとした黒いスーツに似合わない童顔で、一見すると女性とも見間違えるくらいに綺麗な肌が近くの建物の光の中ではっきりと浮かび上がっている。私が一目で男性だと思ったのは着ているスーツのおかげであり、今の時代それはただの偏見で実は女性なのかもしれない。
「本当にすみません。こんなにでかい花束持っていたから前が見づらくて。体は大丈夫ですか?」
「い、いえ。びっくりしただけで体はなんともありません。私の方こそ変なところで突っ立ってたから……そ、それでは」
鞄を拾って彼(彼女?)が来た方向へ歩き出す。
あの人は何故あんなに大きなバラの花束を抱えていたのだろうか。しかもこんな夜中に。
もしかしてこれから彼女の家に行ってプロポーズするつもりなのだろうか。あんなにたくさんのバラの花束を渡すなんて本当に王子様みたい。顔も整っていて優しそうで髪もサラサラで、私だったら絶対にオーケーしちゃうだろう。
ああ羨ましい。
ああいう人とお近づきになって、少女漫画もしくは恋愛ドラマみたいな恋がしたかった。男性が得意ではない私もあんな感じの人だったら多分大丈夫だ。現にさっきもきちんと受け答えできていた。
どんな人がこれからあの人のプロポーズを受けるのだろう。というかそもそもあの人何歳くらいなのだろう。下手すれば高校生にも見えるけど服装や時間を考えたらさすがに社会人だろうし、二十代前半といったところだろうか。二十八歳の私と比べると少し若いか、いや、学生時代ならともかく社会人ならこれくらいの差は珍しくない。
どんな仕事をしているのだろうか。華奢な体からして肉体労働系ではなさそう。営業の仕事だったらお金持ちのマダム相手にかなり稼げそうだ。女子校の先生とかだったら生徒にめちゃくちゃモテそう。モデル、は身長が高くないから難しそうだが俳優なら中学生役もできて重宝されそう。いっそのことアイドルでもいい。
趣味はなんだろうか。音楽はクラシックとか聞いていて欲しい。スポーツならテニスかフットサルとかが似合うかな。でも男性としてはあの小さい体でバスケが上手かったら萌える。お姉さんとかいて少女漫画を読んでいたりするのもいい。
彼への妄想が止まらない。もう二度と関わることのない彼に思いをはせてしまうのはきっと彼が私が求めていた王子様そのものだったから。こんな出会いを欲していたから。
確かに息を吸ったら幸せがよってきた。でもそれは私ではない誰かにとっての幸せで、今までため息をついていた分の効果で私からは逃げていってしまったのだ。
またため息をつこうとしてなんとか思いとどまり、無理やり息を吸って歩いてきた道を意味もなく振り返る。彼はあのまままっすぐ進んだはずだから後ろ姿が見えるはず。
だが、見えたのは後ろ姿ではなかった。
「あの! これ!」
振り返った私の視界にあったのはバラの花束を抱えたまま一生懸命に走る彼の姿だった。花束を抱えていない方の手には小さな紙切れが握られていて、その手を大きく振りながら私を呼んでいる。
バラの花びらを数枚散らしながら彼は立ち止まる私の目の前まで駆け寄ってくる。何が起きているのか、起ころうとしているのか理解できなかった。
「はぁ、はぁ。すみません、これ。あなたのではないですか?」
息を切らしながら彼が私に紙切れを差し出す。今日出席した結婚披露宴の席次表だった。鞄を落としたときに中からこぼれ落ちてしまったのだろう。
「あ、そ、そうです。すみません。わざわざありがとうございます」
「いえ。僕のせいで落としてしまったんですから、届けるのは当然です……結婚式だったんですか?」
「はい。高校の同級生で、先を越されちゃいました。私は相手すらいないのに」
何を言っているんだ私は。これからプロポーズをしようとしている人に独身彼氏なしをアピールしてどうする。
今までこんなことをしたことは一度もない。ずっと王子様を待っていたから自分から仕掛けるなんて考えたこともなかった。こんなことをするのは彼が魅力的過ぎるからだ。
「あの、ありがとうございます。えっと、が、頑張ってください!」
これ以上彼と一緒にいると叶わない気持ちに心を潰されてしまいそうになる。そう思って、彼と彼のお相手の幸せを最大限願って、エールを送った。
「え?」
彼はきょとんとして私を見ている。
「え? そのバラ、てっきりプロポーズでもされるのかなって」
「ああ、これですか」
彼は今にも泣きだしそうな顔で抱えた花束を見つめる。
「もうすでにプロポーズしたんですよ。一時間くらい前に、これを渡して結婚してくださいって言ったんです」
「……それが今あなたの手にあるってことは」
「はい。そういうことです」
ほんの少し涙を浮かべて彼は微笑む。
ぐーっという間抜けな音が二人の間に響き渡った。
「三十まで独身だったらルームシェアして皆で一緒に暮らそうって約束してたんですよ? それなのに三人は結婚してもう一人も同棲中で結婚秒読み。私だけ独身彼氏なしの実家暮らし。ひどくないですか?」
「それは、つらいですね」
「でしょう? 伊藤さんなら分かってくれると思ってました!」
伊藤と名乗った彼と私はいい匂いを振りまいて私を誘惑していた焼鳥屋さんにいた。
伊藤さんはプロポーズ失敗のショックで夕食をとっていなかったらしい。他の客が少ない店内で、四人掛けのテーブル席に向き合って座りタレのかかった焼鳥を二人でつまんだ。
私は自分でも不思議なくらいに不思議と伊藤さんに心を許していて、これまでの人生の鬱憤をお酒の力を借りてぶつけている。濃い目のハイボールが今日のお供だ。
「男って野蛮な人しかいないって思ってずっと避けてて、いつか理想の王子様みたいな人が現れてくれるんじゃないかって夢見てて、気がついたらもう二十八ですよ」
「まだそんなに悲観する年齢ではないと思いますよ」
「それは、そうですけど。周りの皆が結婚し始めてて、未だに彼氏すらできたことがないのはやばいなって……」
「今まで一人も、ですか?」
「そうですよ! 恋愛経験なんて幼稚園の頃に同じ組の男の子と結婚するって約束したくらいです! その子は小学生になる前に引っ越してどこかに行っちゃいましたけど! おかしいですよね。どうぞ笑ってください!」
「……それは、誰にでもそういう経験はあると思いますよ。気にすることでは――」
「彼氏いなかったことのフォローにはなってないですよー!」
私は何をやっているのだろう。珍しくちょっといいなと思った男性を逆ナンまがいに飲みに誘って、彼氏がいない愚痴を吐き出して、しかも相手はプロポーズに失敗した上に振られて傷心中。今までの私だったら考えられない行動に、自分でも制御が効かない。
「……伊藤さんはどうなんですか? 彼女さんと何があってこうなったんですか?」
だからこんな失礼なことでも口から漏れだすのを止められない。
伊藤さんは隣の椅子に置いたバラの花束を一瞥して、どこか吹っ切れたように爽やかに微笑んだ。
「彼女とは一年間交際していました。今日がちょうど交際一年目の記念日で、僕は初めてのデートで行った海の見える公園に彼女を呼び出したんです」
土地勘の薄くどこかを理解していない私に気がついた伊藤さんはスマホで写真を見せてくれた。行ったことはないがドラマのロケが行われたりやデートスポットとして人気の有名な場所だった。
「彼女も私も大事な話があるって言って、僕と彼女は同じ気持ちなんだって思って嬉しくて、この花束を用意して向かったんです」
「それ、何本あるんですか?」
「百八本です」
「えっと……」
バラは色だけでなく花束の本数でも花言葉が違ったはずだ。
「結婚してくださいっていう意味です。でも、断られて振られました。別れて欲しいって。それが彼女の大事な話だったんです」
「……どうして?」
「僕は優しすぎる、だそうです」
伊藤さんは再びにこりと微笑みを私に向ける。
「どうして?」
「いや、だから優しすぎるから……」
「なんで優しいと駄目なんですか? 意味が分かりません!」
優しいなんて最高じゃないか! 顔はもちろん良いし、一年付き合った彼女が優しいと言うならそれも本当のことだろう。そんな人と別れたいだなんて理解できなかった。
「私が――」
伊藤さんと結婚したいくらいなのに。その言葉を発する勇気は、お酒の力を借りても出なかった。
「私は優しい人がいいです……」
「世の中の女性はそういう人ばかりではないようです。彼女曰く僕は刺激が足りないそうです。僕は彼女のことが好きでしたけど、彼女は心のどこかで物足りなさを感じていたみたいです」
「難しいですね、恋愛って」
「そうですね」
伊藤さんはタレのかかったモモ肉の焼鳥を数個串に付いたまま食べ、残りを橋で皿の上に落とした。口の周りを汚さないため、異性の前でできるだけ上品に食べるためだろう。そして別の箸を持って私の分の焼鳥も串から外そうかと尋ねる。そんな小さな気遣いが素敵だと思う。
気遣いに甘えることにした私は作業に勤しむ伊藤さんの顔を見つめた。見れば見るほど綺麗な顔をしていて、外見も顔も整った伊藤さんを振った女の人の気が知れない。
「あの、失礼ですけど伊藤さんっておいくつなんですか?」
「二十八ですよ。斎藤さんと同い年です」
「嘘、同い年? 嘘でしょ? ていうかなんで私の歳知ってるんですか? 言いましたっけ?」
「すみません。披露宴の席次表を拾った時少し見てしまって、新婦の方のプロフィールを見て僕と同い年だということに気がついて、斎藤さんは新婦の方と高校の同級生だとおっしゃったので」
バツが悪そうに頭をかく伊藤さん。とても二十八歳には見えない爽やかで幼い顔をしている。
「下の名前は詩穂さんでよろしいですか? 確か出席者に斎藤さんはお二人いらっしゃいましたが、新婦高校時代友人となっていたのは詩穂さん。職場先輩となっていたのが恵美子さんでしたね」
「は、はい。す、すごいですね」
そんなに覚えるほどじっくり見たのだろうか。いや、丁字路で別れてから伊藤さんが私に声をかけるまでそんなに長い時間はかかっていないはずだ。
「あ、すみません。昔から名簿とか座席表を見て人の名前を覚えるのが得意なんです。子供の頃は父親の仕事の都合で転校を繰り返していたので、早く皆の名前を覚えようとして」
「転校ですか? どれくらいしたんですか?」
「小学校に入る前に一回。小学三年生の途中で二回目。六年生になる直前に三回目。中二で四回目。高一で五回目、ですかね。大学生になって一人暮らしを始めたくらいから父親は異動のない役職に就いて、仕方がないとはいえタイミングが悪いですね。大学の友達とは今も付き合いがありますけど、中学や高校の友達とはそれっきりですね」
「そっかぁ。転校生って友達いっぱい増えるしちやほやされるからちょっと羨ましかったけど、困ることも多いんですね」
「そうですね。好きな女の子がいても、たとえ両想いでも諦めざるをえないですから」
「えー? そういう経験あったんですか? 両想いなのに転校のせいで離れ離れになっちゃったっていう経験」
伊藤さんはもう何度目か分からない微笑みを私に向けた。
「ありますよ。僕も斎藤さんと同じように、幼稚園の頃結婚の約束をした女の子がいましたから」
「へぇ。どんな子だったんですか?」
「そうですね……」
昔を懐かしむように伊藤さんは目を閉じた。しばらくして目を開けると、私の顔を見つめながら語り出す。そんなに見つめられると恥ずかしい。私はハイボールを流し込み、照れて赤くなった顔を誤魔化した。
「優しくて、可愛くて、友達が多い子でした。いつか王子様と結婚するんだって言ってて、僕が王子様になるって言ったら、それなら結婚しようって約束したんです」
まるで私みたいだ。いや、優しいとか可愛いはともかくとして、幼稚園の頃は友達は多かったしその頃から王子様に憧れていたのも事実だ。
「でも、結局その子には何も言わないまま小学校に入る前に引っ越してしまいました。幼稚園児だった僕は色々と気が回らなかった。だからバチが当たったんですよ。あの約束を放置して他の女性と結婚しようとしたから」
「そんな……幼稚園の時の約束なんて」
「その約束があったから人に優しくしようと気をつけたし、もともと童顔なのはありますけど、肌とか髪もケアをちゃんとして外見にも気をつけて、スポーツもして体も鍛えました。王子様になりたかったんですよ、僕は」
伊藤さんは真剣な目で私を見つめている。とても少し前にプロポーズに失敗して振られた人とは思えないくらいに情熱的な目だ。
伊藤という苗字を記憶の中から探すが該当者が多すぎて絞り切れない。でも、かすかに残った記憶の中にそれはいた。和樹君の苗字は確か伊藤だった。
斎藤の私と伊藤の和樹君。似たような苗字が幼稚園児だった私たちにはなんだか面白くて、それがきっかけで仲良くなった。
顔の面影はない。幼稚園の時点で童顔だなんて分かるはずもない。優しいとか気遣いができるとかそんなことも覚えていない。ただ一緒にいると楽しくかったから好きだった。
「和樹君……」
「奇跡だと思った。振られて公園でしばらくぼーっとして、トボトボ帰ろうと歩いていたら、詩穂ちゃんになんとなく似ている女性と出会って、でもそんな偶然はないって思っていた。でも、披露宴の席次表に斎藤詩穂と篠田雅美の名前を見つけた。同じ幼稚園だった二人の名前があるなら間違いないって思って追いかけたんだ。いつの間にか彼女に振られた悲しみよりも詩穂ちゃんと再会できた喜びで泣きそうになっていた」
ずっと空っぽだった心の隙間が埋まっていくような感覚がする。私の二十八年の人生の中で経験したことがない恋という概念が注ぎ込まれていく。二十三年も前の恋とも呼べない何かが私に恋をもたらした。
もし和樹君が私に「付き合って欲しい」と言ってくれたら私は了承する。「結婚してください」と言いながら傍らに置いたバラの花束をくれたら和樹君を抱きしめて、今すぐに仲良しグループのメンバーを呼び出して宴会を始めるだろう。
でも、和樹君から次の言葉はない。
それはそうだ。和樹君はついさっき彼女と別れたばかり。そんなにすぐに他の女性に乗り換えるような軽い男ではない。
だから、私が言わなければならない。
他の女性にプロポーズした事実も受け入れて、過去の約束はそれとして、今の和樹君が好きだと。結婚を前提に付き合って欲しい、と。
「あの、和樹君……」
言え。言うんだ。チャンスなんてこれきりだ。
興奮と緊張で体が、顔が、頭が熱くなる。グラグラと視界が揺れて気持ち悪い。
「詩穂ちゃん? ……詩穂ちゃん!」
私は飲み過ぎたようだ。
朦朧とする意識の中、私は和樹君の肩を借りて歩いた。
言った覚えはないがどうやら言ったらしく、私が宿泊するホテルのロビーにあるソファーに座らされた。
「大丈夫? 詩穂ちゃん」
生ぬるい夜風に当たり、水を飲ませてもらい、少しはましになった私に和樹君が優しく声をかける。こんなんでは告白どころではない。やはり私には恋なんて向いていない。
「チェックインは済ましてあるってフロントの人に聞いたよ。部屋、一人で行ける?」
「うん」
「……それじゃあ、俺は」
「待って」
この場を去ろうとする和樹君の手を掴んだ。自分の目に涙が浮かんでいるのが分かる。和樹君は困ったような目で私を見ている。
「詩穂ちゃん、俺は……彼女に振らればかりなんだ。そんな俺が……」
高貴で純真で愛情深い彼が困っている。
「ごめん」
私の手を振りほどき、和樹君はホテルから出て行ってしまった。
私は呆然とそれを見送る。
私はため息をつき過ぎたのだ。幸せが逃げて行ってしまった。
和樹君が持っていた花束から落ちたバラの花びらを拾い上げて、最後に大きく息を吸ってみた。なんて往生際の悪いことだ。
幸せはよって来なかったがバラの香りがした。
鞄を開けると八本のバラの花束と、連絡先の書いてある紙切れが入っていた。
涙は大粒となってホテルのロビーの床を濡らした。