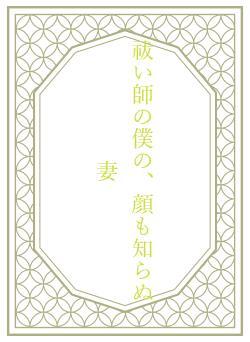「花菜ちゃんが忘れても、僕は絶対に忘れない。
花菜ちゃんは僕の恋人だって、大好きだって、何度でも伝えるよ。
涙が流れたら、僕が拭う。
不安でどうしようもなくなったら、ずっと抱きしめて傍にいる。
記憶がなくなったとしても、僕が恋人だって信じられなくなっても、僕は花菜ちゃんに何度でも告白する。
僕の、恋人になってくださいって。
もしそれで振られても、離れたりしないから」
静かに僕の言葉に耳を傾けていた彼女は、最後の言葉だけは聞き捨てならなかったのか、すぐに否定した。
「私が、駿ちゃんを振るわけないよ。何を忘れても、駿ちゃんのことだけは、駿ちゃんを好きな気持ちだけは、忘れない」
涙を零しながらもハッキリと断言されて、知らずの内に笑みが浮かぶ。
「…うん、そうだね。忘れないね。お互いを想う気持ちだけは、何があっても」
「絶対に、忘れないよ」
「ありがとう。もう、僕にはそれだけで十分なんだ。
花菜ちゃんが…、大好きな彼女が、僕のことを好きでいてくれる。
それ以上に幸せなことなんてないよ」
夜が来なければいいと、ずっと時間が止まってほしいと願ったことも、もちろんある。
でも無情にも時は過ぎ、彼女は自らも知らぬ間に歳を取る。