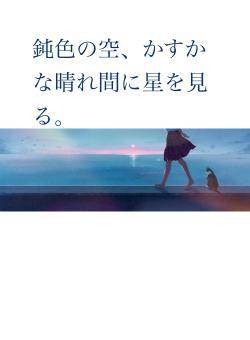『個性』という言葉を聞くたび、僕はいつも疑問を抱いた。
だって、どこまでを個性と呼ぶのだろう。
じぶんの意見をはっきり言うことは、一般的には美徳とされているけれど、社会ではそうではない。
右にならって、『みんなと同じ』ほうがぜったいに生きやすい。
じぶんの意志を持ち、『ひとと違う』ことは、否定されがちだ。
だから、右にならう。
だけどそうしてしまったら、個性は消える。
個性を消したらつまらないと言われ、自我を通したら変わり者と罵られ。
ならば、『なに者』であればいいのか教えてほしい。
なに者であるべきなのか、それさえ教えてくれたら、僕だってちゃんと、社会に適応してみせるのに……。
***
蝶々さんの家に来てから、半月が過ぎていた。
春休みは荷解きをしているうちにあっという間に過ぎていき、いよいよ高校が始まった。
これから三年間通うことになるさくらの森高校は、共学の私立高校だ。偏差値はそこそこ高いが、ばりばりの進学校というほどでもないためか、入学式の新入生の雰囲気はどこかのんびりとしていた。
中学を卒業してからずっと気が重かった高校生活。しかしそれは、始まってみれば案外静かで淡々としていた。
部活に入らず、クラスのなかで必要最低限の関係を築いてしまえば、高校生活はそれほど居心地が悪いものではないのかもしれない。
僕自身のことを、クラスメイトがきらうほど知らないから、というのもあるかもしれないが。
「しおちゃん、新しい学校はどう?」
同居人且つ叔母である寿蝶々さんに声をかけられ、僕は味噌汁が入ったお椀をかき混ぜていた手を止めた。
「まぁ、ふつうです」
お椀を置いて答えてから、あさりの炊き込みご飯が入った茶碗を持ち直す。出汁のいい香りがする。
「新しい友だちはできた?」
「……いえ、べつに。てゆーかいらないですし」
はっきり答えると、蝶々さんは苦笑した。
「またしおちゃんはそんなこと言って」
「……僕はひとりでも大丈夫ですから」
本心だった。
僕はこの街に、ひとりになるために来ている。
地元神奈川の高校を選ばなかったのは、知り合いがいる確率が高かったから。
高校は、僕を知っているひとがひとりもいない場所で、一から始めたかった。ただしそれは前向きに楽しい高校生活を送りたいというわけではなく、完全にひとりになるためだ。
友だちは作らない。彼女もいらない。人間関係は最低限で、三年間なにごともない高校生活を送り、卒業する。卒業後は都内の大学に進んで、そのまま無難な企業に就職する。
神奈川を出た僕は、もう二度とあの街に帰るつもりはない。
たとえ蝶々さんに小言を言われたとしても、この意思は決して揺らぐものではない。そう思っている。
かちゃん、と食器が音を立て、僕は我に返る。
「それにしても、しおちゃんが高校生かぁ。あんなに小さかったのに、感慨深いなぁ。私も歳とるわけよね」
「え、いや、ぜんぜん若いじゃないですか」
蝶々さんは、母の妹だ。歳はたしか、結構離れていたからまだ三十代半ばくらいだったはずだ。
正直、母と蝶々さんはぜんぜん似ていない。
僕の母は中肉中背でどこからどう見てもふつうの主婦だけれど、蝶々さんはモデルのようなスタイルにきれいな顔立ちをしている。おまけに元医師だから頭もいい。
僕は生まれてこのかた、こんなにも完璧なひとを見たことがない。それくらい、蝶々さんは完成したひとだ。
姉妹なのにどうしてこうも違うのだろう。母がもう少し蝶々さん寄りだったら、僕ももう少しいい顔に生まれたかもしれないのに。
小さな不満を抱きつつ、僕は味噌汁を啜る。
上品に動く口元だとか密やかな喉元を眺めながら、そういえば幼い頃は蝶々さんのことを人形だと思い込んでいた頃があったなと思い出す。
きれいにカールした長いまつ毛とか、白く透き通った白目だとかがあまりにも作り物めいていて、だから母が蝶々さんにご飯を出したときはとても慌てた。
それで、親戚中に僕が蝶々さんを人形だと思っていることが露見してしまったのだ。
当時、さんざん笑われた記憶がある。ちくりと刺すような痛みが胸に広がる。あまり思い出したくない、苦い思い出だ。
あのとき、蝶々さんも驚いた顔をしていた。けれど、笑いはしなかった。
そういうところが、ほかの大人と違うところだ。
蝶々さんはいつだって優しい。
子供であっても大人であっても、ぜったいに態度を変えない。からかうようなことも言わない。
僕の悩みを一晩中だって聞いてくれるし、僕の感じたことや意思をぜったいに否定したりしない。
今回、僕が栃木県の高校に通えることになったのも、蝶々さんが両親を説得してくれたおかげだ。
蝶々さんは、いつだって僕の味方になってくれた。だから僕は、蝶々さんにだけは素直になれた。みっともない感情でも吐き出せた。親に言えないことも、なぜだか言えてしまうのだ。
僕にとって蝶々さんは、なくてはならない、酸素のようなひとだ。
母がいやだというわけではないけれど、もしこのひとがじぶんの母親だったら、と思ったことは何度もある。
もう少し、生きやすかったのかもしれない、と。
ぼんやりとしていると、蝶々さんが顔を上げた。
「しおちゃん、今日はなにか予定あるの?」
蝶々さんは菜の花の胡麻和えを口へ運びながら、ひっそりと微笑んだ。
「もし予定がないなら、街を散策してみたらどうかな? こっち来てからほとんど外出てないでしょ?」
「……そうですね。そうします」
蝶々さんは、僕がひとと関わることを避けていることを知っている。だからあまり口うるさいことは言わない。それでもたまに、僕があまりに内側へ引きこもろうとすると、こうして気を遣ってくれる。
蝶々さんに言われたときは、さすがに言うことを聞く。これが母親だったら、ぜったいに無視するけど。
おそらく、蝶々さんは僕がそう思っていることも見抜いている。分かっていてわざと、母親にはぜったいになれない立ち位置から、僕に接してくれているのだと思う。
「そういえば、駅の近くにある紫之宮神社って、すごくきれいなところですよね。能舞台とか、大きな桜の木もあって」
僕の話に、蝶々さんは一度目を丸くしてから、
「あぁ、あの神社ね、紫之宮じゃなくて、紫之宮って読むのよ」
と、微笑んだ。
「えっ! そ、そうなんですか」
この歳になっての言い間違いに、恥ずかしさが込み上げる。
「縁結びの神様が有名なの」
「あぁ、だからユカリ……」
「私もよく行くけど、しおちゃんもお参り行ってきたらいいよ」
「え、いや、僕べつに縁結びとか、恋愛とか興味ないし」
慌てる僕に、蝶々さんは穏やかな口調で言う。
「あら。縁結びは恋愛に限った話じゃないわよ。ひととひとを繋ぐ縁には、ほかにもたくさんあるでしょ。友だちとの縁とか、より良い就職先とか」
「はぁ……」
「巡りあいって、良くも悪くもひとを変えるから」
「…………」
「しおちゃんのひとりでいたいっていう気持ちも分かるわ。ひと付き合いって煩わしいからね……他人は勝手に期待したり評価したり、失望する。大人の私だっていやになるときがある。でも、マイナスなことばかりでもないよ。しおちゃんはまだ、本当に好きなひとと出会ってないだけ」
陽だまりのように優しい声だった。
「……蝶々さんは、出会えたんですか? 本当に好きなひとに」
訊ねると、蝶々さんは少し曖昧に笑った。
ハッとする。受け取るひとによるが、今の発言は少し嫌味に聞こえる内容だ。特に、結婚していない蝶々さんにしていい質問ではない。聞いてしまってから後悔した。
「……すみません」
謝ると、蝶々さんは首を横に振った。
「謝る必要はないよ。私、もう出会えてるから」
「えっ、そうなんですか!? どんなひとですか?」
前のめりに訊ねる。
だって、蝶々さんに恋人がいたとは知らなかった。いったいどんなひとなのだろう。彼女のとなりに並ぶのならば、相当なイケメンなのだろうが。
「もうしばらく会っていないけど、彼女は今でもずっと、私の特別なひと」
一瞬、固まる。理解が遅れた。
「え……彼女って、もしかして女のひと?」
さらに前のめりになる僕に、蝶々さんはひっそりと笑う。
「巡りあいは、べつに恋に限られたものじゃないからね。いわゆる親友ってやつよ」
「あぁ……なるほど」
ホッと胸を撫で下ろし、ふと思う。
昔、母から聞いたことがある。
蝶々さんには、中学生の頃とても仲がいい親友がいたと。けれど、その子は中学三年の冬、突然失踪して行方が分からなくなってしまったらしい。
すぐに行方不明届が出されて、その子の家族も蝶々さんもさんざん探したけれど、とうとう見つからなかったとか。
彼女がどうして消えてしまったのかは、今でも分かっていないらしい。事件なのか事故なのか、それも詳しくは聞いていない。親もあまり話したい内容ではなかったのだろう。それ以上は教えてくれなかった。
おそらく、蝶々さんが語った『特別なひと』というのは、消えてしまったその親友のことなのだろう。
蝶々さんは今、『しばらく会っていない』と言った。まるで、そのうち会うつもりでいるような言い回しだ。
蝶々さんはきっとまだ、その親友が帰ってくるのを待っているのだ。今でも、諦められずに。
「しおちゃん、菜の花の胡麻和えは?」
蝶々さんがおもむろに小鉢を僕に出す。目が合い、我に返った。そういえば食事中だった。
「あ、もういいです。こっち、もらいます」
やんわり断り、代わりにそのとなりの卵焼きをとる。
実を言うと、菜の花は口の中に広がる独特の苦味が苦手なのだ。幼い頃に食べたきり、一度も食べていない。二度と食べないと決めている。
蝶々さんは、栃木の郷土料理や山菜料理をよく出してくれるが、神奈川出身の僕には食べ慣れていないものが多くて、ちょっと苦手だったりする。
僕は笑って誤魔化しながら残りのご飯をお箸で挟み、ひとくちで食べる。醤油とあさりの風味が広がった。最後に玉子焼きを食べ、箸を置く。
「ごちそうさまでした」
食事を終えて部屋に戻ると、カーディガンを持って外へ出た。言われたとおり、少し散歩をしようと思ったのだ。
宛もなく歩いていると、例の神社――紫之宮神社の通りにつく。道の先に神社が見えた。鳥居の下にあの日見た黒猫を見つけ、足を止める。
黒猫は僕を見て、「よお」とでもいうようにひとつ鳴くと、そのままてんてんと跳ねるような歩きかたで神社の奥へと入っていく。
鳥居を見る。
紫之宮ではなく紫之宮と読むらしい。
「縁結びか……」
この前来たときはお参りはしなかったし、せっかくだから寄っていこうかな。
僕は鳥居をくぐった。
石畳が敷かれた参道の両脇には、淡い色の葉をつけた銀杏並木。銀杏の木漏れ日が落ちる参道を抜けると、静けさの落ちた境内が広がっている。
お賽銭を投げ入れて、鈴を鳴らす。
「…………」
お参りを済ませて来た道を戻ろうと回れ右をすると、能舞台が見えた。
あの日満開だった桜は、今や風が吹くたびに花びらを散らしている。見上げると、だいぶ散ってしまっているが、まだまだ美しい。桜の花は、散り際のほうが美しいと思うのは、僕だけだろうか。
「にゃあ」
黒猫の声がした。見ると、黒猫が舞台の上で我が物顔で毛繕いをしている。
そっと近付くと、幻想的な光景が僕の目を焼いた。
「わ……」
能の舞台の床には桜の花びらが広がっている。薄紅色の絨毯のなかに落ちる木漏れ日は、まるでそういう模様のようだ。
しばらくその光景を楽しんだあと、不意に気になって周囲を見回す。前にここで会ったあの子はいないようだ。
いや、べつに会いたいわけじゃないし、がっかりなんてしていない。ただ、なんとなくいそうな気がしたから、ちょっと確認しただけだ。
……と、なぜかいいわけめいたセリフが脳内を過ぎって、振り払うように頭を振る。
「にゃあ」
黒猫が鳴いた。
そっと、驚かせないようにそばに寄り、舞台に背を預ける。
黒猫と同じような体勢で、ぼんやりと桜を見上げた。桜を散らせる風は、ほんのり夏の気配を連れている。
もうすぐ、春が終わるのか。そうしたら、ひとりぼっちの夏が来る。
胸のなかの小さな罪悪感を置き去りにしたまま、僕は次の季節に行くのだ。
――帰ろう。
お参りも済ませたし、もうここに用事はない。
その場を去ろうとしたとき、ふと吹いた風が桜の梢を揺らした。
花びらが僕に向かって降り注ぐ。
「……あれ」
その光景に、僕はなぜか強い既視感を覚えた。
なんだろう。なんかこの光景、前にもどこかで見たような気がする……。
降り落ちる花びらを見上げていると、背後でざりっと砂利を踏み締める音がした。
「あーっ!! 汐風くんだっ!」
振り向きざま、弾けるような声が聞こえた。
「君……」
千鳥さんだ。千鳥さんは、初めて会ったあの日と同じ、ノースリーブの白いワンピースを着ている。
「……あの、前も思ったんだけど、その格好、寒くないの?」
「え? ぜんぜん?」
ふつうじゃない? ケロッと返され、僕は「そうなんだ」としか返せなくなる。
陽は暖かいが、まだまだ長袖は手放せない気候だ。特に今日みたいな風がある日は。
「まさかまたここで会えるなんてすごくない!? 汐風くんって、もしかしてここの近くに住んでるの?」
「え……」
一瞬だけ、言葉につまってしまう。名前で呼ばれたことに驚いたのだ。同年代の子に下の名前で呼ばれるのなんて、久しぶりすぎて。
「……まぁ、この通りの先に家がある」
「へぇ! そうなんだ! 奇遇だね。私もだよ!」
「え、そうなの?」
「うん! 街中に結賀大学附属病院ってあるでしょ。ほら、あそこ!」
千鳥さんはそう言って、銀杏の木の先のほうを指さした。
「……え、君、病院に住んでるの?」
ということはつまり、彼女は入院しているということだ。しかし入院しているなら、ふつう外には出られないのではなかろうか。そう思った矢先、彼女は先回りするように言った。
「でもね、十時は抜け出していい時間なんだよ!」
「……いや、抜け出していい時間ってなんだよ」
外来患者ならまだしも、入院患者にそんな時間はぜったいにないと思うんだが。
「だって病院って、退屈なんだもん」
てへ、と、千鳥さんはペロッと舌を出して笑った。
「いや……それぜったいまずいでしょ。主治医の先生とか知ってるの?」
「いいんだよ! 私、どこも悪くないもん!」
「どこも悪くなかったら、入院なんてしないでしょ」
「おぉ、鋭い!」
「いいから、早く戻りなよ」
「大丈夫! 先生には最近は安定してるからどんどんしたいことしなさいって言われてるし!」
「……えぇ……」
「それより見て、この子! 今日もここにいるの。昨日も一昨日もここにいたんだよね。もしかしたら、この辺に住んでるのかな?」
と、千鳥さんは舞台の上に転がっている黒猫を見て、無邪気に言った。
というか今、どさくさに紛れて昨日も一昨日も抜け出したと言わなかったか、この子。
「さぁ、野良かどうかも分からないし。この子、まだ仔猫だから母猫も近くにいるかもだし」
「え? この子、仔猫なの?」
見れば分かるだろう、と言いたくなったが、前回会ったとき、猫を初めて見ると言っていたことを思い出し、それを呑み込む。
「……そういえば、猫見たことなかったんだっけ」
「うん」
「この子は小さいから、仔猫だと思うよ」
「へぇーそうなんだ」
素直に感心しているようなその横顔を、少し不憫に思った。
ただの仔猫すら見たことがないなんて、彼女はこれまでいったいどんな人生を送ってきたのだろうか。
「辛くない?」
口走ってから、ハッとした。聞いてはいけないことだったかもしれない。
ちらりと千鳥さんを見ると、彼女は僕の言葉に特段気を悪くしたふうでもなく、首を傾げた。
「どういう意味?」
「……あ、いや、その……僕は、入院ってしたことないから分からないけど、いろいろ制限とかされるんでしょ?」
千鳥さんは顎の辺りに手をやって、のんびりと空を見上げた。
「うーん、そうなのかなぁ? 私、生まれたときからずっとこの生活だから、これが私にとっての当たり前だし。よく分かんないや」
のんびりとした声で言う千鳥さんを、僕はやはり不憫に思った。
この子には、自身の生活を悲しむ余地すらないんだ、と。
「これが私の日常だもの! お姉ちゃんはすごく優しいし、先生も看護師さんも優しくていろいろ教えてくれるから大好き!」
「……お姉さんがいるんだ?」
「うん! お姉ちゃんが私の名前を付けてくれたんだ」
千鳥さんは、桜を見上げながら言った。
「へぇ……」
お姉さんが名付け親ということは、千鳥さんとは歳が離れているんだろうか。
「あのね、ソメイヨシノってね、もとは一本の木から生まれたんだって」
「え?」
「桜ってすごくきれいだけど、実を結ばないから子種を増やせないんだって。でも、世界中のどの花より有名で、人種を越えて愛されてるでしょ? それってすごいことだと思わない!?」
「まぁ……」
「桜は、じぶんを愛してくれるたったひとりのひとと巡り会ったことで、世界中に広がっていったんだよ。こういうのを、運命の出会いって言うんだと思うんだ!」
そう言われてハッとする。
僕は、この話をどこかで聞いたことがある。だけど、どこだっけ……?
「私もね、そうなりたいって思ってるんだ」
「……え、増殖したいってこと?」
我に返って訊ねると、彼女はぷはっと息を吐いて笑った。
「あははっ! まさか! 違うよ。そうじゃなくて、役割がなくても、みんなから愛されるひとになりたいってこと」
そう言って、千鳥さんは桜を見上げる。つられるように、僕も桜へ視線を流した。
「……桜になりたい。実を結ばなくてもいいから、たったひとりでいいから、だれかに愛される花に」
「……それって、どういう……」
彼女の言葉の意味が分からず訊ねるが、千鳥さんはただ静かに笑って桜を見上げている。
「私ね、病院には桜がないから、桜が見たくなったらいつもここに来るの。この花を見たら、この世に必要のないものなんてないんだって思えるから。だれかが私を見つけてくれる気がするから」
その言い回しは、やはりどこか引っかかって、僕は再び千鳥さんを見た。
桜を見上げる千鳥さんの瞳には、どことなく寂寥感が滲んでいるように思えた。
「意味があるの、ぜったい。どんなものにも、どんなことにも」
意味、か。そうなのだろうか。
千鳥さんが僕を見る。
「君は?」
「え?」
「どうして俯いてるの?」
視線を泳がせる僕を、彼女はまっすぐに見つめてくる。
「初めて会ったときから、君はなにかに怯えてるみたい」
「べつに……僕は」
鬱陶しくて背中を向けるが、彼女は懲りもせず僕の正面に回り込んでくる。
「なんで隠すの? 怖いものがあるのは当然のことじゃない?」
「……当然?」
「うん。私も怖いものたくさんあるよ。たとえばー……注射とか! あと、目にライトを当てられるのもきらいだし。ピカーって。あれめちゃくちゃ眩しいんだよ!」
言いかたがあまりに子供っぽくて、少しだけ笑いそうになる。なんとかこらえて「そうなんだ」と返した。
千鳥さんはゆっくりと瞬きをしながら、もう一度訊ねた。
「君は、なにに怯えてるの? なにが怖いの?」
「…………僕は」
怯えているのだろうか。
なにに?
そんなの、考えなくても分かりきったことだ。
もし、僕がなにかに怯えているのだとしたら、それはきっと、
「……学校」
ぽつりと呟くと、千鳥さんは不思議そうに首を傾げた。
「学校、楽しくないの?」
「……楽しくないよ。授業は退屈だし夢もないし……それに、僕にはいっしょに遊ぶ友だちもいないから」
「そんなの、今はでしょ? これから作ればいいじゃん! 君、いくつ?」
「……十五歳だけど」
「私と同じだ! えっ、どこの高校?」
「……さくらの森」
「近っ! でも、十五ってことは、まだ高一でしょ? 学校、始まったばっかりじゃん! まだまだこれからだよ!」
「……まだまだ、これから……?」
曇りのない眼差しとその言葉に、僕はいよいよなにも言えずに黙り込む。
千鳥さんは空へ手をかざす。
「私たちはまだ十五歳だよ! 挫けるには早すぎるって!」
逆光になった彼女のシルエットは、まるでヒーローみたいだ。
小さい頃好きだったアニメに出てきたかっこいいヒーロー。彼もいつも前を向いて、手を空へ掲げて、夢を見ていた。彼女のように。
「それにさ、友だちなら私がいるじゃん!」
千鳥さんが振り返り、僕を見る。その眼差しはあまりに眩しくて、僕は目を細める。
「君が、友だち?」
「うん! 私たち、もう友だちでしょ?」
「…………」
千鳥さんは、純粋な眼差しで僕を見つめる。彼女の瞳はまるで澄み切った泉の水のようで、今にも吸い込まれてしまいそうだ。
僕は反射的にその視線から目を逸らした。
違う。僕が望んでいるのは、こういうものじゃない。
「……君は、僕を知らないからそんなことを言えるんだ」
絆されてはいけない。忘れてはいけない。僕は、ひとりでいるべき人間だ。
「じゃあ教えてよ。君のこと。君はどんなひとなの?」
千鳥さんはストレートに訊いてくる。拒まれても、怖気付くことなく。
その姿は鬱陶しくもあるけれど、少しだけ羨ましいと思った。こんなふうにまっすぐ思いを口にすることも、訊ねることも、僕にはできないから。
「……君には関係ないよ」
僕はわざと不機嫌を露わにして言った。こうすればだいたい、だれもその先を聞いてこようとはしない。親でさえ、口を噤む。
「うん」
しかし、彼女はさらに僕の予想に反して、
「関係ないから、聞いてるんだよ?」
「え……」
「関係ない人間だからこそ、先入観なくちゃんと話を聞けると思わない?」
千鳥さんはどこまでもまっすぐに僕を見つめてくる。ぜったいに目を逸らそうとしない。まるで、にらめっこでもしてるみたいだ。
「…………」
しばらくにらめっこをしてみたものの、結局僕はその眼差しに根負けして、話し始める。
「……昔、親友と喧嘩になって、怪我を負わせたことがあるんだ。そのあとも、何度かトラブルを起こして、その結果、友だちはいなくなった」
「…………」
千鳥さんは、なにも言わない。
「……分かったでしょ。僕はそういう人間だよ。だからもうかかわらないほうがいいよ」
ひんやりとした風が僕たちの間をすり抜けて、すぐそばにあった桜の梢を揺らす。
気まずい沈黙が落ち、ちょっとした罪悪感に襲われる。
……どうしよう。少し言いすぎたかもしれない。彼女はただの同級生じゃなくて、病気を患っている子なのだ。もう少し配慮するべきだった。
ふと、千鳥さんが瞬きをした。
「……あのー……君、いちばん重要なことを言い忘れてる気がするんだけど」
「え」
「大切なのって、喧嘩した理由じゃない?」
「……理由?」
「どうして喧嘩したの?」
訊かれて、考える。
考えながら顔を上げると、千鳥さんの大きな瞳と目が合った。どこか蒼ざめたその瞳は、まるで僕とは違うものを見ているみたいだ。
「……僕が、ある女の子を好きって噂が勝手に流されたんだ。だけどその女の子には彼氏がいて、その彼氏が不良グループみたいなところにいるひとだったから、ちょっと揉めて。それから僕はその彼氏連中から嫌がらせを受けるようになった」
この話は、蝶々さんにしか話したことはなかった。親にすら話せなかった。恥ずかしくて、バカらしくて。
それなのに、なんでだろう。
彼女には、なぜかすらすらと話せてしまう。
千鳥さんはまっすぐ僕を見つめている。
興味本位じゃないと分かる真剣な眼差しに、僕のなかでわずかに残っていた迷いが消える。
「あとから、その噂を流したのが親友だって知った。ショックで問いただしたら逆ギレされて、僕もムカついて……」
だけど、その場所が悪かった。
当時言い争いになったのは理科室。しかも実験中だった。揉み合った衝撃でアルコールランプが床に落ち、火の手が上がった。
「火が燃え広がって……僕は親友の手に、火傷を負わせた」
千鳥さんはしばらく驚愕した様子のまま、僕の手を見ていた。
「それ以来、僕はひとりでいるようになった。ひととかかわるのが怖くなったんだ。……だけど中学のとき、クラスメイトがいじめをしていて、僕はたまたまその場に居合わせて……いじめられっ子を助けようとしたんだ」
いじめられていたのは、かつて怪我させてしまった親友だった。
僕たちはあれ以来話すことはなく、他人になっていた。だから、親友がいじめられているなんて僕はこれっぽっちも知らなかった。
中学で同じクラスになり、その場面に居合わせたときはすごく驚いた。
動揺して、咄嗟に知らないふりをしようかとも思ったけど、できなかった。あのときの罪滅ぼしができるかもしれないと思ったのだ。そんなことをしたって、許されるわけないのに。
「結局、騒ぎを大きくしただけだった。それからはもう、とにかくいろんな噂が広まって、僕と仲良くしようとするひとはいなくなった」
千鳥さんはなにも言わず、静かに僕の話に耳を傾けている。
「……僕は、だれかといるとぜったいにそのひとを傷付けちゃう。だから、ひとりでいるべき人間。……いや、この世に存在しちゃいけない人間なのかもしれない」
何度も死にたいと思った。すべてを投げ出したくなったし、無性になにかに当たりたかった。だけど、そんな勇気はなかった。
僕は拳と奥歯に力を込める。
「……あのさ」
千鳥さんが控えめに口を開く。
「……君は、その友だちを傷つけたことばかりを重要視しているようだけど、違くない?」
「え……」
「汐風くんは、理不尽な目に遭わされたことに対して怒っただけだし、そのあとのことだって、ただいじめられっ子を助けただけだよね? 君、べつになにも悪くなくない?」
その言葉は、まるで真冬の寒空に落ちた太陽の光のように、冷え切っていた僕の心を溶かしていく。
「悪く、ない……?」
「うん。たしかに喧嘩した場所は問題だったし、怪我させちゃったことも反省しなくちゃいけないことかもしれないけど。でも、君は悪くないでしょ?」
まるで風船に穴が空いたように、ぱんぱんにふくらんでいたなにかが萎んでいく。
「そんなことない。僕が悪い」
「いやいや」
息を吐くように言うと、千鳥さんは大袈裟に聞こえるくらいの声で、
「そんなの、君の話をちゃんと聞けば分かることじゃん!」
と言った。そうなのだろうか。
僕は、悪くない?
「僕は……悪くなかったのかな」
言葉を知らない子どものように、たどたどしく呟く。
「うん。悪くない。君は正しい。だから気にする必要なし!」
千鳥さんは大きく頷いて、それからにひっと笑った。
僕は唇を噛み締めて、空をふり仰いだ。見上げた青空は、ゆっくりと滲んでいく。
――君は悪くない。
彼女にそうはっきりと明言されて、感情が込み上げる。
そうなのかな。僕は、悪くなかった?
みんな僕を責めたのに? みんな、僕から離れていったのに?
『悪くない』
僕は、悪くなかった……!
心が悲鳴じみた声を上げた。
「そもそも、どうして汐風くんが悪いことになるのかな……」
千鳥さんは不満そうな口調で言った。
「いつも思うの。週刊誌とかでもさ、女優さんとか俳優さんの人柄が話題になったりするでしょ。この俳優は気さくで親しみやすいだとか、この女優は性格最悪だーとか。みんなそれを当たり前のように信じたりするけど、それって変だよ」
「……どうして?」
「だって、ひととひとって相性でしょ。性格が悪いひとっていう表現は間違ってるよ。だって、そのひとの性格が悪いんじゃなくて、たまたま取材したひととか、そばにいたひとたちと性格が合わなかっただけかもしれないじゃない?」
「合わなかった、だけ……?」
「そうだよ。だから私は、噂よりもじぶんで見たものを信じたい。もし君が学校で悪く言われるなら、私が否定するよ。私が知ってる汐風くんは悪者じゃない。私に猫を触らせてくれた優しいひとだよ、って。だからそんな顔する必要なんて少しもないよ。ね、顔を上げて」
ほろ、となにかが頬に触れた。頬に手を持っていく。見ると、桜の花びらが指にくっついていた。花びらが濡れている。
あぁ、泣いてたんだ、と思った。
堪え切れずあふれ出した涙は、次から次へと頬をすべり落ちていく。けれど、僕の涙を見ても彼女はなにも言わない。ただ、微笑んでいた。
――春はパステル色。
駅の広告かなんかにあったキャッチコピーをふと思い出す。
桜の木を見上げ、隙間から降り注ぐ淡い陽の光に目を細めながら、あれは本当だったんだな、と思う。
春は、明るい。そして、春のなかにいる彼女もまた、眩しかった。
「さて、そろそろ戻らなきゃ」
不意に彼女が言った。そういえば、彼女は入院患者だ。ここにいること自体おかしい子だ。
「じゃあ私、行くね」
千鳥さんは舞台から軽やかに降りると、僕に背中を向けて歩き出す。
「あ……うん。気を付けて」
大人しく彼女の背中を見送っていると、不意に千鳥さんが振り返って僕を見た。
「汐風くん!」
「なに?」
「さっきの過去の話だけど。間違えた行動をしたと思ったなら、謝ればいいんじゃないかな! 汐風くんの悪いところは、勝手に自己完結しちゃうところだと思うよ」
ずばっと言われ、背筋を伸ばす。そんな僕を見て、千鳥さんはころころと笑った。
「未だに悩んで後悔してるなら、謝ったらいいんだよ! 後悔は、生きている証拠。成長できる証拠。もちろん、謝ったからって関係が元通りになるわけじゃないかもしれないけど、少しはすっきりするかもしれないよ」
「……うん」
頷くと、千鳥さんはすっと手を伸ばした。彼女の伸ばした指先は、僕の頭上を指している。
「俯きそうになったら、桜の木を探してみて! 桜の花を見ようとすれば、顔を上げられるから! それじゃあね!」
駆けていく千鳥さんの後ろ姿を見送りながら、ゆっくりと瞬きをする。
視界を彩るのは、彼女の白いワンピースと、舞い散る桜の花びら。足元に視線をやると、視界が薄紅色に染まった。
「……桜だらけだ」
なんだか胸の辺りがむず痒くなってきた。
こんなにも春を感じたのは、初めてのことだった。
***
その日の夜。
僕はスマホのメッセージアプリを開き、かつて怪我を負わせてしまった親友のアカウントとにらめっこをしていた。
メッセージ画面は、まっさらだ。
もともとお互い欲しくて交換したわけでなく、中学進学時に連絡網として学校側に強制的に交換させられたものだったからだ。結局、一度も起動しないまま卒業したが、今でも消すことができずにいた。
『――後悔してるなら、謝ったらいいんだよ』
昼間の彼女の言葉に押されるように、指先がかすかに画面に触れる。感度のいい僕のスマホは、憎たらしいことに僕の指を検知した。
「あっ……」
画面が発信中に切り替わり、心臓が暴れ出す。
パニックになり、バツ印を押そうとしたとき。
『――汐風くんの悪いところは、勝手に自己完結しちゃうところだと思うよ!』
もう一度千鳥さんの声が聞こえて、思いとどまる。
そっと耳元にスマホを持っていく。しばらく発信音が響いて、そして、音がプツッと切れた。
『もしもし?』
「あ……」
久しぶりの親友の声に、それまで考えていた言葉がすべて吹っ飛んで、頭が真っ白になった。
「あ、あの、錦野……だけど」
とりあえず名乗ってから、僕は深呼吸をして、乱れていた呼吸を整える。
『あぁ……うん。どうしたの、いきなり電話なんて』
スマホの向こうからも、僕と同じ戸惑うような声が返ってきた。
勢いで電話をしてしまったけれど、どうしよう。とにかく、なにか話さなければ。
「あぁ、うん……あの、どうしてるかなって」
言葉につまって、最終的にざっくりとした問いを投げてしまう。考えてみれば、同級生と会話をするのなんていつぶりだろう。
『高校?』
「う、うん」
相手を前にしているわけでもないのに、どうしてか態度がぎこちなくなってしまう。電話ってこんなに難しかったっけと思う。
『楽しいよ。しおは? 県外に行ったって、噂で聞いたけど』
「うん。栃木」
『……そっか。遠いな』
楽しいか、とは聞かれなかった。
『ひとり暮らししてんの?』
「あ……いや、今は蝶々さ……えっと、叔母の家に居候してる」
『そうなんだ……』
頭のなかにはいろんな感情があふれていて、言いたいことはなにひとつまとまっていない。
僕は頭のうしろあたりを掻きながら、言葉を探して黙り込んだ。
どれくらい経っただろう。遠くからカチカチと時計の音が耳に入ってきて、僕はようやく口を開く。
「あのさ、今さらなんだけど……その……手、大丈夫?」
『あぁ……』
その言葉だけで、親友は僕がなにを言いたいのか分かったようだった。
『いや、うん。ぜんぜん』
「……あのさ……ごめん。その、前に怪我させたこと、ずっと謝れてなくて……」
しどろもどろになりながらも、僕は続ける。
「今さら謝ったって、遅過ぎることは分かってる。許してほしいなんて思ってない。ただ……」
『違うよ』
しんとした声が返ってきて、僕は続けようとしていた言葉を呑み込んだ。
『謝るのは、俺のほう。俺こそずっと謝りたいって思ってた』
返ってきた予想外の言葉に、僕は戸惑う。
「……なんで、凪が」
久しぶりに呼ぶ親友の名前は、なんだか変な感じがした。
『だって、悪いのは俺だろ』
凪が静かな声で話し出す。
『あの事故のときさ、俺、しおに嫉妬してたんだ。しお、結構女子から人気があったから。あの頃好きだった子が、どうやらお前のことを好きらしいって聞いて……俺、悔しくてさ。お前が他に好きな子がいるって噂になれば、諦めてくれるかなって思って……あんな大事になるなんて思ってなかったんだ。本当に、バカだった。……ごめん』
それは、当時も聞いた話だった。
当時凪が好きだった女子が僕に気があるとかなんとか。実際、それが事実かどうかは知らないけれど、凪はそれを本気にしたのだ。
そして、僕に好きな子がいるという噂を流した。相手は、もともと噂になっていた子とはべつの女子――しかも、派手めなグループの女子を名指しで。
当事者である僕は噂になったその子に欠片の興味もなかったから、無視していた。否定も肯定もせずに。しかし、それが余計、相手の彼氏には不快に映ったらしい。
そして僕は、彼らからいじめの対象と認識された。
今思い返してみても、あのときどうするべきだったのか、答えは分からない。
あのときはっきり否定していたとしても、きっといじめられていただろう。槍玉に上がった時点で、僕に逃げ道はなかった。そう思う。
『……辛かったよな』
凪のそのひとことがトリガーとなった。
ぱきっと音がした気がした。固く閉ざされていたはずの心の器が割れた音だ。抑えていた心が、決壊し始めた。
「……うん。ずっと強がってたけど、当時は結構辛かった。噂が広まって、相手の彼氏からいやがらせを受けたことより、凪にずっときらわれてたんだってことのほうが、ショックで」
『きらってなんかない。それは本当だよ。ただ……その、あの頃俺、ガキだったから。出来心みたいなやつだったんだと思う』
凪は振り絞るように呟いた。
『……本当に、バカなことした。ごめん』
あの頃の傷が疼き出す。
苦しい。虚しい。いろんな感情が胸にあふれてゆく。ひとと向き合うっていうのは、こんなに辛いものなのか。思わず胸を押さえて、奥歯を噛み締めた。
『それからさ……もうひとつ、謝りたいことがあったんだ』
「……なに?」
『中学でさ、からかわれてた俺を、しお、助けてくれただろ。俺たちすっかり疎遠になってたのにさ。だけどそのあと俺を助けたせいで標的がしおに変わっちゃって……俺、孤立していくしおを助けられなかった。……いや、助けなかったんだ。またいじめられるかもって思ったら、怖くて』
「……うん」
分かっている。凪を責めることはできない。
僕だってもし凪と同じ立場だったら、きっと見て見ぬふりをしてしまうだろう。じぶんの身を危険に晒してまで、他人を助けることを選べないと、そう思うから。
『俺、ずっと後悔してた。あのとき庇ってくれてありがとうって、それなのに守れなくてごめんって、ずっと言いたかった。……けど、いざ声をかけようと思ったら、周りの目とかいろいろ考えちゃって……話すのが怖くなって、結局なにも言えないまま卒業して……あとから、お前が県外の高校に言ったって聞いて、また自己嫌悪。……俺は、後悔ばっかだな』
凪の口からこぼれた後悔という言葉に、僕の身体のどこかが、なにかが大きく反応した。
――初めて知った。
後悔していたのは、苦しかったのは、僕だけじゃなかったのだ。
『あのときちゃんと向き合ってたら、今もまだしおと友だちでいられたのかなって、ずっと思ってたんだ』
後悔していた。凪も。僕と同じように。
『……しおが連絡くれなかったら俺、ずっともやもやを引きずったままだったと思う。正直、もう連絡なんて来ないと思ってたし』
僕だって、そうだ。
『だから、連絡くれてありがとな』
「……うん」
『それから、俺のこと覚えててくれてありがとう』
ありがとう、なんて、今まで何度も聞いたことのある言葉。それなのに、こんなに胸に沁みるのはなんでだろう。こんなに目頭が熱くなるのはなんでだろう。
「……凪も、僕の連絡先残しておいてくれてありがとう。正直、出てくれないと思ってたからさ。凪の声が聞こえたときびっくりしちゃって……」
『なに言ってんだよ! 消すわけないだろ』
天井を振り仰ぐ。
「……うんっ……」
目を大きく開いていないと、涙が落ちてしまいそうで。
『……ねぇ、なんで連絡くれたの? 今さらになってって言いかたは悪いけど……なんかあったんだろ? きっかけが』
言われて考える。
凪の問いで脳裏を過ぎるのは、彼女しかいない。
「……こっちで出会った子に言われたんだ。後悔してるなら謝れって。後悔は、生きてるからこそだって。謝って過去がなくなるわけじゃないけど、少しはすっきりするかもしれないって。たぶん、そう言われなかったら僕も連絡なんてできなかったと思う」
彼女に出会わなかったら、彼女と話をしなかったら、ぜったいに僕のなかからは出てこない言葉たちだった。
『へぇーいい子だな、その子』
「……まぁ、ちょっと変わってるけどね」
彼女の無邪気な姿を思い出して、自然と笑みがこぼれる。
『あ、もしかして彼女か?』
「え!? ち、違うよ!」
予想外の指摘をされ慌てて否定すると、スマホの向こうで凪が笑う。
『なんだ、残念。……でも好きなんだな。その子のこと』
「なんでそーなんの……」
にやつく凪の顔がありありと脳内に浮かび、げんなりする。
『だってアドバイスされたってことは、じぶんのことその子に話したってことだろ?』
「……それは、まぁ」
『それだけ、心を許してるってことじゃん? しおがじぶんのこと話すなんて』
出会ったばかりの異性にあんな話をしたなんて、今考えても信じられないけれど。事実なのだから否定のしようがない。
『しおも変わったんだな』
「…………そんなことは」
ない、と否定したいが、うまく言葉が出てこなかった。
『なぁ、しお』
「なに?」
『今度、帰ってきたら連絡してよ。遊ぼーぜ』
「……うん」
帰ったら、か……。
つい数週間前、この街に来たとき僕は、もう二度と神奈川へ帰るつもりはなかった。あそこには、いやな思い出がいっぱいあるから。
でも、今は。
ちょっとだけ、楽しかった思い出を思い出せる気がした。
しばらく話すうちに、僕たちはいつの間にか、親友だった頃のように笑い合っていた。
通話を切り、ベッドに身を投げ出す。
静寂が戻った部屋のなか、僕はふぅ、と息を吐きながら胸を押さえた。
心臓のあたりが、なんだか日向でうたた寝しているときのようにあたたかい。僕はそんな気分のまま、静かに目を瞑った。