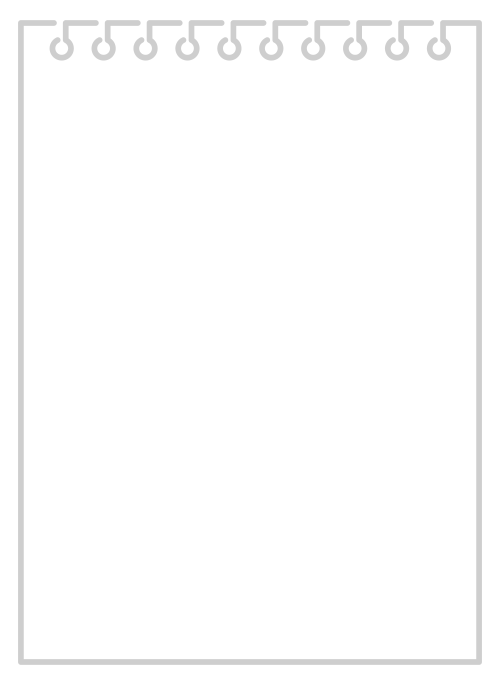「あ、か、川北さん」
「お、疲れ様です、川北さん、それに、三瀬くん」
気まずそうに言葉を私に投げる彼女たちと会話のキャッチボールをする気にはなれず私は静かに会釈をして彼女たちを押しのけるように資料室の中に入った。
「絶対聞こえてたよ」「やば」とこそこそ話している。ぜんぶきこえてるんだよ!この噂好き女どもお!と振り向いてどつきたい気持ちをおさえながら耳と湧き上がる感情を無にする。
がちゃん、と背中で扉が閉まる音がした。
足音が聞こえるということは、三瀬くんも中に入ってきたようだった。なんだかみじめなので話しかけない。
「星子さん」
話しかけないで。
「星子さん」
これ以上、私をみじめにはしないでほしい。
「星子さんってば」
資料をあさる私の手を三瀬くんが後ろから掴んだ。
先ほどの『三瀬くんの気を引くためにわざとやったんじゃない?』という言葉が瞬時に蘇った。そしてその手を振り払う。
「三瀬くんはさ、これ以上私に近づかないほうがいいと思う」
「なんで?」
「変な噂の的になるの嫌でしょ」
「さっきの人たちに何か言われたんですか。そもそも教育係だし近づくも何も」
「教育係が仕事できないんじゃ元も子もないでしょう」
「そんなことないです星子さんは」
「みじめになるから嘘言わないで」
もう喉がつまってうまく言葉が吐き出せなくなってきた。事実なのに自分のみじめさをさらけだそうとすると泣きたくなるのはなんでなんだろうか。こんなにみっともない人間なのだとさらけだすことへの羞恥心なのかもしれない。
「教育係が星子さんでよかった」
「っ」
「本音です」
「なので」と私の手を掴んだ三瀬くんは半ば強引に自分の方に引き寄せる。あっけなく三瀬くんとの距離は近くなった。
「星子さんは、星子さんでいてください」
「ど、どういうこと?」
「そのまんまの意味ですよ」
三瀬くんはどこか色気を含んだ笑みを私に向けた。
こうやって女はいとも簡単に彼におちていくのだと思う。彼は無自覚なんだろうか。無自覚だとしたらたちが悪い。